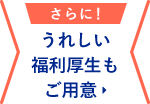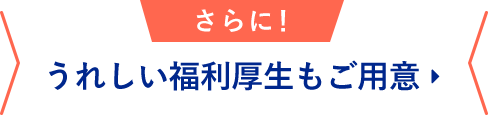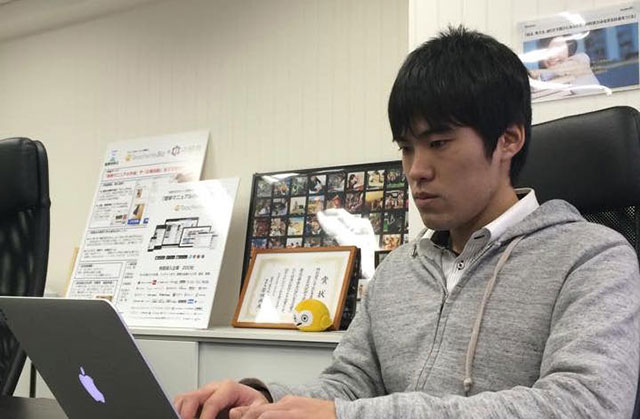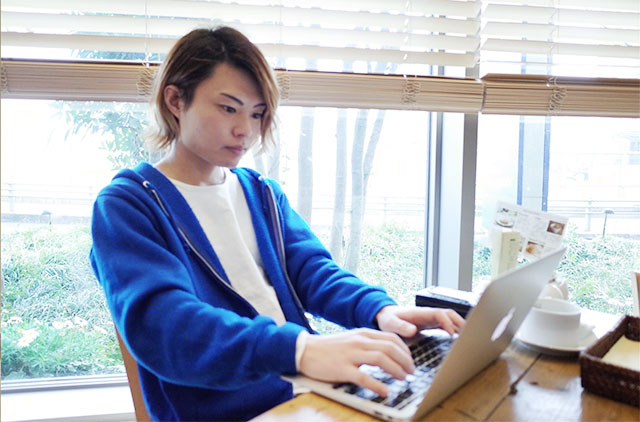本気だから。
フリーランスで
生きていく。
その「本気」、
PROsheet が応援します。
PROsheetが
選ばれる理由
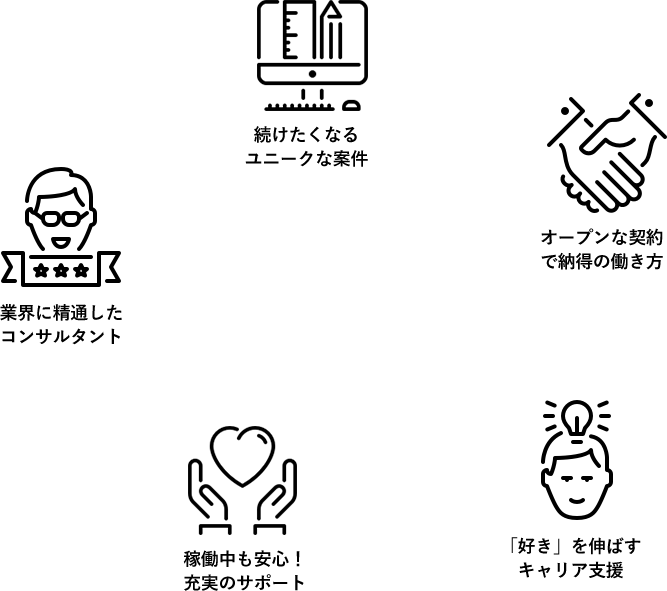
あなたが主役の直接契約
1オープンな契約
ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします
2納得の高額報酬
報酬・サービス利用料を開示!スキルに合った高額報酬を実現します

※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します
※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます
1オープンな契約
ユーザーと企業が結ぶのは「直接契約」すべての契約条件をオープンにします
2納得の高額報酬
報酬・サービス手数料率を開示!スキルに合った高額報酬を実現します
一般的な案件紹介のモデル
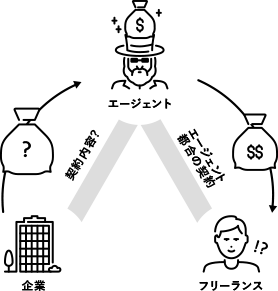
- ※1:サービス手数料率については、本サービス利用者に限り開示します
- ※2:一部クライアントとはSES(準委任)契約を結んでいただく場合がございます
ご利用のながれ
- ご登録の希望条件・スキル情報をもとに企業へ推薦
- PROsheetからオファーが届いたらさっそく企業面談へ
- 企業面談から契約締結、更新手続きもPROsheetが全面サポート
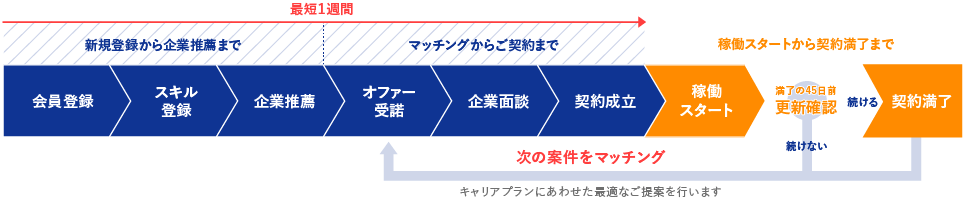
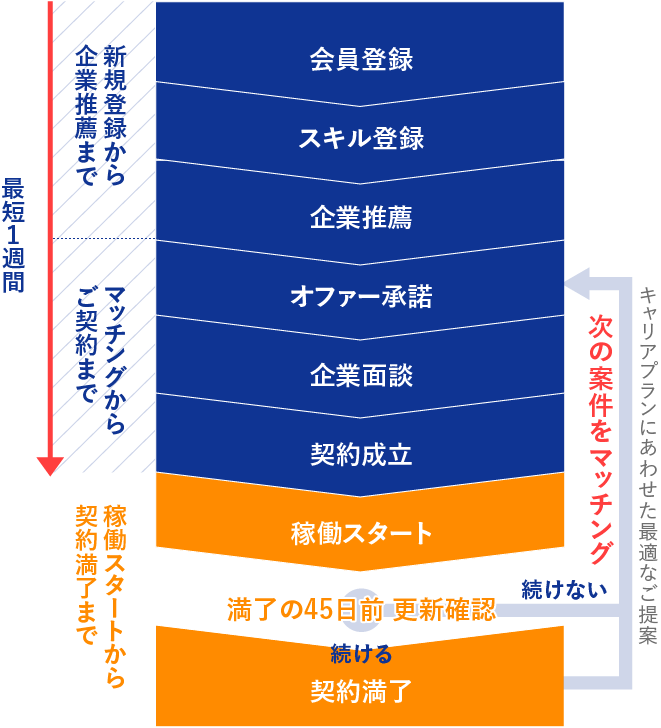
ユーザーの声
「使ってみてどうだった?」
PROsheetを通じて稼働いただいた方の声をご紹介
収入アップ、あきらめていませんか?
身につけたスキルや経験が、ダイレクトに「報酬」として反映されるのがフリーランスの特徴。あなたの実績がきちんと反映されるよう、単価交渉をはじめとするキャリアアップをお手伝いします。
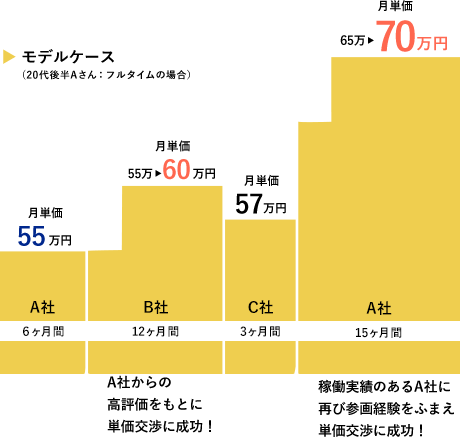
- あなたが築いた実績をもとに担当コンサルタントが単価交渉をサポート
- 稼働実績が増えるほどあなたの市場価値もワンランクアップ
- 契約満了後は次の案件をご提案!収入面の不安もしっかり解消
案件情報
現在募集中の案件を一部ご紹介!
非公開情報もございますので
お気軽にご相談ください。
注目
【PM】動画制作プラットフォームの開発マネ…
プロダクトマネージャーとして、コンセプトの立案・プロダクト設計・プロダクト実装フェーズの問題解決を行…
週4日・5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトマネージャー |
定番
【講師】【サブ講師】新入社員研修PHP講師…
技術力も重要ですが、インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視 ・新入社員PH…
週5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHP新卒研修講師 |
| PHP | |
定番
【Java/Python/C♯】新卒研修講…
技術力も重要ですが、 インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視します。 IT…
週5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 新卒研修講師 |
| Python・Java・C# | |
定番
【React / TypeScript】自…
・新規プロジェクトにおけるフロントエンド領域の実装 ・チーム内相互コードレビュー等による品質向上
週3日・4日・5日
2万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・jQuery・jQuery | |
定番
【フルスタック】スタートアップ企業向けのプ…
既にリリース済みのプロダクト改修や機能追加等の開発をメインで担当いただきます。 また、新規サービス…
週4日・5日
1.9〜3.2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【マーケター】大手広告代理店内にて広告マー…
広告マーケター、ディレクション経験者を募集しています。 リスティングLP、バナー広告、SNS、アフ…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告マーケター/ディレクション |
定番
【サーバーサイドエンジニア|フルリモート】…
【案件概要】 弊社で運営している印刷・広告のシェアリングプラットフォーム事業における印刷ECプロダ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Go・Vue… | |
定番
[Ruby]HRTechにおける自社プロジ…
【事業内容】 勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 …
週5日
570,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【PHP】会員マッチングサイトの開発エンジ…
CMSベースの会員マッチングサイト開発に携わっていただきます。 ・PHPプログラム開発 ・モジュ…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Drupal・HTML・CSS | |
定番
【Swift/Ob-C】日本最大級の料理動…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go】日本最大級の料理動画メディアにおけ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【WEBデザイナー】日本最大級の料理動画メ…
3,000万人以上に利用されている日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、広告用のLP・バナ…
週4日・5日
310,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | デザイナー |
| ‐ | |
定番
【Go|フルリモート】短期就業仕事紹介マッ…
弊社では短期間・短時間の仕事に特化した1日単位のお仕事プラットフォームの開発を行っております。 …
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【WEBデザイナー】動画メディア会社におけ…
自社ライブコマースアプリのリリースや、現在運営しているママ向けメディアや女性向けメディアのアプリ化に…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【Ruby】Webサービスの受託開発
ハイレベルな環境で開発スキルアップにつながる案件で、フルリモートも可能です。
週3日・4日・5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
急募
【人気案件】Python、Ruby、Jav…
弊社ITコンサルタントとともにクライアント先の業務システムの受託開発を、 要件定義から行っていくリ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |
定番
【PHP】自社プロダクト開発業務
自社運営のWebメディア、Webサービスのサーバーサイドのアプリケーション新規構築・機能強化を担って…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・PHP・MySQL・Apac… | |
定番
【React】IT商社が運営するポータルメ…
IT商社に関する企業様です。フロントエンドエンジニアとして、 自社ポータルメディアフロント側にてイ…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Go/PHP / 週5日】HR領域におけ…
【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのWebエンジニア募集! …
週5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Scala… | |
注目
【Ruby】小規模Webサービスの受託開発…
受託開発での小規模プロジェクトにおいて幅広くご担当いただけるサーバーサイドエンジニアの方を募集してお…
週4日・5日
2.4〜2.7万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・on・Ra… | |
定番
【Rubyエンジニア / HR Tech】…
【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのWebエンジニア募集! …
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【JavaScript】チャットボット学習…
チャットボット(テキストや音声を通じて、会話を自動的に行うプログラム)の学習の手間を半減させる自社開…
週5日
240,000円以上/月
| 場所 | 品川不動産前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js,React.j… | |
注目
【Ruby】マーケットプレイスアプリのサー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週5日
2.5〜3.2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
注目
【AndroidJava/Kotlin】H…
弊社の運営するHR系WebサービスのAndroidアプリ開発・保守運用業務をご担当いただきます。 …
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【マーケター】デジタルマーケティング企業で…
ディスプレイ広告・SNS広告の運用業務をご担当いただきます。 (1)メディアプランニング・アカウン…
週4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
[動画制作]官公庁や大学における広報動画
[案件内容] 官公庁や学校(主に大学)などにおける広報映像の制作 Lディレクション~撮影~編集な…
週5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | [動画制作]官公庁や大学における広報動画 |
| Adobe・Premiere・Pro | |
注目
【インフラエンジニア】ITインフラ基盤構築
スタートアップのITコンサル会社で、大手外資系企業企業、日本企業を顧客に持ち、 意欲次第でいろいろ…
週5日
1.6〜3.6万円/日
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・基本的なストレージ構築スキル・・ネットワーク・サー… | |
定番
【フルリモ / React/Typescr…
自社で開発を行っているクラウド人材管理ツールのフロントエンド側の新規機能の開発や既存機能の改善対応、…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Python/RDBMS】HRTech企…
2010年からサービス開始をした業務支援システム 大手からベンチャー企業まで様々なお客様に導入いた…
週5日
410,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【Angular.js / React.j…
自社サービスのフロントエンドを、Angular, TypeScript で開発していただきます。 …
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【デザイナー】自社サービスのWebデザイン…
自社サイトに関わる、Webデザイン・コーディング・画像制作 ・SEO対策を意識したコード修正(指示…
週2日
80,000〜160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・HTML・C… | |
定番
【VB.net】バス会社用自社パッケージシ…
バス会社に提供するシステムの開発をVB.NETを用いて行っていただきます。 ※いくつかのプロジェク…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 埼玉川口駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| C#・VB.NET・VBA・.NETFW | |
定番
【C/C++・C#】ゲームエンジニア
コンシューマーゲームのクライアント開発
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Unreal・Engi… | |
定番
【3DCGモデラー】エフェクトデザインかキ…
3DCGモデラーの中でもエフェクトデザインかキャラクターデザインをお任せします。
週5日
1.6〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGモデラー |
定番
【Javascript・Python】自社…
ユーザーへ価値を届ける最前線となる機能開発や そのバックエンドのAPIを開発する責務を担って頂き…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリケーションエンジニア |
| JavaScript・Python・TypeScri… | |
定番
【AWS】AIプラットフォームのクラウドイ…
AI-OCRのSaaSプロダクトのクラウドインフラエンジニアポジションです。 プロダクトとして…
週5日
740,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモート】保護者…
保護者・学校向け新規プロダクトのサーバーサイド開発に携わっていただけるRubyエンジニアの方を募集し…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Angular | |
定番
【Unix】HRtech領域における自社サ…
[担当プロダクト] 勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムです。 複数拠…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・UNIX系OS、RDBMS(Linux、MySQL… | |
定番
【SREエンジニア|リモート相談可能・週3…
【案件概要】 短期間・短時間の仕事に特化して柔軟な働き方を望む個人と必要な時に必要な分だけ人材を活…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Kotlin・Go・CloudSQL・GCP(GAE… | |
定番
【Python】【講師】エンジニア育成のた…
技術力も重要ですが、 インストラクション能力やコミュニケーション能力の方を重要視します。 IT…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件毎に異なります |
|---|---|
| 役割 | Python新卒研修講師 |
| Python | |
定番
【フルスタック】AI OCRを中心としたA…
AI OCRを中心としたAIプラットフォームを自社開発しております。 今回は、現在リリース済の…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Typescri… | |
定番
【分析・マーケター】ECサイト改善を担うW…
GoogleAnalyticsを始めとした分析ツールを使い、 クライアントのECサイトを分析・改善…
週4日・5日
470,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBアナリスト |
定番
金融デリバティブ取引システム導入およびブリ…
【業務概要】 金融デリバティブ取引システム(FX、暗号資産)のクライアント導入およびオフショア(ベ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM、ブリッジSE【FX 暗号資産】 |
| Java・- | |
定番
【QAエンジニア / HR Tech】HR…
【企業概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのQAエンジニア募集! …
週5日
390,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【Java】自社プロダクトのサーバーサイド…
自社サービスの新規機能開発・改善に携わっていただけるサーバーサイドエンジニアの方を募集いたします。 …
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【Ruby/PHP/Go】急拡大中の自社サ…
日々メディアにも掲載されrる業界No.1の注目度を誇る自社サービスでのバックエンド開発業務になります…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Go・Rails・Laravel・… | |
定番
【Android/IOT】国内最大のタクシ…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用Androidアプリの開発を担当して頂きます。…
週4日・5日
2.7〜4.4万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | [Android/IOT]国内最大のタクシー配車サービスのスマホアプリ開発 |
| AndroidJava・Kotlin・GitHub・… | |
定番
【Unity】VRプロダクトの開発業務
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | VRエンジニア |
| C#・Unity | |
注目
【WEBデザイナー】マーケティングチームで…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内の マーケティングチームにてデザイン業務に携わってい…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー(グラフィック含む) |
| HTML・CSS | |
定番
【Goエンジニア|フルリモート・未経験可能…
弊社開発チームにて以下の開発をご担当いただきます。 ・バックエンドシステムの開発および関連する…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【WEBデザイナー】大手人材企業クリエイテ…
延べ100万人を超える採用・就業支援を通じて培った人事業務のナレッジ先端テクノロジーを融合することで…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PHP/Laravel】国内初プラットフ…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務 1機能単位で設計からテストまで開…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Laravelエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel | |
注目
【Node.js,TypeScript】オ…
スマートフォンをメインターゲットとした、様々なサービスの機能追加、保守運用業務を担当していただきます…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
注目
【TypeScript】オーディオブックサ…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。具体的…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(オーディオブック) |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
注目
【WEBディレクター】 ECサイト・リプレ…
主にCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生産管理(サプライチェーン)の再構築での業務分析、カスタマ…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| ・CRM施策の参画経験 ・UX設計、PDCAサイク… | |
【Python】運用自動化プラットフォーム…
DSLでの処理記述や内部でPythonライブラリ使用するためPython記述の対応をお願いします。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【PHP】ペット関連サービスにおける新規開…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日・4日・5日
1.2〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート】…
【業務内容】 転職支援・採用支援サービスのフロントエンド領域で新機能や改善の実装を中心にプロジェク…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
注目
【ヘルプデスク】100人規模のヘルプデスク…
社内のヘルプデスクとしてPC設定やトラブルシューティング、 各種ヘルプデスク業務を行っていただきま…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅/青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内ヘルプデスク |
定番
【HTML・CSS・JavaScript】…
自社サービス「SPEED M&A」というM&Aマッチングプラットフォームのフロントエンド開発をメイン…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【ディレクター】ECサイト改善を担うWEB…
ECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションを担当いただきます。 サイト…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター |
| ECサイトディレクション | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】クラ…
【案件概要】 自社サービスの共通インフラ基盤に対する環境構築・運用業務。 <業務の流れ> …
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
定番
【データサイエンティスト】フォークリフト自…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【PM】物流倉庫向け業務可視化システムのプ…
現在、物流倉庫向け業務可視化システムを受託開発しております。 今回は上記プロジェクトのPM業務を担…
週5日
720,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【マーケター】自社HR Techサービスの…
全社のマーケティング部門にて、 広告運用を中心としたマーケティング業務をお任せできる方を募集してお…
週2日・3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
定番
【PHP/フルリモート】クラウド人材管理ツ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週4日・5日
580,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / UIデザイナー / 週5日…
【業務内容】 デザインチームにて、サービスに関するデザイン業務全般をご担当いただきます。 具体的…
週5日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Figma・AdobeCC | |
定番
[React]自社サービスのWebアプリ開…
自社で開発したサービスのフロント側の開発を担当いただきたいと思います。 主に要件を元に仕様作成/実…
週4日・5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【Swift/Kotlin】大手鉄道会社の…
【案件概要】 大手鉄道会社から委託を受けているスマホアプリ開発のエンジニアを募集します。 ※ペア…
週4日・5日
3.2〜4.8万円/日
| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Unity | |
定番
【Typescript】自社サービスのTy…
【案件概要】 既にサービスを展開しているチャットサービスの 機能拡張開発を行っていただきます。 …
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Vue/Nuxt.js/Python】自…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【Ruby】不動産売却領域サービスのサーバ…
・社内向けツールの改修、改善 ・不動産会社向けツールの改修、改善 ・事業部横断の共通基盤システム…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
注目
【フルスタック】特殊動画プレイヤー/配信シ…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週4日・5日
3.2〜4.9万円/日
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Vue.js+Nod… | |
定番
CRE(Customer Reliabil…
・問い合わせ事象の技術的な調査と不具合の修正 ・問い合わせ発生状況の分析および分析結果に基づく改善…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | CREエンジニア |
| Python・AWS・AWS・Glue・AppSyn… | |
注目
【不動産営業】注文住宅に関しての営業業務
業務概要:一戸建て(建売)のリモート営業 業務詳細:建売の販売営業 作業場所:フルリモート 稼…
週1日・2日
1.6万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 不動産営業 |
定番
【デジタルマーケティング】自社化粧品の新ブ…
自然派コスメECショップにおける、新規ユーザー獲得のための Web広告の戦略立案および運用などのW…
週4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【PHP】受託開発案件に向けた、PHP開発…
【業務詳細】 大小含めてWEBサイトのデザインからシステム開発まで制作しております。 今回の募集…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Laravel | |
定番
【フルリモートOK|PHP案件】総合エンタ…
【案件概要】 総合エンタテインメント企業が運営する、各サービスのバックエンドAPIの機能追加・保守…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・・PHP ・AWS … | |
定番
【JavaScript】自社コマースサイト…
弊社が運営するコマースサイトのフロントエンド開発をご担当いただきます <使用技術> ・Jav…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
注目
【PMO】コンテンツ配信管理システム開発の…
コンテンツ配信管理システムのプロジェクト管理支援を担当していただきます <技術スタック> ・…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Java・Typescript | |
注目
【DevOps】コンテンツ配信管理システム…
【案件概要】 コンテンツ配信管理システムを構築するための人員を募集いたします。 具体的にはコンテ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | DevOpsエンジニア |
| Docker・Linux・Terraform | |
急募
【Python】レコメンドエンジンのAPI…
デジタルクリエイターのタレント集団が在籍しており、 クライアントに最高のクリエイティブを提供するプ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
自社サービスにおける決済基盤のリプレイス開発を行います。 現在、ECサイトが7〜8プロダクトありま…
週5日
620,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア(シニア) |
| Ruby・RubyonRails | |
注目
【Go】自社サービスにおけるAIカフェロボ…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
注目
【Python】自社AIカフェロボットの組…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【Node.js】モビリティサービス開発に…
弊社が運営しているモビリティサービス事業のサービス開発をご担当いただきます <業務内容> ・…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
【UI/UXデザイナー】iOSゲームアプリ…
開発中のiOS向けゲームのUser Interface部分の導線デザインを担っていただける方を募集い…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー(iOSアプリ) |
注目
【デザイナー】マーケティング組織でのデザイ…
マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務を担っていただける方を募集いたします。 - サ…
週4日・5日
580,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー・WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【QA】自社物流プラットフォームサービスの…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【PM】アジャイル開発プロジェクトでのプロ…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトでのプロジェクトマネージメント業務 業務内容 ・チ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【Laravel】モバイルオーダーシステム…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週5日
300,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
【Ob-C】モバイルオーダーシステム開発に…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
VRライブプラットフォーム開発に向けたサー…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォーム「INSPIX」の サーバサイドの設計、開発、…
週5日
300,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
[Angular]医療領域におけるAIを活…
【具体的な業務】 ・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 ・TypeScript …
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | [Angular]医療領域におけるAIを活用した自社薬歴システム開発 |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【Ruby|フルリモート】取引所の強化やカ…
【案件概要】 暗号資産やブロックチェーンにより生まれる「新しい価値交換」、 またその次に現れる新…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Kotlin】国内最大級の入退室管理シス…
【案件概要】 ・アプリの設計・実装・検証・運用 ・他社サービスとの連携機能開発 ・プラットフォ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
急募
【Android】キャリア向けアプリの機能…
【案件概要】 某キャリア向けAndroidアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ)…
週5日
480,000〜900,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・・Android端末向けアプ… | |
定番
[PdM]ライブ配信プラットフォームのプロ…
ライブ配信プラットフォーム運営における ユーザーや運営のニーズ・KPIからの企画立案、仕様書の作成…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | [PdM]ライブ配信プラットフォームのプロダクトマネージャー |
| ‐ | |
定番
人事給与システム(COMPANY)運用支援…
◇案件詳細:人事給与パッケージ保守対応 ・メイン作業:COMPANYでの設定作業、テスト作業、本番…
週5日
570,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【Drupal】大手クライアントからの受託…
【案件概要】 弊社ではDrupal CMSを使ったシステム開発を行っております。 そのDrupa…
週3日・4日・5日
2〜4.1万円/日
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Drupal | |
注目
【Java,Kotlin】自社SaaSシス…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PL(SaaS) |
| Java・C# | |
定番
【広告】大手キャリア広告の配信事業者との折…
■大手キャリアを中心としたメディアに展開する自社SSPサービスにおいて、DSPやアドネットワークなど…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(アドテク経験者) |
定番
[Ruby]大手BtoBサービス運営企業の…
【案件概要】 今回の募集では、賃貸物件の家賃債務保証を行う事業部にて新規WEBサイト制作や 新規…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅/水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | [Ruby]大手BtoBサービス運営企業の新サービス開発業務 |
| Ruby・RubyonRails Vue ・‐ | |
定番
【フルリモ/Java/週5日】急成長経済メ…
【業務内容】 - 広告配信システムのサーバーサイド開発 - 入稿管理システムのフロントエンド開発…
週5日
520,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・Spring | |
注目
【CakePHP】ネットショップ作成サービ…
◾️ 業務内容 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気通貫でご担当いただきます ・バッ…
週5日
580,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Webアプリケーションエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【UI】AIベンチャーにおけるプロダクト開…
【業務内容】 -プロダクト開発チームにおけるUIデザインを主に担当いただきます。 -配属先は業務…
週5日
2.4〜3.1万円/日
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
急募
【PHPエンジニア】電子書籍取次システム開…
◇案件内容 : 設計から試験まで一通りの工程を対応して頂きます。 また保守対応して頂く可能性がご…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
注目
【Vue.js】自社動画制作サービスのフロ…
自社動画制作サービスの各種機能のフロントエンド開発をご担当いただきます。
週3日・4日
520,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【インフラエンジニア|クラウド/オンプレ/…
【案件概要】 自社で管理しているインフラ案件に参画していただけるのインフラエンジニアを募集しており…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿未定 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Linux】Linuxサーバーによるイン…
①BtoBビジネスのシステム開発のインフラ環境構築 (サーバ・ネットワーク・セキュリティなど。最新…
週5日
2〜2.8万円/日
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PostgreSQL・Gitlab・Docker・J… | |
定番
【iOS】キャリア向けiOSアプリの機能開…
【案件概要】 某キャリア向けiOSアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ) 大規…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Ob-C | |
定番
【Vue.js,TypeScript】テレ…
Webアプリケーション開発にご協力いただけるフロントエンドエンジニアの方を募集しております。 …
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【テスト】SaaSプロダクトを支えるテスト…
【案件概要】 SaaSプロダクトチームの一員となってソフトウェアエンジニアと一緒にテスト設計やテス…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | テストエンジニア |
定番
【機械学習】SaaSプロダクトの価値向上を…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、 プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集し…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・・TensorFlow | |
定番
【SRE】自社SaaSプロダクトを支えるS…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
定番
【フルスタック】自社SaaSサービス開発を…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | ソフトウェアエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
新着
定番
【フルリモ / QAエンジニア / 週4日…
自社クラウド型人材管理ツールのテスト設計や実施など品質に関わる様々な業務をご担当いただきます。 …
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ・ | |
定番
【PJ】FXの顧客向けシステム開発業務
【概要】 当グループ並びに、当グループ関連会社で手がける、WEBサービスの品質管理、デバックテスト…
週5日
170,000〜280,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | テスター・社内SE |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
急募
【フルスタックエンジニア】新規教育関連サー…
◇職種:Webサービス系エンジニア(フルスタック) ◇概要:新規教育関連サービスのフロント・クラウ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【ディレクター/PM】スマホアプリの新規サ…
新規プロダクトとしてスマホアプリの新規サービスを検討しております。 新規PJのため一種に考えて開発…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター/PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【PHP】大手クライアントWEBサイトのリ…
【業務内容】 サッカークラブのサイトリニューアル案件をお任せいたします! 案件を担当しているWe…
週5日
350,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【ディレクター】アフィリエイト広告の記事L…
【案件概要】 マーケティング事業部内の法人アフィリエイターチームの一員として、クライアント(法人・…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター、デザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【Go】Fintech系スタートアップでの…
お金がより自由に届けられ、より明るく楽しい世界を実現できるように、 コンシューマー向けのアプリと、…
週5日
550,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
[インフラエンジニア]AWS構築(保守/運…
●ネットスーパーシステムの開発・運用サポート: 自社パッケージのシステムであるネットスーパーシス…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西中島南方 |
|---|---|
| 役割 | [インフラエンジニア]AWS構築(保守/運用)、AWS移管 |
定番
【UIデザイン】金融機関のWEBシステムの…
【案件概要】 WEB上で住宅ローンを申し込む際のシステムなど金融機関向けWEBシステムのデザイン業…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Java/C#】マルチキャリア対応のモバ…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【Java/Typescript】自社サー…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【React,Redux】新卒採用サービス…
・当社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
注目
【Unity/C#】フィットネスMMORP…
スマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを通過と…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | Unity/C# スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity Photon Mo… | |
定番
【データサイエンティスト】行動×心理状態の…
業務詳細:旭化成では、社員の行動内容(PC操作ログ/スケジュールデータなど)と、 心理状…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【データサイエンティスト】行動×心理状態のデータ分析 |
注目
【C#】美容サロン専用顧客管理システム開発…
【企業情報】 弊社は美容業界向けにICTを駆使し、成長を続ける「美容サロン向けICT事業」、全国の…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア(WCF) |
| HTML・JavaScript・C#・WCF | |
定番
【C#】マンション修繕管理計画認定システム…
【案件概要】 お任せする仕事は、クライアント様より依頼を頂いている マンション修繕管理計画認定シ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Python】AWSを活用したインフラ保…
【案件概要】 AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
| Python | |
定番
【PdM】社内人事給与会計関連システムのP…
【業務内容】 人事給与会計関連の社内業務の効率化を目的としたシステム開発の立案から開発・運用のマネ…
週5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
注目
【Python】ニュース記事要約システムの…
今回は物流倉庫向け業務可視化システムのバックエンド開発に携わっていただける方を募集いたします。
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・FastAPI | |
定番
【Java】AI技術を使った観客参加型エン…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・・SpringBoot・・SpringBo… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート・…
【案件概要】 クライアント先の100店舗以上のチェーン店を対象としたB2B SaaSプロダクトの新…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React・Nu… | |
定番
【UI/UX】自社宿泊予約サイトの機能追加…
■仕事概要 ・宿泊予約サイトのデザイン作成、監修 ・宿泊施設向けシステムのアプリケーションデザイ…
週3日・4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー・アートディレクター |
定番
【React】自社AI発注システムの新規プ…
■具体的な業務 ・新プロダクトにおけるフロントエンドに特化した業務を担って頂きます。 ・新規企画…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【Python|自社サービス】Webアプリ…
自社で開発したサービスのバックエンド側の開発を担当いただきたいと思います。 主に要件を元に仕様作成…
週4日・5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【WEBデザイナー】自社サービスのサイトな…
【業務詳細】 ・freeeサイト全体のデザイン設計・制作業務 ・freeeがする提供するサービス…
週3日・4日・5日
190,000〜330,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| illustrator:Photoshop | |
定番
【フレックス勤務可能|Java案件】販売管…
【案件内容】 ・販売管理のシステムの開発 ・対応領域 : システム開発〜保守運用(要件定義〜基本…
週5日
330,000〜790,000円/月
| 場所 | 神奈川馬車道駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・boot、Teeda、Sea… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート】…
【案件概要】 新規機能の開発やリファクタリングだけでなく、分析結果のビジュアル化の提案やBEMを用…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Angular | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモート】自社で…
【案件概要】 既存システムへの新規機能の開発やリファクタリングだけでなく、フレームワークのアップデ…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
急募
【データベースエンジニア】ElasticS…
◇業務詳細: ニューノーマルな働き方を推進するゼロトラストセキュリティサービス実現のため、 デバ…
週5日
660,000〜900,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| ElasticStack Elasticsearc… | |
【UI/UX】自社プロダクトにおけるUI/…
【業務内容】※強みに合わせてご担当いただきます ・自社プロダクト/サービスのUI/UXデザイン …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Python】IoT・AI自社サービスの…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日・4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【Kubernetes】自社AIデータプラ…
日本最大AIコンペティションサービスやAI人材育成事業など複数のサービスを支えるSREとして、サーバ…
週4日・5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【バックエンド】自社AIデータプラットフォ…
【企業情報】 国内最大のAI開発コンペティションサイトを運営を通し、様々な業種における特徴設計やア…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【AWS】新規開発チームにおけるインフラエ…
・新規、既存サービスのインフラ構築、保守業務 ・開発チームへインフラ構成の共有 ■職務の魅力…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | AWSインフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【PM】自社モバイルPOSサービスの導入提…
具体的には以下タスクを実施していただきます。 ・カスタマイズを伴う大手顧客向け導入提案 ・S…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | 自社サービスプロジェクトマネジャー |
| PHP・Python | |
定番
【PMO】自社SaaSサービスの企画&プロ…
■ポジションの魅力・キャリアパス: プロジェクトマネジメントを通して、顧客のDX化に寄与するこがで…
週3日・4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場 |
|---|---|
| 役割 | 【PMO】企画&プロジェクトマネジメント |
定番
[Swift]クラウド型モバイルPOSシス…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | [Swift]クラウド型モバイルPOSシステムのアプリ開発 |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
注目
【講師】企業向けプログラミング研修の講師案…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | IT研修メイン講師 |
| Java・Spring | |
【AWS】リユース業界の最先端企業における…
【案件概要】 AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS認定資格 | |
【WEB】WEBコンテンツに関する制作管理…
WEBコンテンツに関する制作管理業務をお願い致します. <具体的な業務> ■WEBコンテンツ…
週1日・2日・3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅、大手町 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| HTML・Wordpress・ElementorPr… | |
定番
【Ruby】不動産業界における社内向け機関…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 東京都内だけでなく札幌、…
週4日・5日
610,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
注目
【Python】医療×AIにおけるデータ管…
【案件概要】 内視鏡動画データを管理するための、オンプレミスサーバーのサービス構築及び、その上で動…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
注目
【Python】医療×AIにおける共同研究…
【案件概要】 内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア(評価) |
| Python・PyTorch | |
注目
【Python】医療×AIにおけるデータエ…
【案件概要】 医療×AIにおける動画データを利活用するため、不要なシーンをカットしたり加工し動画の…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【PM】オンライン生放送学習コミュニティ
●業務内容 ・戦略立案(ロードマップ作成、プライシング等) ・マーケティング(市場調査、競合調査…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【AWS】転職/採用支援の自社サービスにお…
具体的な業務内容は自社で運営している人材紹介サービスの運用設計、運用、保守、監視。 ほかにも要件定…
週5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【UI/UX】自社セルフオーダーシステムの…
【案件詳細】 既存の自社サービスである、国内初のセルフオーダーシステムのデザイン業務をご担当いただ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ₋ | |
定番
【PM】SaaSサービスにおけるPMおよび…
■具体的な業務内容 ・社内のエンジニア、デザイナー、営業、CSを巻き込み、ユーザに愛され、利益を生…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
注目
【Typescript】自社サービスにおけ…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【Python,R】データサイエンスの課題…
【業務内容】 ・マーケティング領域をはじめとする、様々な分野でのデータ分析プロジェクトの遂行 (デ…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【Ruby】自社SaaSセールステックプロ…
BtoB向けセールステックSaaSフルスタックエンジニアの業務を依頼します。 【当社 のエンジ…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Python・Ruby・S… | |
定番
【Swift/Objective-C】 業…
◆業務内容 ・「ユビレジ」「ユビレジ ハンディ」をはじめとしたiOS向けネイティブアプリケーション…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・[開発言語] Objecti… | |
注目
【データベースエンジニア】OracleDB…
2022年春に向けて新規本番DB構築が2~3件、既存本番DBサーバの更改対応が2022年夏頃に向けて…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | 【データベースエンジニア】OracleDBA |
注目
VR版ミニゲームの開発案件
VRのミニゲームを開発しておりまして、今回はそのゲームの開発に尽力いただけるエンジニア様を募集いたし…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東京23区以外 保谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア |
| C# | |
【フルスタック】MEO支援SaaSの新規プ…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…
週2日・3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【React Native】オンライン医療…
ヘルスケア領域での自社プロダクト・ 他社との共同開発プロダクトのエンハンス開発をお任せいたします。 …
週3日・4日・5日
670,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | ReactNativeモバイルアプリエンジニア |
| Ob-C・AndroidJava・Typescrip… | |
定番
【Python】サーバーエンジニア(社内向…
社内向業務システムの再構築を行う 新規業務システムの開発(一般消費者向けはないが、取引先向けなど向…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋大塚 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・Vue.js・Linux… | |
定番
【TypeScript,React】Goo…
<業務内容> 複数店舗のGoogleマイビジネスを簡単に管理できる、3万店舗が利用している多店舗運…
週4日・5日
2.8〜3.6万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア(ライクル) |
| Typescript・React・Docker・AW… | |
定番
【広告代理店経験者歓迎!】携帯キャリアの広…
大手広告代理店内に常駐して広告企画、提案・マーケティング運用部隊のディレクション業務をお任せいたしま…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告マーケター/ディレクション |
定番
【JavaScript/jQuery】社内…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 東京都内だけでなく札幌、…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【JavaScript/jQuery】フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【WEBデザイナー】通販化粧品のLP制作デ…
【企業概要】 AI(人工知能)を用いて、ユーザーの感情と購買行動を分析/予測することで成果を最大化…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【データアナリスト】データ分析で自社サービ…
今回募集するのは自社サービス事業のデータアナリストとなります。 データ分析を通じて、ラクスル事業に…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データ基盤エンジニア |
| BigQuery、Redshift、Snowflak… | |
定番
【UI/UX】自社サービスの各種ガイドライ…
【業務内容】 ・ユーザーの課題解決に直結するプロダクトの理想の姿を考え、プロダクトマネージャーをは…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Figma | |
定番
【PM】自社開発や営業支援サービスなどのP…
【業務内容】 ・ユーザーインタビューやデータ分析を通じて、顧客を深く理解し、顧客の課題を把握する …
週2日・3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【PM】自社開発/営業支援サービス |
| JavaScript・PHP・Go・Cake La… | |
定番
【ディレクター】Webサイト開発のディレク…
事業内容 ブランデッドコンテンツ企画・開発、 インタラクティブコンテンツ企画・開発、 スマートフォ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ₋ | |
定番
【Ruby】急成長スタートアップ企業!ビジ…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・ | |
定番
【JavaScript】モビリティーサービ…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Vue.js・… | |
定番
【Goエンジニア】大手オンライン英会話の各…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や 改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を…
週4日・5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
PHP(Laravel)エンジニア
PHP(Laravel)、Vue、Pythonで実装されているアプリケーション API開発をメイン…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Apa… | |
定番
【マーケター】アイドル系スマホゲームのファ…
ファンマーケティングは「どうすればお客様は喜んでもらえるか」を考えながらコミュニケーションプランを企…
週5日
150,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【ディレクター】ゲーム事業のイラストディレ…
■業務内容 イラストディレクション業務 (イラストラフ作成、素材制作指示書作成業務) ・カード…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストディレクター |
定番
【Unity】新規ゲーム事業における開発構…
Unityを使用した新規開発ゲームのゲーム内のアクションバトル構築、レベルデザインなど、ゲームコンテ…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| ₋・₋ | |
定番
【Unity】2DUIアニメーションにおけ…
【業務内容】 ・運用タイトルの2DUIアニメーション全般 ・ゲーム内UIパーツアニメーションやエ…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dアニメーションデザイナー |
| ₋・₋ | |
定番
グラフィックエンジニアリーダー
Unityを使用した新規開発ゲームのグラフィックスエンジニア/描画エンジニアとしてゲームグラフィック…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックエンジニアリーダー |
定番
UIアニメーションデザイナー/ゲーム事業
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・2DUIアニメーション制作全般 ・…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIアニメーションデザイナー/ゲーム事業 |
定番
【UI/UX】ゲーム事業/クオリティリード
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト制…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 【UI/UX】ゲーム事業/クオリティリード |
定番
【UI/UX】ゲーム事業 / UI実装
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト制…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 【UI/UX】ゲーム事業 / UI実装 |
| HTML・CSS・- | |
定番
【デザイナー】2D背景コンセプトアートや設…
・2D背景アーティスト -新規開発案件にて使用される各種背景イラスト制作に関わる業務 -背…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | デザイナー |
定番
【デザイナー】ゲーム事業のバナーデザイン業…
ゲーム事業におきまして、バナーデザインをご担当いただける方を募集いたします。 ・運用施策アセッ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー(バナー制作) |
定番
【ディレクター】2Dキャライラストやアウト…
(業務内容詳細) -新規開発案件にて使用される各種背景イラスト制作に関わる業務 -背景設定をもと…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストディレクター |
定番
【Unity】新規ゲーム事業における開発業…
Unityを使用した新規開発ゲームの画面UIや2D制御など、アウトゲーム全般の実装が担当業務になりま…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| ₋・₋ | |
定番
【社内SE】インターネットマーケティング企…
【業務内容】 社内システムの開発プロジェクトにおいてkintone上に構築された既存システムの追加…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【VB.NET】人事労務系アプリのカスタマ…
◇会社概要:人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献して…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | VB.NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【Ruby,React】ソフトウェアエンジ…
分析基盤構築や運用にかかるデータエンジニアの手間を削減すべく、新機能開発、データソース(DB、広告A…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【SRE】自社プロダクトのインフラ環境の構…
弊社の全てのプロダクトのインフラ環境の構築・運用をお任せします。 採用するサービスやミドルウェア等…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE(インフラエンジニア) |
定番
[UI/UXデザイナー]ToB向け自社開発…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【Tableau】コーチング事業におけるT…
「グローバル・エグゼクティブ・コーチング・ファーム」というタイトルを掲げ、組織の経営トップおよび経営…
週3日・4日・5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Tableauエンジニア |
定番
[Perl]自社サービスサーバーサイドエン…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務 ・仕様調査 ・実装、テスト、運用・サポート ・…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | [Perl]自社サービスサーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【Ruby】教育系オンラインプラットフォー…
高等教育機関(大学・専門学校)向けのマーケティング支援SaaS等を開発するソフトウェアエンジニアを募…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby(Rails6) | |
定番
【Vue.js】自社開発案件におけるWEB…
ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして 使用すればするほど人…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【Angular】自社SaaS開発のフロン…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Ruby】自社SaaS開発のバックエンド…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・On・Rails・AWS・Asa… | |
定番
【Flutter】国内最大級スニーカーフリ…
■お任せしたい業務内容 WebViewが多く使われている現行のアプリからFlutterでフルネイテ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter | |
定番
サプライチェーンリスク管理SaaSのフロン…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PHPエンジニア|週4日~5日・一部リモ…
【案件概要】 走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただけるエンジニ…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・CakePHP・MySQL・… | |
定番
【PHP】自社サイトの追加機能の改修等
【案件内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます※ ・自社サイトの追加機能の改修等
週3日・4日・5日
150,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・PHP | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】業務の自動化ツ…
ライブコマースのプロデュースを行なっている会社様の案件になります。 手作業で行なっている業務…
週2日・3日
110,000〜170,000円/月
| 場所 | 秋葉原町屋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【SRE】次世代アフェリエイトネットワーク…
①インフラチームの立ち上げ ・弊社エンジニア部門のインフラチームを一から立ち上げ ②新規ASP…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| SQL・Linux・MySQL・AWS・Nginx | |
定番
【Ruby】次世代アフェリエイトネットワー…
「サービスを1から作ってみたい」 「組織と共に自分の力を大きく伸ばしていきたい」 「ベンチャー企…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・j… | |
定番
【Android】自社動画サービスにおける…
弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発、機能追加、保守運用業務を担当していただきます。
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【スクラムマスター】データドリブンシステム…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Kotlinエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【未経験歓迎!】企業向けプログラミング研修…
【セミナー開催】 下記案件内容におけるセミナーを開催いたします。 ご興味ある方はお気軽にご連絡く…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | IT研修メイン講師 |
| Java・Spring・Java | |
定番
【Javascript】自動車業界のコーデ…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML、CSS、JavaScriptを利用し、サ…
週3日・4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBコーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
インフラエンジニア(東証一部上場/ソフトウ…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle SQL Cassandra | |
定番
【PM】東証一部上場企業のインフラ運用・保…
自社インフラにPMとして携わって頂くポジションです。 自社インフラ保守、構築・開発のチームの …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【コンサル】DXプロジェクト推進とベンダー…
業務例) ・デジタル技術(EC、AI、BI、BA等)を駆使した新しい事業領域やビジネス分野における…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | ITコンサルタント(DX推進担当) |
定番
【PM】企業向けマネジメント作業
◇作業内容: ユーザのニーズをまとめて、ベンダーへ提示。 社内システムの全体的な見直しの検討…
週5日
480,000〜520,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・開発系で上流工程の経験(PM・PL・PMO) ・… | |
定番
【shopify/EC-CUBE】受託EC…
個人事業主から中小企業、そして当社のEC-CUBEのトップベンダーやShopifyエキスパート獲得に…
週4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | shopify/EC-CUBEエンジニア(EC) |
| shopify・EC-CUBE | |
定番
フロントエンジニア(GCPリーディングカン…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週1日・2日・3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア(GCPリーディングカンパニーでのクラウドサービスの開発) |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Java】GCPリーディングカンパニーで…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア/Java |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring Sp… | |
定番
【インフラエンジニア】AzureAD SS…
[案件概要] MS-Teams電話機能の本社展開作業 技術検証・MSプレミアム窓口問合せ対応など…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 豊洲有明駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
☆フルリモ可☆【ECディレクター】大手企業…
定額制ECサイト制作サービスのディレクション業務をお願いします。 クライアントの商品の売り上げがあ…
週4日・5日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター(ブランド直販グループ) |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PdM】某生保向けチャットボットシステム…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| ‐ | |
定番
【GOエンジニア】暗号資産取引サービスのデ…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【GOエンジニア】暗号資産取引サービスのディーリングシステムの開発・保守 |
| Go・Oracle MySQL Jenkins … | |
定番
【マーケター】EC顧客層へのデジタルマーケ…
弊社は複数の事業を開発し運営しているチームです。 SNS広告事業、コンテンツマーケティング事業、越…
週4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
定番
【Flutter/iOS/Android】…
【業務内容】※詳細は、ご面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社案件の設計・開発および、オフショ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【PHP】外食業向け業務改善プラットフォー…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【PM】外食業向け業務改善プラットフォーム…
弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおいて、業界ならではのニーズや要望をキャッチア…
週4日・5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】行政・自治体向けネットワーク構築の…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただける …
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
☆フルリモ可☆【ECディレクター】大手企業…
EC運用支援グループでディレクター業務をお願いします。 クライアントの楽天とPaypayモールの運…
週4日・5日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター(ECモール運用支援案件) |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【iOS/IoT】国内最大のタクシー配車サ…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週4日・5日
2.7〜4.4万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・GitHub・bitrise・Slack… | |
定番
【PHP】情報システム部門での社内基幹シス…
【業務内容】 弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます 生産現場か…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア(社内システム) |
| PHP・CakePHP、Laravel・AWS | |
定番
【Node.js】教育系サービス開発におけ…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日・4日・5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【TypeScript】脳科学×AIプロダ…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのフロントエンド開発をご担当いただきます ・U…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ/ Scala, Python/…
【担当業務】 - 脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発 【案件の魅力】 - 脳神経疾…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・Scalat… | |
定番
【QAエンジニア】脳科学×AIプロダクトに…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます ・弊社が提…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【React.js】大企業のクライアントと…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日・5日
660,000〜1,340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(テックリード) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【Swift】大企業のクライアントと共に5…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日・5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【Kotlin】大企業のクライアントと共に…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日・5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア(Kotlin) |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【TypeScript】大企業のクライアン…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日・5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア(TypeScript) |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【Go】大企業のクライアントと共に5000…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日・5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア(Go) |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【自社サービスのフルスタックエンジニア】ス…
■チーム内の管理機能の向上 用具管理 資金管理 プレーの動画配信 ■チーム外に向けた情報の発…
週4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・React・-・Java… | |
定番
【リモートワーク可】Google Clou…
2021年4月に大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。「クラウドで日…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモートワーク可】Google Clou…
2021年4月に大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。「クラウドで日…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【Python】B2C Webサービス開発…
【業務内容】 B2C Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には…
週5日
470,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【映像制作】遊技機制作の映像制作デザイナー
【案件概要】 ぱちんこ・スロット遊技機の映像演出制作に関わるコンポジット/3D・2D映像作成ツール…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作 |
| AfterEffects | |
定番
【3Dデザイナー】遊技機制作の3Dデザイナ…
【案件概要】 ぱちんこ・スロット遊技機の映像演出制作に関わる3D/2DCGツールを使用したアニメー…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| AfterEffects | |
定番
【新規プロジェクトゲームエンジニア】クライ…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向け ゲームのアウトゲーム全般の…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | 【新規プロジェクトゲームエンジニア】クライアントサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4 Perfo… | |
定番
【週5/フルリモ】自社サービスのサーバーサ…
自社プラットフォームサービスにおいて、サーバーサイドKotlinでの開発をご依頼いたします。 …
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Kotlinエンジニア |
| Kotlin・GCP・AWS・【開発環境】 フロン… | |
定番
【Webデザイナー】BtoB、コーポレート…
お客様の課題解決として、Webサイト構築・Webシステム開発や、効果的なプロモーションツールの制作を…
週2日・3日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋今池駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ■その他 勤務形態:フルリモート 稼働時間:10… | |
定番
[Java]社内DX促進のための基幹システ…
社内基幹システム(求人や求職者のDBとしての役割、マッチング機能、売上管理ができるシステム)の追加開…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Vue.js MySQL VBScri… | |
定番
【ディレクター/マーケター】大手百貨店オン…
【企業概要】 弊社は某大手百貨店のグループとして、主に百貨店がもつ媒体やオンラインストアなどのマー…
週1日
70,000〜90,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター、マーケター |
定番
【エフェクトデザイナー】エフェクト制作専門…
【案件概要】 ゲームのエフェクトを専門で制作している企業にて受託をしているエフェクト作成の案件へご…
週1日・2日・3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 3Dエフェクトデザイナー |
定番
【Go】新規スポーツマーケットプレイスのサ…
【案件概要】 新規スポーツマーケットプレイスのサーバーサイド開発をリご担当いただくエンジニアを募集…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【C/C++】遊技機の組み込み、制御エンジ…
【案件概要】 弊社で請け負っている遊技機の開発及び制作を行う制御エンジニアとしてご活躍いただきます…
週1日・2日・3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【AWS】インフラ運用・構築ベンダー企業で…
【業務内容】 パブリッククラウドに構築したインフラをIaCを用いて構築、改善をご担当いただきます。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Terraform | |
定番
【Kubernetes】インフラ運用・構築…
担当業務例 ・ Jenkinsで稼働しているジョブをTekton(Kubernetes)に移行…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア/kubernetes |
| kubernetes | |
定番
【DTP】飲食専門のデザイン制作会社におけ…
大手チェーン店を中心に、年間1,500店舗以上の飲食店向けグラフィックツールを企画・制作している会社…
週4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー・DTPデザイナー |
| Photoshop illustrator | |
定番
自社サービスにおける開発ディレクション業務
【概要】 当グループ会社のお客様が利用するアプリケーションの動作や、各種ツール、Webサービスの環…
週5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【SharePoint】NotesからSh…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます。 ・NotesからSharepoint移行 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | SharePointエンジニア |
定番
自社サービスにおけるソフトウェアの開発
【募集要件】 製造、物流、医療、スポーツ等、様々な分野で画像処理を中心としたセンシングソリューショ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| Python・C・C++・C# | |
定番
【Ruby】自社転職サイトのRubyエンジ…
【会社概要】 弊社は、士業・管理部門に特化した転職サイトです。 求人選定から内定承諾まで、本…
週2日・3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Typescript】BtoC自社サービ…
【案件概要】 フロントエンドエンジニア/UXエンジニア/マークアップエンジニアとして、ユーザーやサ…
週1日・2日・3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PM】バーチャルカラオケ配信プラットフォ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのプロジェクトマネージャーを担当いただきます。 ▶ …
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PdM】バーチャルカラオケ配信プラットフ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのプロダクトマネージャーを担当いただきます。 ▶ 業務内…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(PdM ) |
定番
【Webディレクター】バーチャルカラオケ配…
【案件概要】 バーチャルカラオケ配信プラットフォームのディレクターを担当いただきます。 ▶ …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【マーケター|フルリモート】バーチャルカラ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのマーケティング責任者を担当いただきます。 ▶ 業務内容…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(事業責任者) |
定番
【Java】生保更改プログラム開発
【案件概要】 生保更改プログラムの開発 プログラミング作業をメインでご対応いただきます。 言語…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 東京23区以外多摩センター |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・・Javaの開発経験(一人でプログラミング… | |
定番
【システム】ERP導入支援
【案件概要】 ERP導入支援をご対応いただきます。 ①移行方針(移行手法、移行データ、移行元、過…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | ERP導入支援 |
| ・移行方針・移行要件を自律して考えてアウトプットでき… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】国際財務システ…
【案件概要】 リース取引管理システムの改善・保守 (主な機能) 取引受払管理(取引、利息額の入…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL・PowerBuilder 2017R2 | |
定番
【クラウドエンジニア】FX取引システム維持…
【案件概要】 FX取引システム維持保守支援業務になります。 ・FX(外国為替証拠金取引)関連…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| C#・AWS | |
定番
【SAP】基幹システム刷新
役割:Fiori開発経験者 内容:既にある6画面の修正。画面制御強化。
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | ABAPエンジニア |
| ABAP | |
定番
SAP導入プロジェクト(機械部品製造業)
ロジ系/FI系コンサル要件定義から行っていただく案件になります。 【マスタスケジュール】 2…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | SAP導入プロジェクト(機械部品製造業) |
定番
SAP導入プロジェクト(半導体製造)
COコンサルから行っていただく案件になります。 【マスタスケジュール】 22年4月~要件定義…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | SAP導入プロジェクト(半導体製造) |
定番
【システム】mcframe導入支援
【案件概要】 製造業向けシステムに関するmcframe導入の支援プロジェクトになります。 mcf…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿首都圏各駅 |
|---|---|
| 役割 | 【システム】mcframe導入支援 |
| mcframe7・・業務システム設計・開発経験 | |
定番
[インフラエンジニア]サーバーの自動構築化
既存サーバーの自動構築のためのAnsible化をしていただく 該当サーバーは ・構築手順書がある…
週3日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ansible | |
定番
【インフラ・Java】法人、ITスクール向…
・CCNA/LPIC資格取得の個別指導 ・Java等の開発に関する個別指導 ・法人向けセミナー対…
週1日・2日・3日・4日・5日
2〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラ・開発研修講師 |
| Java | |
定番
【マーケター】デジタルマーケティングベンチ…
【案件概要】 リスティング広告・ディスプレイ広告・SNS広告の運用業務をご担当いただきます。 …
週2日
120,000〜150,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
| ・Web広告媒体運用経験・・・レポート ・クリエイ… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】個人向けローン…
【案件概要】 個人向けローンサービス保守・開発支援 ①ライブラリアン作業 本メインに、ユ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・VBA・SQL・svn Jenki… | |
定番
【Go】電子契約サービスのGoエンジニア
自社で開発をしている電子契約サービスのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 【開発環境】 …
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Lin… | |
定番
【Vue.js】電子契約サービスのフロント…
【案件概要】 自社で開発をしている電子契約サービスのフロントエンド開発をご担当いただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【インフラエンジニア】自社サービス開発
Amazon ECSやサーバーレスアーキテクチャーを活用して、月間広告流通額100億円規模の広告プラ…
週5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Ruby】自社広告プラットフォームサーバ…
月間広告流通額100億円規模の広告プラットフォームのサーバーサイド開発をしていただくポジションです。…
週5日
2〜2.4万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・- | |
定番
【データサイエンティスト】自社サービス開発
月間広告流通額100億円規模の広告プラットフォームのデータ分析・課題抽出・改善に向けた取り組みをして…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL・R・- | |
定番
【Cisco】ネットワークエンジニア
ネットワーク機器の選定・セットアップから運用までを担っていただきます。 【稼働条件】 勤務時…
週5日
1.6〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Cisco | |
定番
【マーケター/ディレクター】自社のコミュニ…
業務内容】 ・消費者心理を踏まえた、LINEチャットボットの会話シナリオのデザイン〜ペルソナ設計 …
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター/ディレクター |
定番
【Ruby】急成長中クラウドファンディング…
ローンチ以降成長を続けている当社のクラウドファンディングサービスにおいて、 E2Eの構築~シナリオ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【自社メディア事業立ち上げ】WEBデザイナ…
テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…
週3日・4日・5日
1.9〜2.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【自社メディア事業立ち上げ】Wordpre…
テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…
週3日・4日・5日
1.9〜2.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Backendエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【自社メディア事業立ち上げ】WEBディレク…
テレマーケティングを中心に保険代理店事業を全国展開しています。インターネットメディア立ち上げ時に関わ…
週3日・4日・5日
1.9〜2.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
フルスタックエンジニア
【仕事内容】 得意領域を活かしながらバックエンド〜フロントエンド、インフラなど開発環境の整備まで全…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フロントエンド】大手企業のWEBサイト制…
受託しているWebサイト更新・開発業務を行っていただきます。 ・業務内容はCMS(MT)での更…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【フルリモ/ Javaエンジニア/ 週5日…
【担当業務】 - 大規模決済プラットフォームのデジタル化案件のサーバーサイド開発 【案件の魅…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Springboot TERASO… | |
定番
【PHPエンジニア】大手印刷会社におけるW…
某大手印刷会社において、WEBサービスの開発PJに携わっていただきます。 ※詳細は面談時に説明いた…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・cakePHP Git | |
定番
(Rubyエンジニア)小説投稿サイト企業の…
リーダーの配下でRubyを中心に運用及び開発業務を担当して頂く想定ですが、リーダーと一緒に A社シ…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails(バージョン5.… | |
定番
【リモート可 / React/TypeSc…
自社プロダクトの新規機能追加開発をお願いできるフロントエンドエンジニアを募集いたします。
週4日・5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
自社マッチングサービスのUIデザイナー
今回は下記2ポジションのいずれかでデザイナー募集を検討しております。 ①現在開発中の新規プロダ…
週3日・4日・5日
1.2〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【Kotlin】自社デジタルチケットサービ…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【Java】某エネルギー系卸売業向け基幹シ…
・JavaによるWebシステム (基本ウォーターフォール開発。一部アジャイル開発あり。) スケジ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Java/サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【SQL】損保会社向けDWH刷新PJ
現行のホストシステムを存続しながら、新規でホストシステムを刷新していきます。 データ移行はせず、新…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | SQL/エンジニア |
| SQL | |
定番
【Node/Typescript】バックエ…
■具体的な業務 ・管理コンソール開発のバックエンドを中心にした開発業務を担って頂きます。 ・バッ…
週5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Python・Typescript・Node.js | |
定番
【フロントエンド】DXサービスのフロントエ…
開発チームにて、自社プロダクトの開発業務に関わっていただきます。 【業務詳細】 - ユーザーの体…
週3日・4日・5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋新豊田 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【マーケター】地域政策×Tech領域におけ…
【業務内容】 ・ユーザー獲得のKPI達成のための戦略設計/実行/改善 ・社内の他メンバーとのテキ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | カスタマーサクセス |
定番
エンタメ業界でのプロモーション支援、広告制…
エンタメ業界に特化した事業展開をしています。 メイン商材は、YouTubeCMなどのWEB商材のほ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー・動画制作 |
定番
バックエンドエンジニア(リードエンジニア)
大量営業リストを使ったセールス活動を従来のExcel管理から卒業し、プレリードを一元管理するサービス…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・・Ruby… | |
定番
【インフラ】自社業務システムにおけるインフ…
■業務詳細 当社の情報システムグループにて、全社の業務システム全般の統括管理に携わっていただきます…
週5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝浦駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【バイク事業】経営企画 / データ分析業務
経営戦略等を考える当社のマーケティンググループにて、下記業務をご依頼いたします ①経営情報の可視化…
週5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝浦駅 |
|---|---|
| 役割 | 経営コンサルタント・データアナリスト |
定番
【Java】株式システムの外部接続先との接…
・金融商品取引業者の会員システム開発業務 ・国内株式に関する新規サービスの構築及び、既存システムの…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・・Eclipse ・SVN ・Git … | |
定番
【salesforce】Salesforc…
Rails、Apexを用いたSalesforceと外部サービスとの連携・接続の開発業務をお願い致しま…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | salesforceエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails | |
定番
[PM]SAP基幹システムの物理・仮想サー…
[案件概要] SAP基幹システムの物理・仮想サーバの運用プロジェクトのPM業務になります。 シス…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 豊洲大島駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| SAP・JP1・HULFT | |
定番
[インフラエンジニア]SAP基幹システムの…
[案件概要] SAP基幹システムの物理・仮想サーバの運用プロジェクトのPM業務になります。 シス…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲大島駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SAP・JP1・HULFT・VMware・Stora… | |
定番
【ゲームプランナー】メタバース系ゲームの各…
【案件】 メタバース系ゲームの各種プランニング 【内容】 ユーザーの配信/視聴をモチベート…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件による |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
【AWS/GCP】自社プロダクト開発会社に…
【仕事内容】 ・自社サービスiOS/Androidアプリのバックエンド(Firebase)の設計・…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| GCP・AWS・Docker・Kubernetes | |
定番
【React.js/TypeScript】…
大手ヘルスケアメーカー新規プロジェクトのフロントエンド開発リーダーをお願いします。 日本の開発リー…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Kotlin】自社モビリティサービスのア…
自社のモビリティサービスの制作でFigmaを利用したデザイン及びKotlinを利用したタブレット、ス…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(UI/UXエンジニア) |
| JavaScript | |
定番
【C++,Python】脳科学×AIプロダ…
▼具体的な業務内容 ・脳画像データの処理・パイプラインの開発 ・機械学習・深層学習モデルの設計及…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Scala・C++・Python | |
定番
【Webディレクター】自社動産取引サービス…
今後サービスをグロースしていく上でWebディレクターとして、サービスの改善・新規機能の追加など、日々…
週2日・3日・4日・5日
160,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ₋・Flutter | |
定番
【UI/UX】美容医療関連のアプリケーショ…
▼具体的な業務内容 ・サービスの抱える課題の発見とそれを解決する施策やコミュニケーション方法の検討…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | webデザイナー(UI/UX) |
定番
【Kotlin】アプリエンジニア
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日・5日
660,000〜1,340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア(Kotlin) |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【データ分析】投資サービスに関する分析~提…
受託プロジェクトにて少額で株式投資ができる投資サービスの マネタイズアイデアの企画検討をご支援いた…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | 【PM】大手通信会社案件のPM業務 |
| 分析スキル・ディレクションスキル・PPT | |
定番
【Webデザイナー】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアにおいて、デザイン業務を行っていただきます。 ・バナー、LPなどのビジ…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー(DELISH KITCHEN) |
| Adobe・Photoshop・Illustrato… | |
定番
【Go】日本最大級の料理動画メディアにおけ…
具体的にお任せする業務 ・GoでのAPI設計・開発 ・AWS/GCPにおけるサーバ構築・運用 …
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS・GCP | |
定番
【Android/Java】日本最大級の料…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・・Kotlin… | |
定番
【Javaエンジニア】Webアプリケーショ…
【案件概要】 Webアプリケーションシステム開発・保守対応プロジェクトなります。 ≪主な作業…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸江坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Swift・Ob-C… | |
定番
【Java/Python】データ利活用ソリ…
下記業務にご参画いただけるエンジニア様を募集いたします。 ・データ利活用関連のプラットフォーム…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java/Python) |
| Python・Java | |
定番
【JavaScript】介護系自社サービス…
今回は介護系自社サービスのフロント周りを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていただき…
週5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【C++】UEを使ったゲームソフト制作(ス…
【会社概要】 ゲームソフトの企画・開発を行っています。 【業務概要】 次世代機向けのコンシュー…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅、田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UE4・UE5 | |
定番
[バックエンドエンジニア]介護系自社サービ…
今回は介護系自社サービスのバックエンド周りを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていた…
週5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| PHP・Laravel、FuelPHP | |
定番
[PM]介護系自社サービス/開発チームのマ…
今回は介護系自社サービスの開発マネジメント及び、 実際に手を動かしプロダクトを推進する担当をお願い…
週5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | エンジニアリングマネージャー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【シナリオライター】新規IPタイトル ・既…
【会社概要】 ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | シナリオライター |
定番
【背景イラストレーター】人気アイドル系IP…
【会社概要】 ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 背景イラストレーター |
定番
【Flutter/iOS/Android】…
【業務内容】※詳細は、ご面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社案件の設計・開発および、オフショ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【セキュリティエンジニア】事業会社でのAI…
【案件概要】 IPOを視野にいれた社内ネットワークやシステム及び、自社開発をおこなっているAI製品…
週5日
480,000〜680,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【Web/グラフィック】受託Webサイト・…
【業務内容】 ・Webデザイン/グラフィックデザイン └Webデザイン:弊社では様々な業種のお客…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Web &グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【AWS】音楽コンテンツ販売における開発
【業務期間】2022年5月~ 【精算幅】140‐180h
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
定番
【Ruby】マーケティングプラットフォーム…
■期間:5月~ ■面談:1回or2回 ■場所:フルリモート ■環境: フロントエンド:…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【SQL】プロダクト導入開発
【業務内容】 マーケティング施策要件を叶えるためのシステム構築、データ連携の設計に携わっていた抱け…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| HTML・SQL | |
定番
【PHP】イベント用サイトの開発
【業務内容】 イベント用サイトの開発に携わっていただけるエンジニアの方を募集いたします。 ※業務…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL | |
定番
【C#】デジタル広告企業での新規自社サービ…
当社グループでは、2007年設立当初に開始したインターネット広告事業を中心としたBtoB事業、Bto…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| CSS・JavaScript・C#・Typescri… | |
定番
【PM】給与支払いサービスのシステム開発
【業務内容】 ・開発プロジェクトの進行管理 ・内部/外部の組織との間の円滑な業務コラボレーション…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Spring・Boot | |
定番
クラウド基盤デリバリ・SREおよび技術整備…
大手SIerのクラウド技術部隊にて、新規または更改案件のデリバリ、SRE、 および社内の技術整備活…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウド基盤デリバリ・SREおよび技術整備支援 |
| AWS・Azure・GCP | |
定番
アプリケーション開発におけるテスト設計・自…
大手SIerの開発環境モダナイズ支援部隊におけるテスト高度化チームにて、 エンドユーザやPJ主管で…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリケーション開発におけるテスト設計・自動化支援 |
| Jenkins・Klocwork・SonerQube… | |
定番
【社内SE/PHP】受託開発会社の上流工程…
■業務概要: 要件定義から開発業務をメインで行って頂きます。 顧客管理システムを中心に、「H…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 品川祐天寺駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE・PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
CI/CDプロダクトを活用した基盤運用自動…
大手SIerにおける開発環境モダナイズ部隊の基盤運用自動化チームにて、エンドユーザや社内他事業部に対…
週5日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | CI/CDプロダクトを活用した基盤運用自動化支援 |
| Ansible・Puppet・Serverspec・… | |
定番
【フルスタックエンジニア】美容医療関連のア…
容医療自体の体験向上のために、 ユーザーが利用するクリニック・口コミ検索のアプリやクリニックが利用…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【Kotlin】美容医療関連アプリケーショ…
美容医療自体の体験向上のために、ユーザーが利用するクリニック・口コミ検索のアプリやクリニックが利用す…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・CircleCI | |
定番
【PdM】美容医療関連アプリケーションのプ…
▼主な業務内容 ・プロダクトの抱える課題の発見とそれを解決する施策の立案 ・プロダクトのロードマ…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトマネージャー(PdM) |
定番
【Java】通信キャリア向けアプリ開発案件
Javaにてwebアプリケーションの開発を進めております。 主な担当業務として、製造工程からテスト…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川青物横丁駅 |
|---|---|
| 役割 | 通信キャリア向けアプリ開発案件 |
| Java | |
定番
【React/AWS】新規サービスにおける…
会計パッケージソフトを開発しているお客様内にて、 新規サービス開発の検討をしております。 今回は…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート駅 |
|---|---|
| 役割 | 新規サービスにおけるアプリ開発案件 |
| JavaScript・C#・Typescript・R… | |
定番
【AWS Glue】新規サービスにおける基…
会計パッケージソフトを開発しているお客様内にて、 新規サービス開発の検討をしております。 今回は…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート駅 |
|---|---|
| 役割 | 新規サービスにおける基幹システム開発案件 |
定番
【TypeScript/Java】大手放送…
大手放送局内で動画配信サービス向けに広告システムの新規開発を進めております。 新規開発となりますた…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート駅 |
|---|---|
| 役割 | 大手放送局広告システムの新規開発(フロントエンジニア) |
| Typescript | |
定番
【TypeScript/Java】大手放送…
大手放送局内で動画配信サービス向けに広告システムの新規開発を進めております。 新規開発となりますた…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート駅 |
|---|---|
| 役割 | 大手放送局広告システムの新規開発(サーバーサイドエンジニア) |
| Java・Go | |
定番
【PM】外部サーバーセキュリティシステムの…
弊社でお取引のある証券企業にて、外部サーバーセキュリティシステムの導入支援ができるPMの方を募集して…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java】某アルバイト求人サイトの開発案…
Java開発/設計/レビュー ・基本/詳細設計の経験(レビュアーとしてしっかりと設計業務を行った経…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【AWS】インフラ運用・構築ベンダー企業で…
【業務内容】 ・サービス(プロダクト)毎の現状を把握し、最適な運用を考える ・OSのアップデー…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS) |
| Terraform・AWS | |
定番
【Java】開発エンジニア
【仕事内容】 主に当社が運営するWebサービスの開発、運用をお願いします。 99%を内製化してい…
週5日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・PlayFramework・RubyonR… | |
定番
【HTML/CSS】フロントエンドエンジニ…
【仕事内容】 当社グループで運営するWebサイトの制作・運⽤業務をお任せいたします。(PC・スマー…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【HTML,CSS,Javascript】…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます ・HTML、CSSのコーディング(一部、JQu…
週4日・5日
250,000〜380,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Django,Vue.js】アジャイル開…
1) Djangoを用いたバックエンドの設計・実装 2) Vue.jsを用いたフロントエンドの設計…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | シニア開発エンジニア |
| JavaScript・Python・Django・V… | |
定番
【AWS】クラウドインフラの設計、構築案件
・AWSなどのクラウドソリューションを用いたクラウドインフラの設計・構築案件。 -位置情報システ…
週5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【AWS】クラウドインフラの設計、構築案件
お客様のサービス立ち上げに伴い クラウド共通基盤内における新システムの実装が進行中。 こちらのゲ…
週5日
3.2〜4.5万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
[テックリード]介護系自社サービスのシステ…
今回は当社メインサービスである「みんなの介護」各サービスのバックエンド周りを担当いただきます。 詳…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | テックリード |
| HTML・JavaScript・PHP・React・… | |
定番
【PL】帳票・書類電子化(業務DX)のプラ…
大手建設業における帳票・書類電子化(業務DX)のプランニングフェーズを支援。 ペーパーレス・ハンコ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【SAP】SAPの導入プロジェクト
【業務内容】 SAPの導入プロジェクトにご参画いただける方を募集いたします。 ※業務の詳細に関し…
週3日・4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ITコンサル |
| -・ | |
定番
【PMO】ヘルプデスク運用業務
【業務内容】 ヘルプデスク運用業務に携わっていただけるPMOの方を募集いたします。 ※業務内容の…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京金町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルスタック】新規SaaSサービスのウェ…
完全リモート勤務の旅行系ベンチャーでのSaaS化に向けた新規サービス開発案件 ■開発内容 ・…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【データエンジニア】事業会社での動画編集ツ…
内視鏡動画データを利活用するため、不要なシーンをカットしたり加工し動画の整理を行うためのツール開発や…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【サーバーエンジニア】事業会社でのオンプレ…
内視鏡動画データを管理するための、オンプレミスサーバー(4台程度)のサービス構築及び、 その上で動…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーエンジニア |
| Python・Flask・Ansible・SQLAl… | |
定番
【Python】事業会社での内視鏡AIモデ…
内視鏡AIの製品開発に関連した画像分類・認識モデルを作成するためのモデル開発および周辺のデータ整理や…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask・Ansible・SQLAl… | |
定番
[QAエンジニア]介護系自社サービスの品質…
今回は介護系自社サービスのQAエンジニアを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていただ…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
[インフラエンジニア]ToB向けソフトウェ…
<業務内容> ・新規サービス時の環境増築、また既存インフラ環境の負荷検証、および体制構築検討 ・…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・AWS・でのWEB・サービス・インフラの全体構築 … | |
定番
[コンテンツディレクター]自社メディアコン…
今回は当社メインサービスで各種サービスのメディアコンテンツ設計を担当いただきます。 詳細部分は…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | コンテンツディレクター |
定番
【node.js】アーティストファンクラブ…
アーティストファンクラブアプリの設計・開発を担当していただきます。
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・node.js | |
定番
[Rubyエンジニア]自社サービス開発/運…
自社サービスの開発~運用保守をお願いいたします。 【開発環境】 ・Ruby on Rails…
週5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【PHP】 業界トップクラスの実績を有する…
業務拡大中の自社運営サービス(予約システム)の新機能開発及び既存機能の改修をご担当頂きます。 …
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP・AWS・PostgreSQL・Git… | |
定番
[UI/UX]業務拡大中の自社運営サービス…
業務拡大中の自社運営サービスのデザイン企画・制作、UIUXブラッシュアップなどデザインに関する業務全…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町国会議事堂前駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【Python/データ分析】接客自動化プロ…
【案件概要】 大手通信会社での参画 ・接客の自動化に向けて 接客に関する音声、テキストデータの整…
週5日
500,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS・Linux | |
定番
[SRE]ToB向けソフトウェアサービス
【業務内容】 社内の開発チームや外部チームと共に、サービスへの迅速な新機能の追加と安定稼働を両立す…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| AWS | |
定番
[サーバーサイド]ToB向けクラウドアンケ…
【業務内容】 ToBe向けソフトウェアサービスのバックエンド開発・運用をしていただきます。 実装…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【Laravel,Vue】企画管理システム…
企画管理システムの開発に携わっていただける方を募集いたします。 化粧品メディアが企画する各種企…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 秋葉原小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(Laravel,Vue) |
| JavaScript・PHP・Laravel Vu… | |
定番
[Next.js/Typescript]T…
【業務内容】 ToBe向けソフトウェアサービスのフロントエンド開発を中心に携わっていただきます。 …
報酬額非公開/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・RubyonRails・Jav… | |
定番
【PM】ToB向けソフトウェアサービス
【業務内容】 各種ステークホルダーとコミュニケーションを通じて設計を行い、プロダクト・ユーザー・ビ…
報酬額非公開/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
[QAエンジニア]クラウドアンケートシステ…
・心理的安全性構築に対する意識が高く、コミュニケーションが丁寧で、チームのメンバーがお互いに率直な意…
報酬額非公開/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・・・An… | |
定番
[アライアンスマネジャー]ToB向け連携サ…
・心理的安全性構築に対する意識が高く、コミュニケーションが丁寧で、チームのメンバーがお互いに率直な意…
報酬額非公開/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | アライアンスマネジャー |
定番
【DTPデザイナー】金融機関、保険会社パン…
○会社案内/販促ツールの企画・制作 ○パブリシティの企画・実施 ○インターネット広告の企画制作
週4日・5日
150,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野駅 |
|---|---|
| 役割 | DTPデザイナー |
定番
【インフラ】監視パラメータの設計、設定、設…
主に次の業務内容をチームで取り組みます。 ・ 監視パラメータの設計、設定、設定変更 ・ 電話…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(監視運用) |
| Terraform | |
定番
[Webエンジニア]自社クラウドサービスの…
【案件概要】 フルサイクル/フルスタックに開発を行っていただくリードエンジニアとして期待しておりま…
週4日・5日
760,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町(千代田区) |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
[WEBデザイナー]日本最大級の料理動画メ…
■具体的な業務内容 ・デザインプロセス全体の設計、戦略立案 ・ユーザー体験を考慮したUI設計 …
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー(TIMELINE) |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【Webデザイナー】Webデザイン制作
【業務詳細】 ・Webデザイン制作 Illustrator、PhotoshopでWebデザインを…
週2日・3日・4日・5日
150,000円以上/月
| 場所 | 千葉都賀駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【インフラエンジニア】自社プロダクト(B2…
自社プロダクト(B2B向けサービス)のプロダクト運用保守+一部バックエンド改修+オンプレサーバ移設&…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台勾当台公園駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 使用OS:centos・rocky・linux・am… | |
定番
【Python/Ruby】自社プロダクト(…
自社プロダクト(B2B向けサービス)のプロダクト運用保守+一部バックエンド改修+オンプレサーバ移設&…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台勾当台公園駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・AWS利用サービス(主な):… | |
定番
電子書籍のクリエイティブ制作
大手電子書籍クライアントの広告webバナー、LPの作成をお願いします!
週4日・5日
1.2〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【PL】大手エンタメ会社ゲームのインフラ構…
大手エンタメ会社において、スマホ・PC・アーケードゲームの 新タイトルゲームのリリースや大規模なゲ…
週5日
830,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【PMO】大手金融会社向けPMO業務
【業務内容】 ・英語を使ったPMO業務を担っていただける方を募集いたします。 Lステークホルダー…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【テストエンジニア】仮想通貨サービス開発担…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | テストエンジニア |
定番
【Webデザイン】メディアデザインとUI改…
・web メディアのサイトデザイン (携わる別部署との企画 MTG への参加) ・メディ…
週4日・5日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー・メディアデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【PMO】教育系DX案件における導入サポー…
【業務内容】 上位で受託している教育系DX案件にて、大小プロジェクトの導入部分で 導入サポートを…
週5日
590,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO(PM補佐) |
定番
【Kotlin】幅広いプロダクトにチャレン…
【業務内容】 経験実績豊富なメンバーと幅広い業界のアプリやWebサービスの作成する同社にて スマ…
週5日
590,000〜760,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【インフラ】サーバーの移行・監視業務
【案件概要】 サーバーの監視や、サーバーの移行業務に携わっていただける方を募集いたします。 ※業…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【サーバサイドエンジニア】暗号資産取引所の…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【java/C#】ERPの導入支援
NetsuiteのERP導入のために現在取り組みを行っており、進行が思うように捗らない状況です。 …
週5日
500,000〜690,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋中畑駅 |
|---|---|
| 役割 | ERPの導入支援 |
| Java・C# | |
定番
【PM】全国旅行支援事業 プロジェクトリー…
▽業務内容 要件定義や各種マネジメントを行っていただきます。 既存のGOTOトラベル事業でかなり…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(全国旅行支援事業プロジェクトリーダー) |
定番
【Java/Scala】ToB向けソフトウ…
当社製品におけるサーバーサイドエンジニアとして参画いただきます。 ・サーバーサイドにおけるWeb …
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・C・C++ | |
定番
【PHP】自社営業支援プラットフォーム開発…
営業のプロフェッショナル向けプラットフォーム開発案件になります。 営業戦術と働き方の新時代を創り出…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
[フロントエンドエンジニア]ToB向けソフ…
<業務内容> ・自社Web Applicationのフロント周りの設計/開発/テスト/運用 ・負…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・HTML、C… | |
定番
家具インテリア系専門の広告代理店でのLPデ…
Illustrator、Photoshopでインテリア系のLPデータを制作していただき、WordPr…
週3日
120,000〜140,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【PHP】プラットフォーム開発案件
<概要> プラットフォーム開発案件になります。 <開発環境> ・フレームワークはLarav…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel、Vue… | |
定番
【WEBデザイナー】WEB広告関連のデザイ…
制作物 広告バナー・広告物の制作がメインとなります。 目的を達成するためのターゲット設定から訴求軸…
週2日・3日・4日・5日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【React 】保険DXのSaaS開発
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのフロントエンド開発になります。 ・保険事業会社向け…
週2日・3日・4日・5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Vue.js・An… | |
定番
【Java】電力案件(託送システム)システ…
【案件概要】 電力案件(託送システム)システム刷新にあたり、Javaで開発が可能なエンジニアの方を…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
Salesforce導入支援
【企業紹介】 ・ビジネスパートナー育成ビジネス ・情報システムの開発・構築・運用保守作業の請負 …
週4日・5日
920,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| ‐ | |
定番
【Salesforce】Marketing…
【案件概要】 Marketing Cloudとアプリを主軸として様々な施策を実行し、PoC(検証)…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【PMO】大手非金属メーカー_AWS基盤運…
【業務内容】 大手非金属メーカーのAWS基盤運用支援にご参画いただける方を募集いたします。 今後…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO(AWS) |
定番
【上流SE】電力案件(託送システム)システ…
【案件概要】 電力案件(託送システム)システム刷新にあたり、SE上流工程を担っていただける方を募集…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【インフラエンジニア】暗号資産取引所の開発…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Azure】在庫管理等の分散処理システム…
在庫管理等の分散処理システムをHadoop on Sparkで組んでおり DMCから逆輸入による導…
週5日
2.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
インフラ基盤・運用|電動マイクロモビリティ…
【仕事内容】 ・自社サービス本体、社内向け管理ツール、IoTデバイス関連サーバー等各種サービスの安…
週4日・5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【マーケター/ディレクター】顧客のCVを最…
◎具体的な業務内容 1.営業・アカウントプランナーと連携し、クライアントへの概要説明やヒアリングを…
週4日・5日
550,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | コミュニケーションプランナー |
定番
【Java】都市銀行 法人向けWebサービ…
【業務内容】 次期システム更改案件や現行システム維持保守案件における 設計、製造、テスト、定例/…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C・C++・C#・規模:7・700Kste… | |
定番
【MS365運用】ヘルプデスク業務リーダー…
M365(主にoutlookメールに関する)のグループ会社からの操作や申請に関する電話対応が中心とし…
週5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | ヘルプデスク |
| -・ | |
定番
【フロントエンドエンジニア】コンシューマー…
コンシューマー・スマホ等におけるシェーダー開発、ツール作成など、テクニカルに纏わるあらゆる案件に携わ…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【Ruby】自社サービス開発のエンジニア
・自社開発Webサービスの企画・機能開発・保守運用 ・新規サービスの企画・設計・開発
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・on・Ra… | |
定番
【Python】自社AIサービス開発のエン…
・自社開発Webサービスの企画・機能開発・保守運用 ・新規サービスの企画・設計・開発
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・ Flask | |
定番
エンジニアリングマネージャーとして自社サー…
・ビジネスサイドと協力しながら開発の方針決定・進行 ・開発チームのパフォーマンスを最大化するための…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・Ruby・on・Rails | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
モバイルアプリチーム、およびサーバーサイドチームの Tech Lead業務を担っていただける方を募集…
週4日・5日
550,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / スマホアプリ / 週3〜5…
【業務内容】 ・iOS/Androidネイティブアプリおよび社内ツールの、企画・仕様のレビュー・フ…
週3日・4日・5日
390,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
Androidアプリ開発業務|電動マイクロ…
(仕事内容) ・自社サービスAndroidネイティブアプリの設計・開発 ・社内向けAndroid…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【インフラ】クラウド環境におけるインターフ…
各国に展開するクラウドサービスのマルチクラウド環境におけるインターフェースの構築を進めます。 基本…
週5日
840,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Terraform | |
定番
【Java/システムエンジニア】社内での受…
【業務内容】 社内での受託システム開発(主にJava.net(VB,ASP,C#等による開発) …
週5日
550,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台盛岡駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア・システムエンジニア |
| Java・O・S:Linux、Windows、And… | |
定番
【PM】WEBシステム開発会社のプロジェク…
弊社で請け負っているWebシステムの開発業務全般をPMとして行っていただきます。
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Python・Java・Typescript… | |
定番
【QA】チームマネジメントアプリ開発
■ アプリ開発プロセス上流での仕様レビュー及び仕様改善 ■ テスト計画、テスト設計、テスト実施及び…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| Go・Typescript・React・ReactN… | |
定番
【フロントエンドエンジニア】美容室向けオン…
■業務内容 状況によって変動いたしますが、以下のどれかをお任せいたします。 ・美容室向けオンライ…
週4日・5日
2.2〜2.8万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木自由が丘 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Go】クラウド人材管理ツールの新規機能の…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、マイクロサービス化に関わる開発、公…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Golang・PHP・JavaScript・T… | |
定番
【グラフィックデザイナー】SNSにUPした…
メニュー、パンフレット、チラシ、ポスター、イベントカレンダー、POP… ★試食会や宣材写真・動画の…
週5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【開発プロジェクトリーダー】開発の全行程に…
シニア層の女性向けWEBマガジンを運用しております。 外部ベンダーと協力しながら開発の全行程におけ…
週5日
380,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発プロジェクトリーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【JavaScript; Ruby】フロン…
業務内容 ・現行システム開発対応 ・改修要件の確認と設計、開発テスト、リリースまで対応。不明瞭な…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・SQL・Rubyon… | |
定番
【VC++、VC#、VC.net】CAD/…
・現行システム開発対応 ・改修要件の確認と設計、開発テスト、リリースまで対応。不明瞭な点は既存メン…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(VC++・VC#・VC.net) |
| VC++ VC# VC.net | |
定番
【一部リモート可 / WEBデザイナー /…
[業務内容] 基本業務は証券サイト内infoドメイン内のバナー制作を中心としたWebデザイン周りに…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・ | |
定番
【PM/ディレクター】自社サービスのSEO…
卸売り・仕入れプラットフォームのPM/ディレクターを募集しております。 (主な業務内容) ・…
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター(PM) |
| ・・・ | |
定番
【サーバーサイド】福祉事業のシステム開発
【業務内容】 福祉事業のシステム開発(サーバーサイド)に携わっていただきます。 自社利用及び同業…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京宝町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Spring Laravel | |
定番
【AIエンジニア】リアルタイムAI実装エン…
研究開発で性能上評価されたAIモデルおよびPythonで記述されたアルゴリズムを実機(Linux)で…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
教育系オンラインプラットフォームサービスの…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 サービス・プロダクトがグ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PM,PdM |
| JavaScript・Ruby・Ruby(Rails… | |
定番
日本最大級親子向け情報サイトのサーバーサイ…
【案件概要】 家族向け情報サイトを主軸とした各種事業のWebサービスについて、新規機能開発や改善に…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【Laravel】PHPのスキルを活かせる…
【案件詳細】 - クライアントと要件を詰め、webサービス・モバイルアプリ開発における、仕様書作成…
週5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Flutter】自社toC向けアプリサー…
自社toC向けサービスのスマートフォンアプリ開発をご担当頂きます。 バックエンドエンジニアや他のプ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【PHP】派遣スタッフ管理システムの再構築
■案件名■派遣スタッフ管理システムの再構築 ■案件内容■ 派遣スタッフ管理システム再構築の基本設…
週5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
[PM]ノーコード開発サービスのプロジェク…
ノーコードで本格的な開発ができる開発OSSのサービス拡大に伴い、PMを募集しております。 APIフ…
週4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ノーコード | |
定番
【Wizardry VA(仮)】クライアン…
【業務内容】 Unityを使用したAndroid/iOSゲームアプリ開発。 ゲームロジック実装、…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【ディレクター】自社ブランドの未来を創るブ…
【業務内容】 ・デザインガイドラインの開発や、組織内でのブランドガバナンスの設計/推進する ・ブ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | ブランドディレクター |
定番
【サーバーサイド】IoTエンジニア業務
(業務内容) ・車載IoTデバイスおよび組み込みFW関連の動作検証、デバッグ環境の構築 ・自社サ…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(IoT) |
| C・C++・ | |
定番
【Java】自社サービス エンハンス開発(…
採用における課題解決を目指すHRtechプロダクトです。 弊社プロダクトの採用管理システムでを開発…
週5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア(HR Techプロダクト) |
| Java | |
定番
【PM】保育園の貸し出しシステムのディレク…
・Webサイトの制作ディレクション ・保育園の貸し出しシステムのディレクション、リニューアル業務 …
週2日・3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄宮崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【QAエンジニア】事業会社での全般的な検証…
内視鏡画像認識AIを利用するプロダクト及びサービス開発において、 全般的な検証計画及び検証内容の設…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【Java/Raect】コールセンターシス…
大規模コールセンターシステムのリプレイス作業となります。 8月までは要件定義、9月以降に設計工程に…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Java) |
| JavaScript・Java・SpringBoot… | |
定番
【React / TypeScript】商…
【仕事概要】 プロダクトオーナー、エンジニアを始め様々な部署と密に連携しながら、RaaS事業のフロ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【Ruby】商業スペース向けプラットフォー…
【仕事概要】 プロダクトオーナー、エンジニアを始め様々な部署と密に連携しながら、RaaS事業のバッ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Rails | |
定番
FintecカンパニーのiOSアプリ開発・…
・既存のWebサービスをスマートフォンから利用しやすくするための iOS/Androidアプリの提案…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・・GitHub・Bitrise・Test… | |
定番
FintecカンパニーのAndroidアプ…
・既存のWebサービスをスマートフォンから利用しやすくするための iOS/Androidアプリの提案…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・・GitHub・Bitrise・Tes… | |
定番
【インフラ】Azureシステム構築
【業務内容】 作業内容:Azureシステム構築いたします
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(Azure) |
定番
【React】ゲノミック評価閲覧サービス …
以下のサイトの画面改修および試験を行っていただける方を募集いたします ・農家等会員登録者用サイ…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| JavaScript・-・ | |
定番
【Java】保守チームをまとめる開発メンバ…
保守チームをまとめる開発メンバーの一員として携わっていただきます。 開発言語はJavaでAPI、バ…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大﨑駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【マーケター】美容医療の口コミ/予約アプリ…
・新規利用者の定着やリピート促進によるアップセル、ロイヤリティ向上促進 ・キャンペーンの企画立案~…
週2日・3日・4日・5日
530,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コンテンツマーケター |
定番
[PM/PMO]コールセンター移行プロジェ…
[業務内容] オンプレミスのコールセンターシステムからクラウド基盤(Salesforce+Amaz…
週4日・5日
840,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 品川泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/PMO |
定番
【Go】BtoC向けのFinTechアプリ…
設計〜実装まで一貫して対応していきます。 既存コードもありますので、調査して進めていく部分もありま…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア(Fintech) |
| Go | |
定番
【Node.js,Vue.js】Webエン…
【業務内容】 フロントエンド開発における初期工程を AI によって 自動化するWebエンジニア向…
週3日・4日
470,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Ruby・Go | |
定番
【PHP(Laravel)】PHPエンジニ…
【業務内容】 自社にてECサイト・口コミサイトを開発運営している大手企業での案件になります。 …
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア(リーダー) |
| PHP・Laravel | |
定番
«SREエンジニア/フルリモート»保険DX…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのSREエンジニアの募集になります。 ・保険事業会社…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| ・AWS・Amplify・・Vercel・・Circ… | |
定番
ビジネスパーソン向け某ニュースサイトのiO…
既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグの調査および修…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Xcode | |
定番
«SRE/リモート可»レジャー業界のDXサ…
余暇時間の選択肢を最大化しその質を向上させることで、心の充足を実現し、幸せな社会の実現をめざす、 …
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Java・AWS | |
定番
«バックエンド/リモート可»保育/教育業界…
家族のための新しい社会インフラを創造をめざす、 保育施設向けICTサービス事業を行う勢いあるメガベ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails | |
定番
【インフラ/Azure】既存オンプレシステ…
既存のオンプレシステムをAzureでクラウド上にリストアップしていただきます。 日本の証券会社がエ…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【Java/C#】ポータルサイト構築
ポータルサイト構築(Azure)に携わっていただきます。 日本の証券会社がエンドクライアントになり…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・Azure OpenShift | |
定番
【Java】ServiceNowrを利用し…
業務内容 ・ServiceNowrを利用した開発 今回Javaでの開発に先立ちServiceNo…
週5日
410,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | 【Java】サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【Angular.js】自社広告サーバーの…
【業務内容】 ・広告サーバーのエラー確認、問題修正 ・広告サーバーの追加機能開発 ・広告サーバ…
週3日・4日
260,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【紙媒体の編集経験ある方向け】出版社でのD…
新宿にオフィスを構える出版社での編集・DTPデザイン案件になります。 【お任せする業務】 ・…
週5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目 |
|---|---|
| 役割 | DTPデザイナー |
定番
【ディレクター】コンシューマー向けビジネス…
コンシューマー向けビジネスのクリエイティブディレクターを募集しております。 (主な業務内容) …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【セキュリティ】セキュリティインシデント処…
セキュリティツールが発出するアラートや、顧客会社のグループ会社からの事案報告をトリガーとして、インシ…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【Blender】遊技機の演出・レンダリン…
映像、遊技機、ゲーム、VR開発を行う、総合エンターテイメント会社での遊技機に関わる3D案件になります…
週4日・5日
1.6〜2.4万円/日
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender・cinema4D | |
定番
【Java】リモート可/レジャー業界のDX…
バックエンドエンジニアとしてエンド企業が提供する複数のレジャー関連のサービスを支えるシステムの開発・…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot(Java)・Inte… | |
定番
【VBA】社内向けダッシュボードの維持・管…
・tableau管理チームのメンバーとして、社内向けに提供しているBIダッシュボードの維持、管理、改…
週5日
250,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
[ハードウェアエンジニア]光と音を使ったイ…
光と音を使ったインタフェースの開発に携わっていただきます。 他のエンジニアと連携してデザインとあっ…
週2日
3〜5.1万円/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸豊川駅 |
|---|---|
| 役割 | ハードウェアエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【Java SQL】コンビニ向けマスタ管理…
業務内容 コンビニ向けマスタ管理システム開発。SQLでのバッチ開発がメインになる予定です。 …
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 豊洲浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java・SQL) |
| Java・SQL | |
定番
【PM/PMO】某自動会社向けプロジェクト…
既に開発が進んでいる販売店が取り扱う商品情報閲覧システムに関わるデジタル素材側の制作チームのPM業務…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
【Typescript/React.js】…
【案件内容】 ・大手レコード会社や芸能プロダクションなどのサービスの機能開発 【募集背景】 …
週4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【要件定義】GCP環境におけるデータレイク…
・店舗、ECサイト販売在庫計画(何を何点売るか)の需要予測システム ・Managed AI eng…
週5日
2.4〜4.5万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| GCP | |
定番
【開発メンバー】GCP環境におけるデータレ…
・店舗、ECサイト販売在庫計画(何を何点売るか)の需要予測システム ・Managed AI eng…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【アーキテクト】GCP環境におけるデータレ…
・店舗、ECサイト販売在庫計画(何を何点売るか)の需要予測システム ・Managed AI eng…
週5日
3.2万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【マーケター】美容医療の口コミ/予約アプリ…
・各種オンライン広告の戦略立案、運用改善 ・計測ツールや分析数値を基にした顧客や広告効果の分析とそ…
週2日・3日・4日・5日
530,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | デジタルマーケター |
定番
【AWS】新規決済システム構築案件
・メガバンクによる多頻度小口決済システムの構築要件 ・金融機関、資金移動業者および個人間送金の取引…
週5日
3.2〜4.5万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go・AWS・Git | |
定番
【フルリモ / React Native/…
顧客の本当のニーズに向き合い、根本的な解決をしていくことに力をかけていくため、CREチームを設立しよ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | CREエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Go・React… | |
定番
サーバーサイドエンジニア/自社サービスの開…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
外為(送金業務)のパッケージ導入対応
【企業紹介】 弊社は、長年に渡ってシステム開発や運用保守に携わってきたIT企業です。 最先端技術…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| COBOL・環 境:IBM汎用機、IMS、PL・I | |
定番
次世代アーキテクチャー戦略CIF・預為
【企業紹介】 弊社は、長年に渡ってシステム開発や運用保守に携わってきたIT企業です。 最先端技術…
週5日
840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| COBOL・IBM汎用機、IMS、PL・I・‐ | |
定番
【Ruby/SQL】小売販売店向け配送支援…
大手物流企業の案件です 業務内容 ・スーパーなどで買い物をした顧客に対し、自宅までの宅配を提…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Ruby・SQL) |
| Ruby・SQL | |
定番
【動画ディレクター】番組企画立案やディレク…
番組の企画立案 収録/ライブを問わず、現場でのディレクション・撮影・編集など、映像コンテンツを制作…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 動画制作ディレクター |
定番
[PHP/EC-CUBE]既存システムの改…
今回は下記既存システム(PHP)全般の改修・運用業務をご依頼したいと考えております。 ・古いバー…
週3日・4日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・fu… | |
定番
【WEBデザイナー】LP・バナー制作
【職務内容】 顧客の課題解決に向けた各種プロジェクトのWEBデザインに携わっていただける方を募集い…
週3日・4日・5日
1.2〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【WEBデザイナー】ストレスチェックサービ…
自社で運営するストレスチェックサービスに係るLPやHPデザインの作成をお願いします。
週1日・2日
160,000〜190,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰横山 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【マーケター】広告代理店にて広告運用設計や…
この度は、社内のノウハウ蓄積を目的として、運用設計からナレッジ共有、メンバーとの壁打ちをご担当いただ…
週4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【フロントエンド】AI OCRを中心とした…
AI OCRを中心としたAIプラットフォームを自社開発しております。 今回は、現在リリース済の…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【WEBデザイナー】自社サービスのサイトな…
【業務詳細】 ページデザインや広告LPのデザイン。 UI/UXの改善だけでなく、マーケティングサ…
週3日・4日・5日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| illustrator:Photoshop | |
定番
【Kotlin/Python/Go】AI …
AI OCRを中心としたAIプラットフォームを自社開発しております。 今回は、現在リリース済の…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Kotlin・Go・Type… | |
定番
【フロントエンド】イベント管理システム開発
【業務内容】 管理者が使用するシフトや案件を管理するWEB画面と スタッフがシフト登録や案件登録…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【バックエンド】イベント管理システム開発
【業務内容】 管理者が使用するシフトや案件を管理するWEB画面と スタッフがシフト登録や案件登録…
週5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(サーバーサイドエンジニア) |
| JavaScript・Java・React.js・S… | |
定番
【ReactNative エンジニア】自動…
【案件概要】 ・顧客が自身の車を管理できるアプリの開発 ・メンテ状況や関連コンテンツ(対応可能整…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア|React Nativeエンジニア |
| ReactNative | |
定番
【Javascript】各地方銀行で使用し…
開発エンジニア(フロント側) ※各地方銀行で使用しているスマホアプリの新規・拡張プロジェクト
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Javascript) |
| JavaScript・Java | |
定番
【PM】自社ウェディングECサイトのサービ…
ウェディング業界のDX推進を掲げている、スタートアップITベンチャーでのPM業務です。 自社サービ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿 日の出駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【メガベンチャー担当】販促物のグラフィック…
新商品発売やイベント時の販促物のデザインをお任せいたします。 クライアントとの直取引となり、型が決…
週5日
8〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| illustrataor・Photoshop | |
定番
【インフラ】電子契約プラットフォームシステ…
【業務内容】 ・運用計画の検討と作成 ・AWSを用いたログ監視方式の検討と構築の実施 ・各種リ…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ】検査依頼・報告システム(インフ…
検体検査を請負う機関が、病院、医院、クリニックとの依頼、受付、結果報告を行うシステムの開発 〇…
週5日
840,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川元町中華街駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Angular】検査依頼・報告システム(…
【業務内容】 検体検査を請負う機関が、病院、医院、クリニックとの依頼、受付、結果報告を行うシステム…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川元町中華街駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・-・ | |
定番
【PM】自動運転研究開発
【案件概要】 大手自動車会社様にて自動運転の研究開発チームのPMをご担当いただきます。 アジャイ…
週5日
840,000円以上/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋豊田市駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(自動運転) |
定番
【複数大手クライント担当】販促物のグラフィ…
新商品発売やイベント時の販促物のデザインをお任せいたします。 クライアントとの直取引となり、型が決…
週5日
8〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| illustrataor・Photoshop | |
定番
【TypeScript/React】会員向…
【業務内容】 数百万人の会員数がいる会員向けサイトの開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週5日
2.8〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・ | |
定番
[エンジニア]外資系企業案件のシステム運用…
■企業概要 お客様の未来を創造するソリューションを展開しております。 お客様に技術や知識を提供す…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・HTML・C… | |
定番
[フロントエンドエンジニア]システム開発支…
■企業概要 お客様の未来を創造するソリューションを展開しております。 お客様に技術や知識を提供す…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
[Flutterエンジニア]システム開発支…
■企業概要 お客様の未来を創造するソリューションを展開しております。 お客様に技術や知識を提供す…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・PH… | |
定番
【Unity】アプリ開発エンジニア
【業務内容】 アプリ開発を担っていただけるエンジニアの方を募集いたします。 ※詳細は企業様からご…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【自社開発のメタバースプロダクト】PM,フ…
メタバース領域のエンターテイメントプロジェクト開発をお任せします。 4月から入社した新卒4名エンジ…
週4日・5日
250,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Swift・Kotlin・C・C++・C# | |
定番
【AWS】ECシステムの刷新案件
SAP Hybrisを使って構築されている既存のマルチテナント向けECシステムをマイクロサービスアー…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【Java/PHP】自社サービスの開発業務
Tech Leadにはサービスの開発に関わる全プロセスを担っていただきます。もちろん不得意な部分、…
週4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot・Laravel・Ty… | |
定番
人事系サービスのサーバーサイド開発
人事系サービスのサーバーサイド開発 【勤務地】渋谷(リモート併用応相談) 【勤務時間】10:00…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・django | |
定番
【サーバーサイド】漫画アプリ / ソーシャ…
漫画アプリorソーシャルゲームorAR開発のサーバーサイド開発 【勤務地】都庁前(フルリモート) …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Symfony | |
定番
【ゲームデザイナー】新規・既存ゲーム開発に…
新規・既存ゲーム開発におけるUI、バナー 【勤務地】フルリモート 【勤務時間】10:00~19:…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
定番
新規スマホRPGゲームのクライアントサイド
リース予定の新規タイトルにおいてUnityをメインとした開発を行っていただけるクライアントエンジニア…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C# | |
定番
メタバースのグラフィックデザイナー
・キャンペーンページ/Twitter投稿用/その他 キャラ・背景・バナー 【勤務地】フルリモート…
週5日
250,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
iOSアプリ、iPadを使ったPOSシステ…
iOSエンジニア2~3年生(Swift) 【場所】東新宿(リモート相談可) 【期間】8月
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
デリバリーアプリ サーバーサイドエンジニア
・ユーザ向け、デリバリースタッフ向け、店舗向けのアプリ開発 ・サービスの各種機能に合わせたAPI開…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・AWS | |
定番
【Python】AIエンジニア募集
【案件概要】 POCを中心にAI関連開発(画像、音声、データ分析)専門の会社様様にて学習データ作り…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅(フルリモート) |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア[Python] |
| JavaScript・Python・Java | |
定番
【Java】検査依頼・報告システム(サーバ…
検体検査を請負う機関が、病院、医院、クリニックとの依頼、受付、結果報告を行うシステムの開発を担ってい…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 神奈川元町中華街駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【CakePHP】ネットショップ作成サービ…
・開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気通…
週4日・5日
580,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Webアプリケーションエンジニア |
| PHP・CakePHP・Vue.js | |
定番
【Kotlin、Java】自社のAndro…
【業務内容】 ・自社のAndroidアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただく…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【組み込みエンジニア】カーメータ開発業務
本件はC言語を用いたカーメータ開発業務を想定しています。 また、開発業務の中ではCANを用いて開発…
週5日
250,000〜460,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【組込C】四輪電装機器のソフト開発
【案件概要】 四輪電装機器のソフト開発の要件定義~設計・開発・テストをご担当いただきます。 …
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み/制御系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【WEBディレクター】デザイナー・コーダー…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます※ ・自社メディアの改善・コンテンツデザイン …
週3日・4日・5日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
【スマホアプリ】大手カー用品企業カスタマー…
案件概要:某大手カー用品企業にてリリースしている カスタマー向けアプリ(iPhone・A…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・ReactNative … | |
定番
【ウェブアプリケーションエンジニア】自社プ…
『社内の人材活用』『社外の人材活用』という独自のソリューションを提供することで、DX人材の不足という…
週5日
410,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | ウェブアプリケーションエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【Webデザイナー】クラウドファンディング…
クラウドファンディング支援事業におけるサムネ作成業務等をお任せします。
週1日・2日
1.2〜2万円/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸加美駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【Salesforce】Salesforc…
Salesforce Lightningの機能管理システムによる保守業務を担っていただける方を募集い…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【Java,Vue,React】大手旅行サ…
旅行予約システムのエンハンス開発を担っていただける方を募集いたします。 主にサーバサイド(Java…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【Ruby, Ruby on Rails】…
・仕様案に対しての実装レベルでの取りまとめ ・性能改善、新規機能の開発 ・RubyonRails…
週3日・4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・・Ruby・RubyonRails | |
定番
【Webデザイナー】マンガ配信サービスの広…
自社で運営するマンガ配信サービスにて、 リスティング広告などに使用するバナーを制作して頂きます。 …
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop | |
定番
【React.js】ブロックチェーンデータ…
【案件概要】 弊社ではブロックチェーン技術を活用した複数のプラットフォーム、Saas型アプリケーシ…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京仲御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Go】HRTechのバックエンド開発
HRTechのバックエンド開発業務に携わっていただける方を募集いたします。 (業務内容詳細) …
週3日・4日・5日
550,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【Laravel】マテリアルプラットフォー…
(業務内容詳細) ・新規サービスの開発、およびそれらの基盤を支えるシステム開発 ・PHP、Rub…
週3日・4日・5日
550,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【データエンジニア】自社サービスデータ分析…
【案件概要】 自社サービスのデータ分析システムの構築 ・データレイクやDWHの環境構築 ・…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| HTML・・CSS・JavaScript フロント… | |
定番
【WEBデザイナー】金融システムのデザイン…
金融システムのデザイン業務を依頼いたします。 デザインも含むマークアップ作業ができる方を募集してい…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Ruby】金融システム開発業務
【業務詳細】 ・主に実装を担当します。 ・ブロックチェーン技術を活用したシステム開発をお任せしま…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【Ruby】金融システム開発業務
【業務詳細】 ・テックリードとして開発と指示書作成を担当します。 ・ブロックチェーン技術を活用し…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | テックリードエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【Go/Java】ブロックチェーン開発業務
【業務詳細】 金融商品の投資持ち分などが売買できる、ブロックチェーン技術を活用したシステムの開発案…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go | |
定番
【WEBディレクター】不動産サイトディレク…
【案件概要】 不動産企業様とのお打ち合わせで要件とりまとめから企画、要件定義 進行管理、ベンダー…
週5日
2.8〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
【JavaScript】フロントエンドエン…
当社が運営するメディアにおいて、フロントエンドの開発を担当していただきます。 お任せしたい業務は、…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Angular・JavaScript) |
| JavaScript・Python | |
定番
【Goエンジニア】大手通信会社の運営するW…
当社のSI部門にて、バックエンドエンジニアを募集いたします。 大手通信会社の運営するWEBコンテン…
週5日
330,000〜710,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo・+・GORM | |
定番
【React】自社サービス開発のエンジニア
・自社開発Webサービスの企画・機能開発・保守運用 ・新規サービスの企画・設計・開発
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| JavaScript・React.js・React | |
定番
【ゲームプランナー】アクションゲームのア…
【主な業務内容】 ・プレイヤーアクション ・敵アクションの設計と実装 ・プレイヤーや敵AIの設…
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
【AWSシニア】IaCを用いてパブリックク…
IaCを用いてパブリッククラウドに構築したインフラの構築、改善 Terraformなどを使いAWS…
週5日
690,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS | |
定番
【AWS】IaCを用いてパブリッククラウド…
IaCを用いてパブリッククラウドに構築したインフラの構築、改善 Terraformなどを使いAWS…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS | |
定番
【Ruby】自社プロダクトのSRE
自社プロダクトのSREとして、ユーザーや顧客企業と向き合いながら、サービスの信頼性を向上するための業…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【Android】ネイティブアプリの開発デ…
- Android ネイティブアプリの開発 - 動画配信アプリの開発
週4日・5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター(Android) |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【正社員希望の方優遇!】ネットワーク・サー…
企業様向けの情報システム部のネットワーク運用業務になります。 構築作業もあり、試験仕様書や変更依頼…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Windows・Linux・-・ | |
定番
【Java:SE案件】デリバリシステム開発…
概 要: ・現金精算システムのローカル・マクロなどのシステム統合化 ・セキュリティ、属人化防止、…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Docker | |
定番
【Java:SE案件】有名キャラクターコン…
現在要件定義およびAmazonジャパンと連携し、サーバアーキテクチャを設計中です。 コンシューマア…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【PM】事業会社での新規事業責任者_医療サ…
遠隔地間の内視鏡室をネットワークし、相互に症例等に関するコミュニケーションをとれるサービスを立ち上げ…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java】新システム開発のエンジニア募集
現在運営中のECカートプロダクトを刷新するプロジェクトを進めています。 その新規メンバーとしてご活…
週5日
1.6万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・PostgreSQL… | |
定番
【Unity/C#】大人気アニメシリーズス…
某ITベンチャーにて大人気アニメシリーズスマホ向けソーシャルゲームのアプリ開発を担当頂きます。 開…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原両国 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| PHP・C#・Unity・AWS・Laravel | |
定番
【JavaScript/Google Ap…
MA系プラットフォームを展開している某ITベンチャー企業の社内システム開発を担当頂きます(部署は情シ…
週5日
500,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・SQL・ー | |
定番
【Python Django】IaaS上の…
IaaS上のサーバー開発業務になります。主な内容は、サーバー設計~評価とサーバー運用保守になります
週4日・5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 神奈川武蔵小杉駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【VB.net】製造業向けPKG新規開発
【案件概要】 Sierが保有しているPKG新規開発及び顧客開発支援対応 【期間】 9月~長期 …
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(VB.net) |
| VB.net、Oracle | |
定番
【Java】製造業向け調達システムの新規開…
【案件概要】 調達システムの新規開発(改修案件) 【期間】 9月~長期 【勤務地】 人形町…
週5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java) |
| Java | |
定番
【Java】ユニフォーム販売システムの機能…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・AWS | |
定番
【インフラ】グループウェアシステムインフラ…
グループウェアシステムインフラ基盤の維持管理業務に携わっていただける方を募集いたします。 ※詳細は…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【COBOL】小売店向けシステム(マスター…
小売店向けのシステムのエンハンス対応となります。 対象のシステムは、マスター管理となります。 …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川天王町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| COBOL | |
定番
【Javascript】卸売り向け販売管理…
【業務内容】 卸売り向け販売管理パッケージの開発 【作業範囲】 基本設計~開発・テスト
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・Java・PostgreSQL… | |
定番
【TypeScript】契約書レビュープラ…
- AI契約管理システムのバックエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テスト・保守運用 …
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(TypeScript) |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【PHP】自社グループ会社サービスのサーバ…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、 最新の研究動向を取り入れた…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| PHP | |
定番
【PHP】商社向けデジタルギフトCMS
【案件概要】 商社向けにデジタルギフトの管理システムの改修、機能追加を行っていただきます。 【期…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 品川浜松町(フルリモート) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(PHP) |
| PHP・Smaty | |
定番
【バックエンドエンジニア】大手通信キャリア…
・auサービスに係る様々なプロダクトのバックエンド開発をお願いします。
週3日・4日・5日
180,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go・•・GitHub・Enterprise… | |
定番
[PM]ToB向けソフトウェアサービスのプ…
大手通信会社向けのシステム開発・保守案件でPMを募集しています。 ・顧客要求からの仕様策定 ・仕…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Scala・Swift・Android… | |
定番
【Vue.js/ava】ネットバンクWEB…
ネットバンクWEBアプリ開発(設計、開発、テスト)を担当していただきます 【使用環境】 Ja…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Vue.js) |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【UI・UX】担当プロダクトのUI・UX改…
■業務内容 担当プロダクトの必要要件の洗い出し、制作ディレクション、要件の洗い出し等を行っていただ…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター(UI・UX) |
定番
【フルスタック】自社エンタメ新型プラットフ…
自社新型エンタメプラットフォームの開発エンジニアを募集しています。 今後さらに事業拡大にあたり、エ…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【C/C++エンジニア】車載ECU開発
【業務内容】 車載ECU開発(長期案件) 【業務範囲】 設計~製造・テスト
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋刈谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【C/C++エンジニア】車載ECU開発 |
| C・C++ | |
定番
<WEBアプリ開発 フロントエンドエンジニ…
大手商社やITベンチャーで新規事業を担当してきた代表を中心に、お客さまのビジネスを成功させるためのビ…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・SQL・Re… | |
定番
【UI】ハイエンド系のアクション等のゲーム…
●キャラクターデザイン 3Dキャラクターモデリング、スキニング、テクスチャ作成 ●背景デザイン …
週4日・5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 3Dデザイナー |
| Photoshop(テクスチャ)、Flash(アニメ… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
当社は国内でも数少ないShopify ExpertとしてECサイトに関するコンサルティングから、構築…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【Go/C++/Python】製造業向け画…
主にAI技術を活用した製品開発・システム開発・データ分析を行っております。 画像処理/音声認識/自…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 豊洲八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・C・C++ | |
定番
【Ruby/Vue.js】海外ベンチャー情…
◇業務内容◇ ・Webアプリケーションの開発・運用, 各種API開発 ・サービス要件にあわせた仕…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Vue.js | |
定番
【Ruby/Python】社内向けWebア…
私たちは特装車事業や環境インフラ整備事業などをメインに、60余年に亘り、 さまざまな製品・サービス…
週3日・4日
390,000〜530,000円/月
| 場所 | 神奈川- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【React】マーケティングチームでの上流…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにて プロモーションサイト改修…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / セキュリティ / 週…
急速に拡大していく事業に対して、様々なセキュリティの対応を行っていかなければならないと考えおり、すで…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【Unity】新規スマートフォンゲームのフ…
新規スマートフォンゲームのフロントエンド(Unity)開発、運用を担当していただきます。 ・U…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・C・C++・C#・Unity | |
定番
【フルリモ / Python/Java /…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計/製品サポート …
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】E…
商品へのアクセスや購入データをもとに、商品企画を高速で回せる分析基盤を作ったり、仕入れ用の需要予測や…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北与野駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【Ruby/Vue.js】スタートアップ企…
既にリリース済みのプロダクト改修や機能追加等の開発をメインで担当いただきます。 また、新規サービス…
週3日・4日・5日
390,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】クラ…
【企業情報】 弊社ではサーバーの多様化するニーズに対応した、豊富なサービスを展開しております。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
AWSを用いて、言語処理基盤、機械学習基盤等のデータ基盤を開発をご担当いただきます。 【案件の…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ■開発環境:・AWS、GCP(Big・Query、G… | |
定番
【Python】医療×AIにおけるアノテー…
医療×AIを作成するために、教師用データを作成するための社内サービスを開発・運用を行っていただきます…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask・インフラ | |
定番
【PHP】ECサイト・リプレースプロジェク…
化粧品等の製造開発からEC販売から、 化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングの…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
【案件内容】 社内の複数サービスが抱えるユーザを統合し、データの蓄積及び、 検索が可能なデータ基…
週4日・5日
410,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿-- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Django】保険関連サービスのWEBア…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 またWEBマーケティングの観点…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Djan… | |
定番
【Ruby/Python】自社LegalT…
現在、AIによる契約書レビューサービスを軸とした、企業の契約書作成を包括的にサポートするSaaSを開…
週5日
740,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Ruby・MyS… | |
定番
【フルリモ / Django / 週4日〜…
当初はコンサルティングサービスから始まりましたが顧客ファーストの姿勢から評価され、拡大してまいりまし…
週4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
社内他部署と連携してプロダクトのUIデザインをご担当いただきます。 【業務概要】 ・プロダク…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】医療…
業界全体における就労人口不足にテコ入れをし、全国の地域福祉インフラを支えていくために、これまで10万…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにて、デザイン業務に携わっていた…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務詳細】 アプリケーションを強化するためのアーキテクチャー及びアプリケーションを指定期日内に計…
週5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
この度は日本での「S2b2C」モデルのECサイト立ち上げにあたり、 UI/UXデザイナーを募集いた…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 池袋新大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週5日】医…
人気モデルやアイドルをキャスティングした自社ブランドのカラーコンタクトレンズや、次亜塩素酸水スプレー…
週5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 品川大崎広小路駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【フルリモ / Angular/Vue /…
弊社の事業におけるフロントエンド開発をメインに担当いただきます。 デザイナーと会話をして最終的なデ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿‐ |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
この度、新規事業の立ち上げにあたりwebサービスの要件定義とプロジェクトマネジメントを担当していただ…
週3日・4日・5日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
オンプレからAWS移行における以下の内容をご担当いただきます。 ・環境調査 ・検証 ・移行計画…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
この度社内システムの再構築に向けたエンジニア様を募集いたします。 現在テレビのCM枠を取って自…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
世界初の特許技術を使用した自社ソリューションに関連したAndroid・SDK並びにアプリの設計・開発…
週4日・5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】国際…
業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者がデジタル…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・想定言語 サーバー:PHP… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
私たちは、業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・想定言語: … | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
私たちは、業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
弊社は企業のニーズに合わせたシステム開発及びシステム導入の企画・分析から設計・開発・運用支援までの一…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringMVC | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
弊社のヘルステック分野におけるライフログプラットフォームのWEBデザイン、 ユーザー向けプロダクト…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
システムを支えるAPIプラットフォームの拡充、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
Androidエンジニアの方には、プラットフォームの上で、新サービス開発・他社サービスとのアライアン…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【React.js】教育系Webアプリケー…
弊社は特定分野のソリューションとプロダクトをご提供しています。 Webアプリケーション、Webシス…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
サーバサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発や、インフラ設計・保守な…
週4日・5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
【案件内容】 モバイルアプリの開発において、技術選定から設計・開発・運用までをリードいただきますの…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Flutter・React・N… | |
定番
【Vue.js/Node】ブロックチェーン…
ブロックチェーン案件でのフロントエンドの開発をお任せできる方を募集しております。 【魅力】…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・Vue.js | |
定番
【Python/Typescript】ブロ…
世界最先端のBlockchainプロジェクトと共同している国内屈指のブロックチェーン技術に特化したソ…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript・Node.js | |
定番
【React.js/Angular.js】…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため、医療統計データサービスを提供している会社です…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python/AWS…
ネイル情報サービスのWEBエンジニア兼AWS運用エンジニアを募集しております。 <<業務内容>…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / Python/AWS…
ネイル情報サービスのWEBエンジニアを募集しております。 <<業務内容>> ・ネイルサービス…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
アプリもWEBもあるネイル情報サービスのUI/UXデザイナーを募集しております。 <<業務内容…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
フィットネスアパレルの販売を行う会社です。 販売ルートとして店舗とECサイトの2つを持っています。…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
この度は新規Wi-Fi事業の推進にあたり、各自治体への高速Wi-Fi設置に向けた設計を担っていただけ…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| 【事業内容】 日本の通信費が高く、かつ街中のフリー… | |
定番
【Ruby】自社印刷システム刷新プロジェク…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRail・・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
▼案件概要 当社の研究開発部門にて、全文検索システムに関わる研究開発をお願いします。 当社で…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・ご経験や志向に応じて、自然言語処理や機… | |
定番
【React/Typescript】HRT…
人材に関する社会課題を解決する自社プロダクトの運用開発を行っていただきます。 人材データのサーベイ…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
広告配信プラットフォーム及びメディア向けレポート一元化ツールWebアプリケーションのフロントエンド開…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Pyt…
【案件概要】 弊社は、AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーで…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
【業務内容】 クライアント先での新卒研修の講師をご担当いただきます。 ※各プロジェクト先に…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / ネットワーク/ 週4日〜】…
弊社は、化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのためのデジタル・コンテンツの配信…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
私たちは経営コンサルティングを中心に、コンサル会社向けソリューション開発、M&Aアドバイザリー、CV…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【Flutter】自社物流サービスのネイテ…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
750,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Webディレクター】 サイト制作構築デ…
■業務内容: ・制作進行管理(タスク管理、素材管理、制作指示のとりまとめ作業など) ・品質管理(…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
【Webディレクター|フルリモ】Web制作…
弊社ではオンラインスクールサービスの運営を行っており、スクール内のサービスで利用者に実案件を提供する…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
[情シスPM]自社事業(ワンストップリノベ…
【業務内容】 ■リリース済み、かつ保守改善フェーズにある複数システムについて、 社内の運用チーム…
週3日・4日・5日
660,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトマネージャー |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを誇っています。 …
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】OracleでのD…
当社サービスはOracle基盤で構築していますが、 大型案件の開始に伴い、Oracleからクラウド…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 開発経験豊かなテッ…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】行…
自社サービスである行政ビッグデータと行動科学を応用した公的通知サービスをリニューアルしていくプロジェ…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Angular/Azure…
■業務概要 当社サービスの主にフロントエンドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Django… | |
定番
【フルリモ / Python/Azure …
当社サービスの主にフサーバーサイドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用しております…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・DjangoRESTframework… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◆業務詳細 顧客で契約しているデータセンター廃止にともない、データセンターに設置しているネットワー…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
▼案件概要 情報共有ツールの開発・運営を行うスタートアップです。 今までコストをかけずにステ…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
私たちは、情報共有ツールの開発・運営を行うスタートアップです。 今までコストをかけずにステルス…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・₋- | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】急成…
ユーザー数560万人の経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 ▼主な業務 ・…
週5日
520,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / C++/PHP / …
新しい知識、情熱、考え方を持ったゲームエンジニア人材を募集しております。 ▼業務一例 ・キャ…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
■案件詳細 新規IoT開発案件において、AndroidTV向けアプリケーション開発を行います。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・■開発環境 Android・Kot… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
下記三つの事業を展開しております。 クラウドインテグレーション事業 データ分析サービス事業 …
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 運用チームの一員として、Webアプリケーションの保守・運用を行っていただきます。 …
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Kuebrenets・Kafka・Datadog・具… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
クラウド、OSS、アジャイル、DevOps、データ解析・機械学習等の先端技術について多くの経験および…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
この度は、ゲームコンテンツ開発・運営事業において、 SNSゲームの開発に向けた3DCGデザイナーの…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender・Unity・▼担当範囲 ・アバター… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】所属…
【案件概要】 所属ライバー向けのデータ可視化webツールの開発と新規機能の追加をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】自…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C#・【作業環境】 ・主要言… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計、PoC、製…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにサーバーサイドエンジニアとして関わってい…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・N… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
◇業務概要 以下の業務に携わっていただきます。 -担当範囲は、システム要求定義から開発、テスト…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
toB、toC両方で運営するオンラインマッチングサービスの拡大に伴い、Rubyエンジニアを募集してい…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
【業務内容】 ケアマネジャー向けのコミュニティサイトのフルリニューアルPJに参画いただきます。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
私たちはレジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供しています。 今回の募集は、…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
私たちはレジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供しています。 今回の募集は、…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
モノの買取事業を展開する上場企業グループにて、アドバイザリーチャットボット開発を担えるエンジニアリン…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・C#・CakePHP・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】上場…
テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプリ、システム等…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / C̟++/Pytho…
▼業務内容 -次世代ゲーム機の画像処理関連の開発業務。 -カメラから入力された画像を、ディープラ…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
オンラインクレーンゲームシステム開発に従事していただけるサーバーサイドエンジニアを募集致します。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
SAP導入に向けてはベンダーに入ってもらっていますが、既存サービスの改良・連携も発生するため、下記業…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure(想定) | |
定番
【リモート相談可 / C++/Swift …
▼案件概要 POSIXをベースとした組み込みシステムのインテグレーション作業 -弊社の各種組み込…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Swift・C・C++・-開発に使用する言語は、主に… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
▼案件概要 統計分析の技術を用いてオフライン、オンラインの広告/販促効果を最適化するソフトウェア開…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
▼案件概要 統計分析の技術を用いてオフライン、オンラインの広告/販促効果を最適化するソフトウェアを…
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながらインフラの検討及…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、広告デザインから…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Native・Ne… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】リプ…
■業務内容: ・レガシーなLAMP構成の現在のECサイトとCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
【業務内容】 フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・f… | |
定番
【Ruby/PHP】HR系インターネットメ…
弊社が運営するHR系サービスにおける、サーバーサイド開発業務をご担当いただきます。 各サブシステム…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【インフラ / 週5日】AWS基盤移⾏保守…
◇業務詳細 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・某⾦融系顧客向けオンプレ→AWS基盤への移⾏…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
役割: ・アプリ保守、及びインフラ運⽤サポート 対象システム概要: ・各ロボットとエンドユ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
【企業紹介】 テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアントから請け負っているECサイト構築のフロントエンド開発を担当いただきます。 業務内容とし…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
外国籍の方向けの新規アプリ内の追加アプリ開発チームの立ち上げを担当者とともに進めていただきます。 …
週3日・4日・5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / Laravel/Vu…
今回は弊社のWebアプリケーション開発にご協力いただけますエンジニアの方を募集いたします。 主に運…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【Ruby】契約書レビュープラットフォーム…
自社開発を行っております契約書レビュープラットフォームを、今後さらに多くのユーザーに使っていただくた…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
リーガルテック領域のサービス開発に携わっていただきます。 社員とともに幅広く裁量を持ってお任せ…
週3日・4日
520,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / C++/Java /…
主に下記の業務に携わっていただく想定です。 - 通信モジュール機能追加およびメンテナンス。 -A…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【PHP】WEBシステム開発支援
■業務内容 ・WEBシステムの開発 ・WEBアプリケーション開発 ※案件は複数ありスキルにより…
週5日
580,000〜770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ca… | |
定番
【フロントエンドエンジニア】自社サービスの…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、 最新の研究動向を取り入れた…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript | |
【DTP】社内外の幅広いデザイン案件(DT…
【作業環境】 ・週2以上 ・定時:9:00-18:00 【ご依頼業務】 社内やクライアン…
週2日・3日
120,000〜190,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | DTPデザイナー |
定番
[Shopify]ECモールへ自社ブランド…
【会社概要】 ゲーミングデバイスやアクセサリー、アパレルまで幅広くゲームに関連する商材を中心に取扱…
週2日・3日・4日・5日
2〜2.4万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京幡ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Shopify人材 |
| HTML・CSS | |
定番
【Web・UI/UXデザイナー】NFTマー…
【担当業務】 ・ワイヤーフレーム、画面デザイン作成 └使用ツール:Figma, Slack, J…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー(UI/UX含む) |
定番
【フルスタックエンジニア】自社AI × 音…
弊社コミュニティサイトサービスにおける開発を担当いただきます。 ウェブサービスの改修・機能追加と新…
週3日・4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Kotlin・Nod… | |
定番
【Webディレクター】自社クラウドポスシス…
自社サイトのディレクション業務をお任せします。 継続的な業務として、 WEBサイト制作のディ…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルスタックエンジニア】人材育成/スキル…
・人材育成/スキルの可視化を行うWebアプリケーションの追加機能開発 ・統計学アプローチによるアセ…
週4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・React・Po… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
◆業務内容 -医療機器向けのPFにOSのポーティングがメインです。 -お客様の方で環境の導入済み…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| その他、 -ITRONベースで動作する旧機種から、… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】Mi…
この度は事業の拡大に伴い、データエンジニアを募集いたします。 <募集背景> 事業拡大に伴う体…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】Mi…
この度は事業の拡大に伴い、インフラエンジニア(システム運用)を募集いたします。 <募集背景> …
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 言語 :C#・・・JavaScript・・・Type… | |
定番
【フルリモ / C#/.Net / 週3日…
事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 昨年ローンチしたバーチャルイベントをはじめ、ヘ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C#・JavaScript・TypeScript・H… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
この度は事業の拡大に伴い、フロントエンジニアを募集いたします。 現在進行中のバーチャルイベントまた…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【Ruby】技術マッチングの自社プラットフ…
ものづくり業界に精通した産業コーディネーターの“目利き”と、ITを活用した高精度な探索システムで探し…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・AWS | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
人事データを活用するための開発プロジェクトでのデータエンジニアを募集しております。 大きくは、経営…
週3日・4日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Python・SQL | |
急募
【WEBディレクター】ウェブデザイン経験者…
【会社概要】 福岡県に本社を構える化粧品・健康食品などサブスクD2C・リピート通販を強みとする制作…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【C/C++ / 週5日】無線通信装置向け…
無線通信装置のIC制御に必要となるプログラムの実装および、動作確認の実施をご担当いただきます。 …
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小金井駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・・-開発言語:C言語・ | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
【案件】 大手ToC向けのAndroidアプリの開発・保守を担っていただけるエンジニアの方を1名募…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿自由が丘駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・【開発環境】 … | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週4日〜】ボ…
【企業情報】 私たちグループはヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開…
週5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
Webアプリケーション開発にご協力いただくエンジニアを募集します。 (主な業務内容と作業範囲)…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
Google Cloudを用いた以下のいずれかの基盤の設計・構築・運用に携わっていただける方を募集い…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / C++ / 週3日〜】3D…
【業務内容】 上場企業向けにAIや数理アルゴリズム等の科学技術を提供している会社です。 今回は物…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 現在、ベータテストを終了し、リリースに向けて…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・【開発環境】 ■iOS ・言語:S… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】国…
国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 現在、ベータテストを終了し、リリースに向けて…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・【開発環境】 ■… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
▼案件内容 - アサインされたPJにおけるサーバサイド部分の調査・検証・設計・実装。 - 比較的…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Nginx・AWS・Docker・主な開発環境… | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
ライブコマースサービスのデザイン業務をご担当いただきます。 具体的には下記のような業務をお任せ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / API / 週4日〜…
【業務内容】 弊社提供サービスと、お客様で利用中の既存サービスとの連携開発をメインで行っていただき…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Nginx・AWS・Docker | |
定番
【Go】番組配信サービスにおける保守運用、…
2.5次元俳優/声優さんを起用した番組配信サービスにおける保守運用、新規機能開発をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【C#/ 週5日】自動車メーカ・重量管理管…
自動車メーカ・重量管理管理システムの開発業務になります。 重量管理システムの詳細設計、開発、単体テ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL・開発言… | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】ク…
■クラウド型オープンイノベーション支援サービスのバックエンド開発をお任せします。 【具体的には…
週4日・5日
500,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】ク…
■クラウド型オープンイノベーション支援サービスのバックエンド開発をお任せしたいと思います。 【…
週4日・5日
500,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
■案件概要: ヘルスケアのスマホアプリ保守業務をお願いします。 ◇具体的な作業 ・既存不具…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
▼業務内容 ・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 / オンライン教育を行うシステムの開発 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・【開発環境】 ・… | |
定番
【Vue/Nuxt/TypeScript】…
当社は、ブランド品や骨董品等の査定買取と販売を主軸に行っております。 IT化の進んでいなかったリユ…
週4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Nuxt.js・… | |
定番
【リモート相談可 / Android/PH…
AndroidもしくはPHPのリードエンジニアとしての役割をお任せする予定です。 <業務内容>…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・AndroidJava・Kotlin・And… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
モノの価値をつなぐ “リユース”というビジネスの魅力と可能性を信じ、テクノロジーを駆使し、これまでに…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・【使用技術】 言語:PHP FW:Lar… | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
▼案件内容 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプ…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
受託開発案件でのQAエンジニア(インフラエンジニア)を募集しております。 開発案件内容の詳細に…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Java・Laravel・CakePHP・V… | |
定番
【Ruby】就職支援事業領域サービスのサー…
就職支援事業領域サービスでサーバーサイド開発を担当していただきます。 高度なプロダクト開発とな…
週5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計、PoC、製品サ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
Chatbot, チャットフレームワークを利用したWebアプリケーションの開発を遂行していただきます…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Go・… | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
自社サービスを利用した開発の推進、事業の企画、立上げにも携わっていただきます。 【作業内容】 …
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue・React | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
[案件概要] トレーディングプラットフォーム、データプラットフォームについての設計および開発 …
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Storyboo… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【企業概要】 企業の中枢を管理する次世代型経営管理クラウドを開発・提供しています。 【案件概…
週3日・4日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎広小路駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【Go】短期就業仕事紹介マッチングPF開発
弊社では短期間・短時間の仕事に特化した1日単位のお仕事プラットフォームの開発を行っております。 …
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Kotlin・Go・Gin | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
◾️開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・ReactNative | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのiOSアプリ開発を担っていただきます。 ◾️ …
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・React・Native | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【プロジェクト概要】 ・基幹システムおよび公開サイトの共通部品のメンテナンスおよびアーキテクト支…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・SQL・React・Node.js・Spr… | |
定番
【リモート相談可 /Python / 週4…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスにおける、開発保守運用業務をご担当いただける方…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【業務内容】 AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムと自社製AIカメラを連携させたプ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務詳細】 弊社プロダクトにおけるバックエンド開発のリーディングを担当いただきます。主にはオンラ…
週3日・4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
ITサービスを使用するために必要な環境や設備を導入・保守業務を管理しています。 現行基幹システムが…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 or 沖縄 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・React・‐ | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
▼業務内容 ITサービスを使用するために必要な環境や設備を導入・保守業務を管理しています。 現行…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 or 沖縄 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React・Spri… | |
定番
【フルリモ / React/Next.js…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】理…
理系学生に特化した新卒採用サービスを運営しており、研究領域で事業群を構築していくことを目指しています…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Play2・Framework | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】Laravel…
大手商社やITベンチャーで新規事業を担当してきた代表を中心に、 お客さまのビジネスを成功させるため…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel・Javascript・Cak… | |
定番
【フルリモ / React/Redux /…
【業務内容】 下記の業務をご担当いただきます。 ・新規開発及び機能拡充、性能改善 ・開発チーム…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Swift/RxSw…
【業務詳細】 ・提示された設計に基づくiOSアプリ開発 ・Health Kitからのデータの取得…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・- | |
定番
【フルリモ / React/React N…
下記三つの事業を展開しております。 -クラウドインテグレーション事業 -データ分析サービス事業 …
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
インフラエンジニア(C#/Java)
【案件概要】 組み込み系からウェブ系まで幅広く手掛ける開発会社の案件で、エンド先で生産管理システム…
週5日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堂島駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・C#・Oracle | |
定番
【システムアーキテクト】グループ横断でのシ…
【業務内容】 ・各種プロジェクトにて求められるシステムアーキテクチャ(業務要件定義等) ・各担当…
週5日
480,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムアーキテクト |
| AWS | |
定番
【Webマーケティング】新規サービスのデジ…
・担当新規サービスのデジタルマーケティングチームとしての戦略立案と実行 ・担当新規サービスの集客プ…
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ー | |
定番
Webマーケター(広告運用ディレクション)
【業務内容】 ・運用型広告の設定、入稿、運用業務全般 ・デジタル広告プロバイダーとのコミュニケー…
週5日
270,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【CRMマーケター】自社グループのCRM施…
【業務内容】 ・CRM施策の具体的な分析・企画立案・運用全般 ・既存顧客のファン化 ・カスタマ…
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ー | |
定番
【データアナリスト】データを用いたヘルスケ…
【業務内容】 ・データを用いたヘルスケアサービスの新規開発・改善
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| ー | |
定番
【データアーキテクト】自社グループのデータ…
【業務内容】 ・データレイク/ウェアハウス・マートの設計/開発/運用/保守 ・データの抽出/分析…
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | データアーキテクト |
| Python・SQL・R・AWS・ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
広告プラットフォーム事業やメディア事業を中心としながら、20以上の事業やサービスを運営しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Symfony・Laravel・R… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けの「社員向けスマホアプリ」の開発準備及び開発案件です。 ▼業務内容 スマホ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React(reac… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
ネットワークの回線や装置の情報管理や、工事などの各種作業チケットの管理をしている業務システムの開発・…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】MLO…
【業務内容】 工場での品質管理のために、プロダクトの撮影画像をAWS上に収集し、MLOpsで利用で…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】Q…
【業務内容】 スマホアプリサービスにおけるテスト計画の策定やテスト設計、テストの実施、テスト結果の…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ₋- | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【企業情報】 弊社は美容業界向けにICTを駆使し、成長を続ける「美容サロン向けICT事業」全国の美…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フロントエンドエンジニア】案件内容 :シ…
案件内容 :システムの刷新開発を行っており、スクラム開発で管理しています。フロントとバックエンドにチ…
週5日
580,000〜850,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋竹橋 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・React Postg… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【業務詳細】 ・最善の措置、開発プロセス、およびコーディング基準の追求 ・信頼性の高い、保守性の…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東松原駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine | |
定番
【PMO】PJ品質改善
案件内容 :PMO経験や知識を活かし、標準ドキュメントの作成や、PMの下支えを行う。 作業場所…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川竹芝/天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【PHP】自社メディア・MAツールにおける…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するサービスの開発を担当いただきます。 様々なフェーズを…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Laravel・… | |
定番
【フルリモ / JavaScript/Vu…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js・N… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4…
クラウドファイルストレージをSaaSとして提供している企業様での導入コンサルト業務になります。 営…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【業務詳細】 ・要件定義作成 ・導入時・導入後の… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
【案件概要】 新規スマートフォン向けRPGゲームのサーバーサイドエンジニアとして、開発~リリース、…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・Unity | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】C…
GitLabを利用したCI/CDパイプラインの設計、構築、試験計画、試験実施等を行っていただきます。…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
▼業務内容 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただ…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
自社開発のSaaS「建物・設備メンテナンス管理業務ツール」の開発を行っており、今回はこちらのフロント…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【Java】ソーシャルゲームの企画・開発・…
この度は新タイトルリリースに向けてソーシャルゲーム開発において、 設計・実装および高速化・最適化の…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| JavaScript・node.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ソーシャルゲーム開発において、サーバーアプリケーションの設計・実装および高速化・最適化の業務を行って…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
ソーシャルゲーム開発において、クライアントサイドの新規機能開発・既存機能改修・ゲームリリース作業を行…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity・CocosCreator | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
大手通信会社の共通ポイント事業部署におけるデータ分析、ご提案、Excelデータを分析していただき、結…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VB.NET・VBA | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社ソリューションは、創業以来強みとしているデータ分析と近年マーケティング領域でトレンドとなっている…
週3日・4日
470,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・Java・SQL・R | |
定番
【フルリモ / Ruby/Python /…
今回は、医療用のビッグデータを様々な分析環境に利用するためのデータ基盤を開発いただけるエンジニアの方…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社が運営する顧客管理システムの開発、改修をご担当いただける方を募集いたします。 (業務内容詳…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】社内…
【業務内容】 データ分析基盤の構築・運用をおまかせします。 ・各種システムからのBigQuery…
週4日・5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
世界最先端のBlockchainプロジェクトと共同している国内屈指のブロックチェーン技術に特化したソ…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週3日〜】…
【業務内容】 ・新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務をご担当いただきます。…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【仕事内容】 エンドユーザー・元請け案件を中心に、業務系システムの導入・開発、Webアプリ開発、ビ…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【Javaエンジニア】無人コンビニ開発
案件内容 :実証実験として顧客内で行われている内製開発を商用化に向けて機能拡充を行う。 作業場…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
当社は、独立開業する心理カウンセラー、ビジネスメンター、キャリアコンサルタントの方々を対象として、ク…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸丹波口 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
バーチャルとリアルを行き来する新しい買い物サービス開発の業務をお任せします。 <提供サービス>…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Swift】クラウド型学習支援サービスの…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるiOSの開発です。 小学校~高校、専門学校の先生…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・【求める人物像・】 ・当社の理念に共感… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
【案件概要】 今回の募集では、賃貸物件の家賃債務保証を行う事業部にて新規WEBサイト制作や新規シス…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅/水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Nuxt.js・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【リモート相談可 / java / 週5日…
▼案件概要 販売員が使用するモバイルアプリ(ios/Android)と、管理者(本社の方)が使用す…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
弊社が運営するアルバイト求人メディアのデザイン業務をご担当いただきます。 <業務内容> UI…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Vue.js/React …
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
BtoCの既存WEBシステムのサーバリプレースのインフラ作業をお願いします。 <業区詳細> …
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ※開発側はJava・PHP ※ミドルウェア … | |
定番
【Python】自社toB向けシステムパッ…
自社で開発したプロトタイプのシステムをベースに、商用パッケージを新規開発するプロジェクトの開発担当エ…
週4日・5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
【AndroidJava/Kotlin】ヘ…
当社の基盤事業であるヘルスケアサービスを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするために重要な…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
AI・IoT導入及びビッグデータ活用におけるデータ分析をメインにサービス提供している企業になります。…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL・R・SPSS・Modeler・… | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
様々な業務をsalesforceにより管理しております。 現在、業務改善に向けて様々なsalesf…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】シ…
【サービス】 1.情報システム部門サポートサービス 2.セキュリティサービス 3.システム管理…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 神奈川馬車道駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Springboot・Teeda・Seas… | |
定番
【フルリモ / PHP/Scala / 週…
[案件概要] 下記の業務をご担当いただける方を募集します。 ・法人向けのWEB名刺発注システム …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Scala・Play・Framework・L… | |
定番
【Ruby】HR系インターネットメディアの…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週4日〜…
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
<業務内容> UIデザイン及びコーディングに関連する実務、プロダクトマネージャーやエンジニアとの協…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 医療データを100を超える医療施設から収集を行っています。動画を登録・管理するシステ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Ansible | |
定番
【Python】自社開発プロダクト・データ…
【案件詳細】 自社開発プロダクト、提供API用のアルゴリズム開発 ・数理最適化・配送アルゴリズ…
週5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・SQL・R | |
定番
【C/C++】医療機器(顕微鏡)の開発業務
-市場投入済の医療機器(電子顕微鏡)開発に関する市場不具合調査、保守業務。 -新製品開発の設計…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・-OS:Windows10 -開発言語… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【プロジェクトの概要】 ・資金管理機能 お客様のトレーディング資金を入金するための、クレジット…
週5日
280,000〜570,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【Python】医療関連データの解析業務
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的課題…
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・R | |
定番
【OutSystems経験者募集】サーバー…
Java、C# PM、SE、PGいづれでも構いません。OutSystemsご経験者でお願いします。O…
週2日・3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿倉見駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・OutSystems・楽々Frame… | |
定番
【Java】高速道路関連業務システム開発
既存高速道路関連システムの新システムへの移行追加開発を行っており、9月からの詳細設計・製造フェーズへ…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java) |
| Java・Java、JSP、intra-mart、P… | |
定番
【PM】基幹システム刷新プロジェクトの契約…
【業務内容】 ・要件定義を含めた社内・社外折衝 ・スケジュール管理 ・開発ディレクション ・…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
【Javascript】小売り事業における…
・機能開発における設計~実装~リリースまで ・ユーザーからのフィードバックに基づく改善 ・内製化…
週5日
280,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Webデザイナー】自社複数事業のデジタル…
・Webサービス、スマホアプリのデザイン業務 ・LP、バナー等の広告素材のデザイン制作 ・デザイ…
週5日
350,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ー | |
定番
【PM】プロダクト各種事業の新規立ち上げ、…
・ボディメイク事業における新規プロダクト/サービス企画およびプロジェクトマネジメント ・新規プロダ…
週5日
350,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【SRE】サービスサイトのサーバ・ネットワ…
・AWSを利用したインフラ環境の構築運用 ・TerraForm等を利用したサーバー構築の自動化 …
週5日
350,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| AWS | |
定番
【QAエンジニア】プロダクトリリース品質保…
・内製、外注を含んだ受入検査の実施 ・事業全体を把握し、製品の仕様を把握した上での適切な品質保証体…
週5日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ー | |
定番
【Webマーケター】広告プラン策定・運用・…
・担当サービスの集客プランニング及び実行 ・担当サービスの主要KPIの設定と達成のための戦略立案と…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ー | |
定番
【PMO】PMO支援
・関連部署間の調整、プロジェクト全般の管理、各種ドキュメント作成 ・クライアントユーザーと開発ベン…
週5日
350,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
【RPA】自社グループ会社のRPAプロジェ…
・RIZAPグループ全社のRPA開発リーダー業務 ・RPA開発のプロジェクトマネジメント ・プレ…
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
【クラウド】データ基盤開発エンジニア・アー…
・開発会社と共同し、データ基盤の設計・開発・テスト全般を実施 - データレイク・ウェアハウス・マー…
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| Python・Java・AWS | |
定番
【マーケター】マーケティングデータアナリス…
・顧客データや広告データなどを活用したマーケティング戦略立案 ・タグマネージャーを用いた計測環境の…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| ー | |
定番
【C/C++】cocos2d-xを使った超…
・cocos2d-xを使ったゲームのクライアント実装 ・運用タイトルの機能バージョンアップの開発 …
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++・C++・Unity・cocos2dx・X… | |
定番
【SQL】データエンジニア募集
【案件詳細】 弊社の抱えるプロジェクトにデータエンジニアとして参画していただき、開発に携わっていた…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【企業情報】 主にAI技術を活用した製品開発・システム開発・データ分析を行っております。 画像処…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 豊洲茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【会社概要】 当社はこれまでに数百社との取引実績があり、通信キャリア・大手SI企業・官公庁・大学等…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 豊洲門前中町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】V…
バーチャルライブの基盤となるシステム開発からモバイルアプリケーション開発、演出制作などクライアント開…
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
【仕事内容】 シェアリングサービスのエンジニアとして、インフラ、バックサイド、フロントサイドなど、…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP | |
定番
【Python】IoT・AI自社サービスの…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発から、サービスの…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
▼案件概要 新規プロダクトとしてスマホアプリの新規サービスを検討しております。 新規PJのため一…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
弊社はビジネス課題や、社会課題を解決するためのイノベイティブなアイデア、 そして最先端技術(ブロッ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・angular・Node.js… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを誇っています。 …
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・(開発機器の主な機能) ・センサの情… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
<業務内容> ・日本最大級オンラインギフトプラットフォームのアプリエンジニア開発(Android)…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・Android・CircleCI・Fi… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展に貢献する医療ス…
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【Ruby】プログラミングのオンライン学習…
今回はリードエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発やインフラ設計・構築、新…
週4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rails・Node… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
オンライン学習システムの開発・改善に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を募集いたします。…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・RubyonRai… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▽案件概要 経営陣やビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/…
週4日・5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・AWSで構築しているパーソナル情報信託システムの2次開発。 ・既存のシステムに新た…
週5日
570,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業概要】 弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートする…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask・Django | |
定番
【フルリモ / C# / 週4日〜】自社開…
異なる事業者間での共同配送の実現、分断されるサプライチェーンの統合を目的としたトラック&トレースソリ…
週4日・5日
370,000〜570,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Swift】ヘルステックベンチャーでのi…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Ruby】ICTを活用したクラウド型学習…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 小学…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週5日】人材サ…
■今回の募集に関して アプリ開発における要件定義担当者としてのご依頼になります。 ・事業部担当者…
週5日
580,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・新規PJTにつき現在検討中 | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
強化学習とデジタルツイン開発を得意とするAIベンチャー企業です。 グローバルで活躍できるAI企業に…
週4日・5日
570,000〜680,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
【案件概要】 一例として、EC2上で稼働しているMongoDBを、Amazon DocumentD…
週3日・4日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】自社…
自社プラットフォームを支えるインフラエンジニア業務を依頼します。 それぞれのメンバーの「属性の…
週4日・5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / ReactNative/S…
【業務内容】 ReactNativeでiOSのみに対応したランサーズのスマホアプリの開発、開発運用…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・ReactNative・S… | |
定番
【フルリモ / Kuebrenets / …
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションインフラの設計・構築・運用…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| kubernetes・Kafka・Datadog | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 WebアプリケーションインフラおよびWindowsサーバーの監視・構築・運用、Dev…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 業務詳細: 1)・監視ツールを用いての監視・障害報… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
社内SEとして既存システムの改修や機能追加、または新規のシステム開発を行っていただきます。 ・社内…
週3日・4日・5日
550,000〜610,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトで開発チームのエンジニアをご担当頂きます。 ・PM・…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
ゲーム会社の事業拡大に伴う、ゲーム開発プログラマの募集をいたします。 【業務内容】 コンシュ…
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C・C++ | |
定番
【インフラエンジニア】ディメンションマップ…
GoogleのData Portalの開発・運用をお願いできる方を募集しています。 プロジェクト全…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL | |
定番
【Ruby】ECサービス関連のシステムの改…
・EC市場の様々なサービスとのデータ連係(API、RPA等) ・コアシステムの機能改善および新規機…
週2日・3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・AWS・GitHu… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】最…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
170,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
170,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 1. WEBシステムのフロントエンド開発 ・プロダクトサイト ・ECサイト ・…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Nuxt.js / 週5日…
■業務内容 ・新規サービスのシステム開発(メイン) ・商標登録を安心、カンタンにできるようにする…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】オ…
オンラインによる診察、処方箋発行、治験、メンタルケアなどのサービスを展開しています。 今回はサービ…
週4日・5日
300,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【案件概要】 Webサイト新規構築おけるフロントエンド作業者として、マークアップ部分の全体設計〜構…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / React/Vue.js …
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
【担当いただく業務】 新規プロダクト開発チームへのアサインとなります。 ・新規プロダクトの初期立…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【概要】 下記の業務に携わっていただきます。 -車載ECUの通信系ドライバ開発/ミドルウェア開発…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
【概要】 -Androidのコアな部分に対する修正。 -Ver.UPに追従し、コアコードの都…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿23区内・各駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| C・C++・Android・Flamework | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週5日】次…
【案件概要】 主に下記の業務をご担当いただく想定です。 -自動運転向け次世代地図データの管理・…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Java・C・C++・VB.NET | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週4日…
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
機器の状態を可視化、機器の設定を行うWEBサイトにおいて、グラフやテーブルの描画、フォームの描画と送…
週3日・4日・5日
460,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Node.js・n… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】最新…
最先端システムの開発や強化学習を使ったロボット動作最適化学習などに携わっていただけるAIエンジニアの…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄井尻駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Swift・Kotlin… | |
定番
【フルリモ / セキュリティー / 週3日…
当社は、スマートフォンアプリやWebサービスのセキュリティ診断業務に特化したホワイトハッカーで構成さ…
週3日・4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【React】デスクトップアプリのクラウド…
自社で開発したプロトタイプのアプリをベースに、それをクラウドサービス化するプロジェクトの開発担当エン…
週3日・4日
450,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Angular/Nest,…
▼案件概要 既存の開発チームに新しくジョインしていただき、CTOとコミュニケーションをとりながら、…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Angular・Next・js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】受託サ…
【案件詳細】 コードを書くことに夢中になれるPHPエンジニアを募集します! 【業務内容】 …
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中之島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・・HTML5・CSS3・Sa… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【今回の案件について】 杭メーカーの施工管理システム 【業務詳細】 ・Webアプリケーショ…
週4日・5日
500,000〜730,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・Express・G… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
▼案件概要 今後は、開発ラインを増やし、カジュアルゲーム開発も並行して展開するほか、コンシューマー…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・₋- | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】急成…
【案件内容】 サーバーサイドとインフラの開発をお任せする、フルスタックエンジニアを募集いたします。…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・◆開発環境 サー… | |
定番
【フルリモ / React/firebas…
<業務内容> 少人数での開発になりますので、アプリの開発、リリースをまで担当し、要件定義~実装まで…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・React・Firebase・… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
【仕事内容】 Web開発エンジニアを募集します。 ※プロジェクトにより、詳細仕事内容に変更がある…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸肥後橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SQL・Spring・Struts・・PC… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
BtoBに特化して30年以上、デジタルを活用した、マーケティングでお客様企業の売上に貢献できる、より…
週4日・5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社ではWEBサービス開発を行っていただける、PHPエンジニアを積極的に募集しております。 大…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルスタックエンジニア】BtoBSaaS…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 新プロ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため、医療統計データサービスを提供している会社です…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】社内…
◆案件概要 医療機関のお客様からいただいたデータを分析する際に、社内で可視化して区別できるよう、社…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Tableau・AWS | |
定番
【Kotlin】自社転職/採用支援サービス…
採用したい人材に企業から直接アプローチすることができる、中途採用向けの転職支援・採用支援サービスです…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】Goo…
Googleマイビジネスを利用した店舗集客支援サービスに伴う開発業務をお任せします。 さらなる事業…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Docker・AWS・MySQL | |
定番
【Kotlin】ヘルステックベンチャーでの…
歩数計アプリサービスの新規開発におけるAndroidアプリ開発をご担当いただきます。 【具体的…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 今…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【AWS】リユース業界の最先端企業における…
AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。 AWSに精…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・■業務例 ・AWS(… | |
定番
【Ruby/React.js】カウンセリン…
ユーザーと専門家をつなぐサービスを提供しており、ご利用件数は39,000件に上ります。 業界内での…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
大手フィナンシャル・グループのネット金融サービスの中核会社として、グループ各社との連携により、さまざ…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町、東京 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
東証一部上場企業のグループ会社として、人材サービス向け基幹システムで業界シェアTOPを誇るITベンチ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby/React.js…
ユーザーと専門家をつなぐサービスを提供しており、ご利用件数は39,000件に上ります。 業界内での…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
現行システムの機能追加などの改修をメインでご対応頂きます。 具体的には、お一人でフロントエンド(詳…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React/Java / …
自社でアプリ開発(漫画カメラ)やメディア事業を展開しつつ、受託案件も受けています。 今回はクラ…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【Laravel/Vue.js】採用管理業…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js・Lara… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務内容】 弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Spring・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
今後さらなる成長を遂げるため、自社サービスの開発にも力を注いでいます。 そこで、この度新規および既…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
670,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・V… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
◆業務内容 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・アプリケーションまたは…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Vue.js/Nuxt.j…
自社サービスのフロントエンド開発をご担当いただきます。 開発チームのエンジニアとして、ビジネス…
週4日・5日
370,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・【企業紹介】 金融×不動産×… | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
オンライン完結で提供する自社住宅ローンサービスのバックエンド開発におけるリードエンジニアをご担当いた…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / Python/TypeSc…
データ分野に特化におけるプロダクト開発力・コンサルティング力を強みとし、クライアント企業のデジタルマ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 今回、PHPエンジニ…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Zend | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社画像・動画・音楽クリエイティブプラットフォームの開発業務になります。 【業務】 写真・イ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Sketch・Ad… | |
定番
【リモート相談可 / Java/Pytho…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
【業務内容】 ・自社事業におけるWebサービス刷新プロジェクトの開発リードエンジニア ・リリース…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・PHP | |
定番
【フルリモ / C#/Java / 週5日…
コンピュータソフトウェアの開発会社です。 お客様の状況に最適なシステム開発に即応するべく、現場での…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週4…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
■業務内容 -プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認・テスト、…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
【業務内容】 弊社が運営するBtoB向けのIT製品の比較サイトのフロントエンド開発をご担当いただき…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【Ruby/Rails】SaaS等のシステ…
【業務内容】 ・営業やCSなどのドメインエキスパートと会話をしながら、本当に解決するべき課題を発見…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・Redu… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社マ…
▽案件内容 自社でマーケティングオートメーションツールの開発を行っており、今回はそのシステムのイン…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Ruby/TypeScri…
主に中高生向けの学習塾紹介メディアを自社で運営しております。 今回は上記メディアのサーバサイド…
週4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社プ…
【案件概要】 テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・gRPC・GraphQL | |
定番
【AWS】HRtech領域における自社サー…
[担当プロダクト] 勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムです。 複数拠…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Java】通信事業者向けシステム開発業務
業務詳細: 通信事業者向けシステム開発チームで、基本設計~テスト、運用までご対応可能な方を募集しま…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seaser2・Spring | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
【企業紹介】 当社は情報処理専門会社です。 システムのグランドデザイン、導入コンサル、カスタマイ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
【案件概要】 Flutterを用いたアプリ開発のプロジェクトです。 今回は、Flutterエンジ…
週3日・4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大駅前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| ・GitHub ・Slack ・Chatwork… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】De…
多様なシステムのインフラ設計・開発・運用をお願い致します。 ・安定稼働を実現するためのサービス…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue/TypeScrip…
これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプリ、システム等の開発を行っています。…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・TypeScri… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSサービス開発におけるフロントエンド・サーバーサイドを幅広くご担当いただきます。 【…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Python・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
自社サービス開発全般(主にフロントエンド開発)業務を担っていただける方を募集します。 ・クライアン…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Nuxt.js(Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Java/C/C++…
あらゆる手配業務をチャットで完結できるコンシェルジュチャットプラットフォームを展開しております。 …
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Go・C・… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】経済メ…
弊社アプリのUIデザイン情報設計・経験により以下業務を担当して頂きます。 【業務詳細】 - …
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【Go】国内最大級の金融メディアにおけるサ…
・自社CMSの新規機能開発 ・ 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リー…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【Ruby】ヘルスケアサービスにおけるサー…
弊社が運営するヘルスケアサービスのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 【具体的な業務内容…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
▼具体的な業務内容 B2B領域で、AIプロダクトのUIUXデザインを行っていただきます。 <…
週4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるモニターアライアンス基盤とクライアントのサービスが連携した共同事業のシステム開発に…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・PhalconPHP・… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
現状、自社で運営する多数のメディアのアクセス増に向け、クラウドインフラ基盤の品質向上をできる方を求め…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週5…
今回は新規または既存機能の開発・保守運用も想定しております。(ご経験やご要望によって新規開発か既存開…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・SQL・・AWS・MySQL・Gi… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
一般向け金融メディアで、コミュニケーション設計/デザイン/マークアップの「ディレクション」を担ってい…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・illustr… | |
定番
【フルリモ / Python/Django…
今回は、自社が提供するコーチング事業の中でお客様が利用するアプリケーションツール開発、追加機能の導入…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
弊社の社内業務ツールとしてSaleforce導入いたしました。 今後システム設定やカスタマイズが発…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【React】自社のフロントエンド開発業務
【業務内容】 主にページパフォーマンス改善や、UI/UXの改善。また直近でJamstackでの開発…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【C++/C#】工作機器ソフトウェア開発
【業務概要】 工作機器におけるGUI開発、カメラ制御および、ネットワーク制御に関する開発アイテムの…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 豊洲潮見駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・-OS:Windows、Linux -… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社プ…
【企業紹介】 ゴルフ場予約サイトのプレープランや価格等の比較情報や、ゴルフ場の予約に対応したWeb…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
【企業紹介】 すべての人に、いつまでも健康で美しく生きる「アクティブエイジング」のための商品・サー…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
注目
【Java】大手回転すしチェーンのシステム…
【案件】 大手回転すしチェーンのシステム開発全般 【案件概要】 上記システムをアジャイルに近い…
週5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸天満橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java) |
| Java・Springboot、MySQL | |
【Java】大手電気メーカーのYouTub…
【案件】 大手電気メーカーのYouTube関連システム開発 【案件概要】 現在フェーズ1の設計…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸天満橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java) |
| Java・Springboot | |
定番
サーバーサイドエンジニア/自社サービスの開…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
【React 】ライブストリーミングと動画…
【案件概要】 - ライブストリーミングと動画格納、動画視聴ができるアプリケーションのフロントエンド…
週3日・4日・5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木南青山 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| ・React、Next.js、Firebase | |
定番
【フルスタック】SEO対策/新機能開発
自社プロダクトの SEO施策を実行する開発業務をお願いいたします。 細かな SEO 施策やプロダク…
週5日
2.8〜5.7万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
急募
【システム】決済サービス開発に向けた調査・…
【案件概要】 決済代行会社のシステム部門でのお仕事です。 今や欠かすことのできない「オンライン決…
週5日
620,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| -・ | |
定番
フロントエンドエンジニア
ex 管理画面の機能開発 ex Webサイト表示機能の開発 ・React.js,Next.jsに…
週4日・5日
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・ー | |
定番
Salesforceエンジニア
■現状の業務内容 ・Salesforce の運用・保守 ・Salesforce 連携システムの運…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| ー | |
定番
フロントエンド実装案件
・画面コンポーネント設計 ・マークアップ実装 ・SPA開発 【期 間】9月~11月 【場 所…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| Vue.js・ー | |
定番
【WEBデザイナー】CMS管理システムのデ…
【案件概要】 CMS管理システムのデザインをお任せします。 <必須スキル> ・Bootst…
週4日・5日
3.2〜4.8万円/日
| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| -- | |
定番
【WEBデザイナー】ハイブリッドアプリデザ…
【案件概要】 ハイブリッドアプリデザインをお任せします <必須スキル> ・flutter …
週4日・5日
3.2〜4.8万円/日
| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| -- | |
定番
【Java】メディアコンテンツ売上管理シス…
【業務内容】 ・メディアコンテンツの配信・再生に応じた 売上情報を集計し、他システム連携や明細発…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸南森町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot | |
定番
【リモート相談可/ フロントエンド/ 週4…
【特記事項】 中長期的に稼働を頂ける方の採用を希望される企業のため 業務委託として参画後、将来的…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿 日の出駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・ | |
定番
【React/Next.js】自社サービス…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます。 ・自社サービスのReact/Next.jsの…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Next.js | |
注目
【WEBデザイナー】新規事業に携わっていた…
現状デザイナー正社員2名で動いておりご参画いただく形になります。新規事業責任者やマーケティング部との…
週2日・3日・4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋支社毎に異なる |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Swift】iOSエンジニア データ中継…
iOSエンジニア、データ中継システムの開発 センサーをコントロールしクラウドに情報を送信するi…
週3日・4日・5日
250,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【Typescript、React、Go】…
【案件概要】 データ中継システムの開発 【必須スキル】 ・Typescript、React…
週4日・5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Go,Typescript,React) |
| JavaScript・Go・Typescript・L… | |
急募
【英語の読み書きビジネスレベル対象】海外人…
■事業概要 海外人材/ITエンジニアに特化した、転職プラットフォーム事業 ■ターゲット ①求職…
週3日・4日・5日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
定番
【Java】旅行業向けSalesforce…
【案件概要】 工 程:Salesforce既存システム機能改修 役 割:プライムベンダとして顧客…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
| Java・Apex | |
【PR/広報】プロサッカークラブのイベント…
弊社がめざす「地域活性化に貢献」を推進するお仕事です。 本募集では、主に会員様向けサイトの運営を中…
週1日・2日・3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 中国・四国伏石町駅 |
|---|---|
| 役割 | PR/広報 |
【マーケター】WEBマーケティングで企業を…
【業務内容】 ・顧客の課題特定及びアドバイザー業務 ・サイト改善の企画及び提案 ・web広告運…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【TypeScript/React / V…
【企業紹介】 わたしたちは、リーガルテック領域のスタートアップ企業です。 現在は、AIによる…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【ディレクター】コンテンツ制作チームの進捗…
【業務内容】 作成におけるコンテンツ制作チームの進捗管理、パートナー管理、マニュアル作成、及び量産…
週3日
90,000〜140,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 制作ディレクター |
【情シス】自社情報システム部門のITシステ…
【業務内容】 ・従業員のITシステム環境整備のため以下のような業務を行っていただきます。 ‐PC…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内情シス |
定番
【正社員募集!】新規サービスクラウドインフ…
<概要> インフラエンジニアとして、新規サービスをパブリッククラウド環境で稼働させるための環境構…
週5日
160,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【PMO】社員代替のシステム運用開発/推進…
お客様の立場でお客様社内の請求/回収等の大騎の業務システムの一部の運用開発および推進、管理を行います…
週5日
570,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【TypeScript】入札情報速報サービ…
公庁・自治体等を対象とする入札情報速報サービスのリプレイスプロジェクトをお任せ致します。 現在…
週4日・5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【python/aws/sql】大手企業で…
【業務内容】 インプットデータを元に計算をするwebシステムとなります。 【環境】 ・新規…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町 |
|---|---|
| 役割 | pythonエンジニア |
| Python・SQL・- | |
定番
【Goエンジニア】クラウドシステムの開発・…
社内の人事労務や財務関係(レガシー)の情報管理で使用するクラウドシステムの開発・保守運用を担当 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【フロントエンドエンジニア】大手電気メーカ…
【案件概要】 大手電機メーカーの、LP作成になります。 通常のLP作成よりも少し複雑で、アンケー…
週3日・4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【AWS】インフラエンジニア|某金融系DW…
・現在詳細設計、製造、単体テスト工程中 ・データ移行調整、作業、段取り対応を実施 ・オンプレ→A…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS,JP1) |
| Python・Java・SQL・DataStage(… | |
定番
【GO】決済プラットフォーム開発
大規模決済プラットフォームのデジタル化案件です。 大規模スクラム開発で進めております。新しい技術を…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・言語:Go・Vue.js ・DB:MySQ… | |
定番
【動画クリエイター】自社動画メディア企画
ニュース&エンタメ動画メディアと有名タレントやアスリートのYouTubeチャンネルの動画撮影および編…
週3日・4日
240,000〜300,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作・動画制作ディレクター |
| Premiere・Photoshop | |
定番
【Java】飲食店管理システム
【企業】 大手クライアント案件を中心にシステム開発を行うスタートアップSierです。 【業務…
週5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸南森町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot・Flutter・M… | |
定番
【PdM】自社のプロダクト方針・要件策定
【具体的な業務内容(仕事内容詳細)】 ・市場・環境・競合・ユーザーリサーチ ・ニーズ、課題を解決…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
[業務委託/マネージャーポジション]急成長…
ライブ配信アプリのプロダクト開発におけるプロジェクトマネージャーとして、サービスをグロースさせるため…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| iOSアプリ:Swift Androidアプリ:K… | |
定番
【SQL】地図業界向けコンテンツDB開発
【業務内容】 Postgres SQL設計開発業務 【期間】 9月~ 【勤務地】 田町 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア(PostgreSQL) |
| SQL | |
定番
建設会社向けアプリ開発(ローコード)
【案件概要】 建設会社社員からの要望を伺ってローコード(ノーコード)にてアプリ開発を実施 【…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ローコードエンジニア |
| SQL・Microsoft・Power・Apps | |
定番
【UI/UX】自社プロダクトの情報設計・U…
【具体的な仕事内容】 ■ユーザー要求の仮説立て、ユーザーストーリーの検討 ■情報設計、UIおよび…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【UI/UX】大手ファミレスのアプリ開発企…
業務内容: 大手ファミレスの企画部門として、各種サービスアプリのUIUX設計を行い、売上や事業拡大…
週3日・4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三鷹駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター |
定番
【Java/PHPエンジニア】大手ECサイ…
お客様内で既存ECサイトの新機能開発及び改修を行っております。 作業内容はJavaもしくはPHPに…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Java/PHPエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【Python】大手不動産企業版へのカスタ…
2億件超の不動産ビッグデータを活用したシステム開発のプロジェクトマネジメントをお任せします。 …
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python | |
定番
管理業務支援システム(既存パッケージ)のバ…
顧客の管理業務支援システム(既存パッケージ)のバグの調査、修正 業務パッケージの不具合改修がメイン…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| C#・VB.NET・.NetFramework | |
【リモートあり】UiPathを使ったRPA…
【作業期間】2022/10/1~ 【募集人数】UiPath開発保守 1名 【場所】浜松町駅、また…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川浜松町or品川 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
定番
【PM】プロジェクト管理(スケジュール管理…
プロジェクト管理(スケジュール管理、メンバーマネジメント等)
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【コンサル】コンサル系(導入コンサル、改善…
コンサル系(導入コンサル、改善コンサル、セキュリティ系、経営)
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | コンサル |
定番
【サーバーサイドエンジニア】AI/機械学習…
AI/機械学習系(Python,機械学習系のツール)
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【データベースエンジニア】SQL等のデータ…
SQL等のデータ収集(Oracle Database,MySQL,PostgreSQL,・Micro…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Database・MySQL・… | |
定番
【インフラエンジニア】インフラ系(AWS,…
インフラ系(AWS,GCP,AZURE,Oracle Database)
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・GCP・AZURE・Oracle・Datab… | |
定番
【Unity、C#】XR技術の基礎研究を含…
社内案件として、XR技術の基礎研究を含めた新規サービス・プロダクトの開発業務の携わっていただける方を…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| C# | |
定番
【PHP】レジャー業界の新規サービス(顔認…
新規サービス(顔認証システム)の開発に関わるメンバー募集になります。 ・Amazon Rekogn…
週4日・5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Python・・Laravel ・Amaz… | |
定番
【Python /Go】自社プロダクトを顧…
自社プロダクトを顧客システムへ導入に伴う 開発プロジェクトに対応いただきます。 ※詳細は面談…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・AWS・Lambda | |
定番
【Ruby】お花のサブスクサービスの開発
【会社概要】 〜新しい体験を提供し需要創造、業界全体のサスティナブルな構造変化を目指す〜 顧客へ…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・MySQL・… | |
定番
【Active Directory】システ…
ActiveDirectory廃止PJにおけるPLポジション ActiveDirectory シ…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【マーケター】労働生産性を変える新規事業プ…
【業務内容】 ・新しいサービスのLP構成・内容作成、コミュニケーションのプランニングと実行 ・既…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| HTML・CSS | |
定番
【ディレクター】某教育機関のWEBサイト運…
【業務内容】 某教育機関のWEBサイトの運用業務を受託で行っております。 今回エンドとの要件確認…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | アシスタントディレクター |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Co… | |
定番
【Java】高速道路関連業務システム開発
既存高速道路関連システムの新システムへの移行追加開発を行っており、9月からの詳細設計・製造フェーズへ…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・JSP・intra-mart・Postgr… | |
定番
[Rubyエンジニア]研修事業向けLMSの…
【業務内容】 研修事業向けLMSの内製化をを行っております。 ・企業内研修で受講者が使うLM…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【グラフィックデザイナー|フルリモート・週…
【業務内容】 自社サービスのビジネスサイドで必要になるクリエイティブの制作(バナー・LP等)をお任…
週3日・4日・5日
570,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
大手塾のサイトリニューアル制作のディレクタ…
大手塾のサイトリニューアル制作案件にてディレクション業務を担当いただきます。 稼働中の大規模システ…
週3日・4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ‐ | |
定番
【UI/UX】飲食・フード特化型人材サービ…
飲食・フード特化の人材サービス事業でサイトリニューアルや新規開発のデザイン業務をご担当いただきます。…
週5日
2.4〜4.9万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
定番
【React/Typescript】新規事…
転職特化型のスキルスクール事業を運営しているスタートアップ企業です。 弊社は急拡大の投資フェー…
週4日・5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Vue.js】ヘルステックベンチャーでの…
弊社の下記事業の中での新規事業案件のサービス開発におけるフロントエンド開発をご担当いただきます …
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【JavaScript/PHP】自社広告メ…
弊社のメディアテクノロジー事業本部では、1,000万人以上が利用するスマホアプリ情報を扱う国内最大級…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| CSS・JavaScript・PHP・Laravel… | |
定番
【Ruby】アプリケーション開発のテックリ…
【企業概要】 採用管理クラウドを中心に人材サービスを革新する、クラウドサービス&テクノロジーを自社…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails Coldfu… | |
定番
【PHP】採用管理業務を支援するSaaS型…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel | |
定番
【Go】子育て支援モバイルアプリのAPI周…
今回は子育て支援サービスに関するアプリのAPI周りの開発に携わっていただけるエンジニアの方を募集いた…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Go・(技術スタック) ・バックエンド:… | |
定番
【Go】新規金融サービスのサーバーサイド開…
【案件概要】 自社金融サービスのサーバーサイド開発業務をお願いいします。バックエンド、フロントエン…
週4日・5日
740,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【Swift/Kotlin】Fintech…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【PHP/Perl】Fintechに関する…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Perl・【業務内容】 ・PHP又はPer… | |
定番
【Go/Node.js】Fintechに関…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Go・Node.js・【業務内… | |
定番
【AWS】Fintechに関するAWSエン…
【案件概要】 決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関す…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【業務内容】 ・AWS・・・GCPを利用したWeb… | |
定番
【Ruby/Java】ペット関連のWebサ…
ペット業界のDXを実現するために、事業をより推進していただけるようなエンジニアスタッフを募集していま…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【ReactNative】急成長スタートア…
【募集背景】 ・弊社ビジネスマッチングアプリはReactNativeで実装されているが、現状ディレ…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| 【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステ… | |
定番
【建築・建設・プラント業界経験者向け】次世…
【会社概要】 コンサルティング〜システム開発〜新規事業創出まで行う、DXコンサル企業です。属人的な…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | ソフトウェアエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【C++】建築業界のDX支援のためのSaa…
【会社概要】 コンサルティング〜システム開発〜新規事業創出まで行う、DXコンサル企業です。属人的な…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【Vue.js/Typescript】自社…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 コミュニティ…
週3日・4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【UI/UX】スマートフォンアプリのフルリ…
現在運営中のスマートフォン向け2Dゲームアプリのフルリニューアルに向けたUI設計・画面デザイン・クリ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿‐ |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【コーダー】スポーツ関連Webサイトのコー…
弊社デザイン部署にてWebコーダーとして、PV数の高いサイトを責任もってご担当いただける方を募集いた…
週5日
220,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webコーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Kotlin/Swift】モビリティーサ…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【大手総合商社グループ100%出資】GCP…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。Google Cloudに特化…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【アプリ開発エンジニア】大手総合商社グルー…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。Google Cloudに特化…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【JavaScript】モビリティーサブス…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・‐ | |
定番
【PHP/Pythpn/Java】自社オー…
【業務内容】 ・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・₋ | |
定番
【PHP/Pythpn/Java】自社オー…
【業務内容】 ・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・₋ | |
定番
【PHP】保守サポートやアップグレード等の…
当社は商品やサービスの認知獲得・興味喚起を促すデータを統合し分析。 戦略策定から施策実行までワンス…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Python】異常検出AIシステム開発に…
弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートするスタートアップで…
週5日
520,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・Ruby・Flask Django・… | |
定番
【Ruby】テスト自動化プラットフォームの…
AIを用いたソフトウェアのテスト自動化プラットフォームを自社開発・提供しています。 今回は、機…
週3日・4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【Ruby】家事代行サービスにおけるフルス…
家事代行クラウドソーシングサービスにおける、サーバーサイドとフロントエンドの開発をご担当いただきます…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・Ruby・RubyonRails | |
定番
【コーダー】モビリティーサブスクリプション…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
即日開始 Flutterエンジニア
弊社が新たに開発中の新規プロダクトの機能改修の設計・開発及び保守をお願い致します。 Dartを(F…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| ー・ー | |
定番
美容業界のDX支援☆【Flutter】ネイ…
ネイティブアプリの開発を担当(iOS/Android)。Tech Leadクラスを想定。自身でコーデ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【週5日/リモート/Node.js】Bto…
・ネイティブアプリが利用するAPIサーバー、予約データ管理やネイル画像の管理などのバックエンドシステ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
画像認識を中心としたAI・ディープラーニン…
弊社エンジニアリング部において、画像認識を中心としたAI・ディープラーニング技術の実装・開発、及び、…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | AI開発エンジニア |
| Python・当社のディープラーニング事業で行うプロ… | |
定番
【Ruby】自社プロダクトのWEBアプリケ…
自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、様々な開発・改善を…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyonRails・Rubyon… | |
定番
【Go】暗号資産やブロックチェーンに関する…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。将来を見通したマイクロサービスアーキテク…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| PHP・Go・Shell・SQL・- | |
定番
【スマホアプリ】複数プロダクトのAndro…
「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現。 人々のインフラとなり得るサービス群を…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOS・Androidエンジニア |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルスタック】BtoB向けSaasプロダ…
【企業概要】 当グループは、日本の都心部の大型複合開発や、主要リゾート地でのホテル&リゾート事業を…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【Vue.js】国内最大級の金融経済メディ…
【事業内容】 富裕層向け資産運用メディアや、複数の金融系メディアを運営し、専門性の高い資産運用コン…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js・*・ディレ… | |
定番
【Webデザイナー】新規Webサービスのデ…
【会社概要】 事業承継コンサルティング株式会社は、資産運用・相続・事業承継を専門とするコンサル会社…
週3日・4日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイン |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【フロントエンド】オンライン医療診断ツール…
【募集背景】 オンラインによる診察、処方箋発行、治験、メンタルケアなどのサービスを展開しています。…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| React.js・Redux・GraphQL・git… | |
定番
【Java】AIスタートアップ会社でのデー…
[案件概要] クライアントより依頼をいただいているECサイトのシステム移行プロジェクトにおいて、移…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・VBA・■技術要素 ・S… | |
定番
【UI/UXデザイン】ブラウザ拡張機能ポイ…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアアを開発します。 一般ユーザーと広告主をマッチングさせる…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Illustrator・Sketch | |
定番
【データエンジニア】クライアントの事業・サ…
(業務内容) クライアントが持つ多種多様かつ⼤規模なログデータを活⽤し、データ分析・活用を支える業…
週4日・5日
570,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・R・<業務環境> ・分析環境… | |
定番
【Node.js】ブラウザ拡張機能ポイント…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアを開発いただける方を募集します。 ■業務内容 ・ア…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| SQL・Node.js・React・■案件詳細 主… | |
定番
【React/Python】AIを活用した…
【会社概要】 AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 …
週4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Typescript・React・Dj… | |
定番
【iOS】決済・金融サービスの企画・開発
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概要 新たに手…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・<作業概要> ・新規プロダク… | |
定番
【UI/UXデザイナー】飲食店向けの自社シ…
自社サービス(飲食店向けシステム)のUI/UX改善業務 ・自社アプリ、HPのUI/UX改善→提案 …
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【PHP】ヘルステックベンチャーでのPHP…
医師キャリア支援事業のサービス開発をご担当いただきます。 サービスの企画、設計、開発、テスト、運用…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Linux・Unix・Lar… | |
定番
【TypeScipt|Go】オンライン医療…
【サービス内容】 臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・Typescript・Gin・Echo・AWS… | |
定番
【Java】超有名美容系予約サイトのエンハ…
◆ 内容: ・超有名美容系予約サイトの改修・機能追加に携わって頂きます。 ・要件定義~から関わっ…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【Go】暗号資産販売所のWebアプリケーシ…
・Go言語によるWebアプリケーション開発、API開発 ※バックエンド開発の具体的な業務としては、…
週4日・5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・※可能な方については、アプリケーション要件に基… | |
定番
【PHP】医療系求人サイト開発におけるサー…
当社は自社開発の医療系求人サイトを開発・運営をしております。 医師、看護師、薬剤師などメジャー職種…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・CakePHP・【開発… | |
定番
【インフラ】Webチケット流通プラットフォ…
【事業紹介】 レジャー施設やスポーツ施設などの 集客施設向けのチケッティングシステムを開発・販売…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 東京23区以外三鷹駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| shell・apache・tomcat・ | |
定番
【Java】人材サービス業向け社員向けスマ…
・人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発 ・スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアー…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js・Spring・… | |
定番
【Java】グルメサイトのWEBサイトエン…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【Vue/Python】自社プロダクトにお…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 【業務詳細】…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フロントエンド】新サービスリリースに向け…
2.5次元俳優や声優がメイン顧客となる、ノーコードファンクラブ運営ツールの開発業務 (HP制作、課…
週3日・4日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【AWS】クラウド型点群処理ソフトウェアの…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・【具体的には・・・】 ・数十GBのデータを… | |
定番
【AWS】リユース業界の最先端企業における…
AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。 AWSに精…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
[Webディレクター]ToC向けサイト企画…
【企業】 第2ステージに突入し、より大きく成長させるための人材募集を行います。 【業務内容】…
週5日
380,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| 週1日出社(木曜日の想定) テスト環境の利用が必要… | |
定番
[UIデザイナー]自社開発サービスのUIデ…
【業務内容】 メインポジションとしては自社開発サービスにおけるUIUXデザインの領域をご担当頂き自…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Go】医療×ITのSaaSタレントマネジ…
【企業概要】 「健康」というキーワードで世界を一つにする医療×ITのスタートアップ企業です …
週2日・3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS | |
定番
【WEBデザイナー】WEBサイト更新、バナ…
【案件概要】 過去に作成したクライアントサイトの更新作業を中心に行っていただきます。 バナーやL…
週5日
1.2〜1.8万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【技術営業支援】クラウドサービスに関する技…
案件概要: 法人向けクラウドサービスの導入から保守においてのマニュアル作成業務 案件内容: …
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | 技術営業支援 |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
弊社は急拡大の投資フェーズにおりますが、事業課題の解決及び更なる成長を遂げていきたく、新規事業企画を…
週4日・5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社の下記事業の中での新規事業案件のサービス開発におけるフロントエンド開発をご担当いただきます。 …
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【会社概要】 弊社の事業では、1,000万人以上が利用するスマホアプリ情報を扱う国内最大級の自社メ…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| CSS・JavaScript・PHP・Laravel… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
顧客基盤を持つ自社採用管理システムの新機能追加や、新規開発案件をお任せいたします。 新しいテク…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Coldfusio… | |
定番
【PHP】採用管理業務を支援するSaaS型…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】子育て…
今回は子育て支援サービスに関するアプリのAPI周りの開発に携わっていただけるエンジニアの方を募集いた…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Go・(技術スタック) ・バックエンド:… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】新規金…
自社金融サービスのサーバーサイド開発業務をお願いいします。 バックエンド、フロントエンド、インフラ…
週4日・5日
740,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
【案件概要】 CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューションを提供しており、事業…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP/Perl / 週4…
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Perl | |
定番
【フルリモ / Go/Node.js / …
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Go・Node.js | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】Fi…
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Java …
▽案件概要 ペット関連のWebサービスの改修、新機能開発案件です。 今回は、外部ベンダーで開発し…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / ReactNative /…
チームをリードしていただけるエンジニアの方を募集しております。 【業務内容概要】 ・マッチン…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| ・開発手法:スクラム開発 ・PRJ管理ツール:Ze… | |
定番
【フルリモ / C++ / 週4日〜】次世…
【業務内容】 エンジニアとしての経験を活かし、次世代CADの要件と仕様の理解を行い、チーム開発を牽…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / C++ / 週4日〜】建築…
【会社概要】 コンサルティング〜システム開発〜新規事業創出まで行う、DXコンサル企業です。属人的な…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
【会社概要】 弊社はAIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【UI/UX】スマートフォンアプリのフルリ…
弊社はアクティブユーザー数100万人を超えるゲームアプリの企画・開発・運営を行っている企業です。 …
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿‐ |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
弊社デザイン部署にてWebコーダーとして、PV数の高いサイトを責任もってご担当いただける方を募集いた…
週5日
220,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/Swi…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】クラウ…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。お客様にコンサルティングからシ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【Java】ユニフォーム販売システムの機能…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【PHP】大手ふるさと納税サイトの要件定義…
業務内容 大手ふるさと納税サイトのCMS開発やAPI開発など、要件定義から設計・コーディング・保守…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・ FuelPHP Cak… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP/Pythpn / …
モノづくりカンパニーによる、日常品ブランド。 人が集まる、人が楽しむ空間をプランニングからデザイン…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【フルリモ / PHP/Pythpn / …
人が集まる、人が楽しむ空間をプランニングからデザイン、製作・施工まで、トータルに「造る」会社です。 …
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・₋- | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】保守…
【企業概要】 当社は商品やサービスの認知獲得・興味喚起を促すデータを統合し分析を行い、 戦略策定…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業概要】 弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートする…
週5日
520,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・Ruby・Flask・Django・【… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Vue.js /…
AIを用いたソフトウェアのテスト自動化プラットフォームを自社開発・提供しています。 今回は、機…
週3日・4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Ruby/SPA】家事代行サービスにおけ…
家事代行クラウドソーシングサービスにおける、サーバーサイドとフロントエンドの開発をご担当いただきます…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / JQuery / 週…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【業務詳細】 当社のディープラーニング事業で行うプロジェクト・開発案件をゴールへ導くための技術開発…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、様々な開発・改善を…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週4日〜…
◇案件概要 キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / Java/Go / 週5日…
人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、私たちは「ITの力」を駆使し、ひとつひとつの解決を担うビ…
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、私たちは「ITの力」を駆使し、ひとつひとつの解決を担うビ…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Python /…
当グループは、約70年にわたり、日本の都心部の大型複合開発や、主要リゾート地でのホテル&リゾート事業…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【Vue.js】国内最大級の金融経済メディ…
【事業内容】 富裕層向け資産運用メディアや、複数の金融系メディアを運営し、専門性の高い資産運用コン…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【会社概要】 事業承継コンサルティング株式会社は、資産運用・相続・事業承継を専門とするコンサル会社…
週3日・4日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【React/Python】AIを活用した…
【募集内容】 金融に関する社会課題を解決するプロダクトの運用開発アプリケーション開発担当として、以…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Typescript・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 【職種…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】AI…
クライアントより依頼をいただいているECサイトのシステム移行プロジェクトの移行チームメンバーとして、…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・VBA・■技術要素 ・S… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアアを開発します。 一般ユーザーと広告主をマッチングさせる…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Illustrator・Sketch | |
定番
【マーケター/ディレクター】自社のアカウン…
アカウントプランナーして新規チャット広告事業における各案件の立ち上げを担っていただきます。 他職域…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | アカウントプランナー |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
私たちは、データ分野に特化におけるプロダクト開発力・コンサルティング力を強みとし、クライアント企業の…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・SQL・R・<業務環境> ・分析環境… | |
定番
【フルリモ / Swift/Objecti…
◇案件概要 企画から開発まで担っていただくiOSエンジニアを募集しています。 ◇作業概要 …
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【事業概要】 当社の自社サービスは大手外食チェーンから個店レベルの飲食店まで幅広い規模の飲食店に採…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週4日…
【業務内容】 ・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| 弊社は、Google・Cloudに特化した技術者集団… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】グロ…
◆業務内容 - 当社が開発をしているECサイトの開発・テスト・運用・改善 - 新規サービス及び、…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【PHP】ヘルステックベンチャーでのPHP…
医師キャリア支援事業のサービス開発をご担当いただきます。 サービスの企画、設計、開発、テスト、運用…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Linux・Unix・Lar… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【サービス内容】 臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go・Typescript・【作業内容】 自社プロ… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】超有…
【業務内容】 ・美容系予約サイトの改修・機能追加に携わって頂きます。 ・要件定義から関わって頂き…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・開発環境 Java8(Seasar2・S… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
◆ 内容 ・Go言語によるWebアプリケーション開発、API開発 ※バックエンド開発の具体的な…
週4日・5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・※可能な方については、アプリケーション要件に基… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社は自社開発の医療系求人サイトを開発・運営しています。 医師、看護師、薬剤師などメジャー職種だけ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・CakePHP・【開発… | |
定番
【AWS】Webチケット流通プラットフォー…
【事業紹介】 テーマパーク、水族館、美術館、といったレジャー施設やスキー場、プール、といったスポー…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東京23区以外三鷹駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| shell・apache・tomcat・ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
スマホアプリ開発において、クラウドサービス利用提案、フレームワーク熟知したシステム提案を顧客、プロジ…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【フルリモ / Vue/Python / …
【会社概要】 AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスの フロント周りを開発支援い…
週3日・4日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】クラウ…
【業務内容】 ・数十GBのデータを高速に処理できるAWSアーキテクチャの設計・開発 ・サーバーコ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】リユ…
▼案件概要 AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・AWS | |
【デザイナー】某テレビ局のモバイルサイトに…
弊社が運営しております某テレビ局のモバイルサイトにて配信するデジタルコンテンツ・バナー等のデザインを…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| Photoshop・Illustrator・Adob… | |
定番
【ジュニア歓迎】フロントエンドエンジニア
主な業務はサービスサイトやLPのデザイン制作物のコーディングです。HTML、CSS、Javascri…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Java】FX、暗号資産の取引、経理、顧…
【業務内容】 既存システムの機能追加・改修業務 (法令対応、不具合修正などを含む) データの収…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 品川浜松町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア【Java】 |
| Java・MySQL | |
定番
【Python、React】厨房機器IoT…
【業務内容】 AWS環境を用いてMQTT、HTTPで機器と通信、制御する機能を構築します。 管理…
週5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町(フルリモート可) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Python、React) |
| Python・React、AWS | |
定番
LINE mini appプロジェクトの開…
数十万人規模のto C向けWebアプリケーション開発のポジションです。 POS連携や会員連携を伴う…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・A… | |
定番
社内SE
①社内向業務システムの再構築を行う ②新規業務システムの開発(一般消費者向けはないが、取引先向けな…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿東池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / C# / 週4日〜】Bto…
【企業情報】 1.個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムの開発・販売 2.ペーパー…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・C・C++・C#・Typesc… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
自社サービスのWEBコーディングを依頼させていただきます。 【業務内容】 ・自社独自CMSを…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
【仕事内容】 スマートフォンゲームの企画、開発及び運用を担当していただきます。 【具体的な業…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
【業務内容】 サブシステムの開発 / 保守運用業務 ※WEB アプリケーションの開発 弊社…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】アプ…
オフショアで開発したtoC向け自社アプリのクラウドインフラの運用管理設計ができる人材を探しております…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【QAエンジニア】システム運用保守のテスト…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつか…
週2日・3日
350,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・Java・- | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決を行っているAIベンチャーです。 【…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Node/TypeScri…
【業務詳細】 主にWebアプリケーションのAPIサーバー開発と、フロントエンドサーバー開発のコード…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
業務概要: フィットネスなど有名サービスを複数展開する企業様のインフラ全般を担当する情シス部門の社…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木南青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】航…
某航空会社の発券予約システムの開発を行っていただきます。 基本的にフロントメインとなりますが、サー…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・React.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務内容】 セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務です。 1機能単位…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
UIUXデザイナーとして、自社サービスを始めとしたサービス・プロジェクトに Webデザイナーとして…
週4日・5日
440,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リードエンジニア】自社クラウドサービスを…
【業務内容】 ・『Seculio』における新機能の開発 ・『Seculio』における既存機能の改…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・Ruby・Go・Typescrip… | |
定番
【フルリモ / ReactNative/R…
【業務内容】 ※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントのスマホ向けのリプ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・ReactN… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 【作業…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / React/Go / 週4…
弊社では、オンラインによる診察、処方箋発行、治験、メンタルケアなどのサービスを展開しています。 今…
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / AWS/GCP / 週4日…
◇案件概要 キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】国内最…
当社は国内No.1のスニーカー&ハイブランドフリマを運営しています。 ■お任せしたい業務内容 …
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・■開発環境 【Web】 -言語・FW:Go… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日〜】テスト…
■業務概要 プロダクトのQAエンジニアとして、リリースのための品質保証業務をご担当いただきます。 …
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| QA・■具体的職務 ・内製、外注を含んだ受入検査の… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
【業務概要】 ネイティブ (Swift/Kotlin) で実装されたアプリをFlutterを用いて…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
弊社が運営するニュースアプリのiOSアプリ開発全般を担当していただきます。 【業務内容】 ・…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・UIKit | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐・【開発環境】 ・言語:Kotli… | |
定番
【フルリモ / Python/Go / 週…
弊社が運営するプロダクトのサーバーサイド開発全般を担当していただきます。 【業務内容】 ・A…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Django・Flask | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
弊社請け負ったCM制作やプロモーション映像の制作の担当をお願い致します。 TV番組やCM用の制作を…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| AfterEffects・Unity・Unreal・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】公共…
弊社サービスの根幹を支えるクラウドインフラの設計支援を行って頂けるインフラエンジニアの方を募集します…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 今後新規…
週3日・4日
260,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【C#】音声認識ソリューションを使用したデ…
【業務内容】 音声認識ソリューションを使用したデスクトップアプリケーションの保守・追加開発。 基…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋池袋 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL・ASP… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・AWS基盤へのオンプレからの移行および新規シ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇業務概要 証券会社投信システム(約定計算)の基本設計をお任せします。 ◇作業範囲 投信…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
【案件概要】 以下の業務に携わっていただきます。 ・AWS上でのSSL-VPN(Fortigat…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原門前仲町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| FortiGate・AWS | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】ロボテ…
■ご担当頂きたいこと 当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署と連携してプロ…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| ■技術環境 デザインツール:Figma・・Adob… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務システムの開発を…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・-・Django | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。 【業務内容】 ・KP…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発になります。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.jp・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】AI…
【案件概要】 今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発で…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サービスの魅…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter・◆具体例 ・カスタ… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社はを中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営し…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 ・機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【フルリモ / Go / 週5】広告代理店…
▽案件概要 地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】中古…
今回の募集は、大手中古車販売会社の社内基幹システム開発をお願いできる方を募集します。 現在50…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフルスタックエンジ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・◇作業概要 … | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS/ …
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。 担当業務は主にデザ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Shell・SQL・◇作業概要 ・Go言語に… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
【業務内容】 (当社のクライアント様案件になります。) ・クライアント様のCMSの開発(word…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサ…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・【業務内容】 ・自社サービス… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】エンタテインメ…
■案件概要: エンタテインメント系チケットサイト構築案件 ■求める人材: ・プロジェクトの…
週5日
370,000〜550,000円/月
| 場所 | 神奈川新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【PM】幼稚園・保育園向け写真販売システム
幼稚園・保育園向け写真販売システムに関連する新サービスのプロジェクトマネジメント業務をお任せいたしま…
週5日
2.8〜5.7万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【経営企画】ゲーム開発会社でのデータ作成・…
【業務内容】 ・データを集めるための入力環境の要件設定と入力環境の作成及びメンテ ・集めたデータ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 経営コンサルタント |
| SQL | |
定番
Salesforceの導入案件
【業務内容】 Salesforceの導入に関わる提案から設計、開発、保守まで関わっていただきます。…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【WEBデザイナー】ブランディングと事業展…
中小企業、生産者、メーカー、教育機関などの事業展開に関わるプロモーションツールの企画制作をお任せしま…
週3日・4日・5日
9〜1.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿西18丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【業務委託/メンバーポジション】フルリモー…
【業務内容】 ・設計に応じた機能の実装 ・トラブル対応や、機能改修などの運用作業 ・開発環境、…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(メンバー) |
| Typescript・SQL・API:TypeScr… | |
定番
【Python】フィットネス向け自社サービ…
【案件概要】 自社サービスの開発をアジャイルで担当いただきます。 【期間】 即~長期 【勤務…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄東別院(フルリモート) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Python) |
| Python・AWS | |
定番
【Python】リアルタイム画像解析AI技…
【企業】 ・テクノロジーの力でフィットネス業界を支援するプロダクトの自社開発を行っています ・当…
週2日・3日・4日・5日
2〜3.6万円/日
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・C#・Dj… | |
定番
【Kintoneエンジニア】kintone…
◆業務内容:弊社既存導入済のサイボーズ社kintoneで構築した 販売管理システムの保…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Kintoneエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【PMO】自社SaaSサービスの企画&プロ…
●業務内容 ・アウトバウンドcallでの商談アポ獲得 ・インバウンドリードに対する架電での商談ア…
週3日・4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 豊洲築地市場 |
|---|---|
| 役割 | インサイドセールス |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとしてサー…
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| MariaDB・Mysql・Bash | |
定番
【フルリモ / Android/Kotol…
【業務内容】 自社のAndroidアプリ開発をご担当いただく方を募集いたします。 就活生へ…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
【企業概要】 これまで私たちは、IT技術を活用し、顧客のビジネス課題に寄り添いながら、 成長を続…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
▼案件概要 ①デバイス管理及びEPP/EDRの導入・運用、インターネットアクセス制御の導入・運用、…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】GCP…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(予約…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / C#/Python / 週…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Java/kotlin /…
現在のサイトの基盤を元に、β版をリリースする予定です。 リリース予定の新サービスの API 実装を…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・- | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
主にWebアプリケーションに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニアと協調して行っていただきま…
週4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / React/Python …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
▼仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】EC…
【業務内容】 Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・【会社概要】 Webサイト… | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホ…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala・… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】ク…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・【… | |
定番
【フルリモ / Java/SpringBo…
大手ECサイト運営会社における業務を想定しています。 今までは、PoCとして開発を行ってきましたが…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】Po…
【業務内容】 Microsoft製品を活用して業務プロセスの自動化を実現して業務効率を向上させるこ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PowerApps・PowerAutomate・Lo… | |
定番
【新規事業】開発エンジニア(Web3領域)
【概要】 Web3やNFTなどに関連する新規事業のエンジニアとしての開発業務全般 【業務内容】 …
週5日
670,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・AWS・Solidity・Ruby・on・… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/jQuer…
◆案件概要 弊社では、株式やFXなどの金融商品を扱うオンライン金融サービスを提供しています。 …
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
【業務内容】 大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注し…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
弊社では、ソーシャル経済メディアを提供しています。 【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 …
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・【開発環境】 ・開発言語:な… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】開発…
【業務内容】 ・開発者がより高速に開発できるための開発環境の改善 ・CI/CDやデプロイパイプラ…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AdobeXD / …
【会社概要】 動画事業を中心に顧客課題に寄り添ったコンテンツを作成運用しています。 動画以外に、…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿下北沢駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
【会社概要】 動画事業を中心に顧客課題に寄り添ったコンテンツを作成運用しています。 動画以外に、…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿下北沢駅 |
|---|---|
| 役割 | モーションデザイナー |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】自社ニ…
既存のiOS/AndroidアプリのFlutterリプレイス版における、品質を担保してリリースするた…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / Python/R /…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
840,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・R | |
定番
【TypeScript/Vue.js】運用…
オペレーション業務から人々を解放する為の自動化プロダクトを提供しています。 【案件の魅力】 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
「多言語」に対応した制作を武器に展開してきた制作会社で、現在も紙のグラフィックデザインとウェブのクリ…
週4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するベンチャー企業です。 ▽仕事内容 既存、新規事業…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / C#/AWS / 週3日〜…
◇概要 物理・数学の専門知識を持つトップクラスのエンジニアが集まっており、クライアント内の暗黙知・…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【募集背景】 ・自社プロダクト開発がスタートし、業務が拡大していることが背景です。 【業務内…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| 【企業情報】 弊社はベトナムと日本にオフィスを持ち… | |
定番
【デザイナー】自社アプリサービスにおけるU…
【業務内容】 ・新規アプリのUI/UXデザイン ・UI/UX設計 ・トンマナの設定、スタ…
週3日・4日
450,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| 【会社概要】 医師のコミュニティサイトの運営によっ… | |
定番
【フルリモ / React/Next.js…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
弊社では、産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するさまざまな事業を展開しています。 …
週5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
■業務内容 現行のアプリからFlutterでフルネイティブ化を進めていただきたいです。 スニーカ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / Cisco / 週5日】受…
【企業情報】 ITコンサルティング、アプリケーション開発、インフラ構築運用保守、など様々な事業でク…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Cisco | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営するスタートアップです。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】飲…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日・4日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails・【企業概要】… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】広…
【業務内容】 ・自社Webアプリケーションの開発をお願いしたく思っております。 └サーバーサイド…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/JQuery /…
【企業紹介】 当社では、主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Framew… | |
定番
【フルリモ / Python/PHP / …
【企業紹介】 主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、及びそのた…
週4日・5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・SQL・Laravel・開発環… | |
定番
【フルリモ / QA / 週5日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週5日
550,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
Webサイトとブラウザ拡張機能をベースとしたポイントメディアの開発予定です。 ■業務内容 ・We…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| SQL・Node.js・React | |
定番
【フルリモ / Scala/TypeScr…
複数のプロダクトを並行展開しています。 プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービス…
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Scala・Kotlin・Typescript・Pl… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【想定依頼内容】 -デザインのエレメントパーツの洗い出し・重みづけ -エレメントパーツの制作 …
週3日・4日
260,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・【会社概要】 お客様向けにデザイ… | |
定番
【HTML/CSS】バナー制作・LP・ライ…
ヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開しています。 【案件内容】 …
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
【業務内容】 人材サービス業向けのスマホアプリの開発をご担当いただきます。 就業中(求職中)…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js・Apache・… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】人…
【業務内容】 人材サービス業向けのスマホアプリの開発を担っていただける方を募集します。 就業中(…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React・Node… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 【募集ポジシ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・React(react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】バック…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 当社…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【HTML/CSS】販促物/印刷物発注サイ…
【企業概要】 ブランディング開発やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制作を行っ…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / 週5日】大規模ネットワーク…
【業務内容】 エンド様への提案から実対応(設計、検証、構築)までの全工程を弊社チームで実施いたしま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原品川駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【React】自社サービスフロントエンド開…
自社で開発したプロトタイプのシステムをベースに、商用パッケージを新規開発するプロジェクトの開発担当エ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
【業務内容】 弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただき…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Unity | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、バナーデザインを中心に担当いただくデザイナーの方を募…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社で受託しているサイト制作やWordpress制作の案件に携わっていただきます。 【職務内容…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・顧客情報システム部門のインフラ担当 ・顧客が利用するインフラ(NW/AWS/OS)…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】顧…
【業務内容】 TypeScript・React(Next.js)を利⽤したWebフロントエンドの開…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・ | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
自社開発している、中小企業が集客のために利用する広告代理店への支援サービスや、Googleマイビジネ…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Vue.js・MySQL・AWS・Ci… | |
定番
【フルリモ / Vue/TypeScrip…
【業務内容】 弊社コミュニティサイトサービスにおける開発を担当いただきます。 ウェブサービスの改…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【業務詳細】 自社開発をしているクラウドファンディングシステムのクライアントページのデザインを今回…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】法律×…
弁護士事務所向けの案件管理システムや弁護士用広告メディアの運営を行っている企業です。 【案件概…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自治体向け医療・介護関連データ利活用ビジネスに関するシステム開発をお願いします。 【業務内容】…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
今回は自社制作のアプリの改修や機能追加をご担当いただけるエンジニアの方を 募集いたします。 弊社…
週3日
290,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【UiPath / 週5日】モーターパーツ…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 【業務…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| VB.NET・VBA・UiPath・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular.js / …
【業務内容】 弊社が運営する電子チラシ配信サービスにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきま…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・cordov… | |
定番
【フルリモ / Python/SQL / …
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【HTML/CSS】WEB制作会社でのデザ…
【業務内容】 弊社の顧客から受託したWEBサイトの制作業務をご担当いただきます。 ・静的サイ…
週3日・4日
220,000〜260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【UIUX】某証券会社のスマホアプリ開発に…
某証券会社のスマホアプリ開発案件において現在リソースが不足しているためデザイナーの増員を図るべく募集…
週2日・3日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリデザイナー |
| Figma XD Sketch | |
定番
【PHP】受託業務システム開発のサーバーサ…
■業務システム開発運用 弊社受託既存システムの追加機能開発の設計~リリースまでご担当いただきます。…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(リーダー) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】保険業向けPJ…
エンド様の業務システム(Webマイページ)の更改 基幹システムはI/Fでデータ連携をご担当いただき…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 神奈川天王町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・フレームワーク⇒OW… | |
定番
[Androidエンジニア]Android…
【業務内容】 ・Androidにてカメラを用いたアプリケーションの作成 ・TensorFlowや…
週5日
580,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
[C#]業務用ローコードシステムの機能追加…
【案件概要】 C#による業務用ローコードシステムの機能追加開発 【期間】 即~長期 【勤務地…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(C#) |
| C#・WPF SQLServer | |
定番
【Unityエンジニア】バーチャルカラオケ…
▶ 業務内容 トピアの音声関連の開発全般 ・配信部分の音声に関わる設計/実装 ・ノイズキャンセ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
【Unity】エンジニア
Unityを使用したスマホ向け多人数協力対戦シューティングアクションゲームの、 インゲーム全般(ゲ…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| ー | |
定番
【Unity】エンジニア(アウトゲーム)
Unityを使用したスマホ向け多人数協力対戦シューティングアクションゲームの、アウトゲームUI全般を…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| ー | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■概要 SaaSプロダクト(CRM、請求機能など)に関するフロントエンド開発を担当いただきます。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / ActiveDire…
今回は、某大手銀行のシステム運用を担っていただける方を募集します。 【業務内容】 ・WIND…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| VBA・SQL・MSActiveDirectory・… | |
定番
【システム】化粧品企業のヘルプデスク業務
社内のITヘルプデスク業務に携わっていただける方を募集いたします。 (主な業務) ・エンドユ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop …
本サービスは、クラウドサービス利用時のセキュリティ不安を解消する、クラウドリスク評価データベースです…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
[iOSエンジニア]iOSアプリ向けSDK…
【業務内容】 ・SwiftでのネイティブiOSアプリ開発 ・iOSアプリ向けSDKの開発・改善 …
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
[QAエンジニア]新プロダクトの品質の向上
【業務内容】 本人確認プラットフォームや新プロダクトの品質を高めていただけるQAエンジニアを求めて…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
注目
[PdM]プロダクトのディレクション業務全…
【業務内容】 ・エンジニア・デザイナーへインプットする要件・仕様書の作成 ・開発チームに対する仕…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【UX】ユーザーの体験価値を測定・評価する…
【業務内容】 ・PdM / PMMと共に要件定義(課題整理、UI調査、プロトタイピング...etc…
週2日・3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】 …
動画配信サービスのiOS・tvOSアプリの開発及び運用を担当していただきます。 ・動画配信モバ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【C++ / 週5日】受託サービスにおける…
【主な業務内容】 システム開発(受託・SES) facebook・iPhone・Androidア…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町、武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Visual・C++ | |
定番
【フルリモ / Vue.js/React …
■業務内容 本ポジションでは、当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのフロントエンド開発を…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
弊社求人事業部の運営するメディアの開発業務をご担当いただきます。 <業務内容> ・コンバージ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / PHP/Ruby / 週4…
▽業務詳細 ・エンジニアサポート ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【業務概要】 自社技術を活用した観光アプリ開発におけるUI/UXデザイナーを募集しております。 …
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週5…
大手広告代理店や既存のマーケティングサービスでは対応できなかった、多くの予算・時間を割けない地方の中…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Firewall | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】I…
サポート内容は下記になります。 ①マンツーマンでのメンタリング1on1 ②質問対応 ③課題のレ…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【上流SE】電子契約サービス運営企業での社…
【案件内容】 今回は社内のIT環境整備から情報管理までご対応いただく、社内SEを募集しております。…
週1日・2日・3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四谷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Ruby/PHP / 週4…
ビジネスサイド(マーケ、UXチームなど)と一緒にサービスグロースのためにサーバーサイドエンジニアとし…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【Java】ECサイト保守案件
当社が請けているプロジェクトにてECサイト保守案件の担当をお任せいたします。 【作業内容】 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Seaser2・Oracle11g・Lin… | |
定番
【SQL】医療機関のデータ運用・保守業務
今回は医療機関データ処理の運用・保守業務に携わっていただける方を募集いたします。 【案件の魅力…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週4日〜】…
今回は弊社でご活躍いただけるUI/UXデザイナーの方を1名募集いたします。 (主な業務内容) …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
▽仕事内容 新規で開発しているオンライン授業プログラミングプロダクトのWebUI/UXデザイン業務…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Skech・Figma | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / iOS/Swift / 週…
【募集背景】 すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいて…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / React/Nuxt.js…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・ReactNative・Nux… | |
定番
【Next.js】新規法律関係WEBサービ…
【業務内容】 下記2案件両方を担当頂きます。 ・法律の関するデータベース検索・調査システム ・…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Next… | |
定番
【Ruby】急成長中クラウドファンディング…
【案件内容】 ローンチ以降成長を続けている当社のクラウドファンディングサービスにおいて、システム基…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails(5.2)(slim利用)、Ru… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
弊社では煩雑化する会計周りをシンプル化・DX化を促進する為、経理業務管理ツールの開発を進めてます。 …
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【Java】某自動車会社様次世代IoTプロ…
【業務内容】 自動車とメーカの通信基盤、サーバ間で各種データの取得、更新を行うAPIモジュール開発…
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
私達と一緒にブロックチェーンゲームを手伝ってくれる人を探しています。 ▼仕事内容は下記のいずれかと…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Go・JavaScript・… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
【業務内容】 SEOアフィリエイトメディアの収益改善を行うためのデータ分析SaaSのクローズドベー…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿吉祥寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
実施率向上に向けた、仕組み作り、業務効率化を目的としたSaaS化、情報設計、UI/UXデザインをお任…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
■業務内容 ・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【CSS/HTML】金融メディア・新規立ち…
弊社では金融メディアプラットフォーマーという立ち位置で、WordPress、RCMS、自社CMSでW…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件内容】 システム開発チーム内で一緒に業務を行っていただきます。 目先の開発スピード向上と長…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・React | |
定番
【Python/Go】ブランドプリペイドカ…
・Goを用いたAPIサーバの設計、開発、運用 ・PCI DSSに準拠したインフラの設計、構築、運用…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Python・Go・プラットフォーム:・AWS(EC… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】ア…
■ 構築先 ・クライアント仮想サーバ環境で払い出された仮想サーバ ・仮想基板、ネットワーク管理操…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 クライアントワークにおいて、Webサイト制作においてHTML、CSSでのマークアップ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】映像配…
弊社が運営する動画配信サイトへ書籍の配信サービスを追加するため、このサービスの追加機能の開発をお任せ…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / React/Node / …
旅行商品検索プラットフォームの開発です。 今回は、大手・中堅旅行会社向けの旅行商品検索プラットフォ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / UiPath / 週3日〜…
RPA(UiPath)単独ソリューション提供に加えて、RPAのコラボレーションに関連ソリューション推…
週3日・4日・5日
580,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
プロダクトのAPIサーバー開発を中心として、サービスを安定運用するための基盤システム整備まで幅広い開…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
最先端のアルゴリズムを開発する会社であるため、機械学習に興味がある方を歓迎します。 ◆業務内容…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
新しいアーキテクチャ(jamstack、サーバーレス)の構成における設計、構築、テストをリードしてい…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川戸越銀座 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 インフラ分野の設計や導入支援、アーキテクチャ設計、環境構築、クラウドへの移行支援を担…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・EC2・EKS・ECS・RDS・CF・ELB… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【業務内容】 稼働中のECサイトを新サービスに適用させるための大規模改修として、オンプレからパブリ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・SQL・ShellScript・SQL・O… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
【案件内容】 ・自社サービスシステムにおけるマニュアル作成業務をご依頼いたします。 -最初は社…
週3日・4日・5日
330,000〜5,080,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【業務内容】 官公庁・自治体等の案件入札・落札情報を探せる自社サービスの周辺サービスとしての新規事…
週3日・4日・5日
500,000〜730,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / ゲーム / 週5日】スマー…
【業務内容】 ・スマートフォンタイトルの企画及び仕様作成、簡易なデバッグについて、開発からリリース…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【案件概要】 今後、主力事業だけではなく、法人向けサービスの拡大や新規事業の展開を行っていく上で …
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
現在自社サービスを拡大させるためのUI開発をしております。 具体的には、SEOの改善や成約率アップ…
週3日・4日・5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【JavaScript/PHP】スマートフ…
【案件内容】 弊社が運営する1,000万人以上が利用するスマホアプリ情報を扱う国内最大級のWebサ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / C#/C++ / 週3日〜…
【募集要件】 製造、物流、医療、スポーツ等、様々な分野で画像処理を中心としたセンシングソリューショ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| Python・C・C++・C# | |
定番
【VBA】デジタルエンターテイメント分野N…
【案件概要】 弊社でヘルプデスク業務を担っていただける方を募集いたします。 (対応事項例)…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 池袋東池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】決済…
【案件内容】 現在当社では、自社で開発した既存のPHPシステムを新たにJavaで構成するプロジェク…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・■OS:Linux、Windows ■D… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
▼案件内容 1、オンラインプログラミング教材を作成するための業務支援 ツールの開発・運用をお願いし…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
開発グループのフロントエンドを募集しております。 マーケティング施策の高速PDCAの実現や、受…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Next.js | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件内容】 クライアントが抱える課題に対して、統計的・機械学習的手法によるソリューションを調査研…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Linux/AWS …
【業務概要】 顧客情報システム部門のインフラ担当として、当社社員と一緒に従事いただきます。 …
週5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
某外資系企業様向けの情報システム部のネットワーク運用業務になります。 構築作業もあり、試験仕様書や…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Tanium・Cisco・Umbrella・ArcS… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週4…
【業務内容】 弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおい…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】国内…
【主な業務内容】 インフラ設計、構築、運用、保守、管理を行なっていただきます。 また内製アプリケ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・LINUX | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】新…
・複数のWEB制作プロジェクトのデザイナーとしてご参画いただきます。 -クライアントmtgの参加…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
日本でも珍しい、ハード、ソフト、クラウドサービスを全て自社で行なっている生粋のテクノロジーベンチャー…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【開発環境】 バックエンド:Python・(FW:… | |
定番
【Typescript】自社既存サービスの…
<業務内容> ・機能の要件を、タスクフォースチームや部外関係者と一緒になって議論する ・機能の要…
週5日
330,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・AngularJS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】新規開…
【募集背景】 Webプランニング力、技術力を武器に、様々な大手クライアントのデジタル施策の企画から…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・jQuery・CakePHP… | |
定番
【Nuxt.js】HP制作サービスのフロン…
ホームページ作成サービスのフロントエンド開発業務を担っていただける方を募集いたします。 <業務…
週3日・4日・5日
580,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】データ…
製造業様向けAWSを用いたデータ利活用支援 次期DX基盤構築のための各種作業支援内容 ・ A…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| AWS・Redshift | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
【案件概要】 携帯電話会社のホームページ・リニューアル開発にご対応いただきます。 ※クライアント…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 以下の業務をご担当いただきます。 ・導入先会社の古いExcelマクロをTablea…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・Excel・Tableau | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 下記の業務をご担当いただきます。 ・既存システムの仕様調査 ・社外APIの使用方…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・MySQL・CentO… | |
定番
【Webデザイナー】自社案件のクリエイティ…
【業務内容】 自社案件のWeb・クリエイティブデザイナーを募集しております。 ・バナーデザイ…
週2日・3日
140,000〜240,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| 【その他情報】 チーム人数:2名 就業:フルリモ… | |
定番
【UI】業務効率向上に関するtoB向けの自…
企業の生産性を可視化し、従業員の働き方を変えることで、生産性を向上させ営業利益を拡大を支援する次世代…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【UI】自社HR領域のアプリ、webのUI…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで様々なデザイン業務に携わりま…
週4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【アプリエンジニア】大手通信キャリアのサー…
・通信サービスに係る様々なプロダクトのフロント開発をお願いします。
週3日・4日・5日
180,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・•・GitHub・ •・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】アジャ…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したシステムの監視・運用設計および監視・構築…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
【案件内容】 当グループ会社のお客様が利用するアプリケーションの動作や、各種ツール、Webサービス…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
注目
【SREエンジニア】大手通信キャリアのサー…
・通信サービスに係る様々なプロダクトのSREエンジニアを募集します。
週4日・5日
180,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| AWS・GCP・Azure Git・•・AWS・G… | |
定番
【React、Next.js】受発注マッチ…
・ 設計事務所と部材メーカーとをつなぐ受発注マッチングサービスの本開発フェーズ。(PoCを~6月末で…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア / アーキテクト |
| AWS | |
注目
【データエンジニア】データ基盤開発(SE)
機能設計とテスト設計を担当、ETLに必要なテーブル・入出力の設計等 【作業期間】 :10月~(長期…
週5日
620,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・ー | |
定番
データ・MLエンジニア
* エネルギー業界向けに機械学習を用いた予測システムの開発・運用(詳細は面談にて) * 上記のた…
週4日・5日
750,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・AWS・Azure | |
定番
【Java/Python/Go/React…
【業務内容】 チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ■会社概要 クラウド、OSS、アジャイル、DevO… | |
定番
【SQL】既存システム保守開発、DB整備等
【案件概要】 クライアントから依頼をいただいている、DB整備をご対応頂ける方を探しています。 P…
週5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・開発環境 : 【OS】 Windows1… | |
定番
【Java】AI解析基盤構築案件
■案件内容■ AI解析基盤の新規システム構築 基本/詳細設計・実装~単体/結合テスト Spri…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・jQuery・Spring・F… | |
定番
【ディレクター】料理レシピ動画メディアのコ…
弊社が運営する料理レシピ動画サービスのコンテンツに関わる業務を担当いただきます。 主な業務 …
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ‐ | |
定番
【AWS】クラウド人材管理ツールのインフラ…
クラウド型の人材管理ツールを自社開発しております。 現在急成長中のクラウド人材管理ツールのイン…
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【Go】クラウド人材管理ツールのAPI開発…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・(開発環境) 開発言語:Golang… | |
定番
【PM】ライブ配信プラットフォーム
ライブ動画配信プラットフォームにおいて、プロダクトマネージャーや運営からの案件要望を把握し、中国にい…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| <業務内容> ・プロダクトマネージャーや運営からの… | |
定番
【HTML/CSS】AIベンチャーにおける…
【業務内容】 ・会社横断のマーケティングチームにおけるランディングページ、フライヤー、HTMLメー…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・■会社概要 AIを利活用したサー… | |
定番
【PM】広告×AI事業の立ち上げを行うPd…
【業務内容】 1人目の専任PdMとして、チャットブーストCVのサービスのグロースを担当していただき…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【会社概要】 当社は、最先端のテクノロジーを活用し… | |
定番
【ディレクター】広告×AI事業のプランナー
【業務内容】 クリエイティブ・ディレクター、プランナーのマネージャーとして、新規事業における、クリ…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| 【会社概要】 当社は、最先端のテクノロジーを活用し… | |
定番
【PM】プロダクト企画ディレクター
【業務詳細】 ・ボディメイクの新規プロダクト/サービス企画およびプロダクトマネジメント ・新規プ…
週4日・5日
570,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【HTML/CSS】サイト運営プラットフォ…
【業務内容】 Web体験全般におけるプロダクトのブランドイメージに沿ったコミュニケーション設計、実…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・‐・JavaScript | |
定番
【PM】EdTech/ICT教材開発
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PHP】大手クライアントWEBサイトのリ…
【業務内容】 サッカークラブのサイトリニューアル案件をお任せいたします! 案件を担当しているWe…
週5日
350,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・【開発環境】 ・サーバーサ… | |
定番
【Go】広告代理店向けDMP
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 当社…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【ディレクター】ボディメイク、ヘルスケア大…
想定される具体業務: ・ボディメイクサイトリニューアルに向けた企画設計業務 ・ボディメイクサイト…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
外資系コスメブランドのWEBデザイン業務(…
外資系コスメブランドのクリエイティブ関連の業務を下記を中心にお任せいたします。 ディレクションは米…
週3日・4日・5日
330,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
注目
【WEBディレクター】ECサイトの運用・構…
【企業】 名古屋に拠点をおいたラグジュアリーセレクトブランド 【業務内容】 店舗販売中心に…
週2日・3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | ECディレクター/デザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【C#/.net/SQL】衣食住にまつわる…
【企業概要】 弊社は住宅リフォームから設置型ドリンク販売サービス、LED照明レンタル、学習塾とオン…
週4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸市民広場駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C#・VB.NET・SQL・.net・■具体的な仕事… | |
定番
【PHP/Javascript】不動産情報…
【案件概要】 不動産情報B2Cサイトの改修案件の設計者を募集します。 ・現在サービスインしている…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【PM】自社SaaSプロダクト開発における…
【企業概要】 大手総合商社100%子会社である当社は、新規事業の開発・運営に注力しております。 …
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【業務詳細】 ・コンテンツ企画立案 ・ワイヤーフ… | |
定番
【PM】オンライン医療診断ツールアプリの開…
【職種詳細】 弊社のプロダクト群から共通で利用される認証基盤やビデオ通話関連基盤の開発プロジェクト…
週3日・4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【shopify】海外向け自社腕時計ECサ…
【企業概要】 オリジナルの機械式腕時計ブランドの企画開発製造卸販売を行う会社です。 【業務内…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王線平山城址駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・Illustr… | |
定番
【Ruby】自社ヘルステックサービスのサー…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・【案件の魅力】 … | |
定番
【HTML/CSS】BtoC向けポイントサ…
今回は弊社で対応しています大手ポイントサービス(BtoC)に関する、 サービス運用及びシステム改修…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
| HTML・CSS・【業務内容】 ・プロジェクト管理… | |
定番
【flutter】flutterアプリの追…
【案件概要】 ネイティブで実装されているアプリをflutterに置き換える開発と その後のflu…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| flutter | |
定番
【Java】大手通信会社/管理画面のSPA…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・<プロジェクト内使用言語など… | |
定番
【TypeScript】某大手求人媒体の社…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・SQL・Vue.js・Reac… | |
定番
【PMO】クレジットカード系エンドユーザ向…
●作業内容: ・STシナリオ作成や仕様の説明、環境説明は現在参画済みの開発チームから実施、本体制で…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【SQL】業界内トップシェア店舗予約サイト…
ユーザー数数百万人規模、登録店舗数も数千店の業界内トップシェアサイトの大型リニューアル案件となるため…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
FXシステムの大規模新規開発案件において、開発をご担当頂くJavaエンジニアを募集しております。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Java | |
定番
【Azure】通信事業者Azure設計構築…
◇概要 EOSLに伴い、Iaas(既存Linux)をAzureに移行します。 現在は調査段階です…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【HTML/CSS】サイト運営プラットフォ…
【業務内容】 Web体験全般におけるプロダクトのブランドイメージに沿ったコミュニケーション設計、実…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・‐・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
【案件概要】 自社で開発を行っているアプリの企画や設計、開発、運用といった全フェーズに携わっていた…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails・【工程】要件定義・… | |
定番
【アーキテクト】基幹システム開発プロジェク…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【Java】グルメサイトエンハンス開発
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【React Native/Nuxt.js…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Native | |
定番
【UI/UX】自社WEBサービスのデザイン…
◇会社概要: 荷物を届けたい人とフリーランスドライバーをつなぐマッチングプラットフォームや、ドライ…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Sketch・Illustrator | |
定番
【Swift】子育て支援アプリの開発業務
妊娠妊活子育て中のママパパ向けに情報を届けるWebサービス/アプリの開発運営を行っております。 …
週5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・(技術スタック) ・バックエンド:・g… | |
定番
【PHP】電子書籍取次システム開発支援
◇案件内容: 既に稼働しているシステムに対する機能拡張の改修作業がメインになります。 オンプレ環…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【Ruby】自動応答チャットボットの追加改…
【会社概要】 特定分野のソリューションとプロダクトをご提供しております。 Webアプリケーション…
週3日・4日・5日
410,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・就業時間:コアタイ… | |
定番
【Android/iOS】結婚、婚活支援サ…
アプリ(iOS/Android)をよりユーザーに価値を提供するためプロダクト価値を高めることが出来る…
週5日
350,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・AWS・Slack・Confl… | |
定番
【UIデザイナー】新規事業におけるWebサ…
今回、新しいサービスを、新しい組織を、新しい会社を、新しいビジョンを創るにあたって共に「デザイン組織…
週4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Figma | |
定番
【Java】介護経営支援システムの運用・改…
医療や介護業界向けのサービスを展開している企業様にて、介護事業会社向け経営支援システムの運用と、品質…
週5日
500,000〜900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【インフラ】技術QAの問い合わせに対するテ…
◇業務概要: 製品に関する障害調査、技術QAの問い合わせに対するテクニカルサポート業務、および、金…
週5日
370,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【.NET】大手不動産会社での業務システム…
◆ 業務内容: ・大手不動産会社の情報システム部門にて、社内で使うビル管理や、会計システム、Web…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
定番
【AWS】クラウドネィティブシステムの維持…
◇案件詳細: クラウドネィティブシステムの 維持、改善サポート - マルチクラウドから AWSへ…
週5日
570,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・◇対象システム概要 ・-・各ロボットとエ… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
新規事業立ち上げにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきます。 サービスを運用すると同時…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週5日…
スマートフォンのアプリ及び、BtoB 向けの Web アプリケーションの開発を中心に受託開発をされて…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・AndroidStudio… | |
定番
【リモート相談可 / R/Python /…
【案件内容】 自社CtoCサービスにおいて今後サービスをグロースしていく上で、開発全般をお任せでき…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| ₋-・Flutter | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】ス…
自社サービスのUI/UXデザインを担当して頂きます。 ◆業務内容 ・スポーツクラブ、インフル…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python/PHP…
【開発内容】 ①フロントエンド 顧客から受けているシステム(動画配信、求人検索、レッスン管理シ…
週3日
160,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【業務内容】 フロントエンドエンジニアとして、チャットボット自体のUIや、チャットボットを「作る」…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【Python/C++】複合機向け検査機能…
【概要】 -デジタル複合機向けの検査機能開発(GUI、画像処理、マイコン制御)を担当頂きます。 …
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++・・-OS:Windows … | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
◇業務詳細: MaaS実証実験に伴うネイティブ言語による開発業務のご支援をお願いいたします。 …
週5日
740,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】大…
保険契約者が保険事故発生時に事故報告する代理店向けのwebシステムがあり、 バックエンドはIBMホ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・COBOL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
◇案件内容 : 商品管理システムの業務アプリケーションの機能追加、改修を行っていただける方を募集し…
週5日
300,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・任意スキル: Git操作、FuelPHP … | |
定番
【WordPress】新規口コミアプリ開発…
【案件内容】 この度は大手メディアとの協働に向けて、既存メディア事業で使用されている、独自CMSを…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【デザイナー】小売流通系企業の記事LP作成…
この度はLP作成に向けてWEBデザイナーの方を募集いたします。 【業務内容】 現在3名のWE…
週4日・5日
150,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿広島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Laravel / 週5日…
案件内容: ・中古機械ECサイト向けサーバサイド開発支援 (サイトの手数料変更業務) ・開発から…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【HTML/CMS】自社プラットフォームの…
自動車業界に特化した自動車産業ポータルを運営しています。 【業務内容】 今回は自社で運営して…
週4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週5日…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます。 ・請負会社での基幹システム(製造系)のサーバ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Zend・Framework | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】バ…
【業務内容】 有名IPのバーチャルライブのUnityTimeLineでの舞台設定・演出(Liveコ…
週5日
300,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| 【開発環境】 ・基本ツール:Maya・Unity・… | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
現在は、創業当初から提供しているオンライン英会話だけでなく、AI英語スピーキングテスト、グローバルリ…
週4日・5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【業務詳細】 ・マーケティング組織でデザイン、マークアップ業務 ・サービスサイトやLPの作成、改…
週5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ad… | |
定番
【フルリモ / UIUX / 週4日〜】新…
今回は事業急拡大に向けて、新しいメンバーを募集致します。 <業務内容> ・Webページのデザイン…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| CSS3・Illustrator・Photoshop… | |
定番
【Go】自社開発のデジタルマーケティングS…
【作業フローの一例】 ・機能の要件を、タスクフォースチームや部外関係者と一緒になって議論する ・…
週5日
330,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby/React / …
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【Java】大手建設業向け経理システムの開…
業務詳細: 大手建設業向け経理システムに関するプロジェクト業務になります。 既存のシステムの改修…
週5日
440,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・自社FM | |
定番
【C#】社内分析系システム開発開発
【業務概要】 現在構築されている社内分析系システムを外部に提供できるように機能強化をしていきます。…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Azure | |
定番
【PM or EM】自社サービスの査定P…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、 最新の研究動向を取り入れた…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP | |
定番
【PM】上場化粧品会社の公式アプリ開発(i…
【業務内容】 上場化粧品会社の公式アプリ開発(iOS、Android両方) 現在稼働中の案件…
週4日・5日
3.1〜4.5万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】上場化粧品会社の公式アプリ開発(i…
上場化粧品会社の公式アプリ開発となります。(iOS、Android両方) 現在稼働中の案件に入って…
週4日・5日
1,100,000〜1,320,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
Webディレクター
Shopifyを使ったECサイトやWebサイトの制作・構築・運用のディレクション業務がメインとなりま…
週5日
200,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ー | |
定番
【Ruby/Go】自社開発のアフェリエイト…
リードエンジニアとして、自社サービスや新規計測システム等の開発とサービスグロースの両面を見ていただき…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・・Ruby・on・Rails・ ・… | |
定番
[PHPエンジニア]新サービスの開発業務
幼稚園・保育園向け写真販売システムに関連する新サービスの開発業務をお任せいたします。 【やりが…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・jQuery | |
定番
【AWS】クラウドネィティブシステムの維…
◇案件詳細: ■役割:クラウドネィティブシステムの 維持、改善サポート ーマルチクラウドから …
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・■経緯 -アプリケーションは当社の医薬部門… | |
定番
【VB/.NET】販売管理基幹/生鮮システ…
【作業内容】 1.小売店の既存システムに対する保守案件の要件定義~リリース (2種類)画面、バ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【案件内容】 自社サービスのWeb開発チームで React によるフロントエンド作成。 【募…
週5日
390,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【AWS】電力データ活用基盤移行に伴う基盤…
■案件内容■ ・基本設計書、詳細設計書の執筆 ・パラメータシート作成 ・検証環境の構築 ・基…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・ECS・RDS・S3 | |
定番
【Swift/Kotlin】海外旅行のDX…
マーケットのDX化の推進いただける方を募集します。 【業務内容】 ・デジタルを活用し、海外旅…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Typescript | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript/…
◇業務内容: 住宅事業に特化したWEBサイトのシステム構築、アプリ、ソフト開発の仕事。 Word…
週3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【UIプログラマー|フルリモ・週4日~】ハ…
オリジナルのゲームエンジンや最先端のグラフィックス技術を活用したハイエンドマルチプラットフォームゲー…
週4日・5日
520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| UnrealEngine4 | |
定番
【JavaScript/Python/Ru…
▼案件内容 ・小売企業向けサービスの機能開発・改善。 既にローンチ済の小売企業向けサービスの新し…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【PHP/Rubu/Python】VRゲー…
自社コミュニティサイトの立ち上げを行います。 【担当業務】 ・自社開発のクラウドファンディン…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【Webデザイナー】不動産会社向けサービス…
【案件概要】 有名不動産会社の高級マンションPRサイト、イベントホール、商業施設等のWebサイト制…
週3日・4日・5日
230,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【組み込み】WVD用カメラデバイスドライバ…
◇案件詳細: ・ドライバへの署名、Microsoftへの登録手続き(支援)、インストーラの作成方法…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【フルスタックエンジニア|フルリモート】大…
【案件概要】 カスタマー関連サービスのクラウド開発ができるフルスタックエンジニアの方を募集しており…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
B2C Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には以下の開発項目を…
週4日・5日
350,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript・Python・A… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
自社で新規開発しているクリエイターのスキルシェアマーケットにおけるUIデザイナーを募集しております。…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5】…
PHPで開発されているシステムのJavaへの移行に伴う、Java開発をお願いします。 Ph2完了後…
週5日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
▼業務内容 ・キャディのオペレーションチームや、顧客、サプライパートナーの利用するシステムのバック…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Scala・Kotlin・▼開発環境 ・利用言語 … | |
定番
【UI/UXデザイナー|週3日~5日・フル…
iOS向け音声アプリのデザイン、今後の機能アップデートやAndroid版、ブラウザ版LPや広告・販促…
週3日・4日・5日
330,000〜480,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週4~】フ…
今回のポジションでは、メンバーと共鳴しながら、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Next… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
新規スマートフォン向けRPGゲームのクライアントサイドエンジニアとしてゲームアプリ開発を担当していた…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity・Unity | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
当社の研究成果を公開するサービスにおけるWEBフロントエンジニアを募集いたします。 本サービス…
週3日・4日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Java/Azure…
アプリケーションのデータを収集するサーバの開発業務をお任せします。 本案件では開発工程の募集となり…
週5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【インフラエンジニア|リモート相談可】金融…
【案件概要】 金融機関(生命保険会社・損害保険会社)の業務用システム開発を受託しており、金融系イン…
週5日
380,000〜470,000円/月
| 場所 | 埼玉与野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux・WindowsServer | |
定番
【フルリモ / 週5 / React/Gi…
急成長に伴い、フロントエンド・サーバーサイドの設計・開発を担当していただける仲間を募集しています。 …
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【ネットワーク】5Gインフラプロジェクト …
【業務内容】 ・お客様 NW設計部門から工事設計案件受付 ・ビル内設置リソース確保(スペース・ラ…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【事業概要】 戦略立案~制作/広告運用までデジタルマーケティングを一気通貫でサービス提供を行ってお…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
官公庁・自治体等の案件入札・落札情報を探せる自社サービスのバックエンドエンジニアとして、API開発を…
週3日・4日・5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【UI/UXデザイナー|リモート相談可・正…
【案件概要】 弊社で提供しているWEBアプリケーションをはじめとしたデザインのモックアップ制作など…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| illustrator・Photoshop・Adob… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、バナーデザインを中心に担当いただくデザイナーの方を募…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【Ruby】自社基幹システムのサーバーサイ…
【事業紹介】 ・システムインテグレーション └カーパーツ・バイクパーツの買取・販売業務から、店舗…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川青葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・RubyonRails・【会社詳… | |
定番
【Rubyエンジニア|週4日~5日・フルリ…
【案件概要】 弊社では、アクセス認証基盤を構築しマイクロサービス化されたサービス開発を行なっており…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【DTP】ファッション業界自社Web・店頭…
◇業務内容 Web・店頭販促物等のデザイン、制作および発注納品業務 ◇制作実例 ・キャ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|週4日~5日・…
【案件概要】 弊社ではクラウドサービスを提供しており、今回は自社クラウドサービスのフロントエンド開…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Angular | |
定番
【GS2/Unity】新規サンドボックスゲ…
【企業概要】 私たちはアプリケーションサービス事業とシステムソリューション事業を行っております。 …
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原末広町 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【HTML/CSS】某大手求人媒体の社内D…
▼案件内容 社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集とな…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript | |
定番
【SQL】業界内トップシェア店舗予約サイト…
■内 容■ ユーザー数数百万人規模、登録店舗数も数千店の業界内トップシェアサイトの大型リニューア…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【Unity】XRが当たり前の世界をつくる…
【案件内容】 - 開発(主にUnity、C#) - 技術上の意思決定への関与 - プロジェクト…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Unity | |
定番
【Javascript/Python】Wi…
【業務内容】 Robotチームでのフロントエンド開発 工場でのWindowsタブレット上での…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【Go】保険システムバックエンドエンジニア…
【業務内容】 ・保険SaaSサービスの提供を担っていただきます。 他の開発メンバーや業務チー…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【Kotlin/TypeScript】保険…
【業務内容】 保険契約・請求フォームのノーコードツールのチームに所属いただきつつ、認証認可・権限設…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Kotlin・Typescript | |
定番
【インフラエンジニア|週3日~5日・フルリ…
【案件概要】 インフラ領域の運用エンジニアとして開発を推進していただく方を募集しており、バーチャル…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモート】システ…
【案件概要】 発注先選定支援サービスをRubyonRails/AWS(場合によってReact/Ga…
週5日
300,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React | |
定番
【C/C++】スマホアプリエンジニアオープ…
当社ではWEBサービス開発を行っていただける、スマホアプリエンジニアを積極的に募集しております。 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C・C++・C#・案件による | |
定番
【フロントエンドエンジニア|リモート相談可…
弊社ではHRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題をAIで解決ためのプロダクト開発をしており…
週3日・4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア|週3日~4日・…
【案件概要】 社内の簡易ツールシステムの開発を行っていただくサーバーサイドエンジニアの方を募集して…
週3日・4日
260,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【業務内容】 自社のコーポレートサイト並びに、ECサイトのリニューアルを計画しており、専任でデザイ…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・illust… | |
定番
【Typescriptエンジニア|週3日~…
【案件概要】 ・大手総合商社のスタートアップの子会社におけるWebサイト開発でフロントエンド開発に…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Next.js・G… | |
定番
【UI】飲食店に導入する日本酒レコメンドの…
この度は、現在法人登記中の子会社で立ち上げている新規サービスのネイティブアプリデザインを担当いただく…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能・週3…
【案件概要】 自社サービスアプリのサーバーサイド開発または、社内業務支援ツールの設計・開発に携わっ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Larave・AWS(ECS… | |
定番
【Python】不動産情報B2Cサイトの改…
不動産情報B2Cサイトの改修案件になります。 現在サービスインしているB2Cサイトの基盤の改修・保…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿愛宕駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週5日…
幼稚園・保育園向け写真販売システムに関連する新サービスの開発業務をお任せいたします。 プロダクト開…
週5日
4.1〜5.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社サービスのフロントエンドの改善と新規の作成等を行っていただきます。 開発業務をメインにお任…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(vue js) |
| JavaScript・Vue.js・RubyonRa… | |
定番
音楽コラボアプリのバックエンドの設計・開発…
・サーバサイドAPIの要件定義・設計 ・Python + Djangoを用いたサーバサイドAPIの…
週5日
670,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・フレームワーク:・Django デー… | |
定番
【ライティング】自社コンテンツ向けのライテ…
1.骨子作成 ・SEOの調査を元に骨子作成 →ターゲットキーワード →H2に入れる要素 ・競…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター(SEO) |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
■業務システム開発運用 弊社受託既存システムの追加機能開発の設計~リリースまでご担当いただきます。…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Python /週3…
【企業概要】 弊社は世界最大級の高級陶磁器・砥石メーカーです。 洋食器の製造を目的として創業、輸…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿亀島駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【上流SE / 週5】飲食系SaaSの導入…
顧客への導入の際の計画やハンドリング、利用の定着を支援していただくとともに、導入後もさらなるメリット…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週4~】社内…
複数の受託案件について、顧客折衝、要件整理、要件定義、設計概要整理等を 適宜対応していただく案件と…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Swift / 週5】ネイ…
マネー管理の取引システム開発になり、要件定義~運用保守まで工程、ネイティブアプリのフロントエンド開発…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Swift・Alamofire・RedHat・Cen… | |
定番
【Unity】xRサービス開発支援業務
▼案件内容 某キャリアが展開するxR系の新サービスにおける企画から、要件検討、実現性の調査、機能…
週5日
720,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【システムエンジニア|リモート相談可能】経…
要件定義・開発メンバーの募集をしており、本件ではPMの指示の下、作業を行って頂く形となります。 …
週5日
570,000〜8,030,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【Azure】Oktaを介したインフラエン…
【作業内容】 ※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 弊社のクライアント企業である某鉄鋼メーカー…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川鶴見駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【Java】決済システムの要件定義、設計、…
【業務概要】 決済システムに関する要件への落とし込み、定義した要件に対しての設計及び製造、試験、リ…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【C/C++エンジニア|リモート相談可能】…
【案件概要】 医療システムの開発。設計~実装~テストまで一貫して担当頂きます。 【業務内容】…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【PHPエンジニア|フルリモ】FXの顧客向…
【業務内容】 プロジェクトにおけるシンプル且つ効率的なモジュールの開発及び、初期的な動作テストを行…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
定番
【システムエンジニア|リモート一部可能】不…
【案件概要】 既存のシステムをほぼ新規のシステムとして作り替えるプロジェクトで、入金・支払い・請求…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Java・JQuery・Spr… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ・週3…
弊社ではオンラインイベント・プラットフォームサービスを運用しており、今回は以下の業務をお願いする予定…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【デザイナー】自社サービスにおけるデザイナ…
■案件内容 真似されたくないネーミングを思いついたときに、すぐにオンラインで商標登録が依頼できるプ…
週3日・4日・5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Unity】MicrosoftAzure…
【業務詳細】 3D空間上でバーチャルイベントを開催するプラットフォームの開発およびプラットフォーム…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【TypeScriptエンジニア|フルリモ…
社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・サービス開発、運用をご担当頂きます。 【業務詳…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【AWSエンジニア|リモート相談可能】Ci…
【案件内容】 現在の環境からBCP環境として同様の環境を構築してSQLサーバーを同期させる方法で構…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・AWS | |
定番
【PHP】社内CM枠管理システム再構築に向…
社内システムの再構築に向けエンジニア様を募集致します。 下記プロジェクトにてご希望・適性でお任せす…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Javascriptエンジニア|フルリモ…
【案件内容】 主に、大手士業向け業務システム内の報酬を決定するための機能に関する改修案件にメインで…
週4日・5日
410,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ】通信会社向…
弊社では、東海地区のクライアントを中心にWebサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・データ放…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・MongoDB | |
定番
【コーダー|フルリモ・~週2日】リード獲得…
【案件概要】 弊社内で発生するHTML/CSSでのコーディング業務をご担当いただきます。 【…
週1日・2日
200,000〜260,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【案件概要】 融資の申し込みを管理したり、社内稟議を回すなど金融機関や銀行で使用する 社内向けパ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【JavaScriptエンジニア|リモート…
【概要】 顧客の社内向けWebアプリケーションであるメトリクス可視化システム開発を担当頂きます。 …
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ】Webアプ…
【案件概要】 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経過し、…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven・HTML・… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ・週3…
◇仕事概要 弊社は医療データ解析プラットフォームの開発を行なっており、ローンチに向けてフロントエン…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【PHP】EC事業者向けプロダクト改修案件
クライアント(EC系)の改修案件にて開発業務(設計、実装、テスト・デバッグ、ソースコードレビュー)を…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony | |
定番
【QAエンジニア|リモート相談可能】自社運…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しており、自社が携わるサービスのQA業務を担当いただける方を探…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【Javaエンジニア|リモート相談可能】決…
【案件概要】 1、ID決済を提供するサービスに対する店舗・エンド・社内向けToolの開発業務 2…
週5日
350,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringFramework | |
定番
【C#エンジニア|フルリモ・週3日~】自社…
【案件詳細】 弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 【業務内容】 ・自社アプリケ…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C#・.NETFramewor… | |
定番
【フルスタック】Webエンジニアの採用にお…
■具体的な業務内容 ・Webエンジニアの採用に携わっていただきます。 ・転職ドラフト等を使用した…
週3日・4日・5日
1,690,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【Pythonエンジニア|フルリモ】自社運…
【案件概要】 弊社リーダーのチームメンバーの増員を目的としており、メンバーには運用中の不動産系サー…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Python・-・Django | |
定番
【サーバーサイドエンジニア|リモート相談可…
【案件概要】 本件は、既存統計システムの追加開発・運用プロジェクトで、現状サービス稼働中の統計シス…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala・SQL・BashShellScript・… | |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能】小売…
【案件概要】 小売業のECモールへの新規出店、出品、受注管理を行う業務システムの機能追加・改修・ユ…
週5日
440,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Goエンジニア|フルリモ・週2日~】教育…
●業務内容 弊社では世の中にない新しい価値を生み出すべく、ビジネスチームとすり合わせを行いながらス…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Golang・PHP(Laravel・Code… | |
定番
【PHPエンジニア|フルリモ・週4日~】人…
弊社はITを活用して、スマホアプリゲームの企画・開発・運営及び、人材事業のを運営しています。 …
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【インフラ】AWS環境の要件定義/設計 /…
◇案件詳細 AWS環境の要件定義/設計/テスト/構築 具体的には以下。 ・要件定義の実施 ・イ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【スマホアプリエンジニア|リモート相談可能…
【案件概要】 KPIコミュニケーションアプリの開発支援で、主に以下の業務に携わっていただきます。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・AWS | |
定番
【JavaScriptエンジニア|リモート…
【案件概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービ…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【Javaエンジニア|リモート相談可能】某…
▼作業内容 個人プラットフォームのリニューアル開発を行うためのエンジニア様を募集します。 …
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【システムエンジニア|週4日~】国内初プラ…
▼案件内容 セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務をお任せします。 …
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js・Lara… | |
定番
【上流SE|週4日~】顧客向けシステムの既…
▼案件内容 既存稼働しているシステムの本番・開発環境のシステム更改をお願いします。 上流工程(…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿府中 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【デザイナー】外資系コスメブランドのクリエ…
外資系コスメブランドのクリエイティブ関連の業務を下記を中心にお任せいたします。 ディレクションは米…
週3日・4日・5日
330,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Goエンジニア|フルリモ】データ分析サー…
【案件概要】 ソフトウェア開発及び導入支援の双方をお任せできるを募集しており、基幹システム開発・デ…
週5日
480,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GCP・AWS・Linux・Clickup・N… | |
定番
【.NETエンジニア|リモート相談可能】情…
【案件詳細】 主に先方の営業担当者が利用する販売見積受注システムや、MDMの再構築に際し、AsIs…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・VB.NET… | |
定番
【フルスタックエンジニア|リモート相談可能…
【案件概要】 銀行オンラインサービスのOEM提供対応及び、インフラ見直し、アプリの乗せ換え、機能追…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【Typescriptエンジニア|フルリモ…
■具体的な業務 ・テスト環境整備 ・機能追加作業 ・既存システムへの意見だし ■チームメ…
週1日・2日・3日・4日・5日
1,010,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Vue.js・Nu… | |
定番
【SQLエンジニア|フルリモ・週4日~】品…
お客様の品質管理担当が利用している帳票レポートが、DB基盤のサービス終了に伴い、データ、帳票の移行開…
週4日・5日
410,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | SQLエンジニア |
| SQL | |
定番
【ネットワークエンジニア|フルリモ・週4日…
【業務内容】 大手小売企業のネットワーク設計・構築・運用をはじめとして、その他付随業務をお願いいた…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Cisco・Nexus・Aironet・PaloAl… | |
定番
【データエンジニア|フルリモ】各事業部署に…
【案件概要】 データを分析していただき結果から考えられる提案までを対応いただきます。 ※詳細…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【C/C++エンジニア|フルリモ・週4日~…
建設業界の大手企業が使用する次世代CADソフトの設計・開発で、今回は総勢10名以上のプロジェクトチー…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batchf… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
◇業務概要 クライアントであるリフォーム業者のWebサイト・LPのデザインおよび改修。 アクセス…
週1日・2日・3日・4日・5日
150,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルスタックエンジニア|リモート相談可能…
【案件概要】 自社の経営チームに置ける技術サイドの責任を担い、開発組織の立ち上げをリードするCTO…
週5日
610,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【Rubyエンジニア|リモート相談可能】次…
【業務詳細】 ①エンジニア部門の立ち上げ ②新規ASP制作時のフロントサイド設計・開発業務 ③…
週5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【AWS】自社インフラチームでのインフラエ…
■具体的な職務内容 ・新規、既存サービスのインフラ構築、保守業務 ・開発チームへインフラ構成の共…
週1日・2日
130,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【C#エンジニア|週3日~】スマートフォン…
【業務内容】 主な業務として「要件定義」「基本設計」「詳細設計」「製造・テスト」「運用」をお任せし…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【漫画編集者|リモート相談可能】コミック配…
【仕事内容】 コミック配信サービスで連載するオリジナルレーベル作品及び漫画の企画・編集を担当して頂…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | マンガ編集者 |
定番
【Python】運用中のデータ分析基盤のG…
▼作業内容 某ゲーム会社様向け、運用中のデータ分析基盤のGoogle Cloud環境への移行を行う…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【Webデザイナー|週4日~】顧客のブラン…
【案件概要】 クライアントのコーポレートサイト、ブランディングサイトのWebデザイン業務を行ってい…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| illustrator・Photoshop・Adob… | |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能】顧客…
【案件概要】 顧客が提供しているWebサービスのシステムにおいて開発および運用保守を行っていただき…
週5日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP3 | |
定番
【SQL】小売店向けの業務システムの開発・…
【案件概要】 売店向けの業務システムの保守案件です。 要件定義~リリース、保守まで、開発工程全般…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【Linux】システム開発関連作業
【業務内容】 監視システムの開発・保守 業務に係わる各種システム・ツールの開発、保守作業 ・情…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Linux | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ】法人向けS…
この度はWeb開発をご担当いただき、新機能開発・改修に取り組んでいただける方を募集いたします。 …
週5日
570,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ・週3日~】…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
[インフラエンジニア]クラウドインフラ最適…
【業務内容】 損害保険会社、生命保険会社その他の保険業法の規定により子会社等とした会社で、クラウド…
週1日・2日・3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
[セキュリティエンジニア]アプリのセキュリ…
【業務内容】 損害保険会社、生命保険会社その他の保険業法の規定により子会社等とした会社のアジャイル…
週1日・2日・3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【ITアーキテクト】美容医療の口コミ・予約…
美容医療自体の体験向上のために、ユーザーが利用するクリニック・口コミ検索のアプリやクリニックが利用す…
週5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ITアーキテクト |
| アプリ: ・開発言語:Kotlin・・Swift … | |
定番
[サーバーサイドエンジニア]新機能の開発や…
【業務内容】 新機能の開発や安定運用のための開発 ・顔認証やFIDO認証を実現するバックエン…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
[サーバーサイドエンジニア]某大手旅行会社…
【業務内容】 某大手旅行会社のインターネット通販システムにおいて、Windowsサーバ上で業務負荷…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【Go|リモート可】日本最大級の料理動画メ…
■主な業務内容 ・GoでのAPI設計・開発 ・サービス提供に必要な管理ツールのAPI設計・開…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS・GCP・ | |
定番
【C/C++】ロボティクス関連サーボマイコ…
次世代ドローン向けの、サーボマイコン向けの組込みSW設計、開発を行って頂きます。 -新規デバイ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【VBA】COMPANY導入支援作業
【業務内容】 ・ COMPANY導入支援作業 【作業範囲】 人事給与パッケージCOMPAN…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VBA | |
定番
【C/C++】車載デバイスドライバの開発業…
【案件概要】 車載SoC上で動作するデバイスドライバの開発。 -並行開発中のデバイスドライバ…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【Java】大手中古品小売業社のECサイト…
【案件内容】 ・既存のECサイト全面刷新におけるWeb管理ツールの設計および開発。 ・自社ECサ…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Micronaut・Junit5・Git・… | |
定番
【インフラ】医療系システム更改案件
◇案件概要 医療系システムのハードウェア/ミドルウェア老朽化対応として、システムのリプレースを行…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能】国内…
【案件概要】 弊社で開発・運営している国内最大級のショッピングカートサービスのECカートシステムの…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・GMOクラウド・AWS・Linux(Cent… | |
定番
【HTML/CSS/LP制作】グループ内ク…
【案件概要】 ①弊社作成のライティング原稿に沿ったLPのデザイン・コーディング※ (弊社作成のラ…
週3日・4日
190,000〜260,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【HTML5/Javascript】大手医…
【業務内容】 大手医療系メーカー様からプライムで依頼を受けている顧客管理システムの開発・テスト業務…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上前津駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・VB.NE… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ】AI解析基…
【案件概要】 AI解析基盤構築の新規開発を行うサーバーサイドエンジニアを募集しております。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| JavaScript・Java・Spring・Jav… | |
定番
【グラフィックデザイナー|リモート相談可能…
弊社ではシステム事業、海外事業、コンテンツ事業、コンサルティング事業、スポーツ事業など多彩な事業を展…
週5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿綾瀬駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ】ECサイト…
【案件内容】 RubyonRails製のオープンソースECパッケージをベースに、ECサイトや受発注…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【SQL】アプリケーション・業務運用
【業務内容】 ・サーバ上でのSQL実行や手動シェル実行、ファイル操作、データ調査・抽出等 ・問合…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・AWS・CentOS・PostgreSQL … | |
定番
【システムエンジニア】Microsoft3…
【PJT概要】 Salesforce(Classic)のカレンダーをOffice365(Excha…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| ‐ | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ・週3日~】…
自社で提供している人材系サービスのプロダクトにおけるサーバーサイド開発業務を担当してくれる方を募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【インフラ】不動産情報B2B基幹システムリ…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルをご担当いただきます。 担当業務は主にク…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ECS・Fargate | |
定番
【Typescriptエンジニア|Angu…
弊社サービスは顧客満足を計測・分析しロイヤルカスタマーを生み出すクラウドサービスでCX(顧客体験)調…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Python・Ruby・Typescript・R・A… | |
定番
【Vue】LegalTech業界におけるS…
AI技術を用いて法律業務の効率化や法務経営の実現を目的とするリーガルテックサービスを開発しています。…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Angular.… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ】既存自社P…
自社で開発した既存のPHPシステムを新たにJavaで構成するプロジェクトを進めており、新規メンバー…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・AWS・Linux・… | |
定番
【システム】ADSLマイグレレーション
【業務内容】 1,マイグレに伴う現地調査の実施 2,現地調査結果の作成(移行前、移行後構成図、N…
週4日・5日
70,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ・週4日~】…
弊社ではスポーツビジネスの活性化のために以下の事業に取り組んでおります。 1.スポーツチーム支…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西国分寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【HTML/CSS】モビリティーサービス開…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
460,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【システム】某大学様向け無線LAN環境の詳…
某大学様向けに、無線LAN環境のNW機器リプレイスを行います。 設計、構築、試験実施、現地導入の対…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【Python】業務システムの開発DX推進…
東証一部のガス会社から直請けの案件(業務システムの開発DX推進)に携わっていただきます。 ■業…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・Gut・Docker | |
定番
【Go】教育系Webサービスの自社開発
●仕事内容 新規事業である高等教育機関向けDXのサービス開発をご担当いただきます。 新規事業なの…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・‐ | |
定番
【SREエンジニア|リモート相談可能】自社…
【案件概要】 SERエンジニアとしてAWS上で運用されているシステムに関する業務を行っていただきま…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| AWS(ECS・EC2・Lambda・Aurora・… | |
定番
【フロントエンド】ブロックチェーンに関わる…
■案件概要 日本で初のIEOを行ったPLTによって動作する、ブロックチェーンに関わる開発業務を行っ…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ・週4…
クライアントの社内商品企画や開発で利用するプラットフォーム構築プロジェクトで、マーケティングデータを…
週4日・5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【インフラ】notesデータ移行処理業務
【案件概要】 主にデータ移行処理をご担当いただきます。 ①Sharepointの移行 not…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【データエンジニア】受託データ分析から提案…
大手通信会社の共通ポイント事業部署におけるデータ分析、ご提案 Excelデータを分析していただ…
週5日
2〜2.2万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【HTML/CSS/Javascript】…
【案件概要】 既存のコーポレートサイトのリニューアルや新規事業部でのキャンペーンサイトやLP制作の…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Webデザイナー】自社用のLP作成&バナ…
【案件内容】 ※下記は例になりますので、詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 ・自社用のLPデザ…
週3日・4日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【AWS】証券系基盤更改業務(基本設計)
【業務内容】 当社が保守担当している証券系システムについて、現⾏基盤のハードウェア保守期限に伴い、…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京王府中駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・SQL | |
定番
【TypeScriptエンジニア|リモート…
【事業内容】 ・ゲームの企画・開発・運営 ・スマートフォンアプリの企画・開発・運営 ・業務系シ…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・・JavaScr… | |
定番
【Typescriptエンジニア|Node…
【プロジェクト概要】 法人向けネットワークサービスのWebアプリ開発 アジャイアル開発プロセ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・Node.js・AWS・Pos… | |
定番
【Java/PHP】メディアサイトの会員管…
【案件概要】 メディアサイトの会員管理システムの要件定義、設計、実装、テスト、運用 ・会員管理機…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Seasar… | |
定番
【インフラ】インフラ基盤関連タスクの保守・…
■想定業務内容 アーキテクチャ・新基盤における運用管理関連タスクと インフラ基盤関連タスクの保守…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ■業務環境(一例) ArielAirOne・v8 … | |
定番
【C#エンジニア|リモート相談可能】大手会…
【業務内容】 既存システムはDynamics CRMで構築されているシステムをクラウド(Azure…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿門前仲町 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C#・.NET・React.js・Azure | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ/Re…
【案件内容】 新規開発と機能改善に伴う改修の双方の業務を担当していただけるエンジニアを募集していま…
週5日
300,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Typescript… | |
定番
【UIUX】ゲーム開発におけるUIUX設計…
新規プロジェクトの立ち上げから開発に携わっていただき、チームの中心としてご活躍いただける方を求めてお…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| ₋-・₋- | |
定番
【Python】カメラ系クラウドサービス開…
【案件概要】 -クラウドサービス(マルチカメラライブ)向けの設計・実装・評価を行っていただきます。…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 神奈川新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | 制御系エンジニア |
| Python | |
定番
【C#】生産管理共通サブシステム製造ポータ…
【業務内容】 製造業向けERPの生産管理モジュールと連携するフロント機能の開発プロジェクトになりま…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C#・Azure | |
定番
【Unity/C#】自社ゲームの開発案件
【業務内容】 自社2Dゲームの開発案件です。 仕様書が既に固まっている案件のため、開発に集中でき…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C#・‐ | |
定番
【コーダー/テスター|フルリモ】自社サービ…
弊社では金融商品を提供しているテールブローカーへ様々な商品を提供しており、今回は以下のような業務をお…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
定番
【Swift】来客者受付iOSアプリのエン…
【業務内容】 来客者受付アプリ(iOS/iPad)の調査・改修 アプリ改善点の調査、作業設計を行…
週1日
90,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・CocoaPod・Cartha… | |
定番
【リードエンジニア|フルリモ・Java・C…
【業務内容】 下記2つのいずれかの業務に携わっていただけるリードエンジニアの方を募集いたします。 …
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【Rubyエンジニア|リモート相談可能・週…
【案件概要】 今回はサービス開始後に多くの申し込みをいただいている中で、開発のスピードを上げ、問い…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【UIデザイナー|フルリモ・週3日~】画像…
弊社では、画像/動画/音楽のクリエイティブプラットフォームを運営しており、今回はプラットフォーム上の…
週3日・4日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・figma・Photoshop・I… | |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能】自社…
【案件概要】 弊社ではゴルフ場予約サイトのプレープランや価格等の比較情報、ゴルフ場の予約に対応した…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【PHP】不動産上場企業でのコーポレートエ…
不動産会社の情報システム部門にて、 ①不動産仕入部門の業務システムの設計・開発 ②ダッシュボード…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【PHP】福祉事業会社向け 新規業務システ…
お客様が運営する就労支援事業所で、福祉支援に従事する社員が使うシステムのバックエンドの開発を担当して…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・Laravel・AWS・Vue.js・Nux… | |
定番
【Webデザイナー|フルリモ・週3日~】販…
弊社は印刷ECサイトを運営を行う会社のグループ会社としてデザイン、企画・プレゼンテーション・開発まで…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【Swift】オンラインマッチングサービス…
既にWEBアプリで公開しているオンラインマッチングサービスのiOSアプリ立ち上げに伴い、iOSエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【Webデザイナー|フルリモ・週3日~】物…
【案件概要】 採用・就業支援を通じて培った人事業務のナレッジ先端テクノロジーを融合して、クライアン…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【UI/UXデザイナー|リモート相談可能・…
【案件概要】 弊社では自社運営サービスの経験及び請負開発の経験を活かして企画提案型の開発/制作を行…
週3日・4日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・ | |
定番
【iOS】クイックコマースiOSアプリ開発
案件内容 :クイックコマースサービスアプリの保守開発、 不具合改修、機能改善開発 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【React】Webサイト開発、改修のフロ…
【業務内容】 ・実装、レビュー、検証、リリースなどのWebサイトの開発と開発に必要なことの調整や、…
週5日
350,000円以上/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【Pythonエンジニア|リモート相談可能…
【企業紹介】 単なるテクノロジーの提供ではなく、それぞれの事業で得た各業界の慣習や生活者の実態への…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・TypeScript・React… | |
定番
【Javaエンジニア|一部相談可能】新規生…
【案件概要】 生損保Webシステムの新規開発に携わるサーバーサイドエンジニアの募集になります。 …
週5日
640,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門ヒルズ駅 or 神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【Python】クラウドエンジニア(自社S…
■業務例 サービス提供している企業様によって異なります。 ・コンテナ基盤構築 ・ビックデータ分…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Go・GCP・AWS・Azure・Do… | |
定番
【PHPエンジニア|フルリモ】小売流通業向…
■業務内容:小売企業向けサービスの機能開発・改善 既にローンチ済の小売企業向けサービスの新しい…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【Azure】外資系金融会社向けクラウド基…
【業務内容】 ・大手物流グループ企業の国内、海外NWの設計、構築、保守、運用 ・技術調査 ・シ…
週5日
410,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【Goエンジニア|フルリモ・週4日~】オン…
【案件概要】 弊社が展開している日本最大級オンラインギフトプラットフォームにおいて、メディアやEC…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・PHP・TypeScript・Git・Flue… | |
定番
【Javascriptエンジニア|フルリモ…
弊社ではコンピュータソフトウェアの受託開発やパッケージソフトの開発及び販売等を行っている会社になりま…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿和田塚駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js・Vue.js… | |
定番
【Go】新規スマートフォン向けゲームのサー…
・ゲームのサーバ側APIの設計と実装 ・基盤ライブラリ、フレームワークの調査、利用、拡張 ・開発…
週5日
500,000〜10,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【AWS】QAエンジニア保険DXのSaaS…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのQAメンバーの募集になります。 ・保険事業会社向けの保…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Typescript・… | |
定番
【Typescript】法人向けネットワー…
<プロジェクト概要> 法人向けネットワークサービスの商用リリース前のPoC環境にて動作するWebア…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【Webデザイナー】アートディレクター・グ…
◇業務内容:AF・GDの指示のもと以下の業務を実施 1.取り扱うグラフィックデザインの軽微な対応…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【Pythonエンジニア|リモート相談可能…
【案件概要】 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・AWS・Git・・MyS… | |
定番
【HTML/CSS】新卒向け就業支援サービ…
【業務内容】 新卒向け就業支援サービスを展開している企業内でのデザイン業務。 Wordpress…
週3日・4日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Webデザイナー|フルリモ・週2日~】】…
当社は、医師が創業した医療・ヘルスケア領域のベンチャーで、国内医師が参加する医師限定プラットフォーム…
週2日・3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・AdobeCC・Slack・Mac | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ・週5日】自…
【業務内容】 ・自社CX/EXサービスの管理画面などの新規開発 / 改修 / 運用・保守 ・E2…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Java】FXスマホアプリの開発業務
▼ 業務内容 1からアプリを作成するのではなく、既にあるFXアプリを改修・機能追加して、 他社向…
週5日
720,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | AndroidJavaエンジニア |
| Java・AndroidJava・Android | |
定番
【Ruby】ゲームメディアサービスの新規開…
当社は、日本最大級のゲーム総合情報メディアを運営しています。 ゲームメディアの新規開発領域において…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【Java】大手流通決済後方システムの設計…
大手流通エンドユーザーの決済データ管理システムの改修。 対応工程:基本設計~詳細設計、製造、テスト…
週5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・WebAPI・・tomcat・・Apach… | |
定番
【Java】量販店向けパッケージカスタマイ…
量販店パッケージのカスタマイズで詳細設計から総合テストを対応頂きます ※開発PC持込でお願いし…
週3日・4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川蒲田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【TypeScript】某大手求人媒体の社…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【Swift/Kotlin】国内製ウェアラ…
【案件概要】 ■プロジェクトについて ・国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 …
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可能/週5…
【案件概要】 弊社WEBシステムの速度問題を解決したく、負荷分析ツールの解析ややスロークエリなどを…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・CodeIgniter・CentOS… | |
定番
【Node.js】ムービーサービスにおける…
▼案件概要 ムービーサービスにおけるフロント・バッグエンド開発 ▼案件内容 ムービーサ…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js・React | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
この度は事業の拡大に伴い、SEを募集いたします。 【業務詳細】 ・クラウドサービスを利用した開発…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【Java】アーキテクチャ(人材サービス業…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 【募集ポジシ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【Azure/C#】生産管理共通サブシステ…
【業務内容】 製造業向けERPの生産管理モジュールと連携するフロント機能の開発プロジェクトです。 …
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Oracle・Azure | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
▼背景 現在既存社員でベトナム人WEBデザイナーがおり、ベトナムチームと日本チームのブリッジ業務を…
週4日・5日
280,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【C#】決裁システムサーバー構築等の業務
◇業務内容 ・決済(クレカ等)システムサーバー構築 ・決済画面フロントエンド制作 ・ライセンス…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Typescript】法人向けネットワー…
◇プロジェクト概要 法人向けネットワークサービスのWebアプリ開発 アジャイアル開発プロセス…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js | |
定番
【Ruby】自社開発SaaSプロダクト開発
▼ 案件概要 自社開発している社内コミュニケーション活性化SaaSへのSSO実装にあたり、設計~実…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【TypeScript/React】ウェビ…
【業務詳細】 ・Reactを使用したフロントエンド開発 ・アプリケーションの設計 ・開発に関…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React | |
定番
【PHPエンジニア|フルリモ/週3日~】ホ…
【案件概要】 Tabiqチームの中で話し合って決めた、プロダクトの方向性に沿って開発をしていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿博多駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・AWS・Swift・AWS・Github・S… | |
定番
【RubyonRails】自社開発!AIチ…
【案件概要】 バックエンドエンジニアとして、チャットボットを構築・運用するWebアプリケーションを…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【AdobeIllustrator/Pho…
【業務内容】 マーケティング組織でのデザイン業務を行っていただきます。 主に、web広告に関…
週4日・5日
250,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【PHP/フルリモート】仮想通貨会計ソフト…
仮想通貨の個人向け会計ソフトについて、プロダクトを安定的に稼働、成長させるために必要な要件を中心に開…
週5日
2万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel Vue.js Nuxt.… | |
定番
【Python】バックエンド/携帯電話基地…
◇案件概要 携帯電話基地局の監視業務効率化。 AWS ECS上にDjangoRestFramew…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【Javascript】自動運転関連プロジ…
【案件内容】 自動運転関連プロジェクトのWebアプリケーション部分のフロント開発 【業務内容…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿和田塚駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【C/C++】ファイルシステム製品の機能拡…
【概要】 -弊社製 FAT/exFAT ファイルシステム製品の機能拡張/改修。 -他社製Linu…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・言語:C言語 | |
定番
【JavaScript】クライアントに向け…
【案件概要】 ・某企業様のアプリケーションをクライアントの要望に合させてカスタマイズ開発をお願いい…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外立川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【C#エンジニア|フルリモ・週5日】 大手…
【案件概要】 自動車大手のお客様にて、現在Azure上(AKS利用)に構築されたSitecore…
週5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・AWSPaaS・AzureAKS・Lambda… | |
定番
【Webデザイナー】インハウスのWebデザ…
▼業務内容 ・WEBページのデザイン制作 ・ワードプレス更新 ・バナー広告のデザイン制作 ・…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【SQL】金融系運用保守
【案件概要】 流通系カード会社様の構築済みDWHシステムの運用保守業務(ルーティンワーク多め)をご…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・ | |
定番
【Kotlin】物流大手配送ドライバー向け…
▼案件内容 配送ドライバーの業務全般を支援するアプリの開発業務です。 …
週5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【案件概要】 ネット金融サービスの中核会社として、グループ各社との連携により、さまざまなサービス展…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フロントエンドエンジニア|WebGL/T…
【案件概要】 5Gを活用したフラッグシップサービスの開発になります。 現在、画像から位置を測…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Three.js | |
定番
【Java】ファンクラブの会員管理APIの…
▼案件概要 スポーツ系ファンクラブサービスの下記内容をPLの指示のもと業務を実行していただきます。…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java | |
定番
【Unreal Engine】急成長スター…
【案件概要】 AI・3次元点群処理・自走ロボット急成長スタートアップでのアプリケーション開発をお願…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【HTML/CSS】新卒向け就業支援サービ…
【業務内容】 新卒向け就業支援サービスを展開している企業内でのデザイン業務。 Wordpress…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【テスター】自社SaaSシステム刷新PJに…
SaaS型WebサービスおよびAndriodプラットフォームを使用する組込み機器のテスト担当として、…
週5日
460,000円以上/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【VB.NET/C#】経営改善クラウドサー…
【業務内容】 在宅医療の訪問スケジュール最適化による経営改善クラウドサービスの開発業務です。 高…
週3日・4日・5日
260,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C#・VB.NET・ASP.net | |
定番
【Typescript】新規メディア立ち上…
【案件概要】 当社はWebメディアを運営しています。 読者の生活の質を向上させる記事を発信してい…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Java/PHP】医療系システムの刷新の…
【案件概要】 ・Javaソースを元に、PHPの業務ロジック部分の開発を行います。 下記の業務…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿春日駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・SQL・‐ | |
定番
【Unity】クライアントサイドエンジニア…
▼案件概要 ゲームの企画段階から設計、開発まで幅広い工程に関わっていただきます。 状況・ご経験に…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【インフラ】外資系企業内のシステム基盤運用…
◇案件概要 外資系企業内のシステム基盤運用・構築 様々な分野・産業に対し戦略、業務、ITなどのあ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Python】AWSを活用した新規システ…
【案件概要】 AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
【Nuxt.js/Vue.js】自社基幹シ…
【業務内容】 Webアプリケーション・システム等の自社サービスの開発・運用を手掛けています。 今…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川青葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Nuxt.js・Vue.js | |
定番
【SQL】自社健康保険組合向け製品の運用業…
健康保険組合向け製品の開発・運用、健康保険組合の加入者向け通知物の開発・運用業務に携わっていただける…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【Salseforce】自社業務支援システ…
▼業務内容 不動産仲介業務で使用する業務システムの開発をお願いします。 ▼主な業務 1.エ…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| JavaScript・Apex・VSCode・・Gi… | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモ/週3日~】…
【業務内容】 システム開発の事業として、顧客の要望に合わせてオーダーメイドのシステムを作成する受託…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・PostgreSQ… | |
定番
【GCP】自社新サービスにおけるインフラ…
【サービス概要】 当サイトは豊富なテンプレートや、各ブラウザで見たまま編集できる手軽さが好評で、日…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【SQL】新MDシステムのIF開発対応
◇案件概要 小売系システム(新MDシステムのIF開発対応) ◇業務詳細 T-SQL(Tra…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【システムエンジニア|リモート相談可能/週…
【案件概要】 デジタルカメラ・カムコーダの評価・リリース作業をお願いします。 具体的には、各…
週5日
220,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【PHP/Vue】オンライン学習サービス開…
この度は、オンライン学習サービスの追加機能開発をお任せするエンジニアを募集いたします。 ▼業務…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【Salesforce】アプリケーショ ン…
【業務詳細】 Salesforce上での設計・開発、テスト業務を行っていただきます。 アジャイル…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce | |
定番
【Rust】クラウドサービスのサーバーサイ…
◆主な業務内容 ・EmotionTech CX / EX のマイクロサービス化、既存システムの改良…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Go | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【業務内容】 弊社のトレーディングデスク事業部にてクライアントワークにおけるバナー、動画、ランディ…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【デザイナー】自社法人向けアセスメントサー…
【業務内容】 以下のポジションで募集しています。 1.クリエイター -プロダクトグロースを…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Java/SQL】自動車会社向け基幹シス…
【案件概要】 ・パッケージソフトのインターフェース連携部分の開発 ・NativeのJavaでの開…
週5日
410,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【デザイン】大手企業のグラフィックデザイナ…
◇案件概要 某会社様がビジュアルコミュニケーションをアップデートする、インハウスのブランドクリエテ…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【業務内容】 ・ウェブベースのSaaSシステムの開発 ・Webフロントエンドの設計/開発 ・U…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【AWS】クラウド共通基盤グループ支援(運…
【案件概要】 ・CACと別ベンダーにてAWS基盤の保守/運用を実施 ・関連メンバーは、お客さんプ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VPC・EC2・RDS・S3・Lambda | |
定番
【Java】無人コンビニシステムの開発支援
▼案件概要 稼働中の無人コンビニシステムの開発・運用業務 …
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・AWS・MySQL | |
定番
【Java】決済代行システム開発 消費税…
業務詳細: 今回は、消費税改正のため、既存の決済代行システムの改修作業をお願いいたします。 稼働…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留(新橋) |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seaser2・Oracle | |
定番
【プログラミング研修講師|フルリモ/週5日…
【案件概要】 「Python及びフレームワークDjangoの習得」を目指したIT研修講師業務 今…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【JavaScript】コロナ渦で注目のH…
▼募集概要 - 現在 3つのサービスをエンジニア2名で開発・運営しております。新シリーズの調達を予…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【インフラ】ファイルサーバー/仮想基盤更改…
主に仮想基盤環境の要件確認、移行設計、構築、テスト、移行 ■業務詳細 大手生命保険会社のファ…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【PHP】某交通系企業向け保守PJ
▼業務内容 該当システムに関する下記の業務をお任せします。 ・連絡窓口の設置、保守対応性の維持 …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【セキュリティエンジニア|週4日~】某協会…
【業務内容】 ・サーバー管理、運用監視 ・問い合わせ対応 ・障害対応 ・ウィルス監視 ・S…
週4日・5日
250,000〜280,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【Swift/Kotlin】金融アプリケー…
【案件概要】 AndroidやiOS環境における金融アプリケーションの開発業務を担っていただける方…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Ob-C・AndroidJava・Kotlin・Sw… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【業務内容】 ・主にクライアントか自社のWebサイトの作成 ・WEBシステムの開発、検証、運用、…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・CakePH… | |
定番
【サーバーサイド】損保・Webネット保険シ…
【業務内容】 損保会社様向けネット保険システムの企画・提案業務になります。 企画~開発までご対応…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【Vue.js,/Angular】アプリケ…
【業務内容】 大手SIerのアーキテクチャデザイン支援部隊にて、エンドユーザや社内他事業部に対して…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【Kotolin】スマホアプリにおける開発…
【案件概要】 主に下記の業務を行っていただきます。 ・スマホからの位置情報を取得してkafkaな…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【Java】物販管理の再構築に伴う開発業務
◇事業紹介 企業のニーズに合わせたシステム開発及び、システム導入の企画・分析から設計・開発・運用支…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・Sprin… | |
定番
【Ruby/JavaScript】自社アプ…
▼業務内容 ・自社アプリの開発・運用 ・その他弊社サービス開発に関わる業務全般 ・必要に応じて…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿南新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【インフラ】DX推進支援プロジェクトの開発…
◇案件概要: 弊社は、テレワーク導入企業に向けたDX推進支援プロジェクトを進めています。 具体的…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Kotlin,Swift】Android…
弊社では、複数の事業でモバイルアプリを展開しております。 新バージョンOSのリリース時に、OSネイ…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【Java/Kotlin】C to C向け…
▼案件内容 C to C向けスマホアプリの機能追加、機能改修。 C to C向けアプリの機能開…
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【Go】新規事業におけるシステム根幹を担う…
▼案件概要 今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバ…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【Salesforce】金融系会社の既存シ…
◇案件概要 某金融グループにて、業務改善のため既存システムからSalesforceに移行。 要件…
週5日
740,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【Vue.js】法人向けネットワークサービ…
◇職種:フロントエンドエンジニア ◇概要:法人向けネットワークサービス Webアプリ開発(PoC環…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
▼作業内容 運用中ソーシャルゲームにて2Dグラフィックスの制作をお任せいたします。 具体的には下…
週3日・4日・5日
250,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】サー…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Android】クイックコマースAndr…
案件内容 :クイックコマースのAndroidアプリの保守開発 クイックコマースサービス…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
Webディレクター
様々な業界の大規模大手企業のWebサイトやSNSの企画・構築・運用業務主に大手企業のデジタルマーケテ…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【SRE】業界最大手飲食特化型HRサイトの…
業界最大手飲食特化型HRサイトのリニューアルプロジェクトにおけるSREを募集します。 直接クライア…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| AWS | |
定番
【React/Next】大手HR会社求人掲…
大手HR会社の求人掲載システムの企業側画面のReact/NextでつくるSPAの開発メンバー募集しま…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Typescript・React.js | |
定番
【TypeScript/Python】Sa…
チャットボット型Web接客ツールの開発案件になります。 自社で開発をしているチャットツール開発の、…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・AWS・Django・Flask・Vu… | |
定番
【フロントエンド】大手ECサプリメント事業…
健康食品、健康グッズ、スキンケア商品の販売事業を展開している大手ECサイトでのグロースハック(改善A…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
健康食品やサプリメントといった機能性食品の研究開発・製造・販売を手がけている会社のECサイト開発に携…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日~】Fi…
Webシステム開発をご担当いただきます。 基本的な業務は、お客様の課題に合わせたBtoBのWEBア…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・RSpec | |
定番
【フルリモ / RubyonRails /…
大学の願書出願システムの継続開発案件において、以下をお任せします。 ・機能追加 ・不具合修正 …
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・Java・Script・CSS・… | |
定番
【リモート相談可 / SOC / 週4日~…
▼案件内容 セキュリティシステム企画・整備を主業務として、SOC(セキュリティオペレーションセンタ…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。 今回は、ホテ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日~…
【案件情報】 未経験でも以下の業務に興味がある方を募集しています。 ・AWSおよび社内情報システ…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【開発環境※一部】 クラウド:AWS バックエン… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモ / Kot…
【案件概要】 下記事業におけるサーバーサイドエンジニアの募集です。 ・保険事業会社向けの保険…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週5…
■下記のプロダクトのいずれかに、フロントエンジニアとしてご参画いただく想定です。 1)リアル・クリ…
週5日
610,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・・Web・API:GraphQ… | |
定番
【Javaエンジニア|リモート相談可能】F…
【案件概要】 既存事業として存在するFX/暗号資産ディーリングシステムを、SaaS型サービスに切り…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【Androidエンジニア|フルリモ / …
ソフトウェア仕様やテストの品質向上のために、新規メンバーを募集します。 【担当業務イメージ】 …
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・AndroidStudio・Swift… | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
今回の募集では、求人事業部もしくは、生活事業部での企画・デザイナー職のポジションを想定しています。 …
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京県庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Git・jQ… | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日~】自社シ…
【企業紹介】 弊社は、法人向けの自社プロダクトの企画・開発、WEBシステム等の受託開発、オンライン…
週3日・4日・5日
570,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5】…
【業務概要】 ・追加機能の基本設計 ・結合試験仕様書作成、試験支援業務 サーバーサイドのアプリ…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
自社副業マッチングサービスにおけるフロントエンドの開発を行っていただけるエンジニアの方を募集いたしま…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日~】某大手…
【業務内容】 以下の業務を行っていただきます。 ・法人向けクレジットカードサービスでPMやデザイ…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
◇新規教育関連サービスのフロント・クラウド・バックエンドエンジニアリング業務に携わっていただきます。…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS /週3日…
バナー制作やLP、ライティング、Webサイトデザインなどのクリエイティブ業務をご担当いただけるWEB…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
国内最大級のゲームプラットフォームにおいて、インストール型ゲーム・買い切り型パッケージゲームを取り扱…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【PHP】写真計測システムのソフトウェア開…
【案件概要】 自社オリジナルソフトの開発を担当していただきます。 画像をサーバーに送信し、ユーザ…
週4日・5日
190,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【Python】人口動態等のデータを用いた…
◇職種:データエンジニア ◇概要:人口動態等のデータを用いた混雑予測分析・各種データ整備 ◇勤務…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【PHP/Python】自社開発案件におけ…
弊社は、ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして、使用すればする…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript | |
【Webデザイナー】webマーケティング課…
Webサイト・バナー広告・LP等のデザイン業務全般をお任せします。 小規模から大規模まで、幅⾊く引…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【システム】既存システムの開発・保守業務
【案件概要】 大手SIerグループで利用しているクラウドサービスを利用した間接材購買システムの運用…
週4日・5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【サーバーサイド】Coldfusionを使…
【案件概要】 大きな顧客基盤を持つ自社採用管理システム「RPM」の新機能追加や、新規開発案件をお任…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Coldfusion・fusebox ・・DB:P… | |
定番
【Goエンジニア|フルリモ・週4日~】タク…
【業務内容】 ・タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発業務 ・配車…
週4日・5日
2.8〜4.1万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript・GCP・AWS・Pyth… | |
定番
【システム】業務システムの依頼対応支援
【業務概要】 以下の業務に携わっていただく予定です。 ・業務システムへの作業依頼の対応 ※各種…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】決済…
【案件内容】 新規システム開発に関わるプロジェクトリーダーです。 自社で開発した既存のPHPシス…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
<ポイント> ・日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ・IT業界で必須となる先進的な…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・-・<開発環境> 画面 :vue.j… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
当社のサービスのフロントエンド開発をお任せします。 現在、これまで外部ベンダー様のご協力を受けて運…
週5日
480,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロンドエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C#/J…
■案件概要 ショッピングのサービス開発の業務をお任せします。 ■開発体制 ・アジャイル開発 …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・C#・Unity・Unity・C#・Jav… | |
定番
【フルリモ / Swift/Ob-C / …
iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションのネイティブアプリ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Pyt…
【業務内容】 自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【AWS】某情報通信業者向け広告関連プラッ…
【案件概要】 大手情報通信業者にて、広告関連のプラットフォームを新規で構築するにあたり、フロントエ…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Go・Typescript・AWS・■技術… | |
定番
【インフラエンジニア|リモート相談可能・週…
▼業務詳細 各エンドユーザ向けPrisma Access導入プロジェクトのため、運用設計以降のご対…
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Ruby/Python】位置情報サービス…
【案件概要】 自社サービスプラットフォームの開発に携わっていただきます。 自社で培った技術や…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・Rails | |
定番
【インフラエンジニア|週5日】顧客インフラ…
【業務内容】 ・各種サーバーの運用保守(AD、Proxy、WSUS、FileServer、AADC…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Microsoft365・ActiveDirecto… | |
定番
【PM】業界最大級の福利厚生サービスのPM…
【案件概要】 業務リーダーとして、お客様との調整や、外部連携先の開発ベンダーとの調整、進捗管理、課…
週5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Azure】自社グループ会社サービスアプ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI/Webアプリケーションの設計、開発 ・LINE査定アプリ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【SQL】広告業界向けデータ活用業務支援
【案件概要】 広告/人材サービス業向け データ活用業務支援 【メイン業務】 ・クライアン…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| SQL・Tableau | |
定番
【Java】業務系案件のエンジニア案件
【事業内容】 ・システムインテグレーション ・ERPの導入支援サービス ・インフラの構築 …
週5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二重橋前駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C#・VB.NET | |
定番
【Rubys】運用中サービスの内容把握と改…
【業務内容】 システム開発の事業として、 1.お客様の要望に合わせてオーダーメイドのシステムを作…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【Java】DXツール(パッケージ)導入に…
■概要 下記の業務を担っていただける方を募集します。 DXツールの導入に関わる、設計、開発、テス…
週3日・4日・5日
390,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・vue.js… | |
定番
【Vue/Nuxt】新規案件におけるフロン…
【案件概要】 テクノロジーを活用し、スポーツビジネスを通して社会を豊かにすることを目指します。 …
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西国分寺駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt・V… | |
定番
【AWS】インフラ設計構築業務
◇業務詳細: AWSインフラ(VPC周り、EC2、RDS、ELB、Route53等)構築案件におけ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【Java】サーバーサイドエンジニア
【案件概要】 プロダクト大規模な機能拡張に伴って、バックエンドエンジニアが不足しているため募集いた…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
■案件概要 同社のプロジェクトリーダー候補として、エンドユーザーに直接届けるWEBシステム開発、サ…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【Python】自社サービスのカスタマイズ…
【業務内容】 下記の業務に携わっていただきます。 ・自社サービスのカスタマイズ案件対応 ・サー…
週5日
410,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python・Nod… | |
定番
【Java】チケット販売システム・払戻業務…
【作業内容】 ・払戻業務負荷軽減のための対応⇒払戻情報表示サイトの刷新、払戻受付Webサイトの新規…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell・teraterm・sq… | |
定番
【常駐 / C/C++ / 週5日】官庁系…
▼業務概要 官庁系システムの機能追加開発になります。 主に詳細設計から結合テストまでご対応いただ…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿三鷹駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【常駐 / VBA / 週5日】共通IT財…
【案件概要】 OracleからS4-Hanaへのデータ移行の移行ツール作成、移行作業に伴うデータ授…
週4日・5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| VBA・Linux | |
定番
【システムエンジニア|フルリモ・週4日~】…
【案件概要】 ・セキュリティ監視システムの開発・保守 ・SOC業務に係わる各種システム・ツールの…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
▼案件概要 サービスの立ち上げから数年経過し、負債が増大、構成はモノリシックになってきています。 …
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【CSS/HTML】金融メディア・新規立ち…
【業務内容】 金融メディアプラットフォーマーという立ち位置で、WordPress、RCMS、自社C…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【Java】クライアント先での新卒研修のJ…
【案件概要】 クライアント先での新卒研修の講師をご担当いただきます。 ※各プロジェクト先にて…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務内容】 今回は、AIアルゴリズムを利用したスマホアプリ(画像&動画を解析→ユーザーへ提供)の…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【インフラエンジニア|リモート相談可 / …
【業務内容】 ・現在稼働中のシステム基盤の製品EOS対応を通じてパブリッククラウド上にシステムを移…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】受託開…
【案件詳細】 弊社提供の観光系Saasサービスシステムにおいて複数のエンハンス案件に対応して頂きま…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【週5日 / Java / 常駐案件】受託…
【案件概要】 ・システム開発(受託・SES) ・iOS/Androidアプリ開発 ・WEBサイ…
週5日
630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町、武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Typescript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週2〜】組織…
【募集背景】 ・従業員の成功を加速させるオンボーディングプラットフォームの開発力を強化していくため…
週2日・3日・4日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
【案件概要】 Webページのデザイン及びコーディング業務 【スキル】 ・WEBデザイナー:…
週2日・3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋千種駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・ | |
定番
【Java/SQL】次世代勘定系銀行システ…
【案件概要】 銀行システムの開発がメインとなりますが、品質強化テスト(テストケース作成、テスト)な…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・SQL・Spring-framework・… | |
定番
【Javaエンジニア|週4日~】WEB業務…
【案件概要】 エンド側の内製チームとして参画し、お客様と協力し調査や保守作業を行っていただきます。…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門、神谷町 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・SQL・MarkLogic | |
定番
【開発ディレクター】Go x GraphQ…
大手アパレルプラットフォームのDX化を行うWebアプリケーションの開発ディレクターを募集します。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
| Go・gqlgen Postgres sqlbo… | |
定番
【WordPressエンジニア】医療機関の…
医療機関のプロモーション事業における、クライアントのHP改修など、 WordPressエンジニアと…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】海外向けコミッ…
新規立ち上げの海外向けコミック配信サービスのサーバアプリケーションの開発に携わっていただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・SQL | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ】新規…
新規立ち上げの海外向けコミック配信サービスのWebフロントエンドの開発に携わっていただきます。 ■…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
【C#エンジニア】製薬企業向けデータ分析ツ…
【業務内容】 ・製薬企業向けデータ分析ツールの開発プロジェクト 【環境】 ・フロントはRe…
週5日
620,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Typescript/React/フルリ…
フロントエンドにスペシャリティをもつエンジニアとして、プロダクトの継続的な成長にコミットしていただき…
週4日・5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| HTML・CSS・Typescript・React・… | |
定番
【VBA】医療関連システムの運用支援
案件概要 <作業内容> ・医療関連データベースセンターの運用支援 ・データベースへのデータ登…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA・SQL | |
定番
【SAP SAP/CO】大手製造業向け会計…
大手製造業向け会計全面稼働PJ準備支援案件(SAP/FI) 大手製造業向け会計全面稼働PJ準備支援…
週3日・4日・5日
330,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | SAPエンジニア |
| SAP・S・4HANAのFIモジュール | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【業務内容】 以下の業務を遂行するために、プロダクトマネージャーやエンジニアと協業しながら意思決定…
週3日・4日・5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿関内駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【COBOLエンジニア|リモート相談可 /…
【業務内容】 現在使用中のCOBOLのシステムがあり、2年後のリプレイスまでの間一部機能を改修して…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| COBOL | |
定番
【Typescript|フルリモート / …
【募集内容】 金属加工の商取引プラットフォームサービスのグロースに向けた機能開発をお任せします。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Next.js・R… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】Q…
開発組織内や関係部署にて実施している品質保証を担うチームを立ち上予定です。 チーム立ち上げやプロダ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅/都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
◇会社概要 日本国内の大手企業の課題解決や新規事業開発を目的とした DXコンサルティングを中心に…
週3日・4日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Rea… | |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】オンライ…
この度は事業拡大に伴い、コーディングのできるWEBデザイナーを募集いたします。 エンジニアの方やW…
週4日・5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【インフラエンジニア|リモート相談可 / …
【募集内容】 社内/社外利用環境や場所に依存せず、いつでも・どこでも利用可能とするゼロトラスト環境…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer・ActiveDirect… | |
定番
【SharePoint|リモート相談可 /…
【案件内容】 SharePointにおけるサイトやページの制作をお願いいたします。 客先常駐にて…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| SharePoint | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモート/週5日…
基地局の工程管理アプリの開発を行っていただきます。 工事業者が報告書をExcelで出しWEB化する…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・jQuery・Spr… | |
定番
【リサーチャー】マーケティング戦略コンサル…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます※ 製薬メーカーや医療機器メーカーに対して、ニー…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | 戦略コンサルタント |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件概要 APIManagerのDevelopperPortalの刷新のため、新規で構築を行う…
週5日
440,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java | |
定番
【Goエンジニア|リモート相談可 / 週5…
【業務内容】 新機能の実装を中心とし、プロジェクトによっては企画や要件定義から関わっていただきます…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・バックエンド:Go ・フロントエンド:Re… | |
定番
【C++ / 週5日】工業用顕微鏡アプリケ…
工業向け顕微鏡 ARアプリケーション開発を担当頂きます。 主に下記の業務に携わっていただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【SQL/データエンジニア|フルリモート/…
【案件概要】 大手メディア企業が保持するユーザー視聴ログデータや外部データを結合してユーザーに合っ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・GCP(BigQuery・CloudFunc… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】化学…
■案件内容■ 化学製品メーカーの製品化研究を管理するシステムの機能改修開発を行っていただきます。 …
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
■募集ポジション 保守開発PJTのリーダー(PMはプロパー。PMから下記内容を依頼する予定) …
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【Java / 週5日】自社VODサービス…
■業務内容 大手ケーブルTV事業者のVODサービスのシステム開発(100%自社内開発)の要件定義、…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【インフラ / 週5日】Azure環境の保…
【案件概要】 Azure環境の保守や運用作業をメインでご対応いただきます。 設計・開発・構築はす…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【UI・UXデザイナー|リモート相談可能】…
【業務内容】 ・ウェブサイトや証券取引アプリ(iOS/Android)の顧客体験向上・顧客満足度向…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Adobe・… | |
定番
【PHPエンジニア|リモート相談可 / 週…
【募集内容】 自社事業における開発プロジェクトに参画してくれるPHPエンジニアを募集しております。…
週5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・SQL・AWS・Docker | |
定番
【C#/AWS / 週5日】FX取引システ…
【業務詳細】 ・FX関連システムの新規構築・維持管理 ・クラウドを対象としたアプリケーションの開…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本⽊一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C#・AWS・Oracle | |
定番
【Perlエンジニア|リモート相談可 / …
【業務内容】 ・課金ライブラリの開発 ・既存課金レコード作成の改修、課金ファイル生成処理改修 …
週5日
300,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【React/TypeScript / 週…
【案件概要】 システム運用保守、社内インフラ維持保守(サーバーおよびネットワーク) AD運用、ア…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フロントエンドエンジニア|C# / 週5…
◇案件概要 既存の物流管理システムのOS、ミドルウェアバージョンアップに伴うリプレイスを行う想定で…
週5日
300,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【React・TypeScript|リモー…
【募集概要】 弊社サービスは、複数のデリバリー/テイクアウトサービスからの注文を一元管理できるサー…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
◇案件概要 大手通信会社がビジュアルコミュニケーションをアップデートする、インハウスのブランドクリ…
週1日・2日・3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週1日〜】…
▼案件概要 現在開発中のヘルス管理系新サービスでのUI/UXデザイナーの募集となります。 立ち上…
週1日・2日
130,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・AdobeInDesign | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【案件詳細】 モダンな環境での少数精鋭開発です。 100%自社サービスのWebアプリケーション開…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| ₋- | |
定番
【AWS / 週5日】インフラの各種設計、…
▼案件概要 現行環境のリプレース案件で、AWSにて稼働している環境を追加された要件を取り込みながら…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八幡山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Java/TypeScri…
【案件概要】 Java/TypeScriptを使用したWebサービス(SaaS)開発で、下記2案件…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・Next.js・ | |
定番
【スマホアプリエンジニア| iOS / …
【案件の内容】 弊社の画像認識アルゴリズムの提供基盤をさらに展開するにあたってiOS/Androi…
週3日・4日・5日
240,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Python・Swift・AndroidJava・K… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】レン…
【業務内容】 弊社で開発・運営しているレンタルスペースの予約プラットフォームのユーザーマイページの…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【C++ / 週5日】デジタルカメラネット…
【業務概要】 -主にデジタルカメラ機器向けのネットワーク機能開発におけるSW設計・実装をメインに行…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【セキュリティエンジニア |週4日〜】自社…
【業務内容】 導入企業の増加に伴い、導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集い…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTTP/Swift…
▼想定業務 ・動画配信モバイルアプリ、テレビ向けアプリ開発業務。 ・詳細設計/製造/単体テスト…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Ob-C・Swift | |
定番
【Java】小売店向け開発支援
Microsoft製品に関する各種導入支援サービスと運用支援サービスを中心に、サービスを展開していま…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【Webデザイナー|リモート一部相談可・週…
ファミリー向け動画メディアのデザイナーとして、ユーザーマッチング事業のバナーやLPを中心にクリエイテ…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / AWS/TypeScrip…
大手情報通信業者にて、広告関連のプラットフォームを新規で構築するにあたり、フロントエンドもしくはバッ…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Go・Typescript・AWS | |
定番
【リモート相談可 / PM/Unity /…
■案件内容■ 音声×SNSを目的とした新規スマホアプリの開発を行っており、開発PMとして進捗管理及…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Unity・【開発環境】 バックエンド:P… | |
定番
【フルリモ / AWS/TypeScrip…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのSREエンジニアの募集になります。 ・保険事業会社向け…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Typescript・AWS・▼技術スタック… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【仕事内容】 Web開発エンジニアとして以下の業務を中心に上流工程からコーディング、テスト、バグ修…
週5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Node.js・E… | |
定番
【フルリモ / PHP/AWS / 週5日…
動画配信システムのお客様向けカスタマイズ開発作業を担当して頂きます。 新規立ち上げサイト、または新…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・AWS・【開発環境・使用技術など】 ・LA… | |
定番
【リモート相談可 / SQL/AWS / …
店舗売上本部会計システムにおける在庫管理、運用支援機能の開発支援に携わっていただきます。 ・SQL…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL・AWS・Linu・PostgreSQL | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
▼案件概要 主に下記の業務をお任せします。 ・ウェブベースのSaaSシステムの開発 ・API設…
週4日・5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・- | |
定番
【フルリモ / SQL/TypeScrip…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Typescript・SQL | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】開…
各プロジェクトのインフラ専門チームとして、以下の業務を行っていただきます。 ・弊社IaaS(KCP…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / React.js/Type…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React/RubyonR…
新規プロダクトの機能実装・バグFix等をご担当いただきます。 実装方針や仕様の詳細部分でのやりとり…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| RubyonRails | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【想定業務例】 新規サービス、プロダクトのCVR、LTV、MAUや自然流入数、及びNPS向上に向け…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【業務詳細】 弊社プロダクトにおけるバックエンド開発のリーディングを担当いただきます。主にはオンラ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 /Python/Java…
【業務概要】 プロダクトの大幅なアップデートのため、開発組織の責任者として、Paymeを一緒にグロ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【 HTML/CSS / 週3日〜】自社ブ…
▼案件概要 自社ブランドでの化粧品やサプリメントの開発や販売を行っております。 実店舗のほか、E…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【フルリモ / Oracle / 週5日】…
■業務内容 大手損保様の基盤の維持管理案件に参画いただきます。 今回は生保様のプロパー様代替とし…
週5日
460,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Oracle | |
定番
【リモート相談可 / Python/Jav…
▼プロジェクト概要 法人向けに提供しているSaaSで主に「ID一括管理」「連携SaaSへのSSO」…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python・Jav… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件概要】 某携帯電話の情報配信サービスにて、キャリア公式の読み物コンテンツをCMSによる運用で…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java/HTML …
【案件概要】 今回は、画面開発部分をご担当いただきます。 データアクセス層(DA層)と呼んでいる…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 /C/C++ / 週5日…
案件概要 :プログラマブルなホワイトボックス・スイッチを利用した データ・プレーンの転…
週5日
460,000〜920,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
▼案件内容 新規の電子書籍取次システムの開発をご担当いただきます。 システムの刷新開発を行ってお…
週5日
580,000〜850,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・React・Postgr… | |
定番
【フルリモ / CI/CD / 週5日】テ…
【事業内容】 ・ICTソリューション事業 ・システム開発事業 すでに開発済みのプログラムに…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
【案件概要】 PythonでのAPI開発をご担当いただきます。 サーバーシステム運用が中心となっ…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【 VBA / 週5日】損保・社員支援業務
【業務内容】 損保会社様向け社員支援業務になります。 主に基本設計以降の工程をご対応いただきます…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / C#/HTML / 週5日…
▼案件概要 主に下記の情報共有システムの改修をご担当いただきます。 ・情報共有システムの改修・機…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・-C# | |
定番
【フルリモ / DB / 週5日】大手通信…
▽案件情報は下記の2つです。 1.大手通信会社のデータ分析基盤にてデータカタログに登録するメタデー…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】某事…
▼案件概要 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・加盟店がユーザーに対して、能動的に集客でき…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・・SpringBoot | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【求人概要】 CMS再構築プロジェクトの中核メンバーとしてフロントエンドエンジニアを募集します。 …
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / A-Auto / 週5日】…
▼案件概要 主に、案件推進を行うPMO業務、システム構成/NW構成の検討、見積資料、定義書等の作成…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Java/kotlin /…
◇職種:バックエンドエンジニア <プロジェクト概要> ニューノーマル社会の実現に向けたゼロト…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
【業務内容】 タクシーアプリやその他新規事業における、サーバサイド開発を総合的に行っていただきます…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Kubernetes・Docker | |
定番
【フルリモ / PP/MM / 週5日】S…
▼案件内容 下記の業務をご担当いただきます。 ・調達、在庫、実績収集業務に関するSAP導入、関連…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋静岡 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Node.js/Ja…
▼作業範囲 現在新規開発中の社内ワークフローシステムの機能開発における、詳細設計~製造単体テスト~…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Vue.js・… | |
定番
【リモート相談可 / Java/MySQL…
【案件内容】 IoTシステムの管理者向けWebサイトの改修、技術調査や方式検討、PoCなどプロダク…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Kotlin・SpringFW・MySQL・必須スキ… | |
定番
【Unity / 週5日】スマホアプリのプ…
【運営事業】 ・スマホ向けのアプリケーション開発 ・ゲーム開発 ・xR技術を用いたアプリケーシ…
週5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【WEBディレクター】サイトリニューアル制…
大手音楽事業会社のポータルサイトや、受注・倉庫管理システム会社のコーポレートサイトのリニューアル案件…
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| ‐ | |
定番
[Webディレクター]自社ECサイトおよび…
【業務内容】 ECサイトやオウンドメディアのUI/UXの改善を行っていただきます。 デザイン戦略…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXディレクター |
定番
[SalesForceエンジニア]大手通信…
【業務内容】 ビジネスチャット運用、開発要員 ・システム開発(SalesForce担当) …
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
[PM / PMO]通信企業様のビジネスチ…
【業務内容】 サービスの申込サイト画面における課題や要件をとりまとめ、製造ベンダ等に開発、改善、改…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM / PMO |
定番
【PHP】美容健康食品・化粧品ブランド事業…
美容健康食品・化粧品ブランド企業のシステム開発・保守/運用、インフラまわりの管理、の業務をご担当いた…
週3日
290,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルスタックエンジニア|フルリモ・週3日…
【案件概要】 自社内にてサービスの開発および運用を行っているお客様に向けて、新規・既存を含めた様々…
週3日・4日・5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・・React・Angul… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
【業務内容】 顧客プロモーション支援にともなうアプリ開発をご担当いただく予定です。 ※詳細は面談…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
●業務概要 コンビニ向けセキュリティ系システムの結合テスト~本場後におけるプログラム保守までご担当…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 IT企業を中心に人材育成サービスを展開しています。 IT企業のお客様に対しまして、…
週5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件内容】 ポータルサイトのリニューアル開発です。 個人プラットフォームのリニューアル開発を…
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python/R / 週3…
【案件概要】 下記の業務をご担当いただきます。 ・広告効果を推定するための統計手法や、広告予算配…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・R・Julia | |
定番
【フロントエンド】大手HR事業のプロダクト…
テレビCMでもおなじみの大手HR事業のエンハンス施策に関わるフロントエンドエンジニアリングが主業務と…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】マテ…
▼案件概要 下記の業務をご担当いただきます。 ・新規サービスの開発、およびそれらの基盤を支えるシ…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Java・S… | |
定番
【フルリモ / PHP/ 週3日〜】店舗向…
【案件内容】 ・PHP/LaravelにてB2B自社サービスを開発しています。 ・Google …
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby/JavaScri…
【業務内容】 C2C向けフリマサービスのWEBアプリ開発業務をしていただきます。 数名のチームメ…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
【内容】 外部結合試験が実施されるので、試験対応や障害が発生した際にご対応を頂きます。 【フェー…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C・C++・SQL・shell | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Jav…
▼案件概要 この度は、新規で立ち上げている主婦向けの口コミアプリ開発に向けたフルスタックエンジニア…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・V… | |
定番
【Swift / 週5日】大手不動産会社の…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションを提供…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件内容】 アスリート追っかけサービスのフロントエンド開発です。 こちらの対応スポーツ追加や機…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・【開発環… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社で開発したプロトタイプのアプリをベースに、それをクラウドサービス化するプロジェクトの開発担当エン…
週3日・4日
450,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Hyper-V / …
【業務詳細】 顧客標準仮想基盤の再構築に伴い、以下作業を実施。 ・新仮想基盤の検証 ・仮想ゲス…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer2016・Hyper-V | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
▼案件内容 機械学習に関するデータ分析業務に関して、フィジビリティ検証やPoC開発を行うチームの…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】新…
◇職種:QAエンジニア ◇概要:新規教育関連サービスのQAエンジニア <業務内容> ・スト…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React.js/T…
更なる事業拡大に伴い、新メンバーを募集することになりました。 【具体的な業務内容】 航空券の…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript/Ja…
▼業務内容 ・BtoCでECサイトの運営をしている ・AWS構想の連携でトラブルの際の復旧作業 …
週4日・5日
240,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / Java/Linux…
【案件概要】 既存のECサイト全面刷新におけるフロントおよびバックエンドの機能開発をご担当いた…
週5日
410,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Java/TypeScri…
【案件概要】 支出の見える化、見積の取得、購買、契約管理、支払・請求などの機能をオールインワンでも…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Vue.js・Nuxt.js・TypeSc… | |
定番
【Linux / 週5日】金融機関システム…
【案件概要】 金融系インフラエンジニアとして、インフラ設計・構築・運用業務を担当していただきます。…
週5日
470,000〜550,000円/月
| 場所 | 東京23区以外多摩センター |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C#】自社販売管理パッケージのカスタマイ…
【業務内容】 (※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) ・販売管理(受注~売上、発注~仕入れ)…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
▼案件概要 弊社の取引先企業様から直接案件を持ち帰り弊社のエンジニアチーム(ラボ開発)にてPJを受…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Photoshop/Ill…
<制作実績> 大手通信系企業やハウスメーカーのコーポレートサイト の制作を行っております。 そ…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【フルリモ /ネットワーク / 週4日〜】…
【案件概要】 大手小売企業のNW設計/構築/運用、その他付随業務を行います。 大きく2チームがあ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【AndroidJava / 週5日〜】大…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
弊社クライアントの受託開発案件にご参画いただきます。 生保業界向けネイティブアプリ開発となります。…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅島駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
▼業務内容 基本設計・詳細設計・実装・UT・IT 作業としては設計工程も含みますが、こちらに…
週4日・5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿岩本町 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】オン…
<業務内容> 日本最大級オンラインギフトプラットフォームのソフトウェアエンジニアのサーバーサイド開…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Git・Fluentd・Sentry・Dat… | |
定番
【フルリモ / PHP/Wordpress…
▼案件詳細 下記の業務をご担当いただきます。 ・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・【会社概要】 ・モノの価値をつなぐ・“リユ… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
■案件内容■ データ管理システムや投資家向けサービスを提供する事業会社にて、自社プロダクトのUIU…
週5日
250,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【業務内容】 ・各種Linuxサーバの構築と手順書作成 ・運用時のためのスクリプト作成 ・サー…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React・【会… | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
【案件概要】 世界初の特許技術を使用した自社ソリューションに関連したAndroid・SDK並びにア…
週4日・5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
急募
Webディレクター
【企業】 神奈川県を拠点に、サイト制作やSNSマーケティングなどクライアントの課題を総合的に解決す…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター・コーダー・デザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社顧客…
【企業紹介】 転職特化型のスキルスクール事業を運営しているスタートアップです。 弊社の下記シ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java / 週5日】レーザー顕微鏡開発
レーザー顕微鏡開発(顕微鏡制御・GUIアプリケーション)において、顧客より要求をヒアリングし、設計~…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C・C++・(環境) -OS:Windo… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【企業情報】 ヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開しています。 …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / React/Ruby / …
受託開発における業務をお任せします。 ESGの観点で企業評価をスコアリングするためのサービス開…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 /Java / 週4日〜…
当社のサービス基盤を企画~開発~運用まで幅広く経験できる業務です。 ご経験やご志向に応じた部署にア…
週4日・5日
480,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【業務詳細】 ある程度ある型にあわせて、週1本程度デザインや、バナーなどを対応いただくと共に、デザ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ₋-・₋- | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】団地…
▼案件概要 基幹系システム最適化に係る団地再生システムの再構築案件です。 日立汎用機(COBOL…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海浜幕張 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
▼案件概要 社員数50人規模の社内ネットワーク運用・改善を中心に、各種ITサービスやPC・スマート…
週3日
190,000〜230,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / サーバサイド / 週…
【事業内容】 ・ICTソリューション事業 ・システム開発事業 【案件概要】 今回は弊社が…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| ASTERIA | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
【業務詳細】 現在弊社メンバーが参画しているリプレース案件の増員となります。 下記の業務をご担当…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
【業務内容】 ・主にマーケティング活動で使用するWeb/グラフィックデザインの業務を依頼します。 …
週3日・4日・5日
250,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【PM】英語でのコミュニケーションが可能な…
Webサイトやアプリの制作、客先常駐型のオンサイト運用などをおこなっている会社です。 担当プロダク…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Swift/iOS …
▼ 業務内容 FXスマホアプリの開発をご担当いただきます。 ※具体内容や今後については面談時にお…
週5日
730,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・iOS・- | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
■業務内容 フロントエンド開発、およびE2Eテストをはじめとしたテスト自動化の開発をお任せします。…
週4日・5日
840,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
◇職種:フロントエンドエンジニア ◇概要:法人向けネットワークサービス Webアプリ開発(PoC環…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 ・広告代理業 ・イベント事務局の運営 ・催事、コンベンション及び会議の企画立案、…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週5日…
◇案件詳細 顧客標準PDF編集ソフトウェアのバージョンアップ 要件定義支援、設計、スクリプト開発…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / VB/.Net / 週5日…
【業務内容】(※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) 以下の業務に伴うハンディターミナルを用いて…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】情報…
▼案件概要 現行SAP BWからSnowflakeへの移行を想定しています。 以下の作業を行って…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【PdM】Webプロダクトの企画、要件定義…
Webプロダクトの企画、要件定義や開発プロジェクトのディレクション業務に携わっていただける方を募集い…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM(開発ディレクター) |
【swiftエンジニア|フルリモ・週4日~…
【案件概要】 弊社が提供しているサービスを中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木八幡駅 |
|---|---|
| 役割 | Swift(Flutter)エンジニア |
| Swift・Flutter・Dart・Swift・K… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
【業務内容】 ・商標登録を安心、カンタンにできるようにするクラウドサービスを支える独自システム(W…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【PHP/Java / 週3日〜】小売店向…
【案件内容】 弊社開発メンバーの一員としてクライアントから依頼を受けている開発業務に携わっていただ…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿博多駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
▼案件概要 この度は事業の拡大に伴い、クラウドエンジニアを募集いたします。 ▼業務詳細 ・…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【開発環境】 言語 :C#・・・JavaScrip… | |
定番
【フルリモ / Java/SpringBo…
■案件概要 学習系管理WEBアプリの開発となります。 3つのシステムが絡んでいるため、API周り…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java11・SpringBoot・Spr… | |
定番
【リモート相談可 /Python / 週3…
【業務内容】 - 成長戦略を踏まえたKPI設計 - サービス運営で定常的に発生する分析企画と工数…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・- | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【企業概要】 ・クラウドインテグレーション事業 ・データ分析サービス事業 ・DevOps関連サ…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
【案件概要】 保険に関連した機能追加や、より使いやすいようUX改善の実施を担っていただける方を募集…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Shopify / …
▼案件概要 業績好調につきデザイナー&EC担当として活躍いただける方を募集しています。 海外向け…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王線平山城址駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・Illustr… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
■募集職種:バックエンド,サーバーサイド ■担当工程:基本設計,詳細設計,実装,テスト,運用・保守…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・・インフラ:GMOクラ… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】ス…
【業務内容】 下記機能追加の開発、単体テスト設計、テスト実施、結合テスト設計・実施、UT実施をご担…
週5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべてをお任せ致します。…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【フルリモ / JavaScript/SQ…
新規プロジェクト開始に伴い、下記内容に参画頂けるエンジニアを募集いたします。 ■PJT概要 …
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
▼業務内容 マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務に携わっていただきます。 主に下…
週4日・5日
250,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【C/C++ / 週5日】IoT機器ソフト…
【案件概要】 RasberryPi 4Bを用いたIoT機器の試作開発 ① RasberryPi …
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・C・C++・RasberryPi | |
定番
【インフラ / 週3日〜】ヘルステックベン…
グループ全社のクライアントPCやそれに付随するヘルプデスク業務をご担当いただきます。 【具体的…
週3日・4日・5日
280,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 /Java / 週5日】…
【案件内容】 ポータルサイトのリニューアル開発 個人プラットフォームのリニューアル開発を担当いた…
週5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Java/SQL / 週4…
【案件内容】 アドオン開発(要件定義~設計~製造~テスト~リリース)の推進・保守(エンドユーザから…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Oracle(Oracle・12C… | |
定番
【フルリモ /上流SE / 週5日】Win…
【案件概要】 現在稼働中のWinActorロボについて、システム刷新に伴い、修正を行っていただきま…
週4日・5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務詳細】 クライアントに対してブランディングデザインからご提案する機会も多く、コーポレートサイ…
週3日・4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【VB/SQL / 週5日】販売管理基幹シ…
◇作業内容 小売店の既存システムに対する保守案件の要件定義~リリースまでをご担当いただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| VB.NET・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP/Ruby / 週5…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・BtoBオークショ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 /PHP / 週5日】中…
▼案件内容 中古機械ECサイト向けサーバサイド開発支援 (サイトの手数料変更業務) の開発から…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Github・AWS | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】ビ…
▼案件概要 既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【C/C++ / 週5日】3次元画像処理シ…
【業務概要】: 画像や映像から立体形状を復元する3次元画像処理システムの検証、アルゴリズム検討、実…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】X…
◆案件内容 某キャリアが展開するxR系の新サービスにおける企画から要件検討、実現性の調査、機能要…
週5日
720,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【PHP】SEO対策/バックエンドエンジニ…
自社プロダクトの SEO施策を実行する開発業務をお願いいたします。 細かな SEO 施策やプロダク…
週5日
2.8〜5.7万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フロントエンドエンジニア|リモート相談可…
官公庁・自治体等向けサービスの施策を実行する開発業務をお願いいたします。 今回は細かなSEO施…
週5日
2.8〜5.7万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|Typescr…
【案件内容】 官公庁・自治体等の入札・落札情報を探せる入札情報サービスのプロダクト改善のための機能…
週5日
2.8〜5.7万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週5日…
幼稚園・保育園向け写真販売システムに関連する新サービスの開発業務をお任せいたします。 プロダクト開…
週5日
4.1〜5.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / javascript…
■業務内容 動画配信サービスの運用保守/新規開発をご担当いただきます。 ■業務例 ・既存サ…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・■開発環境 … | |
定番
【フルリモ /サーバーサイド / 週5日】…
下記三つの事業を展開しております。 クラウドインテグレーション事業 データ分析サービス事業 …
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】動画配…
◆ 案件概要 動画配信プラットフォームを使用したポータルサイトの開発案件です。 今回は、動画別/…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
◆案件概要 MNOの新規・乗り換えの申し込みページ等の開発です。 また、突発の案件対応やトラブ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Redux・Nod… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
【概要】 自社開発のWEBマーケティング支援ツールの開発と運用 【案件詳細】 ・少人数での…
週4日・5日
2万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週4日〜…
◆案件概要 ゲーム事業にプラットフォーム開発/運用業務のマネジメント、スクラムマスター ◆募…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| PHP・Go・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
この度は、社内アクセラレーションプログラムから生まれたスマートウォッチシリーズの開発に携わっていただ…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / PHP/Laravel /…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日・4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●業務詳細 ・2週間スプリ… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Go …
【案件概要】 ・AIカフェロボットのバックエンドの開発 ・root Cを支える「root C C…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【Android / 週5日】toC向けス…
C to C向けアプリの開発をお任せいたします。 アプリの対象はAndroidで、言語はJavaで…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【SQL / 週5日】Linux環境でのC…
【案件概要】 開発メインで携わっていただきます。 C言語開発ですのでポインタの読み書きは必須です…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿蒲田 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C・C++・SQL | |
定番
【リモート相談可 / C#/.NET / …
◇業務詳細 主に先方の営業担当者が利用する「販売見積受注システム」や、「MDM」の再構築に際し、A…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【Python】ニュースメディアのバックエ…
ニュースサイトのコンテンツ自動生成プロジェクトに携わっていただきます。 特定のデータソース(企…
週3日・4日・5日
380,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲外苑前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・開発言語:Ruby・・Python・・… | |
【Webデザイナー】eコマースサイトで販売…
【企業情報】 飛躍的に成長した既存事業への経営資源集中、事業提携・M&Aにより拡大してきたグループ…
週2日・3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【エンタメ業界向け分析サービス】Goのご経…
弊社で開発している、大手レコード会社や芸能プロダクションなどを対象とするCD売上やSNSの動向を分析…
週4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・言語:・Go・・Python フレームワーク… | |
定番
【Java】開発エンジニア
【仕事内容】 主に当社が運営するWebサービスの開発、運用をお願いします。 99%を内製化してい…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【Java】開発エンジニア
【仕事内容】 主に当社が運営するWebサービスの開発、運用をお願いします。 99%を内製化してい…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【unityエンジニア】CG担当者の作成後…
【企業情報】 「映像コンテンツ」と「テクノロジー」の融合による高品質な映像表現を目指し、「XR(V…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | unityエンジニア |
| C・C++ | |
定番
Webディレクター募集
当社はHPの新規作成・リニューアルにて様々な業界のお客様とお仕事をしております。 本案件では、コー…
週4日・5日
8〜1.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿南森町 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
自社決済システムフロント開発支援(上級PG…
お客様の自社システム新規開発支援を担当いただきます。 エンド社員様が要件定義は担当しておりますので…
週5日
620,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【フルリモ / Java/SQL / 週5…
下記の業務をご担当いただきます。 ・基本設計 ・詳細設計 ・PG ・試験 ・調査 現行処…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【業務内容】 ・新規アプリのUI/UXデザイン ・UI/UX設計 ・トンマナの設定、スタ…
週3日・4日
450,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| 【会社概要】 医師14万人が参加するコミュニティサ… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】CX…
カスタマーサクセス支援/顧客エンゲージメント向上ツールを提供しています。 積極的に新規機能開発(企…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・【開発環境】 開発言語:Ruby サー… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。Google Cloudに特化…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件内容 在庫管理や会計処理のほか、各種マスタ管理などを含めた基幹システムの要件定義。および、外…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
地域情報プラットフォームへ掲載いただいている企業や、地方自治体から依頼をいただいたLPやバナー作成を…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 東京23区以外西船橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・【企業情報】… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
1.ネットスーパーシステムの企画・開発に携わっていただきます。 2.物流管理システムの企画・開発に…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三国駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / テストエンジニア/ …
-車載ECUソフトの評価・受入対応。 -要件定義、アーキ設計~詳細設計をINPUTとして単体テスト…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
3Dのバーチャル空間で多人数が同時接続するシステム構築・企画段階から参加をして、技術的な課題解決、要…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
チャットボット型Web接客ツールの開発案件になります。 自社で開発をしているチャットツール開発の、…
週5日
1.6万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・OS:Windows・Linux D… | |
定番
【デジタルマーケター(サービスグロース)】…
美容医療の口コミ/予約アプリ「トリビュー」をより多くの方に、より高頻度でご利用いただくために、事業計…
週4日・5日
410,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | デジタルマーケター |
定番
【フルリモ / React.js/Type…
旅行予約サイトを中心に自社でサービスを開発しています。 今後、レストランなどあらゆる商品が予約でき…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【AWS / 週5日】インフラの各種設計、…
現行環境のリプレース案件で、AWSにて稼働している環境を追加された要件を取り込みながら、別アカウント…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八幡山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
◆案件概要 下記の業務に携わっていただきます。 ・会社横断のマーケティングチームにおけるランディ…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Larave…
自社サービスに従事するメンバーが使う社内用業務システムのリプレイス/開発を担当頂きます。 具体…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・・Vue.js・Nuxt.j… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
医師の研究をサポートするプロダクトにおけるUI/UXデザイナー募集しております。 【仕事内容】…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Adobe・XD・・リポジトリ管理・ツー… | |
定番
【リモート相談可 / MLOps/Lara…
全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる 入札情報速報サービスを自社事業とし…
週3日・4日・5日
670,000〜1,600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
◆案件概要 口座開設、残高照会、入出金明細照会などの機能を持つ銀行スマホアプリ開発 Kony…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Java・jQuery | |
定番
【リモート相談可 /インフラ / 週5日】…
既存医療機関向けポータルサイトをAWSに移行業務をご依頼します。 ポータルサイトは、オンライン資格…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
【具体的な募集内容】 自社プロダクトを支えるリードエンジニアを募集しています。 運用自動化プラッ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【事業紹介】 ・SRDU開発事業 ・フリーランスエージェント事業 ・フリーランスコミュニティプ…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Laravel/Vue.j…
【業務内容】 事業拡大に伴い、プロダクトの機能開発および運用をお願いできるエンジニアを募集しており…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・日本商品の海外向けインターネット通販サイトの運用を支える基盤システムの運用と管理をご担当いただきま…
週5日
360,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
【概要】 3D自律移動ロボットのSW開発・品質向上・保守を行って頂きます。 -自律ソフトウェ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
この度は大手家電量販店を代表に、多くのプロジェクトをご依頼いただいているため、新たな開発メンバーを募…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Java・VB.NET・₋- | |
定番
【フルリモ / Javascript/Ty…
【業務内容】 自社プラットフォーム開発におけるスマホアプリエンジニアの業務を依頼します。 ・弊社…
週3日・4日
260,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【Python / 週5日】サーバーサイド…
▼案件詳細 開発中または運営中のタイトルにかかわるサーバーサイド開発 ・iOS/Android向…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Angular/No…
【概要】】 IoTクラウドサービスにおけるログ解析システム開発を担当頂きます。 業務内容は下…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿北八王子駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Angular・No… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
▼案件概要 電子書籍取次システム機能開発支援様々な業務をご担当いただきます。 ▼詳細 -…
週5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
▼業務内容 ・デプロイ時の自動テストの運用が一番のメインになります。 ・E2Eテストは不安定なの…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Ruby・rspec・Selenium… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
<業務内容> 第4のデバイスとして注目を集め、人々の新しいライフスタイルを創造するAndroidエ…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Python・Swift・Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
【案件概要】 マーケティングを支援するためのツールの開発や、自社アフィリエイトの提供をしているチー…
週4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・クラウドインフラ:Fargate・・E… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
<案件概要> ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・PHP・Pos… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ECサイト構築を担っていただきます。 ・新規ECサイト構築 ・ECサイト運用 ・社内業務改善ツ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件詳細】 WEBデザイナーを急募しています。 【業務内容】 ・ECのUIデザイン ・…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜町 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【案件概要】 タスク管理機能(To Do List)を新たなモダンな開発環境への移行に伴う、 フ…
週5日
370,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・node… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】製造…
◆案件概要 主に、製造業調達システムのサプライヤーと情報連携ツール作成と業務支援に関するシステム開…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【 C/C++ / 週5日】自社製品CI開…
【概要】自動ビルド/自動テスト/自動結果解析のためのテストの拡充とツール導入のための作業をご担当いた…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野阪上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Gitlab / 週…
社内で提供しているサービスの監視システム構築のため、基本設計から詳細な監視設定を作成し、作成した監視…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【COBOL / 週5日】【COBOL】損…
▼業務内容 損保会社向け契約管理システム開発業務になります。 設計、開発、テストまでご担当いただ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| COBOL | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】新規…
【案件概要】 当社は様々な情報を届ける、Webメディアを運営しています。 リリースしたばかり…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
▼案件概要 大手消費財メーカー様のSalesforce初期導入PRJ.全国に1,500名ほどいる営…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / RubyonRails /…
◆概要 オンライン契約締結管理サービスの主にバックエンドエンジニアをお任せします。 具体的には……
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【AWS / 週5日】AWSインフラ開発・…
案件概要 :既存システムからのインフラ変更、最適化 案件内容 :既存システム環境(AWS)から…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Node.js/Ja…
▼業務内容 自社健康診断パッケージのバージョンアップ 現時点では計画、立案が終わり…
週5日
500,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Nodeエンジニア |
| JavaScript・Node.js・・jQuery | |
定番
【C# .Net】視聴率算出を行うWebA…
視聴率算出を行うWebAPIの開発。詳細設計~移行・リリース作業等 リモートメイン(現状は週1…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・GCP(Cloud・Run、BigQuery)… | |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
【業務内容】 自社案件のWeb・クリエイティブデザイナーを募集します。 ・バナーデザイン …
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ /JavaScript/PHP…
【募集背景】 当社サービスの成長をさらに加速するため、事業推進いただける立上げメンバーを募集中! …
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【 Python / 週5日】健康保険組合…
業務内容 健康保険組合加入者向けWebサービスのバックエンド開発をお願いいたします。 現在、要件…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Linux/C++ …
【業務概要】 -主にカムコーダのUI操作系(Menuなど)や各種機能に基づくMWとのIF開発におい…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】ス…
【業務内容】 新規事業として、スマホアプリのブロックチェーンゲーム開発を予定しており、立ち上げから…
週5日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop …
▼案件概要 マーケティング組織でのデザイン業務をご担当いただきます。 作業一例: ・マス…
週4日・5日
150,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| AdobeIllustrator・Photoshop | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】建…
◆案件概要 この度は、建築業界のタスク管理(施工管理)ツールのUI/UXデザインを担当いただけるデ…
週5日
240,000〜280,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【案件概要】 下記ゲームにおける開発業務をお任せいたします。 某ゲーム企業向け Web(PC /…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・₋- | |
定番
【フルリモ / React/Kotlin …
【業務内容】 某生命保険会社様向けにシステム開発を並行して多数行っておます。 ・テスト計画書…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【Java】某大手企業でのJava開発業務
【企業】 大連、吉林にオフショア開発基地を持っております。 お客様の立場で考えご提案・ご協力でき…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【PM】注目Aiベンチャーでのエンタープラ…
【業務内容】 ※今回募集するポジションでは、エンタープライズプロジェクトマネージャーとして、効果的…
週5日
840,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | エンタープライズプロジェクトマネージャー(PM) |
定番
【TypeScript】注目Aiベンチャー…
【業務内容】 当社の音声認識システムにかかわるプロダクトのソフトウェア開発およびフロントエンドおよ…
週5日
840,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(TypeScript) |
| Typescript・言語:TypeScript・・… | |
定番
【SRE】社内SE(業務システム)/システ…
進行中の複数プロジェクトのうち、スキルや経験に応じてプロジェクトにアサインいたします。 ・顧客管理…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(SRE) |
| PHP・Java | |
定番
【PHP/Java】社内SE(業務システム…
進行中の複数プロジェクトのうち、スキルや経験に応じてプロジェクトにアサインいたします。 ・顧客管理…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / C++/Linux …
【概要】 検体分注機およびPCモニタ機能開発における設計・実装・テストをご担当頂きます。 顧客よ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【 Linux / 週5日】EPCコアネッ…
◆案件内容 EPCコアネットワークの試験環境を構築します。 主に、開発に必要なビルド環境や自動化…
週5日
240,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小杉駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Python】データアナリティクス・戦略…
データ分析担当者として課題設計から、 分析設計、仮説検証、実装、効果検証までの幅広い範囲を担ってい…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL・- | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【業務詳細】 ・AWS基盤の保守/運用業務 ・新サービス利用時の利用ルールの策定/セキュリティ評…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本⽊一 丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / JavaScript/Ty…
▼案件概要 既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・メインサービスのフロントエンド開発…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◆案件内容 データサイエンスプラットフォームサービスの立ち上げメンバーとして、サービスの企画・開発…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【PM】社内SE 基幹システム(企画系)
社内IT企画、導入、運用(管理職候補)事業の 様々な課題に対して最新のITソリューションを企画・導…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | PM(社内SE 基幹システム(企画系)) |
定番
【フルリモ / Java/SpringBo…
▼案件概要 想定プロジェクトB、プロジェクトC ・両案件ともクライアントは同一で、とある大手EC…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】情報分…
【案件詳細】 現行SAP BWからSnowflakeへの移行想定しています。 作業内容は以下にな…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | SQLエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
【企業概要】 当社は主に、モノの移動に課題をもつユーザーにソリューションを提供しています。 …
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Java …
ペット関連のWebサービスの改修、新機能開発業務を担っていただきます。 外部ベンダーで開発していた…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・J… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【業務詳細】 ある程度ある型にあわせて、週1本程度デザインや、バナーなどを対応いただくと共に、デザ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / React/Node.js…
国内最大級動画ソリューション企業にて以下の業務をご担当いただきます。 ・HTML/CSS/Java…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
EAIパッケージ製品を使用したアプリケーション開発案件です。 SFTPを使用し外部関連機関よりファ…
週5日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
下記の業務をご担当いただきます。 ・仕様や設計の検討 ・実装/テストコード追加/レビュー/検証/…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go・Typescript・ES2015(ES6)+… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
オリジナル化粧品・美容雑貨などを企画・販売しているメーカーです。 自社製品のWEBデザイン(バナー…
週5日
130,000〜150,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸三国駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・₋ | |
定番
【フルリモ / Python/C++ / …
このたび、弊社の画像解析アプリを用いて、機器メーカーとPoC(実証)をやることになりました。 その…
週3日・4日・5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Node.js/JavaS…
現在、国内外のWebニュースをクローリングし、HTMLからニュースタイトル、日付、本文等を抽出するク…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React/SQL …
【業務内容】 ・障害発生時の原因調査、不具合対応 ・問い合わせに対する調査、回答 ・改善要望の…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社で開発したプロトタイプのシステムをベースに、商用パッケージを新規開発する開発担当エンジニアを募集…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇業務詳細 AWSインフラ(VPC周り、EC2、RDS、ELB、Route53等)運用案件における…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/VueJS / …
◇概要 アプリケーション向けのCMS(配置情報とARコンテンツ等を管理し、配信するシステム)の開発…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・VueJS | |
定番
【フルリモ /グラフィック/ 週3日】★副…
▼案件概要 食品業界に特化したブランディング支援の会社において以下職種の募集をしています。 ・ラ…
週3日
90,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】就活…
▼案件概要 工学系学生に特化した就活支援サービスを行っており、企業ごとの選考時期や面接で何を聞かれ…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【業務内容】 ネットワークの回線や装置の情報管理や、工事などの各種作業チケットの管理をしている業務…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Typ…
【案件概要】 ノーコードで高精度なAIモデル開発ができる「Learning Center」に関する…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件概要 顧客で契約しているデータセンター廃止にともない、データセンターに設置しているネットワー…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
自社海外プロダクトについて、日本語での技術サポート、関連業務を行っていただきます。 ■業務イメ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
定番
【リモート相談可 / WordPress/…
この度は案件の拡大に伴いWEBデザイナーの方を募集いたします。 【業務詳細】 現在請けている…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
現在会社の成長に伴い、請負案件にて開発リソースが不足しております。 WEBアプリケーション開発にて…
週5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【PHP / 週5日】勤怠管理システム
PHPコーディング、単体テスト仕様書作成等の資料作成をご担当いただきます。 ◆実装される主な機…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お台場海浜公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP | |
定番
【インフラ / 週4日〜】AWS環境へリプ…
▼業務内容 ・官公庁の人事給与システムのAWS環境へのリプレース作業 ・AWSへの移行およびAW…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
この度は案件拡大に伴い、WEBデザインからコーディングまで対応いただける方を募集いたします。 …
週3日・4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ /サーバーサイド / 週3日〜…
▼案件概要 現在社内ツールとして「Tableau」を活用しております。 今後システム設定やカスタ…
週3日・4日・5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【Swift/XCode / 週5日】iP…
【案件概要】 iPadアプリケーションソフトウェアの設計、コーディング、テストまでご対応いただきま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・XCode | |
定番
【フルリモ / Vue.js/AWS / …
▼業務内容 下記の行をメインにご担当いただきます。 ・要件チームとの調整 ・フロントエンドから…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・Go・RubyonR… | |
定番
【リモート相談可 / Reactjs/Ty…
今回はニアエルのDjango化プロジェクトの中心人物として仕様検討、設計、実装、テストなどをお願いし…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
▼案件概要 当社クライアントの大手ゲーム会社様にてWindowsサーバチームのリーダー業務を担当し…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
<業務内容> ■自社システム「NASシステム」の開発 ①商品の自動登録の機能開発 自社システム…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・Amazon・MWS | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Java /…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのバックエンドエンジニアの募集になります。 ・保険事業会…
週3日・4日
330,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】建設…
【内容】 ①機材管理システム及び工場管理システムの開発要員の増員となります。 担当して頂くフェー…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringFW・Thymeleaf | |
定番
【フルリモ / Java/Springbo…
▼案件概要 請求管理周りの業務に沿って作成されたシステム化業務フローや洗い出された機能をもとに、外…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・Springboot | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件内容】 対話型Vtuberと関係性を育むことができる次世代のコミュニケーションサービスのiO…
週3日・4日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【 Java / 週5日】パッケージ基盤開…
下記の業務をご担当いただきます。 ・パッケージ基盤のアーキテクト開発 ・顧客製品の開発基盤のアー…
週5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / React/Kotlin …
▼案件内容 保険業界向け営業支援アプリケーション開発案件です。 開発言語といたしましては、 ・…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Azure・AW… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
エンタメ系の情報コンテンツを提供するPC、スマホ向けWebサービスの改修案件となります。 機能…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】会計仕…
当社では仕分けソフトを大手税理士事務所や会計事務所などに提供しております。 この度は、サービス拡大…
週5日
330,000〜480,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】Lega…
【業務内容】 ユーザーの課題を解決しプロダクトを成長させるために機能開発・改善業務を担当していただ…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ /HTML/CSS/ 週3日】…
ヘルステックサービスアプリのUI/UX統一から、店舗での販促資材、医療機関HP向けのデザインまでサポ…
週3日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
【業務概要】 リアル決済領域に関わる各種プロダクトを使用した、SWテスト、UiPathやAster…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守 |
| Uipath・ASTERIA | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】W…
▼案件概要 学習系管理WEBアプリの開発となります。 3つのシステムが絡んでいるため、API周り…
週4日・5日
2〜2.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / CSS/TypeScrip…
■本ポジションの役割 -プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Lar…
健康食品やサプリメントといった機能性食品の研究開発・製造・販売を手がけている会社のECサイト開発に携…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
【案件概要】 子育て支援サービスのアプリの開発に携わっていただけるアプリエンジニアの方を募集いたし…
週3日・4日・5日
660,000〜1,340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 /ネットワーク / 週4…
【案件概要】 WAN展開要員として自社サービスを含む製品の導入作業をお任せします。 また、PMが…
週4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / RubyonRails /…
保育施設向けICTサービス事業を行う勢いあるメガベンチャー企業にてのバックエンドエンジニアの募集にな…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Ruby・Java・Swift・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】サ…
・プロダクトデザインチームや関連システムの担当者とコラボレーションしサービス開発を担っていただける方…
週4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルスタック】美容医療関連のアプリケーシ…
技術面でチームをリードしていただき、技術課題のマネジメントや開発フローの整備など、様々な時間軸でチー…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | リードエンジニア |
| Ruby・Swift・Kotlin・Typescri… | |
定番
Unityエンジニア
スマートフォン向けソーシャルゲームの開発/運用業務となります。 Unityゲームの新規機能・機能改…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿確認 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
定番
【AWS / 週4日〜】不動産売却領域サー…
【お任せしたい業務】 デジタルトランスフォーメーション事業本部の開発基盤グループに所属して以下の業…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / ReactNativ…
【案件概要】 某大手カー用品企業にてリリースしているカスタマー向けアプリ(iPhone・Andro…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
【会社概要】 国内の大手企業や外資系企業を中心に、様々な企業に対して幅広いITサービスを提供してい…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| React.js | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【仕事内容】 ソーシャルゲームのUIデザイン制作業務を担当いただきます。 UI/UXデザイナーと…
週4日・5日
300,000〜480,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / AWS/Laravel /…
■案件の内容 仮想通貨の個人向け会計ソフトについて、プロダクトを安定的に稼働、成長させるために必要…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・Nuxt.js… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/WordPr…
【業務詳細】 会社HP、サービスサイト、求人サイトなど幅広いジャンルの案件に携われます。 ・コー…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア |
| PHP・Laravel・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Larave…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / RubyonRail…
今回、既存サービスの機能拡充と新規サービスの立ち上げにあたって開発チームのメンバーを募集します。 …
週5日
170,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails・Dj… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社はCM・Web映像・グラフィック・サイト構築・iPhone用アプリ・Webアプリなど、ビジュアル…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京阿佐ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
この度は事業の拡大に伴い、Unityエンジニアを募集いたします。 <募集背景> 事業拡大に…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| 【参考】 言語 :C#・・・JavaScript・… | |
定番
【WindowsServer,Java】某…
・既存システムへの追加開発・リリース対応 ・クレジットブランド会社とのシステム連携中継システム対応…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・WindowsServer、HULFT、J… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】自社H…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで様々なデザイン業務に携わりま…
週4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / Python/Git…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
220,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
当社は日本では誰も見たことのない新しいサービスを海外から輸入し、不動産業界の活性化をめざしてプロダク…
週5日
300,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグの調査および修…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築 ※P…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
大型サイトのリニューアルに伴いテストが始まるため、テストエンジニアとして人材を募集します。 モンキ…
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・【企… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】ゲ…
大人気ソーシャルゲームのUIデザイン業務です。 機能追加・改修をメインに、UI設計をお任せいたしま…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
◆お願いする業務 ・ECサイト構築・運用におけるHTML/CSSコーディングPC/SP版、またはレ…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【コーダー】医療・ヘルスケア事業のコーポレ…
【業務内容】 医療・ヘルスケアICT領域の事業を展開する企業で、コーポレートサイト、クリニックサイ…
週3日
250,000〜290,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
【PM】倉庫業務可視化・作業計画作成支援ツ…
【業務内容】 倉庫業務可視化・作業計画作成支援ツール開発の要件定義 【作業内容】 ・要件定…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java】ポイントシステムのエンハンス開…
WEBポイントシステムのエンハンス開発業務。 小規模・複数のシステム改修案件を、月次サイクルで…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・SAStru… | |
定番
【Java】 販売管理システム開発
既存システムとそのサブシステムに関連する保守運用、追加開発対応。 長期参画を前提としてお考えい…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 埼玉 さいたま新都心 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
【動画制作ディレクター】ニュース&エンタメ…
まずはサブディレクターとしてディレクターと共に様々な業務を担当してもらいます。 ゆくゆくはディレク…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅一丁目 |
|---|---|
| 役割 | 動画制作ディレクター(TIMELINE) |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件内容 一般的なWebJavaおよびAWSサーバレスアーキテクチャで構成されたシステムの運用要…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【動画制作ディレクター】ニュース&エンタメ…
まずはサブディレクターとしてディレクターと共に様々な業務を担当してもらいます。 ゆくゆくはディレク…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | ライブディレクター(TIMELINE) |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
◆案件概要 サーバーサイドとフロントエンドどちらもご対応頂ける方を募集します。 直近ではバックエ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
▼案件概要 本研究所の研究成果を公開するサービスにおける画像処理・処理システム構築のエンジニアを募…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・R・シェルスクリプト | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
■案件内容■ ・基地局の工程管理アプリの開発を行っていただきます。 ・工事業者が報告書をExce…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】大…
【案件内容】 バックエンドエンジニアとして、自社副業マッチングサービスにおけるバックエンド開発/保…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / サーバーサイド / …
◆業務内容 Oracle ERP Cloud運用業務 …
週5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL/VBA / 週4日…
DB移行時の自動検証ツールの担当をお願いします。 ※PL/SQL、VBA、シェル等を利用したツール…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| VBA・SQL | |
定番
【フルリモ / Node.js/TypeS…
【業務内容】 ・要件に応じたDB設計〜機能の実装 ・開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Unity・Firebase・GoogleAnaly… | |
定番
【フルリモ / PHP/Laravel /…
◆案件内容 教育系WEBサービスの開発に携わっていただきます。 新規機能追加や、既存機能の改修な…
週5日
2〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・PHP・RubyonRa… | |
定番
【リモート相談可 / SQL/VBA / …
【案件詳細】 資産管理アプリを使うユーザーの情報をデータベースから抽出し、様々な切り口で分析できる…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| VBA・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
【概要】 お任せするお仕事は、主に自社サイトの開発/保守/運用が中心になります。 また、新たにス…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回は、開発をリードいただけるテックリードを募集します。 ▼業務詳細 ・プロダクトのフロント…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Rub… | |
定番
【リモート相談可 / C#/Java / …
【案件概要】 道路交通システムの組込み機器向けテスト環境開発及び、保守管理アプリの開発をご担当いた…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
◇案件概要 キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 マイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
SaaS事業として、クライアント先のマーケティングDXを推進させるツールを自社内で開発・提供していま…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【リモート相談可 /Python / 週5…
【業務内容】 統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Typescript・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】自社事…
【主な仕事内容】 開発・分析業務の補佐していただきます。 - マスタデータ整備 - SQL…
週5日
570,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・Excel・JIRA・Notion | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【業務内容】 PHP/JavaScriptを使用し、受託開発の案件にご参画いただきます。 大手か…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄直方駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
▼案件内容 主に下記の業務に携わっていただきます。 ・スマホからの位置情報を取得してイベント処理…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【Java/C+ / 週5日】コンビニ向け…
【案件概要】 管理者がユーザ打合せ、仕様、テストのやり取りを行い、その指示にもとづき、 調査、仕…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C・C++・PL・SQL・スキル: ・j… | |
定番
【リモート相談可 / VRops/Vsph…
■業務内容■ ・銀行の仮想化基盤更改案件 ・設計構築業務 ・Vsphere、Vsanを利用した…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ /デザイナー / 週5日】EC…
▼案件概要 某ECサイトでの入稿作業をご担当いただきます。 ▼業務詳細 画像の編集は不要(…
週5日
260,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】某国…
■仕事内容 AI解析基盤(プラットフォーム)の新規システム構築をご対応いただきます。 ■担当…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・■基本スキル 基幹システム開発のご経験 … | |
定番
【フルリモ / Python/SQL / …
【業務内容】 ・医療機関との共同研究 ・解析用データベース構築とデータ解析 ・医療機器開発 …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・SQL・SciPy・【開発環境】 P… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/Swi…
<案件概要> ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週5日】N…
ネットワークシステムに関する維持管理・運用業務をご担当いただきます。 ▼業務詳細 ・ネットワ…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【UIデザイナー】スマホアプリ・SNS掲載…
◇案件概要 :UIデザイン、クリエイティブのデザイン、制作 アプリエンジニア側との各…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大崎 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / HTML5/JavaScr…
今回募集するポジションでは既存メディアおよび新規事業サービスの企画、コーディング全般をお任せします。…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】保険DX…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのUIデザイナーの募集になります。 ・保険事業会社向けの…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】オン…
■業務内容 ・新規サービスのシステム開発(メイン) ・商標登録を安心、カンタンにできるようにする…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
▼案件概要 iOS向け音声アプリの開発に関わっていただきます。 (順次Andoroidブラウザア…
週3日・4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / C++/Python / …
◇案件概要 どこでもだれとでも仕事ができるワークプレイスを提供することを目的としています。 …
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++・【必須スキル】 ・チーム… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
【業務内容】 コーディング業務をご担当いただける方を募集いたします。 デザイナーご経験をお持ちの…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
開発経験とスタートアップへの興味がある方を募集しています。 【仕事内容】 ・組織/人事領域の…
週3日・4日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
■募集内容 案件自体は運用フェーズですが、運用面での課題を解消しきれておらず、技術的/PM的な視点…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
▼案件概要 運用設計、運用テスト、訓練実施、運用保守業務をお任せします。 ▼業務内容 -運…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / CSS/HTML /…
この度、新たにWEB事業部を立ち上げることとなり、ご参画いただく方には、自社サイトの構築からクライア…
週3日・4日・5日
190,000〜260,000円/月
| 場所 | 東京23区以外立川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Javascrip…
このたび事業拡大に伴い、サロン向け顧客管理システム開発に携わっていただけるフルスタックエンジニアを募…
週3日・4日・5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸伊勢市駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【Java】ユニフォーム販売システムの機能…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Javaエンジニア】会計関連のシステム運…
【業務内容】 給与計算、請求周りは1機能あたりの開発スパンが長いので、企画側とも一緒になって仕様を…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
サーバーサイドエンジニア/Go
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Kotlin・Go・… | |
定番
【リモート可 / PM】自動発注システムパ…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週5日
970,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PMO】AIエンジン発注導入プロジェクト…
案件概要 :AIエンジン発注導入プロジェクトPMO支援 作業場所 :大崎(9:00 ~ 18…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大崎 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Java】ユニフォーム販売システムの機能…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【インフラ】大手通信会社の小規模案件対応に…
大手通信会社の小規模案件対応における各種システム開発対応 (AWS上に構築したシステムで顧客の…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / ABAP / 週5日】検索…
SAP ABAPを使用して検索アルゴリズム・検索システムの開発を遂行していただきます。 チャットフ…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Unity/C# / 週5…
ファンクラブアプリ内のゲーム開発案件になります。 Unity、C#でのゲーム開発経験のある方に非常…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
弊社で請け負っているWEB制作業務をご担当いただきます。 その他、WebサイトのUIやビジュアルを…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 群馬・栃木・茨城宇都宮駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・【使用ツール… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【業務内容】 ①と②のどちらか又は両方の開発案件に携わっていただきます。 ①発達児童の支援施設に…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大森駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
当社は北海道で仕事用品店やアパレルショップを運営する老舗企業です。 この度は、ECサイト運営の拡大…
週3日
90,000〜190,000円/月
| 場所 | 北海道:札幌新道東駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
主に下記の業務に携わっていただきます。 ①車載ECU向け基本ソフトウェアの開発(AUTOSAR仕様…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【PHP】大手小売業の基幹システム刷新にと…
大手小売業の基幹システム刷新にともなう開発案件。担当していただく領域は、受発注、貿易系の機能。
週3日・4日・5日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Linux(AWS) PHP shell… | |
定番
【Windows LinuxのOS SQL…
大手求人広告サイト運用・保守 ・求人広告サイトの運用(広告店舗、原稿・画像の削除) ・リリース資…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | SQLエンジニア |
| SQL・Linux Shell Oracle・1… | |
【CSS/JavaScript】産廃事業に…
<業務内容> 産廃事業に特化したIX支援フロントエンドエンジニアを募集します。 初期リリースが完…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Typescript・… | |
定番
【SAP SAP/PP】大手製造業向け会計…
精密機器メーカー様向けSAPグローバル展開案件(SAP/HANA導入支援)になります。 S4の…
週4日・5日
580,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(SAP/PP) |
| SAP・HANA | |
定番
バージョンアップに伴うデータ移行
某大手プラント会社の大型リプレイス案件です。 プリザーブ(PKG)の導入及びバージョンアップや、関…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・AWS | |
定番
[AIエンジニア]自然言語処理エンジンの研…
AIを活用した自然言語処理エンジンの研究開発です ・対象システムの自然言語処理エンジンの研究開発 …
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【Notes SharePoint】情シス…
エンドクライアント情シス担当様のサポートとして、システム開発の管理系業務をサポートする。 現在…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【データエンジニア(ETL)】 日本で最大…
弊社サービスを利用するにあたり、旧システムまたはExcel等で管理していたデータを、弊社サービスに投…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア(ETL) |
| 【開発環境】 Zoho・Excel | |
定番
【業務委託】Webディレクター
既存事業のグロース支援、中規模・大規模の受託案件に参画し、顧客体験設計、UI/UX設計のディレクショ…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| ‐ | |
定番
【WEBディレクター】大手ふるさと納税サイ…
大手ふるさと納税サイトにて、プロモーション企画やマーケティング施策において進行管理を業務サポートを行…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| ‐ | |
定番
【フロントエンドエンジニア】大手通信キャリ…
auウェルネスにおける下記業務をお願いします。 ・アプリの機能追加または改善 ・アプリflutt…
週5日
180,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【アートディレクター】運営する各メディアの…
複数メディアのアートディレクターとして業務を行っていただきます。 ■具体的な業務内容 ・各メ…
週3日・4日・5日
2〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | アートディレクター |
| Figma・Photoshop・illustrato… | |
定番
【英語人材】 Webサービスのプロジェクト…
AWS上で構築されているWebサービスのプロジェクト管理者。 サービスの要件管理/進捗管理/予算管…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM、PMO(英語) |
| PHP・SQL・・・ハードウェア:・Mac・・・Wi… | |
【Java】デリバリーサービスの配送管理シ…
新チームのSE枠となります。 案件リードをする元請企業のプロパーのもとで、要件定義をもとに設計以降…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Oracle MySQL Redis … | |
【Java SpringBoot(Spri…
大手情報サービス会社が提供するセルフオーダーサービスを、他社のPOSレジへ接続するシステム開発の案件…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Git・Github SpringBoo… | |
定番
【Java SpringBoot(Spri…
大手情報サービス会社が提供するセルフオーダーサービスの、サーバーサイド開発の案件です。 スクラムベ…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Git・Github SpringBoo… | |
【PM,Java】デリバリーサービス店舗管…
某有名フードデリバリーサービスにおける、店舗の方が使用するシステム開発チームのリーダーの募集です。 …
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・SpringBoot Spring | |
定番
【Java講師案件|2024年4月~6月】…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | IT研修講師 |
| Java・Spring・ | |
定番
【C#】ユニフォーム販売システムの機能改修…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【C#】ユニフォーム販売システムの機能改修…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【PM】重要プロジェクトのPM業務
開発組織のケイパビリティ、FourKeys等、各種データを計測・可視化・経営へのレポーティングまで、…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
インフラエンジニア(新製品開発)
新製品のWebシステムの開発(クラウドインフラ構築)に携わっていただきます。 勤務地:東京都江…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go・Typescript・SQL・NextJS | |
定番
社内SE募集
関わる全ての方のより良い人生をつくることを掲げています。 本案件では、社内SEとして、社内の困りご…
週5日
160,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| HTML・VBA・SQL | |
定番
【アプリエンジニア】上場化粧品会社の公式ア…
上場化粧品会社の公式アプリ開発(Android) 現在稼働中の案件に入っていただく流れ。 大元の…
週4日・5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | iOS/Androidエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【コーダー】新規Webページ作成・ディレク…
●運用業務 - 新規ページ作成や既存ページの修正 - HTMLやCSSの編集・作成が必要と…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS | |
【HTML/CSS/Typescript】…
◆主な業務内容 ・スポーツ関連Webサイトのデザイン制作 ・サイトのコーディング ・担当クライ…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【WEBデザイナー】自社サービスサイトを充…
■募集背景 事業拡大に伴い増員募集となります。 オペレーティングな業務のみではなく、 マーケテ…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Webデザイナー|フルリモート】受託案件…
【案件概要】 受託制作/開発事業を運営しており、主にWeb制作の案件を中心に受託しており、今回はW…
週5日
2万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
【Flutter】自社ニュースアプリの開発…
【業務内容】 ・Flutter でのニュースアプリの開発業務 ・アプリの新機能開発業務 ・機能…
週3日
350,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
定番
【Java】大手家電量販店向け開発支援
既存システムの改修、機能追加等 顧客とのやり取りや打ち合わせも発生いたします。 同顧客でのいくつ…
週5日
160,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・VB.NET | |
定番
【PM】オンライン学習サービスを運営してい…
【案件内容】 オンライン学習サービスを運営している企業でのPMを募集しております。 プロダクト企…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【週5/C#/フルリモ】ユニフォーム販売シ…
・既存のユニフォーム販売システムの機能改修、追加開発。 ・利用企業様ごとに制作した制服を注文しても…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【PHPエンジニア】大型ECサイト保守対応
【業務内容】 大型ECサイト保守対応をお願いいたします。 2-3日、1週間、1か月くらい掛か…
週4日・5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・CakePHP | |
定番
【TypeScript】マーケティング効率…
主な業務内容として、CSチームを通じてAutoStreamサービスをご利用いただくお客様へ、 技術…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
【Webディレクター】 サイト制作構築ディ…
・制作進行管理 ・品質管理 ・ベンダーコミュニケーション管理 ・クライアント定例への参加
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
定番
【ディレクター】「Aucfan.com」の…
作業内容 自社サービスのディレクションをお任せします。 具体的な作業は以下です。 ・要件定…
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| ・-・・ | |
定番
【ディレクター】「Aucfan.com」の…
自社で動画制作サービスの立ち上げ、グロースを考えており、運用含めてディレクションをおまかせしたい。 …
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEB/動画編集ディレクター |
| ・-・・- | |
定番
【PHP】大手不動産会社(コンシューマー)…
【会社概要】 品質管理とプロジェクト管理を強化し、 高品質なシステム開発のご要望にお応えすべく強…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・VB.NET | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】システム運用保…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつか…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| ・ | |
定番
【Node.js】ゲーム系サービス開発にお…
【案件概要】 受託をしているゲーム系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただ…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
【JavaScript/PHP】人材紹介会…
【会社概要】 品質管理とプロジェクト管理を強化し、 高品質なシステム開発のご要望にお応えすべく強…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京丸の内or豊洲 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・VB.NET | |
定番
【Java】大手流通決済後方システムの設計…
大手流通エンドユーザーの決済データ管理システムの改修。 対応工程:基本設計~詳細設計、製造、テスト…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・WebAPI・・tomcat・・Apach… | |
大手物流会社の物流&倉庫作業管理システム開…
【会社概要】 品質管理とプロジェクト管理を強化し、 高品質なシステム開発のご要望にお応えすべく強…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・VB.NET | |
定番
【ゲーム】ゲームアプリのウェブマーケティン…
【部署・企業について】 チーム:約40名 品質と生産性のいずれも大事にゲーム作りをしているチーム…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
【フルリモ / 週3~】フロントの開発以外…
弊社のメインサービスのフロントエンドの改善および機能追加の開発業務に取り組んでもらいます。 また、…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・or・Node.js | |
【フルリモ / 週3~】サーバーの開発以外…
弊社メインサービスのバックエンドの改善および機能追加の開発業務に取り組んでもらいます。 また、今後…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【HTML/CSS/Typescript】…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript | |
定番
【PM】自社サービスのプロジェクトマネージ…
グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先端の人口知能技術(AI)を用い…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Webマーケター|フルリモート・週2日~…
【案件概要】 全社のマーケティング部門にて、広告運用を中心としたマーケティング業務をお任せできる方…
週2日・3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
WEBサービスのプロジェクトマネージャー
本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者など、多くのチ…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可/運用保守/週5日】自社シ…
【業務内容】 自社システムの保守・運用業務を担っていただけるエンジニア様を募集いたします。 ※案…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・Java | |
定番
ゲーム開発企業でのデザイン案件(副業可)
【会社概要】 世界中で楽しまれるゲームタイトルを展開するグローバル・エンターテインメント分野のリー…
週3日・4日・5日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| PC(Windows・Mac)、Photoshop、… | |
定番
【GCP実務経験ある方向け】インフラエンジ…
<業務内容> ・ 新規クラウドログの取り込み ・Cloud Data Fusionパイプライン作…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Cloud・IAM・VPC・CloudSto… | |
定番
【運用/保守】自動車損保向けシステム増員募…
自動車向け損保システムの保守を行いながら、 追加テーマの設計〜リリースまで担当頂きます。 現在は…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 神奈川天王町 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【運用/保守】新サービス案件に伴う開発/及…
既存Webシステム(保険システム外部連携情報吸い上げの接続システム)の機能や運用の見直しを行っており…
週5日
670,000〜710,000円/月
| 場所 | 品川リモート |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・SQL | |
【マーケター】募集プロモーションにおけるマ…
【業務概要】 人員の募集強化に伴い、募集プロモーション実施したく、企画の立案から 実行まで一緒に…
週1日・2日
160,000〜230,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【COBOL】 経費システム/次期経費シス…
【業務内容】 経費システム 次期経費システム対応 【環境】 MicroFocusCOBOL…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 / 高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | COBOLエンジニア |
| COBOL | |
定番
【PHP】IDaaS関連プロダクトの開発業…
◇案件概要: 自社でIDaaS関連のプロダクトを開発しており、PHPでのご経験をお持ちの方を募集…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【Java,Kotlin】チケットアプリの…
アプリと外部ハードの連携 【勤務地】白金高輪(リモート併用※頻度応相談) 【期間】即日~※相談可
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・ー | |
定番
AIソーシャルゲームのサーバーサイドエンジ…
AIソーシャルゲームのサーバーサイドエンジニア 【勤務地】都庁前 ※基本はフルリモート 【勤務時…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHPUnit | |
定番
ソーシャルゲーム サーバーサイド開発
ソーシャルゲーム サーバーサイドエンジニア 【勤務地】都庁前 【時間】10:00~19:00 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Perl | |
定番
オンラインアルバムサービス向けコーディング…
・コーディング業務(メイン) ・Webデザイン業務 【期間】即日or10月 【勤務地】渋谷…
週3日・4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
GA4を用いた社内、エンドクライアント様対…
GA4のデータを取得してそれを基盤に開発している。 人材としては、お客様へ改善策等の対応方法をお伝…
週3日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| ー | |
定番
【PM】アジャイル開発プロジェクトにおける…
顧客のドメイン(UX、市場、ユーザーニーズ、ビジネスプラン)や今後実現したいことを理解し、最適なソリ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【Python】研究開発プロジェクトにおけ…
【業務内容】 研究開発プロジェクトにおいて対話システムを開発しております。 Pythonでの対話…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 東北:仙台五橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【PM】プロジェクト責任者
【業務内容】 プロジェクトマネージャーとして、DevOps・データモダナイゼーション・アジャイル・…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【コーダー】資格取得講座サイトのコーディン…
資格取得講座サイトの全面リニューアルの案件にご参画いただきます。 【業務詳細】 ◆メイン業務 …
週5日
230,000〜300,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【Typescript】大手企業でのWeb…
■案件概要 インプットデータを元に計算をするwebシステム (詳細は面談にて口頭で説明させて頂き…
週1日・2日・3日・4日・5日
1,010,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Typescript) |
| Typescript・React | |
定番
【Go】報道テクノロジーベンチャーの自社サ…
▽具体的には ・Goを使ったAPI、Webアプリケーションの設計、開発、運用 ・GCPを利用した…
週5日
670,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GraphQL・Next.js | |
定番
【運用/保守】保険相談サービス企業のWeb…
Webシステムの機能改修、及びサイト運営保守の対応 社内の開発業務における技術的なサポート作業 …
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Laravel・CakePHP | |
【React/Vue】新卒の学生向けサービ…
急成長中の勢いのあるベンチャー企業で、 開発業務に携わっていただける人材を募集しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React Vue | |
【Go/Ruby】中途採用向けサービスのサ…
急成長中の勢いのあるベンチャー企業で、 開発業務に携わっていただける人材を募集しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | 【サーバーサイドエンジニア】中途採用向けサービス(Liiga) |
| Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】若手実力…
主にGo/GraphQLを使った設計、開発、運用をご担当いただきます。 企画レイヤーにも携わること…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Typ… | |
【フロントエンドエンジニア】金融系サービス…
【企業概要】 金融サービスを行うクライアントを対象にしたクラウドインフラの構築を行う企業になります…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【3Dデザイナー】3DCGでシーン内を演出…
▼概要 リアルタイムに描画される3DCGでシーン内を演出するエフェクト等を制作していただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | 3Dデザイナー |
定番
宿泊予約サイトの広告プランニング・コンサル…
全国旅行割の開催期間中に様々な広告宣伝を実施したいと考えています 十分な広告ディレクションが行えて…
週2日・3日・4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケティング責任者 |
| ー | |
【React/Vue】フィンテック企業にお…
【企業概要】 オルタナティブデータや投資に関する網羅的なサービスを提供する企業。 【業務内容】 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PM】フィンテック系上場企業におけるプロ…
【業務内容】 ・次世代型デジタル保険サービスの設計、開発、運用にかかるPM ・業務チームとエンジ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【週5/PHP/フルリモ】社内向けWEBシ…
【会社概要】 Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・データ放送コンテンツ等の制作・開…
週5日
1.6〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【マネージャー候補】フィンテック企業におけ…
【業務に内容】 証券・保険・金融サービスを行う企業にて以下の業務をご対応頂きます。 ・品質向上の…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ・Amazon・Web・Services ・Ter… | |
定番
【リモート可 / React / 週5日】…
開発中のFinTechサービスにおける、Webフロントエンドエンジニア(React)を募集しています…
週5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| JavaScript・React | |
定番
【Webディレクター|フルリモ・週3日~】…
受託Webサイト制作案件を担当していただくWEBディレクターを募集いたします。 【業務内容】 …
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | webディレクター |
定番
【週5/PHP/リモート相談可】ECサイト…
【会社概要】 東海地区のクライアントを中心に、Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・…
週5日
1.6〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【AWS/Python】データアナリスト(…
【業務内容】 1.AWS、Pythonを利用した運用システムの構築・データ分析・DB構築 2.定…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・AWS | |
定番
【Python】データ基盤エンジニア(デー…
【業務内容】 ・様々なオルタナティブデータを効率よく管理・提供できるデータ基盤の設計、構築、運用 …
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・SQL・AWS | |
定番
【Java/Go/Scala等】サーバーサ…
【業務内容】 ・プロダクトの要件定義/仕様作成/工数見積 ・システム設計 ・サーバーサイド実装…
週5日
500,000〜800,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・Scala・AWS | |
定番
【Unreal Engine 4/Unit…
【業務内容】 Unreal Engine 4/Unity上でのエフェクトの作成、モデリング、テクス…
週4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| ー | |
定番
【週4,5日&一部リモートOK】太陽光発電…
【具体的な仕事内容】 ・プロダクトやプロジェクトの立ち上げ、推進、終結 …
週4日・5日
390,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
フロントエンドエンジニア
- プロダクト概要:microCMSで管理している記事コンテンツを扱うWebメディア - 業務内容…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿確認 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・-・フロ… | |
定番
【プロダクトマネージャー】金融系Saasの…
金融事業者向けの新規Saasの開発における、プロダクトの企画、ロードマップの策定に携わっていただきま…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【システムエンジニア】金融系Saasのシス…
■業務内容: システムエンジニアとして弊社システム開発業務に携わっていただきます。 ご経験により…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・- | |
定番
【Go,TypeScript】金融系Saa…
■業務内容: エンタープライズ向けに提供している弊社Saas導入プロジェクトのシステム開発担当者を…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・Go・Typescript・Rea… | |
定番
【データエンジニア】自社システムツール開発…
・ツール開発(EXCEL、ETLツール、SQLなど) ・基幹システム保守(障害調査、問い合わせ…
週2日・3日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・ー | |
定番
【Python】自社システムのサーバーサイ…
<業務一例> ・プロダクトマイルストンの実現に必要なアーキテクチャの設計 ・PdMと伴走しながら…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿護国寺駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
注目
[サーバーサイドエンジニア]小売業向けシス…
【業務内容】 小売業クライアントにおいて保守運用業務を実施していますが、オンサイト業務の補強を検討…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【Tableau】事業戦略、財務管理
経営(事業)企画を実施しており、担当内での人材増強を予定しております。 主に事業戦略、財務管理で社…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【JavaScript】大手通信会社の運営…
大手通信会社の運営するWEBコンテンツ内新規開発となります。 詳細は可能な範囲で面談にてお伝えいた…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【RPA】受託案件の業務効率化
【企業情報】 人材系の上場企業を親会社に持ち、官公庁や金融機関、小売業者を中心としたクライアントの…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 池袋池袋 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
| VBA | |
【PHP】Webシステム開発・Webアプリ…
受託開発の業務全般や新規事業立ち上げのためのWebサービスの開発をお願いします。 Webに特化した…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【データベースエンジニア】OracleDB…
データベースエンジニア(Oracle設計・構築・運用・保守)として 既存のDBAチームにご参画頂き…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
定番
【PM・PMO】PM・PMO業務
PM・PMOとしてご活躍いただける方を募集いたします。 ※業務内容の詳細はご面談時に企業様からご説…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM・PMO |
定番
【スマホアプリエンジニア】Flutterを…
【案件概要】 大手人材サービスのtoC向けモバイルアプリ開発になります。 既存アプリの機能改善・…
週4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【ライター】オウンドメディアのWEBライテ…
【具体的な業務】 オウンドメディアにおけるコンテンツ配信に関する、 ・企画 ・執筆依頼(外注管…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 品川馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBライター |
【バックエンドエンジニア】新卒の学生向けサ…
急成長中の勢いのあるベンチャー企業で、 開発業務に携わっていただける人材を募集しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | 【バックエンドエンジニア】新卒の学生向けサービス(外資就活ドットコム) |
| Go・React・Next.js | |
定番
Webデザイナー(コーディングも可能な方)
【案件について】 ・受託制作/開発事業を運営中 ・Web制作の案件を中心に受託(Webサイト、L…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Javaエンジニア】自社サービス エンハ…
■業務内容: ・Javaを用いたアプリケーション/API開発 ・プロダクト機能設計 ・既存機能…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・JSP・Servlet・・Post… | |
定番
【JavaScript|週2~OK】"自立…
"自立自走型" のテクノロジー人材を輩出するためのIT人材育成プログラムを講師として運営していただき…
週1日・2日・3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件毎に異なります |
|---|---|
| 役割 | JavaScript講師 |
| JavaScript | |
定番
【Ruby on Rails/リモート】大…
願書出願サービスの継続開発 作業内容としては以下です。 - 新機能開発 - リファクタリング …
週4日・5日
580,000〜6,770,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| CSS・JavaScript・Ruby・Rubyon… | |
定番
小売業界向けLINEミニアプリ開発【フロン…
小売や自治体など、様々なクライアントに対して会員システムやプリペイド、クーポン、商品券などの機能をL…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Typescript・… | |
定番
【WordPressエンジニア】Webサイ…
卸売関連企業:アパレル素材の卸を生業としている企業サイトの運用保守・新規サイト作成 漁業関連企業:…
週3日・4日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・ー | |
定番
【UI/UXデザイナー募集】アルバイト向け…
【サービス】 アルバイト向けの採用サービスやシフト管理サービスを開発・提供。 様々な企業から出資…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Figma・… | |
定番
【Python SQL】データアナリスト
・アカウント個別の分析・施策企画・効果検証 ・アカウント横断での改善のためのKPI設計・運用企画・…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・SQL・AWS(Athena・Glue… | |
定番
【PHPエンジニア】VMインスタンス構成か…
【業務内容】 VMインスタンス構成からのサーバレス化の設計 【背景】 GCPサービス選定と…
週1日・2日・3日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Python | |
【地方案件・リモート可】WEBサイトのディ…
【企業概要】 長野県内に本社を置くウェブ系制作会社になります。 県内の顧客向けにウェブサイトの制…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 東北:仙台滋野 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PM/PdM】小売業界のBtoBtoC向…
・店舗運営企業の集客・売上の向上支援 ・ネイティブアプリやLINEアプリの事業課題提案 【勤務地…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PM / PdM |
| AndroidJava・Kotlin・ー | |
急募
【急募:メールマーケティング構築】外国人向…
【具体的な業務】 サイトの登録者に対して、ユーザーのアクティブ利用率向上を目的として メール施策…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
【Salesforceエンジニア】外国人向…
【企業】 外国人向け仕事マッチングサービスを行う企業になります。 【業務内容】 現在使っている…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
| Apex | |
定番
【UI/UXデザイナー】一般社会人向け教育…
toB/toC向けオンライン教育プラットフォームのWebシステム開発プロジェクトです。 動画教材の…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【PHP|60代以上活躍中!】自社サイトの…
【案件内容】 ・自社サイト(教育関連)の追加機能の改修等 ※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます…
週5日
250,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【kotlin/Android】スマホ故障…
スマホ故障診断アプリの継続改修 アジャイル開発 具体業務内容:設計~ST 就業時間: 9:…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・ー | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 運用チームの一員として、Webアプリケーションの保守・運用を行っていただきます。 …
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Kuebrenets・Kafka・Datadog・具… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
この度は、ゲームコンテンツ開発・運営事業において、 SNSゲームの開発に向けた3DCGデザイナーの…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender・Unity・▼担当範囲 ・アバター… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】所属…
【案件概要】 所属ライバー向けのデータ可視化webツールの開発と新規機能の追加をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript/Vu…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js・N… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
iOS/Androidアプリ・Webでの総合的・横断的なUI/UXデザインをリード頂ける方を募集して…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
■HR領域でクライアント向けサービス ・サイトのデザインを担当いただきます。 ・プランナー、ディ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・※一部コーデ… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
■HR領域でクライアント向けサービス ・サイトのデザインを担当いただきます。 ・プランナー、ディ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| AdobeXd・sympli(デザイン共有ツール) … | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】自…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】自…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C#・【開発工程】 ・要件定… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計、PoC、製…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにサーバーサイドエンジニアとして関わってい…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・N… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
◇業務概要 以下の業務に携わっていただきます。 -担当範囲は、システム要求定義から開発、テスト…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
toB、toC両方で運営するオンラインマッチングサービスの拡大に伴い、Rubyエンジニアを募集してい…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
【業務内容】 ケアマネジャー向けのコミュニティサイトのフルリニューアルPJに参画いただきます。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
モノの買取事業を展開する上場企業グループにて、アドバイザリーチャットボット開発を担えるエンジニアリン…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・C#・CakePHP・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】上場…
テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプリ、システム等…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / C++/Python…
▼業務内容 -次世代ゲーム機の画像処理関連の開発業務。 -カメラから入力された画像を、ディープラ…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
①弊社作成のライティング原稿に沿ったLPのデザイン・コーディング ②クリエイティブ素材各種の作成 …
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
オンラインクレーンゲームシステム開発に従事していただけるサーバーサイドエンジニアを募集致します。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
SAP導入に向けてはベンダーに入ってもらっていますが、既存サービスの改良・連携も発生するため、下記業…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure(想定) | |
定番
【週5/フルリモ/Java】キャリア系WE…
■内 容: ・伝送システムのWEBアプリの追加機能開発を行っていただきます。 ・現在30~35名…
週5日
1.6〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
【案件概要】 オリジナル化粧品・美容雑貨などを企画・販売しているメーカーです。 自社製品のWEB…
週5日
130,000〜150,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務内容】 弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Spring・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / UX / 週4日〜】…
【業務内容】 新規AIプロダクトや機能開発にあたってのエクスペリエンスデザインがミッションです。 …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、広告デザインから…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Native・Ne… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】リプ…
■業務内容 ・レガシーなLAMP構成の現在のECサイトとCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生産…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
【業務内容】 フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・f… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
【業務内容】 ヘルスケア音声ガイドアプリマーケティングやWEB制作など、幅広く関連事業を行っている…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
▼案件概要 統計分析の技術を用いてオフライン、オンラインの広告/販促効果を最適化するソフトウェア開…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
▼案件概要 統計分析の技術を用いてオフライン、オンラインの広告/販促効果を最適化するソフトウェアを…
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】AWS基盤移⾏保守…
◇業務詳細 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・某⾦融系顧客向けオンプレ→AWS基盤への移⾏…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
対象システム概要: ・各ロボットとエンドユーザ向けインターフェイスとの間で情報コントロールするマネ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【C/C++ /週5日】自社ソフトウェア製…
【概要】 以下の業務をご担当いただきます。 -弊社製OS(eMCOS AUTOSAR)のテスト作…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
【企業紹介】 テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアントから請け負っているECサイト構築のフロントエンド開発を担当いただきます。 業務内容とし…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
外国籍の方向けの新規アプリ内の追加アプリ開発チームの立ち上げを担当者とともに進めていただきます。 …
週3日・4日・5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週4日〜…
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
AWSを用いて、言語処理基盤、機械学習基盤等のデータ基盤を開発をご担当いただきます。 【案件の…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java,Pytho…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
大手通信会社の共通ポイント事業部署におけるデータ分析、ご提案、Excelデータを分析していただき、結…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VB.NET・VBA | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
【案件内容】 社内の複数サービスが抱えるユーザを統合し、データの蓄積及び、 検索が可能なデータ基…
週4日・5日
410,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】行…
自社サービスである行政ビッグデータと行動科学を応用した公的通知サービスをリニューアルしていくプロジェ…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Python/Django…
当初はコンサルティングサービスから始まりましたが顧客ファーストの姿勢から評価され、拡大してまいりまし…
週4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】社…
社内他部署と連携してプロダクトのUIデザインをご担当いただきます。 【業務概要】 ・プロダク…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】V…
バーチャルライブの基盤となるシステム開発からモバイルアプリケーション開発、演出制作などクライアント開…
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】医療…
業界全体における就労人口不足にテコ入れをし、全国の地域福祉インフラを支えていくために、これまで10万…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / GraphQL / 週3日…
【会社概要】 デザイン思考とUXデザインを駆使した新規サービスの企画・既存プロダクトの改善や、AI…
週3日・4日・5日
500,000〜730,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・React・Express・G… | |
定番
【フルリモ / Java/MQ / 週5日…
▽業務内容 官公庁向けのシステムを一部リプレースします。 MQで汎用系システムやオープン系シ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにて、デザイン業務に携わっていた…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務詳細】 アプリケーションを強化するためのアーキテクチャー及びアプリケーションを指定期日内に計…
週5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
この度は日本での「S2b2C」モデルのECサイト立ち上げにあたり、 UI/UXデザイナーを募集いた…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 池袋新大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Angular/Vue /…
弊社の事業におけるフロントエンド開発をメインに担当いただきます。 デザイナーと会話をして最終的なデ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
この度、新規事業の立ち上げにあたりwebサービスの要件定義とプロジェクトマネジメントを担当していただ…
週3日・4日・5日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
▼案件概要 弊社はイベント情報比較検索サービスをメインに運営するベンチャー企業です。 この度…
週3日・4日
220,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
▼案件概要 この度、新規事業の立ち上げにあたり、webサービスの要件定義とプロジェクトマネジメント…
週3日・4日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
この度社内システムの再構築に向けたエンジニア様を募集いたします。 現在テレビのCM枠を取って自…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
世界初の特許技術を使用した自社ソリューションに関連したAndroid・SDK並びにアプリの設計・開発…
週4日・5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】法律×…
弁護士事務所向けの案件管理システムや弁護士用広告メディアの運営を行っている企業です。 【案件概…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】国際…
業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者がデジタル…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
私たちは、業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
私たちは、業界構造を改革する物流業界のテクノロジーカンパニーです。 国際物流に関わるあらゆる事業者…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
現在既存社員でベトナム人WEBデザイナーがおり、ベトナムチームと日本チームのブリッジ業務を行っていま…
週4日・5日
280,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
システムを支えるAPIプラットフォームの拡充、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
Androidエンジニアの方には、プラットフォームの上で、新サービス開発・他社サービスとのアライアン…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
サーバサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発や、インフラ設計・保守な…
週4日・5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
【案件内容】 モバイルアプリの開発において、技術選定から設計・開発・運用までをリードいただきますの…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Flutter・ReactNa… | |
定番
【リモート相談可 / Python/AWS…
ネイル情報サービスのWEBエンジニア兼AWS運用エンジニアを募集しております。 <<業務内容>…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ネイル情報サービスのWEBエンジニアを募集しております。 <<業務内容>> ・ネイルサービス…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
アプリもWEBもあるネイル情報サービスのUI/UXデザイナーを募集しております。 <<業務内容…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Photoshop/Ill…
この度は生徒数の増加に伴い、生徒からの壁打ち依頼や成果物の添削をご担当いただける講師の方を募集いたし…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
この度は新規Wi-Fi事業の推進にあたり、各自治体への高速Wi-Fi設置に向けた設計を担っていただけ…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
弊社は急拡大の投資フェーズにおりますが、事業課題の解決及び更なる成長を遂げていきたく、新規事業企画を…
週4日・5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
▼案件概要 当社の研究開発部門にて、全文検索システムに関わる研究開発をお願いします。 当社で…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
オンプレからAWS移行における以下の内容をご担当いただきます。 ・環境調査 ・検証 ・移行計画…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
広告配信プラットフォーム及びメディア向けレポート一元化ツールWebアプリケーションのフロントエンド開…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Pyt…
【案件概要】 弊社は、AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーで…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
【業務内容】 クライアント先での新卒研修の講師をご担当いただきます。 ※各プロジェクト先に…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
私たちは経営コンサルティングを中心に、コンサル会社向けソリューション開発、M&Aアドバイザリー、CV…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【Linux / 週5日】官公庁向けシステ…
◇ 業務概要 ①プロキシサーバ移行業務 Linux(RHEL)技術者 プロキシ:In…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】データ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながら、 データベー…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを誇っています。 …
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】OracleでのD…
当社サービスはOracle基盤で構築していますが、 大型案件の開始に伴い、Oracleからクラウド…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 開発経験豊かなテッ…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Angular/Azure…
■業務概要 当社サービスの主にフロントエンドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Django… | |
定番
【フルリモ / Python/Azure …
当社サービスの主にフサーバーサイドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用しております…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・DjangoRESTframework | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◆業務詳細 顧客で契約しているデータセンター廃止にともない、データセンターに設置しているネットワー…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにデザイナーとして関わっていただける方を募…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
▼案件概要 情報共有ツールの開発・運営を行うスタートアップです。 今までコストをかけずにステ…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
私たちは、情報共有ツールの開発・運営を行うスタートアップです。 今までコストをかけずにステルス…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・₋ | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
【案件概要】 今回の募集では、賃貸物件の家賃債務保証を行う事業部にて新規WEBサイト制作や新規シス…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅/水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Nuxt.js・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】急成…
ユーザー数560万人の経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 ▼主な業務 ・…
週5日
520,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / C++/PHP / …
新しい知識、情熱、考え方を持ったゲームエンジニア人材を募集しております。 ▼業務一例 ・キャ…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとしてサー…
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| MariaDB・Mysql・Bash | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
■案件詳細 新規IoT開発案件において、AndroidTV向けアプリケーション開発を行います。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【フルリモ / Vue.js/React …
■業務内容 本ポジションでは、当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのフロントエンド開発を…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】地域…
◆主な業務内容 地域共通ポイント事業を中心としたスマートフォンアプリの開発 ※希望に応じて、運用…
週3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・◆使用技術 ・R… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
下記三つの事業を展開しております。 クラウドインテグレーション事業 データ分析サービス事業 …
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフルスタックエンジ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
フィットネスアパレルの販売を行う会社です。 販売ルートとして店舗とECサイトの2つを持っています。…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週4日〜】…
今回は弊社でご活躍いただけるUI/UXデザイナーの方を1名募集いたします。 (主な業務内容) …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【リモート相談可 / Laravel/Vu…
今回は弊社のWebアプリケーション開発にご協力いただけますエンジニアの方を募集いたします。 主に運…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】契…
自社開発を行っております契約書レビュープラットフォームを、今後さらに多くのユーザーに使っていただくた…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / React/Node / …
旅行商品検索プラットフォームの開発です。 今回は、大手・中堅旅行会社向けの旅行商品検索プラットフォ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
リーガルテック領域のサービス開発に携わっていただきます。 社員とともに幅広く裁量を持ってお任せ…
週3日・4日
520,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / C++/Java /…
主に下記の業務に携わっていただく想定です。 - 通信モジュール機能追加およびメンテナンス。 -A…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】ア…
【業務詳細】 -プロダクトオーナーから提示される仕様のレビューやフィードバック -テスト設計およ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながらインフラの検討及…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
◆業務内容 -医療機器向けのPFにOSのポーティングがメインです。 -お客様の方で環境の導入済み…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】Mi…
この度は事業の拡大に伴い、データエンジニアを募集いたします。 <募集背景> 事業拡大に伴う体…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】Mi…
この度は事業の拡大に伴い、インフラエンジニア(システム運用)を募集いたします。 <募集背景> …
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / C#/.Net / 週3日…
事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 昨年ローンチしたバーチャルイベントをはじめ、ヘ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / Python/C#/ 週3…
【募集背景】 事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 <本案件₋業務内容> 現…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C#・Azure | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
人事データを活用するための開発プロジェクトでのデータエンジニアを募集しております。 大きくは、経営…
週3日・4日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Python・SQL | |
定番
【C/C++ / 週5日】無線通信装置向け…
無線通信装置のIC制御に必要となるプログラムの実装および、動作確認の実施をご担当いただきます。 …
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小金井駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・・- | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
▼案件概要 この度は事業の拡大に伴い、フロントエンジニアを募集いたします。 現在進行中のバーチャ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
【案件】 大手ToC向けのAndroidアプリの開発・保守を担っていただけるエンジニアの方を1名募…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿自由が丘駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】ボデ…
【企業情報】 私たちグループはヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開…
週5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
Webアプリケーション開発にご協力いただくエンジニアを募集します。 (主な業務内容と作業範囲)…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
Google Cloudを用いた以下のいずれかの基盤の設計・構築・運用に携わっていただける方を募集い…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 新卒向け就業支援サービスを展開している企業内でのデザイン業務です。 Wordpre…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
デモ用Webアプリケーション及びバックエンドAPIの作成支援です。 企画含めてプロトタイプ案件…
週5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / C++ / 週3日〜】3D…
【業務内容】 上場企業向けにAIや数理アルゴリズム等の科学技術を提供している会社です。 今回は物…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Java …
▽案件概要 ペット関連のWebサービスの改修、新機能開発案件です。 今回は、外部ベンダーで開発し…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 現在、ベータテストを終了し、リリースに向けて…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】国…
国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 現在、ベータテストを終了し、リリースに向けて…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
▼案件内容 - アサインされたPJにおけるサーバサイド部分の調査・検証・設計・実装。 - 比較的…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Nginx・AWS・Docker | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週4日〜…
【業務詳細】 スマートフォンアプリベースのSFAのiOS開発の機能開発をお願いします。 【稼…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Ob-C・Nginx・AWS・Docker | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
【業務詳細】 スマートフォンアプリベースのSFAのAndroid開発の機能開発をお任せします。 …
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Nginx・AWS・Dock… | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
ライブコマースサービスのデザイン業務をご担当いただきます。 具体的には下記のような業務をお任せ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【C#/ 週5日】自動車メーカ・重量管理管…
▼案件概要 自動車メーカ・重量管理管理システムの開発業務になります。 重量管理システムの詳細設計…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】ク…
■クラウド型オープンイノベーション支援サービスのバックエンド開発をお任せします。 【具体的には…
週4日・5日
500,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】ク…
■クラウド型オープンイノベーション支援サービスのバックエンド開発をお任せしたいと思います。 【…
週4日・5日
500,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
■案件概要: ヘルスケアのスマホアプリ保守業務をお願いします。 ◇具体的な作業 ・既存不具…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【QA/テスター】国内初プラットフォーム型…
【業務内容】 セルフオーダーシステムにおけるテスト業務をお任せいたします。 WEBサービス、…
週4日・5日
1.6〜2.4万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週4…
【業務内容】 現在3名のWEBデザインチームにてクライアント要望をもとにしたWEBデザイン制作に携…
週4日・5日
150,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿広島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / セキュリティ / 週…
急速に拡大していく事業に対して、様々なセキュリティの対応を行っていかなければならないと考えおり、すで…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / Python,Java /…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計/製品サポート …
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】E…
商品へのアクセスや購入データをもとに、商品企画を高速で回せる分析基盤を作ったり、仕入れ用の需要予測や…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北与野駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【Python|週1日~OK】"自立自走型…
"自立自走型" のテクノロジー人材を輩出するためのIT人材育成プログラムを講師として運営していただき…
週1日・2日・3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件によって異なる |
|---|---|
| 役割 | 講師(基本情報技術者試験内の基本的な内容のサブ講師登壇) |
| Python・Python・Java・Excel・P… | |
定番
【Python】機械学習を用いたAIエンジ…
【業務内容】 ・機械学習に関連する応用研究開発 ・機械学習に関連するソフトウェア開発 など
週3日・4日・5日
1,010,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・PyTorch・HuggingFace… | |
定番
【Ruby】自社サービスのSaaS開発
サービス本体の開発に加え、サービス運営に必要な管理画面など各種プロダクトのサーバーサイド開発を担当し…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・RubyonRails | |
定番
【React / フルリモート】保険DXの…
# 現状の開発対象 - ユーザー向けのwebアプリケーション - 保険商品のランディング…
週3日・4日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
大手総合商社子会社のスタートアップ ECサ…
・在庫管理システムや社内ツールの管理画面構築 ・社外で利用される EC や買取アプリ等の画面構築 …
週2日・3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【Python】大手総合商社DX開発エンジ…
・ソフトウェアの要件整理/設計/開発/運用/管理 ・実証実験用のデジタル技術選定 【期 間】…
週5日
3.2〜4.9万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【Ruby】保育/教育業界のDXサービス開…
家族のための新しい社会インフラを創造をめざす、 保育施設向けICTサービス事業を行う勢いあるメガベ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【PdM】保育/教育業界のDXサービス開発…
家族のための新しい社会インフラを創造をめざす、 保育施設向けICTサービス事業を行う勢いあるメガベ…
週5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java】バックオフィス改善SaaSの開…
支出の見える化、見積の取得、購買、契約管理、支払・請求などの機能をオールインワンでもつSaaSの開発…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Typescript | |
定番
物流DX BIエンジニア データベースエン…
物流DX会社におけるデータ設計及びBIツールの選定/導入を行っていただきます 【期 間】4月~…
週1日・2日・3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript | |
定番
【Ruby/フルリモート】オンライン契約締…
オンライン契約締結管理サービスの主にバックエンドエンジニアをお任せします。 具体的には… ・…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
«フルリモート»オンライン契約締結管理SR…
オンライン契約締結管理サービスの主にSRE業務をお任せします。 【期 間】即日〜中長期 【勤…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| - | |
定番
【TypeScript ソフトウェアエンジ…
保険の申込・請求などお客様とのインターフェースを自由に作り出せるSaaS開発 Vertical S…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・NestJS・Nextjs | |
定番
某大手求人媒体の社内DX部署にてエンジニア…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・SQL・Vue・React | |
定番
海外旅行のDX事業(サービス開発)のiOS…
マーケットのDX化の推進いただける方を募集します。これまでの海外旅行サービスにはないネイティブアプリ…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Typescript・Sw… | |
定番
大型調達済み マーケティングスタートアップ…
・広告効果を推定するための統計手法や、広告予算配分最適化のための数理最適化手法を開発する ・社内の…
週3日・4日・5日
1.6万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモート】Ruby on Rails…
■楽天ポイント連携機能の拡充 ■サーバーレス/コンテナ基盤へのシステム刷新 ■顧客情報基盤のため…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails・Laravel・Django | |
定番
【フルリモートOK/PM】新規バーティカル…
社内外のステークホルダーを巻き込んで、開発プロジェクトのマネジメント・調整をリードしていただきます。…
週3日・4日・5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby・Java・C# | |
定番
【コンサルタント】注目ベンチャー企業様での…
【業務詳細】 お客様はエンタープライズ企業が中心です。お客様に対して、 機能改善に関するご要望を…
週3日・4日・5日
840,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント |
定番
【リモート併用OK/プロジェクトマネージャ…
・プロジェクトマネジメント - 要件及び仕様について、社内調整及びプロジェクトの推進 - 開発案…
週5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート併用OK/iOSエンジニア】サー…
・iOSにおける、ネイティブスマホアプリケーションの開発 ・バックエンドチームと連携したI/F設計…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート併用OK/Androidエンジニ…
・Androidにおける、ネイティブスマホアプリケーションの開発 ・バックエンドチームと連携したI…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート併用OK/リードエンジニア】サー…
・ネイティブスマホアプリケーションのリード開発 ・アプリのUI/UX機能向上 ・アプリの性能改善…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモートOK/バックエンドエンジニア…
請求書や領収証などの証憑管理ストレージサービスへの機能追加、エンハンス&保守運用を行っていただきます…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモート/フロントエンド】関連事業の…
既存ECシステムにポイント機能や顧客ロイヤルティ機能などを追加実装 【期 間】即日 【勤務地…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモート/バックエンド】関連事業のE…
既存ECシステムにポイント機能や顧客ロイヤルティ機能などを追加実装 【期 間】即日 【勤務地…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモート/バックエンド】物流DX S…
運送業務管理支援システムのバックエンド開発 【期 間】即日 【勤務地】フルリモート 【時 …
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモート】バックエンドエンジニア/全…
・実装仕様の策定 ・REST APIのエンドポイント設計 ・データベース設計 ・PHP・Lar…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモート/バックエンド】外部交通事業…
外部交通事業者とのAPI連携プロジェクトのバックエンド開発 【期 間】即日 【勤務地】フルリ…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
フルリモート/レジャー業界向けサービス開発…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモートOK】福祉事業所向けのSaa…
新規機能開発における設計・実装を中心に、特にバックエンド開発 【勤務地】フルリモート 【時 …
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Kotlin/Java】ビジネスニュース…
UIの設計と実装、バグの特定と修正、メンテナンス性向上のためのリファクタリング 【期 間】即日…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモートOK】プロジェクトの技術的な…
営業担当者とともにクライアントとの交渉、商談成立後の営業・技術部門への橋渡し、納品後のクライアントフ…
週3日・4日・5日
1.6万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | セールスエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモートOK/フロントエンドエンジニ…
●ユーザー向けWebアプリケーションの開発・運用・改修 ○TypeScriptでの開発、テストな…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモートOK】保険DXベンチャーのモ…
APIやスマホセンサーとの連携、商品や機能追加、UX改善を行っていただきます。 【期 間】即日…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
感動体験サービスのWEBアプリ開発(QAリ…
感動体験サービスのWEBアプリ開発の案件となります。 体験ツアーを購入したユーザーが撮影ポイントを…
週5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| ー | |
定番
建設機械向けのマネージメントシステム(アプ…
・建機向けのマネージメントシステムのPoC開発を行なっており、WEBアプリケーションを現地ディラー様…
週5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| AWS | |
定番
【Swift/Kotlin】AI技術を活用…
・タクシーアプリの新規開発案件となります。現在リリースされているものの追加開発をメインに行なっており…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Android/PH…
AndroidもしくはPHPのリードエンジニアとしての役割をお任せする予定です。 <業務内容>…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・AndroidJava・Kotlin・And… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社マ…
▽案件内容 自社でマーケティングオートメーションツールの開発を行っており、今回はそのシステムのイン…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【概要】 下記の業務に携わっていただきます。 -車載ECUの通信系ドライバ開発/ミドルウェア開発…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
460,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】運用監視システム新…
◇ 業務概要 NW機器及び端末監視システムの新規導入作業を担っていただける方を募集します。 仮…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
モノの価値をつなぐ “リユース”というビジネスの魅力と可能性を信じ、テクノロジーを駆使し、これまでに…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
▼案件内容 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプ…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS/Azure …
受託開発案件でのインフラエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Azure | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
受託開発案件でのQAエンジニア(インフラエンジニア)を募集しております。 開発案件内容の詳細に…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Java・Laravel・CakePHP・V… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社の下記事業の中での新規事業案件のサービス開発におけるフロントエンド開発をご担当いただきます。 …
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
【案件概要】 金融系クライアント向けに自社サービスのリリースを予定しております。 AWSを使用し…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go・AWS | |
定番
【フルリモ / Kuebrenets / …
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションインフラの設計・構築・運用…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| kubernetes・Kafka・Datadog | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
自社サービスを利用した開発の推進、事業の企画、立上げにも携わっていただきます。 【作業内容】 …
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
[案件概要] トレーディングプラットフォーム、データプラットフォームについての設計および開発です。…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Storyboo… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
[案件概要] トレーディングプラットフォーム データプラットフォーム ・上記2サービスにつ…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js・Express | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
▼案件内容 ・需給に関するデータパイプラインとダッシュボードの新規開発 ・ブローキング業務支援の…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・tableau | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【企業概要】 企業の中枢を管理する次世代型経営管理クラウドを開発・提供しています。 【案件概…
週3日・4日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎広小路駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
◾️開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・ReactNative | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのiOSアプリ開発を担っていただきます。 ◾️ …
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【プロジェクト概要】 ・基幹システムおよび公開サイトの共通部品のメンテナンスおよびアーキテクト支…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・SQL・React・Node.js・Spr… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスにおける、開発保守運用業務をご担当いただける方…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【業務内容】 AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムと自社製AIカメラを連携させたプ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務詳細】 弊社プロダクトにおけるバックエンド開発のリーディングを担当いただきます。主にはオンラ…
週3日・4日・5日
3.2〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
ITサービスを使用するために必要な環境や設備を導入・保守業務を管理しています。 現行基幹システムが…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲or沖縄 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・React・‐ | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
▼業務内容 ITサービスを使用するために必要な環境や設備を導入・保守業務を管理しています。 現行…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 or 沖縄 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React・Spri… | |
定番
【フルリモ / React/Next.js…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】理…
理系学生に特化した新卒採用サービスを運営しており、研究領域で事業群を構築していくことを目指しています…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Play2・Framework | |
定番
【フルリモ / React/Redux /…
【業務内容】 下記の業務をご担当いただきます。 ・新規開発及び機能拡充、性能改善 ・開発チーム…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / Swift/RxSw…
【業務詳細】 ・提示された設計に基づくiOSアプリ開発 ・Health Kitからのデータの取得…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・- | |
定番
【フルリモ / React/React N…
下記三つの事業を展開しております。 -クラウドインテグレーション事業 -データ分析サービス事業 …
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
広告プラットフォーム事業やメディア事業を中心としながら、20以上の事業やサービスを運営しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Symfony・Laravel・R… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計、PoC、製品サ…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けの「社員向けスマホアプリ」の開発準備及び開発案件です。 ▼業務内容 スマホ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React(reac… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
▼案件概要 ネットワークの回線や装置の情報管理や、工事などの各種作業チケットの管理をしている業務シ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】新…
■複数のWEB制作プロジェクトのデザイナーとしてご参画いただきます。 -クライアントmtgの参加…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】MLO…
【業務内容】 工場での品質管理のために、プロダクトの撮影画像をAWS上に収集し、MLOpsで利用で…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】Q…
【業務内容】 スマホアプリサービスにおけるテスト計画の策定やテスト設計、テストの実施、テスト結果の…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【企業情報】 弊社は美容業界向けにICTを駆使し、成長を続ける「美容サロン向けICT事業」全国の美…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ヘルステック分野におけるライフログプラットフォームのWEBデザイン、ユーザー向けプロダクトのUI/U…
週3日・4日
390,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】自社H…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで様々なデザイン業務に携わりま…
週4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【リモート相談可 / API / 週4日〜…
【業務内容】 弊社提供サービスと、お客様で利用中の既存サービスとの連携開発をメインで行っていただき…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Nginx・AWS・Docker | |
定番
【フルリモ / Ruby/JavaScri…
【業務内容】 自動運転システムの開発です。 主に、自動車に設置されたセンサーデータを元に有意義な…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/jav…
【業務詳細】 下記の業務に携わっていただきます。 ・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 /…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・-・React | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【業務詳細】 ・最善の措置、開発プロセス、およびコーディング基準の追求 ・信頼性の高い、保守性の…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東松原駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【業務概要】 自社技術を活用した観光アプリ開発におけるUI/UXデザイナーを募集しております。 …
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4…
▼案件概要 クラウドファイルストレージをSaaSとして提供している企業様での導入コンサルト業務にな…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【業務詳細】 ・要件定義作成 ・導入時・導入後の… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
【案件概要】 新規スマートフォン向けRPGゲームのサーバーサイドエンジニアとして、開発~リリース、…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
▼業務内容 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただ…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ソーシャルゲーム開発において、サーバーアプリケーションの設計・実装および高速化・最適化の業務を行って…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
ソーシャルゲーム開発において、クライアントサイドの新規機能開発・既存機能改修・ゲームリリース作業を行…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity・CocosCreator | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
弊社求人事業部の運営するメディアの開発業務をご担当いただきます。 <業務内容> ・コンバージ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【仕事内容】 エンドユーザー・元請け案件を中心に、業務系システムの導入・開発、Webアプリ開発、ビ…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
私たちはレジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供しています。 今回の募集は、…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
私たちはレジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供しています。 今回の募集は、…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社ソリューションは、創業以来強みとしているデータ分析と近年マーケティング領域でトレンドとなっている…
週3日・4日
470,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・Java・SQL・R | |
定番
【フルリモ / Ruby/Python /…
今回は、医療用のビッグデータを様々な分析環境に利用するためのデータ基盤を開発いただけるエンジニアの方…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社が運営する顧客管理システムの開発、改修をご担当いただける方を募集いたします。 (業務内容詳…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
強化学習とデジタルツイン開発を得意とするAIベンチャー企業です。 グローバルで活躍できるAI企業に…
週4日・5日
570,000〜680,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】社内…
【業務内容】 データ分析基盤の構築・運用をおまかせします。 ・各種システムからのBigQuery…
週4日・5日
500,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
【概要】 -Androidのコアな部分に対する修正。 -Ver.UPに追従し、コアコードの都…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| C・C++・Android・Flamework | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
世界最先端のプロジェクトと共同している国内屈指のブロックチェーン技術に特化したソリューション提供カン…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週3日〜】…
【業務内容】 ・新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務をご担当いただきます。…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
当社は、独立開業する心理カウンセラー、ビジネスメンター、キャリアコンサルタントの方々を対象として、ク…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸丹波口 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
バーチャルとリアルを行き来する新しい買い物サービス開発の業務をお任せします。 <提供サービス>…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【リモート相談可 / java / 週5日…
▼案件概要 販売員が使用するモバイルアプリ(ios/Android)と、管理者が使用するWEB画面…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
弊社が運営するアルバイト求人メディアのデザイン業務をご担当いただきます。 <業務内容> UI…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
【仕事内容】 シェアリングサービスのエンジニアとして、インフラ、バックサイド、フロントサイドなど、…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
BtoCの既存WEBシステムのサーバリプレースのインフラ作業をお願いします。 <業区詳細> …
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ※開発側はJava・PHP ※ミドルウェア … | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
【企業情報】 金融系クライアントからの受託開発のリリースを控えている自社サービスの開発を軸として事…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【案件概要】 スポーツ団体向け会員管理システムのクラウドサービスにて、クライアント案件のサイト構築…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、バナーデザインを中心に担当いただくデザイナーの方を募…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社で運営しているサービスサイトのコーディング、ディレクションを担っていただける方を募集します。 …
週3日・4日
130,000〜330,000円/月
| 場所 | 神奈川港南台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
AI・IoT導入及びビッグデータ活用におけるデータ分析をメインにサービス提供している企業になります。…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL・R・SPSS・Modeler・… | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
様々な業務をsalesforceにより管理しております。 現在、業務改善に向けて様々なsalesf…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
【企業紹介】 当社は情報処理専門会社です。 システムのグランドデザイン、導入コンサル、カスタマイ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【ディレクター】出版物の編集ディレクターの…
パンフ制作・はがき制作・動画制作・他 印刷会社・動画制作会社・などへ業務を振っていただくご担当をし…
週5日
160,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | 制作ディレクター |
| リーダー経験 | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
「多言語」に対応した制作を武器に展開してきた制作会社で、現在も紙のグラフィックデザインとウェブのクリ…
週4日・5日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】シ…
【サービス】 1.情報システム部門サポートサービス 2.セキュリティサービス 3.システム管理…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 神奈川馬車道駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Springboot・Teeda・Seas… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】アジャ…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したシステムの監視・運用設計および監視・構築…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / PHP/Scala / 週…
[案件概要] 下記の業務をご担当いただける方を募集します。 ・法人向けのWEB名刺発注システム …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Scala・Play・Framework・L… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発から、サービスの…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
<業務内容> UIデザイン及びコーディングに関連する実務、プロダクトマネージャーやエンジニアとの協…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 医療データを100を超える医療施設から収集を行っています。動画を登録・管理するシステ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Ansible | |
定番
【Python / 週5日】動画編集デスク…
【案件概要】 医療データの動画を効率的に管理するために、新しく動画編集機能及びアノテーションを行う…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
大手フィナンシャル・グループのネット金融サービスの中核会社として、グループ各社との連携により、さまざ…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町、東京 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
♦事業内容 1. ITサービス事業 2. 衣裳事業 3. 婚礼プロデュース事業 4. コンサ…
週3日・4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日の出駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【主な仕事内容】 ・新規領域ECサイトのUI/UXデザイン業務 ・サービス内で使用する画像の改善…
週3日・4日・5日
570,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD・Adobeillustrator・A… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【概要】 弊社サービスのマーケティングにおけるデザイナー業務をご担当いただきます。 【業務内…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Il… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
弊社は企業のニーズに合わせたシステム開発及びシステム導入の企画・分析から設計・開発・運用支援までの一…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringMVC | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】専門…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【企業情報】 主にAI技術を活用した製品開発・システム開発・データ分析を行っております。 画像処…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 豊洲茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【会社概要】 当社はこれまでに数百社との取引実績があり、通信キャリア・大手SI企業・官公庁・大学等…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 豊洲門前中町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
▼案件概要 新規プロダクトとしてスマホアプリの新規サービスを検討しております。 新規PJのため一…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
弊社はビジネス課題や、社会課題を解決するためのイノベイティブなアイデア、 そして最先端技術(ブロッ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・angular・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
テレビ視聴データ分析サービス(SaaS型)を提供しており、業界トップクラスのシェアを誇っています。 …
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・(開発機器の主な機能) ・センサの情… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
<業務内容> ・日本最大級オンラインギフトプラットフォームのアプリエンジニア開発(Android)…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・Android・CircleCI・Fi… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展に貢献する医療ス…
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▽案件概要 経営陣やビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/…
週4日・5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼案件概要 ビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/UXデザ…
週4日・5日
370,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Vue.js/Nuxt.j…
自社サービスのフロントエンド開発をご担当いただきます。 開発チームのエンジニアとして、ビジネス…
週4日・5日
370,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
オンライン完結で提供する自社住宅ローンサービスのバックエンド開発におけるリードエンジニアをご担当いた…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
オンライン学習システムの開発・改善に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を募集いたします。…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・RubyonRai… | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日】W…
弊社で行ってるHP制作を中心にデザインを行って頂ける方を募集致します。 <制作実績> 大手通…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週5日】次…
【案件概要】 主に下記の業務をご担当いただく想定です。 -自動運転向け次世代地図データの管理・…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Java・C・C++・VB.NET | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
<業務内容> 顧客からシステム開発の発注を受け、WEBデザイナーとしてフロントエンドでの開発に携わ…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・AWSで構築しているパーソナル情報信託システムの2次開発。 ・既存のシステムに新た…
週5日
570,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業概要】 弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートする…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask・Django | |
定番
【フルリモ / C# / 週4日〜】自社開…
異なる事業者間での共同配送の実現、分断されるサプライチェーンの統合を目的としたトラック&トレースソリ…
週4日・5日
370,000〜570,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / iOS / 週5日】人材サ…
■今回の募集に関して アプリ開発における要件定義担当者としてのご依頼になります。 ・事業部担当者…
週5日
580,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・新規PJTにつき現在検討中 | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
今回弊社事業(クラウド会計ソフト関連)をさらに推進したいと考えており、 その為のUIデザインとフロ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・illust… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】自社…
自社プラットフォームを支えるインフラエンジニア業務を依頼します。 それぞれのメンバーの「属性の…
週4日・5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
【案件概要】 一例として、EC2上で稼働しているMongoDBを、Amazon DocumentD…
週3日・4日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社プ…
【企業紹介】 ゴルフ場予約サイトのプレープランや価格等の比較情報や、ゴルフ場の予約に対応したWeb…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
【案件概要】 弊社コンサルティング部にてsalesforceでの業務を行っていただきます。 ダッ…
週3日
290,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| 【企業概要】 弊社ではエンジニアを育成するオンライ… | |
定番
【フルリモ / ReactNative/S…
【業務内容】 ReactNativeでiOSのみに対応したランサーズのスマホアプリの開発、開発運用…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・ReactNative・S… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 WebアプリケーションインフラおよびWindowsサーバーの監視・構築・運用、Dev…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 業務詳細: 1)・監視ツールを用いての監視・障害報… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
社内SEとして既存システムの改修や機能追加、または新規のシステム開発を行っていただきます。 ・社内…
週3日・4日・5日
550,000〜610,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトで開発チームのエンジニアをご担当頂きます。 ・PM・…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python/Typ…
■業務内容 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・各SaaSサービスのインテグレート、設計、開…
週5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| JavaScript・Typescript・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
ゲーム会社の事業拡大に伴う、ゲーム開発プログラマの募集をいたします。 【業務内容】 コンシュ…
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【3DCGデザイナー / 週4日〜】家庭用…
【案件概要】 ゲーム会社の事業拡大に伴う、3DCGデザイナーを募集をいたします。 【業務内容…
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| 【職種について】 3DCG背景、モーションデザイン… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】LA…
①想定しているアサインプロジェクト ・作業内容としてはCMS(内容管理システム)の開発です。 …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿野並駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 1. WEBシステムのフロントエンド開発 ・プロダクトサイト ・ECサイト ・…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件詳細】 ECサイトやプロモーションサイトのUI/UXの改善をもっとはやく進めたい! ロボッ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜町 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】最…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
170,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Nuxt.js / 週5日…
■業務内容 ・新規サービスのシステム開発(メイン) ・商標登録を安心、カンタンにできるようにする…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】オ…
オンラインによる診察、処方箋発行、治験、メンタルケアなどのサービスを展開しています。 今回はサービ…
週4日・5日
300,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【案件概要】 Webサイト新規構築おけるフロントエンド作業者として、マークアップ部分の全体設計〜構…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / React/Vue.js …
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
【担当いただく業務】 新規プロダクト開発チームへのアサインとなります。 ・新規プロダクトの初期立…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Node.js | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週4日…
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
機器の状態を可視化、機器の設定を行うWEBサイトにおいて、グラフやテーブルの描画、フォームの描画と送…
週3日・4日・5日
460,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Node.js・n… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】最新…
最先端システムの開発や強化学習を使ったロボット動作最適化学習などに携わっていただけるAIエンジニアの…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄井尻駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Swift・Kotlin… | |
定番
【フルリモ / セキュリティー / 週3日…
当社は、スマートフォンアプリやWebサービスのセキュリティ診断業務に特化したホワイトハッカーで構成さ…
週3日・4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / Angular/Nest,…
▼案件概要 既存の開発チームに新しくジョインしていただき、CTOとコミュニケーションをとりながら、…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Angular・Next・js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】受託サ…
【案件詳細】 コードを書くことに夢中になれるPHPエンジニアを募集します! 【業務内容】 …
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中之島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【今回の案件について】 杭メーカーの施工管理システム 【業務詳細】 ・Webアプリケーショ…
週4日・5日
500,000〜730,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・Express・G… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【仕事内容】 デザイン設計において、投資家向けの資料デザイン、弊社教育事業のスライドのリデザイン、…
週3日・4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Sketch… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
▼案件概要 今後は、開発ラインを増やし、カジュアルゲーム開発も並行して展開するほか、コンシューマー…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・₋- | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】急成…
【案件内容】 サーバーサイドとインフラの開発をお任せする、フルスタックエンジニアを募集いたします。…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
弊社デザイン部署にてWebコーダーとして、PV数の高いサイトを責任もってご担当いただける方を募集いた…
週5日
220,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React/firebas…
<業務内容> 少人数での開発になりますので、アプリの開発、リリースをまで担当し、要件定義~実装まで…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・React・Firebase | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
【仕事内容】 Web開発エンジニアを募集します。 ※プロジェクトにより、詳細仕事内容に変更がある…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸肥後橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SQL・Spring・Struts | |
定番
【Javascript】VisualSLA…
<案件概要> L5G関連のナショナルプロジェクト(NP)にて使用する評価用アプリケーションの開発実…
週4日・5日
460,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【Java、SpringBoot,、AWS…
キャラクターコンテンツ配信サービスの新規開発になります。 Java SpringBoot、AWSを…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Backlog、Git、Slack、Goo… | |
【Swift又はKotlin】キャラクター…
キャラクターコンテンツ配信サービスの新規開発になります。 SwiftまたはAndroid Kotl…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
BtoBに特化して30年以上、デジタルを活用した、マーケティングでお客様企業の売上に貢献できる、より…
週4日・5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
170,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社ではWEBサービス開発を行っていただける、PHPエンジニアを積極的に募集しております。 大…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため、医療統計データサービスを提供している会社です…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】社内…
◆案件概要 医療機関のお客様からいただいたデータを分析する際に、社内で可視化して区別できるよう、社…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Tableau・AWS | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【主な仕事内容】 ・新規領域ECサイトのUI/UXデザイン業務 ・サービス内で使用する画像の改善…
週3日・4日・5日
570,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD・Adobeillustrator・A… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 今…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
建設現場調査・情報共有アプリケーションを開発しており、今回はLaravelエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Slack・Jira・その他… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
一部上場企業のグループ会社として、人材サービス向け基幹システムで業界シェアTOPを誇るITベンチャー…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【プロダクトプランナー】注目のAIベンチャ…
・新規・既存開発プロジェクトにおけるユーザー課題の洗い出し ・ユーザー課題解決に向けたソリューショ…
週3日・4日・5日
840,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトプランナー |
【ライター】求職者向け自社紹介資料
【企業概要】 製薬業界に特化した業務支援サービスとコンサルティングサービスを提供しています。 …
週2日・3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
定番
【テスター】大手通信会社向けWEBコンテン…
当社SI部門でのテスター業務に従事いただきます。 ※詳細は面談内にてお伝えいたします。 大手通信…
週4日・5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
現行システムの機能追加などの改修をメインでご対応頂きます。 具体的には、お一人でフロントエンド(詳…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java/kotlin /…
現在のサイトの基盤を元に、β版をリリースする予定です。 リリース予定の新サービスの API 実装を…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・- | |
定番
【フルリモ / React/Java / …
自社でアプリ開発やメディア事業を展開しつつ、受託案件も受けています。 今回はクライアント様の入…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】Goo…
Googleマイビジネスを利用した店舗集客支援サービスに伴う開発業務をお任せします。 さらなる事業…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Docker・AWS・MySQL | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
今後さらなる成長を遂げるため、自社サービスの開発にも力を注いでいます。 そこで、この度新規および既…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
670,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・V… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
◆業務内容 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・アプリケーションまたは…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Python/TypeSc…
データ分野に特化におけるプロダクト開発力・コンサルティング力を強みとし、クライアント企業のデジタルマ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 今回、PHPエンジニ…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Zend | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社画像・動画・音楽クリエイティブプラットフォームの開発業務になります。 【業務】 写真・イ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
【業務内容】 ・自社事業におけるWebサービス刷新プロジェクトの開発リードエンジニア ・リリース…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・PHP | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】自…
【業務内容】 ・ユーザーの課題解決に直結するプロダクトの理想の姿を考え、プロダクトマネージャーをは…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Figma | |
定番
【フルリモ / C#/Java / 週5日…
コンピュータソフトウェアの開発会社です。 お客様の状況に最適なシステム開発に即応するべく、現場での…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週4…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムとミルキューブ(自社製AIカメラ)を連携させたプ…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【案件概要】 物流業界向けSaaSの開発に従事してくれるUI/UXデザインをお願いします。 その…
週3日・4日・5日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大前駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
■業務内容 -プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認・テスト、…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
【業務内容】 弊社が運営するBtoB向けのIT製品の比較サイトのフロントエンド開発をご担当いただき…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / Ruby/TypeScri…
主に中高生向けの学習塾紹介メディアを自社で運営しております。 今回は上記メディアのサーバサイド…
週4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】子育て…
今回は子育て支援サービスに関するアプリのAPI周りの開発に携わっていただけるエンジニアの方を募集いた…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Go・Golang・AWS・Fargate… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社プ…
【案件概要】 テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
弊社では企業のデジタルマーケティングを支援していくために自社運営メディアを用いて企業の課題を解決して…
週5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
【案件概要】 Flutterを用いたアプリ開発のプロジェクトです。 今回は、Flutterエンジ…
週3日・4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大駅前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】De…
多様なシステムのインフラ設計・開発・運用をお願い致します。 ・安定稼働を実現するためのサービス…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue/TypeScrip…
これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプリ、システム等の開発を行っています。…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・TypeScri… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSサービス開発におけるフロントエンド・サーバーサイドを幅広くご担当いただきます。 【…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Python・Typescript… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【募集概要】 ・弊社で請け負っているWEB制作業務をご担当いただきます。 ・WebサイトのUIや…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 群馬・栃木・茨城- |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・【使用ツール… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
自社サービス開発全般(主にフロントエンド開発)業務を担っていただける方を募集します。 ・クライアン…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Nuxt.js・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Java/C/C++…
あらゆる手配業務をチャットで完結できるコンシェルジュチャットプラットフォームを展開しております。 …
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Go・C・… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】経済メ…
弊社アプリのUIデザイン情報設計・経験により以下業務を担当して頂きます。 【業務詳細】 - …
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
▼具体的な業務内容 B2B領域で、AIプロダクトのUIUXデザインを行っていただきます。 <…
週4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるモニターアライアンス基盤とクライアントのサービスが連携した共同事業のシステム開発に…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・PhalconPHP・… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
現状、自社で運営する多数のメディアのアクセス増に向け、クラウドインフラ基盤の品質向上をできる方を求め…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 当社のクライアント企業での、Webアプリケーションのサーバーサイド開発をお願い致しま…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原新御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
一般向け金融メディアで、コミュニケーション設計/デザイン/マークアップの「ディレクション」を担ってい…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・illustr… | |
定番
【フルリモ / Python/Django…
今回は、自社が提供するコーチング事業の中でお客様が利用するアプリケーションツール開発、追加機能の導入…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
弊社の社内業務ツールとしてSaleforceを導入いたしました。 今後システム設定やカスタマイズが…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
【業務内容】 主にページパフォーマンス改善や、UI/UXの改善。また直近でJamstackでの開発…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
【企業紹介】 すべての人に、いつまでも健康で美しく生きるための商品・サービスを提供している企業です…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【会社概要】 弊社の事業では、1,000万人以上が利用するスマホアプリ情報を扱う国内最大級の自社メ…
週4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| CSS・JavaScript・PHP・Laravel… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】新規金…
自社金融サービスのサーバーサイド開発業務をお願いいします。 バックエンド、フロントエンド、インフラ…
週4日・5日
740,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
【案件概要】 CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューションを提供しており、事業…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP/Perl / 週4…
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Perl | |
定番
【フルリモ / Go/Node.js / …
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Go・Node.js | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】Fi…
【案件概要】 事業拡大に伴うサーバーサイドエンジニアの業務を依頼させて頂きます。 【業務内容…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
▼業務内容 ・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 / オンライン教育を行うシステムの開発 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・【開発環境】 ・… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
顧客基盤を持つ自社採用管理システムの新機能追加や、新規開発案件をお任せいたします。 新しいテク…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Coldfusio… | |
定番
【フルリモ / ReactNative /…
チームをリードしていただけるエンジニアの方を募集しております。 【業務内容概要】 ・マッチン…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| ・開発手法:スクラム開発 ・PRJ管理ツール:Ze… | |
定番
【フルリモ / C++ / 週4日〜】次世…
【業務内容】 エンジニアとしての経験を活かし、次世代CADの要件と仕様の理解を行い、チーム開発を牽…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / C++ / 週4日〜】建築…
【会社概要】 コンサルティング〜システム開発〜新規事業創出まで行う、DXコンサル企業です。属人的な…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
【会社概要】 弊社はAIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/Swi…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週5…
今回は新規または既存機能の開発・保守運用も想定しております。(ご経験やご要望によって新規開発か既存開…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・SQL・AWS・MySQL・Git | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
Chatbot, チャットフレームワークを利用したWebアプリケーションの開発を遂行していただきます…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Go・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】クラウ…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。お客様にコンサルティングからシ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】アプリ開…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。 お客様にコンサルティングか…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP/Pythpn / …
【業務内容】 ・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【フルリモ / PHP/Pythpn / …
【業務内容】 ・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】保守…
【企業概要】 当社は商品やサービスの認知獲得・興味喚起を促すデータを統合し分析を行い、 戦略策定…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業概要】 弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートする…
週5日
520,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・Ruby・Flask・Django・【… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Vue.js /…
AIを用いたソフトウェアのテスト自動化プラットフォームを自社開発・提供しています。 今回は、機…
週3日・4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / JQuery / 週…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / React/Python …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・AWS基盤へのオンプレからの移行および新規シ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【業務詳細】 当社のディープラーニング事業で行うプロジェクト・開発案件をゴールへ導くための技術開発…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、様々な開発・改善を…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週4日〜…
◇案件概要 キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / Java/Go / 週5日…
今回は、自社プロダクト(HR領域)開発全般をご担当いただける方を募集しています。 ・機能拡張/改善…
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
今回の募集は、弊社の複数プロダクトのAndroidアプリ、iOSアプリ開発をご担当いただきます。 …
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Python /…
当グループは日本の都心部の大型複合開発や、主要リゾート地でのホテル&リゾート事業を手掛けてきた不動産…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 ・機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇業務概要 証券会社投信システム(約定計算)の基本設計をお任せします。 ◇作業範囲 投信…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【会社概要】 資産運用・相続・事業承継を専門とするコンサル会社です。 【業務内容】 フロン…
週3日・4日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 【職種…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】AI…
クライアントより依頼をいただいているECサイトのシステム移行プロジェクトの移行チームメンバーとして、…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・VBA・Salesforce… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアアを開発します。 一般ユーザーと広告主をマッチングさせる…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Illustrator・Sketch | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
私たちは、データ分野に特化におけるプロダクト開発力・コンサルティング力を強みとし、クライアント企業の…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・SQL・R・<業務環境> ・分析環境… | |
某出版社CMSのフロントエンド開発【Vue…
出版社のサイトリニューアル・プロジェクトのサブプロジェクト。 業務支援機能の中でも重要なCMSをS…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4…
■案件概要 ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアを開発します。 ■業務内容 ・アーキ…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| SQL・Node.js・React・主な機能 ①… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・◇作業概要 … | |
定番
【フルリモ / Swift/Objecti…
◇案件概要 企画から開発まで担っていただくiOSエンジニアを募集しています。 ◇作業概要 …
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【事業概要】 当社の自社サービスは大手外食チェーンから個店レベルの飲食店まで幅広い規模の飲食店に採…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【サービス内容】 臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go・Typescript・【作業内容】 自社プロ… | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
リリース予定の教育Webアプリケーションの開発業務に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
▽事業紹介 Javascriptフレームワークなどを用いたWebアプリケーションを構築。 特にU…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
スマホアプリ開発において、クラウドサービス利用提案、フレームワーク熟知したシステム提案を顧客、プロジ…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・redux・red… | |
【テスター】新補聴器フィッティングシステ…
新補聴器フィッティングシステムの開発案件にて、テスト設計・実施をご担当いただきます。 今回の募集背…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター(テスト設計) |
| C#・VB.NET・Windows・C#.net | |
感動体験サービスの開発(テスター)
感動体験サービスのWEBサービス(Frontメイン)開発の案件となります。 体験ツアーを購入したユ…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| React | |
注目
【Javaエンジニア】情報管理系大規模業務…
【業務内容】 保有している情報を一元管理で行うシステムをJavaを中心に開発している案件です。 …
週5日
3.2〜4.5万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバ―サイドエンジニア |
| Python・Java・AWS・CI・CD | |
定番
[編集ディレクター]Web企画・制作
【企業】 主に50代からの女性を対象とした出版、通信販売、店舗、講座イベントなどの各種事業を行って…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【サーバーサイド】アライアンスシステム開発…
案件内容 :アライアンスPJにおけるシステム開発、PF開発 およびそれらのテスト …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町紀尾井町 |
|---|---|
| 役割 | 【サーバーサイド】Java/Pythonエンジニア |
| Python・Java・AWS | |
定番
【フルリモ / Ruby/React.js…
ユーザーと専門家をつなぐサービスを提供しており、ご利用件数は39,000件に上ります。 業界内での…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】超有…
【業務内容】 ・美容系予約サイトの改修・機能追加に携わって頂きます。 ・要件定義から関わって頂き…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・開発環境 Java8(Seasar2・S… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
・Go言語によるWebアプリケーション開発、API開発 ※バックエンド開発の具体的な業務としては、…
週4日・5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・※可能な方については、アプリケーション要件に基… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社は自社開発の医療系求人サイトを開発・運営しています。 医師、看護師、薬剤師などメジャー職種だけ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・CakePHP・【開発… | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
MS365テナントのデータ移行(outlook、onedrive、sharepoint,teams)…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Microsoft365 | |
定番
【フルリモ / Vue/Python / …
当社が提供するサービスのソフトウェア開発のポジションです。 本募集においては主にフロントエンド開発…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
IT会社の社内システム開発業務です。 調査、設計、製造、試験をご担当いただきます。 既存メンバー…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】EC…
Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設計からサイト運用…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・【会社概要】 Webサイト… | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスの フロント周りを開発支援い…
週3日・4日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】リユ…
AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。 AWSに精…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・AWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】グロ…
◆業務内容 - 当社が開発をしているECサイトの開発・テスト・運用・改善 - 新規サービス及び、…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週4日…
【業務内容】 ・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| 弊社は、Google・Cloudに特化した技術者集団… | |
定番
【フルリモ / C# / 週4日〜】Bto…
【企業情報】 1.個別受注生産向け生産スケジューラ、生産管理システムの開発・販売 2.ペーパー…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・C・C++・C#・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
・AWS上でのSSL-VPN(FortigateもしくはF5 BIG IP APM)のPoC対応 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原門前仲町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| FortiGate・AWS | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
自社サービスのWEBコーディングを依頼させていただきます。 【業務内容】 ・自社独自CMSを…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
【仕事内容】 スマートフォンゲームの企画、開発及び運用を担当していただきます。 【具体的な業…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
【業務内容】 サブシステムの開発 / 保守運用業務 ※WEB アプリケーションの開発 弊社…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
【業務内容】 弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただき…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】アプ…
オフショアで開発したtoC向け自社アプリのクラウドインフラの運用管理設計ができる人材を探しております…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決を行っているAIベンチャーです。 【…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Node/TypeScri…
【業務詳細】 主にWebアプリケーションのAPIサーバー開発と、フロントエンドサーバー開発のコード…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
フィットネスなど有名サービスを複数展開する企業様のインフラ全般を担当する情シス部門の社員代替の業務に…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木南青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】航…
某航空会社の発券予約システムの開発を行っていただきます。 基本的にフロントメインとなりますが、サー…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・React.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務内容】 セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務です。 1機能単位…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
UIUXデザイナーとして、自社サービスを始めとしたサービス・プロジェクトに Webデザイナーとして…
週4日・5日
440,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / ReactNative/R…
【業務内容】 ・弊社クライアントのスマホ向けのリプレイスをお願いしたいと考えております。 (弊社…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・ReactN… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 【作業…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / React/Go / 週4…
弊社では、オンラインによる診察、処方箋発行、治験、メンタルケアなどのサービスを展開しています。 今…
週4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / AWS/GCP / 週4日…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / QA / 週4日〜】テスト…
■業務概要 プロダクトのQAエンジニアとして、リリースのための品質保証業務をご担当いただきます。 …
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| QA・■具体的職務 ・内製、外注を含んだ受入検査の… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
ネイティブ (Swift/Kotlin) で実装されたアプリをFlutterを用いてフルリプレイスす…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
弊社が運営するニュースアプリのiOSアプリ開発全般を担当していただきます。 【業務内容】 ・…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・UIKit | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 【業務内容…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐・【開発環境】 ・言語:Kotli… | |
定番
【フルリモ / Python/Go / 週…
弊社が運営するプロダクトのサーバーサイド開発全般を担当していただきます。 【業務内容】 ・A…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Django・Flask | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
弊社請け負ったCM制作やプロモーション映像の制作の担当をお願い致します。 TV番組やCM用の制作を…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| AfterEffects・Unity・Unreal・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】公共…
弊社サービスの根幹を支えるクラウドインフラの設計支援を行って頂けるインフラエンジニアの方を募集します…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 今後新規…
週3日・4日
260,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】ロボテ…
■ご担当頂きたいこと 当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署と連携してプロ…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| ■技術環境 デザインツール:Figma・・Adob… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務システムの開発を…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・-・Django | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。 【業務内容】 ・KP…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【AWS / 週5日】ECサイトのライブラ…
【案件内容】 ECサイトのライブラリ管理をご担当いただきます。 AWSの知見があり、運用経験があ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発になります。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.jp・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】AI…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サービスの魅…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter・◆具体例 ・カスタ… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社はを中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営し…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
既に上位会社参画中の案件に弊社リーダーと一緒に参画いただけるメンバーを募集しております。 アジ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】バック…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 当社…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週5…
大手広告代理店や既存のマーケティングサービスでは対応できなかった、多くの予算・時間を割けない地方の中…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5】広告代理店…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】中古…
今回の募集は、大手中古車販売会社の社内基幹システム開発をお願いできる方を募集します。 現在50…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS/ …
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。 担当業務は主にデザ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
【業務内容】 (当社のクライアント様案件になります。) ・クライアント様のCMSの開発(word…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・【業務内容】 ・自社サービス… | |
定番
【フルリモ / Android/Kotol…
【業務内容】 自社のAndroidアプリ開発をご担当いただく方を募集いたします。 就活生へ…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
【企業概要】 これまで私たちは、IT技術を活用し、顧客のビジネス課題に寄り添いながら、 成長を続…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週4…
【業務内容】 弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおい…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
①デバイス管理及びEPP/EDRの導入・運用、インターネットアクセス制御の導入・運用、OS・アプリケ…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / Scala/TypeScr…
複数のプロダクトを並行展開しています。 プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービス…
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Scala・Kotlin・Typescript・Pl… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】GCP…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(予約…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【BIエンジニア/データアナリスト】顧客ア…
■概要 グローバル最大手の動画学習プラットフォームに関する顧客アンケートでの年度定点調査から特定の…
週5日
550,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | BIエンジニア/データアナリスト |
| AWSAthena・S3・TableauCloud・… | |
定番
【フルスタックエンジニア】Webアプリケー…
機械翻訳訳Web アプリケーションT-tact AN-ZINの開発業務を全般的にご担当頂きます。 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webアプリエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【Javaエンジニア】新規プロダクト開発に…
【業務内容】 新規プロダクト開発におけるJavaエンジニアを募集しています。 ※詳細はご面談の際…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
コンシューマーゲームにおけるゲームデザイナ…
【企業】 PlayStation 4、Nintendo Switch、PC(steam)など、様々…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草 |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
定番
【フルリモ / C#/Python / 週…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Shell・SQL・◇作業概要 ・Go言語に… | |
定番
【フルリモ / React/Vue / 週…
主にWebアプリケーションに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニアと協調して行っていただきま…
週4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
▼仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホ…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala・… | |
定番
【データサイエンティスト】データサイエンス…
【業務内容】 データサイエンスの知見を活かした社内外に提示するコンテンツの作成。 過去実施のWE…
週3日・4日・5日
390,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
【HTML,CSS,Liquid】自社サイ…
・2023年1月中リリースを目指して、アップデートに伴う実装を行う。 Liquidという言語を使用…
週2日・3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
【Webデザイナー】色の教育事業サービスの…
◎パーソナルカラーに関する教材企画、提案にも関わることができます。 ◎教材の費用補助があり、カラリ…
週3日・4日・5日
250,000〜5,080,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】ク…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・【… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】クラウ…
【業務内容】 ・数十GBのデータを高速に処理できるAWSアーキテクチャの設計・開発 ・サーバーコ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Java/SpringBo…
大手ECサイト運営会社における業務を想定しています。 今までは、PoCとして開発を行ってきましたが…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】Po…
【業務内容】 Microsoft製品を活用して業務プロセスの自動化を実現して業務効率を向上させるこ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PowerApps・PowerAutomate・Lo… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/jQuer…
◆案件概要 弊社では、株式やFXなどの金融商品を扱うオンライン金融サービスを提供しています。 …
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / SPIRAL / 週5日】…
【業務内容】 ・CRMのSPIRAL構築業務を行っていただきます。 ※クライアント様の案件になり…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
弊社では、ソーシャル経済メディアを提供しています。 【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 …
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・【開発環境】 ・開発言語:な… | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
【業務内容】 大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注し…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】開発…
【業務内容】 ・開発者がより高速に開発できるための開発環境の改善 ・CI/CDやデプロイパイプラ…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AdobeXD / …
【会社概要】 動画事業を中心に顧客課題に寄り添ったコンテンツを作成運用しています。 動画以外に、…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿下北沢駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
【会社概要】 動画事業を中心に顧客課題に寄り添ったコンテンツを作成運用しています。 動画以外に、…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿下北沢駅 |
|---|---|
| 役割 | モーションデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python/R /…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
840,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するベンチャー企業です。 ▽仕事内容 既存、新規事業…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / C#/AWS / 週3日〜…
◇概要 物理・数学の専門知識を持つトップクラスのエンジニアが集まっており、クライアント内の暗黙知・…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
▽仕事内容 新規で開発しているオンライン授業プログラミングプロダクトのWebUI/UXデザイン業務…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Skech・Figma | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【募集背景】 ・自社プロダクト開発がスタートし、業務が拡大していることが背景です。 【業務内…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| 【企業情報】 弊社はベトナムと日本にオフィスを持ち… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
【業務内容】 ・新規アプリのUI/UXデザイン ・UI/UX設計 ・トンマナの設定、スタ…
週3日・4日
450,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| 【会社概要】 医師のコミュニティサイトの運営によっ… | |
定番
【フルリモ / React/Next.js…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
弊社では、産業のデジタルトランスフォーメーションを推進するさまざまな事業を展開しています。 【…
週5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Cisco / 週5日】受…
【企業情報】 ITコンサルティング、アプリケーション開発、インフラ構築運用保守、など様々な事業でク…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Cisco | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営するスタートアップです。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】飲…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日・4日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails・【企業概要】… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】広…
【業務内容】 ・自社Webアプリケーションの開発をお願いしたく思っております。 └サーバーサイド…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/JQuery /…
【企業紹介】 当社では、主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / Python/PHP / …
【企業紹介】 主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、及びそのた…
週4日・5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・SQL・Laravel・開発環… | |
定番
【フルリモ / QA / 週5日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週5日
550,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
Webサイトとブラウザ拡張機能をベースとしたポイントメディアの開発予定です。 ■業務内容 ・We…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| SQL・Node.js・React | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【想定依頼内容】 -デザインのエレメントパーツの洗い出し・重みづけ -エレメントパーツの制作 …
週3日・4日
260,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・【会社概要】 お客様向けにデザイ… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
弊社はヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開しています。 【案件…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
【業務内容】 人材サービス業向けのスマホアプリの開発をご担当いただきます。 就業中(求職中)…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js・Apache・… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】人…
【業務内容】 人材サービス業向けのスマホアプリの開発を担っていただける方を募集します。 就業中(…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・React・Node… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 【募集ポジシ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java・React(react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【企業概要】 ブランディング開発やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制作を行っ…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週5日】…
【業務内容】 エンド様への提案から実対応(設計、検証、構築)までの全工程を弊社チームで実施いたしま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原品川駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社で受託しているサイト制作やWordpress制作の案件に携わっていただきます。 【職務内容…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 ・顧客情報システム部門のインフラ担当 ・顧客が利用するインフラ(NW/AWS/OS)…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】顧…
【業務内容】 TypeScript・React(Next.js)を利⽤したWebフロントエンドの開…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・ | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
自社開発している、中小企業が集客のために利用する広告代理店への支援サービスや、Googleマイビジネ…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Vue.js・MySQL・AWS・Ci… | |
定番
【フルリモ / Vue/TypeScrip…
【業務内容】 弊社コミュニティサイトサービスにおける開発を担当いただきます。 ウェブサービスの改…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【業務詳細】 自社開発をしているクラウドファンディングシステムのクライアントページのデザインを今回…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自治体向け医療・介護関連データ利活用ビジネスに関するシステム開発をお願いします。 【業務内容】…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
今回は自社制作のアプリの改修や機能追加をご担当いただけるエンジニアの方を 募集いたします。 弊社…
週3日
290,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
開発グループのフロントエンドを募集しております。 マーケティング施策の高速PDCAの実現や、受…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Next.js | |
定番
【UiPath / 週5日】モーターパーツ…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 【業務…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| VB.NET・VBA・UiPath・‐ | |
定番
【フルリモ / Python/SQL / …
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 弊社の顧客から受託したWEBサイトの制作業務をご担当いただきます。 ・静的サイ…
週3日・4日
220,000〜260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【フルリモ / Angular.js / …
【業務内容】 弊社が運営する電子チラシ配信サービスにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきま…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・cordov… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■概要 SaaSプロダクト(CRM、請求機能など)に関するフロントエンド開発を担当いただきます。 …
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / ActiveDire…
今回は、某大手銀行のシステム運用を担っていただける方を募集します。 【業務内容】 ・WIND…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| VBA・SQL・MSActiveDirectory・… | |
定番
【フルリモ / PHP/Ruby / 週4…
▽業務詳細 ・エンジニアサポート ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Firewall | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】I…
サポート内容は下記になります。 ①マンツーマンでのメンタリング1on1 ②質問対応 ③課題のレ…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/PHP / 週4…
ビジネスサイド(マーケ、UXチームなど)と一緒にサービスグロースのためにサーバーサイドエンジニアとし…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / iOS/Swift / 週…
【募集背景】 すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいて…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / React/Nuxt.js…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・ReactNative・Nux… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
- シェアフルサービス内での給与即払いのための給与計算周り - 請求周り 基本的には上記の開発を…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
弊社では煩雑化する会計周りをシンプル化・DX化を促進する為、経理業務管理ツールの開発を進めてます。 …
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
【業務内容】 SEOアフィリエイトメディアの収益改善を行うためのデータ分析SaaSのクローズドベー…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿吉祥寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
実施率向上に向けた、仕組み作り、業務効率化を目的としたSaaS化、情報設計、UI/UXデザインをお任…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
■業務内容 ・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / CSS/HTML /…
弊社では金融メディアプラットフォーマーという立ち位置で、WordPress、RCMS、自社CMSでW…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件内容】 システム開発チーム内で一緒に業務を行っていただきます。 目先の開発スピード向上と長…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・React | |
定番
【マーケター】マーケティング全般の設計と実…
■マーケティング全般の設計と実行 ナショナルクライアントの担当者及び意思決定者の認知~検討~意…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
【コーダー】メディア開発(PHP/Word…
自社メディアの開発プロジェクトです。 PHP特にWordPressを利用した開発を行なっていただき…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】ア…
■ 構築先 ・クライアント仮想サーバ環境で払い出された仮想サーバ ・仮想基板、ネットワーク管理操…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 クライアントワークにおいて、Webサイト制作においてHTML、CSSでのマークアップ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
▼案件内容 1、オンラインプログラミング教材を作成するための業務支援 ツールの開発・運用をお願いし…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】映像配…
弊社が運営する動画配信サイトへ書籍の配信サービスを追加するため、このサービスの追加機能の開発をお任せ…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / UiPath / 週3日〜…
RPA単独ソリューション提供に加えて、RPAのコラボレーションに関連ソリューション推進および開発等に…
週3日・4日・5日
580,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
プロダクトのAPIサーバー開発を中心として、サービスを安定運用するための基盤システム整備まで幅広い開…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
最先端のアルゴリズムを開発する会社であるため、機械学習に興味がある方を歓迎します。 ◆業務内容…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
新しいアーキテクチャ(jamstack、サーバーレス)の構成における設計、構築、テストをリードしてい…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川戸越銀座 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 インフラ分野の設計や導入支援、アーキテクチャ設計、環境構築、クラウドへの移行支援を担…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・EC2・EKS・ECS・RDS・CF・ELB… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【業務内容】 稼働中のECサイトを新サービスに適用させるための大規模改修として、オンプレからパブリ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・SQL・ShellScript・SQL・O… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
【案件内容】 ・自社サービスシステムにおけるマニュアル作成業務をご依頼いたします。 -最初は社…
週3日・4日・5日
330,000〜5,080,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【業務内容】 官公庁・自治体等の案件入札・落札情報を探せる自社サービスの周辺サービスとしての新規事…
週3日・4日・5日
500,000〜730,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / ゲーム / 週5日】スマー…
【業務内容】 ・スマートフォンタイトルの企画及び仕様作成、簡易なデバッグについて、開発からリリース…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【案件概要】 今後、主力事業だけではなく、法人向けサービスの拡大や新規事業の展開を行っていく上で …
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
現在自社サービスを拡大させるためのUI開発をしております。 具体的には、SEOの改善や成約率アップ…
週3日・4日・5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】決済…
【案件内容】 現在当社では、自社で開発した既存のPHPシステムを新たにJavaで構成するプロジェク…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・■OS:Linux、Windows ■D… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
私達と一緒にブロックチェーンゲームを手伝ってくれる人を探しています。 ▼仕事内容は下記のいずれかと…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python・Jav… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件内容】 クライアントが抱える課題に対して、統計的・機械学習的手法によるソリューションを調査研…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Linux/AWS …
【業務概要】 顧客情報システム部門のインフラ担当として、当社社員と一緒に従事いただきます。 …
週5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
日本でも珍しい、ハード、ソフト、クラウドサービスを全て自社で行なっている生粋のテクノロジーベンチャー…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【開発環境】 バックエンド:Python・(FW:… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【企業紹介】 クライアントのセールスプロモーションを成功に導くために運営から人材手配、制作までワン…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】新規開…
【募集背景】 Webプランニング力、技術力を武器に、様々な大手クライアントのデジタル施策の企画から…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・jQuery・CakePHP… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】データ…
製造業様向けAWSを用いたデータ利活用支援 次期DX基盤構築のための各種作業支援内容 ・ A…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| AWS・Redshift | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
【案件概要】 携帯電話会社のホームページ・リニューアル開発にご対応いただきます。 ※クライアント…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 以下の業務をご担当いただきます。 ・導入先会社の古いExcelマクロをTablea…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・Excel・Tableau | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 下記の業務をご担当いただきます。 ・既存システムの仕様調査 ・社外APIの使用方…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・MySQL・CentO… | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
某外資系企業様向けの情報システム部のネットワーク運用業務になります。 構築作業もあり、試験仕様書や…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Tanium・Cisco・Umbrella・ArcS… | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Webデザイナー / 週3…
【業務内容】 自社案件のWeb・クリエイティブデザイナーを募集しております。 ・バナーデザイ…
週3日
140,000〜250,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| 【その他情報】 チーム人数:2名 就業:フルリモ… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
【案件内容】 当グループ会社のお客様が利用するアプリケーションの動作や、各種ツール、Webサービス…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】国内…
【主な業務内容】 インフラ設計、構築、運用、保守、管理を行なっていただきます。 また内製アプリケ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・LINUX | |
定番
【C++ / 週5日】受託サービスにおける…
【主な業務内容】 システム開発(受託・SES) facebook・iPhone・Androidア…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町、武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・VisualC++ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】 …
動画配信サービスのiOS・tvOSアプリの開発及び運用を担当していただきます。 ・動画配信モバ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【スマホアプリ】ネットスーパー向け新規アプ…
案件内容 :ネットスーパー向け新規モバイルアプリ開発プロジェクトのスマホアプリ開発 作業場所 …
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop …
本サービスは、クラウドサービス利用時のセキュリティ不安を解消する、クラウドリスク評価データベースです…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【SEOマーケター】SEOコンテンツの制作
【業務内容】 Q&A(toB向け)コンテンツ ・タイトル/ディスクリプションの適正化 ・記事の…
週2日・3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅、乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOマーケター(ライター含) |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
【業務詳細】 認証系または位置情報⇔カレンダー連携スマホアプリの開発に携わっていただける方を募集し…
週4日・5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービスアプリのサーバーサイド開発、または、社内業務を支援するツールの設計開発に携わっていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【案件概要】 既存のコーポレートサイトのリニューアルや新規事業部でのキャンペーンサイトやLP制作の…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP/Javascrip…
このたび事業拡大に伴い、サロン向け顧客管理システム開発に携わっていただけるフルスタックエンジニアを募…
週3日・4日・5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸伊勢駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
▼案件概要 MNOの新規・乗り換えの申し込みページ等の開発、また突発の案件対応やトラブル対応など…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Redux・nod… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇業務詳細 AWSインフラ(VPC周り、EC2、RDS、ELB、Route53等)構築案件における…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【C/C++ / 週5日】自社製品開発
【概要】自動ビルド/自動テスト/自動結果解析のためのテストの拡充とツール導入のための作業です。 …
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野阪上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C/C++ / 週5日】自社製品 CI …
【概要】 自動ビルド/自動テスト/自動結果解析のためのテストの拡充とツール導入のための作業をご担当…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
◇案件内容 既に稼働しているシステムに対する機能拡張の改修作業がメインになります。 オンプレ環境…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Oracle / 週…
◇作業内容 Oracle ERP Cloudに関わる以下業務 ①四半期アップデート対応 ②会計…
週5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモート】ネイティブアプリエンジニア…
■仕事内容 主力サービスのコミックビューア開発、および関連サービスにおけるネイティブアプリ(iOS…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア(ios/Android) |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / JavaPython…
案件概要 既存のECサイト全面刷新におけるフロントおよびバックエンドの機能開発を担っていただけ…
週5日
410,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】Q…
【業務概要】 現在、開発組織内や関係部署にて実施している品質保証を担うチームを立ち上げます。 チ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅/都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| 【詳細要件】 今回の業務委託採用の目的は下記点です… | |
定番
【インフラ / 週3日】ヘルステックベンチ…
グループ全社のクライアントPCやそれに付随するヘルプデスク業務をご担当いただきます。 【具体的…
週3日
170,000〜220,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】バ…
有名IPのバーチャルライブのUnityTimeLineでの舞台設定・演出(Liveコンテンツ)などの…
週5日
300,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| 【1日の流れ(例)】 ・各自、担当の作業をおこない… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
業務内容: EAIパッケージ製品を使用したアプリケーション開発です。 SFTPを使用し外部関連機…
週5日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【Android / 週5日】CtoC向け…
▼作業内容 CtoC向けアプリの開発をお任せいたします。 アプリの対象はAndroidで、言語は…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
【業務概要】 ・医療機器(ベッドサイトモニタ)向けPFにOSのポーティング作業を行って頂きます。 …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Linux/C++ …
【概要】 検体分注機およびPCモニタ機能開発における設計・実装・テストをご担当頂きます。 顧客よ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
▽作業内容 主に、個人プラットフォームのリニューアル開発を行っていただく想定です。 サーバーサイ…
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringBoot… | |
定番
【リモート相談可 / .NET / 週5日…
◇業務詳細 情報サービス会社向けMDM・共通機能再構築です。 主に先方の営業担当者が利用する「販…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・VB.NET… | |
定番
【Python / 週5日】健康保険組合加…
【案件概要】 健康保険組合加入者向けWebサービスのバックエンド開発をお願いいたします。 現在、…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
◇案件概要 小売業のECモールへの新規出店、出品、受注管理を行う業務システムの機能追加、改修ならび…
週5日
440,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
弊社は、企業のニーズに合わせたシステム開発及び、システム導入の企画・分析から設計・開発・運用支援まで…
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・Sprin… | |
定番
【Javascript / 週5日】IoT…
案件概要 大手メーカーより提供されているIoTデータ収集基盤において、フロントシステムからバックエ…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】ラ…
<業務内容> ・プロダクト(Web/iOS/Android)のUI/UXデザイン ・スクラム的な…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【セキュリティ / 週4日〜】自社セキュリ…
この度は、導入企業の増加に伴い、導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集いたしま…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
【具体的な募集内容】 自社プロダクトを支えるリードエンジニアを募集しています。 クラウド基盤の開…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【Java / 週5日】パッケージ基盤開発
案件概要 パッケージ基盤のアーキテクト開発です。 顧客製品の開発基盤(フレームワーク)のアーキテ…
週5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【組み込み / 週5日】電子決済端末評価の…
案件概要 電子決済端末に搭載する複数の決済機能の評価 作業内容 電子決済端末に搭載する複…
週5日
280,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿鴨居駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【事業概要】 戦略立案~制作/広告運用までデジタルマーケティングを一気通貫でサービス提供を行ってお…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【業務内容】 本件では、Windows PCに接続したWindowsのタブレット上で、PCに接続し…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
PaloAltoのSaasFWであるPrismaAccessを大手各社が導入する動きが高まっており、…
週4日・5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
当社クライアントの大手ゲーム会社様にてWindowsサーバチームのリーダー業務を担当していただきます…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週5日…
【業務内容】 ・コンテンツ作成(バナー作成、ホワイトペーパー作成、LP作成) ・ウェビナー運営な…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 コーディング業務をご担当いただける方を募集いたします。 デザイナーご経験をお持ちの…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】業…
お客様のPJが2つ進んでおり、こちらのPM業務を担っていただ終える方を募集しております。 ※詳しく…
週5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
この度は、社内アクセラレーションプログラムから生まれたスマートウォッチシリーズの開発に携わっていただ…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 /インフラ / 週5日】…
◇業務詳細 ネットワーク再構築を担っていただける方を募集します。 顧客で契約しているデータセンタ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Java/AWS/PostgreSQL】…
【業務内容】 エンジニアやデベロッパーとして、得意な領域をおまかせしたいと思っております。 開発…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルスタックエンジニア】多種多様なホーム…
・他企業とのコラボ案件をご担当いただきます。 →新規案件につき、要件定義~テスト、実装までお一人で…
週3日・4日・5日
250,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 神奈川湘南台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週5…
概要: EOSLに伴い、Iaas(既存Linux)をAzureに移行します。 設計工程~構築完了…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】オン…
すでにWEBアプリで公開しているオンラインマッチングサービスのiOSアプリ立ち上げに伴い、iOSエン…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【案件概要】 自社サービス開発・運用と多角的に事業展開をしているLHLで、主にバックエンドエンジニ…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
新規事業立ち上げにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきます。 サービスを運用すると同時…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】会計仕…
【案件概要】 この度は、サービス拡大に伴うPHPエンジニアを募集いたします。 現在、ドキュメント…
週5日
330,000〜480,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・当社… | |
定番
【リモート相談可 / 動画制作 / 週4日…
2ポジションで募集しています。 クリエイター -プロダクトグロースを狙ったマーケティング活動…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 動画制作ディレクター |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 クライアントかた受託しているビジネス向けテンプレート配布サービスのリニューアル案件へ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】Mic…
この度は事業の拡大に伴い、C#エンジニアを募集いたします。 【業務詳細】 ・クラウドサービス…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Nux… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【業務詳細】 3D空間上でバーチャルイベントを開催するプラットフォームの開発およびプラットフォーム…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【業務詳細】 3D空間上でバーチャルイベントを開催するプラットフォームの開発およびプラットフォーム…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
この度は事業の拡大に伴い、クラウドエンジニアを募集いたします。 【業務詳細】 ・クラウドサー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件概要 大手中古品小売業者の基幹システムの刷新 ◇案件内容 在庫管理や会計処理のほか各…
週5日
480,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java/Vue.j…
▼案件概要 この度は、新規で立ち上げている主婦向けの口コミアプリ開発に向けたフルスタックエンジニア…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・V… | |
定番
【フルリモ / PHP/Vue / 週3日…
この度は、オンライン学習サービスの追加機能開発をお任せするエンジニアを募集いたします。 ▼業務…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
【案件概要】 アプリケーションをクライアントの要望に合させてカスタマイズ開発をお願いいたします。 …
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 東京23区以外立川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
【業務内容】 ・自社健康診断パッケージのバージョンアップ 現時点では計画、立案が終わり、調査・分…
週5日
500,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇業務詳細 AWSインフラ(VPC周り、EC2、RDS、ELB、Route53等)運用案件における…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / C#/.NET / …
◇業務詳細 主に先方の営業担当者が利用する「販売見積受注システム」や「MDM」の再構築に際し、As…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / React/Pyth…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Scipy・Numpy・Scikit-Learn・P… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】M…
<募集背景> インフラ領域の運用エンジニアとして開発を推進していただく方を募集します。 <業…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
この度は事業の拡大に伴いエンジニアを募集いたします。 <募集背景> 事業拡大に伴う体制強化…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・Typ… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
①CentOSによる業務環境構築全般 ・DMZ構築 ・Dockerで仮想環境構築 ・ファイルサ…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開しています。 【案件内容】…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【求人概要】 CMS再構築プロジェクトの中核メンバーとしてフロントエンドエンジニアを募集します。 …
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・【今回の募集… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
この度社内システムの再構築に向けたエンジニア様を募集いたします。 下記プロジェクト内にてご希望や適…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・システムの再構築にあたって下… | |
定番
【Vue.js / 週5日】レンタル機器サ…
【案件概要】 弊社で受託開発を行っている、レンタル機器メーカーの基幹システムの構築のフロントエンド…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
■プロジェクトについて ・国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 ・睡眠および活動…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・【担当業務イメージ】 ■… | |
定番
【Unity / 週5日】スマホアプリのプ…
【運営事業】 ・Android/iOS向けのアプリケーション開発 ・ゲーム開発 ・VR/AR/…
週5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Unity・▼プロジェクト例 ・音楽関連の正… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 証券CRMシステムの刷新開発を長期間行います。 ・共通部品作成(サーバ、フロント)…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Java …
【案件概要】 ペット関連のWebサービスの改修、新機能開発です。 外部ベンダーで開発していたが、…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・J… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
◆案件概要 弊社の取引先企業様から直接案件を持ち帰り弊社のエンジニアチーム(ラボ開発)にてPJを受…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
プロジェクトについて ・国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 ・睡眠および活動計…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・【担当業務イメージ】 ■新規・・・修… | |
定番
顧客のブランディングに関わるWEBデザイナ…
■会社概要 顧客のブランディング支援事業やコンサルティング、広告・マーケティング支援を主軸とした…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】大手通信キャリ…
大手通信キャリアのサービスに係る様々なプロダクトのバックエンド開発をお願いします。
週4日・5日
180,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・GitHub・Enterprise・Cloud… | |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
この度は大手メディアとの協働に向けて、既存の独自CMSをWordPressにて置き換え可能か検証頂け…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / jQuery / 週3日〜…
この度は案件拡大に伴いWEBデザイナーの方を募集いたします。 【業務詳細】 現在請けている新…
週3日・4日
180,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / Angular/No…
【概要】 IoTクラウドサービスにおけるログ解析システム開発を担当頂きます。 -顧客より要求…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿北八王子駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Angular・No… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【案件概要】 不動産会社の情報システム部門にて下記の業務に携わっていただきます。 ①不動産仕…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
この度は大手家電量販店を代表に、多くのプロジェクトをご依頼いただいているため、新たな開発メンバーを募…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 プロダクトの大幅なアップデートのため、開発組織の責任者として、Paymeを一緒にグロ…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Go/Ruby / 週5日…
今後は単なるタクシー配車にとどまらず、タクシー利用者や、タクシー事業者に嬉しい機能を順次開発していき…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】飲食店…
この度は、新規サービスのネイティブアプリデザインを担当いただく方を募集しています。 【業務詳細…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Javascript/Ty…
弊社は動画レンタル配信サービスを運営する会社です。 【業務内容】 ・自社の動画配信サイトのア…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Electron・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件内容 一般的なWebJavaおよびAWSサーバレスアーキテクチャで構成されたシステムの運用要…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
【案件概要】 ゲーム事業部を新設し、自社サービスとしてゲームを開発を行っております。 サーバーの…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原末広町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【インフラ / 週5日】某大学向けコンピュ…
◇ 業務概要: 以下構成におけるコンピュータ室更改作業をご担当いただきます。 ・LDAP・ファイ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
▼ 業務内容 新規アプリを作成するのではなく、既にあるFXアプリを改修・機能追加して、他社向けのF…
週5日
730,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・iOS・- | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
▼ 業務内容 新規アプリを作成するのではなく、既にあるFXアプリを改修・機能追加して、他社向けのF…
週5日
720,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Android | |
定番
【リモート相談可 / 組込みエンジニア /…
【概要】 弊社製品の開発および検証業務に従事して頂きます。 -3~ 50名程度のチームのメンバー…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組込みエンジニア |
定番
【AWS / 週5日】損保・Webネット保…
業務内容: 損保会社様向けネット保険システムの企画・提案業務になります。 企画~開発までご対応い…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】医療系システム更改…
◇案件概要 医療系システムのハードウェア/ミドルウェア老朽化対応として、システムのリプレースを行…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / VB/PLSQL /…
◇作業内容 小売店の既存システムに対する保守案件の要件定義からリリースまでをご担当いただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
◇案件概要 3Dのバーチャル空間で多人数が同時接続するシステム構築 企画段階から参加をして、技術…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件概要】 大手鉄道会社から委託を受けているスマホアプリ開発を行うに伴い、インフラエンジニアを募…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
【案件概要】 自社で開発を行っているアプリの企画や設計、開発、運用といった全フェーズに携わっていた…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【C# / 週5日】物流管理システムリプレ…
◇案件概要 既存の物流管理システムのOS、ミドルウェアバージョンアップに伴うリプレイスを行っていた…
週5日
300,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【AndroidJava / 週5日】大手…
様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコアとした企業向けマーケティングソリューション…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【Swift / 週5日】大手不動産会社の…
様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコアとした企業向けマーケティングソリューション…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
業務詳細: 大手建設業向け経理システムに関するプロジェクト業務になります。 既存のシステムの改修…
週5日
440,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・自社FM | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
案件概要 ・電子書籍取次システム機能開発支援 ・電子書籍の取次に関するシステムの開発、保守運用 …
週5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務詳細】 弊社プロダクトにおけるバックエンド開発のリーディングを担当いただきます。主にはオンラ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Typescri… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
◇仕事概要 弊社は医師の研究や新薬開発をサポートし、医療の質向上を目指す、医療データ解析プラットフ…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
医師の研究をサポートするプロダクトにおけるUI/UXデザイナー募集しております。 【仕事内容】…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Adobe・XD | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
【業務内容】 ・Windowsサーバーの保守 ・SQLサーバーの保守 ・ルーター等ネットワーク…
週3日
140,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
◇概要 現在稼働中のシステム基盤の製品EOS対応を通じてパブリッククラウド上にシステムを移行する必…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 東北:仙台天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】就活…
【案件内容】 工学系学生に特化した就活支援サービスを行っており、企業ごとの選考時期や面接で何を聞か…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
◇職種:バックエンドエンジニア ◇プロジェクト概要 ・ニューノーマル社会の実現に向けたゼロト…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】子…
学校教育・民間教育・家庭教育に関するWebメディアやアプリ、システムなどの開発・運営や、勉強や受験を…
週5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
●案件概要 ・ネットスーパーシステムの企画・開発に携わっていただきます。 ・物流管理システムの企…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
【案件概要】 融資の申し込みを管理したり、社内稟議を回すなど金融機関や銀行で使用する 社内向けパ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
【案件概要】 今回は不動産業界のクライアント向けにSalesforceシステム開発を、要件定義以降…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】新…
<業務内容> ・ストーリーテストや探索的テスト、UATなどのテスト計画/設計/実施 ・開発メンバ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript/ 週…
【案件概要】 現在、国内外のWebニュースをクローリングし、HTMLからニュースタイトル、日付、本…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【AWS / 週4日〜】不動産売却領域サー…
【お任せしたい業務】 デジタルトランスフォーメーション事業本部の開発基盤グループに所属して以下の業…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / フルスタック / 週…
【案件概要】 ノーコードで高精度なAIモデル開発ができるシステムに関する開発業務に携わっていただけ…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務内容】 ネットワークの回線や装置の情報管理や、工事などの各種作業チケットの管理をしている業務…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
当社はゲーミフィケーションを応用した対話型アニメーション教材の研究・企画・開発と販売、学校・学習塾向…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【フルリモ / React/ 週3日〜】管…
主にデジタル領域において、システム開発やコンサルティングサービスを提供しています。 【案件概要…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【事業内容】 弊社では自社運営サービスの経験及び請負開発の経験を活かして企画提案型の開発/制作を行…
週3日
250,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【PM】toC向け電力アプリ開発のディレク…
【企業】 国内最大規模のデジタルマーケティング会社 業務内容】 ・toC向け電力アプリ開発のデ…
週2日・3日・4日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(ディレクター経験含む) |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
健康食品やサプリメントといった機能性食品の研究開発・製造・販売を手がけている会社のECサイト開発に携…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】自…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 自社が携わるサービスのQA業務をご担当いただけ…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| 【その他】 ・歓迎スキルは業務の中で教わり、習得す… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【概要】 主に下記の業務に携わっていただきます。 ①車載ECU向け基本ソフトウェアの開発 ②上…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C++ / 週5日】工業用顕微鏡アプリケ…
【概要】 工業向け顕微鏡 ARアプリケーション開発を担当頂きます。 -顧客より要求をヒアリングし…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
弊社は、Webアプリケーション、Webシステム開発では最新プラットフォームや、フレームワークを用いた…
週3日・4日・5日
410,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】テス…
【事業内容】 ・ICTソリューション事業 ・システム開発事業 【案件概要】 すでに開発済…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / システム / 週3】調査・…
【案件概要】 某携帯電話の情報配信サービスにて、キャリア公式の読み物コンテンツを CMSによる運…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】EC…
【業務内容】 今回は、弊社がおこなっている事業の中でもデジタルコンテンツ事業における、「ECサイト…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿蒲田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
【案件概要】 新規スマートフォン向けRPGゲームのクライアントサイドエンジニアとしてゲームアプリ開…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / データ / 週5日】…
【案件概要】 大手通信会社の共通ポイント事業部署におけるデータ分析、ご提案 Excelデータ…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
<募集背景> 今回は自社サービスとして新規のアプリ開発を行う予定で メンバーとして参画いただける…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
【業務内容】 弊社プロダクトにおけるフロントエンド開発をメンバーとして担当いただきます。 クライ…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Nux…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / システムエンジニア/ 週5…
【PJT概要】 Salesforce(Classic)のカレンダーをOffice365(Excha…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / React/Ruby / …
企業評価をスコアリングするためのサービス開発を行います。 企業ごとのスコアリングの結果を表やグラフ…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Java/C# / 週5日…
【業務内容】 下記2つのいずれかの業務に携わっていただけるリードエンジニアの方を募集いたします。 …
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【案件概要】 このポジションでは、AIアルゴリズムを利用したスマホアプリ(画像&動画を解析→ユーザ…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
<業務内容> 下記の業務に携わって意tだきます。 ・PC/モバイル向けWebアプリ、ワイヤーフレ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【Angular/Node.js / 週5…
【概要】 顧客の社内向けWebアプリケーションであるメトリクス可視化システム開発をご担当頂きます。…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件内容 下記の業務をメインでご担当いただきます。 ・ID決済を提供するサービスに対し、店舗、…
週5日
350,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
■ご依頼業務 社内ネットワーク運用・改善を中心に、各種ITサービスや、PC・スマートフォンなどの管…
週3日
190,000〜230,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
【概要】 次世代ドローン向けの、サーボマイコン向けの組込みSW設計、開発を行って頂きます。 …
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
【概要】 3D自律移動ロボットのSW開発・品質向上・保守を行って頂きます。 -ロボット内で動…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【案件概要】 ゲーム開発における、APIの開発をお願いします。 DB設計やAPIの設計から携わり…
週4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Javascript/Ty…
自社プラットフォーム開発におけるスマホアプリエンジニアの業務を依頼します。 【業務内容】 ・…
週3日・4日
260,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Go/Java / 週3日…
自社プラットフォーム開発におけるスマホアプリエンジニアの業務を依頼します。 【業務内容】 自…
週3日・4日
310,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概略】 福利厚生関連システムにおける、キオスク端末向けシステムリプレイス業務を担っていただけ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python/C++ / …
【案件概要】 このたび、弊社の画像解析アプリを用いて、機器メーカーとPoC(実証)をやることになり…
週3日・4日・5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
▼案件概要 当社はWebメディアを運営しています。 この度は、新規メディアの立ち上げやアプリ開発…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件概要】 弊社AWS事業全般に関わって頂けるポジションです。当職種では、AWS導入の提案から保…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇開発内容 ①フロントエンド 顧客から受けているシステム(動画配信、求人検索、レッスン管理システ…
週3日
160,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要 iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のネイティブアプリケーション…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【インフラ / 週5日】医療系システム更改…
◇案件概要 医療系システムのハードウェア/ミドルウェア老朽化対応として、システムのリプレースを行っ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
健康食品やサプリメントといった機能性食品の研究開発・製造・販売を手がけている会社のECサイト開発に携…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
今回は子育て支援サービスに関するアプリの開発に携わっていただけるアプリエンジニアの方を募集いたします…
週3日・4日・5日
660,000〜1,340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【概要】 医療システムの開発。設計~実装~テストまで一貫して担当頂きます。 -アプリ層へのI…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Python/C++…
▼案件概要 デジタル複合機向けの検査機能開発(GUI、画像処理、マイコン制御)を担当頂きます。 …
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【概要】 -弊社製 FAT/exFAT ファイルシステム製品の機能拡張/改修。 -他社製Linu…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C++ / 週5日】ネットワークカメラ機…
【概要】 主にネットワークカメラ機器向けのSW設計・実装をメインに行なっていただきます。 直近で…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】建…
この度は、建築業界のタスク管理ツールのUI/UXデザインを担当いただけるデザイナーさんを募集いたしま…
週5日
240,000〜280,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
この度は、不動産業界中心にシステム開発をになっていただけるバックエンドエンジニアを募集します。 動…
週5日
300,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / テストエンジニア /…
■募集目的 現在は、Googleフォームの開発に向けた詳細設計を行っています。 その後フォームの…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| GAS | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】来…
来客者受付アプリ(iOS/iPad)の調査・改修 アプリ改善点の調査、作業設計を行い、改修を行って…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・CocoaPod・Cartha… | |
定番
【Vue/Laravel / 週5日】国内…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務です。 1機能単位で設計からテスト…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
今回は、弊社のサーバーサイドのエンジニアを募集します。 ▽業務内容 主に下記の業務をご担当…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
弊社で運営しているサービスのWebデザイン、販促物作成を依頼致します。 【業務内容】 ・webデ…
週3日
90,000〜250,000円/月
| 場所 | 神奈川鎌倉駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
【業務内容】 ・障害発生時の原因調査、不具合対応 ・問い合わせに対する調査、回答 ・改善要望の…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
【案件情報】 未経験でも以下の業務に興味がある方を募集しています。 ・AWSおよび社内情報システ…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Angular / 週4日…
◆会社概要 CX(顧客体験)調査からデータ分析・改善までを行っております。 顧客満足を計測・分析…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Typescript・Angular | |
定番
【フルリモ / Linux/AWS / 週…
◆会社概要 CX(顧客体験)調査からデータ分析・改善までを行っております。 顧客満足を計測・分析…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
●概要 運用設計、運用テスト、訓練実施、運用保守 -運用作業管理、運用監視、バックアップ管理 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Java /…
【業務内容】 チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】DX推進支援プロジ…
◇案件概要 弊社はテレワーク導入企業に向けたDX推進支援プロジェクトを進めています。 具体的には…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / DB / 週4日〜】インフ…
【業務内容】 新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務していただきます。 …
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Go・・コンテナ基盤の設計、導入、検証、テスト ・… | |
定番
【フルリモ / DB / 週4日〜】インフ…
【業務内容】 新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務していただきます。 …
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | アジャイル開発エンジニア(DB) |
| Go・・コンテナ基盤の設計、導入、検証、テスト ・… | |
定番
【リモート相談可 / Salesforce…
◇案件概要 某金融グループにて、業務改善のため既存システムからSalesforceに移行予定です。…
週5日
740,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
■ご依頼業務 自社ショッピングのサービス開発の業務をお任せします。 提供するサービス ・バ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・C#・Unity | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】フリ…
【業務内容】 C2C向けフリマサービスのWEBアプリ開発業務をしていただきます。 数名のチームメ…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / スマホアプリ / 週…
■ご依頼業務 自社ショッピングのサービス開発の業務をお任せします。 提供するサービス ・バ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【事業内容】 ゲームの企画・開発・運営 スマートフォンアプリの企画・開発・運営 業務系システム…
週5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【事業内容】 ゲームの企画・開発・運営 スマートフォンアプリの企画・開発・運営 業務系システム…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Javascript/ 週…
【案件内容】 自動運転関連プロジェクトのWebアプリケーション部分のフロント開発 【業務内容…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿和田塚駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社で開発したプロトタイプのアプリをベースに、それをクラウドサービス化するプロジェクトの開発担当エン…
週3日・4日
450,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Javascript/No…
【案件内容】 自動運転関連プロジェクトのWebアプリケーション部分のフロント開発 【業務内容…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿和田塚駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】法人…
【具体的な仕事内容】 ・Ruby on Railsを利用したバックエンド開発 ・Vue.js, …
週5日
570,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇案件概要 APIManagerのDevelopperPortalの刷新のため、新規で構築を行って…
週5日
440,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java | |
定番
【Rubyエンジニア】自社サービスの追加開…
【業務内容】 自社サービスにおけるRubyエンジニアを募集しています。 ※詳細はご面談の際にご説…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談OK/ テックリード/ 週5…
【担当業務】 - 自社SaaSプロダクトのメインシステムのリプレイスに関わる業務全般 Lテック…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(リードエンジニア) |
| Python・Java | |
定番
【Goエンジニア】最高の決済体験を追求する…
【業務内容】 ■決済基盤開発・運用 今後のスケーラビリティに耐えうるために、 2500億円規模…
週4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(バックエンドエンジニア) |
| PHP・Go・Typescript | |
定番
【バックエンド開発】自社サービスに伴う開発…
■認証・認可基盤開発・運用 開発組織ではマイクロサービス化を推進しており、 その最初のプロジェク…
週4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(バックエンドエンジニア) |
| PHP・Go | |
定番
【PM】大手証券会社でのシステムリスク管理…
【業務内容】 システムリスク管理、システム企画・開発・運用管理及び外部委託管理、サイバーセキュリテ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【バックエンドエンジニア】自社サービスのス…
・次世代版実行者向け管理画面の開発/運用 プロジェクトの開始前から完了のサポートまで、 実行者が…
週4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(バックエンドエンジニア) |
| PHP・Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
下記の業務をお任せします。 ・連絡窓口の設置、保守対応性の維持 ・調査及び確認作業、技術的な問い…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
・当社が提供する決済システム&サービスの要件定義~設計~開発~テスト~商用リリースおよび運用~サポー…
週4日・5日
480,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 自社プロダクトをPHPのLaravelで開発しております。今回は社内ツールの作成や、…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
スポーツビジネスの活性化は上記の課題の多くを解決出来る可能性を秘めています。 我々はテクノロジーを…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / C++ / 週4日〜】建築…
【業務内容】 ・アルゴリズム開発 ・アーキテクチャ設計 ・プロトタイピング、具体的な機能開発 …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【仕事内容】 Web開発エンジニアとして以下の業務を中心に上流工程からコーディング、テスト、バグ修…
週5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Node.js・E… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ク…
現在、案件の規模が大型化してきている状況を受け、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀…
週3日・4日・5日
410,000〜590,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大型サイトのリニューアルに伴いテストが始まるため、テストエンジニアとして人材を募集しています。 モ…
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【フルリモ / Java/SpringBo…
プロジェクトB:他社ECサイト製品ページのクローリング プロジェクトC:他社ECサイト購入履歴のス…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週3日…
【案件概要】 業務のデータ処理の自動化システムを作成していただきます。 csv読み込み → デー…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Scala/Kotl…
▼業務内容 ・キャディのオペレーションチームや、顧客、サプライパートナーの利用するシステムのバック…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java/C++ /…
【業務概要】 下記の業務をご担当いただきます。 ①車載ECU向け基本ソフトウェアの開発 ②上記…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務概要】 ・追加機能の基本設計 ・結合試験仕様書作成、試験支援業務 サーバーサイドのアプリ…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日…
このポジションでは、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべ…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
東証一部のガス会社から直請けの案件(業務システムの開発DX推進)に携わっていただきます。 5名チー…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・Gt・Docker | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【リモート相談可 /UI/UX / 週5日…
▼運用中開発タイトルにおける下記業務をご担当していただきます。 ・画面遷移制作 ・画面レイアウト…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Illustrator/P…
【業務内容】※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 主にマーケティング活動で使用するWeb/グラフ…
週3日・4日
190,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【週3~/フルリモ/Go】国内No.1オン…
・将来スケールが可能かつ反復型/自律的開発を可能にするアーキテクチャのカルチャーをチームを超えて醸成…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(テックリード) |
| PHP・Python・Go・Typescript・-… | |
定番
【フルリモ / PHP/ Python/ …
【業務内容】 ・社内の簡易ツールシステムの開発を行っていただきます。 ・言語選定も自由です。 …
週3日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】新規…
▼案件概要 当社は情報系Webメディアを運営しています。 この度は、リリースしたばかりのiO…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
【案件概要】 開発リーダーから要件をヒアリングしPPTで要件書の作成を行い、要件書をインプットに外…
週5日
440,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】開…
【プロジェクト概要】 各プロジェクトのインフラ専門チームとして、以下の業務を行います。 ・弊社I…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
多くのECスタートアップに利用されているRubyonRails製のオープンソースECパッケージをベー…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・‐ | |
定番
【C/C++ / 週5日】3次元画像処理シ…
【業務概要】 画像や映像から立体形状を復元する3次元画像処理システムの検証、アルゴリズム検討、実装…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
【案件概要】 デジタルカメラ・カムコーダの評価・リリース作業をお任せします。 -各種デジタルカ…
週5日
220,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件概要】 デザイナーチームと密にコミュニケーションを取りながらHTML/CSSでのコーディング…
週3日
310,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS | |
定番
【Java / 週5日】レーザー顕微鏡開発
【業務概要】 レーザー顕微鏡開発(顕微鏡制御・GUIアプリケーション)において、設計~実装~テスト…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
◆案件内容 現在、配送ドライバーの業務全般を支援するアプリを開発中。 …
週5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React/HTML / …
・案件内容 新規開発と機能改善に伴う改修双方を担当・フロント エンドの開発/運用 ・対象 …
週5日
300,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
案件内容 : ポータルサイトのリニューアル開発案件です。 個人プラットフォームのリニューアル開発…
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Coldfusion…
【案件概要】 大きな顧客基盤を持つ自社採用管理システム「RPM」の新機能追加や、新規開発案件をお任…
週3日・4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Coldfusion・fusebox | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【業務概要】 -主に組込み系システム(Linux)の上で動作するアプリケーションの開発にも携わって…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| JavaScript・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / サーバーサイド / …
RPAなどを用いてECサイト運用にあたる各種業務の自動化、商品ページ自動生成する仕組みを作れるエンジ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【.NET / 週5日】販売管理基幹/生鮮…
作業内容 :1.小売店の既存システムに対する保守案件の要件定義~リリース (2種類) 画面、バ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
自社で新規開発しているクリエイターのスキルシェアマーケットにおけるUIデザイナーを募集しております。…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React Nati…
【案件概要】 某大手カー用品企業にてリリースしているカスタマー向けアプリ(iPhone/Andro…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件内容】 ポータルサイトのリニューアル開発です。 個人プラットフォームのリニューアル開発を担…
週5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Nuxt.js/Vue.j…
【案件内容】 通常業務としては、以下を想定してます。 ・デザインモックアップに基づいたフロントエ…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
【業務概要】 -主にカムコーダのUI操作系(Menuなど)や各種機能に基づくMWとのIF開発におい…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C++ / 週5日】デジタルカメラネット…
【業務概要】 -主にデジタルカメラ機器向けのネットワーク機能開発におけるSW設計・実装をメインに行…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
◇案件概要 医療系カルテの管理システム開発の一環で進んでいる、美容形成外科専用の予約システムデザイ…
週3日・4日・5日
330,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【Vue.js / 週5日】法人向けネット…
▼案件概要 法人向けネットワークサービスの商用リリース前のPoC環境にて動作するWebアプリ開発で…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【Node.js / 週5日】法人向けネッ…
▼案件概要 法人向けネットワークサービスの商用リリース前のPoC環境にて動作するWebアプリ開発で…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
<業務内容> Androidエンジニアを募集します! 少人数での開発になりますので、アプリの開発…
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Python・Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 /Java / 週5日】…
◇案件概要 モバイルソリューションの開発に携わっていただきます。 新しい製品の提案はもちろん、最…
週5日
240,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
<業務内容> 高品質のホワイトペーパーを誰でも簡単に制作できるSaaSサービスの運営をしております…
週3日
190,000〜220,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・N… | |
定番
【フルリモ / Salseforce / …
<業務内容> 不動産仲介業務で使用する業務システムの開発をお願いします。 cloudサービス…
週3日・4日・5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| JavaScript・Apex | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【案件内容】 自社CtoCサービスをサービスをグロースしていく上で、開発全般をお任せできるテックリ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】データ分…
■具体的な仕事内容 ・システムの安定稼働に向けた機能設計・開発・運用 ・障害/不具合対応 ・テ…
週5日
480,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / CSS/TypeScrip…
■業務概要 -PMFに必要な新機能の実装や全体的なUIUX改善リニューアルをメインに今後進めていく…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
■業務概要 -PMFに必要な新機能の実装や全体的なUIUX改善リニューアルをメインに今後進めていく…
週3日・4日・5日
570,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
●案件内容 ムービーサービスにおいてフロントエンド、バッグエンドのシステム開発をしていただきます。…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| Typescript・Node.js・React | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】仮…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・日本商品の海外向けECサイトの運用を支える基盤システムの運用/管理をご担当いただきます。 ・自社…
週5日
360,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP/Wordpr…
自社サービスのサーバーサイド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定買取と販売を主…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【業務内容】 ・障害発生時の原因調査、不具合対応 ・問い合わせに対する調査、回答 ・改善要望の…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】自社事…
【主な仕事内容】 開発・分析業務の補佐していただきます - マスタデータ整備 - SQLを…
週5日
570,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
| SQL | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【事業紹介】 ビジネスプロダクト事業 ITソリューション事業 ゲームコンテンツ事業 【案…
週3日・4日・5日
570,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / JavaScript/Nu…
【事業紹介】 ・システムインテグレーション事業 (買取・販売業務、店舗間在庫連携、卸業者との受発…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川青葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Nuxt.js・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
【業務内容】 今回は、当社製品のフロントエンド開発を行っていただける方を募集します。 デザイナー…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Next… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Java / 週…
【事業紹介】 ・システムインテグレーション事業 (買取・販売業務から、店舗間在庫連携、卸業者との…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川青葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
■募集ポジション 開発PJTのLDR(PMはプロパー。PMから下記内容を依頼する予定) ■…
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
■募集ポジション 開発PJTのLDR(PMはプロパー。PMから下記内容を依頼する予定) ■…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄旭橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
▼業務内容 ・5~6年前にリリースした基幹システムおよび公開サイトの共通部品のメンテナンスおよびア…
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台、新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js・【チーム体制】… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 【募集ポジシ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・React(react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / React.js/Type…
更なる事業拡大に伴い、新メンバーを募集することになりました。 【具体的な業務内容】 ・航空券予約…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Three.js /…
◇プロジェクト概要 5Gを活用したフラッグシップサービスの開発です。 ※フラッグシップサービスと…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・-・Three.js | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
更なる事業拡大に伴い、新メンバーを募集することになりました。 【具体的な業務内容】 ・航空券予約…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【具体的な業務内容】 航空券の比較販売サイトのインフラの新規開発、安定運用を行うことがミッションで…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】オン…
<業務内容> 日本最大級オンラインギフトプラットフォームのサーバーサイド開発を担当いただきます。 …
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Git・Fluentd・Sentry・Dat… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
◇案件概要 外資系企業内のシステム基盤運用・構築 様々な分野・産業に対し戦略、業務、ITなどのあ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】オンラ…
<業務内容> 自社プラットフォームのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ソフトウェアエンジ…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Go・Git・PHP・Fluentd・Sent… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社の経営チームに置ける技術サイドの責任を担い、開発組織の立ち上げをリードするCTOを担っていただけ…
週5日
610,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
当社のtoC向けサービス「Schoo」のスマートフォンアプリ開発をご担当頂きます。 ●具体的には …
週3日・4日・5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
Webサイト開発、改修のフロントエンドエンジニア業務を依頼します。 【業務内容】 ・実装、レ…
週5日
350,000円以上/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【案件詳細】 弊社既存サービス 国内初のセルフオーダーシステムのデザイン業務 【概要】 …
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ₋ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
◇案件詳細 役割:クラウドネィティブシステムの 維持、改善サポート - マルチクラウドから A…
週5日
570,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
急募
【フロントエンドエンジニア】サイト制作に携…
【企業概要】 Web・グラフィック・広告制作を事業展開する企業でご就業いただけるエンジニアの方を探…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸五条 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【マーケター】最先端スマート家電のYout…
【案件概要】 YouTube・SNSのアカウント運用 (スマート家電ロボットの認知拡大が目的) …
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【フルリモ / UE4 / 週4日〜】ゲー…
オリジナルのゲームエンジンや最先端のグラフィックス技術を活用したハイエンドマルチプラットフォームゲー…
週4日・5日
520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| UE4 | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】大…
【案件概要】 自社副業マッチングサービスにおけるバックエンド開発/保守を行っていただけるエンジニア…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件概要】 自社副業マッチングサービスにおけるフロントエンドの開発を行っていただけるエンジニアの…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【Linux / 週5日】EPCコアネット…
◆案件内容 EPCコアネットワークの試験環境を構築します。 開発に必要なビルド環境や自動化シェ…
週5日
240,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小杉駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
【案件内容】 今回は自社管理ツールのサーバーサイドエンジニアを募集します。 ・PHP/Larav…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
案件内容 下記の業務をご担当いただきます。 ・C to C向けスマホアプリの機能追加、機能改修。…
週5日
350,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【AWS / 週5日】GPS課金対応
案件概要 既存システムからのインフラ変更、最適化 業務内容 ・既存システム環境(AWS)か…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
【案件概要】 主にデータ移行処理をご担当いただきます。 ①Sharepointの移行 not…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件概要】 自社サービスで展開をしているAIカフェロボットの開発を進めていただきます。 ・…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 年賀状のデザインレイアウトの選択サイトをECサイト風に構築していただきたいと思ってお…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務内容】 ・年賀状サイトシステム(バックエンド側)の構築 ・管理画面やCSV登録などにより、…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務内容】 年賀状のデザインレイアウトの選択サイトをECサイト風に構築していただきたいと思ってお…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】プログラ…
▼案件概要 サーバーサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発やインフ…
週5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Rubys / 週3日〜】…
【業務内容】 システム開発の事業として2軸ございます。 お客様の要望に合わせてオーダーメイドのシ…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rubys / 週5日】運…
【業務内容】 システム開発の事業として2軸ございます。 お客様の要望に合わせてオーダーメイドのシ…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / HTML5/CSS / 週…
今回は事業急拡大に向けて、新しいメンバーを募集致します。 <業務内容> ・Webページのデザイン…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・Illustrator・Photo… | |
定番
【フルリモ / HTML/Javascri…
今回募集するポジションでは既存メディアおよび新規事業サービスの企画、およびコーディング全般をお任せし…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP/ 週4日〜】自社メ…
今回は事業急拡大に向けて、新しいメンバーを募集致します。 【職務詳細】 ・自社サービス施策の要件…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・WordPress・Solr… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【職務内容】 ・自社サービスと運営を支えるバックエンドシステムの設計・実装 ・行動ログなどの定…
週4日・5日
520,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Javasc…
<会社概要> ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Postgre… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
<会社概要> ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
<会社概要> ホスピタリティ事業として宿泊先仲介プラットフォーム事業を展開している企業になります。…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
■PJT概要 基幹システムのリプレイス ■募集ポジション 要件定義・開発メンバー 基本的…
週5日
570,000〜8,030,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・ReactJS… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【案件概要】 主に下記の業務をご担当いただきます。 -車載ECU搭載 非接触IC(NFC)/C…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
【概要】 主に下記の業務をご担当いただきます。 -車載ECUソフトの評価・受入対応。 -要件定…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Javascript/Ty…
弊社クライアントの受託開発案件にご参画いただきます。 生保業界向けネイティブアプリ開発となります。…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / 組み込み / 週5日…
◇案件詳細 ・Media Foundation APIでアプリ等からカメラデバイスとしてアクセスで…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
■役割:クラウドネィティブシステムの 維持、改善サポート ・マルチクラウドから AWSへの移行(一…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Java/Scala / …
◆主な業務内容 ・EmotionTech CX / EX のマイクロサービス化、既存システムの改良…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】シス…
【案件内容】 システム開発に特化した発注先選定支援サービスを Rails / AWS(場合によって…
週5日
300,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails・react | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
ヘルスケア業界向けの自社SaaSプロダクトであるAI姿勢分析システム及び電子カルテの急成長に伴い、フ…
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
経営サポートシステムリニューアルに際して、基幹システムのリプレイスのご依頼となります。 ■募集…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・ReactJS… | |
定番
【フルリモ / Python/JavaSc…
小売企業向けサービスの今後の開発に関わっていただくことがメインとなります。 その他の弊社サービスに…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】クラ…
◇プロジェクト概要 弊社では、法人のお客様向けにWebサービスを提供しております。 サービスの立…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | 【Java】Web開発エンジニア/管理画面のSPA開発,SAML・OIDCの認証機能開発 |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
最先端のアルゴリズムを開発する会社であるため、機械学習やMLOpsに興味がある方を歓迎します。 …
週5日
170,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails・Dj… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】自…
自社で展開しているSREサービスに従事する、クラウドエンジニアを募集しております。 ■業務例 …
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Go・GCP・AWS・Azure・Do… | |
定番
【フルリモ / JavaScript/Ru…
小売企業向けサービスの今後の開発に関わっていただくことがメインとなります。 その他、弊社サービスに…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】オン…
■業務内容 ・新規サービスのシステム開発(メイン) ・商標登録を安心、カンタンにできるようにする…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】ホテ…
【仕事内容】 Tabiqチームの中で話し合って決めた、プロダクトの方向性に沿って開発をしていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿博多駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・AWS | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】プロダ…
【業務詳細】 ・事業における新規プロダクト・サービス企画およびプロダクトマネジメント ・新規プロ…
週4日・5日
570,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
現在会社の成長に伴い、請負案件にて開発リソースが不足しております。 WEBアプリケーション開発にて…
週5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
【業務概要】 下記の業務をご担当いただきます。 3D自律移動ロボットのSW開発・品質向上・保守 …
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
急募
【戦略立案】医療ビックデータの活用PJTで…
【案件】 医療系ビッグデータを取り込み製薬会社など向けに利活用する方法を提案 【業務内容】 ・…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
ヘルステックサービスアプリのUI/UX統一から、店舗での販促資材、医療機関HP向けのデザインまでサポ…
週3日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
【案件の内容】 ACESの画像認識アルゴリズムの提供基盤をさらに展開するにあたって、iOS/And…
週3日・4日・5日
240,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Python・Swift・AndroidJava・K… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件の内容】 アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード…
週5日
220,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【リモート相談可 / C#/C++ / 週…
当社ではWEBサービス開発を行っていただける、スマホアプリエンジニアを積極的に募集しております。 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・案件による | |
定番
【リモート相談可 / RubyonRail…
バックエンドエンジニアとして、チャットボットを構築運用するWebアプリケーションを中心に機能拡張を進…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】
大学の願書出願システムの継続開発案件において、以下をお任せします。 ・機能追加 ・不具合修正 …
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| CSS・JavaScript・Ruby・Rubyon… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
<プロジェクト例> ・当社が全面的に運用している会社四季報オンラインが、リニューアルから3年を迎え…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・<ポイント> ①日本を代表する大企業… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 -クラウドサービス(マルチカメラライブ)向けの設計・実装・評価を行っていただきます。…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 神奈川新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / JavaScript/Ru…
【仕事内容】 従業員の成功を加速させるオンボーディングプラットフォームの採用 ・組織/人事領域の…
週3日・4日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
UI/UXデザイナーとしてiOS向け音声アプリのデザイン、今後の機能アップデートやAndroid版、…
週3日・4日・5日
330,000〜480,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
iOS向け音声アプリの開発に関わっていただきます。 (順次Andoroidブラウザアプリもリリース…
週3日・4日・5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しており、企業や個人のお客様にショッ…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・AmazonMWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【仕事内容】 3次元都市データ上での水の流体表現アプリケーション開発 1)3次元都市データ上…
週4日・5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【AWS】大手採用情報サイトシステム運用保…
【企業】 同社のクライアントは業界大手ばかりです。またほとんどのプロジェクトで直接取引をしている為…
週4日・5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Python/SQL / …
業務内容としては、データ解析と医療機器開発です。 弊社は自主性、対話、スピード感を重んじており、弊…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・SQL・SciPy | |
定番
【フルリモ / React/Javascr…
【募集背景】 開発経験とスタートアップへの興味がある方を募集しています。 【仕事内容】 ・…
週3日・4日
330,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】自社…
既存の基盤を元に、β 版をリリースする予定です。 面談では製作中の未公開プロダクトもお見せしながら…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フロントエンドエンジニア】新規サービスの…
【業務内容】 ・オンライン面談の新規サービス立ち上げ WEB申し込み、面談予約などの機能開発 …
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
【エンジニア】美容サロン集客サイトの開発
【業務内容】 美容サロン集客サイトの開発で0→1フェーズで依頼いたします。 【環境】 マー…
週3日・4日・5日
2万円以上/日
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【PM】ライブコマース事業のPM
【業務内容】 ライブコマース事業にて、新たなライブコマース開発のPMポジションを依頼いたします。 …
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 中国・四国高松駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java】物流管理システムの開発
大手の家具製造小売業です。消費者から受けた注文に対し、最速で商品を届けるためのシステム全般を開発しま…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿王子神谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java Vue.js SpringF… | |
定番
【スクラムマスター】航空券予約管理システム…
大手航空会社。国際線・国内線のサービス、システムを統合し、利用者の利便性を高めるための開発です。 …
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スクラムマスター |
| Java・Java AWS SpringBoot… | |
【急募】大手テーマパークのマーケットリサー…
【企業概要】 国内・海外を問わず様々な企業のリサーチなどをてがける企業にて 大手テーマパークのマ…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | リサーチャー |
| R | |
【C/C++】組み込みエンジニアとしてIO…
■業務詳細 ・自社開発中のIoT製品はもちろん、受託開発においてはお客様から多様な依頼をいただくた…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
【コーダー】メディア開発(PHP/Word…
自社メディアの開発プロジェクトです。 PHP特にWordPressを利用した開発を行なっていただき…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【データエンジニア】海事分野におけるデータ…
現在、船舶の電気に関するトラブルシューティングを高度化するためのデータ分析を主に取り組んでいます。 …
週4日・5日
670,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
定番
【Java / 週5日】大手運輸・物流系シ…
【業務概要】 大手運輸・物流系システムの機能改善業務になります。 主に詳細設計、開発支援、受入テ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・VB.NET | |
定番
【フルリモ / Nuxt/Vue / 週4…
スポーツビジネスの活性化は上記の課題の多くを解決出来る可能性を秘めています。我々はテクノロジーを活用…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt・V… | |
定番
【リモート相談可 / テスター / 週5日…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトにおきまして、SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週5日
460,000円以上/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
【業務概要】 リアル決済領域に関わる各種プロダクトを使用した、SWテスト、UiPathやAster…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Uipath・ASTERIA | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 今回は、既存BtoC画面の追加改修(要件定義からリリース、運用まで) 他社開発シス…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot・JQuery・My… | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【案件概要】 今回は、銀行オンラインサービスOEM提供対応を担っていただける方を募集します。 イ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・Type… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】ブ…
【業務内容】 新規事業として、スマホアプリのブロックチェーンゲーム開発を予定しており、立ち上げから…
週5日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity・▼運営事業・・・ ・プログラミン… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/SQL / …
【業務内容】 PHP / JavaScriptを使用し、受託開発の案件にご参画いただきます。 大…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄直方駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【Java/PHP / 週5日】メディアサ…
【案件概要】 メディアサイトの会員管理システムの要件定義、設計、実装、テスト、運用をご担当いただき…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Seasar… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
◇案件概要 キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Shell・SQL | |
定番
【SQL / 週5日】小売店向けの業務シス…
【案件概要】 売店向けの業務システムの保守案件です。 要件定義~リリース、保守まで、開発工程全般…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / ABAP / 週5日】検索…
SAP ABAPを使用して検索アルゴリズム・検索システムの開発を遂行していただきます。 1) ソフ…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ₋- | |
定番
【Swift / 週5日】iPadアプリケ…
【案件概要】 iPadアプリケーションソフトウェアの設計、コーディング、テストまでご対応いただきま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・XCode | |
定番
【リモート相談可 / React/Type…
【募集概要】 リリースから間もない段階ですが、既に多くの店舗でご利用いただいているサービスです。 …
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React.js/Vue.…
AI技術を用いて法律業務の効率化や法務経営の実現を目的とするリーガルテックサービスを開発しています。…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Angular.… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】Lega…
【業務内容】 ユーザーの課題を解決しプロダクトを成長させるために開発・改善業務を担当していただきま…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 /システム / 週5日】…
<業務内容> ・ストーリーテストや探索的テスト、UATなどのテスト計画/設計/実施 ・開発メンバ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【会社概要】 業務系のシステム開発メインに元受けの受託開発を専門の企業になります。 【業務内…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大森駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / ASTERIA / …
【事業内容】 ・ICTソリューション事業 ・システム開発事業 【案件概要】 今回は弊社が…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| ASTERIA | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】W…
Webアプリケーションエンジニアの方には、AAIプラットフォームの拡張、新サービス開発、他社アライア…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】自社プラ…
【業務内容】 今回は自社で運営している自動車産業ポータルサイトのコーディング業務をメインにお願いし…
週4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / C /C++ / 週…
【業務概要】 車載向けSKB(Smart Key Box)向けのデジタルキープラットフォーム(認証…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リAndroidJava / 週5日】A…
【案件概要】 今回は、Androidアプリケーションソフトウェアの設計、コーディング、テストをご担…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・AndroidStudio | |
定番
【AWS / 週5日】Citrix Vir…
現在、BCP環境として同様の環境を別箇所にも構築しSQLサーバーを同期させる方法で構築する予定です。…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築を行って…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】
◇会社概要 フリーランスドライバーをつなぐマッチングプラットフォームや、ドライバーなど物流に関わる…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Sketch・Illustrator | |
定番
【インフラ】Oktaを介したインフラエンジ…
【作業内容】※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 弊社のクライアント企業である某鉄鋼メーカー様に…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 神奈川鶴見駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【C# / 週5日】社内分析系システム開発…
【業務概要】 現在構築されている社内分析系システムを外部に提供できるように機能強化をしていきます。…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Azure | |
定番
【週5/.NET/フルリモ】確定拠出年金シ…
【会社概要】 Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・データ放送コンテンツ等の制作・開…
週5日
8〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
◇業務内容 地図アプリの作成における、以下の業務をご担当いただきます。 ・ PMとPGとのつなぎ…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Rea… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】決裁シ…
◇業務内容 ・決済(クレカ等)システムサーバー構築 ・決済画面フロントエンド制作 ・ライセンス…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【募集内容】 自社サイトの更新に伴うコーディングをメインにご担当いただきます。 【業務内容一…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobePhotoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
◇案件詳細 顧客Modern ITロードマップ策定におけるWindowsAD DS設計・導入、Az…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer・ActiveDirect… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
◆ 内容 ・某ネット銀行様(エンドユーザー企業)での新規サービス構築、新認証方式導入などを設計、開…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅、大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】移行…
【業務概要】 主に下記の業務に携わっていただきます。 ①Sharepointの移行:notesま…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| sharepoint・Exchange | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】介護…
◆内容 ・医療や介護業界向けのサービスを展開している企業様にて介護事業会社向け経営支援システムの運…
週5日
500,000〜900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / PHP/Laravel /…
◆ 内容 動画配信プラットフォームを使用したポータルサイトの開発案件です。 今回は動画別/ユーザ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP/JavaSc…
◆ 案件概要 ・医療や看護、建設業界等をメインに人材系サービスを展開している企業様です。 ・下記…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・◆備考 ・・コミュニ… | |
定番
【.NET / 週4日〜】大手不動産会社で…
◆ 内容 ・大手不動産会社の情報システム部門にて、社内で使うビル管理や、会計システム、Webシステ…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
◇概要 ▼案件概要 大手通信会社がビジュアルコミュニケーションをアップデートするインハウスのブラ…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼案件概要 大手通信会社がビジュアルコミュニケーションをアップデートするインハウスのブランドクリエ…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(コーダー) |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / JavaScript/HT…
▼業務内容 主に以下の業務に携わっていただきます。 ・WebベースのSaaSシステムの開発 ・…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・- | |
定番
【PM|フルリモ・週3日~4日】CO2排出…
【案件概要】 GXの領域のSaasの「CO2排出の取引量の算出の抽出プロダクト」の開発におけるプロ…
週4日・5日
600,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(プロダクトマネージャー) |
【カスタマーサクセス】サービスを導入した顧…
【業務内容】 サービスを導入した顧客への利用案内・運用提案業務 BtoBtoCサービスにおけ…
週2日
130,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | ヘルプデスク(カスタマーサクセス) |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
▼業務内容 主に下記の業務に携わっていただきます。 ・ウェブベースのSaaSシステムの開発 ・…
週4日・5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
【コーダー】メディア開発(PHP/Word…
自社メディアの開発プロジェクトです。 PHP特にWordPressを利用した開発を行なっていただき…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【リモート相談可 / データアナリスト /…
【業務内容】 - 成長戦略を踏まえたKPI設計 - サービス運営で定常的に発生する分析企画と工数…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・- | |
定番
【Java / 週5日】IT企業様向け、講…
◆案件概要 IT企業のお客様に対しまして、エンジニアの研修を実施しております。 今回はその研…
週5日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 講師 |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【作業内容】 ・払戻業務負荷軽減のための対応⇒払戻情報表示サイトの刷新、払戻受付webサイトの新規…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell・teraterm・sq… | |
定番
【フルリモ / Tableau / 週3日…
▼案件概要 現在社内ツールとして「Tableau」を活用しております。 今後システム設定やカスタ…
週3日・4日・5日
240,000〜350,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / C++/Python / …
◇目的 以下2点を実現することを目的としています。 (1)大手鉄道会社様が所持している複数の離れ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Kotolin / …
下記の業務に携わっていただける方を募集します。 ・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイ…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【ネットワーク】クラウドサービスに関する技…
案件概要: クラウドサービスに関する技術営業支援業務 法人向けクラウドサービス(Iaas基盤)の…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 /インフラ / 週4日〜…
下記の業務に携わっていただける方を募集します。 ・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイ…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
【業務内容】 ・ゲームのサーバ側APIの設計と実装 ・基盤ライブラリ、フレームワークの調査、利用…
週5日
500,000〜10,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
◇業務内容 住宅事業に特化したWEBサイトのシステム構築、アプリ、ソフト開発案件です。 Word…
週3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / React/Ruby / …
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【業務詳細】 今回は、自社のHPにてある程度ある型にあわせて、週1本程度デザインや、バナーなどを対…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Azure/PHP / 週…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby/PHP / 週5…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】クレジ…
●作業内容 STシナリオ作成や仕様の説明、環境説明は現在参画済みの開発チームから実施、 本体制で…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】レン…
【業務内容】 弊社で開発・運営しているレンタルスペースの予約プラットフォームのユーザーマイページの…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】教育…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービの開発を担当して頂きます。 フロントエンドや…
週3日・4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】新規事…
●業務内容 当社の新規事業のサービス開発をご担当いただきます。 世の中にない新しい価値を生み出す…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・●具体的には ・要件定義〜リリース管理 ・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】ライブ…
<業務内容> ・プロダクトマネージャーや運営からの案件要望の吸上げと把握 ・仕様書作成 ・中国…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・会社横断のマーケティングチームにおけるランディングページ、…
週4日・5日
2.4〜3.2万円/日
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】自社…
健康保険組合向け製品の開発・運用、健康保険組合の加入者向け通知物の開発・運用業務に携わっていただける…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Lararvel /…
受託開発案件でのPHPエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお話…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Lararvel | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
【今回の募集】 自社サービスのRubyエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申し込…
週4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【急募】大手テーマパークのマーケットリサー…
【企業概要】 国内・海外を問わず様々な企業のリサーチなどをてがける企業にて 大手テーマパークのマ…
週3日・4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | リサーチャー |
| R | |
定番
【週5/フルリモ/C#】通販事業者向け販売…
【会社概要】 東海地区のクライアントを中心に、Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・…
週5日
8〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
【Java・PHP・Phython等・一部…
弊社が運営する心療内科クリニックまたは美容医療クリニックの基幹システムを自社で企画開発していきます。…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【Python】鉄道車両データ分析アプリ
[概要] 鉄道車両走行中に取得するバイナリーデータを分析し、特徴量算出をする案件となります。 企…
週3日・4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
受託案件に対する、複数PJにまたがったPM…
受託開発案件における、PM兼上流工程の対応業務 ・PJの顧客との仕様調整、MTG対応 ・…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
不動産売買契約の電子化サービス開発支援
既存パッケージのカスタマイズ作業 ・作業場所 基本リモート 参画時と必要に応じた出社依頼に…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Vuetify・… | |
定番
IoTデバイスを使用したダッシュボードアプ…
下記の要件を満たすアプリの設計・開発・結合テスト・総合テスト ・APIで収集したデータを表示する…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
各システムの保守(問い合わせ・障害対応)、…
■業務内容 各システムの保守(問い合わせ・障害対応)、機能追加 ■対象システム 人事管理シ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【PM】債権管理回収WEBシステムのカスタ…
既にある標準プロダクトをベースに新規導入企業のニーズ、差分を整理、カスタマイズ要件を決定し、カスタマ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【上流SE】債権管理回収WEBシステムのカ…
既にある標準プロダクトをベースに新規導入企業のニーズ、差分を整理、カスタマイズ要件を決定し、カスタマ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【業務概要】 決済システムに関する要件への落とし込み、定義した要件に対しての設計及び製造、試験、リ…
週5日
520,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】広告…
【業務内容】 1人目の専任PdMとして、チャットブーストCVのサービスのグロースを担当していただき…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PHP/Java / 週5日】小売店向け…
業務系のWEBシステム開発やホームページの開発などの受託開発をメインに、 サービスやパッケージを組…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿博多駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 Web体験全般におけるプロダクトのブランドイメージに沿ったコミュニケーション設計、実…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・‐・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】EdT…
【事業内容】 ・ディープラーニング等を活用したアルゴリズムモジュールの開発と、ライセンス提供事業 …
週3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Vue.js/React.…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / T-SQL / 週5…
◇案件 小売系システム(新MDシステムのIF開発対応) ◇詳細 T-SQL(Transac…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【Python / 週5日】IoT機器ソフ…
【案件概要】 RasberryPi 4Bを用いたIoT機器の試作開発 ① RasberryPi …
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・C・C++・RasberryPi | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
【案件概要】 車載SoC上で動作するデバイスドライバの開発案件です。 -並行開発中のデバイスドラ…
週5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / React/Nuxt.js…
【業務内容】 今回は、自社新規プロダクトの開発業務におけるフロントエンド開発をご担当いただきます。…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【HTML/Javascript / 週5…
【企業概要】 弊社は様々な業種のお客様から直接案件を頂いております。 現在は自社サービスの開発も…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上前津駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・VB.NE… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
◇概要 アプリケーション向けのCMS(配置情報とARコンテンツ等を管理し、配信するシステム)の開発…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・VueJS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
①エンジニア部門の立ち上げ ・エンジニア部門の一からの立ち上げ →ご自身が理想とするチーム…
週5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】写真…
自社オリジナルソフトの開発を担当していただきます。 画像をサーバーに送信し、ユーザーに転送するシス…
週4日・5日
190,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
外資系コスメブランドのクリエイティブ関連の業務を下記を中心にお任せいたします。 ディレクションは米…
週3日・4日・5日
330,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / React/Vue.js …
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / カスタマサポート / 週4…
自社海外プロダクトについて、日本語での技術サポート、関連業務を行っていただきます。 ■メイン業…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | ヘルプデスク |
| ・業務イメージ 当社サポートサイトにメール等で問い… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
■想定業務内容 アーキテクチャ・新基盤における運用管理関連タスクと インフラ基盤関連タスクの保守…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / ECS / 週5日】…
【案件概要】 現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルをご担当いただきます。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ECSFargate | |
定番
【フルリモ / React/Kotolin…
【業務内容】 某生命保険会社様向けにシステム開発を並行して多数行っており、ベンダー側として品質の向…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 最終的にDjango上で簡単な画面等を作成できればと思っています。 ■到達目標…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】ヘ…
現在開発中のヘルス管理系新サービスでのUI/UXデザイナーの募集となります。 立ち上げ間もない…
週3日
190,000〜380,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・AdobeInDesign | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、『Salesforce』を活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
【企業概要】 主にはカーメンテナンス向けSaaSサービスの開発・運営をしております。 【業務…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 クライアント課題に合わせて、2,3名でチームを組みFileMakerでクライアントの…
週5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日・4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
【業務内容】 統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Go …
【業務内容】 統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Typescript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築案件です…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 業績好調につきデザイナー&EC担当として活躍いただける方を募集しています。 海外向…
週3日・4日・5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王線平山城址駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・Illustr… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
【仕事内容】 ソーシャルゲームのUIデザイン制作業務を担当いただきます。 UI/UXデザイナーと…
週4日・5日
300,000〜480,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しており…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | 【アーキテクト】基幹システム開発プロジェクト |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / UX/UI / 週3日〜】…
【想定業務例】 ・新規サービス、プロダクトのCVR、LTV、MAUや自然流入数、及びNPS向上に向…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【企業紹介】 お客様の課題に応じて柔軟にご支援をする受託開発企業です。 【主な開発環境】 …
週4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】自社イ…
■具体的な職務内容 ・新規、既存サービスのインフラ構築、保守業務 ・開発チームへインフラ構成の共…
週3日
190,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 ・インターフェイスの開発では、…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】国内最…
【案件概要】 配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 …
週4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript・社内のコミュニケーション… | |
定番
【フルリモ / React/Vue.js …
【業務内容】 事業拡大に伴い、プロダクトの機能開発および運用をお願いできるエンジニアを募集しており…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
■具体的な業務内容 Webエンジニアの採用に携わっていただきます。 ・paiza、Green、転…
週3日・4日・5日
1,690,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / Java/TypeScri…
Java/TypeScriptを使用したWebサービス(SaaS)開発で、下記2案件の開発に携わって…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・Next.js・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
◆案件概要 ・課金ライブラリのエンハンス開発 ・既存課金レコード作成の改修、課金ファイル生成処理…
週5日
300,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
◇案件詳細 AWS環境の要件定義/設計/テスト/構築 具体的には以下の業務(一例)をご担当いただ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / React.js/Type…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件概要】 当社の最新サービスのWebアプリケーションについて、追加機能の開発を担当するポジショ…
週4日・5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【業務内容】 以下の業務を遂行するために、プロダクトマネージャーやエンジニアと協業しながら意思決定…
週3日・4日・5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿関内駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート可 / PM / 週5日】自社顧…
弊社の下記システムのPMを担っていただきます。 現在弊社では下記のサービスを開発しております。 …
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React/ 週5日】総合…
▼案件概要 開発メンバーとして電子書籍事業のECサイトに携わっていただきます。 大きく分けて3つ…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■業務内容 動画配信サービスの運用保守/新規開発をご担当いただきます。 【業務例】 既存サ…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・■担当工程 … | |
定番
【リモート相談可 / Java/Kotli…
■業務内容 動画配信サービスの運用保守/新規開発をご担当いただきます。 基本的にネイティブアプリ…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】CX…
【案件概要】 カスタマーサクセス支援/顧客エンゲージメント向上ツールを提供しています。 積極的に…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
業務内容】 B2C Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には以…
週4日・5日
350,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript・AWS・GitH… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】自…
【業務内容】 (※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) ・販売管理(受注~売上、発注~仕入れ)…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】ス…
【業務内容】(※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) 下記機能追加の開発、単体テスト設計、テスト…
週5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件内容】 自社サービスWeb開発チームで React によるフロントエンド(UIフロント)作成…
週5日
390,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
【案件内容】 世界一のブロックチェーンゲームの会社を目指しております。 私達と一緒にブロックチェ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・C#・Node.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】教育…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日・4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Vue・React・RubyonRails・… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【事業内容】 ・システムインテグレーション ・ERPの導入支援サービス ・インフラの構築 …
週5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
【案件詳細】 弊社提供の観光系Saasサービスシステムにおいて複数のエンハンス案件に対応して頂きま…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社はCM・Web映像・グラフィック・サイト構築・iPhone用アプリ・Webアプリなど、ビジュアル…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / システム / 週3日〜】業…
【業務概要】 ・業務システムへの作業依頼の対応を行う ※各種マスタ追加対応、その他チケット対応、…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / VB.Net / 週…
【業務内容】(※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) 以下の業務に伴うハンディターミナルを用いて…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日】自社…
【募集背景】 ビジネス機能の追加を予定しており、サービスの成長とともに組織拡大を予定しています。 …
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
①HTMLタグの配置業務 WEBの多言語サービスに対応するための、プログラマーが制作したソースに、…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【Swift/Objective-C】サー…
■作業内容 サービス運用保守がメインとなります ■作業場所 ・リモートワーク可 ・作業場…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / SharePoint…
【案件内容】 SharePointにおけるサイトやページの作成をお願いいたします。 客先常駐にて…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【リモート相談可 / ML Ops / 週…
全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる入札情報速報サービスを自社事業として展…
週3日・4日・5日
670,000〜1,600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】基幹シ…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます。 ・請負会社での基幹システム(製造系)のサーバ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Zend・Framework | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【募集背景】 ・自社プラットフォームの成長に伴い、サービスをグロースさせてくれる方を募集しています…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件内容】 対話型Vtuberと関係性を育むことができる次世代のコミュニケーションサービスのiO…
週3日・4日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / VBScript /…
【業務概要】 下記の業務をご担当いただく想定です。 ・顧客(某製薬会社)標準PDF編集ソフトウェ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VBScript・PowerShell | |
定番
【フルリモ / Flutter/ 週3日〜…
【業務内容】 顧客プロモーション支援にともなうアプリ開発をご担当いただく予定です。 ※その他詳細…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
【概要】 自社開発のWEBマーケティング支援ツールの開発と運用 【詳細】 ・インフラからフ…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】広告業…
【案件概要】 広告/人材サービス業向け データ活用業務支援 【メイン業務】 ・クライアン…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL・Tableau | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
【案件内容】 フロントエンジニアとして自社メディアと新規Webサービスの開発・立ち上げに携わって頂…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・【業務内容】 ・X・… | |
定番
【フルリモ / PP/MM / 週5日】S…
役割:PP/MM 【業務内容】 ・調達、在庫、実績収集業務に関するSAP導入 ・関連システムの…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋静岡 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
【業務内容】 ・商標登録を安心、カンタンにできるようにするクラウドサービスを支える独自システム(W…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 既存のECサイト全面刷新におけるWeb管理ツールの設計および開発を担っていただける方…
週5日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Micronaut・Junit5・Git | |
定番
【Java】開発エンジニア
【仕事内容】 主に当社が運営するWebサービスの開発、運用をお願いします。 99%を内製化してい…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・※こんな人におすすめ ・コミュニケーショ… | |
定番
【週5/フルリモ/.NET】出版業向け各種…
【会社概要】 Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・データ放送コンテンツ等の制作・開…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋リモート |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
【スマホアプリエンジニア】iOS/Andr…
自社製品であるデバイスをBLEと通信し、データの可視化やサーバーへのアップロードなどを処理するアプリ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ECサイト構築を担っていただきます。 ・新規ECサイト構築 ・ECサイト運用 ・社内業務改善ツ…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/HTML / 週3…
Webシステム開発をご担当いただきます。 基本的な業務は、お客様の課題に合わせたBtoBのWEBア…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
【業務詳細】 会社HP、サービスサイト、求人サイトなど幅広いジャンルの案件に携われます。 ・コー…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / HTML/PHP / 週3…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【リモート相談可 / PM/PL / 週5…
同社のプロジェクトリーダー候補として、エンドユーザーに直接届けるWEBシステム開発、サーバーサイドの…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Solidity / 週5…
<仕事内容> ブロックチェーンを活用したアプリの開発 スマートコントラクトの開発 スマ…
週5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Solidity・Rails それ以外にもブロック… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件内容】 アスリート追っかけサービスのフロントエンド開発 (サーバーサイド等も理解が深い方で…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【Java / 週5日】自社VODサービス…
ストレージ商品・ネットワーク機器の提供をしています。 大手ケーブルTV事業者のVODサービスのシス…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件概要】 大手消費財メーカーやサービス事業者などに対してのCRMソリューションプラッ トフォ…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 既存統計システムの追加開発・運用プロジェクトになります。 現状サービス稼働中のうご…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala・SQL・bash・shell・scrip… | |
定番
【リモート相談可 / React/Node…
【案件概要】 国内最大級動画ソリューション企業にて下記の業務に携わっていただきます。 ・HTML…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
現在はオープンソースのセキュリティのみをテーマにしていますが、ミドルウェアやOSレイヤーの脆弱性、ソ…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・-・ | |
定番
【コーダー/フロントエンドエンジニア】事業…
基本業務としては、事業部門が運営している既存サービスサイト(約19サイト)のページ制作・更新案件をH…
週5日
360,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・AdobeC… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
【運営事業】 ・システム事業 ・コンサルティング事業 ・スポーツ事業 等々 【業務概要】…
週5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿綾瀬駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】ス…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・スポーツクラブ、インフルエンサー、アイドルなどの特設ページ…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/Ruby …
この度は人員を増加し、事業の更なる拡大を目指しております。 【業務内容】 ・Ruby on …
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
既存医療機関向けポータルサイトをAWSに移行業務をご依頼します。 ポータルサイトは、オンライン資格…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【AWS / 週5日】証券系基盤更改業務(…
▼業務内容 大きく以下3つの観点にて検討、対応を実施いただきます。 ・基盤更改(オンプレ→クラウ…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京王府中駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・SQL | |
定番
【C# / 週5日】FX取引システム維持保…
【業務詳細】 ・FX(外国為替証拠⾦取引)関連システムの新規構築・維持管理 ・クラウドを対象とし…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本⽊一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C#・AWS・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
【業務詳細】 顧客標準仮想基盤の再構築に伴い、以下作業をご担当いただきます。 ・新仮想基盤の検証…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer2016・Hyper-V | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】クラ…
【既存保守業務】 ・AWS基盤の保守/運用業務 ・新サービス利用時の利用ルールの策定/セキュリテ…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本⽊一 丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
【業務詳細】 現在弊社上位様メンバーが参画しているリプレース案件の増員となります。 ・複数システ…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
【業務詳細】 ・マーケティング組織でデザイン、マークアップ業務 ・サービスサイトやLPの作成、改…
週5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ad… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
■案件概要 社内のオンドメディア・webコミュニティーの開発/改修、イノベートなど。 ■具体…
週3日・4日・5日
1,010,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
当社のサービスのフロントエンド開発をお任せします。 現在、これまで外部ベンダー様のご協力を受けて運…
週5日
480,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロンドエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週5…
■下記のプロダクトのいずれかに、フロントエンジニアとしてご参画いただく想定です。 1)リアル・クリ…
週5日
610,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・GraphQL・Rest・Am… | |
定番
【フルリモ / React/ 週3日〜】医…
■下記のプロダクトのいずれかに、フルスタックエンジニアとしてご参画いただく想定です。 1)リアル・…
週3日・4日・5日
740,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| R・GraphQL・Rest・AmazonCogni… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
【案件概要】 自社サービスプラットフォームの開発 私達は場所や時間にとらわれることなく、パフ…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Android/iO…
アプリ(iOS/Android)をよりユーザーに価値を提供するためプロダクト価値を高めることが出来る…
週5日
350,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・AWS・Slack・Confl… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
更なるサービスの質の向上と事業拡大に向けて、リードエンジニアの方を募集します。 弊社サービス)の…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Spring・Boot・Linux… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
更なるサービスの質の向上と事業拡大に向けて、インフラエンジニアの方を募集します。 具体的には、サー…
週5日
470,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・Spring・Boot・Linux・MyS… | |
定番
【Linux / 週5日】金融機関システム…
・案件概要 金融系インフラエンジニアとして、インフラ設計・構築・運用業務を担当していただきます。 …
週5日
470,000〜550,000円/月
| 場所 | 東京23区以外多摩センター |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C・C++・<具体的な案件情報> ◆金融系システム… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・案件概要 金融系インフラエンジニアとして、インフラ設計・構築・運用業務を担当していただきます。 …
週5日
380,000〜470,000円/月
| 場所 | 埼玉与野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C・C++・<具体的な案件情報> ◆金融系システム… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】エ…
【業務内容】 経験実績豊富なメンバーと幅広い業界のアプリやWebサービスの作成する同社にてスマート…
週5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
◆作業内容 運用中ソーシャルゲームにて2Dグラフィックスの制作をお任せいたします。 具体的には下…
週3日・4日・5日
250,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
生損保Webシステム新規開発プロジェクトメンバー募集となります。 ・要件定義が終了したサブシステム…
週5日
640,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門ヒルズ駅 or 神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 クライアントから依頼をいただいている、DB整備をご対応頂ける方を探しています。 P…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
本研究所の研究成果を公開するサービスにおけるWEBフロントエンジニアを募集いたします。 本サービス…
週3日
350,000〜390,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
本研究所の研究成果を公開するサービスにおける画像処理・処理システム構築のエンジニアを募集いたします。…
週3日
350,000〜390,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【担当業務】 主な業務はサービスサイトやLPのデザイン制作物のコーディングです。 HTML、CS…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Java /…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのバックエンドエンジニアの募集になります。 ・保険事業会…
週3日・4日
330,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
支出の見える化、見積の取得、購買、契約管理、支払・請求などの機能をオールインワンでもつSaaSの開発…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Vue.js・Nuxt.js・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
スマートフォンのアプリ及び、BtoB 向けの Web アプリケーションの開発を中心に受託開発をされて…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・AndroidStudio | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務内容】 下記の業務をメインでご担当いただきます。 ・仕様や設計の検討 ・実装/テストコー…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Go・Typescript・ES2015(ES6)・… | |
定番
【フルリモ / HTML/TypeScri…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / SQL/TypeScrip…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・SQL・Vue・React | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】保険DX…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのUIデザイナーの募集になります。 ・保険事業会社向けの…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
本ポジションの魅力ややりがい - iOS(Swift)とAndroid(Kotlin)をFlutt…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
・在庫管理システムや社内ツールの管理画面構築 ・社外で利用される EC や買取アプリ等の画面構築 …
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Python・Go・Typescript・React… | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Java /…
▼案件概要 既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / JavaScript/Ty…
既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・メインサービスのフロントエンド開発(React …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】オン…
オンライン契約締結管理サービスの主にバックエンドエンジニアをお任せします。 具体的には… ・シス…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
急募
【UI/UXデザイナー】基幹事業のサービス…
弊社のいずれかのプロダクトにおけるUIUXデザイナーとして以下の業務をお任せします。 ■案件概…
週3日・4日・5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| PlayFramework・Slick・Angula… | |
定番
【バックエンドエンジニア】自社プロダクトの…
自社サービスにおいて、下記の業務をお任せします。 ・システム改善・パフォーマンスチューニングや…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Python・Kotlin・Typ… | |
定番
【フルスタックエンジニア】動画解析サービス
自社サービスにおいて、下記の業務をお任せします。 ・システム改善・パフォーマンスチューニングや…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・Python・Typescript… | |
定番
☆資金調達済・急成長企業☆【UI/UXデザ…
No.1アンケート・コミュニケーション・プラットフォームになる ユーザー・顧客の声を集めDX化…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
| 【環境】 ・macOS(MacBookPro) … | |
定番
【3Dデザイナー】スマートフォン向けゲーム…
【企業概要】 大人気少年漫画を取り扱った現在運営中の スマートフォン向けゲームのプロジェクトに携…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【3Dデザイナー】スマートフォン向けゲーム…
【企業概要】 大人気少年漫画を取り扱った現在運営中の スマートフォン向けゲームのプロジェクトに携…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【UIデザイナー】スマートフォン向けゲーム…
【企業概要】 セガサミーグループ子会社/設立以来安定経営/スマートフォン向けオンラインゲーム/ …
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【クライアントサイドエンジニア】スマートフ…
【企業概要】 セガサミーグループ子会社/設立以来安定経営/スマートフォン向けオンラインゲーム/ …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回は、開発をリードいただけるテックリードを募集します。 «具体的には…» ・プロダクトのフ…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Rub… | |
定番
【フルリモ / システム / 週4日〜】既…
【業務内容】 大手SIerグループで利用しているクラウドサービスを利用した間接材購買システムの運用…
週4日・5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【Java/SQL / 週4日〜】次世代勘…
【案件内容】 品質強化テスト(テストケース作成、テスト)など、ソースレビューも発生する可能性がござ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・SQL・Springframework・s… | |
定番
【AWS / 週5日】人事給与システムのA…
【案件概要】 下記の2つの業務をメインにご担当いただきます。 1) 官公庁向け人事給与システムの…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・RHEL・AWS | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】シ…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・プロダクトデザインチームや関連システムの担当者とコラボレー…
週4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【AWS / 週5日】インフラの各種設計、…
現行環境のリプレース案件で、AWSにて稼働している環境を追加された要件を取り込みながら別アカウントの…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八幡山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / java / 週4日〜】大…
保険契約者が保険事故発生時に事故報告する代理店向けのwebシステムがあり、 バックエンドはIBMホ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・COBOL | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
データサイエンスプラットフォームサービスの立ち上げメンバーとして、サービスの企画・開発から運用までを…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【AWS / 週5日】インフラの各種設計、…
現行環境のリプレース案件で、AWSにて稼働している環境を追加された要件を取り込みながら別アカウントの…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八幡山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
【案件概要】 オンプレミス → AWSへの移行 ・請求業務のシステムとなり、インボイス(適格請求…
週4日・5日
620,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Terraform | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日〜】…
Azureシステム構築。以下①~③を実施いただきます。 ①以下環境を構築 ② 上記構築したものを…
週4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
プログラミングを含む現場レベルの開発から仕組みづくりまで、色々な経験をしてみたいこの職種では特に以下…
週5日
270,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Types… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週4日…
画面開発部分をご担当いただきます。 データアクセス層(DA層)と呼んでいるDBから情報を取得してく…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
画面開発部分をご担当いただきます。 データアクセス層(DA層)と呼んでいるDBから情報を取得してく…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手配送会社向けの配送連携システムのリニューアル案件となっております。 詳しい案件内容については面…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】AI…
■案件内容■ AI解析基盤の新規構築 ※新規システム構築 基本/詳細設計・実装~単体/結合テ…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・jQuery・SpringFr… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】化学…
■案件内容■ ・化学製品メーカーの製品化研究を管理するシステムの機能改修開発 ・既に稼働している…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / システム / 週4日〜】製…
セキュリティシステム企画・整備を主業務として、SOC(セキュリティオペレーションセンター)、SASE…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【インフラ / 週5日】AWS環境へリプレ…
・官公庁の人事給与システムのAWS環境へのリプレース作業。 ・AWSへの移行およびAWS上へのサー…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
■案件内容■ ・Azure上にてSPAでフロントエンド開発を行う。 ・作業工程は基本設計から結合…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript | |
定番
【セキュリティ / 週4日〜】某協会向けサ…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・サーバー管理、運用監視 ・問い合わせ対応 ・障害対応 …
週4日・5日
250,000〜280,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】バッ…
・バッチ基盤:Linux上で稼働するバッチ基盤のエンハンス業務 ・Oracle基盤:バッチ基盤と連…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【システム / 週5日】システム運用案件(…
【業務内容】 システム運用保守、社内インフラ維持保守(サーバーおよびネットワーク) AD運用、ア…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【C/C++ / 週5日】linux環境で…
【案件概要】 C言語開発ですのでポインタの読み書きは必須です。 DBアクセス処理などでSQLも使…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿蒲田 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・SQL | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】業界内…
■内 容■ ユーザー数数百万人規模、登録店舗数も数千店の業界内トップシェアサイトの大型リニューア…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / SQL/java / 週5…
ユーザー数数百万人規模、登録店舗数も数千店の業界内トップシェアサイトの大型リニューアル案件となるため…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【フルリモ / java/SQL / 週5…
【募集要項】 新規システム開発に関わるプロジェクトリーダーです。 自社で開発した既存のPHPシス…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・SQL | |
定番
【フルリモ / VBA/SQL / 週4日…
当初対応としてはDB移行時の自動検証ツールをご担当いただきます。 ※PL/SQL、VBA、シェル…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VBA・SQL | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【案件概要】 口座開設、残高照会、入出金明細照会などの機能を持つ銀行スマホアプリの開発になります。…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Java・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / java / 週5日…
<プロジェクト概要> 法人向けに提供しているSaaSで主に「ID一括管理」「連携SaaSへのSSO…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python・Jav… | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】NW…
ネットワークシステムに関する維持管理・運用業務 ・ネットワーク関連の障害、トラブル対応 ・ネット…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
注目
【コーダー】クリエイティブ案件のコーディン…
案件名: クリエイティブ案件のコーディング(フロントエンド、Webレイアウト) 案件内容: …
週5日
460,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町紀尾井町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー / フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】情報分…
【業務内容】 現行SAP BWからSnowflakeへの移行を想定している作業は以下となります。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【Linux / 週4日〜】システム更改(…
顧客向けシステムの既存システム更改対応を担っていただける方を募集します。 ・既存稼働している…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿府中 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【システム / 週5日】ウェブシステムのシ…
【業務内容】 主な試験対象は以下の3つです。 1)Windowsアプリケーション 2)集計処理…
週5日
410,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】WE…
■案件内容■ ・基地局の工程管理アプリの開発を行っていただきます。 ・工事業者が報告書をExce…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・jQuery・Spr… | |
定番
【フルリモ / HTML/C# / 週5日…
【業務内容】 ・情報共有システムの改修・機能追加を行う。 ・改修対象:SharePointリスト…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】道…
道路交通システムの組込み機器向けテスト環境開発及び、保守管理アプリの開発に携わっていただきます。 …
週5日
460,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
エンタメ系の情報コンテンツを提供するPC、スマホ向けWebサービスの改修案件となります。 提供する…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・機能追加として、本システムに以下の機能追加し… | |
定番
【Java / 週5日】不動産会社向けシス…
既存のシステムがありますが、そちらをほぼ新規のシステムとして作り替える プロジェクトで、入金、支払…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Java・Query | |
定番
【PMO】プロジェクト全体の進捗管理(WB…
・プロジェクト全体の進捗管理(WBSの作成、〆切管理等) ・各種審査の支援 ・システムセキ…
週4日・5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】団地…
【業務内容】 基幹系システム最適化に係る団地再生システムの再構築案件です。 日立汎用機(COBO…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海浜幕張 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】某大…
某大学様向けに、無線LAN環境のNW機器リプレイスを行います。 設計、構築、試験実施、現地導入の対…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / .NET / 週5日…
既存システムはDynamics CRMで構築されているシステムをクラウド(Azure)に再構築するも…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿門前仲町 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C#・.NET | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】自…
データ管理システムや投資家向けサービスを提供する事業会社にて、自社プロダクトのUIUXデザイナーを募…
週5日
250,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 /インフラ / 週5日】…
下記の乗務がメインとなります。 ・設計構築業務 ・Vsphere、Vsanを利用した仮想化基盤、…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
【案件概要】 基地局の工程管理アプリの開発を行っていただきます。 工事業者が報告書をExcelで…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringBoot… | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
現在BPOとして外部へアウトソースしている業務のRPA化を実施いただきます。 業務のなかからRPA…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
主に大手士業向け業務システム内の報酬を決定するための機能に関する改修案件にメインで参画いただく予定で…
週4日・5日
410,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript | |
定番
【Linux / 週5日】官公庁向けプラッ…
下記の業務をメインでお任せします。 ・サーバ構築 ・DNSレコード変更関連作業(追加/削除) …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三鷹 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
大手消費財メーカー様のSalesforce初期導入PRJ 全国に1,500名ほどいる営業へSFAと…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
監視システムの開発・保守 業務に係わる各種システム・ツールの開発、保守作業 ・情報機器の監視(イ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Linux | |
定番
【フルリモ / システム / 週4日〜】S…
セキュリティ監視システムの開発・保守 ・SOC業務に係わる各種システム・ツールの開発、保守作業 …
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】情報…
現行SAP BWからSnowflakeへの移行想定している作業は以下です。 ・移行:計画、移行設計…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週4日〜】社…
▼案件概要 上位様で行っている複数の受託案件について、顧客折衝、要件整理、要件定義、設計概要整理等…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週3日…
EPM Cloud導入に関わる以下の外部設計~結合テストをご担当頂きます。 ・レポートの設計開発 …
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
▼案件概要 ※新規システム構築を担って意tだ開ける方を募集します。 基本/詳細設計・実装~単体…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Java・Azure | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】品質…
新しいシステム基盤への移行をご担当いただきます。 <主な作業> ・品質管理用レポート(データ収集…
週4日・5日
410,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
<プロジェクト概要> サービスの立ち上げから7年以上経過し、負債が増大、構成はモノリシックになって…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
▼案件概要 基本設計・詳細設計・実装・UT・IT 作業としては設計工程も含みますが、こちらについ…
週4日・5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿岩本町 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
動画配信システムのお客様向けカスタマイズ開発作業を担当して頂きます。 新規立ち上げサイト、または新…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・AWS | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】フ…
スポーツ系ファンクラブサービスの下記内容をPLの指示のもと業務を実行していただきます。 ・会員登録…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・【開発】 ・各種APIの詳細設計~テスト… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
実装される主な機能 (参画中のエンジニアを含め現在のメンバーと着手のできる箇所から順に開発になるか…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お台場海浜公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】大手…
案件情報は二つあります。 1.大手通信会社のデータ分析基盤にてデータカタログに登録するメタデータの…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【SQL / 週5日】通信キャリア向けデー…
【案件が異様】 現在稼働中のシステムにおけるデータ保全業務になります。 データ不整合等の各種不具…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモート / Ruby / 週5日】…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
▼案件概要 請求管理周りの業務に沿って作成されたシステム化業務フローや洗い出された機能をもとに、外…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・Springboot | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【業務内容】 ・要件に応じたDB設計〜機能の実装 ・開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【Linux / 週4日〜】共通IT財務プ…
データ移行の移行ツール作成、移行作業に伴うデータ授受業務です。 ・財務会計のマスタデータ(exce…
週4日・5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VBA・Linux | |
定番
【Ruby】自社マッチングアプリサービスの…
業務内容としては・マッチングサービスknewのサーバーサイドの開発・運用業務、安定性、パフォーマンス…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
【JavaScript/Vue.js/Nu…
Merpay / SoftwareEngineer(Frontend) ソフトウェアエンジニア…
週4日・5日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア【Merpay / SoftwareEngineer(Frontend)】 |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【サーバーサイド】自社サービスにおけるAI…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【マーケター】自社案件/受託案件の広告運用
【企業】 世界中にユーザーを持つ無料のイラスト作成ツールの開発・提供や、 受託で広告の運用などを…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【フロントエンドエンジニア】自社サービスH…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【PM】自社サービスのプロジェクトマネージ…
グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先端の人口知能技術(AI)を用い…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Python】サーバ開発の仕様設計支援・…
サーバ開発の仕様設計支援・開発支援 ・Python、AWSにおける開発業務(IDAP環境での作業)…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【インフラ / 週5日】技術QAの問い合わ…
◇業務概要 製品に関する障害調査、技術QAの問い合わせに対するテクニカルサポート業務。及び、金融系…
週5日
370,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL/JavaScrip…
▼業務内容 基本設計、詳細設計、PG、試験、調査 現行処理、既存機能の調査が必要なことも多く、設…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
▼業務内容 ・JAVAソースを元に、PHPの業務ロジック部分の開発(コンバート作業に近いです) …
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿春日駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・SQL・‐ | |
定番
【フルリモ / Azure / 週5日】外…
業務内容: ・大手物流グループ企業の国内、海外NWの設計、構築、保守、運用 ・技術調査 ・シス…
週5日
410,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週4日…
【案件概要】 リプレース案件の増員となります。 ・複数システムのデータ統合にともなうデータ移行設…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Excel・VBA | |
定番
【システム / 週4日〜】ADSLマイグレ…
・業務内容 1,マイグレに伴う現地調査の実施 2,現地調査結果の作成(移行前、移行後構成図、NW…
週4日・5日
70,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
<想定業務> ・動画配信モバイルアプリ、テレビ向けアプリ開発業務。 ・詳細設計/製造/単体テス…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Ob-C・Swift | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
国内最大級のゲームプラットフォームにおいて、インストール型ゲーム・買い切り型パッケージゲームを取り扱…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
【業務内容】 この度は、現在新規開発中の社内ワークフローシステムの機能開発における、詳細設計~製造…
週4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週4日〜…
ゲーム事業にプラットフォーム開発/運用業務のマネジメント、スクラムマスター ▼案件概要 ・フロン…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| PHP・Go・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
▼案件概要 サーバーサイドとフロントエンドどちらもご対応頂きます。 直近ではバックエンド機能(B…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel・AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / システム / 週4日〜】W…
現在稼働中のWinActorロボについて、システム刷新に伴い、修正をお願いします。 ◆業務内容 …
週4日・5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / NW / 週5日】5…
【業務内容】 ・お客様 NW設計部門から工事設計案件受付 ・ビル内設置リソース確保(スペース・ラ…
週5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
◆業務内容 案件推進を行うPMO業務、システム構成/NW構成の検討、見積資料、定義書等の作成方針検…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
資産管理アプリを使うユーザーの情報をデータベースから抽出し、様々な切り口で分析できるようデータ加工、…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| VBA・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・デプロイ時の自動テストの運用が一番のメインになります。 ・E2Eテストは不安定なので、失敗したと…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・rspec・Selenium… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【案件概要】 クライアント(EC系)の改修案件にて開発業務(設計、実装、テスト・デバッグ、ソースコ…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
▼業務内容 店舗売上本部会計システムにおける在庫管理、運用支援機能の開発支援 ・SQLのレビュー…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・AWS・Linux・PostgreSQL | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】W…
【案件概要】 大手Webサービス/Webサイト制作、運用企業です。 HR系プロダクトのアジャイル…
週3日・4日・5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
■概要 本募集は、新規売主向けサービス展開に関連するプロダクト開発を担当していただくことを想定して…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
SaaS事業として、クライアント先のマーケティングDXを推進させるツールを自社内で開発・提供していま…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go/Python / 週…
【案件概要】 顧客サービス製品におけるサーバサイドエンジニアを募集します。 ・サーバーサイドにお…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・C・C++・C… | |
定番
【フルリモ / QA/JavaScript…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのQAメンバーの募集になります。 ・保険事業会社向けの保…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Java /…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのバックエンドエンジニアの募集になります。 ・保険事業会…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 【…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript | |
定番
【フルリモ / CSS/TypeScrip…
下記の事業を行う勢いあるベンチャー企業にてのSREエンジニアの募集になります。 ・保険事業会社向け…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| CSS・Typescript・AWS | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】ビ…
既存事業の拡大に向けて以下業務をお任せします。 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグの調査および修…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / SRE / 週5日】レジャ…
余暇時間の選択肢を最大化しその質を向上させることで、心の充足を実現し、幸せな社会の実現をめざす。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Java・Typescript・AWS・Spring… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】保育…
保育施設向けICTサービス事業を行う勢いあるメガベンチャー企業にてのバックエンドエンジニアの募集にな…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・Swift・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
保険契約・請求フォームのノーコードツールのチームに所属いただきつつ、認証認可・権限設計の知見で他チー…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Kotlin・Typescript | |
定番
【フルリモ / SQL/TypeScrip…
社内システムを統括した部署で、社内DXのための開発をメインに行っている部署での募集となります。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Typescript・SQL | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
マーケットのDX化の推進いただける方を募集します。これまでの海外旅行サービスにはないネイティブアプリ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Typescript | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
◆業務内容 ・広告効果を推定するための統計手法や、広告予算配分最適化のための数理最適化手法の開発。…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・R・Julia | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日…
某ゲーム会社様向け、運用中のデータ分析基盤(Redshift)のGoogle Cloud環境への移行…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Cisco / 週4…
【案件概要】 今回は、WAN展開要員として自社サービスを含む製品の導入作業をお任せします。 また…
週4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
▼案件概要 フロントエンド開発、およびE2Eテストをはじめとしたテスト自動化の開発をお任せします。…
週4日・5日
840,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
概要: ・法人向けクレジットカードサービスでPMやデザイナーとともに開発 ・バックエンド、フロン…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
■案件概要 大人気ソーシャルゲームのUIデザイン業務です。 機能追加・改修をメインに、UI設計を…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
▼案件概要 今回は、ゲームの企画段階から設計、開発まで幅広い工程に関わっていただきます。 尚、状…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【Python / 週5日】開発中または運…
◆業務内容 ・iOS/Android向けのネイティブゲームの設計/開発/運用 ・開発環境の構築(…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
▼業務内容 ・自社アプリの開発・運用 ・その他弊社サービス開発に関わる業務全般 ・必要に応じて…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿南新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【システム / 週5日】システム導入経験者…
▼案件概要 飲食系SaaSの導入~運用要員募集! 顧客への導入の際の計画やハンドリング、利用の定…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】特殊…
【案件内容】 ・既存のコードの理解と保守改善 ・既存システムへの新規機能の開発やリファクタリング…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・AWS・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
作業内容:KPIコミュニケーションアプリの開発支援 ・スマホアプリの基本設計・実装 ・追加開発の…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
to C向けマッチングサービスの開発支援に携わっていただける方を募集します。 ◆業務内容 ・…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / AWS/Javascrip…
主に、下記の業務をご担当いただきます。 ・要件チームとの調整 ・フロントエンドからサーバーサイド…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Go・RubyonR… | |
定番
【HTML/CSS|週1~OK】"自立自走…
"自立自走型" のテクノロジー人材を輩出するためのIT人材育成プログラムを講師として運営していただき…
週1日
90,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件毎に異なります |
|---|---|
| 役割 | 講師(ジグソー法のメイン講師登壇) |
| Python | |
定番
【html、CSS、Bootstrap、J…
ある程度形になっているデザインを(XD)をBootstrap を使いソースに落とし込む作業。ユーザビ…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(HTML CSS JavaScript) |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・B… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
◇概要 ・業務内容:AD・GDの指示のもと以下の業務を実施 1.取り扱うグラフィックデザインの…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
▼案件概要 大手SIerのアーキテクチャデザイン支援部隊にて、エンドユーザや社内他事業部に対して、…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / グラフィック / 週3日〜…
▼案件概要 食品業界のブランディングに特化した企業でのデザイン案件になります。 社員が企画した内…
週3日
90,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社開発している社内コミュニケーション活性化SaaSへのSSO実装にあたり、設計~実装までの業務を担…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / java / 週5日】決済…
【新規システム開発に関わるプロジェクトリーダーです!】 自社で開発した既存のPHPシステムを新たに…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・AWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】オンラ…
▼募集内容 オンラインイベントプラットフォームの開発をお願いします。 立ち上がったイベントのペー…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
AWS・GCPを利用したクラウド環境構築案件です。 人財プール案件のため、プロジェクトの終了後…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】データ…
大手メディア企業が保持するユーザー視聴ログおよび外部データを利用した広告商品開発・効果最適化を目標と…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・GCP・BigQuery・CloudFunc… | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
案件概要 :プログラマブルなホワイトボックス・スイッチを利用した データ・プレーンの転…
週5日
460,000〜920,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件内容】 下記の業務をご担当いただきます。 ・中古機械ECサイト向けサーバサイド開発支援 (…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Github・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
【案件内容】 音声×SNSを目的とした新規スマホアプリの開発を行っており、開発PMとして進捗管理及…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| PHP・Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】サーバ…
▼案件概要 教育系WEBサービスの開発に携わっていただきます。 新規機能追加や、既存機能の改修な…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・PHP・RubyonRa… | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】ポータルサ…
・主にクライアントか自社のWebサイトの作成 ・WEBシステムの開発、検証、運用、コンサルティング…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・CakePH… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
【案件内容】※業務内容例 - 開発(主にUnity、C#など) - 技術上の意思決定への関与 …
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】某国…
■仕事内容 AI解析基盤(プラットフォーム)の新規システム構築をご対応いただきます。 担当工…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】マテ…
・新規サービスの開発、およびそれらの基盤を支えるシステム開発 ・PHP、Ruby、Node.js(…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Java・S… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービスに従事するメンバーが使う社内用業務システムのリプレイス/開発を担当頂きます。 具体的に…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・Nuxt.js… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
■案件内容■ ・基本設計書、詳細設計書の執筆 ・パラメータシート作成 ・検証環境の構築 ・基…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ECS・RDS・S3 | |
定番
【インフラ / 週5日】クラウド(AWS)…
【案件概要】 ・CACと別ベンダーにてAWS基盤の保守/運用を実施 ・関連メンバーは、お客さんプ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VPC・EC2・RDS・S3・Lambda | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
■業務内容 社内インフラの運用支援業務全般 ・メイン業務としては、PJの設計担当として運用体制強…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
≪具体的な業務内容≫ ■システム開発 ・フロントサイドのSPA/SSR ウェブサイト開発 ・バ…
週5日
750,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / React/Kotlin …
保険業界向け営業支援アプリケーション開発案件です。 開発言語といたしましては ・Frontend…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Oracle / 週…
■業務内容 大手損保様の基盤の維持管理案件に参画いただきます。 今回は生保様のプロパー様代替とし…
週5日
460,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Oracle | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】ファ…
【概要】 大手生命保険会社のファイルサーバー/仮想基盤更改、移行プロジェクトに参画いただきます。 …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
◆案件内容 下記の業務をご担当いただきます。 ・IoTシステムの管理者向けWebサイトの改修 …
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Kotlin・SpringFW・MySQL | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
【概要】 新機能の実装を中心とし、プロジェクトによっては企画や要件定義から関わっていただけます。 …
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・React・Redux・Swift・Kotli… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】建設…
①某建設会社様向けの機材管理・工場管理システムの開発要員の増員となります。 担当して頂くフェーズは…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringFW・Thymeleaf | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【募集背景】 現在の課題:WEBシステムの速度改善 弊社WEBシステムの速度問題を解決したく…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・CodeIgniter・CentOS… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【業務内容】 ・サーバ上でのSQL実行や手動シェル実行、ファイル操作、データ調査・抽出等 ・問合…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・AWS・CentOS・PostgreSQL | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】W…
学習系管理WEBアプリの開発となります。 3つのシステムが絡んでいるため、API周りの開発/バッチ…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / Java/SQL / 週4…
【内容】 アドオン開発(要件定義~設計~製造~テスト~リリース)の推進・保守(エンドユーザからQA…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Oracle12C | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
ReactをメインにTypeScriptや既存ライブラリを利用したWebアプリケーションの開発をご担…
週4日・5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】福祉…
お客様が運営する就労支援事業所で福祉支援に従事する社員が使うシステムのバックエンドの開発を担当してい…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・Laravel・AWS・Vue.js・Nux… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】ビジネ…
▼案件概要 想定される主な業務は以下です。 - サーバーサイドの設計、開発 - 開発中に起こる…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel・MySQL・CloudSQL… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】学…
■案件概要 学習系管理WEBアプリの開発となります。 3つのシステムが絡んでいるため、API周り…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java11・SpringBoot・Spr… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
【案件概要】 マーケティングを支援するためのツールの開発や、自社アフィリエイトの提供をしているチー…
週4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】仮想通…
■案件内容 仮想通貨の個人向け会計ソフトについて、プロダクトを安定的に稼働、成長させるために必要な…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・Nuxt.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社が開発・運営しているECカートシステムの、新機能開発や既存機能の改修、性能改善といったソフトウェ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・GMOクラウド・AWS・Linux・Cent… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】子育て…
【案件概要】 子育てにまつわる負を解決するために様々なサービスを提供しており、大型資金調達も行われ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・SpringBoot・jQu… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】仮想通…
仮想通貨の個人向け会計ソフトについて、プロダクトを安定的に稼働、成長させるために必要な要件を中心に開…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・Nuxt.js… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社が開発・運営しているECカートシステムの、新機能開発や既存機能の改修、性能改善といったソフトウェ…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・GMOクラウド・AWS… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】5年以上…
【概 要】 自動車大手のお客様にて、現在Azure上(AKS利用)に構築されたSitecore …
週5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / Ruby/PHP / 週5…
・プロダクトマネージャーやデザイナーとチームを組み、企画/設計/開発/リリース/運用までを一気通貫し…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Laravel・RubyonRai… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 チャットボット型Web接客ツールの開発案件になります。 自社で開発をしているチャッ…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Windows・… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】モ…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
【案件詳細】 ドキュメント作成業務および、PMのサポート業務をお願いしたいと考えております。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
●募集ポジション サービスに関する管理者兼実行者として戦略立案・施策のプランニングをしていただくと…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【フルリモ / Webデザイナー / 週4…
▼業務内容 ・WEBページのデザイン制作 ・ワードプレス更新 ・バナー広告のデザイン制作 ・…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
【業務詳細】 パートナー企業(AWSの認定パートナー)にて運用チームを作り、AWSのテクニカルサポ…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】データ…
この度事業の拡大に伴い弊社クライアントと分析者の間に入っていただけるPMを募集いたします。 【…
週3日
500,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿博多駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM/Ruby / 週3日…
■仕事概要 WEBサービスの企画・設計・開発・運用業務やサイトの改善・改修 新サービス開発プロジ…
週3日・4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】投資サー…
受託プロジェクトにて少額で株式投資ができる投資サービスのマネタイズアイデアの企画検討をご支援いただき…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PdM / 週3日〜】新規…
この度、新規事業の立ち上げにあたりwebサービスの要件定義とプロジェクトマネジメントを担当していただ…
週3日・4日・5日
440,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務詳細】 クライアントに対してブランディングデザインからご提案する機会も多く、 コーポレート…
週3日・4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】C…
CRM(Salesforce)をより業務に最適化した形で活用すべく、追加要件への対応と日々の運用体制…
週5日
830,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
【案件内容】 弊社で受託している案件にてシステム部門における、PJ管理、保守チケット管理、要員管理…
週5日
410,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
【事業概要】 戦略立案~制作/広告運用までデジタルマーケティングを一気通貫でサービス提供を行ってお…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大成長中…
【案件概要】 事業責任者と密に連携し、プロダクトを作り上げていく開発リーダーとしてご活躍いただきま…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【PM / 週5日】ERPパッケージ(IF…
◇案件詳細 ・ERPパッケージ(IFS)導入において、ユーザー側の立場でプロジェクト推進支援やベン…
週5日
720,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
Webアプリケーションとして既にサービスを運営をしておりますが、そのPM業務および開発業務に携わって…
週3日・4日・5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
▼業務内容 ・デジタルマーケティング新サービスリリースにあたり、各社にまたがる多様なデータソースシ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社サ…
<業務内容> 自社でのフリーランスの支援プラットフォーム開発にて、プロジェクトマネージメント、チー…
週3日・4日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Cake | |
定番
美容業界のDX支援☆【TypeScript…
【業務内容】 ネイリストと個人を繋ぐSNS型予約システム(自社アプリ)の開発に携わっていただきます…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・Node.js・Next.js | |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
【案件概要】 新たに物流センターオープンに伴うLP作成業務をご担当いただきます。 サイトの企画、…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】新…
新規プロジェクトを立ち上げ、収益化に貢献していただくPJ管理と現場指揮ができるPM候補を募集いたしま…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・C#・【開発工程】 ・要件定… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ネ…
各エンドユーザ向けにセキュリティ製品の導入プロジェクトを行っております。 そのため、下記のポジショ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 豊洲大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
当社は北海道で仕事用品店やアパレルショップを運営する老舗企業です。 この度は、ECサイト運営の…
週3日
90,000〜190,000円/月
| 場所 | 北海道:札幌新道東駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
この度、新たにWEB事業部を立ち上げることとなり、ご参画いただく方には、自社サイトの構築からクライア…
週3日・4日・5日
190,000〜260,000円/月
| 場所 | 東京23区以外立川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Salesforce…
◇案件内容 大手ネットビジネス会社のSalesforceに関わる開発支援、コンサル業務、PM対応な…
週5日
440,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】新プロ…
【案件概要】 社長直下のポジションを想定しており、パートナー企業との協業プロジェクトを推進していた…
週5日
830,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】通…
◇概要 通信事業者の会員向けシステムに関して業務部門と要件定義を行っていただきます。 外部・内部…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇概要 通信事業者の端末販売ECサイト(アプリ)の要件定義チームでの業務となります。 リニューア…
週5日
630,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
【案件概要】 社内で動いている複数のPJにPMとしてご参画いただきます。 ▼PJ例 ・広告デー…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社TV…
【案件概要】 自社の開発プロジェクトのPMとして、チームマネジメント、協業先会社やSIerとの渉外…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
■業務内容 カード会社ユーザ部署が主体的に推進しているシステム更改案件において、社員に近い立場でシ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
【業務詳細】 クリエイティブ・ディレクターやデザイナーなど複数のメンバーとともに、プロジェクトに参…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】CMS…
この度は弊社新規トレーニングサービスの認知向上に向けて、 サービスPRを担当いただける方を募集いた…
週3日・4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
◇概要 通信事業者の会員向けシステムに関して業務部門と要件定義~設計を行っていただきます。 外部…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社メディア・国内最大級規模の金融プラットフォーム事業部門の技術責任者を担っていただける方を募集して…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】オンライ…
この度は事業拡大に伴い、コーディングのできるWEBデザイナーを募集いたします。 エンジニアの方やW…
週4日・5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】テレビ…
大規模なWebシステムの開発プロジェクトで、PMOチームとして複数サブプロジェクトの開発マネジメント…
週5日
660,000〜740,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| ▼業務詳細 ・開発状況の把握とゴールに対しての課題… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 新卒向け就業支援サービスを展開している企業内でのデザイン業務です。 Wordpre…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
【Java・SQL】社内システム開発
社内システムの開発業務となります。 弊社ではネット広告に関する事業を行っており、社内の広告運用…
週4日・5日
250,000〜530,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL | |
定番
外国為替取引事業や仮想通貨交換業におけるイ…
【業務概要】 仮想通貨交換業における ネットワークサーバ、プラットフォームのインフラ基盤運用をお…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【QAテスター】自社WEBアプリケーション…
・WebアプリケーションのQA経験、デバッグやテスト業務経験 ・テスト対象の分析及びテストケースの…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不動産前 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【C/C++|週1日OK】"自立自走型" …
"自立自走型" のテクノロジー人材を輩出するためのIT人材育成プログラムを講師として運営していただき…
週1日・2日・3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿案件毎に異なります |
|---|---|
| 役割 | 講師(4/14・17~19の4日間の講師登壇) |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | CTO |
定番
【PM / 週5日】SFA導入を支えるPM…
【業務詳細】 ・プロジェクト進行管理 ・社内での要望とりまとめ ・外注先との折衝 社内に…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
この度は案件拡大に伴い、WEBデザインからコーディングまで対応いただける方を募集いたします。 …
週3日・4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Node.js/Py…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Saas / 週5日…
【業務詳細】 - プロダクトの要件定義 /仕様設計 - アプリケーションの設計/開発 - アプ…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アーキテクト |
| Java・Scala | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】親…
今回は、当社の要である企画・立案から関わっていただくPMを増員にて募集します。 【業務内容】 …
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| VB.NET・【一連の流れ】 ・営業担当と共にクラ… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
【案件詳細】 大手出版会社が保有するWEBサービスにおける、開発プロジェクトのマネジメントをお願い…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
①当社がスクラッチ開発をしているサービスをカスタマイズする開発となります。 現行のCMSから当社開…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | スクラムマスター |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日】自社画像…
自社画像・動画・音楽クリエイティブプラットフォームのデザイン業務です。 【業務】 - 仕様設…
週3日
250,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / UWP/C# / 週4日〜…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・C#・◇開発体制 開発は1チーム3〜6… | |
定番
【リモート相談可 / PDM / 週4日〜…
子育て中のママパパ様向けアプリ・Webメディア事業のマネジメント全般を担っていただける方を募集いたし…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ※具体的には、 ①既存クライアントへ定期サポート、… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
歩数計アプリサービスのプロジェクトマネージャーとしてサービス企画及び運用をリードしていただきます。 …
週4日・5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】自治体及び行政のDX化…
この度は事業の拡大に伴い、PMを募集いたします。 <業務内容> 自治体とともに、行政のDX(…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/JavaScri…
【業務内容】 Webページのデザイン及びコーディング業務をご担当いただきます。 ※Webデザイン…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋千種駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・■Webデザ… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件概要】 AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】t…
【作業内容】 主にtoC向けのアプリ/WEBサービスの受託開発でのPMやディレクターを募集中! …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Swift・Kotlin・Laravel・React | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Ruby /…
【担当業務】 ・自社開発のウェブアプリケーション(クラウドファンディング&コンテンツ、画像、文章、…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Ruby /…
【担当業務】 ・自社開発のクラウドファンディング&コンテンツ(画像、文章、pdfなど)のアップロー…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
【具体的な業務内容】 ■プロジェクトの体制検討、コミュニケーション設計・整備 ■プロジェクトの目…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】仮想通…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【お願いする業務】 ECサイト構築・運用におけるHTML/CSSコーディング ・PC/SP…
週3日・4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】W…
ユーザー向けWebサービスの設計・開発、進行管理をご担当していただきます。 弊社のサービスは全て自…
週5日
500,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
〈案件内容〉 ・当社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・当社グ…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日〜】…
自社サービスAzure開発のエンジニアリングマネージャーをお任せします。 当社は、ブランド品や骨董…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Azure | |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】基幹…
弊社は、Webアプリケーション・システム等の自社サービスの開発・運用を手掛けています。 基幹システ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川青葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】東…
大手Web系企業にてさらにサービス向上に向けて、当社サイトのプロジェクトを指揮していただける方を募集…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【具体的な業務内容】 ■自社サービスの運用、新規開… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】I…
組込み機器のソフトウェア開発における要件定義、仕様化、ドキュメンテーションをご担当いただける方を募集…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 社内のWebデザインや制作スタッフと連携しながらデザイン、コーディング作業 (※実…
週3日・4日・5日
230,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】新事…
【案件概要】 新規事業:ペット保険サービスにかかわるシステム開発チームのマネジメントをお任せします…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発での募集となります。 人材派遣会社にて就業中(又は求職中)の…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】急成長…
【業務内容】 ・ サービス全体に関する意思決定 ・ 戦略立案と開発計画ロードマップの作成 ・ …
週3日・4日・5日
660,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
今回の募集では、求人事業部もしくは、生活事業部での企画・デザイナー職のポジションを想定しています。 …
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京県庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・G… | |
定番
【フルリモ / Ruby/JavaScri…
今回のポジションではエンジニアの育成・マネジメントやプロセス改善などの問題解決、組織的改善を行ってい…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby・CircleCI・D… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】高校生向…
高校教育でのプログラミング義務化に伴い、高校生が“プログラミングを楽しく学べる”為のプロダクト開発を…
週5日
260,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】B…
【業務概要】 BPOキッティングプロジェクトにおけるPM業務 ・プロダクトオーナーの要望をもとに…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ヘ…
業務提携先のパートナー企業と協業しながら、歩数計アプリサービスのプロジェクトマネージャーとしてサービ…
週5日
570,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】オンラ…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 医療領…
週4日・5日
480,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】受託揮…
【案件詳細】 当社のリードエンジニアとして、自身が手を動かすことは勿論、チーム内のエンジニア管理も…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Python・Ruby・■具体的な業務内容 … | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】急成…
【案件内容】 開発の要となるエンジニアリングマネージャーを募集します。 このポジションでは、プロ…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週3…
【具体的な仕事内容】 ・システムコンサルティング 中小企業が抱える現状の課題や要件をヒアリングし…
週3日・4日・5日
390,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Java・C・C++・C# | |
定番
【フルリモ / PdM / 週3日〜】自社…
【業務内容】 ・各プロダクトの戦略立案と浸透業務 ・KGI・KPIマネジメント ・全体の施策管…
週3日・4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社ネ…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しており、企業や個人…
週4日・5日
740,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】採用管…
【業務内容】 弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Java・Spring… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
◇案件詳細 ・プロジェクトマネジメント関連作業 PMの管理業務サポート/情報サービス会社向けのB…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| ※本顧客プロジェクトは販売見積受注システム、MDMシ… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】
新サービスの企画~ディレクションを一手に担っていただくプロダクトマネージャーを募集します! 【…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Python・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社サービスの家具の会員制シェアマーケットを成長させるための機能追加、改善案の企画・実施、業務システ…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・Java・Apache・Tomca… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
〈案件内容〉 ・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、 …
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社開…
【業務内容】 ・ユーザーインタビューやデータ分析を通じて、顧客を深く理解し、顧客の課題を把握 ・…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Go・Cake・Lal… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
【業務詳細】 ある程度ある型にあわせて、週1本程度デザインや、バナーなどを対応いただくと共に、デザ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
350,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【Linux / 週5日】為替システム更改…
<募集背景> 現在、為替システムの保守運用の新規案件を予定しており、長期プロジェクトを予定しており…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Linux | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
システム運用業務の効率化を検討する企業へ、自社プロダクトの提案から要件定義・設計を行い、自動化プロジ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Vue・独自のDSLを覚えて頂く必要が… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手通信…
大手通信会社のユーザ向けスマホアプリ開発における、要求部門からの個別案件に対して、受付から要件定義、…
週5日
660,000〜790,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
【業務内容】 タクシーによるプレミアムなフードデリバリーサービスの、Flutterによるアプリ開発…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【illustrator / 週4日〜】顧…
【業務内容】 ■webサイトデザイン サイト構造を考慮したナビゲーション、情報設計に基づいたレイ…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| illustrator・Photoshop | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】ボディ…
【案件内容】 オフショア開発に伴うPM/ブリッジエンジニアとして活動出来る方を募集しております。 …
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】自社サービス開発におけ…
【案件概要】 ・コンシェルジュプラットフォームの構想を企画・仕様設計・プロダクト構築・運用までお任…
週5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【弊社で働く魅力】 ・自社プロダクトの企画・仕様決… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
弊社はリフォーム産業のデジタル化で、安心できる暮らしを提供するために、レガシーな領域での DX 化を…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・CakePHP・Ang… | |
定番
【PMO / 週5日】金融機関向け検索シス…
【案件概要】 金融機関向け検索システムの機能改善対応のPM補佐として進捗管理、開発ベンダのコントロ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
案件は弊社がプライムで提案している案件になります。 SFA・CRM・販売管理・契約管理業務に対する…
週3日・4日・5日
660,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
| JavaScript・Java・Apex・Visua… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
【案件概要】 弊社が開発しているAIソフトウェアにおけるPMO業務をご担当いただきます。 ・スケ…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】業…
現在、プロダクトの企画開発を加速すべく、プロダクトマネージャーの外部要員を募集しております。 …
週5日
830,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で今回はその自社新規システムに関…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週4日・5日
410,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
下記三つの事業を展開しております。 ・クラウドインテグレーション事業 ・データ分析サービス事業 …
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
【業務概要】 加盟店の申込から構築の手前までの加盟店運用の業務効率化を目的としたシステムの要件定義…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
☆フルリモ可☆【自社サービスシステム開発】…
自社サービスの開発・保守・運用する仕事です。 ユーザーにより良い価値を提供するためサービス改善を日…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・SQL(MySQL系) Git・ | |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Kotlinエンジニア |
| Kotlin | |
定番
自社プラットフォームサービス開発エンジニア…
・当社が運用するサービスのサービス開発に関わる業務全般 ・ユーザの利用状況の分析と改善案の提案 …
週5日
2〜3万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
注目
【UI/UX】ふるさと納税の老舗サイト関連…
・ふるさと納税ポータルサイトおよび、関連サービスのUI設計/デザイン ・営業、開発チームとの連携
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【週5/フルリモ/Ruby】エンタメ系自社…
・200万ユーザが利用する大規模サービスにおけるサーバーサイドの実装をメインでご担当いただきます。 …
週5日
8〜3万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
注目
【HTML5,CSS3,JavaScrip…
サイトの運用、新規コンテンツやページのマークアップ作業を中心に担当していただきます。 静的なコーデ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【マーケター】シニア向けBtoCサービスの…
【業務内容】 主にシニア層向けのBtoCサービスを行っている企業向けの広告運用 月100~200…
週1日・2日
160,000〜270,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【PM / 週5日】証券会社でのシステム開…
◆案件概要 ・システム開発案件における案件ディレクションの補佐 ・事業側から起案された案件につい…
週5日
520,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手企業のブランドサイトやプロモーションコンテンツを中心としたWebサイト開発のデザイン業務全般をお…
週5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
【案件内容】 ※下記は例になりますので、詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 ・自社用のLPデザ…
週3日
220,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】Fin…
【案件概要】 大手クライアントとの直接取引の中で、ウェブを通じたコミュニケーションの企画・提案・実…
週4日・5日
610,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / 開発ディレクター / 週3…
【職種詳細】 新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。 …
週3日・4日・5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
| Ruby・Typescript | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】大手建…
【業務内容】 上流工程だけでなく設計や開発、状況によっては運用まで関与できるのでプロジェクトに関係…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / HTML / 週4日〜】顧…
【会社概要】 サービス提供範囲としてEC戦略からマーケティング、UI/UX、カスタマーサービス・物…
週4日・5日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインの業務になります。 もし可能であればユーザビ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 自社のコーポレートサイト並びに、ECサイトのリニューアルを計画しており、専任でデザイ…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・illust… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】プロジェ…
お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・保守まで一気通貫でサービスを提供しています。 …
週5日
610,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Python / 週3日…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
グラフィックに特化した新規ゲーム事業におけるUI/UXデザイナーの業務を依頼します。 【業務内…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】Web…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 ■業務内容 - 視…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS/ 週5日…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 ◆案件概要 デ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / AIエンジニア / 週5日…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】外…
【業務内容】※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 弊社には外国籍エンジニアが多く在籍しており、外…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社プロ…
弊社のいずれかのプロダクトにおけるプロジェクトマネージャー(PM)として以下の業務をお任せします。 …
週5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】仮…
【案件概要】 自社で仮想通貨に関するアプリの新規開発を行っており、今回はそのプロジェクトにおけるプ…
週5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| (主な業務内容) ・ご担当いただくプロジェクトにお… | |
定番
【PM / 週3日】自社プロダクトのPM
パートナー企業様と連携・協業しながら、アプリケーションサービスプラットフォームに必要な要件定義から設…
週3日・4日・5日
410,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社で仮想通貨に関するアプリの新規開発を行っており、今回はそのプロジェクトにおけるプロダクトマネージ…
週3日・4日・5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
DSLでの処理記述や内部でPythonライブラリ使用するためPython記述の対応をお願いします。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
弊社の複数プロダクトのAndroidアプリ、iOSアプリ開発を担当いただきます。 Androidア…
週5日
570,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】転職/…
具体的な業務内容は自社で運営している人材紹介サービスの運用設計、運用、保守、監視。 ほかにも要件定…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】動…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
◆2D背景アーティスト 新規開発案件にて使用される各種背景イラスト制作に関わる業務です。 ・-背…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発です。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿、初台 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・React・Node.js・Apache・… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
以下の業務をお任せいたします。 ・テストデバッグ:弊社で運用しているテストデバッグ表に基づきWeb…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋今池駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・【具体的な業務… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状況を…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
旅行系ToC新規サービスの開発業務です。 iOSスマートフォンアプリの開発の設計と実装をお願いしま…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
美容業界の求職者向け求人ページ作成システムのリニューアル案件です。 リニューアルに伴い求職者・…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるクレジットカードや電子マネーの支出を一括管理するモバイルアプリ、キャッシュレス決済…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ア…
【業務概要】 顧客内にて開発を行っているアプリ開発支援 ・顧客折衝 ・要件定義 ・設計以降の…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社サー…
今回は新規PJとしてスマホアプリの開発を企画しており、アプリケーションにて弊社サービスの展開をしてい…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 要件定…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】仮想…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発になります。 すでに稼働しているシステムで機能追加を中心に…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Alamofire・RedHat・Cent… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日~】…
さらなる事業拡大を実現していくことを目指し、今回メンバーを募集しております。 現在立ち上げフェ…
週3日・4日・5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
さらなる事業拡大を実現していくことを目指し、今回メンバーを募集しております。 現在立ち上げフェ…
週3日・4日・5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・【具体的な業務内容】・ ・当社が運用す… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
受託や自社開発における様々なWebサイト制作、アプリケーション開発プロジェクトに参加いただけるエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
新規プロダクトのフロントエンドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 具体的にはプ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週5日
500,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】テレビ視…
テレビ視聴データをBI提供するレアSaaS開発において、主に開発チームのPMを募集します。 【業務…
週5日
920,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Typescript・Vue | |
定番
【フルリモ / デザイナー/ 週3日〜】V…
【案件概要】 VRのミニゲームを制作しており、開発を手伝ってくださる方を募集しております。 …
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外保谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】 フ…
フリーランスプラットフォームのシステム設計・開発・運用の中で、マーケと連携しSEO関連の開発対応をご…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】ドキュ…
◇業務内容 ・対カスタマーのドキュメント(要件定義、MTGアジェンダ等)作成 ・対エンジニアのド…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Swift・AndroidJava・◇プロジ… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】家事…
家事代行クラウドソーシングサービスにおける、サーバーサイドとフロントエンドの開発をご担当いただきます…
週5日
580,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】動…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週4日・5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
DSLでの処理記述や内部でPythonライブラリ使用するためPython記述の対応をお願いします。 …
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・役割:PG・SE フェーズ:詳細設計… | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
自社プロダクト(HR領域)開発全般をご担当いただきます。 ・機能拡張/改善の設計、実装、効果検証 …
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【サービス内容】 臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポ…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
【業務内容】 自社新規サービスのプロダクトマネージャー業務をお任せします。 ・新規サービスの全体…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Jira・Figma・Notion | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】イ…
【案件内容】 外資系コンサル(日本法人)が今後導入する新システムPJTのPM(PMO)ポジションを…
週5日
300,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
【業務内容】 現状のビジネスプロセス(データ処理を含む)の可視化とプロセス最適化の提案 BPRプ…
週5日
500,000〜900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【UI/UX】事業拡大によるデザイン作成
新規事業として急成長しているサービスのデザイナーを事業拡大に伴って募集しています。 こちらのサ…
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週4日〜】…
クリエイティブ・ディレクター、デザイナーとして、新規チャット広告事業における、クリエイティブ作成、そ…
週4日・5日
330,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【Rubyエンジニア】暗号資産に関わる自社…
本募集は、お客様の資産をお預かりし、 管理するウォレット開発運用部のオープンポジションです。 ※…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】親…
今回は、当社の要である企画・立案から関わっていただくPMを増員にて募集します。 【業務内容】 …
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
◇業務概要 クライアントであるリフォーム業者のWebサイト・LPのデザインおよび改修。 アクセス…
週3日・4日・5日
160,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・【Webデザ… | |
定番
【HTML/CSS / 週3日】ゲーム業界…
【会社概要】 ゲーミングデバイスやアクセサリー、アパレルなどゲームに関連する商材を中心に取扱いして…
週3日
250,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京幡ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / PM/PdM / 週3日〜…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 /サーバーサイド / 週…
当社はソリューション提供を通して企業の業務改善をサポートしています。 現在では、⾦融機関・通信会社…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| FileMaker | |
定番
【リモート相談可 /サーバーサイド / 週…
当社はソリューション提供を通して企業の業務改善をサポートしています。 現在では、⾦融機関・通信会社…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿勾当台公園 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| FileMaker | |
定番
【リモート相談可 /サーバーサイド / 週…
当社はソリューション提供を通して企業の業務改善をサポートしています。 現在では、⾦融機関・通信会社…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄西都城 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| FileMaker | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
【作業内容】 ※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 クライアントである大手サービス事業者様でセ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ド…
【業務内容】 ※クライアント様案件の為、詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 現在のECサイ…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・某査定アプリケーシ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【Vue.js / Nuxt.js】自社サ…
自社サービスシステムアーキテクチャーの刷新を担うフロントエンドエンジニアを募集しています。 【…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】マネジ…
▼業務内容 ・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基盤…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
〈案件内容〉 ・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモート/レジャー業界向けサービス】…
レジャー業界向けサービスを多数展開する企業において、システム統廃合のプロジェクトにバックエンドエンジ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【PM / 週5日】大手自動車会社でICT…
【業務内容】 大手自動車会社に常駐していただきます。 ・ベンダーコントロール ・クライアントへ…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】オンラ…
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
【案件概要】 ・ゲームのサーバ側APIの設計と実装 ・基盤ライブラリ、フレームワークの調査、利用…
週5日
500,000〜10,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】自社H…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週4日・5日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
【業務概要】 大手通信サービスのプロジェクト推進をご対応いただきます。 プロジェクト企画書や要件…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Java | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日〜】アジ…
【企業概要】 下記三つの事業を展開しております。 ・クラウドインテグレーション事業 ・データ分…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 インフラ運用全般を担当するMSPサービスを展開しており、物理環境から仮想・クラウドま…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
自社開発のクラウド人材管理ツールのUI/UXデザインを担っていただける方を募集いたします。 自…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】自社HR…
自社HRサービスのUIデザイン全般をご担当いただきます。 ・ユーザー側のプロダクト:求職者が使…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ベンチャー企業でのPHPエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社サービスのRubyエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申し込みをいただいている…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
マイクロサービスの開発手法を用いた自社サービスプロダクトのiOS向けのネイティブアプリ開発をお願いい…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
こちらはホテルや医療機関向けに自動精算機や受付、フロントなどの管理システムを提供している会社です。 …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社運営の旅行メディアのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 <主な業務> ・Rails…
週3日・4日・5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
今回は、自社英単語学習アプリサービスのアプリ開発業務をご協力いただけるアプリエンジニアを募集しており…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】英単語…
アプリサービスの開発をご協力いただけるサーバーサイドのエンジニアを募集しております。 社内に複…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務内容】 フロントエンドエンジニアとして、上場のための法人カードの管理及び振込代行機能を備えた…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】B…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Rails | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
iOS向けニュース系キュレーションアプリのサーバーサイド開発 業務詳細 - web上からキュ…
週3日・4日
260,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
春頃リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダ…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Swift・Node.js | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
「自社開発中」のiPhone向けニュース系アプリの開発(swiftを使用します) メインの開発…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
ベンチャー企業として自社のEC開発を行っております。 直近で資金調達をしたため人員を大量に募集して…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
ベンチャー企業でのRubyエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時に…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためののPythonエンジニアを募集しております。 開発…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・今回人員をたくさん募集しており、また求… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためののJavaエンジニアを募集しております。 開発案件…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・今回人員をたくさん募集しており、また求める… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためのSwiftエンジニアを募集しております。 開発案件…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・今回人員をたくさん募集しており、また求め… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためのKotlinエンジニアを募集しております。 開発案…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・今回人員をたくさん募集しており、また求… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためのTypescriptエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・今回人員をたくさん募集しており… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】スクラ…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためのGoエンジニアを募集しております。 開発案件内容の…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・今回人員をたくさん募集しており、また求めるレベ… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
ベンチャー企業で自社サービスグロースのためのVue.jsエンジニアを募集しております。 開発案…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・今回人員をたくさん募集しており… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】営…
今回、自社サービスをグロースさせるためRubyエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・-【求めるレベル】… | |
定番
【フルリモ / PHP/Laravel /…
今回、自社サービスをグロースさせるためPHPエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Lravel・【求めるレベル】 実務経験と… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
今回、自社サービスをグロースさせるためフロントエンジニアを募集します(Vue.js)。 サービ…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・【求めるレベル】 実務経験と… | |
定番
【フルリモ / Python/ 週3日〜】…
今回、自社サービスをグロースさせるためPythonエンジニアを募集します。 サービス開始後、多…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・【求めるレベル】 実務経験として最低… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】営…
今回、自社サービスをグロースさせるためJavaエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・【求めるレベル】 実務経験として最低3年… | |
定番
【フルリモ / GO / 週3日〜】営業支…
今回、自社サービスをグロースさせるためGoエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申し…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・【求めるレベル】 実務経験として最低3年以上… | |
定番
【フルリモ / Swift/Ktolin …
今回、自社サービスをグロースさせるためスマホアプリエンジニアを募集します。 サービス開始後、多…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・【求めるレベル】 実務経… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
今回、自社サービスをグロースさせるためフロントエンドエンジニアを募集します。 サービス開始後、…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・【求めるレベル】 実務経験と… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
自社で運営するマンガ配信サービス リスティング広告などに使用するバナーを制作して頂きます。 …
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・V… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・N… | |
定番
【リモート相談可 / 2Dデザイナー / …
【業務内容】 ※詳細については選考・面談にてご説明させていただきます。 今回は弊社で運営しており…
週5日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
| Photoshop・Illustrator・Afte… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社新…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Nod… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Sacla / 週3日〜】…
主に、各企業の個別課題へのソリューション設計・提供を行うアルゴリズム開発事業と、 汎用性の高い課題を…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ze… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・Z… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社サ…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Typscriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
<募集背景> 今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Swift・Node.js | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】小中…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・No… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】小…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・N… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
リリース予定の小中学生向けICT教材サービスの開発をお任せします。 現在成長フェーズでモダンな…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社運営の旅行メディアの開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androidアプリ…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・‐ | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社旅…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
自社運営の旅行メディアのWEBサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・And…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 このサー…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【Go,TypeScript】金融系Saa…
■業務内容: エンタープライズ向けに提供している弊社Saas導入プロジェクトのシステム開発担当者を…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・Go・Typescript・Rea… | |
定番
【スマホアプリ】コンビニ向けiOSアプリ開…
案件内容 :クリーンアーキテクチャによる小売店業種向けスマホアプリ開発 スマホアプリの…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【スマホアプリ】iOSアプリ開発業務
案件内容 :某小売店の公式のiOSアプリ開発 作業場所 :大崎(09:00 ~ 18:00) …
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【React】NFTマーケットプレイスのフ…
弊社がクライアント様から開発全般を委託されたWebサービスの運用開発をご担当頂きます。 基本的な要…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【PM】自社SaaS、PM(プロジェクトマ…
【業務内容】 顧客である大手金融機関やシステムベンダーと協力し、 プロジェクトの計画・管理・実行…
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Go】NFTマーケットプレイスのサーバー…
弊社がクライアント様から開発全般を委託されたWebサービスの運用開発をご担当頂きます。 基本的な要…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【Go】クラウド人材管理ツールのサーバーサ…
【業務内容】 ・新規機能の開発 ・マイクロサービス化に関わる開発 ・公開APIの開発 ・運用…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
【JavaScript/Ruby】アプリケ…
■事業内容 自社開発アプリケーションの開発、運営、販売 ■仕事内容 ● ユーザーの要望等を…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリケーションアーキテクト |
| JavaScript・Ruby・Rails・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React/Vue.…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】英単…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】英…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】英単語…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語WEBアプリサービスを運用しております。 今回は、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】Bt…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】Bto…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】B…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【即日採用!】ReactでBtoB、Bto…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
【業務概要】 弊社が運営するSaaSプロダクトのWEBフロントエンド(SPA)の開発全般を担当して…
週4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】地…
◆事業内容 ・地域情報流通事業 ・公共ソリューション事業 ・マーケティング支援事業 ◆主…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 東京23区以外西船橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Next.js/TypeS…
弊社のプロダクト群から共通で利用される認証基盤の開発プロジェクトに携わっていただきます。 ユーザ…
週3日・4日・5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザインプロジェクトの開発です。 自社で開発したプロト…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
弊社内のデザインチームにおいて、自社プロダクトやSI事業におけるフロントエンド開発のデザイン業務を担…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
弊社グループ企業でのスマートフォンアプリ開発をご担当いただきます。 ◆具体的な仕事内容 既存…
週3日
290,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】デジタ…
今回は自社サービスであるポータルサイトの企画・設計・開発に携わっていただける方を募集しております。 …
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| CSS・JavaScript・C#・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
【作業内容】 ・現場でIncortaというBIツールのシステム詳細を把握し、情シスと協同し、システ…
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川尼崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
【業務内容】 新規開発中のストレスチェックサービス開発において、AngularにおけるWEBコーデ…
週4日・5日
370,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Android / 週3日…
弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発、機能追加、保守運用業務を担当していただきます。 【諸…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】自社…
弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発、機能追加、保守運用業務を担当していただきます。 【諸…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】サ…
【案件内容】 ゼロからサイトを構築するのではなく、現在稼働しているものに対して、顧客要望を整理して…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日〜】PM…
今回は弊社内のPJにてPMOのサポートポジションに入っていただける方を募集しております。 【業務イ…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】某外資…
弊社にて某コンサルファーム様向けに複数の開発案件をご支援させて頂いております。 弊社代表が統括PM…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐・【業務内容】 ・MTGの参加、議事録作成(特に… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・‐ | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社旅…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・‐ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
自社運営の旅行メディアのサービス開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Androi…
週3日・4日・5日
460,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週4日・5日
570,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
NFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探しています。 A…
週4日・5日
660,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【VBA / 週5日】受託案件SE候補の募…
【企業情報】 映像サービス関連の開発やRPAを使用した業務効率化、自動化支援を中心にサービスを展開…
週5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 ・当社グループサイトのWordpressを使った開発案件です。 ※ポジションが複…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】自社グ…
弊社は、テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、アプリ、シ…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / ReactNativ…
【業務内容】 弊社が開発するヘルスケアアプリの開発業務をご担当いただきます。 現在の開発はオフシ…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】ITベン…
【業務内容】 CTO候補、またはPMとしてプロジェクト管理や後進の育成に携わっていただきます。 …
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上小田井駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / システム / 週4日〜】デ…
お客様の課題解決にあたり、当社プロダクトの導入支援、および運用サポートを担当いただきます。 顧…
週4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件概要】 リリースをしたばかりの女性向けのダイエットアプの広告クリエイティブ/UIUXを担当い…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週4日…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】B…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】Bto…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Scala / 週4日〜】…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】国…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
【業務内容】 下記の業務をご担当いただきます。 ・新規サービスにおけるUI/UXデザイン …
週3日・4日・5日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川関内駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】国…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【エンジニア】自社開発のWebサービス機能…
【案件概要】 ・自社開発のWebサービスの機能開発、改善 ・バックエンド・フロントエンドの開発 …
週4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【Python / 週5日】HR領域サービ…
【企業・業務概要】 累計導入社数20万社を突破した国内最大級のHR系SaaSのWebエンジニアを募…
週5日
410,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・ | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモ・週4…
【案件概要】 本案件は弊社で運用しているサービスの機能追加・保守運用業務を担当していただきます。 …
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(フロントエンドより) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】国内…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Rails | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのリプレイス案件を担当頂きます。 人員を大募集し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【インフラエンジニア】情報基盤構築人材募集
【業務内容】 ・データポータル化 ⇒Looker Studioを使用して対応いただく流れ …
週5日
4.1〜6.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
【案件概要】 医療法人社団のIT担当者としてHP作成/運用やSEO対策、DX推進などを行っていただ…
週5日
150,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
デザイナーとして、MoTが展開するサービスにおけるマーケティング・プロモーションのデザインをメインに…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社サ…
ベンチャー企業としてメインで自社のEC開発を行っております。サービス自体はいくつか運営をしているので…
週3日・4日・5日
240,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
【業務内容】 お客様先にてインフラ運用担当としての業務支援を担っていただける方を募集します。 …
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Go】機能要求を満たすプロダクトの設計・…
主な業務内容 ・プロダクトマネージャー、デザイナーなどと協働し、機能要求を満たすプロダクトの設…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS・GCP | |
定番
【AWSアプリ開発】請負立上支援(プリセー…
■業務内容 1, プリセールス時(受注前):AWSのクラウド基盤で動くWebアプリプロジェクトの営…
週2日・3日
290,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
一般社会人向け教育システムのエンハンス開発
oE/toC 向けオンライン教育プラットフォームのWeb システム開発プロジェクトです。 動画教材…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【2Dデザイナー】新規ゲームタイトルの2D…
未発表新規プロジェクトでの2Dペイントによる設定画(デザイン画)ならびに細部資料制作の業務です。 …
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【フルスタックエンジニア】自社プロダクトの…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するEdTechのベンチャー企業です。 ▼業務概要▼ …
週4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React … | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週4日〜】金…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 弊社のトレーディングデスク事業部にてクライアントワークにおけるバナー、動画、ランディ…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・-・‐ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
【案件概要】 クライアントである一部上場企業様の整備板金業向けのポータルサイトの開発に携わっていた…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】グ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStrutsベースの… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週5…
・スマホからの位置情報を取得してイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデータをスマホで取…
週5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】ECサ…
会員管理システムの開発業務をご担当いただきます。 【案件概要】 shopifyを使ったECサ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】技術情報…
▼仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】ソフト…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】ソ…
◆業務内容 ・ビジネスパートナー向けのWebフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週5日
570,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社ヘ…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】自社ヘ…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。 担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】オン…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】オンラ…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】オ…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】オンラ…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】自社転…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】自…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Sacala / 週3日〜…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Sacalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社転…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】A…
SaaS事業 AIによる自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿す…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】A…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】AI…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】AIに…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】AIに…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【Node.js】自動車サブスクリプション…
<業務内容> オンラインカーリースサービスの運用保守 今後の事業拡大、新しいチャレンジをして…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
SaaS事業 AI による自動動画制作ツール提供しています。 写真やテキストなどの素材を入稿…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ク…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】クラ…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】ク…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】クライ…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】クライ…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
現在、新規のサービスのリリースを進める上で、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀なチ…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PMO / 週4日〜】某外…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】新規…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】新…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【プロダクトマネージャー】金融系Saasの…
金融事業者向けの新規Saasの開発における、プロダクトの企画、ロードマップの策定に携わっていただきま…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】androidアプリの開発管理案件
【企業】 某大手通信キャリアのショップで使用するタブレット端末に 載せるandroidアプリの、…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
[営業事務] EC中心に商品登録や事務周り…
現在楽天やAmazonは勿論、8月からYahooショッピング/Shopifyへ新規出店し、国内の大型…
週2日・3日・4日
1.6〜2.8万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京幡ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 営業事務 |
定番
医療業界特化のSalesforceコンサル…
経験者募集/顧客の課題解決から構築までを一気通貫でお任せします! 構築ができるSEの方も募集中です…
週2日・3日・4日・5日
8〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【週5/フルリモ/Java】給与システムの…
■ PJ概要 ・給与システムの開発プロジェクトです。 ・開発をメインに、詳細設計~リリースまでを…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Kotlin | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】新規自…
<詳細> ・当社が運営する新規サービスに関するサーバーサイド実装 ・既存サービスにおける新規機能…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C・C++・… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・ある程度開発… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】新規…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・ある… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】新…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・あ… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・あ… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】新規サ…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・ある程… | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala・… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・ある程度開発… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】新規サ…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・ある程… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
新規プロダクト開発プロジェクトにご参画いただけるフロントエンドエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】ベ…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】ベ…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】ベンチ…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ベ…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Scala | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】ベンチ…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C・C++・… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】ベン…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
急成長中のベンチャー企業の案件となります。 (A)スクール向けの運営/顧客システム開発 (B)サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日・4日
390,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】モビ…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】リニ…
【会社概要】 保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェー…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【会社概要】 保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェー…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】リ…
【会社概要】 保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェー…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】リ…
【会社概要】 保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェー…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / C#/ 週3日〜】リニュー…
【会社概要】 保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェー…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】リニュ…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
保険関連サービスを自社開発し運営を行っている企業でございます。 これから成長フェーズに入るためスキ…
週3日・4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【企業紹介】 私たちのサービスは、単なるテクノロジーの提供ではなく、それぞれの事業で得た各業界の慣…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】飲食…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】飲…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】飲…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】飲食業…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】飲食業…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
自社サービスとして飲食店のメニュー・注文・決済を電子化するサービスを展開しております。 今回は…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】オフシ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
3D スキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフ…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【SRE】デジタルウォレットアプリにおける…
デジタルウォレットアプリにおけるサービスインフラの設計・構築・運用を担っていただきます。 金融…
週5日
550,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Go・AWS・ECS・Fargate・Lambda・… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 新サービスをゼロから立ち上げる醍醐味を味…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 新サービスをゼロから立ち上げる醍醐味を味…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】新規…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】新…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】新規事…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】新規事…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・・適正、ご要… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 フロントオフィス~…
週5日
570,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週5日
610,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 【依頼予定の業務…
週5日
570,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
■ アプリ開発 顧客の運用業務をサポートするコンテナアプリケーションの開発( ■ インフラ構築 …
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・-・Django | |
定番
【フルリモ / Vue.js/TypeSc…
当社が提供するサービスにおけるソフトウェア開発のポジションです。 本募集においては主にフロントエン…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
【業務詳細】 当社が提供するサービスのソフトウェア開発のポジションです。 本募集においては主にフ…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Rea…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Typescript・React・Dj… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
大手・中堅旅行会社向けの旅行商品検索プラットフォームの開発にフルスタックエンジニアとして携わっていた…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
【新規事業立ち上げ】週3日〜Pythonを…
自社サービスの開発全般をお任せいたします! ・新規/既存プロダクトおよび機能の設計・実装・テスト・…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
注目
【アーキテクトエンジニア】自社開発製品の設…
・プロダクトの内部設計(データモデル・モジュール構成)、外部設計(UI・インタラクション)のアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | アーキテクト |
注目
【業界トップシェア】自社サーバーサイドエン…
・各サービスの仕様策定と設計、開発・運用 ・Ruby on Rails、MySQL(Aurora)…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Fla… | |
注目
☆業界トップシェア☆【自社SaaSシステム…
・要件定義(連携仕様の整理、作業範囲の明確化等)、基本設計 ・システム連携先担当者との折衝業務、コ…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PL |
| JavaScript・Ruby・Swift・Ruby… | |
注目
【マーケティングマネージャー】マーケティン…
仕事マーケティンググループのマネージャーとして、マーケティング施策の立案・実行やメンバー育成をはじめ…
週3日・4日・5日
840,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
IT/インフラ業務サポート
・大手化粧品会社のアプリ開発に伴うインフラ、セキュリティ関連のタスク進行 DNS設定/SSL証明…
週4日・5日
550,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【開発ディレクター】キャリアメッセージング…
■業務概要 ・キャリアメッセージングアプリの公式アカウント運用 (配信内容立案、関連部調整、配…
週4日・5日
550,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【C++】光学顕微鏡関連の開発
光学顕微鏡関連の開発 →SDK開発・メンテナンス、シミュレータの改良・提案、 テストツール作…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川大船駅 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C++エンジニア】OpenCVを動作させ…
案件概要: メーカー開発の独自回路が載ったボード上で、 OpenCVを動作さ…
週5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++・Linux | |
定番
金融商品の取引管理システム開発&保守業務
・金融商品の取引管理システム開発&保守業務 ・金融取引の統合管理するシステム(Pkg)の保守業務、…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【PMO】エコサービスの運用および追加開発…
・システムの2次開発に向けた仕様検討および要件定義 ・上記に伴う、社内調整や各種問い合わせ対応、…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【業務内容】 ・社内の簡易ツールシステムの開発を行っていただきます。 ・言語選定も自由です。 …
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週3…
【業務内容】 ・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナ…
週4日・5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
今回は、自社が提供するコーチング事業の中でお客様が利用するアプリケーションツール開発、追加機能の導入…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 ネイル情報サービスのWEBエンジニアを募集しております。 <<業務内容>> …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週4日〜】…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C・C++・… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日〜】自社…
■仕事概要 ・プロジェクトに関する社内プロセスの管理 ・プロジェクトのデータを収集と共有、関連す…
週3日・4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / プランナー / 週5…
【案件概要】 新規スマートフォン向けRPGゲームのサーバーサイドエンジニアとして開発~リリース、運…
週5日
480,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日・4日・5日
740,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社サ…
自社サービスサイトのサーバーサイド開発を行います。 これから成長フェーズになるので多くのエンジニア…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
自社サービスサイトのサーバーサイド開発を行います。 これから成長フェーズになるので多くのエンジニア…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日】Sp…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週5日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】 これまでの広告・接客の課題を解決するためのPJを実施します。 ※詳細は、面談時にお…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】大…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・【… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】大成…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・【仕… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・【… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】大成長…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・【仕事… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・【仕事の魅力… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】大成長…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・【仕事… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・【仕事の魅力… | |
定番
【マーケター】自社オウンドメディアの改善
自社オウンドメディアの課題抽出、改善、収益化、LTV向上を目的としたマーケティング支援。
週5日
390,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋茗荷谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コンテンツマーケ |
定番
【C++】5GC アプリケーション開発支援
案件概要 :正常系呼処理機能を具備し、データをエッジで収集、保存、および処理をする …
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【SQL】インフラエンジニア
弊社クライアントの開発案件にご参画いただきます。 融資業務支援パッケージ開発業務となります。
週4日・5日
410,000〜510,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸北新地駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| C#・VBA・SQL | |
定番
【上流SE】スマートフォンアプリ開発仕様検…
案件概要 :スマートフォンアプリ開発仕様検討支援業務 案件内容 :スマートフォン向けクロスプラ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町/溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Swift・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【案件概要】 大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます! ■仕事内容 優…
週3日・4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Androi… | |
定番
【フルリモ / Node / 週3日】法律…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】自…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
・バージョンアップなどのリニューアル対応 ・クライアントごとの導入先により拡張カスタマイズに伴う開…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / Go/React / 週5…
当社が運営するサービスに関するフロント・バックエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サ…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Rea… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・【技… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
メインは受託企業で生保向けシステム開発を行っていただきます。 使用している開発言語はJava,C,…
週3日
260,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Perl・C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
・現在サービスインしているB2Cサイトに対して定期リリースしていく改修案件の要件整理、設計、開発依頼…
週3日
2.4万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。 担当業務は主にデザ…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設…
週3日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / .Net / 週3日…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
お金がより自由に届けられ、より明るく楽しい世界を実現できるように、 コンシューマー向けのアプリと、…
週3日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・開発はGo言語ですが、他言語でも、 APIサ… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務です。…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | 【Java】Webアプリエンジニア/クラウドネイティブ化およびマイクロサービス化 |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただきます。 ▼業務内容 ・仕様調査…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 業務詳細: 自社…
週3日
170,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【PHP(Laravel)/一部リモート】…
不動産業界に特化したソリューション提供として、Webシステムの設計・開発・運用をご担当頂きます。 …
週5日
410,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Java/C# / 週3日…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 すまいステップは、サービスを…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・業務詳細: ・社… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 フロントオフィス~バ…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【rails】特権ID管理製品の開発プロジ…
【企業紹介】 当社は、創業以来積み重ねてきた多くの技術、経験、ノウハウを活かし、アプリケーションテ…
週5日
250,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バック…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●具体的には ・2週間スプリン… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜420,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】東証一…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・裁… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Vue.js・Nod… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は、自社プロダクト…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 【業務内容】 ・クラ…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性の項目を可視化す…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や、改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行…
週3日
290,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービスや、ログ・セキュリティ等の共通方式が必要と…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
プロダクトは大きく3つあるのでその中におけるプロジェクトマネージャー(PM)として業務をお任せします…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】アーキテ…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週3日
340,000〜420,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / UX / 週3日】金…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】ソフトウ…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜400,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・Webフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定義からデプロイまでのプロ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ECサ…
【会社概要】 Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設…
週3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホ…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 ■業務内容 - 視…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB、プロジェクトC 案件Bは製品ページのクローリングを行います。 案件CはE…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件概要】 スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していた…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 全国主要都市のオフィス物…
週3日
360,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 全国主要都市のオフィス物…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・jQue… | |
注目
[システムエンジニア]自社ECサイトの開発…
■募集の概要: ・MakeShopサイトの改修・改良 ・WordPressで運用するメディアサイ…
週5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【Python/Node.js/JavaS…
・自社サービスのカスタマイズ案件対応 ・構築するシステム(フロントエンド/バックエンドシステム、A…
週5日
330,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】新…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Android / 週3日…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。フロントエンドや各…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】ECサイ…
【会社概要】 Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java,Kotlin /…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および特…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・W… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
100%自社サービスのWebアプリケーション開発業務になります。 最初は保守運用メインとなりますが…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週3日】金融…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】小…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築案件です…
週3日
280,000〜460,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
【SQL】インフラエンジニア
総合人材企業全体のデータベース開発をご担当いただきます。 具体的にはグループ間全体のデータベースを…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2SAStrutsをベースとし… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
急募
【フロントエンドエンジニア】サイト制作に携…
【企業概要】 Web・グラフィック・広告制作を事業展開する企業でご就業いただけるエンジニアの方を探…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸五条 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【PM 英語】自動車業界/グローバル企業の…
日系自動車メーカーとスウェーデン開発チームのプロジェクト管理をお任せいたします。 ・スウェーデン本…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(英語経験必須) |
定番
【Javaエンジニア】某国際プロジェクトの…
【概要】 自社サービスとして提供するRestAPIの開発メンバーとして基本設計からシステム試験を担…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外三鷹駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【SCCM運用】アプリケーションの配布、セ…
【案件詳細】 顧客標準PC(約7万台)に対して、アプリケーションの配布、セキュリティ更新プログラム…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
定番
【AWS等】アプリケーション運用
【案件詳細】 ・サーバ上でのSQL実行や手動シェル実行、ファイル操作、データ調査・抽出等 ・依頼…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
モバイルアプリ・クラウドWeb開発
【案件詳細】 ・当社のAI技術(HCTech、感情認識、心拍推定等)を適用したモバイルアプリ(An…
週4日・5日
670,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【AIエンジニア】AIアプリケーション開発…
【案件詳細】 当社の感情認識・映像脈波AIアプリケーション製品の開発・保守を中心業務とした、開発要…
週5日
620,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| C# | |
定番
【インフラ】AWS環境の設計/構築/保守対…
【案件詳細】 ・CloudFormationを利用した環境構築 ・新規AWSサービスのリスク評価…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
クラウド共通基盤グループ支援(AWS基盤運…
【案件詳細】 ・CACと別ベンダーにてAWS基盤の保守/運用を実施 ・顧客先にてAWSサービスの…
週4日・5日
670,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ】Azure AD認証変更作業
【案件詳細】 クラウドアプリへのSSO認証を一部、オンプレミスAD FS認証からAzure AD認…
週4日・5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
オンプレミスActive Director…
【案件詳細】 オンプレミスActive Directory導入(Enterprise向け)の設計・…
週4日・5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
国際財務システム保守
【案件詳細】 リース取引管理システムの改善 (主な機能) 取引受払管理(取引、利息額の入出金管…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【Java・JavaScript】証券系基…
【案件詳細】 証券系システム(SIRIUS-B、流動性リスク管理(円貨)、流動性リスク管理(外貨)…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外府中 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【セキュリティエンジニア】自社サービスのセ…
・自社が提供するサービス、プロダクトのセキュリティ強化 ・全社的な情報セキュリティ管理状況の評価、…
310,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
| AWS | |
定番
BizDev(事業開発)
【業務内容】 ・市場、競合調査 ・事業開発のロードマップ策定 ・事業企画~プロジェクト必要要件…
310,000〜630,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
定番
【マーケティングメンバー】集客効率を最大化…
【業務内容】 ・集客効率を最大化するためのマーケティング戦略の立案と実行 ・チームメンバーによる…
380,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】受…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript・▼主な業務内容 ・ク… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週5日】自社グル…
〈案件内容〉 弊社は、テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
【業務内容】 ※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 弊社クライアントのスマホ向けのリプレ…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社はウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営しております。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社はウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営しております。…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日
340,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
近年リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探してい…
週3日
390,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【会社概要】 弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化…
週3日
220,000〜240,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】MEO支…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様にて、今回はその自社新規システム…
週3日
340,000〜420,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜360,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイン |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
当社グループでは、インターネット広告事業を中心としたBtoB事業、BtoC事業の2つの領域にて多様な…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
当社グループでは、インターネット広告事業を中心としたBtoB事業、BtoC事業の2つの領域にて多様な…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております。 クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【SQL / 週3日】東証一部上場企業の工…
当社は、永い伝統に培われた優れた技術と最新鋭の製造設備を、万全の品質管理体制のもとにシステム化し、定…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 神奈川小島新田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は、自社の教育系…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rails6・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務です。 【業務内容】 1機能…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 ■…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件概要】 物流業様向けにAIアルゴリズムの開発を行っております。 今回は本プロジェクトにご参…
週3日
340,000〜470,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容: 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社Sa…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 企…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
顧客のマスターデータマネジメントのプロジェクトに携わっていただける方を募集いたします。 ※詳細はご…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【ライター】制作会社のライティング担当
【案件概要】 学校・教育系の媒体へのライティングをお願いいたします。 テープから文字を起こして作…
週2日・3日
140,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
定番
【Unity / 週5日】VRプロダクトの…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週3日】…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインの業務です。 もし可能であればユーザビリティ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】VR…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜230,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
〈案件内容〉 ・バリュエンスグループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・オンライン…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【データ分析】PJ内でのデータ分析実装
【業務内容】 クライアント内で顧客のデジタルシフトを専門とした部隊があり、さまざまな受託案件を行っ…
週2日・3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿PJによる / リモート |
|---|---|
| 役割 | データ分析 |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 ユーザー数560万人の経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 …
週3日
300,000〜490,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】転職/採…
具体的な業務内容はプロダクトの新機能や改善施策の企画・設計・テスト・実装などで、メイン業務は実装とな…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【データサイエンティスト/機械学習】PJ内…
【業務内容】 クライアント内で顧客のデジタルシフトを専門とした部隊があり、さまざまな受託案件を行っ…
週2日・3日・4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿PJによる / リモート |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト・機械学習エンジニア |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務内容】 フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【TypeScript ソフトウェアエンジ…
保険の申込・請求などお客様とのインターフェースを自由に作り出せるSaaS開発 Vertical S…
週4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務詳細】 今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 ・Wor…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【TypeScript ソフトウェアエンジ…
保険の申込・請求などお客様とのインターフェースを自由に作り出せるSaaS開発 Vertical S…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】インフラ…
新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務していただきます。 開発言語はGpで…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝業務から…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
【詳細業務内容】 UnityベースにPhotonやMonobitエンジンを用いてスマホ向けのMMO…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【Laravel/Unity / 週3日】…
ネイティブプラットフォーム(App Store、Google Play)でのソーシャルゲームの立ち上…
週3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【案件概要】 内視鏡動画データを管理するための、オンプレミスサーバーのサービス構築及び、その上で動…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務詳細】 ▼大枠の業務 - 新規プロジェクトの工数見積もり、設計、開発 - 各種ツール・フ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【業務内容】 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 ・クライアントメディア開発 ・クライア…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【PM/データサイエンス】データ利活用ナレ…
■業務概要 ・ビジネス部門のデータ活用推進のためのナレッジ社内共有サービス開発において、データ利活…
週3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/データサイエンス |
定番
【Python】大手通信会社キャリア決済の…
■作業内容 施策の実行とそれに伴う必要なデータ分析/資料作成/運用支援などの施策実行支援業務 …
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL・AWS | |
定番
iOSエンジニア
担当いただくプロジェクトとしては新機能追加、UI/UXの改善、パフォーマンス向上、技術刷新などがあり…
280,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Ruby・Swift・Ob… | |
定番
【Rubyエンジニア】リニューアルシステム…
・リニューアルシステムの仕様・設計のキャッチアップ、開発、運用 上記をメインに、下記興味のある…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・S… | |
定番
【PHP/Ruby】Webエンジニア
・図面管理・情報共有システムの設計・開発 ・開発要件の優先付け ・新規プロジェクトリーダーやエン…
280,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【Vue.js】Webフロントエンドエンジ…
・図面管理・情報共有システムの設計・開発 ・開発要件の優先付け ・新規プロジェクトリーダーやエン…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
インフラメンバー(SRE)
・大量の図面や写真データを処理するWebアプリケーションやiOSアプリから接続されるAPIなど、多様…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【プロダクトディレクター】システム要件定義…
・ユーザーや営業から寄せられる課題の理解、整理 ・自社開発システムを用いた課題に対するソリューショ…
380,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
プロダクトマネージャー/エンジニアリングマ…
自社開発システムはこれまで図面、写真、報告書など手持ちのアイテムをすべてiPadに格納、外出先でオフ…
440,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【PM】アライアンスディレクター
・ユーザーや営業から寄せられる課題の理解、整理 ・自社開発システムとアライアンス先とのシステムの座…
380,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
エグゼクティブオープンポジション(組織開発…
・プロダクト開発サイクルの整備・強化(継続的な見直し・改善) ・ベロシティの向上 ・信頼性の高い…
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
テクニカルサポートエンジニア
・テクニカルサポート対応 ・品質管理、レビュー ・リリース業務 ・バッチプログラムやツールの作…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
SharePointOnlineをベースと…
SharePointOnlineをベースとした「社内ポータルサイトの改善」 全社アンケート等を…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/テックリード |
| VB.NET・SQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日】Sp…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【業務内容】 総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当い…
週3日・4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【案件概要】 医療×AIにおける動画データを利活用するため、不要なシーンをカットしたり加工し動画の…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
・自社CMSの新規機能開発 *・金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リー…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】ソフ…
自ら課題発見を行うなど、これから訪れる様々な困難を一緒に解決してプロダクトをともに成長させていくこと…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
* ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsによる各種機能開発 * コ…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 Androidエンジニアの方には、プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービ…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべてをお任せ致します。…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・₋ | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / フルスタック / 週…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Ob-C / 週3日…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
メインは受託企業で生保向けシステム開発を行っていただきます。 使用している開発言語はJava,C,…
週3日
260,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Perl・C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇案件詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなります。 既存資材を…
週3日
230,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Javasc…
不動産情報B2Cサイトの改修案件の設計者を募集します。 ・現在サービスインしているB2Cサイトに対…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲は以下です。 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイ…
週3日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / .Net / 週3日…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | VB.NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつAPI開発ができる、フルスタックエンジニアを募集してい…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社サ…
【案件内容】 弊社は、BtoB領域に特化したサービスを展開しています。 この度、サービス拡大によ…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇案件概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業に…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただけるエンジニアを募集しています。 …
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
Ruby on Railsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ◆業務内容 …
週3日
170,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】マル…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
100%自社サービスのWebアプリケーション開発業務になります。 最初は保守運用メインとなりますが…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週3日】金融…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●業務詳細 ・2週間スプリ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・AWS | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
▼案件概要 スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
・社内向け機関システム開発(メイン業務) 物件検索システムを自社開発しており、システムの機能追加や…
週3日
360,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国内最…
【業務内容】 主に下記の業務に携わっていただきます。 ・開発メンバーマネジメント ・効率的な開…
週4日・5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】コンシュ…
【業務内容】 ・様々なコンシューマー向けサービスの開発管理 ・オフショア開発チームのコントロール…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 …
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
【業務内容】 HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアッ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
【依頼予定の業務】 既存システムと新規システムの移行の設計をお願いします。 ※場合によって、開発…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 フロントオフィス~バックオフィスが利用…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【COBOL】自動車業界向けのシステム開発
・設計全般 基本設計・詳細設計作業 ・実装 terraformでInfrastruct…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・・Azure ・Teraform ・De… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 フロントオフィス~バックオフィスが利用…
週3日
360,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Go/Python …
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】自…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
PMとしてプロジェクト計画、WBS/スケジュール作成、進捗管理、議事録作成などから入って徐々にステッ…
週4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 秋葉原飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・Cassandra・業務詳細:… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Vue.js・Nod… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は、プロダクトのア…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 【業務詳細】 ・クラ…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
【週3~&フルリモートOK】サーバーサイド…
今年リリース予定の自社新サービスのテックリード業務 まずはプログラム設計から作成のリーディングをお…
週3日・4日・5日
330,000〜710,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(テックリード) |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
【PJ概要】 本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Web…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / React/Vue.js …
■案件概要 プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービスや、ログ・セキュリティ等の共…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js/TypeS…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB・C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 案件C:他社…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / JavaScript/HT…
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】経営ダッ…
■業務内容 ・ダッシュボードの要件定義・運用設計・テスト ・業務要件・画面要件定義及び要件定義書…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要: iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のネイティブアプリケーショ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
■案件概要 ・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能につい…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 現在、社内向けツール機能は最…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●業務詳細 ・2週間スプリント… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜420,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python/R / 週3…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】MEO支…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 現…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ク…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築をお願い…
週3日
280,000〜460,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStruts Sp… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜400,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・Webフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定義からデプロイまでのプロ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ECサ…
弊社は、Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設計からサ…
週3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】ECサイ…
弊社は、Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設計からサ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
社内NFT事業におけるUI/UXデザイン、…
【業務内容】 社内NFT事業におけるUI/UXの改修作業、意見出し。 【特徴】 スタートア…
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【PHP】WEBシステム開発会社のエンジニ…
弊社で請け負っているWebシステムの開発業務をご担当いただきます。エンジニアリーダーとしてPMと協働…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿霞が関 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【PM】自動車メーカーアプリ(IoT連携)…
■案件概要 ・大手自動車メーカーの新規サービス開発を行っています。 ・ハードウェアと連携したプロ…
週2日・3日
330,000〜460,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜470,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
<募集背景> 今回、WE場プリの開発エンジニアを募集いたします。 サーバー型のアプリ開発を想定し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Elasticsearch…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しておりまして、企業…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で今回はその自社新規システムに関…
週3日
340,000〜420,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜360,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイン |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML、CSS、JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】自社グル…
〈案件内容〉 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
決済代行会社様にて追加開発、新規開発、チームの一員として、お客様と対話しながら、一緒に開発を進めてい…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【PM / 週5日】IFA業務部門、システ…
■業務内容 ・IFA業務部門での新規案件の立案・計画の支援 ・IFA業務部門での業務要件の作成支…
週5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】エネルギーメーカー Project…
■案件概要 ・全国数千店舗で利用されるQRコード決済のモバイルアプリケーション開発プロジェクトでf…
週4日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
事業拡大に向け、本格的に採用活動をスタートします。 今回は、フロントエンドエンジニアとして、情…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
この度、受託開発案件の増加に伴いお客様との折衝も行っていただけるエンジニア様を募集いたします。 …
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・業務詳細 ・WordPre… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、業務の生産性向上と効率化のためのシステム導入・カス…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
今回はスマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Python・C・C++・C#・Unity・Mono… | |
定番
【ディレクター】日系企業におけるLP制作・…
■案件概要 ・マーケティングソリューション(SaaS)企業における、LP制作・LINE運用のディレ…
週3日・4日
260,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【PM】保険業関連企業でのNW・SEC環境…
■案件概要 ・NW環境、セキュリティ環境のリデザインに向けたコンサルティングの推進 -NW環境の…
週3日・4日・5日
550,000〜770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【イラストレーター】自社キャラクターのポー…
自社キャラクターの、ポージングパターンをいくつかデザインいただける方を募集しています。 ■働く…
週1日・2日・3日
250,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
定番
【PM/PMO】大手銀行システム部における…
■案件概要 大手銀行における各種サービスの開発支援 既存サービスのエンハンス、新サービス開発、法令…
週5日
550,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM・PMO |
定番
【TypeScript】社内システム開発
■作業内容 社内システムの開発業務となります。 ■作業場所 ・リモートワーク可 ・作業場…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・SQL | |
定番
【バックエンド/ リモートOK】誰もが1日…
サービスを拡大するフェーズに突入した今、プロダクトの根幹から携わるアプリ開発エンジニアを募集します!
週4日・5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・-・開発言語:Python -・フレ… | |
定番
【リーダー】UIデザイナー
スマートフォンゲームのデザイナーとして画面設計・UIデザインだけでなく、UIアニメーション等を用いた…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リーダー】3Dエフェクトデザイナー
スマートフォンゲームの3Dエフェクトデザイナーとして、エフェクトの制作及びクオリティ管理を行っていた…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | エフェクトデザイナー |
定番
【3Dモデラー】スマートフォンゲームの美術…
スマートフォンゲームの3Dモデラーとして、3Dゲームの背景を中心に、キャラクターやpropなどのモデ…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【3Dモデラー】スマートフォンゲームのキャ…
スマートフォンゲームの3Dモデラーとして、3Dゲームのキャラクターのモデリング ・キャラモデルの作…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【Unity,Maya】3Dモーションデザ…
スマートフォンゲームの3Dモーションデザイナーとして、キャラクター(人体、クリーチャーなど)の手付け…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【アートディレクター】スマートフォンゲーム…
スマートフォンゲームのアートディレクターとして2D/3D全般(キャラデザイン/モデリング/モーション…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アートディレクター |
| ー | |
定番
スマートフォンゲームのシナリオディレクター
スマートフォンゲームのシナリオディレクターとして、シナリオのクオリティコントロールを行ってもらいます…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | シナリオディレクター |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社はECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションをワンストップで行ってお…
週3日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript・G… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントのスマホ向けのリプレイ…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 ・機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社AI…
【仕事内容】 自社プロダクトの価値を最大化させるために、開発チームをリードしていただける方を募集い…
週5日
410,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐・【具体的には】 ・プロダクトの課題を発見し、開… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジニ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正などに携わっていただけるエンジ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は、自社の教育系…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務をご担当いただきます。 1機能単位…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容: 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 要件…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などの…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべてをお任せ致します。…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
UI/UXデザイナー(新製品開発)
新製品(詳細は面談にて)の開発において、UI/UXデザイナーとして参画いただきます。 ■仕事内…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Unity / 週3日】VRプロダクトの…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週3日】…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインです。 もし可能であればユーザビリティのお手…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・ShellScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】VR…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜230,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / HTML/JavaS…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
弊社ソリューションは、データ統合の技術を活用し、マーケターの意思決定を支援する、データ活用のコンサル…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
メインは受託企業で生保向けシステム開発を行っていただきます。 使用している開発言語はJava,C,…
週3日
260,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Perl・C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
不動産情報B2Cサイトの改修案件の設計者を募集します。 現在サービスインしているB2Cサイトに…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。担当業務は主にデザイン…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲は下記の通りです。 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インター…
週3日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / .Net / 週3日】人事…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
コンシューマー向けのアプリと、法人向けのプラットフォームを提供しています。 金融という高い公共性の…
週3日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務です。…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・- | |
定番
【バックエンドエンジニア】自社サービスHP…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【PM or EM】自社査定プラットフォー…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM or EM |
定番
【プロジェクトマネージャー】自社サービスH…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【BIエンジニア】顧客連携基盤の開発
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | BIエンジニア |
定番
【フロントエンドエンジニア】自社プラットフ…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【ネットワークエンジニア】基地局構築サポー…
案件概要 :問題管理、他部署と連携したトラブルシューティング 基地局機器正常性確認 …
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川/川崎 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Linux | |
定番
【SQL・Python】d払い利用促進・加…
■作業内容 1) アクティブリスト、ターゲットリストなどのリスト作成業務 2) アクティブ率…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
【React、JavaScript】自社内…
自社サービスの開発および運用。新規・既存を含めた様々な案件の技術支援を行っていただきます。 フ…
週5日
250,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 携帯電話基地局の監視業務効率化 AWS ECS上にDjangoRestFramework…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPA(Spring, …
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただける方を募集します。 詳細: ・…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ▼業務詳細 ・自…
週3日
170,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
具体的な業務内容はプロダクトの新機能や改善施策の企画・設計・テスト・実装などで、メイン業務は実装とな…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Python/Go …
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】自…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要 iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションのネ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 対応する機能については、エンジニア自…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【PM】社内ポータルサイトの改善
【案件詳細】 社内ポータルサイトの改善。 全社アンケート等をで課題を吸い上げて、それらに対し…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| C# | |
定番
人事給与パッケージ「COMPANY」の保守…
・顧客人事部から要件ヒアリングを行いながら、システム要件定義を行う。 ・COMPANYの設計(設定…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
【Kotlin】一部リモートOK|モバイル…
■主な業務内容 ・モバイルアプリ(Android) の開発・運用 ・企画メンバーと協力しながらク…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Kotlin・AWS Github MacBoo… | |
定番
【Kotlin】AI技術を活用した新たなタ…
・タクシーアプリの新規開発案件となります。現在リリースされているものの追加開発をメインに行なっており…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
急募
【リモート可】QAエンジニア
新補聴器フィッティングシステムの開発案件にて、 テスト計画書・テスト進捗管理・テスト設計・実施・P…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| C#・VB.NET・C#.net | |
定番
【Swiftエンジニア】大手バンキングアプ…
バンキングアプリの開発案件となります。設計や実装をメインに行なっていただきます。 ・就業時間 …
週5日
250,000〜510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・RXSwift・(Swift) | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Android / 週3日…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発 ・機能追加 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】自社動…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・弊社が運営する、各種サービスのアプリ開発 ・機能追加 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> 社内向け機関システム開発を担っていただけるエンジニアを募集します。 物件検索システ…
週3日
360,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<業務内容> 社内向け機関システム開発を担っていただけるエンジニアを募集します。 物件検索システ…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・AWS | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
【PJ概要】 本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
全プロダクト共通のアプリケーション基盤における以下の業務をご担当いただきます。 ・共通基盤の技…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
社内システム運用の支援を担っていただける方を募集します。 業務内容として、社内業務を理解して業務内…
週5日
390,000円以上/月
| 場所 | 神奈川日吉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL・・SQL、DB操作経験 ・ドキュメント整備… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【フルリモ / C++ / 週3日】Lin…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホスト…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【コンサルティングファーム】B2B商材の事…
エンドクライアント・自社内向けのコンサルを募集しております。 理由としては弊社社員同等に動ける人員…
週5日
840,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | VBA・Excelエンジニア |
| MSスキル(Excel:sumif、vlookup、… | |
定番
【自社サービス】技術PM(PdM)
スマホアプリを基盤にした自社サービスのPMをお任せいたします。 Swift・KotlinからFlu…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Flutter Node.js・EXPRESS … | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログや、いただくお問い…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB・C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリング 案件C:他社ECサイ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
急募
【アプリ系】UIデザイナー
カフェや個室ブースなどの空き席をアプリから予約し、ワークスペースとして利用できるWorktechサー…
週1日・2日
130,000〜330,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Swift・Sketch:・UIデザインツール O… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
主な作業内容は以下の通りです。 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポ…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 主な作業内容は下記になります。…
週3日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、l今回はその自社新規システム…
週3日
340,000〜420,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜360,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイン |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
〈業務内容〉 ・当社グループサイトのWordpressを使った開発案件 ※ポジションが複数…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】ECサイ…
会員管理システムの開発業務をご担当いただきます。 shopifyを使ったECサイトの構築 2…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回、クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバ…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
仕事内容: AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・1… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】HR…
今回の案件は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務で…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
急募
【自社サービス】エンジニアリングマネージャ…
◆業務内容 ・エンジニア組織の設計・構築 ・エンジニア組織のピープルマネジメント(テックリード・…
週3日・4日・5日
580,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | CTO |
| Swift・Ob-C・CocoaPods・Xcode… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週3…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日
2〜3万円/日
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、 顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日
340,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
新リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探していま…
週3日
390,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
【自社プロダクト】PdM(CRM)
・プロダクト戦略・ポリシーの立案・策定・遂行 ・ 製品企画・開発・リリース・成長のロードマップを策…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM(CRM) |
| ・エンジニア+PMもしくはWebディレクターとしての… | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforcを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 新規開発中のストレスチェックサービス開発において、AngularにおけるWEBコーデ…
週3日
220,000〜240,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
【自社プロダクト】PdM(本部システム)
・プロダクト戦略、ポリシーの立案/策定/遂行 ・製品企画、開発、リリース、成長のロードマップを策定…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM(本部システム) |
| ・エンジニア+PMもしくはWebディレクターとしての… | |
定番
【フルリモ / Git / 週3日】MEO…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 すまいステップは、サービスを…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・業務詳細 ・社内… | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●具体的には ・2週間スプリン… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜420,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python/R /…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】シ…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
注目
【業界トップシェア】 リードデザイナー(マ…
市況・お客様のニーズの変化を踏まえた新規プロダクトのリリースや既存プロダクトのUI/UXの改善等が増…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー(リードデザイナー) |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・Cassandra・業務詳細 … | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPCnGraphQL | |
注目
【業界トップシェア】リードデザイナー(マネ…
・応募者の管理・対応 ・面接、面談の日程調整(オンライン) ・採用パートナーとの連携・連絡・調整…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 採用担当 |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 【業務内容】 ・広告…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【大手金融系】Node.js開発案件
・バンキングアプリの開発案件となります。設計や実装をメインに行なっていただきます。 就業時間:8:…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【大手金融系】androidアプリ開発案件
・バンキングアプリの開発案件となります。設計や実装をメインに行なっていただきます。 アサイン後2週…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 弊社クライアントのスマホ向けのリプレイス…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【スマホアプリ】オークションiOSアプリ開…
案件内容 :オークションサービスアプリの新規機能開発、既存機能改修。 開発はペアプログ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町紀尾井町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
QAエンジニア
【業務内容】 QA担当として、システム変更に伴うテスト設計、テスト仕様書の作成、テスト推進を担当し…
週3日・4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、お客様のデータを活用した機械学習モデルの開発、シ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】小…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築です。 …
週3日
280,000〜460,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStrutsベースの… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】バックエ…
地方の中小・ベンチャー企業や個人商店を救うためのサービスを提供しています。 日本企業の99.7%は…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / SQL/Python / …
今回ご依頼案件として、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインい…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
【案件概要】 クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正などに携わって…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【SQL / 週3日】東証一部上場企業の工…
弊社は、永い伝統に培われた優れた技術と最新鋭の製造設備を、万全の品質管理体制のもとにシステム化し、定…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 神奈川小島新田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rails6・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務を担っていただける方を募集します。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近は、…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 要件定…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【Laravel/Unity / 週3日】…
ネイティブプラットフォームでのソーシャルゲームの立ち上げに携わっていただきます。 開発・企画・…
週3日
240,000〜290,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
・自社CMSの新規機能開発 ・金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リーダ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
分析基盤構築や運用にかかるデータエンジニアの手間を削減すべく、新機能開発、データソース(DB、広告A…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
下記の業務を依頼します。 * ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsに…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 ユーザー数560万人の経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 …
週3日
300,000〜490,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【テックリード】ペット専門サービスを運営す…
ミッションは、ペット業界の様々な課題や問題点をITの技術で解決すること。 課題や問題点に取り組める…
週4日・5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | テックリード |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
具体的な業務内容はプロダクトの新機能や改善施策の企画・設計・テスト・実装などで、メイン業務は実装とな…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などの…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
このポジションでは、メンバーと共鳴しながら、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日】イ…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメイン、もし可能であればユーザビリティのお手伝いなど…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】VR…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます。…
週3日
170,000〜230,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】電子チ…
【業務内容】 弊社が運営する電子チラシ配信サービスにおける開発ディレクション業務をご担当いただきま…
週4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・CakePHP・cordova・Angula… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜470,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しておりまして、企業…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js / …
【業務内容】 フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務詳細】 今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 ・Wor…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
生産性向上と効率化のためのシステム導入・カスタマイズなどをお任せします。 【具体的な業務内容】…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
スマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを通過と…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社は、今後も成長するEC分野において、様々な業種業態の企業、多種多様なツールを活用したソリューショ…
週3日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / Java/C# / 週3日…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【システムエンジニア】小売業基幹システムの…
案件内容 :ユーザーマスターの移行に伴う各種機能の要件定義からリリースまでの作業 作業場所 :飯田…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【Webディレクター】SNSのトレンドをつ…
案件の増加と、さらに1案件ごとの予算増加などで クリエイティブチームがリソース不足となっています。…
週4日・5日
390,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
プランナー(新規企画:リーダー)レベルデザ…
スマートフォンゲームのレベルデザイナーとして、新規開発中もしくは運用中のスマホゲームのレベルデザイン…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
ゲームディレクター(新規企画/運用)
スマートフォンゲームのプランナーとして、新規開発中もしくは運用中のスマホゲームのディレクション及びプ…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームディレクター |
定番
プランナー(新規企画/開発プランナー)
スマートフォンゲームのプランナーとして、新規開発中もしくは運用中のスマホゲームのプランニング業務に関…
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
プランナー(新規企画:リーダー)レベルデザ…
新規スマートフォンゲームのバランス設計、チューニング業務に携わっていただきます。 キャラクター…
280,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | バランス設計 |
定番
【Python / SQL】リードデータエ…
データ基盤の運営を行うリーダーとして、チャットボット事業における、事業環境の変化やデータ基盤の技術ト…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・SQL・AWS Athena Gl… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|リモート相談可…
【案件概要】 弊社で提供しているデータ解析SaaSにおけるシステムの信頼性と拡張性の向上のための新…
週5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Rust(ActixWeb・t… | |
定番
【3Dデザイナー】スマートフォン向けゲーム…
【企業概要】 大人気少年漫画を取り扱った現在運営中の スマートフォン向けゲームのプロジェクトに携…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【AWS等】社内の開発環境などに関わるクラ…
当社が取り扱うソリューション(クラウド、AI、データレイクの環境・技術を活用したソリューション)や、…
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS Linux Windows | |
定番
【フルリモ / PM/PdM / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件概要】 HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスター…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 現在、フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、…
週3日
340,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
弊社ソリューションは、マーケターの意思決定を支援する、データ活用のコンサルティングサービスを提供して…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
弊社ソリューションは、マーケターの意思決定を支援する、データ活用のコンサルティングサービスを提供して…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【Java / 週3日】生保向けシステム開…
メインは受託企業で生保向けシステム開発を行っていただきます。 使用している開発言語はJava,C,…
週3日
260,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Perl・C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Javasc…
不動産情報B2Cサイトの改修案件の設計者を募集します。 ・現在サービスインしているB2Cサイトに対…
週3日
2.4万円以上/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。 担当業務は主にデザ…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設計…
週3日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / .Net / 週5日…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理アプリケーションの開発にご協力いただけるソフトウェアエンジニアを募集…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務に携わっていただける方を募集します。 ・仕様調査 …
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ◇業務内容 ・自…
週3日
170,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇業務内容 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業に…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
◇案件概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業に…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから負債が増大…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから負債が増大…
週3日
390,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 ・クライアントメディア開発 ・クライア…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
▼業務内容 EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、…
週3日
440,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】自…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があり、それ…
週3日
240,000〜330,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要 iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のネイティブアプリケーション…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
■具体的な業務 ・HTML/CSSを利用した画面の作成 ・Angularを利用した機能開発 ・…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】クラ…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / Java/Go / 週3日…
■案件概要 ネクストビートは、複数のプロダクトを並行展開しています。 プラットフォーム化にあたり…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●業務詳細 ・2週間スプリ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】クラ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】クラウド…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 ・社内向けツールの改修、…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●業務詳細 ・2週間スプリント… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜420,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・◆… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】基幹シス…
基幹システムの構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。依頼予定の業務としては上記の通り基…
週3日
340,000〜420,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / UX / 週3日】金…
弊社では、日本の金融リテラシー向上のためにユーザー体験を最適化し、メディアを進化させ続けることに注力…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
【インフラエンジニア】業務支援パッケージ開…
弊社クライアントの開発案件にご参画いただきます。 業務支援パッケージ開発となります。
週3日・4日・5日
410,000〜510,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸北新地駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java・C#・VBA・SQL | |
定番
外国為替取引事業や仮想通貨交換業におけるD…
【業務概要】 仮想通貨交換業における ネットワークサーバ、プラットフォームのデータベース関連業務…
週3日・4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅/浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・MySQL | |
定番
【データサイエンティスト】感情データからの…
データサイエンティスト ・フルリモート可 ※出社をお願いする可能性あり ・週4〜5日 ・単価6…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・Python・Pandas・R・Dig… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜400,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・ビジネスパートナー向けのWebフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
【業務内容】以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホストマシ…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 下記の業務をご担当いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB・C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 案件C:他社…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
下記の開発に携わっていただける方を募集します。 ・スマホからの位置情報を取得してイベント処理システ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注し…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 主な作業内容: 自社サービス…
週3日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> 社内…
週3日
360,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> 1.…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・jQue… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ECサ…
【会社概要】 Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回、クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバ…
週3日
290,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜490,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
◆仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・1… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
【案件詳細】 弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 また、フロントエンドをNuxt…
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】医…
【案件内容】 医療機関・患者双方に支持されるプロダクトをつくることにコミットする、エンジニアリング…
週4日・5日
500,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜470,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜340,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 企…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】某…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 弊社クライアントのスマホ向けのリプレイス…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart | |
定番
ECカートプロダクト刷新プロジェクトにおけ…
【業務内容】 現在運営中のECカートプロダクトを刷新するプロジェクトを進めています。 その新規メ…
週5日
500,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンド |
| JavaScript・Typescript・SQL・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っているADNWの広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるi…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ク…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】小…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築案件です…
週3日
280,000〜460,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、 顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2・SAStrutsベースの顧… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週3…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 大手…
週3日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
今回は某医療機器メーカーや某アカデミア機関と共同で開発を進めているプロジェ クトに携わっていただきま…
週3日
340,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
新リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探していま…
週3日
390,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【会社概要】 弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化…
週3日
220,000〜240,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】MEO…
自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 現在新規プロダクト…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【SQL / 週3日】東証一部上場企業の工…
弊社は、永い伝統に培われた優れた技術と最新鋭の製造設備を、万全の品質管理体制のもとにシステム化し、定…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 神奈川小島新田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務に従事いただける方を募集します。 …
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【C#】航空会社の基幹システムリプレイス案…
業務内容 ・システムのサーバー側の構築 ・C#での開発 ・定例MTG対応 ・仕様書等ドキュメ…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
UIデザイナー_デジタル同人作品販売サービ…
業務内容 ・某ITメガベンチャーにて、二次元コンテンツ同人サービスのUI設計および提案、開発、運用…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【AWS/プレイングマネージャー】プリセー…
【業務内容】 プロジェクト受注前)AWSのクラウド設計・構築のプリセールス プロジェクト受注…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルスタック】社内向けWebアプリの新規…
社内向けWebアプリの新規開発案件のフルスタックエンジニアを募集します。 メインはフロントエン…
週1日・2日・3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
クラウド移行に伴う設計/構築
・某システム開発会社にて、受託し内製で進めるクラウド移行に伴う設計/構築 を担当頂きます。 ※…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
定番
【オープンポジション】IoT機器からのデー…
・タクシーアプリの新規開発案件となります。現在リリースされているものの追加開発をメインに行なっており…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| (一例)・AzureDWH・Pipeline・Rep… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 要件定…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回はその自社新規システムに…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイン |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~海外開発拠点での開発マネジメントをご担当いただ…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript・主にPHPやJavaS… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 当社はテクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】自社グル…
〈案件内容〉 弊社はテクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 詳細: 1、自社…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務内容】 情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発に携わっていただきます。 希望…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 ・WordPressを使…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】ク…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝業務から…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
今回はスマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社はECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションをワンストップで行ってお…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 ▼主な業務 ・サーバ…
週3日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
具体的な業務内容はプロダクトの新機能や改善施策の企画・設計・テスト・実装などで、メイン業務は実装とな…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / SRE / 週3日】自社S…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Ob-C / 週3日…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【Webディレクター】Webサイト/ECサ…
複数のホームページ改訂案件のディレクションをご担当いただける方を募集しています。 ■稼働時間 …
週2日・3日・4日・5日
2〜2.8万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
【PM】androidアプリの、 開発管理…
■業務内容 某大手通信キャリアのショップで使用するタブレット端末に載せるandroidアプリの、…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
ネイティブアプリエンジニア_国内最大級C2…
・国内最大級スニーカー&ハイブランドの自社CtoCマーケットプレイスのネイティブアプリ開発を担当頂き…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
[ネットワーク]タブレットキッティング・配…
[案件] タブレット端末への専用アプリキッティング業務 キャリアショップで使用するアプリ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【Java】IT人材育成プログラム研修講師…
・某エンジニア研修事業をしている会社で、研修プラットフォームを用いての 新人エンジニアへの研修/…
週2日・3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 講師 |
| Java・C# | |
【インフラ】小売り業向けクラウド環境構築案…
クラウドアーキの検討部分から入れる人材を募集しています 設計以降の工程もご対応頂く想定です。 ※…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主に以下の業務をご担当いただきます。 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 ・クライアントメ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
◆案件内容 EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【Java】製造業の情報銀行案件
案件概要:製造業の情報銀行案件 ・顧客情報の開示範囲の管理や顧客先へ の連携をするシステム …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
弊社ソリューションは、マーケターの意思決定を支援する、データ活用のコンサルティングサービスを提供して…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
メインは受託企業で生保向けシステム開発を行っていただきます。 使用している開発言語はJava,C,…
週3日
260,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Perl・C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000円以上/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。担当業務は主にデザイン…
週3日
240,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計をご担当いただきます。 ・画面設計 ・インタ…
週3日
280,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / .Net / 週3日】人事…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務をご担…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などの…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
このポジションでは、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日】内…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインになります。 もし可能であればユーザビリティ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++・ShellScript | |
定番
【フルリモ / Git / 週3日】VRラ…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】薬…
▼業務内容 今下記の募集は、テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【Unity / 週3日】新規ソーシャルゲ…
ネイティブプラットフォーム(App Store、Google Play)でのソーシャルゲームの立ち上…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
弊社は、世界の内視鏡医療の発展に貢献する医療スタートアップ企業です。 【案件概要】 内視鏡動…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
弊社は、世界の内視鏡医療の発展に貢献する医療スタートアップ企業です。 【案件概要】 医療×A…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【UI/UX / 週3日】ゲーム事業 / …
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】国…
* 自社CMSの新規機能開発 * 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リ…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
下記の業務をお任せします。 * ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.js…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】イン…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / PL/PM / 週5日】化…
■業務内容 ・上場企業様公式ネイティブアプリの開発・運用業務 ・クライアント企画/要望を受けての…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Swift・Kotlin・Laravel・G… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・React・react・red… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】フ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 ・社内向けツールの改修、…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●具体的には ・2週間スプリン… | |
自社コンテンツに関わるマーケティング施策
自社メディアに対してのマーケティング。 ・コンテンツのリライト ・Google広告の分析 ・S…
週3日
130,000〜190,000円/月
| 場所 | 東京23区以外西調布駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOマーケター |
定番
【バックエンドエンジニア】自社サービスの設…
■具体的な業務 RDBのデータベース設計 Glue JobでPythonを利用したETL処理の設…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
データ基盤構築、パフォーマンスチューニング…
■具体的な業務 分析要件に必要なテーブル、ログの定義設計 AWS Glue Job(Spark)…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
SETエンジニア_ECシステムのテスト自動…
業務内容 ・テスト自動化戦略の策定 ・テスト自動化の実装、実行、メンテナンス ・QA技術のサポ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・裁… | |
定番
【リモート相談可 /JavaScript …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Vue.js・Nod… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・gRPC・GraphQL | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】管理…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから負債が増大…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【リモート相談可 / Perl / 週3日…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務を担っていただける方を募集します。 ・仕様調査 ・…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
■具体的な業務 ・HTML/CSSを利用した画面の作成 ・Angularを利用した機能開発 ・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・バ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / Java/Go / 週3日…
■案件概要 ネクストビートは、複数のプロダクトを並行展開しています。 これまで単独でグロースさせ…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
プロダクトは大きく3つあるのでその中におけるプロジェクトマネージャー(PM)として業務をお任せします…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】需要予…
▼案件概要 需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集…
週4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業があります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】自…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業がます。 …
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業がます。 …
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業紹介】 私たちのサービスはto C/B to B to C/to Bの3つの事業がます。 …
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 豊洲清澄白河駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】ス…
◇案件概要 下記の業務をメインにご担当いただきます。 ・バージョンアップなどのリニューアル対応 …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | 【iOS/Android】モバイルソリューション「moconavi」の ネイティブアプリケーションの保守/機能追加 |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
【業務内容】 研究領域が抱える複雑な課題に向き合い、弊社が提供するサービスで、あらゆる開発を推進し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】マル…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サービ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM/PdM / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【業務内容】 自動車のサブスクリプションサービスのオウンドメディアに関わる開発業務をご担当いただき…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> 今回は、社内向け機関システム開発を担っていただける方を募集します。 物件検索システ…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<業務内容> 今回は、社内向け機関システム開発を担っていただける方を募集します。 物件検索システ…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既存ア…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホスト…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 ▼業務詳細 - 視…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB・C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 案件C:…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発エンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容は以下になります。 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、…
週3日
290,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週3…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 大手…
週3日
2〜4.6万円/日
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】金融…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、 顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / pm / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための 0~1フェーズの開発にコミットいただきます。 現時点でワイヤーフレーム…
週3日
340,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
新リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探していま…
週3日
390,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 新規開発中のストレスチェックサービス開発において、AngularにおけるWEBコーデ…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】MEO支…
自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベースは自社開発のプラ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】ECサイ…
【案件概要】 shopifyを使ったECサイトの構築で、会員管理システムの開発業務をご担当いただき…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【Webディレクター|フルリモ】Web制作…
弊社ではオンラインスクールサービスの運営を行っており、スクール内のサービスで利用者に実案件を提供する…
週5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 営業・Webプロデューサー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【テクニカルサポート/ヘルプデスク|一部リ…
【案件概要】 社員向けのテクニカルサポート窓口としてリモートワークメインでメール・電話・WebMe…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート/ヘルプデスク |
定番
【AWS】CMSを用いたWEBシステム開発…
《 業務の概要 》 クラウドを使用したインフラの環境構築を中心に既存システムパフォーマンス改善、 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿霞が関 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
社内におけるマーケティング担当
【業務内容】 1.アクセス解析 2.リスティング広告運用 3.SEO 4.1~3を用いた集客…
週5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
【Java】自動車保険刷新案件
【案件詳細】 面談時に詳細はお話しさせていたします 【開発環境】 Azure、Java、ロ…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【C言語】金融系/オンプレ環境アプリ基盤の…
金融系システムの基盤部分(OS、ミドル、アプリ基盤)の構築。 弊社から4名で参画中の案件ですが、来…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | オンプレエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【PM/PMO】ネット証券会社システム部に…
■案件概要 証券会社における各種サービスの開発支援 既存サービスのエンハンス、新サービス開発、法…
週5日
550,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】地域金融機関向けアプリ開発のPM
■案件概要 地銀向けアプリの開発PM。 顧客のシステム部長直下にて、地銀向けアプリ開発のPM…
週4日・5日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】インターネットバンキングアプリ開発…
■案件概要 新勘定系システム構築プロジェクトにおけるインターネットバンキングサービスと認証サービス…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【インフラエンジニア】メガバンクのSwif…
【案件概要】 メガバンクのSwift連携Hub開発におけるLinux/Oracleでのインフラ環境…
週5日
660,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・Oracle | |
定番
【データサイエンティスト/データアナリスト…
■案件概要 大手小売企業が新規に展開中の衣類レンタルサブスクリプションのレコメンドシステムの開発に…
週5日
580,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト・データアナリスト |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
◆仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・1… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
【案件詳細】 弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 また、フロントエンドをNuxt…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、 顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●業務詳細 ・2週間スプリ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜440,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週3日
340,000〜640,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【PM】大手通信会社における新規事業検討支…
■案件概要 大手通信会社の順プロパーとして、顧客グループ会社と協業し新規事業の企画構想・実現までを…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM】大手通信会社における新規事業検討支…
■案件概要 大手通信会社の顧客グループ会社と協業し新規事業の企画構想・実現までを支援。 特に、AI…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・ビジネスパートナー向けのWebフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ECサ…
【会社概要】 Webサイトの制作や業務システム、スマートフォンアプリの設計からデザイン、インフラ設…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【案件概要】 クライアントである一部上場企業様の整備板金業向けのポータルサイトの開発に携わっていた…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、 顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStrutsベースの… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 大手…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】 自…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回はその自社新規システムに…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML、CSS、JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~開発拠点での開発マネジメントをご担当いただきま…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 ・当社グループサイトのWordpressを使った開発案件に携わっていただけるエンジ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜720,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容: 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【VB.NET】通信教育の申込データを処理…
〇役割 VB6⇒VB.NETへのマイグレーションにおいて、先行してプロジェクトに携わっているメンバ…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| C#・VB.NET・VB6 | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 企…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】AIを…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】某…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントのスマホ向けのリプレイ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
Webアプリケーション開発にご協力いただけるフロントエンドエンジニアの方を募集しております。 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社はスマートフットウェアを中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社はスマートフットウェアを中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っているADNWの広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるi…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っているADNWの広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるi…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております。 クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【案件内容】 今回ご参画いただきたいのは自社内で使用する設備点検システムの開発です。 複数のパッ…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川小島新田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務です。 1機能単位で設計からテスト…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
今回はVRプラットフォーム上でのアバターを中心に3DCG(キャラクター)デザインをご担当いただきます…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 ■…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発に携わっていただ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託開…
この度、受託開発案件の増加に伴いお客様との折衝も行っていただけるエンジニア様を募集いたします。 …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・・WordPressを使った… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】ク…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【C#・AWS・Azure・COBOL】日…
【業務内容】 エンジニアやデベロッパーとして、得意な領域をおまかせしたいと思っております。 開発…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・COBOL・AWS・Azure・NETCore… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【flutterエンジニア】エネルギーメー…
■案件概要 ・全国数千店舗で利用されるQRコード決済のモバイルアプリケーション開発プロジェクトでf…
週4日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| flutter | |
定番
【アプリエンジニア】エネルギーメーカー
■案件概要 ・全国数千店舗で利用されるQRコード決済のモバイルアプリケーション開発プロジェクトでf…
週4日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Go・flutter・AWS | |
定番
【Webアプリケーションエンジニア】メディ…
■対応内容 ソフトウェアエンジニアとして弊社が展開しているメディアやECシステムの開発をバックエン…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go・AWS・MySQL・AmazonAur… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝業務から各部門における業務の生産性向上と効率化のためのシス…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
【案件概要】 今回はスマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社はECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションをワンストップで行ってお…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch・【利用技術】 ・Py… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
【業務内容】 自社の開発に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を募集いたします。 (業…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
これから訪れる様々な困難を一緒に解決してプロダクトをともに成長させていくことが出来るメンバーを募集し…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
* 自社CMSの新規機能開発 * 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リ…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【案件概要】 医療×AIにおける動画データを利活用するため、不要なシーンをカットしたり加工し動画の…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【案件概要】 内視鏡動画データを管理するための、オンプレミスサーバーのサービス構築及び、その上で動…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【Unity / 週3日】新規ソーシャルゲ…
ネイティブプラットフォーム(App Store、Google Play)でのソーシャルゲームの立ち上…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜350,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
【案件概要】 プラットフォーム上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などのプ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
このポジションでは、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【Unity / 週3日】VRプロダクトの…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインになります。 もし可能であればユーザビリティ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・ShellScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Ruby / 週3…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 複数のポジションでハイスキル人材を…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜350,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】新規VR…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
【募集背景】 すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいて…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
【業務内容】 WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサ…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue / 週3日】…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集しています。 …
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンアップ ・要件定義支援 …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Go・Typescript・Git・UNIX… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【業務内容】 総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当い…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 タクシー事業者…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 顧客情報システム部門のインフラをご担当いただきます。 具体的な作業内容は以下参照。…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| 【OS・その他】 ・Windwosサーバ構築 ・… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 2021年下半期に発表した自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
2Dペイントによる設定画(デザイン画)なら…
・新規プロジェクトでの2Dペイントによる設定画(デザイン画)ならびに細部資料制作 ・3Dモデルのキ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイン |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】フー…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Azure・Web・Applicatio… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレットデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただき…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
・プロダクトの課題を発見し、開発チームと協力して解決を図る ・事業戦略に基づくプロダクト機能開発、…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサインいただき業務に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
定番
2Dデザイナー
・某スマホゲーム会社が制作しているタイトルにて、ゲーム開発におけるイラスト制作を 担当頂きます。…
週5日
360,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【フルスタックエンジニア】クラウド型モバイ…
各種プロダクト/サービスの開発部門にアサイン後、 サービスそれぞれの機能/問題点をキャッチアップし…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・Typescript | |
定番
【iOS/Androidエンジニア】業界T…
iOS/iPadOS・Androidプロダクトの開発エンジニアとして、 提供中プロダクトの機能追加…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・Ob-C・Kotlin・Typ… | |
定番
【PHPエンジニア】クラウド型モバイルPO…
◆具体的な仕事内容 ・新規開発/機能改善/追加における開発の全工程(機能提案、設計/実装、リリース…
週4日・5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter | |
定番
プランナー(データメイン)
・未発表新規プロジェクトでの各種ゲームコンテンツのマスターデータ作成 ・プレイヤーが遊ぶステージデ…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | プランナー(データメイン) |
定番
【フロントエンドエンジニア】WordPre…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】ITス…
●業務内容 フルリモートでプログラミングスクール受講者のサポート業務をお願いいたします。 主…
週3日
140,000〜220,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】GCP…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML T…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】新規ス…
【案件概要】 新規スポーツマーケットプレイスの開発をリードいただくPMの方を募集しています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 ・クライアントメディア開発 ・クライアント…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【ASP.NET/中長期】Webシステムの…
情報システムを担っている会社にて、機能追加や新規改修が多く、「ASP.NET」「Webシステム開発」…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外中神駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇作業概要 ・Go言語によるWebアプリケーション開発、API開発、バッチアプリケーションの開発 …
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python/SQL…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000〜360,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
不動産情報B2Cサイトの改修案件の設計者を募集します。 ・定期リリースしていく改修案件の要件整理、…
週3日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 /HTML/CSS / …
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。担当業務は主にデザイン…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設…
週3日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / .Net / 週3日】人事…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
フロント周りを開発支援いただけるエンジニアを募集しております。 【業務詳細】 - 新規プロジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
【企業情報】 ゲームづくりで培ったノウハウを生かし、急速に変化する市場や顧客のニーズを捉えた挑戦を…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸京阪中之島線中之島駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】教…
●具体的には - Webサービス、アプリのUI/UXデザイン - プロトタイプ制作・画面設計 …
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 ユーザー数560万人の経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 …
週3日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
▽業務内容 弊社の開発チームにて、サーバーサイドをご担当いただきます。 ・プロダクトの新機能、…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
この度は事業拡大のためにモバイルオーダーシステムの開発を担うiOSエンジニアの方を募集いたします。 …
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】マル…
◇案件概要: マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【業務内容】 自動車のサブスクリプションサービスのオウンドメディアに関わる開発業務をご担当いただき…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPR…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただける方を募集しています。 ◇業務内…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ▽業務詳細 ・自…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】自社プロ…
【概要】 プロダクト開発を行うチームにテックリードとして従事し、バックエンド、フロントエンド、イン…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
今回は膨大なSNSマーケティングデータを扱うtoB向けSaaSプロダクトのML開発業務をご担当いただ…
週3日・4日・5日
1,210,000〜1,820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【グラフィックデザイナー】自社サービスのサ…
<主業務> ・マーケティングを中心とした、弊社ブランドガイドラインに基づくビジュアルデザイン業務。…
週3日・4日・5日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| illustrator・Photoshop | |
定番
【自動車フリマ】UIデザイナー
自社サービスのUIデザイナー様を募集しております。 ユーザーにより良い価値を提供するためサービス改…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | 【自動車フリマ】UIデザイナー |
| SQL(MySQL系)・Git・自動車好きの方大歓迎… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Kotlin/ Swift…
◇案件概要: iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のネイティブアプリケーショ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
■具体的な業務 ・HTML/CSSを利用した画面の作成 ・Angularを利用した機能開発 ・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
【業務内容】 研究領域が抱える複雑な課題に向き合い、あらゆる開発を推進していただきます。 エンジ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 主に下記の業務に携わっていただきます。 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、We…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
〈案件内容〉 ・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グ…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や、改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービスや、ログ・セキュリティ等の共通方式が必要と…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / PM / 週52500日】…
〈案件内容〉 ・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グ…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【業務内容】 以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホスト…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 主に下記の業務をご担…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログや、いただくお問い…
週3日
340,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB/C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリング 案件C:他社ECサイ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注し…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容は以下になります。 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、…
週3日
290,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・‐ | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件概要】 オーディオブックサービスを構築するための人員を募集いたします。 スマートフォンを…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 主要都市のオフィス物件情…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 主要都市のオフィス物件情…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・<… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。依頼予定の…
週3日
340,000〜640,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では、日本の金融リテラシー向上のためにユーザー体験を最適化し、メディアを進化させ続けることに注力…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・Webフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定義からデプロイまでのプロ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / QA / 週52500日】…
【業務内容】※詳細は、ご面談時にお伝えさせていただきます。 スマホ 、タブレット、ウエアラブルの金…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】技術情報…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
◇仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
【案件詳細】 100%自社サービスのWebアプリケーション開発業務になります。 最初は保守運用メ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
【業務詳細】 自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】WEB…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】広告代…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 さら…
週3日
250,000〜560,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための0〜1フェーズの開発にコミットいただきます。 現時点でワイヤーフレーム・…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
新リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探していま…
週3日
390,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
急募
【Rustに挑戦したい人歓迎!Java /…
大学や企業の研究領域において複数のサービスを展開しています。 バックエンドはRust、フロントエン…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Jav… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 新規開発中のストレスチェックサービス開発において、AngularにおけるWEBコーデ…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】MEO支…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築をご担当…
週3日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
■概要 新規で複数の機能開発を予定しており、顧客サービスのDX化、請求周りのシステム開発を予定して…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStrutsベースの… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】サ…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | [Go]バックエンドエンジニア 広告代理店向けDMP |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回はその自社新規システムに…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】受…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【C#、C、VC++、MFC】計測&解析用…
【業務内容】 ・医療機器メーカーのWindowsアプリケーション開発 ・計測&解析用のWindo…
週5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿調布駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C# | |
【PHP(Laravel)】広告配信プラッ…
アプリで配信する広告を入稿する管理画面の開発作業。 クライアントからの要望・要件を元に、クライアン…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PL |
| PHP | |
定番
【Javascript・TypeScrip…
お客様からの指摘等の問題点を ソース、詳細設計書等から洗い出し、対応内容を整理した上で修正・単体テス…
週5日
500,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】自社グル…
〈案件内容〉 テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目指して、…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が受託にて開発予定の薬品会社内での実験機器の自動化ソフトウェアの開発をご担当いた…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【業務内容】 ※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントの某証券会社のスマ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、お客様のデータを活用した機械学習モデルの開発、シ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
【案件内容】 SaasサービスのPM業務を行っていただきます。 ・クライアントと社内(開発サイド…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
【会社概要】 弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発のクラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正などに携わっていただ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby(Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務をご担当いただきます。 1機能単位…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 ▼主な業務 ・サーバ…
週3日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
【業務内容】 弊社の開発チームにて、サーバーサイドをご担当いただきます。 具体的な業務内容はプ…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
シナリオライター(ゲーム)
・イベント企画書 / 仕様書作成 ・業務の資料化 / マニュアル化 ・お知らせ / Push通知…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西日暮里駅 |
|---|---|
| 役割 | プランナー |
定番
【Visual Basic/SQL】SCA…
Visual Basicで組まれたプログラムを使用しているが、 上手く動作しないことがあり、開発担…
週2日・3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸北巽駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET・SQL | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、ペアプロまたはモブプロをしな…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【インフラ】法人、ITスクール向けのIT講…
・CCNA/LPIC資格取得の個別指導 ・Java等の開発に関する個別指導 ・法人向けセミナー対…
週5日
2〜2.7万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラ・開発研修講師 |
| Java | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【Unity / 週3日】ゲーム事業 / …
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
カスタマーサポート
以下内容のお問い合わせをメールにて対応していただきます。(電話対応はありません) 外注会社からのエ…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | カスタマーサポート |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
* 自社CMSの新規機能開発 * 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リ…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】ソフ…
自ら課題発見を行うなど、これから訪れる様々な困難を一緒に解決してプロダクトをともに成長させていくこと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
* ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsによる各種機能開発 * コ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
【業務内容】 フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務詳細】 今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 ・Wor…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】ク…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】 S…
事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝業務から各部門における業務の生産性向上と効率化のためのシス…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
【案件概要】 ※詳細については面談時にお話させていただきます。 今回はスマホの前で行う運動量を映…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
今後も成長するEC分野において、様々な業種業態の企業、多種多様なツールを活用したソリューションなど、…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
PM【※正社員限定※】
責任者として、自社プロダクトのグロースをミッションに 開発・制作・事業計画に沿った商品開発・広告戦…
280,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【SRE|週5|フルリモ】プロダクト品質向…
サーバーやネットワーク、データベースの設計構築、システムの自動化、パフォーマンス改善、耐障害性やセキ…
週5日
410,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Ruby・PHP・Go・TypeScript・Rub… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【案件概要】 プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などの…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【C# / 週3日】VRプロダクトの開発業…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインです。 もし可能であればユーザビリティのお手…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】VRラ…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜720,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 今…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
【仕事内容】 自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当し…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】輸入車サー…
車関連サービスの開発チームや社内プロダクト関連の、デザイン作成業務を行っていただきます。 主に…
週5日
190,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【案件内容】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的な…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇詳細 T-SQL(Transact-SQL)を利用した作業がメインとなりますが、既存資材を流用す…
週3日
230,000〜360,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【案件概要】 不動産情報B2Cサイトの改修案件になります。 ・現在サービスインしているB2Cサイ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。担当業務は主にデザイン…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設…
週3日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / .Net / 週3日…
◇会社概要 人事・労務のソリューション・アウトソーシングを提供し、経営効率化による事業成長に貢献し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務をお任…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】マル…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 ・フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BP…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 ・フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BP…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 - 自…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】新規VR…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
【募集背景】 すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいて…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue / 週3日】…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
▼業務内容 ・需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー …
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
Ruby on Railsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダク…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき業務をリーディン…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / メンター / 週3日】IT…
サポート内容として、 ①マンツーマンでのメンタリング1on1 ②質問対応 ③課題のレビューとい…
週3日
140,000〜220,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとして アサインいただき業務に携わ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【注目案件!】Azure_IaaS環境構築…
◇案件詳細 顧客情報システム部門のインフラをご担当いただきます。 NW: ・FW、ルータの…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
主に下記の業務に携わっていただきます。 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 ・クライアント…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の要望…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】Spl…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社Webアプリケーションの開発をお願…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【グラフィックデザイナー】既存プロダクト、…
■業務内容 1.既存プロダクトのUI/UXデザイン ・コーポレートサイトのアップデート ・自社…
週2日・3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィック/WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Webデザイナー】NFTスポーツエンタメ…
・某ベンチャー企業のWeb3・NFT事業部門にて提供する、 NFTスポーツエンタメ領域での推し活…
週5日
460,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【React/TypeScript】地域活…
【業務内容】 自治体の課題である地域活性化を推進するためのアプリの開発を推進しており、 そちらに…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
PHPエンジニア(社内システム開発支援員 …
ファムロードが経営している学習塾「ブレストインキュベーション」のシステム開発。 PHPを用いた生徒…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜市港南台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【業務内容】 ・Go言語を用いたバックエンド開発 ・React(TS)を用いたフロントエンド開発…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Typ… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】インフ…
【業務内容】 ・プロジェクト内にある5つ程度のチームのマネジメントを行って頂きます。 ・各チーム…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】自社E…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GCP | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社E…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社E…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理アプリケーションの開発にご協力いただけるソフトウェアエンジニアを募集…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただきます。 ・仕様調査 ・実装、テスト…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
Ruby on Railsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダク…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要 iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応モバイルソリューションの …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】
【案件概要】 当社並びに、当社関連会社で手がける、WEBサービスのプロジェクトマネージャー業務を担…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 サービスをリリースして間もな…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Rails・●具体的には ・2週間スプリン… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】ビジ…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・裁… | |
定番
【PHP / サーバーサイドエンジニア】E…
■案件概要 スタートアップ企業パッケージ開発の案件となります。 ITとしてのものづくりを楽しみた…
週3日・4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿用賀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・AWS・Vue.js | |
定番
【GCP/プレイングマネージャー】プリセー…
【業務内容】 プロジェクト受注前)GCPのクラウド設計・構築のプリセールス プロジェクト受注…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
国内最大級アプリのAndroidエンジニア
■お任せする業務内容 自社サービス(マッチングアプリ)のAndroid開発に携わってもらいます。 …
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
デジタルマーケティングベンチャーでの広告運…
■作業内容 アフィリエイト広告代理業を行う部署にて、数百万/月〜1,000万円/月規模の案件に携わ…
週3日・4日・5日
1.2〜2万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
急募
【マーケター】大手SaaS型クラウドサービ…
広告企画・アライアンス締結等、マーケターおよびアドバイザー業務 マーケター、アライアンス経験者…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎 |
|---|---|
| 役割 | マーケティングコンサルタント |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 【業務内容】 ・クラ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
【PJ概要】 本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】W…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や、改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
■案件概要 全プロダクト共通のアプリケーション基盤における業務をご担当いただきます。 これまで単…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ移行し稼働させるために、Azur…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP・TypeScript・Git・UNI… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】IOT…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
【急募】化粧品メーカー_Webデザイナー/…
【業務内容】 ・自社サイト(化粧品)の新規制作および改修 ・LP/バナー作成等 【稼働】 …
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Window… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプ…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを担っていただける方…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。フロントエンドや各…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【UI/UXデザイナー】マンガ事業デザイン
マンガ事業WEBTOONアプリの開発、WEBTOONの制作を担う事業部になります。 アニメ化、ゲー…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【グロースハッカー|リモート相談可能・週2…
弊社のいずれかのプロダクトにおけるマーケティングWEBディレクターとして以下の業務をお任せします。 …
週2日・3日
170,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | グロースハッカー |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。依頼予定の…
週3日
340,000〜640,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
Ruby on Railsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダク…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML Tabl…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・Webフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定義からデプロイまでのプロ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
※急募※競馬アプリのディレクター募集!(リ…
【案件】 競馬ゲームの開発ディレクターの募集。 欠員発生による急募案件になります。(即日希望) …
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます! ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとして アサインいただき業務に携わ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
ゲームイベントの新規プラットフォーム(イン…
【案件内容】 ・他社と協業して取り組む、国内で先駆け的な存在となるゲーム領域の新規プラットフォーム…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | プランナー |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホストマシンとの接…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
想定プロジェクトB・C 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 案件C:…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
ゲームイベントの新規プラットフォーム(イン…
【案件内容】 ・他社と協業して取り組む、国内で先駆け的な存在となるゲーム領域の新規プラットフォーム…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注し…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> 社内…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> 社内…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【SEMマーケター|フルリモート・週2日~…
【案件内容】 弊社で運営しているゲームメディアにおけるSEMマーケティング業務を担当いただきます。…
週2日・3日・4日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SEMマーケター |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】日…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
ゲームイベントの新規プラットフォーム(イン…
【案件内容】 ・他社と協業して取り組む、国内で先駆け的な存在となるゲーム領域の新規プラットフォーム…
週2日・3日
250,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 経理担当 |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
◆仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・1… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 また、フロントエンドをNuxt.jsに置き換え…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Nuxt.js / 週3日…
【会社概要】 インフルエンサー関連事業、デジタルマーケティング事業、クリエイティブプロデュース事業…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Nuxt.js | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2 SAStrutsベースの… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【React/Go】NFTマーケットプレイ…
弊社がクライアント様から開発全般を委託されたWebサービスの運用開発をご担当頂きます。 基本的な要…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・React | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 事業…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日
340,000〜720,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【C#】 POS開発対応
【業務内容】 ・POSとAWS間のインターフェースを中⼼に設計書作成、プログラムを⾏う ・Win…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
販売管理システム開発⽀援
【業務内容】 販売管理システムの周辺システム開発 ・JavaScript、SQL Server2…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【エンジニア】地方在住者限定_フロント・サ…
【企業】 導入企業1500社、発注企業60万社が利用する BtoB-ECプラットフォームを開発・…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸京都市役所前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【デザイナー】自社サービスのWebデザイン…
【企業】 BtoB-ECプラットフォームを開発・提供しています。 【業務内容】 自社サービ…
週3日・4日・5日
330,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸京都市役所前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| adobe | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
注目
【RF】開発プロジェクト・マネジャー
・テスト~本番リリースにおけるプロジェクト管理を行っていただきます。 【具体的には】 ・『d…
週4日
2〜2.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しています。 今回…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / プロダクトデザイナー / …
Fintech企業の決済アプリのプロダクトデザイン全般をお任せします。 プロダクトマネージャー、U…
週5日
550,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
| Figma・Illustrator・Photosho… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 ・機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告に対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジニアの…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【メガベンチャー担当】WEBディレクション…
各クライアントへの販促物デザインをお任せいたします。 100%直接取引のため営業に同行しての顧客へ…
週5日
1.2〜1.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| illustrataor・Photoshop | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート】…
【案件について】 ・弊社で運用しているNuxt.jsのプロジェクト(SSG)のビルド時間が長くなっ…
週5日
2万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【動画編集/映像エディター】ブランディング…
【背景】 映像制作の内製化を行っております。 今後、映像回りの案件が増加する見通しのため、動画編…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 動画編集/映像エディター |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】新…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週5…
◇案件詳細 顧客が利用するインフラ(NW/AWS/OS)の保守運用 ※具体的な作業内容は以下参照…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働している…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP・TypeScript・Git・UNI… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】IOT…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Unreal Engine…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / iOS/Swift / 週…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue / 週3日】…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
・需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー ・具体的には、…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】情報シ…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML Tabl…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
PMフルリモ / PHP / 週3日】自社…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】国内…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で今回はその自社新規システムに関…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【週4~|Ruby|リモート相談可】自社物…
【企業概要】 デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込んで産業構造を変革するこ…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・AuroraMyS… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 当社グループサイトのWordpressを使った開発案件をご担当いただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【スマホアプリ】ネイティブアプリ開発の開発…
【企業概要】 デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革す…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Javaエンジニア|フルリモート】テレビ…
【案件概要】 窓口となる営業担当やPMとコミュニケーションを取りながら、複数のクライアントに向けて…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C・C++・C#・COBOL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】自社グル…
〈案件内容〉 弊社は、テクノロジーを駆使し、これまでに無い新たな視点での価値の可視化、最大化を目…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
弊社のデータプラットフォームである自社プロダクトの開発管理に携わっていただきます。 弊社のプロ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・ECサイトの保守(機能追加等)のディレクション ・顧客対応、メンバーへの指示 ・プログラムの修…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っているADNWの広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるi…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は、自社の教育系…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務 上記に伴う作業全…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿シンガポール |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】広告代…
事業拡大に伴い開発体制を強化中で、開発チームメンバーと共にプラットフォーム開発保守をお任せします。 …
週3日
2〜4.6万円/日
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】大手保…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】金融…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
NFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探しています。 A…
週3日
390,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【会社概要】 弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】MEO支…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 現…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
大手転職サービスの基幹シス テムエンハンス…
【業務内容】 基幹システムのエンハンス開発を、アーキテクトとして 技術面で主導する。 ・各種チ…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(Posサ…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(Posサービス)のエンハンス案件 Javascri…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
某大手銀行の為替取引システムの機能拡張(C…
【業務内容】 ・UNIXサーバ上での開発となります。 ・オンライン業務(C言語による画面)、バッ…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・SQL | |
定番
健康食品通販事業における業務企画検討および…
【業務内容】 大手健康食品通販事業の業務変更案件や新商品追加案件に対する、 業務企画検討・調整~…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(給与支払…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(給与支払いサービス)のエンハンス案件 Java (…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(給与支払…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(給与支払いサービス)のエンハンス案件 Javasc…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js / …
フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発に携わっていただ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【業務詳細】 今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 (自社サービ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】クラウド…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、事業収益を最大化するためにベンダーとの折衝業務から…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
スマホの前で行う運動量を映像からの骨格認識により解析し内容をもとにポイント加算、そのポイントを通過と…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社はECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションをワンストップで行ってお…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【モバイルアプリエンジニア】日本最大級のコ…
【事業内容】 コーワーキングマッチングサービスに関わるアプリ開発案件 【業務内容】 ・自社…
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・・An… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社メデ…
【業務概要】 BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発を担当いただきます。 様…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【会社概要】 当社は、iPadを活用したSaaS型POSシステムの開発・提供を行っております。 …
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】急成…
【業務詳細】 経済メディアのサーバーサイド開発を担っていただきます。 ▼主な業務 ・サーバ…
週3日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務概要】 新プロダクトの機械学習エンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 現…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript・【具体的な業務一… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Jav…
開発するマイクロサービスをターゲットとした少人数(3〜5人)のチームで、 ペアプロまたはモブプロを…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Sca… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
【業務詳細】 ・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SRE |
| Python・Java・Go | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
具体的な業務内容はプロダクトの新機能や改善施策の企画・設計・テスト・実装などで、メイン業務は実装とな…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Re…
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 チームメンバーはバックエン…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用…
週3日
140,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させるマネジメント業務…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【社内システム運用の支援】 社内業務を理解して業務内容の資料化及び業務改善(業務効率化)の提案・実…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川北山田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【業務内容】 弊社コミュニティサイトサービスにおける開発を担当いただきます。 ウェブサービスの改…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
顧客情報システム部門のインフラをご担当いただきます。 具体的な作業内容は以下参照。 NW …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働して…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 主に下記の業務をご担当いただきます。 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 ブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識し…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript・社内のコミュニケーション… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / Unreal Engine…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【SNSマーケ】美容医療プラットフォームの…
【業務内容】 ・認知/利用拡大と新規ユーザー獲得に向けた戦略/戦術立案、実行 ・KPI設定・予実…
週3日・4日・5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
定番
【Kotlin】Leanbackライブラリ…
Leanbackライブラリを使ったAmazon FireTVアプリ開発になります。 Android…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
製造系ERPシステム導入に伴う、共通サブシ…
【案件詳細】 製造業向けERPの生産管理モジュールと連携するフロント機能の開発プロジェクト。 …
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 神奈川溝の口 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・.NETFramework4.8 | |
クラウド共通基盤グループ支援(AWS基盤運…
EKSを利用したシステムの運用・保守業務 現在稼働しているEKSを利用したシステムの運用・保守作業…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
クラウド共通基盤グループ支援(AWS基盤運…
EKSに関わるCI/CD環境の運用・保守業務 EKSに関わるCI/CD環境の運用作業の一部を担って…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
急募
【Typescript】動画配信サービスに…
既存のサービスをもっと著名な配信者が自分のページ、ファンコミュニティを作れるようにし、 それぞれの…
週2日・3日
190,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | SETエンジニア |
| Typescript | |
定番
学校教育を変えるサービスのアーキテクトを募…
■主な業務内容 - 学校運営PaaSの要件定義・設計 - アーキテクチャ設計 - 要求分析・業…
週4日・5日
1,010,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園 |
|---|---|
| 役割 | アーキテクト |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設…
週3日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
【募集背景】 自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスの開発業務のフ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Laravel/Unity / 週3日】…
ネイティブプラットフォームでのソーシャルゲームの立ち上げに携わっていただきます。 開発・企画・…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
▼PJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイアウト制作 ・UI…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイン…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
* 自社CMSの新規機能開発 * 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リ…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】ソフ…
プロダクトやチームが一気にスケールするタイミングにおいて、自ら課題発見を行うなど、プロダクトをともに…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
* ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsによる各種機能開発 * コ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
顧客と社内開発部門等、関係者を取りまとめながら、DXや技術承継等のプロジェクトをマネジメントしていた…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【業務内容】 ・ソフトウエア開発を中心としたプロジ… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】サイトの…
【企業の特徴】 ①日本を代表する大企業のプロジェクトに携われます。 ②IT業界で必須となる先進的…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
◇案件 小売系システム(新MDシステムのIF開発対応) ◇詳細 T-SQL(Transac…
週3日
230,000〜360,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Javasc…
不動産情報B2Cサイトの改修案件になります。 ・現在サービスインしているB2Cサイトに対して定期リ…
週3日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルする案件になります。担当業務は主にデザイン…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Visual… | |
定番
プロジェクト管理基準の策定と展開
【業務内容】 公共関連のクラウドリフト系プロジェクトに対して、 リスク管理及びリスク対策の策定、…
週4日・5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(給与支払…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(給与支払いサービス)のエンハンス案件 稼働システム…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・SQL | |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(給与支払…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(給与支払いサービス)のエンタープライズ版開発案件 …
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
某大手銀行の為替取引シス テムの機能拡張(…
【業務内容】 ・UNIXサーバ上での開発となります。 ・オンライン業務(C言語による画面)、バッ…
週4日・5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C・C++・SQL | |
定番
【Java】大手転職サービスの基幹システム…
【業務内容】 WEBアプリケーション(Java)の開発エンジニアとして、 要件定義~システムテス…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Java | |
定番
【Java】大手飲食店予約サービスのバック…
【業務内容】 ・大手飲食店予約サービスのバックエンドのエンハンス案件 ・月1回のリリースサイクル…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SQL・JUnit | |
定番
大手店舗業務支援Web サービス(認証サー…
【業務内容】 大手店舗業務支援Webサービス(認証サービス)のエンハンス案件 Java(Spri…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八重洲 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
サービス業オープン系Webシステム/保守開…
【業務内容】 現行Webサービスシステム(共通ID・ポイント基盤システム:Javaスクラッチ開発に…
週5日
450,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八重洲 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】新ソリ…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】Spl…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サービスの企画・開発…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サーバーサイド開発を…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社Webアプリケーションの開発をお願…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
具体的な業務としては、暗号資産を売買するシステムの開発がメインとなるため、ブロックチェーン開発ではな…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき、業務をリーディ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件。 Auto ML Tab…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
開発メンバーのマネジメントや効率的な開発体制作りをお願いできる方を募集します。 ・基盤となるAPI…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発などのプロジェクトにお…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集します…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・TensorFlow | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
このポジションでは、社会課題解決に繋がるプロダクトを立上げ、グロースさせ、世の中に実装するまでのすべ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js/Py…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日】イ…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインになります。もし可能であればユーザビリティのお…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】 VR…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
急募
【salesforceエンジニア】Apex…
・Apexを使った設計、開発、運用 ・企画レイヤーにも携わることができます ・API開発やWEB…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | salesforceエンジニア |
| Apex | |
定番
【PM】新規事業開発部で立ち上げている越境…
【お任せしたいこと】 新規事業開発部で立ち上げている越境EC事業のプロジェクトマネージャー(業務委…
週5日
840,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ …
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務に携わっていただける方を募集します。 ・仕様調査 …
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
顧客が利用するインフラ(NW/AWS/OS)の保守運用 具体的な作業内容は以下参照。 NW …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【常駐】ウェブ広告の運用プランナー募集(週…
【業務内容】 企業から受託の各種クリエイティブや広告運用案件を扱う企業様にて、 Google広告…
週4日・5日
160,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田 |
|---|---|
| 役割 | SEMマーケター |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンアップ ・要件定義支援 …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】国…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 単に開発を行う…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
【Python】データ分析業務案件
■案件名 データ分析業務 ■作業内容 ・SQLを用いたデータ抽出、集計、分析業務 ・共通…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・SQL・snowflake | |
定番
【 Ruby / 週5日】フルスタックトエ…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、 産業構造を変革することを目指し、…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue・React・Angul… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認がメインの業務です。 テスト仕様書(項目)をもとに、WE…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
・需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー ・具体的には、…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 2021年下半期に発表した自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき、業務をリーディ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築業務です。 ・WAF等を用いた脆弱性…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要 iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のネイティブアプリケーション…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】バック…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】マル…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
弊社サービスについてはリリースして間もないため、社内向けツールも機能は最小限となっており、今後、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Rails・●業務詳細情報 ・2週間スプリ… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務概要】 リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます…
週3日
490,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】急成…
【業務内容概要】 ・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・裁… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は自社プロダクトの…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 【業務内容】 ・クラ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 主要都市のオフィス物件情…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 主要都市のオフィス物件情…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
TypeScriptエンジニア
薬局と患者の関係性を管理し、双方のエンゲージメントを向上するプロダクトの機能開発を担っていただきます…
週3日・4日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript | |
定番
【データサイエンティスト/データアナリスト…
■案件概要 ・車両企画担当部署における電気自動車の車両全体性能に関する分析依頼。 ・電気自動車の…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト・データアナリスト |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 主に顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンアップをご担当いただきます…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP・TypeScript・Git・UNI… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【PHP / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / WordPress …
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
■具体的な業務 ・HTML/CSSを利用した画面の作成 ・Angularを利用した機能開発 ・…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】W…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
【会社概要】 HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
共同開発している無料で簡単に遊べるNFTゲーム、サービス全体の開発をリードいただけるテックリード(フ…
週5日
750,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
【依頼予定の業務】 ・移行設計 既存システムと新規システムの移行の設計をご担当いただきます。 …
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【データアナリスト】退学等リスクの要因分析…
■案件概要 ・データサイエンティストの指揮のもと大学に在籍する学生データから、退学等各種リスクの要…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■PJT概要 ・経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 フロントオフィス~バック…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
ゲーム業界の発展とゲーマーの地位向上を牽引する会社です。 共同開発している無料で簡単に遊べるNFT…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
■案件概要 プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービスや、ログ・セキュリティ等の共…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
弊社は「人口減少社会」に対してテクノロジーを通じた価値貢献を実現するためにWEBサービスを展開してお…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<企業情報> 再生可能エネルギーや電力消費を最適化するためのソリューションとして、蓄電池等を最適制…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【業務内容】以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホストマシ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【データサイエンティスト】退学等リスクの要…
■案件概要 ・大学に在籍する学生データから、退学等各種リスクの要因を分析していただきます。 ・…
週3日
350,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【Webディレクター|フルリモート】自社運…
【案件概要】 弊社が運営するWEBメディアの企画制作・運用をメインにWEB関連業務全般に関わってい…
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅/新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター(デザイン含む) |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
BtoC向けのストアアプリ開発(iOS o…
システム開発、アプリ開発、クラウド設計構築、システムエンジニアリングサービスなど、関西を中心に行なっ…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
【業務内容】 ・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合…
週3日
340,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sp…
想定プロジェクトB・C プロジェクトB:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 プロ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
以下の業務をご担当いただきます。 ・スマホからの位置情報を取得し、イベント処理システムを経由してデ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 ■主な作業内容 自社サービス…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバー ・顧客側プロ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバー ・顧客側プロ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバー ・顧客側プロ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。フロントエンドや各…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
◆概要 提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サ…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとして アサインいただき業務に携わ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【業務内容】 この度は、弊社コミュニティサイトサービスにおける開発を担当いただきます。 ウェブサ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 顧客が利用するインフラの保守運用をご担当いただきます。 NW ・FW、ルータの…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働している…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
Webディレクター
■業務概要:WEBディレクター 案件の増加に伴い、WEB制作チームを強化すべく、人員の募集を行いま…
週5日
280,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルリモ / PSQ / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては 大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
顧客が利用するインフラ(NW/AWS/OS)の保守運用 具体的な作業内容は以下参照。 【NW】 …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働している…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回はその自社新規システムに…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 当社が運営する新規サービスに関するUI/UX設計をおまかせします。 表面上のUIを…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】受…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
〈案件内容〉 ・当社グループサイトのWordpressを使った開発案件です。 ※ポジション…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
大手からベンチャー企業まで様々なお客様に導入いただき急成長を遂げています。 今回は、自社プロダ…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Python/React …
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・ビジネスパートナー向けのWebフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】バ…
【案件概要】 バーチャルカラオケ配信プラットフォームのRubyエンジニアをご担当いただきます。 …
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不問駅(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週3…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 地方…
週3日
250,000〜560,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】金融…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
新サービス立ち上げのための 0~1フェーズの開発にコミットいただきます。 現時点でワイヤーフレーム…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
NFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探しています。 A…
週3日
390,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【業務内容】 新規開発中のストレスチェックサービス開発において、AngularにおけるWEBコーデ…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】新規プロ…
【案件概要】 ベースは自社開発のストアマーケティングプラットフォームです。 現在新規プロダク…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社は、ブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザイン…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき、業務をリーディ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML Tabl…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】新規We…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java/Kotlin /…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】技術…
AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および特許情報を活用…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 最初は保守運用メインとなりますが、いずれ開発に携わ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週3日】アー…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週3日
340,000〜640,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向けた進化を通して、日本の金融リテラシー向上のためにユーザ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PM】ツールの選定や導入支援、課題や要求…
要求整理とベンダー・ツール選定 ・システム的な改善要望に対しての要求・要件定義 ・要求に対して新…
週2日・3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【新規事業】バックエンドエンジニア
新プロダクトのバックエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 ご入社頂くタイ…
週3日・4日・5日
670,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・-- | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rails… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務概要」 セルフオーダー・セルフレジのプラットフォーム型サービスの開発業務をご担当いただきます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・codeigniter | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
■業務内容: 仮想通貨の取引システム開発でネイティブアプリの機能追加をご担当いただきます。 …
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Alamofire・RedHat・Ce… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】小…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築 ※P…
週3日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【案件概要】 クライアントである一部上場企業様の整備板金業向けのポータルサイトの開発に携わっていた…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra・裁… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 今回は、自社プロダクト…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【企業概要】 弊社は日本全国に向けてモーターパーツの販売事業を中心に展開しています。 現時点でW…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸近鉄日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき、業務をリーディ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週5日】大…
案件の内容 ・C++11を用いたソーシャルゲームのクライアントサイド開発 ・開発補助ツールの開発…
週5日
390,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】大…
当社はオンラインゲームの企画・プロデュース・開発・運営を行う会社です。 今回は、Unity を利用…
週5日
390,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして使用すればするほど人工知…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 こ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件概要】 物流業様向けにAIアルゴリズムの開発を行っております。 今回は本プロジェクトにご参…
週3日
340,000〜720,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【Laravel/Unity / 週3日】…
ネイティブプラットフォームでのソーシャルゲームの立ち上げに携わっていただきます。 開発・企画・…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・Laravel・Unity | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask・【利用技術】 ・Pyth… | |
定番
【Python / 週3日】医療×AIにお…
【企業概要】 弊社は日本内視鏡専門医の英知を集めたAI(人工知能)を開発し、世界の内視鏡医療の発展…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonデータエンジニア |
| Python・Typescript・FFMpeg・O… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼トライブナインPJTにおける下記業務をご担当いただきます。 ・画面遷移図制作 ・UIレイア…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、業務可視化のために、ユーザーがデータを入力するイ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】国…
* 自社CMSの新規機能開発 * 金融・人材領域での新規自社サービスの立ち上げ・開発 開発リ…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
これから訪れる様々な困難を一緒に解決してプロダクトをともに成長させていくことが出来るメンバーを募集し…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
* ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Vue.jsによる各種機能開発 * コ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【案件概要】 内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PHPReact/ 週3日…
【業務内容】 ※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントの某証券会社のスマ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社はウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営しております。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿ー |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【業務内容】 お客様のデータを活用した機械学習モデルの開発、システム導入やデータを活用した最適化シ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンア…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 - 自…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認を行っていただきます。 テスト仕様書(項目)をもとに、W…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】アセスメ…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsを扱いバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・共…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認の案件です。 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービ…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】アセス…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【Java】開発エンジニア
【仕事内容】 主に当社が運営するWebサービスの開発、運用をお願いします。 99%を内製化してい…
週5日
240,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
【Typescript】後払い決済サービス…
【案件内容】 テックリードとしてチームの方針を決め進行していただきます。 要件定義、業務仕様を元…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【新規事業】UI/UXデザイナー
チームメンバーとともにユーザインタービューの設計、参加 インタビューや利用実態で得た知見をもとに最…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
デザイナー兼コーダー_D2Cコスメブランド
・HTML, CSSでのコーディング ・自社商品のWEBページのデザイン、制作/更新 ・WEBプ…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | デザイナー兼コーダー |
| HTML・CSS・HTML・CSS・Photosho… | |
【React/Typescript】自社サ…
【業務内容】 ・React/Next.jsを使ったWebアプリ実装 └機能要件は弊社エンジニアで…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインいただき、業務をリーディ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
【YouTubeサムネイル作成】グラフィッ…
【企業】 動画メインで企業のYouTubeチャンネルの運営やSNSを活用した プロモーションの代…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造・プラント・建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】SP…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただきます。 ・仕様調査 ・実装、テスト…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日】基幹シ…
■PJT概要 経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件 ・フロントオフィス~バックオ…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◇案件概要: iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションの…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】マー…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】バッ…
【業務内容】 研究領域が抱える複雑な課題に向き合い、弊社が提供するサービスで、あらゆる開発を推進し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内No…
【本求人について】 国内初の次世代型テレビCM出稿サービス及び国内No.1のCM効果分析ツールのP…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務内容】 ・自社メディア開発 ・自…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Splunk / 週3日】…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
CM・映画・ゲーム・PV等の映像制作を行う企業の3Dエンジニア業務に携わっていただきます。 今…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・C・C++・Unity・Unrea… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
■PJ概要 本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性の…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】W…
【業務内容】 ・アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行い…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
プラットフォーム化にあたり、決済・ポイント等の共通サービスや、ログ・セキュリティ等の共通方式が必要と…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
プロダクトは大きく3つあるのでその中におけるプロジェクトマネージャーとして業務をお任せします。 …
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】EdTe…
弊社のプロダクトマネジメントを担っていただきます。 ●業務内容 ・データ抽出・分析 ・開発…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・‐ | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
下記業務をご担当いただきます。 ・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 …
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件。 Auto ML Tab…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させるマネジメント業務…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【QAエンジニア】クラウド人材管理ツールの…
自社クラウド型人材管理ツールのテスト設計や実施など品質に関わる様々な業務をご担当いただきます。 …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript/Vu…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】新…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
顧客情報システム部門のインフラをご担当いただきます。 NW ・FW/ルータの設定変更 ・障…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働して…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
◇案件詳細 ・顧客標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンアップ ・要件定義支援 …
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】各種タク…
◆仕事内容 タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 …
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】短…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
・需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー ・具体的には、…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社サ…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】を活用…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML Tabl…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】大…
・新規または既存Webサイトのデザイン ・アプリケーションのUI/UX設計 ・Webサイトの企画…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD・Figma | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】T…
【仕事内容】 ・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン …
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
●仕事内容 当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンド…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・●具体的には ・2週間スプ… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
▼業務内容 主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニ…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サービスの魅…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
【業務内容】 医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】GCPリ…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
<業務内容> 現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
【業務内容】以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホスト…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・- | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合わせから見えてく…
週3日
340,000〜830,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】大手…
想定プロジェクト 案件B:他社ECサイト製品ページのクローリングを行います。 案件C:他社ECサ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
業務内容 ・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】暗…
◆主な作業内容 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 …
週3日
290,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Oracle・MySQL・Jenkins・JI… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインチームでマークアップエンジニアを1名募集しております。 主な作業内容 自社サービス、…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】新規We…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・最… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
仕事内容 技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件内容】 今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバー…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのリードエンジニアをご担当頂きます。 設…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】新規…
仕事内容 AI、データ可視化技術を活用した特許検索・分析プラットフォームの開発、企画、運営および特…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・W… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Vue…
弊社既存サービスの機能拡張開発案件になります。 最初は保守運用メインとなりますが、いずれ開発に携わ…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週3日】金融…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
■業務概要 新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> ・社…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
<会社概要> 不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 <業務内容> ・社…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】料理動画メディアにおけ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 【業務内容】 …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 【内容】 ・既…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】アーキテ…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。 依頼予…
週3日
340,000〜640,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go/TypeScript…
【業務概要】 創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バッ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社は、個人の金融リテラシーやニーズに合わせた情報を届けるメディア、サービスを開発しています。 今…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP/Go / 週3日】…
◆業務内容 ・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】新…
■案件内容 本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】デ…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・React・Azure・AWS・Doc… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
◆業務内容 ・Webフロントエンド製品の開発および継続的な改善 ・要件定義からデプロイまでのプロ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
◆業務内容 ・Flutterのプロダクト開発サイクルの理解 ・Flutterを使用したiOSおよ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ■システムの詳細 ・販売管理(…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】小…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築案件です…
週3日
280,000〜700,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | 【UI/UXデザイナー】小売店向けES向上のWEBサービス案件(D685) |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】整備板…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】エ…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
■概要 新規で教育系コンテンツ管理を行うLerning Management System構築を予…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
■案件名 金融機関向け Fintech WEBアプリ構築PJ ■概要 新規で複数の機能開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週3日
340,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2・SAStrutsベースの顧… | |
定番
【フルリモ / Go/JavaScript…
【案件概要】 サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】広告代理…
さらなる事業拡大に伴い開発体制を強化中で、開発チームメンバーと共に開発保守をお任せします。完全フルリ…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
【具体的な業務】 ・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 ∟Androidアプリ…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとして アサインいただき業務に携わ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / iOS / 週5日】医療領…
【具体的な業務】 ・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 ∟iOSアプリケーショ…
週5日
1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】新…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇具体的な作業内容 NW ・FW、ルータの設定変更 ・障害時FW、ルータのログ調査 AW…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】医…
具体的な業務 ・顧客の課題の洗い出しと対応施策の検討 ・具体的な機能への落とし込みとプロトタイピ…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】某…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントの某証券会社のスマホ向…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社ウ…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、お客様のデータを活用した機械学習モデルの開発、システム導入やデー…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を目的とした、派遣スタッフとのコミュニケーショ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるバ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】アプリ基…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EKS…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】短…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【UI/UX】人材管理ツールにおけるUI/…
自社サービスのUI/UXデザインをお任せします。 “BtoBサービス”、“人事システム”と聞くと堅…
週4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】オンライ…
【職種詳細】 弊社のプロダクト群から共通で利用される認証基盤やビデオ通話関連基盤の開発プロジェクト…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
近年リリースしたNFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応していただけるエンジニアを探し…
週3日
390,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、Salesforceを活用したデジタル化をお任せします。 業…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【会社概要】 弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
【案件概要】 自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベース…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 AWS、CMSを用いた温泉サイトのフロントエンド、バックエンド開発・保守業務になりま…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
観客参加型エンターテイメントのプラットフォームアプリのサーバーアプリケーション開発に携わっていただき…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】オフショ…
製造・プラント・建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において、10名以下規…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】3…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
◇概要 AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になり…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】管理…
◇開発概要 pingfederateを用いた認証機能の開発と、設定等を行うSPAの開発に従事いただ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・-・ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
【業務内容】 表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジ…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML/CSS/JavaScriptを利用し、サ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】新…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社E…
【業務内容】 自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインです…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】受…
大手クライアントから受託した案件の要件定義、基本設計~フィリピン開発拠点での開発マネジメントをご担当…
週3日
340,000〜960,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
◆具体的な仕事内容 弊社が取り扱っている広告SDKに対する問い合わせに対応いただけるiOSエンジ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務内容】 弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行ってい…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【SQL / 週3日】東証一部上場企業の工…
【案件内容】 今回ご参画いただきたいのは自社内で使用する設備点検システムの開発です。 複数のパッ…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川小島新田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
【案件概要】 学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby(Rails… | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
リノベ不動産物件の販売や設計をしてる企業でのWordpressエンジニア業務になります。 直近…
週3日
190,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】IT企画…
【業務内容】 ・働きやすさとセキュリティの両立を担保した基盤づくりを行います。 ・ユーザーサポー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】WEBサ…
■業務内容 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者…
週3日
160,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿シンガポール |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】広告代…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 …
週3日
250,000〜560,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】新…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス・アプ…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日】需要予…
・需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー ・具体的には、…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML T…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
【案件概要】 物流業様向けにAIアルゴリズムの開発を行っております。 今回は本プロジェクトにご参…
週3日
340,000〜720,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
日本全国で実施された介護サービスと介護を受けた方々のその後の状態データを基に、見守りサービスを展開し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日】レストラングループの…
■業務内容 基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴か…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【業務概要】 弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go/Ruby / 週3日…
【業務内容】 弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
<業務内容> ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しております。 今…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】動画…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】新規機…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
Quorum(ブロックチェーン)を用いた取引システムを、AWS上に構築・運用して いく案件となりま…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
【案件概要】 大手飲食店向け公式アプリなどの保守開発をラボ体制で実施しています。 プロジェクト推…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【作業内容】 ・走り始めの複数案件が動いており、PHPでのWebサービス開発を担当いただきます。 …
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川北品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回はその自社新規システムに…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【PM】MDM(マスタデータマネジメント)…
MDM(マスタデータマネジメント)導入フェーズ(外部ベンダー主体)の開発フェーズへ成果物レビューおよ…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| SQL・InformaticaMDMSaaS(Cus… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務です。…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
【サービス概要】 地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ /C/C++ / 週3日】新規…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
【業務概要】 弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロ…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPRを含め…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】基幹…
■概要 フロントオフィス~バックオフィスが利用する現行システムの複雑化・煩雑化に伴い、BPRを含め…
週3日
340,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】薬局との…
◇業務内容 ・WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサ…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】アセスメ…
今回は、需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します…
週3日
390,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】社内管理…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日
290,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【Java / 週3日】証券会社投信システ…
◇作業範囲 投信システム(約定計算)の基本設計 ・画面設計 ・インターフェイス・バッチ設計…
週3日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java/C# / 週3日…
◇案件概要 マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案は…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C#・◇開発体制 開発は1チーム3〜6名… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
コンシューマー向けのアプリと、法人向けのプラットフォームを提供しています。 金融という高い公共性の…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・◇職務内容: -アプリの事業を攻守共に支える… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】クラウド…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】行政・自…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【お任せしたい業務】 ・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータな…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【案件概要】 不動産情報B2Cサイトの改修案件になります。 ・現在サービスインしているB2Cサイ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】クラ…
◇プロジェクト概要 法人のお客様向けのWebサービス提供しており、サービスの立ち上げから7年以上経…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Spring・Maven | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Perl / 週3日】自社…
当社が提供する決済システム&サービスの開発業務をご担当いただきます。 ・仕様調査 ・実装、テスト…
週3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 【作業内容】 ・…
週3日
170,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回は大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイン…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】新…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ …
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働して…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 【業務】 ・自社メディア開発 ・自社サ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 【…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社開…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】Spl…
◆業務要件 EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、…
週3日
440,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
【業務概要】 弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サー…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】飲食…
【業務概要】 弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サー…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】広告…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 自社Webアプリケーションの開発をお願い…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
<募集背景> 現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探して…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇作業概…
週3日
350,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
◇会社概要 暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ◇案件概…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EKS…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【プランナー|フルリモート・週3日~】クラ…
【案件内容】 クライアントの課題に対してプランナーとして市況感の調査・調査データのリサーチ・改善企…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | プランナー |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】国内最…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
【案件概要】 インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日】…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【サーバーサイド】自社プロダクト・業務シス…
お客様のDXを実現する自社プロダクト開発、業務システム開発において、自社の工場やお客様の元へ足を運ん…
週5日
160,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・SQL・Windows・Lin… | |
定番
【Go】動画配信サービスにおけるソリューシ…
案件内容: 動画配信サービスの開発をご担当いただきます。 アジャイル開発で進めています。 …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | ソリューションアーキテクト |
| Go・golang・gin・AWS・RDS・Gith… | |
急募
【Go】動画配信サービスにおけるサーバーサ…
案件内容: 動画配信サービスの開発をご担当いただきます。 アジャイル開発で進めています。 …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・golang・gin・AWS・RDS・Gith… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日】保…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日】システ…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML T…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】国内最大…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日
240,000〜570,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
▼案件概要 フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えたWebシステムの開発に…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
【業務詳細】 今回の募集ではシステム開発担当として下記業務に携わっていただきます。 ・Wor…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】ク…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
急募
【Goエンジニア】アプリケーションエンジニ…
弊社が新たに開発中の新規プロダクトの機能改修の設計・開発及び保守をお願い致します。 バックエンドは…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】Sa…
業務システムであるセールスフォースの最適化を行い、各部門における業務の生産性向上と効率化のためのシス…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity/C# /…
【案件概要】 ※詳細については面談時にお話させていただきます。 スマホの前で行う運動量を映像から…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Photon・Mono… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託案…
【案件内容】 受託システム開発の運用業務、開発部分がメインの業務です。 毎月の運用業務を複数対応…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Wordpress・Mova… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
【業務内容】 複数のメディアを運営する弊社の新規Webサービスの立ち上げに関わるプロジェクトです。…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ‐ | |
定番
【VBA / 週5日】立替精算業務における…
【案件概要】 立替精算業務をシェアードサービスセンターで、集中的に行うにあたって必要となるエンドユ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VBA | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
▶案件概要 バーチャルカラオケ配信プラットフォームのUnityエンジニアを担当いただきます。 ▶…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
【案件概要】 バーチャルカラオケ配信アプリのアバターアイテムの制作やUnityを用いた実装などを担…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
バーチャルカラオケ配信アプリでの、アバターアイテムの制作やUnityを用いた実装などを担当していただ…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのUnityエンジニアを担当いただきます。 ▶ 業務内容…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / CTO / 週5日】…
VPoE・CTOに就任いただき、開発チームの組織づくりやバーチャルカラオケ事業の開発マネジメントをお…
週5日
740,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】バーチャ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのプロダクトマネージャーを担当いただきます。 ▶ 業務内…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】バ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのRubyエンジニアを担当いただきます。 ▶ 業務内容 …
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】バ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのUnityエンジニアを担当いただきます。 ▶ 業務内容…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】大手小…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ …
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働して…
週3日
290,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日
520,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・・redux-sa… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
大手Sier社内(金融系)インフラ業務になります。 ネットワーク技術者、サーバー技術者をそれぞれ募…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby/ 週3日〜】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】社内管…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【業務内容】 弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジ…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML T…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
急募
【メンター】ITスクールの受講者サポート業…
●業務内容 ・受講生と13:00-22:30の時間内で定期メンタリング(オンライン)を実施 …
週1日・2日・3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | メンター |
| フォロー体制がありますので、メンターが初めてでもチャ… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【メンター】ITスクールの受講者サポート業…
●業務内容 ・受講生と13:00-22:30の時間内で定期メンタリング(オンライン)を実施 …
週1日・2日・3日・4日・5日
160,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | メンター |
| フォロー体制がありますので、メンターが初めてでもチャ… | |
定番
【Java教材編集者|フルリモート】自社サ…
【案件概要】 弊社ではオンラインスクールサービスの運営を行っており、スクール内のサービスで利用者に…
週3日・4日・5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Java教材編集者 |
| Java | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・red… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】社内管…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【Go未経験可能】NFTエンタメ領域でのサ…
・某ベンチャー企業のWeb3・NFT事業部門にて提供する、 NFTスポーツエンタメ領域での推し活…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Java・Go | |
定番
【UI/UXデザイナー】パーソナルヘルスケ…
【業務内容】 ・アプリのUI/UXデザイン ・トンマナの設定、スタイルガイドの作成 ・アプリリ…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件になります。 Auto M…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リードエンジニア(フルスタック)】自社の…
【業務内容】 ■自社クラウドシステムの開発エンジニア 勤怠管理・交通費精算クラウドシステムの開発…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | リードエンジニア(フルスタック) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】]国内…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】EC…
化粧品等の製造開発からEC販売から化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのための…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Java・Laravel・Dj… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】EC…
化粧品等の製造開発からEC販売から化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのための…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
・スポーツクラブ、インフルエンサー、アイドルなどのサービス内外に出す広告物/バナー画像/LPなどの制…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / QA / 週4日〜】スポー…
作成した、テスト設計書は仕様作成者や実装担当者からのレビューを受け、チーム全体で品質を意識を持ちなが…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ス…
下記の業務をご担当いただきます。 ・アーキテクチャ設計・開発・保守 ・クラウドインフラの運用サポ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・5 | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
具体的には、下記の業務内容を想定しています。 ・仕様や設計の検討 ・実装/テストコード追加/レビ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】スポー…
・各種プロダクトに関する企画・設計 ・新しい機能やビジネスモデルの企画立案と開発企画ロードマップの…
週4日・5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
建設業向けの受発注管理や工事管理、および各種工事書類作成の機能を提供するWEBシステムの開発になりま…
週5日
520,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
iOSエンジニアとして、マルチキャリア対応モバイルソリューションのネイティブアプリケーション保守/機…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】デー…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇業務内容 オンプレミスで稼働して…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【案件概要】 クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】顧客…
製造業様向けSAS製品導入後の定着化支援 Java+SASシステムのリプレース対応 ・フロン…
週5日
390,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SAS | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・K… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
【案件内容】 クライアントから請け負っているECサイト構築のフロントエンド開発を担当いただきます。…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日・4日・5日
670,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
自社開発のデジタルマーケティングSaaSのバックエンドの設計〜運用までを担っていただきます。 …
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社プ…
【募集背景】 現状はCPOとUI/UXデザイナーが兼任でPdMの役割を担っていますが、2スクラム体…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ▼担当業務の詳細・(1つの新機能開発開始から完了まで… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【コンサルティングファーム】ドローン企業の…
■業務内容 ・ドローン企業のソリューション営業 ・適宜会議での顧客折衝 ・進捗管理 長期案件…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | ドローンビジネスのソリューション営業 (戦略、立案含む) |
| コンサルティングスキル・ディレクションスキル・ | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査 …
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇業務内容 オンプレミスで稼働して…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認を行っていただき、不具合検出…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
・開発メンバーマネジメント ・効率的な開発体制作り ・Akerunの基盤となるAkerun AP…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】家賃債…
本サービスに関しては、ベータ版をリリースし、何社かのお客様へ導入を頂いております。 今後は、ベータ…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Swift・Kotlin・T… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
・導入先会社の古いExcelマクロをTableauへ置き換え ・導入先会社からの依頼にてTable…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・Excel・Tableau | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー ・顧客側プ…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・・scala… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【美容系企業LP制作】美容商材のLP制作・…
弊社が開発している業務用美容機器の 導入店舗を増やすべくtoBマーケティングに注力しております。 …
週1日・2日・3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【インフラ】会計仕分けソフト開発に向けたイ…
当社では仕分けソフトを大手税理士事務所や会計事務所などに提供しております。 サービス普及後の事…
週5日
330,000〜480,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【マーケティングアシスタント】自社マーケチ…
【業務内容】 ・デジタル広告周りのアシスタント(簡易なアカウント操作作業含む) ・競合調査 ・…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケティングアシスタント |
【急募】健保組合向け特定健診サポートシステ…
【業務内容】 運用中の特定健診サポートシステムのシステムリソース、 ミドルウェアのバージョンアッ…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Perl・AmazonLinux2・Post… | |
定番
【UI/UXデザイナー】toBのマッチング…
・概要 toBのマッチングサイト、および連結する基幹システム両方のデザイン ・スキル デザ…
週3日・4日・5日
2.4〜3.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に本気で立ち向かっていくAIスタートアップです。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ …
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇業務内容 オンプレミスで稼働して…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件内容〉 ・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBto…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
▼案件内容 対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担っていただける方を募集し…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
▼案件内容 WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEB…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4 Perfo… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
▼募集要項 需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー …
週3日・4日
520,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Web・Application・Firewall … | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML Tabl…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】車検シ…
【案件概要】 パソコンから車に機器を接続し、車検に必要なデータを車から取得するシステムの開発支援 …
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL・SQL… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
【案件概要】 チケット販売システムにおけるAPL保守をご対応いただきます。 主な作業 ・ア…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては 大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景 オンプレミスで稼働して…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件内容〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーショ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【React,TypeScript】イベン…
【業務内容】 主にマップUIでイベント情報を配信するWEBサイトの設計・構築を担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・React・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
【業務内容】 タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発をご担当いただきます。 今…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【ディレクター/フルリモ】自社HP制作にお…
■会社概要 美容皮膚科・美容外科の運営 全ての患者様が日々の暮らしを今よりも明るく、より積極的に…
週2日・3日
140,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルリモ/ Go/ 週5日】アプリケーシ…
【担当業務】 - Kubernetes上で稼働するアプリケーションの開発業務 - Go言語を用…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・Terraform Kubernetes | |
定番
【ディレクター】自社サービスにおける記事コ…
当社が運営するレシピ動画メディアにおいて、配信する記事コンテンツのチェック業務や入稿業務を担当いただ…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【Goエンジニア】ライブ配信アプリのバック…
Q&Aに特化したライブ配信アプリのAndroidアプリを鋭意開発中でございます。 上記開発のPdM…
週5日
920,000〜1,690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Go・AWSorGCP・git・GitHub … | |
定番
【iOSエンジニア】ライブ配信アプリのアプ…
Q&Aに特化したライブ配信アプリのiOSアプリを鋭意開発中でございます。 ※詳細情報は面談時にご説…
週5日
920,000〜1,690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア(Swift) |
| Swift・swift・AWSorGCP・git・G… | |
定番
【Androidエンジニア】ライブ配信アプ…
Q&Aに特化したライブ配信アプリのAndroidアプリを鋭意開発中でございます。 ※詳細情報は面談…
週5日
920,000〜1,690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Kotlinエンジニア |
| Kotlin・Kotlin・AWSorGCP・git… | |
定番
【PdM】ライブ配信アプリのアプリ開発のプ…
Q&Aに特化したライブ配信アプリのAndroidアプリを鋭意開発中でございます。 上記開発のPdM…
週5日
920,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトマネージャー |
| Kotlin・AWSorGCP・git・GitHub… | |
定番
ETL/ELT処理開発、DWH構築などのデ…
Databricks、Airflow、AWS Glueを利用したデータパイプラインの開発・運用 A…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【広告運用マーケター】自社マーケティング支…
自社サービス認知における広告運用のディレクション及び運用まで一気通貫で対応できる方を求めております。…
週2日・3日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
| ・- | |
定番
RPA技術者(クライアント取引先での委託業…
【業務内容】 RPAツールを使用し、お客様先での開発を担当いただきます ■弊社主催の研修講師をお…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
| VBA・WinActor・UiPath・BizRob… | |
新着
定番
【フルリモ / Goエンジニア / 週5日…
【案件概要】 NFT・ブロックチェーンの技術を応用したコミュニティアプリの開発・運用をお任せできる…
週5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Kotlin・Go・AWS・GCP・Docker・S… | |
【フロントエンド】サービス・システムの設計…
・プロダクトの企画から携わり、機能要求を満たすサービス・システムの設計・開発を行う ・自社や顧客が…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript | |
【サーバーサイド】コンテンツや広告の配信を…
・小売店舗内のサイネージ(STB/タブレット端末など)にコンテンツや広告の配信を行うシステムの開発 …
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・Go・Typescript | |
【サーバーサイド】サービス・システムの設計
・プロダクトの企画から携わり、機能要求を満たすサービス・システムの設計 ・開発を行う ・自社や顧客…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・Java・Go | |
iOSエンジニア
- 新規・既存アプリ内での新規機能提案、仮説検証から設計・開発・テスト・リリースの実施 - 既存ア…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iosエンジニア |
| Swift | |
【データサイエンティスト】アクセスログ、購…
- アクセスログ、購買POSデータ、在庫データ、位置情報データ等を組み合わせたデータ解析 - マー…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【Androidエンジニア】新規・既存アプ…
- 新規・既存アプリ内での新規機能提案、仮説検証から設計・開発・テスト・リリースの実施 - 既存ア…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
【データエンジニア】CDP/DMP構築・デ…
CDP/DMP構築 ・設計(使用サービスの選定、基盤内のデータの持ち方含む) ・基盤構築(開発に…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
データコンサルタント
データ戦略の課題を様々なアプローチで考え、どのようなデータが必要かから、生成、蓄積、その後の活用まで…
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データコンサルタント |
定番
【Kintone】kintoneアプリとの…
【業務内容】 画面よりバックエンドを通じてkintoneアプリと連携することによるデータの参照、作…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Kintoneエンジニア |
| Kintone | |
定番
【自社内開発】サーバーサイドエンジニア
Webアプリやカーナビ地図など、地理情報を活用したさまざまなシステム開発をお任せします。 We…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【Rubyエンジニア|ゲーム開発経験不問】…
【案件概要】 エンジニア向け就職・転職サービスやメディア事業、プログラミング学習教材制作などを展開…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rubyonrail… | |
定番
M365-Microsoft Sentin…
工程:基本設計以降 作業場所:大崎 在宅有無 :有(10日/月) 作業時間 :9:00-1…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
〈案件詳細〉 ・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーション…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
【業務内容】 タクシー社内に設置している乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
■業務内容: 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるP…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
▼案件内容 WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEB…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
◇案件詳細 Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ◇募集背景:オンプレミスで稼働してい…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【案件内容】 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【PHPエンジニア|フルリモート・週4日~…
自社クラウドシステムではkintoneで管理している各種報告書等あらゆるデータをPDFやExcel形…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter・Laravel(来年… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメン…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
■業務内容 自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
<具体的な内容> ・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
▼案件内容 WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEB…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件内容】 自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
【業務内容】 今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロ…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
[業務概要] 主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
【業務内容】 GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件になります。 Auto M…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
チームマネジメントアプリ及びスポーツ量販店様の販促物のデザイン業務をご担当いただける方を募集いたしま…
週4日・5日
390,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
要望に対する調査、設計、製造、試験、リリースを行います。 Webアプリおよびネイティブアプリ向けの…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SVN・CLI・AWS・ - | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
【案件概要】 教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思いま…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
生命保険業務基幹システムの維持管理、社員代替業務のご対応となります。 社員代替としてユーザ部門と要…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
【担当業務内容】 ・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
【案件の内容】 スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
AIカメラのデータをネットワークから切り出してて、人の姿勢等を感知するシステムを開発中! 画像を飛…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】電子契…
自社で開発をしている電子契約サービスのPdMをご担当いただきます。 仮説検証の推進およびアジャイル…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社客先が複数の顧客(通信事業者)向けにZアプリケーションを使用しております。 その環境構築業務を…
週5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Python・Linux | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
【案件概要】 ・アプリの設計・実装・検証・運用 ・他社サービスとの連携機能開発 ・プラットフォ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Go・C・C++・NodeJS・Go・ShellSc… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】E…
自社プロダクトが各種データソース(DB、広告API、CRMツール等)とのデータ連携を行うための、Em…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築をご担当いただきます。 ・WAF等を用いた脆弱性対策…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
【案件概要】 開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAker…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
・プロダクトの課題を発見し、開発チームと協力して解決を図る ・事業戦略に基づくプロダクト機能開発、…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
サーバーサイドエンジニア
案件概要 : システム開発支援 工 程 : 基本設計~ 作業場所 : 新宿御苑 ※リモートメイ…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿3丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Go言語 | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証に携わっていただきます。 ◇募集背景 オンプレミス…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 - 自…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutte・S… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認業務をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をも…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・react・redux・・re… | |
【Swift】就活会議のIOS機能開発
【開発内容(詳細)】 ・GraphQL 等を利用した API 連携と UI 開発 ・DM 配信の…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】iO…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
急募<プライム/大型案件>大手小売業でのD…
【業務内容】 大手小売企業のDX支援業務。(以下それぞれで募集中) ①業務コンサルティング ②…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させるマネジメント業務です。 …
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます ・Scalaもしくは…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
編集ディレクター
・紙編集のディレクション ・編集進行管理 ・キャッチコピー作成 ・見積もり・納品・他(制作 提…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | 編集ディレクター |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証をご担当いただきます。 オンプレミスで稼働している仮…
週3日・4日
390,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 551 :Azure/インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 【詳細】 ・…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【業務内容】 総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当い…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EK…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript・社内のコミュニケーション… | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
【案件概要】 新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal …
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ/ Angular/ 週3日〜】…
【担当業務】 ・リーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアのフロントエンド開発 ・…
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認業務をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をもとに…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー業務を担っていただけ…
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【グラフィックデザイナー】バナー、LP制作…
【業務内容】 PM、エンジニア、カスタマーサクセスと密に連携しながら、プロダクトのUI/UX改善を…
週3日・4日・5日
570,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができる、フルスタックエンジニアを募集しています。…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【Shell / 週3日〜】某流通系システ…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う (店舗定型作業、本番稼働検証(日中日…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Shell | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
※詳細は面談時に、お伝えさせて頂きます。 自社プロダクト新規構築のソフトウェアエンジニア(フロント…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| C#・Typescript | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築をご担当いただきます。 ・WAF等を用いた脆弱性対策…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【デザイナー】自社情報共有ツールに関わるデ…
【案件概要】 現状の自社サービスである情報共有ツールのサービスページのデザインブラッシュアップをお…
週3日・4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・wordpr… | |
【フロントエンジニア】0→1でデジタルコン…
現在はデジタルコンテンツを販売するECサイトの開発段階なので、一緒に開発してくれる人を探しております…
週2日・3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Nuxt3・Vue3 | |
定番
【PM/PMO】インターネットバンキングア…
■案件概要 新勘定系システム構築プロジェクトにおける地銀向けインターネットバンキングサービスと認証…
週5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM・PMO |
定番
【サーバーサイドエンジニア】インターネット…
■案件概要 新勘定系システム構築プロジェクトにおけるインターネットバンキングサービスと認証サービス…
週5日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・GraphQL | |
定番
【シニアコンサルタント】SAP導入プロジェ…
■案件概要 大手SIerにおいて、SAP導入プロジェクトのシニアコンサルタントとして参画 ※具体…
週5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | シニアコンサルタント |
定番
【データアナリスト/データサイエンティスト…
■対応内容 ・Pythonによる探索的データ分析 ・分析設計補助 ・分析設計の下での相関分析 …
週2日・3日・4日・5日
840,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト・データサイエンティスト |
定番
【Ruby on Rails】自社メディア…
●各種事業のWebサービスのビジョンを実現する新規機能開発や改善 ●技術選定や実装だけではなく、企…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【アプリエンジニア/リモートワーク可】お出…
■仕事内容 ・Flutterでのアプリ開発業務( iOS / Android ) ・アプリのリリ…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【PMO】大手通信会社におけるキャリア向け…
■案件概要 ・大手通信会社において、キャリア向けのデータ基盤システム開発をする部隊における開発PM…
週5日
550,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
【自社サービス】カスタマーサクセス
・ヘルプページの指標設計、改善、ディレクション ・チャットボットの回答精度向上 ・お客様の声の収…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎 |
|---|---|
| 役割 | カスタマーサクセス |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証業務をご担当いただきます。 オンプレミスで稼働してい…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【UI/UXデザイナー】自社サービス_有名…
当社のメインプロダクトに関わる幅広いデザインをお任せします ・ワイヤーや遷移図等のプロトタイピ…
週4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| 【グラフィック制作】 ・Adobe・のツール全般 … | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認業務をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をも…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ /C/C++ / 週3日〜】ク…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを担っていただける方…
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rub…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週4…
弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいて、リリース後の…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【リモート相談可 / Java/PHP /…
弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいて、リリース後の…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】EC…
ECサイトサービスに関するサーバーサイド開発に携わっていただけるエンジニア様を募集いたします。 …
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
新しいアーキテクチャ(jamstack、サーバーレス)の構成における設計、構築、テストをリードしてい…
週5日
740,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川戸越銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue・Reac… | |
定番
【フルリモ / API / 週5日】開発・…
クライアントが利用しているChatbot(LivePerson社のConversational Cl…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
定番
【フルリモ / UiPath / 週5日】…
UiPath Studio/Orchestratorを使用したRPAの要件定義、設計、開発、テスト、…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
スキルにより、リーダーまたはメンバーとして業務をご担当いただきます。 ①全体テスト管理、推進業務 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築をご担当いただきます。 ・WAF等を用いた脆弱性対策…
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証をお任せします。 ・オンプレミスで稼働している仮想サ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー・SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【Node.js/TypeScript等】…
弊社が運営しているモビリティサービス事業のサービス開発をご担当いただきます ■作業内容 オン…
週4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
【Typescript】自社後払い決済サー…
自社開発の後払い決済サービスのバックエンドエンジニアを募集しております。 【業務内容】 ・後…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C・C++・C#・COBOL・Typesc… | |
定番
自動車サブスクリプションサービスの開発
■作業内容 オンラインカーリースサービスに関するフロント開発をメインに行なっていただきます担当いた…
週4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| PHP・React・Lambda・DynamoDB | |
定番
【JavaScript】コーダー
【業務内容】 自社で製作しているLPのコーディングがメインのお仕事です その他、クライアントのH…
週4日・5日
160,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【広告運用マーケター】WEB広告運用担当(…
【業務内容】 主に美容関係(エステサロン、脱毛サロン、クリニックなど)のクライアントが中心です …
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・当社グループのAPI、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオ…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
【企業概要】 弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
【Flutter / フルリモ】受託開発案…
【企業】 WEBシステム、WEBアプリの受託開発を中心に取り組んでいます。 【業務内容】 …
週3日・4日・5日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿越谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
主にWEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をもとに…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 …
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
【企業概要】 弊社ブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
主にWEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をもとに…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させるマネジメント業務。 …
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
【企業情報】 弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わって…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週5日…
情報サービス会社向けのBPR推進プロジェクトの販売見積受注システムの帳票部分をご担当いただきます。 …
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| CSS・JavaScript・C#・.NET・Azu… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
AWS上に構築されたシステムのRDSバージョンアップ対応 RDSバージョンアップに関する課題対応、…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PowerShell・JP1・AWS | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】アジャ…
1) セキュリティ・監視・運用設計 2) リリースフローの運用 3) インフラの構築・保守・監視…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
1) Djangoを用いたバックエンドの設計・実装 2) Vue.jsを用いたフロントエンドの設計…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Djang・Vu… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
弊社は健康食品・サプリメントを研究開発・製造・販売をしている会社です。 大手ECモール内のショ…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸沖縄県 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Typescri… | |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週3日…
1.コンサル ユーザー要件を収集し、コンフィグ/カスタマイズ/アドオンについて米国チームへのイン…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日〜】基幹…
基本的に、PMの指示の下、作業を行って頂く形となります。 PMにて実施するPM業務のサポートやチー…
週3日
360,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションのネイティブアプリ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】マ…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】バ…
・全社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Pla… | |
定番
【Ruby / 週3日〜】不動産売却領域サ…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 弊社は、サービスをリリースし…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日〜】…
当社のtoC向けサービスと法人向けサービスの開発を担当して頂きます。 フロントエンドや各プロダクト…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Rails・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます。 ・国内…
週3日
490,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 既存のホームぺージのフロントを一新す…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】ソフ…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra | |
定番
【メンター】ITスクールの受講者サポート業…
●業務内容 ・受講生と13:00-22:30の時間内で定期メンタリング(オンライン)を実施 …
週1日・2日・3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | メンター(Webアプリ) |
| Ruby・フォロー体制がありますので、メンターが初め… | |
定番
【AWSインフラエンジニア】複数プロジェク…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フロントエンドエンジニア】新規サービスの…
【業務内容】 ・クリニック様向けの患者様の集客を支援する新規サービス立ち上げ WEB申し込み、…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【QAエンジニア】自社のクラウドファンディ…
ブロックチェーン技術を活用しているクラウドファンディングサービスやNFT事業の品質管理をお任せします…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
注目
【Railsエンジニア(Rails 6系・…
ブロックチェーン技術を活用しているクラウドファンディング2.0サービスに関わる開発業務をお任せします…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / React/Java…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
テレビCM等の広告効果を数値化できる分析ツールの開発を行っております。 プロダクトのアーキテクトと…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・gRPC・GraphQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
アルゴリズムを構築するデータサイエンティストとしての業務を依頼します。 ・クライアントのマーケ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
本プロダクトにより薬局経営のオーナーや現場薬剤師に対して、薬歴業務・収益・患者関係性の項目を可視化す…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【Androidエンジニア】薬剤師の業務支…
【具体的な業務内容】 ・グループが運用するサービスのアプリ開発と改善 ・ユーザの利用状況の分析と…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| PHP・Ruby・Swift・Kotlin・Go・V… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発(フロントメイン・バックエンド)業務…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】IC…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】大…
Go言語で開発されているプラットフォームの新規開発や、改修を各部署からの要件から設計を行い、開発を行…
週3日
290,000〜730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go・Apache・Nginx・MySQL・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社プ…
全プロダクト共通のアプリケーション基盤における以下の業務を担っていただける方を募集します。 ・共通…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社プロ…
プロダクトは大きく3つあるのでその中におけるプロジェクトマネージャー(PM)として業務をお任せします…
週3日
230,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
オーディオブックサービスを構築するための人員を募集いたします。 スマートフォンをメインターゲット…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
社内向け機関システム開発 物件検索システムを自社開発しており、システムの機能追加や性能向上のための…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
社内向け機関システム開発 物件検索システムを自社開発しており、システムの機能追加や性能向上のための…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・jQuery・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週3日
290,000〜360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
日本最大級の料理動画メディアのiOSアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営に関わる…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・Xcode | |
定番
【Go / 週3日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 ・GoでのAPI…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
お部屋探しプラットフォーム、不動産仲介業者向けSaaS、その他新規事業のWebフロントエンドエンジニ…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麹町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・・ | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート・…
【案件概要】 弊社ではデジタルコンテンツを販売するECサイトの開発を行っており、フロントエンド開発…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Nuxt3・Vue3 | |
定番
【リモート相談可 / Nuxt.js / …
・RubyonRailsで構築された社内向けWebアプリケーションJava/JavaScriptを用…
週5日
370,000〜940,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
現行のドローン制御用タブレットアプリをクロスプラットフォーム化いたします。 Androidにて実装…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【フルリモ / Next.js / 週3日…
誰でも簡単にWebサイトが作れるサービスのフロントエンド開発に携わっていただける方を募集いたします。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Next.js・React・N… | |
定番
【Go】自社マーケティング分析サービスのバ…
弊社で開発している、大手レコード会社や芸能プロダクションなどを対象とするCD売上やSNSの動向を分析…
週4日・5日
670,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Gin | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査 …
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ドローンシステム向けWebアプリの開発を実施致します。 Webアプリの作成としてHTMLの作成、J…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript | |
定番
【Python/Go】データ分析自社サービ…
SET (Software Engineer in Test)として弊社のデータ分析ウェブサービスの…
週3日・4日・5日
670,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | SETエンジニア |
| JavaScript・Python・Go・Gin・G… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EKS…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
【企業概要】 大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しておりま…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【PMO】システム開発/アプリ開発 プロジ…
役割 ・PMの指示の下、見積や提案書の作成サポート ・PMと共にスケジュール管理、品質管理 ・…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいている為、開発体制…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・redux-sag… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
スポーツに特化したビジネスを展開している当社にて デザイナーの方を募集いたします。 既存大手ナ…
週5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・- | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】情報…
今回は、弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【Java|週2出社】サイバーセキュリティ…
エンジニアが安心してプロダクトを開発できる、セキュリティ対応に割かれる膨大な工数が削減される、そんな…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【Javascript】UI画面の設計業務
製品は無線通信機器。 機器組込やサーバーへ繋ぐバックエンドは別担当が行い、今回の入替で必要とされて…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ/ React/ 週2日〜】検索…
【担当業務】 ・製薬会社の検索データベースのフロントエンド開発(モックアップの実装) 【案件…
週2日・3日・4日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Next・js・ECS・RDS… | |
定番
【Flutter】美容サロン集客サイトの開…
【業務内容】 美容サロン集客サイトの開発で0→1フェーズで依頼いたします。 【環境】 マー…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter | |
定番
【フロントエンドエンジニア|フルリモート・…
【案件概要】 自社クラウドサービスの開発に携わるエンジニアとして、設計から開発までに必要なすべての…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・AWS(EC2)・Jquery | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証を担っていただける方を募集します。 オンプレミスで稼…
週3日・4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】イン…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】Sw…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】薬局…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認業務をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をもとに…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日・4日・5日
740,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
【グラフィックデザイナー】 グラフィックデ…
【業務内容】 グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン全般 ・アパレル、インテリア、建築、飲…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィック・エディトリアルデザイナー |
| ・ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
新たに発足するプロジェクトのインフラ構築、運用を担当頂きます。 本業務の最上流工程からプロジェクト…
週3日
190,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
自然言語処理の開発を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設計と実装 2) ソース…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Java | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 介護…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・・redux-sa… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサインい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】デー…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証を担っていただける方を募集します。 オンプレミスで稼…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | Azure/インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】自社システム、…
【仕事内容】 ・自社システムの開発、顧客の要望に合わせたカスタマイズ、導入後のメンテナンス ・ア…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄博多駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・PHP・Java | |
定番
【フルリモ/ フロントエンド/ 週5日】電…
【担当業務】 ・電鉄系物流会社のBIツール開発 ・既存の出入荷管理システムからデータ連携し、最新…
週5日
190,000〜360,000円/月
| 場所 | 池袋向島駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Typescript・node.js・Re… | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモート・週4日…
【案件概要】 エンジニア向け就職・転職サービスやメディア事業、プログラミング学習教材制作などを展開…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【PM/PDM|フルリモート・週3日~】ク…
【案件概要】 弊社クライアントのプロジェクトにおいて非機能要件の定義をしていただけるPM・PDMの…
週3日・4日・5日
2.4〜4.1万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証業務をご担当いただきます。 オンプレミスで稼働している仮…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【PHP / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・新規設計開発、及び追加開発・保守 ・技術上の調査及び提案のための研究 ・顧客との要件定義、打ち…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
マリン系サーバーシステムの移植対応案件 ・ASPアプリのJAVA移植、およびJAVAシステムのフレ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外立川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】新…
新規スマートフォン向けRPGゲームのクライアントサイドエンジニアとしてゲームアプリ開発を担当していた…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PHP/SQL】バックエンドエンジニア_…
・要件・エンハンス業務 ・要件ヒアリング ・アーキテクチャの設計 ・開発業務 ・運用業務(問…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【PMO】当社自社開発プロダクトにおけるP…
当社自社開発プロダクトにおけるPMOの募集となります。 PMの元で以下の業務に対応をいただく予定で…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Go+PHP / 週4日〜…
【業務内容】 ・新規機能の開発 ・実装メイン(設計が得意な方であればお任せする場合もあります) …
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go・Laravel・ | |
定番
【Java|フルリモート】AIによる契約書…
【仕事内容】 - AI契約管理システムのバックエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java) |
| Java・SpringFramework・Spark… | |
定番
【Python/一部リモート可/週5日】デ…
内視鏡データ(動画)を管理するデータベースシステムの開発を中心に、 次世代の内視鏡AIの開発の基盤…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Go・・ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・redux・・redux-sa… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】薬局…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認業務をご担当いただきます。 テスト仕様書(項目)をも…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
・ユーザー側の機能についての新規機能の実装・既存機能の保守運用 (例)会員獲得のための自己分析ツー…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 まずは基幹システムの開発…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
弊社は、大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。 今回…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【正社員採用案件】自社プロダクトのエンジニ…
【担当業務】 - サーバーサイドエンジニア/エンジニアリングマネージャー業務全般 - 既存のプロ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【正社員採用】自社プロダクトのサーバーサイ…
【担当業務】 - プロジェクトの技術的なリード - サーバーアーキテクチャ設計 - アプリケー…
週5日
440,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川目黒 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・RubyonR… | |
定番
サーバーサイドエンジニア(シニアエンジニア…
シニアエンジニアとして既存もしくは新規のプロダクト開発のリードをしていただきます。 将来的にはエン…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川目黒 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・AWS・RubyonRails | |
定番
サーバーサイドエンジニア_シニアエンジニア…
事業は順調に急成長をしており、所属人員も約90名を超えていますが、今後の更なる成長を見越し、中核を担…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川目黒 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
弊社は、「テクノロジーと人財の力で「創造」と「成長」を実現する」を事業目的に活動をしております。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【SQL / 週3日〜】インターフェース開…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 ご依…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
某キャリア向けモバイルコア5GCアプリケーション開発 コントロールプレーンネットワークファンクショ…
週5日
460,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Wireshark | |
定番
【Java / 週3日〜】企業向けプログラ…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 講師(言語等記入) |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】WEB…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜930,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 業…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / Reac / 週3日〜】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】オン…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】情報…
今回は、弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト(リーダーレベル) |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・顧客側プロダクトオーナーや社内サービスデザイナー/UIデザイナーとの仕様調整 ・プロダクトの設計…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
データ分析を共に担えるメンバーを募集しております。 ・KPI改善のためのデータ分析 ・オペレーシ…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Lob分析サービス開発運用プロジェクトになります。 TVなどの操作Logをもとにランキングなどを出…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS・React.js・EMR・Re… | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
店舗で利用されているAndroidアプリ(お客様独自で生成されているアプリ)をiOSアプリに移行する…
週5日
700,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Git | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
【コンサル/PM|フルリモート】ERP、S…
【業務内容】 (1)業務コンサルタント(サプライチェーン、会計、人事給与) (2)テクニカル…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM・PMO・コンサル(IT) |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ネットワーク / 週3日〜…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【Python / C++】脳科学×AIプ…
▼具体的な業務内容 ・臨床的課題を解決するための画像処理技術の開発 ・共同研究に用いるプロトタイ…
週5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | 画像処理エンジニア |
| Python・Scala・C・C++ | |
定番
SAPエンジニア
SAPエンジニア 今回募集しているのは、弊社ですでに稼働しているSAPのシステムについて ・業務…
週1日・2日・3日
290,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | SAPエンジニア |
定番
【フルリモ/ React, TypeScr…
【担当業務】 ・React+Typescriptを利用したWebアプリケーションの開発 ・Web…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 プロダクトのテクニ…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件になります。 Auto ML Tables…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine・Perforc… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件をご担当頂きます。 AWS EK…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【C# / 週3日〜】OCR(光学式文字読…
自社で開発を行っておりますOMR(光学式マーク読取専用装置)やOCR(光学式文字読取装置)製品の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【サーバーサイドエンジニア / 週5日】販…
小売店向けの業務システムの保守開発プロジェクトになります。 周りと連携と取りながら要件定義からリリ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラット…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,280,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー 具体的には、 …
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 プロダクトのテクニ…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
開発機能: 商品検索、見積依頼、メッセージング 画面数:26、機能数:大分類で23 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
[Ruby]SaaS系プロダクトのRail…
【案件概要 】 弊社で自社開発している社内コミュニケーション活性化SaaSのバックエンド設計~実装…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Docker | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
大手SI企業でのシステム開発案件
【職務概要】 クライアント先に常駐し、開発・設計・構築などのエンジニア業務をお任せします。 クラ…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Python・Java・C・C++・C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
インフラ(NW/AWS/OS)の保守運用 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ル…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【C# / 週4日〜】業界No1ECサイト…
【業務概要】 ECサイト向けパッケージを用いて、クライアントのECサイトを構築頂きます 。顧客折衝…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| Java・C#・AWS・特になし | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【PHPエンジニア】データサイエンス事業
・データサイエンス事業(AI 自社サービス、受託開発) ・ARソリューション事業(AR/MR/VR…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Python】AIエンジニア
・データサイエンス事業(AI 自社サービス、受託開発) ・ARソリューション事業(AR/MR/VR…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
アプリエンジニア【iOS・Android】
自社サービスアプリの機能アップ、ARコンテンツ設定、アプリのメンテナンス 受託開発アプリの設計、実…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園 |
|---|---|
| 役割 | アプリエンジニア【iOS・Android】 |
定番
【HTML/CSS/JavaScript】…
・子育てプラットフォームの企画・開発・保守 ⇒補助金・監査・ダッシュボード等の、自治体と保育園な…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【フルリモ / PHP/ 週5日】自社開発…
【担当業務】 - 自社プロダクトの企画・開発・保守 - 既存システムのエンハンス開発 - シス…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(PHP) |
| PHP・CakePHP・Laravel・Spring… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
・子育てプラットフォームの企画・開発・保守 ⇒補助金・監査・ダッシュボード等の、自治体と保育園な…
週4日・5日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・ | |
定番
【Python】ネットショップ作成サービス…
◾️ 業務内容 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気通貫でご担当いただきます ・バッ…
週5日
580,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【ディレクター|フルリモート・週3日からO…
【案件内容】 他社と協業して立ち上げ中の新規事業に携わる仕事です。 具体的には、ゲーム領域に特化…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター(プランナー業務含む) |
定番
【TypeScript】webフロントエン…
Webフロントエンジニアは、主に社内向けのWeb管理画面を中心としたWebフロントプロダクトを担当い…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | webフロントエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EKS…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】 行政…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】顧客…
顧客に対するインフラの企画立案/導入/運用業務 AWSを利用し、弊社製品の動作環境を顧客毎に構築/…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Androidjav…
Android向けのSMTP/IMAPに完全対応したメールアプリの開発プロジェクトになります。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Git・Firebase・C… | |
定番
【SQL / 週3日〜】販売管理(生鮮)シ…
小売店向けの業務システムの保守開発プロジェクトになります。 周りと連携と取りながら要件定義からリリ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】決…
大規模決済プラットフォームのデジタル化案件です。 状況によりアサインチーム(弊社チーム、他チーム)…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Go・Springboot・TERASOL… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週3日〜】…
自然言語処理の開発を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設計と実装 2) ソース…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Java | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・加盟店向けのダッシュボード・申し込みフォーム開発 ・加盟店サポート向けツール開発 ・カスタマー…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
薬局向けECサイト倉庫管理画面開発案件
薬局をメインにtoBやtoCの自社サービスを提供している企業の開発案件となります。 今回は、薬局同…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・FuelPHP、CakePHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】自社物…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができる、フルスタックエンジニアを募集しています。…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手企業のサイトデザイン経験が豊富な方を募集してます。 大手上場企業のものであり、そのトップページ…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
受託しているWebサイト更新・開発業務を行っていただきます。 ・業務内容はCMS(MT)での更…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
携帯電話基地局の建設業務における効率化を目的とした開発 開発形態はモブプログラミング、ペアプログラ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・jQuery・R… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】決済プラ…
大規模決済プラットフォームのデジタル化案件です。 状況によりアサインチーム(弊社チーム、他チーム)…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Java・Go・Vue.js・React | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】アジャ…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したシステムの監視・運用設計および監視・構築…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
・ユーザー側の機能についての新規機能の実装・既存機能の保守運用 (例)会員獲得のための自己分析ツー…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】国…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / UI/UXデ / 週3日】…
・プロダクトのUIUX改善 ・自社サービスのWebサイトデザイン、LPデザイン ・Photosh…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【リモート相談可 / NW / 週3日】大…
大手Sier社内(金融系)インフラ業務になります。 NW技術者、サーバー技術者をそれぞれ募集いたし…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Typescri… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
スポーツに特化したビジネスを展開している当社にて デザイナーの方を募集いたします。 既存大手ナ…
週3日
190,000〜410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手消費財メーカーやサービス事業者などに対してのCRMソリューションプラットフォームのモジュール開発…
週3日
140,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
弊社が運営するSaaSプロダクトのWEBフロントエンド(SPA)の開発全般を担当していただきます。 …
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
下記の業務をご担当いただきます。 ・KPI改善のためのデータ分析 ・オペレーションチーム(シナリ…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Lob分析サービス開発運用プロジェクトになります。 TVなどの操作Logをもとにランキングなどを出…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS・React.js・EMR・Re… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】バ…
大量営業リストを使ったセールス活動を従来のExcel管理から卒業し、プレリードを一元管理するサービス…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・Rubyo… | |
定番
【リモート相談可 / swift / 週3…
店舗で利用されているAndroidアプリ(お客様独自で生成されているアプリ)をiOSアプリに移行する…
週3日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Git | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】WE…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 東京23区以外シンガポール |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】フルス…
得意領域を活かしながらバックエンド〜フロントエンド、インフラなど開発環境の整備まで全員が携わっていま…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週3日】サ…
既存サーバーの自動構築のためのAnsible化をしていただく該当サーバーは ・構築手順書がある …
週3日
1.6〜3万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・- | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
開発チームにて、自社プロダクトの開発業務に関わっていただきます。 - ユーザーの体験設計、プロ…
週3日
190,000〜750,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋新豊田 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
大小含めてWEBサイトのデザインからシステム開発まで制作しております。 今回の募集ではシステム開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
某キャリア向けモバイルコア5GCアプリケーション開発 コントロールプレーンネットワークファンクショ…
週3日
270,000〜710,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Wireshark | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
・管理コンソール開発のバックエンドを中心にした開発業務を担って頂きます。 ・バックエンド開発業務 …
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
・JavaによるWebシステム (基本ウォーターフォール開発。一部アジャイル開発あり。) 環…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
現行のホストシステムを存続しながら、新規でホストシステムを刷新していきます。 データ移行はせず、新…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】IoT…
要望に対する調査、設計、製造、試験、リリースを行います。 Webアプリおよびネイティブアプリ向けの…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SVN・CLI・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【React/JavaScript】フロン…
自社開発したブロックチェーンを活用しNFTマーケットプレイスやSaasプロダクトを開発する ベンチ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御徒町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【iOSエンジニア】資材・機材の入出庫管理…
当該顧客が扱う資材・機材の入出庫管理を行うシステムの新規開発 開発対象システムはWebアプリおよび…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【WEBデザイナー】リニューアル予定のWE…
・英語の指示書を元に制作が可能な方 ・リニューアルするWEBサイトの制作 ・新規事業のWEBペー…
週5日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
昨年度サービスインしたNFTマーケットプレイスの機能追加・改善。 案件単位でお願いするため、フロン…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・Next.js・n… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・金融商品取引業者の会員システム開発業務 ・国内株式に関する新規サービスの構築及び、既存システムの…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Eclipse・SVN | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週5日】E…
各ECサイトでの入稿作業 ∟画像の編集不要(先方で用意したものあり) ∟コードが組んであるテキス…
週5日
260,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装 ・ 3Dを併用したUI実装 ・ マルチプ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
開発機能: 商品検索、見積依頼、メッセージング 画面数:26、機能数:大分類で23 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS EKS…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます 。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【Python|フルリモート】感情AIサー…
【企業概要】 私たちの創発した感情AIは、ありとあらゆる感情交流データをスコアリングし、その変化を…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿 or 赤坂 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【PM】MicrosoftAzure業界ト…
<本案件₋業務内容> <PM・AWS・Azure> エンジニアやデベロッパーとして、得意な領…
週3日・4日・5日
580,000〜830,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【SNS運用/PR】ソーシャルメディアの運…
・FacebookやTwitter、Instagramといったソーシャルメディアの運用 ・イベント…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川関内 |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
定番
【バックエンドエンジニア】自社プロダクトに…
【具体的な業務内容】 ・自社プロダクトに関連する新プロジェクトの新規開発 ・自社プロダクトに関連…
週4日・5日
1.3〜2.1万円/日
| 場所 | 豊洲勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Typescri… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア|正社員切り替え…
【案件概要】 本案件では、幼稚園・保育園向け写真販売システムの保守運用業務及び関連する新サービスの…
週4日・5日
1.3〜1.8万円/日
| 場所 | 豊洲勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・AWS | |
定番
【フロントエンド】サービス拡充に向けた新機…
【具体的な業務内容】 ・サービス拡充に向けた新機能(商材)開発におけるフロントエンド実装 ・開発…
週5日
1.3〜1.8万円/日
| 場所 | 豊洲勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Vue.js | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML TablesとBQMLで…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
HRや介護・子育て・製造などあらゆる業界の社会課題に立ち向かっていくAIスタートアップです。 弊社…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありました…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】受託開…
弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいて、リリース後の…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
勤怠管理とシフト作成が同時に行える、クラウド型業務支援システムを運用しております。 今回の案件…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
大手鉄道会社から委託を受けているスマホアプリ開発のエンジニアを募集します。 ※ペアプログラミングで…
週3日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・-・Unity | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ス…
・FiNANCiEのアーキテクチャ設計・開発・保守 ・クラウドインフラの運用サポート ・パフォー…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails5 | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
・スポーツクラブ、インフルエンサー、アイドルなどの特設ページの作成 ・募集ページや、コーポレートサ…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は医療関連のデータを解析していただけるデータサイエンティストを募集しております。 ・社会的…
週3日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社開発のデジタルマーケティングSaaS「AIアナリスト」のバックエンドの設計から運用まで、一手に担…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
自社サービスのフロントエンドを、Angular/TypeScript で開発していただきます。 ・…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したアプリケーション開発および基盤の構築を担…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Djang・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日】情…
情報サービス会社向けのBPR推進プロジェクトの販売見積受注システムの帳票部分をご担当いただきます。 …
週3日
240,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| CSS・JavaScript・C#・.NET・Azu… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
広告運用(LPデザイン&コーディング含む)
・HTML, CSSでのコーディング ・自社商品のWEBページのデザイン、制作/更新 ・WEBプ…
週3日・4日・5日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター・Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・・Illust… | |
【クリエイティブディレクター|フルリモート…
【案件概要】 食品関連のLP制作に関わるディレクション業務を担っていただける方を募集しております。…
週2日・3日・4日
260,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日】A…
・消費者心理を踏まえた、LINEチャットボットのクリエイティブのデザイン ・LP製作、広告用バナー…
週3日
190,000〜480,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】S…
Rails、Apexを用いたSalesforceと外部サービスとの連携・接続の開発業務をお願い致しま…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・C#・Typescript・Ru… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】新規…
・新規、既存サービスのインフラ構築、保守業務 ・開発チームへインフラ構成の共有 弊社のインフ…
週3日
190,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
弊社の運営するHR系WebサービスのAndroidアプリ開発・保守運用業務をご担当いただきます。 …
週3日
190,000〜470,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
具体的には、下記の業務内容を想定しています。 ・仕様や設計の検討 ・実装/テストコード追加/レビ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
Webシステム開発をご担当いただきます。 基本的な業務は、お客様の課題に合わせたBtoBのWEBア…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【PM|リモート相談一部相談可】生保システ…
【案件概要】 新規システム構築のプロジェクト推進・実施やシステム子会社社員の作業支援をお願いできる…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿多摩センター |
|---|---|
| 役割 | PM |
【データエンジニア】AI技術を活用した新た…
・タクシーアプリの新規開発案件となります。現在リリースされているものの追加開発をメインに行なっており…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Kotlin・RXSwift・Swif… | |
定番
WebサービスのUIUXデザイナー
■役割 ・PC/モバイル向けWebアプリのUI/UXデザイン ・情報設計/ワイヤーフレームの作成…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【UIデザイナー】画面や画面遷移の設計、お…
▼入社後の業務イメージ ・デザインツールを使ったUIデザイン・ビジュアルデザイン ・画面や画面遷…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ニューノーマル社会の実現に向けたゼロトラストソリューションの実現に向け デバイスログ/認証ログ/ア…
週3日
390,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
Androidエンジニアの方には、プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアン…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
某外資系企業様向けの情報システム部のネットワーク運用業務になります。 構築作業もあり、試験仕様書や…
週3日
280,000〜590,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Tanium・Cisco・Umbrella・ArcS… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日】AW…
・システムであるネットスーパーシステムの企画・開発 ・物流管理システムの企画・開発 いずれも自社…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西中島南方 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
処方せんを先に送っておくことで待合室での待ち時間を短縮できる機能や、いつもの薬剤師さんにチャットで気…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
事業拡大に伴い既存サービスやHPコンテンツの改善を行うにあたってデザイナーを募集いたします。 to…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】DX…
2Cサービスを全国展開されている企業様にて、店頭でのお客様へのご案内、契約に利用するiPadアプリ、…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 プロダクトのテクニ…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
開発機能: 商品検索、見積依頼、メッセージング 画面数:26、機能数:大分類で23 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたます。 ※ ご希望ありまし…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン等を活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます。 ・プロダクトの設計・開発・…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】 イ…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【テックストラテジスト/PM|正社員切り替…
VPoE配下の「技術戦略課」にてテックストラテジストとして経営戦略における技術面を戦略的に推進いただ…
週4日・5日
2〜2.6万円/日
| 場所 | 豊洲勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | テックストラテジスト/PM |
| AWS | |
定番
【SREエンジニア】マッチングサービスにお…
・クラウドにおけるサーバーやネットワークなどの構築、運用 ・システムの安定稼働への取り組み( 障害…
週2日・3日
290,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【スマホアプリ】動物系自社サービスを動かす…
我々のミッションはペット業界の様々な課題や問題点をITの技術で解決すること。 そのため、"より多く…
週3日・4日・5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【インフラ】IT/インフラ業務サポート
■案件概要 大手化粧品CL内のWebサービス内に新規機能の追加検討、施策。 導入したサービスのイン…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
生命保険業務基幹システムの維持管理、社員代替業務のご対応となります。 社員代替としてユーザ部門と要…
週3日
340,000〜510,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日】サーバ…
パソコンから車に機器を接続し、車検に必要なデータを車から取得するシステムの開発支援 基本設計書から…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL・SQL… | |
定番
【PHP / 週3日】外食業向け業務改善プ…
弊社が開発している自社開発クラウドサービスの開発・運用および各種アプリの開発、新サービスの企画・開発…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】ソフト…
・データドリブンなマインドセットで、大胆な新機能の設計・開発・テストを行う ・チーム全体で、メルカ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】バ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのUnityエンジニアを担当いただきます。 バーチャルカ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】バーチャ…
VPoE・CTOに就任いただき、開発チームの組織づくりやバーチャルカラオケ事業の開発マネジメントをお…
週3日
440,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
①ライブラリアン作業 ②システム保守・開発支援(テスト支援) 以下の作業がメインで、習熟され…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・VBA・SQL・svn・Jenkin… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日
340,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日】A…
-プロダクト開発チームにおけるUIデザインを主に担当いただきます。 -配属先は業務状況によるため、…
週3日
290,000〜590,000円/月
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管理 ・カバー先追加の対…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】構築…
パブリッククラウドに構築したインフラをIaCを用いて構築、改善をご担当いただきます。 ・AWS…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Terraform | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】構築…
パブリッククラウドに構築したインフラをIaCを用いて構築、改善をご担当いただきます。 ・AWS…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Terraform | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】ア…
メインとなるのは新しい機能の実装ですが、随時バグ改修も行います。 新しい機能を実装する際には要件定…
週3日
230,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Py…
新プロダクトのサーバーサイドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 参画頂くタイ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【フルリモ / システム / 週3日】ER…
ERP導入支援をご対応いただきます。 ①移行方針(移行手法、移行データ、移行元、過去データ、移行範…
週3日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】マ…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】新規スポ…
新規スポーツマーケットプレイスのサーバーサイド開発をリご担当いただくエンジニアを募集しております。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】RO…
顧客ヒアリングからPGへの指示出しと工数算出いただき、障害時の調査対応やPGのコードレビュー、実装相…
週3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】RO…
顧客ヒアリングからPGへの指示出しと工数算出いただき、障害時の調査対応やPGのコードレビュー、実装相…
週3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】toB…
toB向けSaaSプロダクトのサーバーサイドの新規機能開発をご担当いただきます。 Goを使った…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては。大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【テスター|フルリモート】Webサービス及…
【案件概要】 Webサービスや開発システムにおける品質管理及びデバックテスト業務ができるテスターを…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海外 |
|---|---|
| 役割 | QAテスト/テスター |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / グラフィックデザイナー /…
広告クリエイティブ作成の業務(デザイナー)をご担当いただきます。 主に「バナー:動画=8:2」の比…
週2日
80,000〜250,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【Rubyエンジニア】マッチングサービスに…
・Rubyを使った自社サービスのWebサービス・アプリケーションの設計、開発、運用 ・マーケティン…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ubuntu・nginx・unicorn・… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【Rubyエンジニア|フルリモート】自社で…
【案件概要】 自社で開発しているCXサービスのマイクロサービス化や既存システムの改良をお任せできる…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・AWS | |
定番
【正社員】ソフトウェアエンジニア
企画チームとの協業による施策の立案、その効果検証 上記施策の実装/テスト インフラ(Heroku…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | ソフトウェアエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜950,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】情報…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発を担っていただける方を募集します。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件 Auto ML TablesとBQMLで…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】ソフト…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計・開発・運用のご依頼です…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができるフロントエンドエンジニアを募集しています。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 今回…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
アーキテクチャ・新基盤における運用管理関連タスクとインフラ基盤関連タスクの保守・運用・コンサルティン…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
デジタルマーケティング部門におけるITイン…
デジタルマーケティング部門におけるITインフラ管理支援 (保守・運用)
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ー | |
定番
デジタルマーケティング部門における3Dモデ…
デジタルマーケティング部門における3Dモデリングデザイナー支援(企画) 勤務:週1日オンサイト…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
SI企業におけるMicrosoft製品の技…
SI企業におけるMicrosoft製品の技術支援 (アプリケーション開発標準策定・運用、技術指導…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | PowerAppsエンジニア |
| ー | |
定番
SI企業におけるITインフラ領域リーダー …
SI企業におけるITインフラ領域リーダー (ITインフラ領域におけるPM, PMO) 企画・計画~…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
【Webディレクター】旅行系サービスサービ…
・大手Webサービス企業で旅行系サービスのサービス拡大に伴い、同領域の Webディレクターを担当…
週5日
500,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【インフラ】顧客システムにおける運用支援業…
【業務内容】 AWS上の主にEC2、RDS、EKSで稼働しているアプリケーションを安定稼働させるた…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルオペレーションエンジニア(Ops) |
| Docker Terraform | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週3日】SA…
・調達/在庫/実績収集業務に関するSAP導入 ・関連システムの導入支援 ・要件定義支援 ・SA…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋静岡駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
建設業向けの受発注管理や工事管理、および各種工事書類作成の機能を提供するWEBシステムの開発になりま…
週3日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】国内最大…
アプリやその他新規事業における、サーバサイド開発を総合的に行っていただきます。 アーキテクチャ…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【SQL / 週3日〜】国際財務システム改…
リース取引管理システムの改善・保守 (主な機能) 取引受払管理(取引、利息額の入出金管理) 会…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL・PowerBuilder・2017R2 | |
定番
【AWS / 週3日〜】FX取引システム維…
FX取引システム維持保守支援業務になります。 ・FX関連システムの新規構築・維持管理 ・クラ…
週3日
290,000円以上/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C#・AWS | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
・導入先会社の古いExcelマクロをTableauへ置き換え ・導入先会社からの依頼にてTable…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・Excel・Tableau | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
Unity開発全般 ・リアルタイム配信/視聴まわりの改善や機能追加 ・3Dアバターの描画・着せ替…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】バ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのRubyエンジニアを担当いただきます。 ・新機能のAP…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【C++】放送業界向け映像編集システムにお…
放送業界向け映像編集システムにおける映像加工機能の開発 ■担当工程 詳細設計、C++を用いた…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【コーダー募集】制作会社にてwordpre…
【企業】 新潟県の制作会社での勤務になります。 【業務】 クライアントからの依頼を基に、以下の…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 東北:仙台新潟駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【Webディレクター】スポーツ団体向け会員…
◆主な業務内容 下記のうちよりスキルセットに合わせて実施頂きます。 ・新規会員管理サービス(Sa…
週4日
370,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】バーチャ…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのRubyエンジニアを担当いただきます。 バーチャルカラ…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社サ…
主に下記の業務に携わっていただける方を募集します。 ・運用計画の検討 ・各種リソース・パッチなど…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 東北:仙台山形駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
すでにアプリ自体は運用が開始されており、サービスの拡充、機能改善等の要望をいただいている為、開発体制…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
UnrealEngine4(UE4.26)を使用したスマートフォン向けゲームのアウトゲーム全般の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週3日〜】情報システム部門で…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発 開発機能: 商品検索、見積依頼、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスの、クリエイティブ全般UIデザイナーを募集します。 主な…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスの、クリエイティブ全般UIデザイナーを募集します。 …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ふ…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスにおける以下の業務に携わっていただきます。 主な仕事…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| - | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】ソフ…
当サービスにおけるサーバー、ネットワーク、セキュリティなどインフラ全般の設計、開発、運用のご依頼です…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・SQL・Cassandra | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】顧…
製造業様向けSAS製品導入後の定着化支援 Java+SASシステムのリプレース対応 ・フロン…
週3日
230,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SAS・-・ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
クライアントから請け負っているECサイト構築のフロントエンド開発を担当いただきます。 業務内容とし…
週3日
240,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】バ…
バーチャルカラオケ配信アプリでの、アバターアイテムの制作やUnityを用いた実装などを担当していただ…
週3日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのUnityエンジニアを担当いただきます。 バーチャルカ…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
iOSエンジニアとして、マルチキャリア対応モバイルソリューションのネイティブアプリケーション保守/機…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
弊社は保育事業を軸に保育園運営、婚活事業、ウェディング事業、レストラン事業と数多くの事業を多岐に渡っ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Smarty・Vue.… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【マーケター】市場調査・広告戦略 等
広告運用戦略担当者 当社では法律相談サービスの提供を目的とし、各分野ごとにサービスサイトを運営…
週4日・5日
220,000〜440,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
定番
PowerAppsでの各種開発支援(リーダ…
・PJ課題検討および品質管理 ・詳細機能の要件確認 ・設計書のレビュー ・総合テストの仕様書作…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週3日〜】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週3日・4日・5日
660,000〜2,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週3日・4日・5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】情報…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
建設/設計領域におけるBtoBマッチングプラットフォーム新規開発(PoCフェーズ) 画面数 開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週3日〜】シス…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件。 Auto ML TablesとBQML…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週3日・4日・5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】大手…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】新シス…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環…
週3日・4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・スポーツ関連webサイトのデザイン制作 ・サイトのコーディング ・担当クライアントの定例ミーテ…
週5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】And…
国内最大級動画ソリューション企業にて動画配信モバイルアプリ開発を担当していだだきます。 ・Andr…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava | |
定番
【Typescript / 週5日】大手新…
ご紹介企業のフロント開発をご担当いただきます。 ご希望やご経験に合わせて、案件内容はご相談をさせて…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】クライア…
自社サービス導入企業に対してクライアントサイドのデータ管理におけるオペレーションの最適化をADMを中…
週5日
700,000〜1,590,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Javascript / …
フロントエンドに関わる開発業務全般のリードをご担当いただきます。 LIssueに対してのスケジュー…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】受託…
新卒HR領域のカスタマー側のサービスにおけるバックエンド開発をご担当いただきます。 新規サービスリ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / UIUX / 週5日】受託…
人材業界最大手のHR事業プロダクトにおいて、機能改善施策・エンハンス施策に関わるデザインが主業務とな…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】受託案件…
・教育支援webサービスのUI設計 ・画面遷移図制作 ・デザインシステムの設計・運用 ・画面仕…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】国内最…
配車アプリ事業を中核として支える、基盤システムのGoリプレイス案件を担当頂きます。 AWS E…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS/ 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】行政・…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
人事給与パッケージ「Generalist」…
・人事給与パッケージ「Generalist」運用保守 ・パッケージ構成する各種パラメータ設計・設定…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
定番
自社サービスのプランナー
アプリ・イベントの企画 企画資料・企画書の作成 データーの入力 プロジェクトに関するアドバイス
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | プランナー |
定番
自社サービスのコーダー
WEB・アプリのHTML/CSSのコーディング 言語:HTML、CSS ツール:Photos…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
認証基盤等サーバ運用、保守、改善業務(綱島…
認証基盤等サーバ運用、保守、改善業務 お客様先のインフラ保守チームに参画し、サーバ系をメインとした…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川綱島 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
BIツール運用、保守、改善業務(綱島&テレ…
BIツール運用、保守、改善業務 BIツール(Power BI/Azure Synapse Anal…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 神奈川綱島 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【自社サービス】VPoE
・チームビルディング、エンジニア人事 ・メンタリング、コードレビュー ・コミュニケーション促進に…
週4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | VPoE |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
内視鏡に関連したテーマでの画像分類・認識モデルを作成し、論文作成の補助をご担当いただきます。 …
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
イベントにて展示される、利用者とコンテンツがインタラクティブに動く仕組みのプロダクトとなっており、具…
週3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【Unity / 週3日〜】VRプロダクト…
開発中の新規VR筐体に合わせた簡易ゲームコンテンツの開発・実装に携わっていただける方を募集しておりま…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインです。もし可能であればユーザビリティのお手伝い…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】V…
スマートフォン向けのバーチャルライブプラットフォームのサーバサイドの設計、開発、運用を行って頂きます…
週3日
170,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】自社メ…
BtoB企業向けに提供するMAツールのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 様々なフェーズを迎…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・‐・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジェクトメンバーと…
週3日
240,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で、今回は、その自社新規システム…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
お客様先にてインフラ運用担当としての業務支援 ・サーバ構築を手順書に従っての作業やその設定の意…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】教育系…
以下業務を中心に対応いただきます。 ・toB向けプロダクトの各種機能の設計/開発 ・社内シス…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・‐ | |
定番
【リモート相談可 / shopify / …
個人事業主から中小企業、そして当社のEC-CUBEのトップベンダーやShopifyエキスパート獲得に…
週3日
230,000〜510,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| shopify・EC-CUBE | |
定番
【Python / 週3日】自社プロダクト…
今回は、自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるサーバーサイド側の開発業務をお願い…
週3日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
・プロダクト(Web/iOS/Android)のUI/UXデザイン ・スクラム的なPMと協力しての…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週3…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】農業…
現状だと紙ベースでの申し込みになってしまっている会員サイト上でWeb申し込みができるようにする。 …
週3日・5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Git・Docke… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】販促物…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
レガシーブラウザ(IE7)を前提としていたシステムをIE11とchromeに対応するように改修する案…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】デジタル…
今回は自社サービスであるポータルサイトの企画・設計・開発に携わっていただける方を募集しております。 …
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| CSS・JavaScript・C#・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
自社開発を行っております、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正など…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】社内構…
インフラ運用全般を担当するMSPサービスを展開しており、物理環境から仮想・クラウドまで、お客様インフ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は、自社の教育系…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby(Rails… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきます。 具体的に…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Vue.js | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日】Unit…
新規事業として、スマホアプリのブロックチェーンゲーム開発を予定しており、立ち上げからご参画いただける…
週3日
140,000〜400,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えた Webシステムの開発に携わってい…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java/Python /…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設計と実装(テスト…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日】ソ…
分析基盤構築や運用にかかるデータエンジニアの手間を削減すべく、新機能開発、データソース(DB、広告A…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
【Ruby】賃貸管理会社向け入居者管理サー…
【業務内容】 ・Ruby on Railsを用いたバックエンド開発 ・WebアプリケーションやW…
週4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャー 具体的には、 …
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日】フ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週4日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週4…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜590,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・・scala… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日〜】…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / NW/AWS / 週…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 599 :インフラ(NW・AWS・OS)保守 |
サーバーサイドエンジニア
【業務内容】 基本設計からのシステム開発支援をお願いいたします 場所:品川シーサイド ※現状…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・java・spring・Git・L… | |
注目
サーバーサイドエンジニア
案件概要 : 決済システム開発支援作業 作業場所 : 勝どき ※現在は70%~80%テレワーク …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき |
|---|---|
| 役割 | COBOLエンジニア |
| COBOL・Net-COBOL・UNIX | |
サーバーサイドエンジニア
案件:証券代行業務システム開発 概要:証券代行イメージワークフローシステムのインシデント対応をご担…
週5日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明大前 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java・Sprig・AWS・Linux・… | |
サーバーサイドエンジニア
【業務内容】 内容:ユーザー社員配下でシステム開発全般の支援を行います。 基本的には要件定義、基…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外多摩センター |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java・Sprig・AWS・Linux・… | |
サーバーサイドエンジニア
【業務内容】 通信会社向け開発支援作業を行っていただきます。 作業内容 :基本設計 ~ テス…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Java・Sprig・AWS… | |
広告運用コンサルタント
WEB広告の最適化をPDCAを回しながら行い、 クライアントの事業拡大・売上拡大に貢献する仕事とな…
週1日
60,000〜160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | コンサル(広告運用) |
定番
【フルリモ/女性商材案件/週1日稼働OK】…
【業務内容】 広告バナー・LPのデザイン制作 美容系・整形系・求人媒体・学習塾の業種をメインに、…
週1日
40,000〜130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ・ | |
定番
【動画クリエイター】インスタやtiktok…
インスタやtiktokなどのショート動画制作を行っていただきます。
週1日
40,000〜90,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作 |
定番
【フロントエンドエンジニア】SPA, MP…
【企業】 大手銀行の基幹システムをクラウドにリプレイスするサービスを展開する企業。 (2021年…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
※詳細は、打ち合わせ時にお伝えさせていただきます。 ・サーバープログラムや機能の設計・開発 ・新…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】仮想…
メイン業務としては、 サービス提供ユーザーの声をベースにCSチームと連携をした機能開発 既存サー…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js・Nuxt.js | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
弊社サービスのユーザー体験に紐づく全体の戦略策定を担う ・ユーザーニーズ分析(インタビューやアンケ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】大規…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのPLをご担当頂きます。 設計から行いチ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
・toC開発プロダクトのアプリ(特にiOS)においてユーザーやビジネスサイド、PdMからの要求事項か…
週3日
290,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週3日】…
某キャリア向けiOSアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ) 大規模スクラムでのA…
週3日
280,000〜810,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週3日】…
某キャリア向けiOSアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ) 大規模スクラムでのA…
週3日
280,000〜810,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
某キャリア向けAndroidアプリの機能開発(コンシューマ向けポイント機能アプリ) 大規模スクラ…
週3日
280,000〜810,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
自社で開発を行っているクラウド人材管理ツールのフロントエンド側の新規機能の開発や既存機能の改善対応、…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日】…
・オンプレミス、GCP、AWSを利用したハイブリッドクラウドの構築 ・開発チームと共にマイクロサー…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
機械学習、自然言語処理等の技術を利用して、 プロダクトの価値を高めるデータサイエンティストを募集し…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・PyTorch・・TensorFlow… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 Androidアプリケーションの開発 …
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】医…
・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 iOSアプリケーションの開発 シス…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】医…
具体的な業務 ・顧客の課題の洗い出しと対応施策の検討 ・具体的な機能への落とし込みとプロトタイピ…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・‐ | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
フロントエンドエンジニア/UXエンジニア/マークアップエンジニアとして、ユーザーやサービス視点で自社…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週3日
290,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / プロダクト / 週3日〜】…
Fintech企業の決済アプリのプロダクトデザイン全般をお任せします。 プロダクトマネージャー、U…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
| Figma・Illustrator・Photosho… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日】…
AWS基盤の設計・構築 ・Quorum(ブロックチェーン)を用いた取引システムを、AWS上に構…
週3日
240,000〜480,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
新プロダクト開発において、以下のような業務に従事していただきます。 ・機械学習アルゴリズム選定、モ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
新プロダクトにおけるフロントエンドに特化した業務を担って頂きます。 ・新規企画および顧客要望を基に…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
コーポレートページ・社内報などコンテンツ制作を行っております。 WEBコンテンツの作成や紙媒体…
週3日・4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| illustrator・Photoshop・abob… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日】…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】行政・自…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
安定供給を実現する為の自社サービスであるサプライチェーンリスク管理サービスの開発に携わっていただきま…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
タクシー社内に設置している、乗務員様用Androidアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【iOS / 週3日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週3日
340,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・ | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Fint…
お金がより自由に届けられ、より明るく楽しい世界を実現できるように、コンシューマー向けのアプリと、法人…
週3日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】Webア…
・Go言語によるWebアプリケーション開発、API開発、バッチアプリケーションの開発 ・アプリケー…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
具体的な作業内容としては、新規/既存システムのDB構築、論理設計、物理設計、構築業務、運用保守、リリ…
週3日
390,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】3…
3D スキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
下記三つの事業を展開しております。 ・クラウドインテグレーション事業 ・データ分析サービス事業 …
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
オーディオブックサービスを構築するための人員を募集いたします。 スマートフォンをメインターゲット…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
不動産(オフィス)のコンサルティングをしている会社です。 主要都市のオフィス物件情報を自社サービス…
週3日
360,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・React・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 小学校~高校、専門学…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
Webデザイナー_二次元コンテンツ販売事業
1.キャンペーン訴求ページ制作( 美少女ゲーム/PCゲーム・同人・電子書籍) 2. バナー対応…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】ク…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】新…
新入社員向けJava研修の講義・教室運営をお任せします。 メイン講師の方と一緒に講義を行う、サブ講…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東陽町 |
|---|---|
| 役割 | 講師(C#) |
| C#・VB.NET・Spring | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週4日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ/ Python/ 週5日】マー…
【担当業務】 - マーケティング施策の運用業務や表示ロジックの開発 - マーケティングオートメー…
週5日
500,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フロントエンドエンジニア】各種自社システ…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【バックエンドエンジニア】各種自社システム…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript | |
定番
【サーバーサイド保守エンジニア】Oracl…
原価システム(mcframe)、販売会計システムの維持運用、保守をご担当頂く。 【勤務場所】基…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
| Java・SQL・mcframe | |
定番
インフラPM
【案件概要】 ・サーバー、電話、インターネット回線のインベントリの作成(既存のものが更新されていな…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア・PM |
定番
SAPエンジニア
【案件概要】 外資製薬会社の工場において、既存SAP/ECCをS4 HANA に更新する全社プロ…
週5日
330,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒 |
|---|---|
| 役割 | SAPエンジニア |
| SAP | |
定番
【SAP】SAP L1サポート
・SAP L1サポートチームメンバとして以下の作業を実施 ・一部SAP管理業務 ・日本ユーザと海…
週5日
330,000〜920,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【サーバーサイド】業務システムの引継ぎ対応…
受注から財務会計までの工場系システムがいくつかある中で、 保守開発対応として発生する要件に対して改…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・VB.NET・SQL | |
定番
【PM】ERP Dynamics365 F…
ERPのシステム導入支援を行っていただきます。 ①D365プロジェクトマネージャー ②D365生…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| AX2009・or・AX2012・or・Dynami… | |
【コンサル/マーケ】日本最大級AIコンペサ…
【業務内容】 自社プロダクト・サービスのPR/マーケティング(BtoB) ターゲットに対して、最…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コンサル(新規事業) |
【Java】モバイル英語学習サービスの開発…
【業務内容】 ・Webアプリの開発・運用 ・企画メンバーと協力しながらクオリティとユーザー目線を…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週4日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日】行…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】ク…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
提供中プロダクトの機能追加、改善をプロジェクトをマネージしているPM/リーダーと協力し、サービスの魅…
週4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】自…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週3日
2.8〜5.5万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / Rails / 週3日】教…
主にRubyで自社サービスの開発を行っていただきます。 新規立ち上げのサービスになるので積極的に新…
週3日
340,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Rails・‐ | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】インタ…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社A…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日】自…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日】大…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
公共系イントラネットのサーバ、クライアント端末の大規模開発プロジェクトになります。 結合試験工程以…
週5日
410,000〜910,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| VmwareESX・ActiveDirectory | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
通信会社向けインフラ構築検討・運用支援プロジェクトになります。 主な業務としては、 ・通信会…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| OpenStack・Git・Kubernetes | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】自社プ…
プロダクト開発を行うチームにテックリードとして従事し、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの技…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
幼稚園・保育園向け写真販売システムの開発業務をお任せいたします。 約 3,000 の園に導入いた…
週5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
①ドットアニメ制作 キャラ原画を縮小してドット化、アレンジ。ドット絵から直接アニメを作成する事もあ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| Photoshop・Unity | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
Pythonを用いた分析処理のバッチシステム開発を行います。 主に分析処理の前処理にあたるデータ加…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイド開発業務を担当していただきます。 ・GoでのAPI…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Scala・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】大…
今回の募集では、賃貸物件の家賃債務保証を行う事業部にて新規WEBサイト制作や新規システム構築の業務に…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅/水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue ・‐ | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週3日
290,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
NFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探しています。 AWS…
週3日
390,000〜810,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモート】プランナー/ディレクター
スマホアプリゲームの運用や施策提案・仕様決定など、幅広くご対応をしていただくプランナー/ディレクター…
週4日・5日
250,000〜390,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日】大…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
キャリア向け音声認識エンジンサービス開発業務支援プロジェクトとなります。 音声認識エンジン(SDK…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++・AWS・Android・i… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】医療・…
新業務フローの取りまとめ、人事側の運用策定、推進を出来る方、各テストの進捗課題管理を人事側に寄り添っ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
スキルにより、リーダーまたはメンバーとして業務をご担当いただきます。 ①全体テスト管理、推進業務 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現行CI/CD環境のフルリプレースに伴い、既存スクリプトを新しく書き直すエンジニアを募集しています。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】共…
基本設計以降の開発業務を行います。 ・基本設計/詳細設計の成果物作成およびレビュー 例)API…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社コ…
自社コンテンツの新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正 Redmineで案件管理されて…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
【Javascript/SQL】運用保守支…
・AdobeAnalyticsを用いたHR領域の事業サポート ・各サイトの品質改善、維持サポート …
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・SQL | |
【ASP】Webシステムの開発支援|エネル…
・Webシステムの開発/テスト/マスタメンテの支援 ・レビュー等は別運用メンバーにて実施 ・業務…
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | ASPエンジニア |
| VBA・SQL | |
【Java/Angular】パッケージ更改…
・顧客先パッケージ更改に伴う周辺機能のI/F(インターフェース)開発支援 ・Javaを使用した周辺…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript | |
【AWS】クラウド共通基盤業務支援
・共通基盤更改プロジェクト支援 ・事業会社とITインフラ構築チームの間に立ち検討支援 ・事業会社…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社サー…
当社並びに、当社関連会社(証券会社・FX会社)で手がけるWEBサービスの、開発プロジェクトを推進する…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
マーケティング組織でのデザイン業務を担っていただける方を募集いたします。 主な業務としては、 …
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務を担っていただける方を募集いたします。 - …
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
【PHPエンジニア】大手小売業の基幹システ…
【案件概要】 大手小売業の基幹システム刷新にともなう開発案件。 担当していただく領域は、受発注、…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 池袋東池袋 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・PHP・shell・SQL・Linu… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】情…
・TypeScript, React, Next.jsを使用したSPAの開発 / 設計 ・フロント…
週3日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】販促物…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日】…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 今回…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日】行…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】医療×…
医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただきます。 PHP…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【PHP / 週3日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が受託にて開発予定の薬品会社内での実験機器の自動化ソフトウェアの開発をご担当いただきます。 具…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
・Webコーディング(HTML、CSS、javascript) ・Shopify、カラーミーショッ…
週3日・4日・5日
350,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Vue.js / 週3日】外食業向け業務…
弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロントエンド開発業…
週3日
290,000〜490,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインですが、新製品の開発…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして使用すればするほど人工知…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】自社…
ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして使用すればするほど人工知…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダッシュボード系シ…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Typescript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
既にサービスを展開しているチャットサービスの機能拡張開発を行っていただきます。 サービスツールはA…
週3日
270,000〜470,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
当社は、HTML/CSSしたBtoB事業、BtoC事業の2つの領域にて多様な独自サービスを展開してい…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
企業や団体の課題に対してIT技術を用いた課題解決策を分析/提案をご対応いただきます。 ・オンプレ環…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Azure・OpenShift・kubern… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
・新規企画および顧客要望に基づくアプリケーション開発 ・TypeScript やAngularを用…
週3日
290,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化を目指している、…
週3日
220,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化を目指している、…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおけるフロントエンド開発…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
【サーバーサイドエンジニア】経費精算サービ…
【概要】 経費精算サービスの開発を行なっていただきます。 AI+OCRでの登録をするサービスの構…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・AWS・git・(A… | |
定番
【Ruby】自社CMSサイトの設計、開発、…
【業務内容】 ・自社CMSサイトの設計、開発、構築 └新規プロジェクトになります。 【使用…
週4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・・ | |
定番
【フロントエンドエンジニア】大手カー用品向…
【業務概要】 WEBページから店舗で実施するサービス予約ができるフロントサイトの開発と予約を実現す…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・React.js | |
定番
コンサルティングセールス(個店担当)※正社…
・新規顧客の開拓/提案 ・クライアントの課題やニーズの把握 ・課題解決方法の提案/効果分析 ・…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | セールス |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】販促物…
弊社はブランディング開発(CI・VI設計)やコンテンツ、コミュニケーションデザインを意識したWEB制…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日】…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】行政・自…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】新…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
2Cサービスを全国展開されている企業様にて店頭でのお客様へのご案内、契約に利用するiPadアプリ、サ…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
・仕様検討、顧客との仕様調整、開発チームへの仕様展開、仕様調整 ・業務仕様の理解、開発チームとの連…
週5日
750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附(永田町) |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Typescript / 週5日】大手新…
ご紹介企業のフロント開発をご担当いただきます。 ご希望やご経験に合わせて、案件内容はご相談をさせて…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
移行統制・移行計画 全体の移行計画、移行計画に従ってリハーサル計画を具体的な作業に落とし込み、…
週5日
750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| 指定なし | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援するkakari/kakari for Clinicでは、新たな基幹サービ…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週4日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週4日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【Ruby / 週3日】不動産売却領域サー…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 社内向けツールも機能が最小限…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
・マーケティング仮説を検証するためのデータフロー設計 ・タグ・パラメータなどの入力データの選定と整…
週3日
340,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】ペット…
既存事業の開発業務をサポートいただけるサーバーサイドエンジニアを募集しております。 PHPを用いて…
週3日
140,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日】オ…
今回は、サービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 医療領域…
週3日
280,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Java/C# / 週3日…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】オンラ…
・toC,toB事業で動いているシステムのアップデート ・DX事業の立ち上げに必要な基幹システムの…
週3日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
今回は取引所の強化やカバー取引機能の高度化を進めるため、人員を募集します。 ・取引所・カバー取…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週3日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週3日
390,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】We…
・PHPを使ったCMSプラグインの開発・実装 ・Webアニメーションのコーディング ・外部API…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】社…
・社内システムの運用、整備 ・バックエンド開発案件の見積もり作成、開発、実装 ・バックエンド開発…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【EC経験者優遇!|フルリモ|週4~5日】…
【案件 概要 】 当社が運営する複数のECサイト(Shopifyをはじめとした各種ECサイト)およ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Webデザイナー|フルリモート】ECサイ…
【案件概要】 弊社で運営する複数のECサイトおよびクライアントサイトのデザイン制作や結果分析、改善…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【EC経験者優遇!|フルリモ|週4~5日】…
【 具体的な仕事内容 】 ■ECサイト構築・開発ディレクション ■Shopifyテーマの設計、開…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【正社員切り替え案件!】自社のwebディレ…
【案件概要】 ・本案件は、業務委託→後々に正社員へと切り替えていただく案件になります。 (切り替…
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フルリモ! / PHP / 週5日】メデ…
■業務内容 ・自社メディア、サービス運用開発 ・クライアントメディア、LP運用開発 ・上記の運…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
【フルリモ|週4~5日】♦WEB広告運用経…
【 具体的な仕事内容 】 ■クライアント様ECサイト広告の予算策定・効果測定・運用 ■アクセス解…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBマーケター |
| HTML・CSS | |
【VB.NET/SQLServer】某物流…
◎大手物流会社向けインフラサーバ構成支援 ・帳票出力部分、WEB画面、運用系バッチ(ガベージやデー…
週5日
500,000〜630,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅or調布駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(VB.NET/SQL) |
| VB.NET・SQL | |
認証システム移行PJにおけるPMO支援
・認証システム移行PJにおける技術支援 ・進捗管理、品質管理、会議体調整、チーム間連携調整 ・自…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲上野駅or溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【グラフィックデザイナー/フルリモート・週…
【業務内容】 自社のプロダクトマーケティングにおける、課題の発掘・検証のために以下の分析・解析や…
週3日
350,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】フロン…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaも…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週4…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日】大…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / 2Dデザイナー / 週5日…
人気アイドル系IPタイトルのキャラクター等のモーション制作全般の業務を行っていただきます。 ・…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【Java/ 週5日】某流通系システム運用…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う 構成管理:プログラムに使用する項目の…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Shell・Java | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日】自社HR…
自社HRサービスのUIデザイン全般をご担当いただきます。 ・ユーザー側のプロダクト:求職者が使…
週3日
240,000〜510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週3日】オ…
React Nativeを用いたネイティブアプリ開発です。 ヘルスケア領域での自社プロダクト・他社…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】オン…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
TV/映画/アニメ等のコンテンツ配信サービスに関わるデータ連携システムの更改開発作業になります。 …
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Perl・SQL・BusinessOb… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社EC…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GCP | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日】自…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【HTML/CSS / 週3日】輸入車サー…
車関連サービスの開発チームや社内プロダクト関連の、デザイン作成業務を行っていただきます。 主に…
週3日
110,000〜370,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】SaaS…
自社SaaSサービスのプロダクト開発のエンジニアとしてご参画いただきます。 ベースは自社開発のスト…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / React / 週3日】フ…
・Go言語を用いたバックエンド開発 ・React(TS)を用いたフロントエンド開発 ・運用後のフ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Typ… | |
定番
【PHP / 週3日】整備板金業向けのパッ…
クライアントである一部上場企業様の整備板金業向けのポータルサイトの開発に携わっていただきます。 予…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】自社プロ…
ADVA(アドバ)のプロダクト開発を行うチームにテックリードとして従事し、 バックエンド、フロント…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
発注や配送など現状人手で手配を行っているものを実績データをもとにした 需要予測を行い、発注、配送計…
週5日
580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザインプロジェクトの開発です。 自社で開発したプ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
今回は膨大なSNSマーケティングデータを扱うtoB向けSaaSプロダクトのML開発業務をご担当いただ…
週3日・4日・5日
1,210,000〜1,820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】A…
AWS上で稼働しているシステムに対する機能拡張の改修プロジェクトになります。 ・開発・保守作業…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 神奈川竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Java・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
医療機関・患者双方に支持されるプロダクトに関するエンジニアリング業務全般をお任せします。 ・サ…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・Ruby… | |
定番
【広告運用】デジタルマーケティングベンチャ…
■作業内容 アフィリエイト広告代理業を行う部署にて、数百万/月〜1,000万円/月規模の案件に携わ…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
| 参画当初は出社とリモートのハイブリットから始める想定… | |
定番
募集ポジション業務委託_データサイエンティ…
分析組織のプロジェクトマネージャーのもとで、事業におけるマーケティング分析や統計・機械学習モデルの開…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R・ー | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 ・オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日〜】…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
RPAソリューション開発支援事業にて、RPAツール使用のセミナーやお客さまがRPAを導入する際…
週3日・4日・5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】販促物…
総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当いただきます。 …
週3日
240,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
・新規または既存Webサイトのデザイン ・アプリケーションのUI/UX設計 ・Webサイトの企画…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD・Figma | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
弁護士事務所向け自社サービスのサーバーサイド開発を行っていただきます。 取締役全員がエンジニアのベ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Angular / 週3日…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ・販売管理(予約管理、受発注、見…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日】GC…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 システムの詳細 ・販売管理(予…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】モビリ…
自動車のサブスクリプションサービスのオウンドメディアに関わる開発業務をご担当いただきます。 具体的…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】バー…
バーチャルカラオケ配信プラットフォームのRubyエンジニアをご担当いただきます。 バーチャルカ…
週3日
340,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原田原町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】フ…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】新…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / CC++ / 週4日】クラ…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】情報シ…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】介…
今回は当社メインサービスのweb/モバイルアプリ周りをご担当いただきます。 ・Web、モバイルアプ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
【週3~5日|フルリモOK!】WEBサイト…
【企業】 WEBサイト制作を中心に、コンサルティング事業からメディアクリエイティブ事業と幅広く展開…
週3日・4日・5日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター(デザイン知識必要) |
【MS or VBAエンジニア】某確定拠出…
■担当業務: レコードキーパー業務を運用・管理するEUCツール群(250ツール超)の保守 ■…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA・MicrosoftAccess2016 | |
定番
【カリキュラムプランナー|週3日~5日・フ…
本案件では高校生向けのプログラミング教材のカリキュラムプランナーとしてプロダクト開発における責任者と…
週3日・4日・5日
270,000〜380,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | カリキュラムプランナー |
【マーケター/アドバイザー】MAツールの運…
【業務内容】 MAツール上での以下業務 ・MA設計設定業務 ①データマネジメント(配信対象者…
週3日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター/アドバイザー |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週3日〜…
・ベンダコントロール(アプリベンダ、UATベンダ) ・部内およびIT部門との社内調整 ・プ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Node.js / 週5日】某オンライン…
・HTML, css(Sass/Scss), JavaScriptを用いた設計・コーディング ・N…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
主に自社サービス開発業務です。 基本設計~対応可能な要員を探しており、長期的にぜひご支援いただきた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・ベンダコントロール(アプリベンダ、UATベンダ) ・部内およびIT部門との社内調整 ・プロ…
週3日・4日・5日
500,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】健康・福…
既存システムの改修や簡単な新規開発のサポート業務をご支援いただきます。 基本的にはバックエンドシス…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社顧客…
弊社の下記システムのPMを担っていただきます。 ①顧客管理システム ②①に紐づくLMS(ラー…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
弊社の下記システムの開発を担っていただきます。 現在では下記の開発をしております。 ・カウン…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・RubyonRails・PHP・L… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】ス…
スマートフォン向けゲームコンテンツのUIデザイン業務 ・画面レイアウトの制作 ・デザインテイスト…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】フ…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
急募
【リモート相談可/週5日】3次元点群データ…
■3次元点群を用いたデータ解析や3Dデータを用いたAIアルゴリズムによるデータ解析及び研究開発、セン…
週5日
250,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【リモート相談可/iOS/週5日】iOSエ…
仕事の内容 ■3次元点群を用いたデータ解析や3Dデータを用いたAIアルゴリズムによるデータ解析及…
週5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
急募
【リモート相談可/ROS/週5日】ROSエ…
仕事の内容 ■3次元点群を用いたデータ解析や3Dデータを用いたAIアルゴリズムによるデータ解析及…
週5日
250,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | ROSエンジニア |
注目
【リモート相談可/Unreal Engin…
仕事の内容 ■3次元点群を用いたデータ解析や3Dデータを用いたAIアルゴリズム開発の為のシミュレ…
週5日
250,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Unreal Engineエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】行政・自…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】新…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日
340,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】リユー…
AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。 AWSに精…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AI / 週3日】自社グル…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日】…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 独自映像技術を活用し…
週3日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Node.js・… | |
【Javascript/SQL】運用保守支…
・AdobeAnalyticsを用いたHR領域の事業サポート ・各サイトの品質改善、維持サポート …
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・SQL・AWS | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】商品デ…
・AWSに構築されたデータ品質チェックシステムの保守運用 ・システムはCloudWatch、Far…
週5日
240,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日】転職/採…
弊社の開発チームにて、サーバーサイドをご担当いただきます。 具体的な業務内容はプロダクトの新機能…
週3日
290,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
社内の営業が使用する社内システムの内製プロジェクトに参画いただきます。 ・ReactのhookとT…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週3…
Azure環境の保守や運用作業をメインでご対応いただきます。 設計・開発・構築はすでに完了しており…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日】…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
現在サービスインしているB2Bの基幹システムをリニューアルをご担当いただきます。 担当業務は主にク…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿愛宕駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ECS・Fargate | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】クライ…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週4日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業 ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれば対応事項…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 プロダクトのテクニ…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【PHP / 週4日】情報システム部門での…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます。 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】販促物…
総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当いただきます。 …
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日〜】国内…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
インターフェイスの開発ならび、データ移行業務です。 インターフェイスの開発では、システム間連携の構…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】行政・自…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】都市…
・事業計画に基づく開発/改修計画の策定 ・開発リソースの確保 ・開発 および PM ・コードレ…
週4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
モバイルオンラインゲームの データ基盤の開発・運用を担当するグループのサーバサイド担当エンジニアと…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】決済…
決済代行会社のシステム部門でのお仕事です。 今や欠かすことのできない「オンライン決済」や「店舗向け…
週5日
610,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
音楽業界向けのシステム開発を行う企業様で現在運用中のウェブサービスの開発を行っていただきます。 顧…
週3日
240,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・Linux・Postgr… | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
SFA・CRM・販売管理業務に対するSalesforce導入の保守案件に携わっていただけるエンジニア…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日】大…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日】…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週4…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証 オンプレミスで稼働している仮想サーバーをクラウド環境へ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】フ…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜770,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / Python/Ruby /…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【PM】プロジェクトのグランドデザイン、プ…
【具体的な業務内容】 AIを用いた多用なソリューションを展開する当社のプロジェクトマネージャーとし…
週3日・4日・5日
550,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Unity / 週4日】大…
クライアントである大手通信業者様で実施しているDXプロジェクト内のPoC開発をご担当いただきます。 …
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】サーバ…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・TypeScript・Git・UNIX・Li… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】販促物…
弊社はデザインのみならず、企画・プレゼンテーション・開発まで行う制作会社になります。 ブランディン…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日】国内最…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週4日
450,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】国内最大…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日
450,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | [Go]Webエンジニア/国内最大のタクシー配車サービス |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日】…
大手企業向け統合人事システムの開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供しております。 イン…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・Oracle・Windowsバッチ | |
定番
【iOS / 週4日】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週4日
450,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】自…
当社が運営する新規サービスに関するフロントエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービ…
週4日
450,000〜890,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】行政・自…
自治体での住民向けのネットワーク(Wi-Fi等)のPJがあり、リードしていただけるPM/ネットワーク…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
弊社マイクロサービスとして切り出されているサーバサイドKotlinの部分は以下となります。 -…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】新…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
【Flutter】美容サロン集客サイトの開…
【業務内容】 美容サロン集客サイトの開発で0→1フェーズで依頼いたします。 【環境】 マー…
週1日・2日・3日・4日・5日
160,000〜670,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Firebase | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、 運用保守業務をご担当いただく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】薬局との…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日】…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週4日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
【リモート相談可/AI/週5日】オープンポ…
下記の事業のサポート(業務サポート・事務・秘書) ◆自律駆動型ロボットの自社開発 ◆大手メーカー…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | オープンポジション |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
今回はサービス普及を求める声に答えるため、開発チームの強化へむけての人材を募集します。 Rubyo…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フロントエンドエンジニア】新規事業におけ…
【具体的な業務内容】 ・web標準を前提としたHTML/CSSによるコンテンツとUIの設計、開発、…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【TypeScript】オンライン医療診断…
TypeScriptのバックエンド(Redwood.js, Prisma, GraphQL)を中心と…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・RubyonRails | |
定番
【Webデザイナー】NFTのデザインにも携…
・オーナーのプロジェクトに関連するデザイン制作 (プロジェクト紹介のカバー画像、説明図、バナーなど…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週4日】短…
・React Native でのアプリ開発 ・Nuxt.js でのWeb開発 (両方ともType…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】新…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・UnrealEngine | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】D…
エンド企業様のDX関連開発におけるiOSアプリケーションの開発及び、運用保守業務をご担当いただく案件…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOS/Swiftエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】薬…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日】ク…
・ UnrealEngineのUMGを使用したUI実装およびアウトゲーム開発業務全般 ・ 3Dを併…
週4日
390,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・UnrealEngine4・Perfor… | |
定番
【フルリモ / SCM / 週4日】需要予…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日
520,000〜1,610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Java / 週4日】人材…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週4日
390,000〜1,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日】オン…
Ruby on Railsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 プロダクトのテ…
週4日
240,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】フード…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週4日
390,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】情報シ…
弊社の情報システム部門にて、社内システム開発/設計を担っていただきます・ 生産現場からの要望を整理…
週4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をプロジェクへアサイン…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Azure / 週4日】保…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週4日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / PHP/Python / …
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日】システ…
GCPで顧客の構造化データを使用して、予測を行うAI案件です。 Auto ML TablesとBQ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】国内最大…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日】サーバー…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日】…
・プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps ・顧客側プロダク…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Kotlin・Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / React / 週4日】フ…
スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用、最新アーキテクチャを採用した大規模開発…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日】i…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週4日
520,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・Swift・Kotlin・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日】自社AI…
事業戦略に則し、エンジニアやデザイナー、ビジネスサイドのメンバーと協力しながら開発効率を最大化させる…
週4日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Scalaもしく…
週4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Scala・http4s・scalat… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのデータ分析・モデリングの要求・要件定義をご担当いただきます。 …
週4日
520,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・PyTorch・NumPy | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日】脳…
弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのQA業務をご担当いただきます。 ・弊社が提供するプロダク…
週4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ‐・‐ | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日】大手小…
今回ご依頼案件としては、大手小売業界クライアント様の需要予測モデルの運用・改善をメンバーとしてアサイ…
週4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週4日
440,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週4日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS/NW / 週…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週4…
Azure IaaS環境の設計、構築、検証業務を担っていただける方を募集します。 ・オンプレミ…
週4日
390,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
(※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます) 主な業務としては、自社Webサイトのデザイン&コーディ…
週3日
170,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
[PM]自社開発/大手クライアント案件中心
【仕事内容】 スマホ、Webアプリ開発のディレクター(PM/PL)をお任せします。 スキルに合わ…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜新町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
大手SIerのアーキテクチャデザイン支援部隊にて、エンドユーザや社内他事業部に対して現行運用のヒアリ…
週5日
330,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Springboot・Vue.… | |
定番
[フロントエンド]自社開発/大手クライアン…
【仕事内容】 クライアント案件サイトのサイト実装・サーバ構築やWebサイトおよびスマホアプリなどの…
週5日
390,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
iOSを中心に技術面でチームをリードしていただき、技術課題のマネジメントや開発フローの整備など、様々…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・CircleCI | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手宅配運送会社向けの配送連携システムのリニューアルに向けてPJを立ち上げております。 開発内容と…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Spring・FrameWork・Post… | |
定番
【リモート相談可 /デザイナー / 週4日…
今回はマーケティング組織でのデザイン業務をお任せします。 ・マス広告に関連するLP、バナーの作成 …
週4日・5日
150,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| AdobeIllustrator・Photoshop | |
定番
【フルリモ / Django / 週3日〜…
特徴量を解析しており画期的なソリューションになります。 大量データの解析や、AWS 環境の構築につ…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・・Django | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
インテグフローを理解した、ローカルビルドの実施と運用をご担当いただきます。 具体的にはビルドエラー…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・Shell・Git・Android・A… | |
定番
【Java / 週3日〜】某流通系システム…
運用保守業務 日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う。 構成管理:プログラ…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・Shell | |
定番
【リモート相談可 / Python / …
•製品の問題を分析し、正確なテクニカルレポート作成 •特定された問題に固有の自然言語処理および音声…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川綱島駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
小売業のECモールへの新規出店、出品、受注在庫管理を行うシステムの機能追加、改修業務です。 業務シ…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
全社横断的な技術領域における課題解決やエンジニア育成などのミッションを担う、当社が統括する組織への配…
週3日・4日・5日
410,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
カード会社におけるDX推進業務。「SRE」の位置づけでインフラ周りを中心に構築・運用業務に携わってい…
週5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| OpenShift・Kubernetes・ArgoC… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】業界最…
弊社内で収集したデータをもとに、相関分析など主に統計的な手法により、課題とその発生要因の特定を目指し…
週3日・4日・5日
660,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
・自社サービスの貿易サポートシステムのバーションアップ、後進育成 ・フロントエンド・バックエンド開…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】テレビ…
テレビ視聴データをBI提供するレアSaaS開発において、主に開発チームのPMを募集します。 具…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】受託プ…
・クリエーションラインの取り扱うデータ関連プロダクト(MongoDB, Neo4j, Conflue…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・‐ | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
既存サイト運用をご担当いただきます。 ・社内既定により算出したスケジュールでのクライアント折衝 …
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
・弊社のiOSアプリ開発 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグの調査および修正等 ・ユニットテス…
週4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】開発チー…
・プロダクトオーナーと共に各PDT、PJTの開発進捗確認・管理を行う ・開発仕様の検討 ・プロダ…
週5日
330,000〜930,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
注目
【WEBデザイナー】幼稚園・保育園向けの写…
【業務詳細】 ・WEBサイトやアプリケーションのプロトタイピング ・WEBサイトやアプリケーショ…
週4日・5日
2.4〜2.8万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【SRE】AIによる契約書レビューサービス…
AIによる契約書レビューサービスを軸に企業の契約書作成を包括的にサポートするSaaSを開発・販売して…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
【Java/Spring】情報・通信会社支…
場所 :門前仲町 基本テレワーク 期間 :4月~長期 作業内容 :方式設計~
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋門前仲町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Java・Sprig・AWS・Linux・… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】フ…
・健康経営SaaSのプロダクト開発 ・提供するサービスの新規開発及び機能拡充、性能改善 ・マイク…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】某…
・業務:宅配、店舗システムでのプロモーション再構築 ・対応工程:要件整理、要件定義、システム要件設…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】大手ふ…
大手ふるさと納税サイトのCMS開発やAPI開発など、要件定義から設計・コーディング・保守運用まで一貫…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP/SQL / 週5日…
大手ふるさと納税サイトにて、Webサイト・サービスのプロダクト開発のシステムエンジニアを募集します。…
週5日
410,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・SQL・- | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・ネットワーク機器の運用・保守を担当 ・インフラ・ネットワーク機器でのトラブル対応・切り分け ・…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
某金融機関インターネット接続/社内環境のリプレイスの案件です。 元請様の自社メールサービス、NWサ…
週5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】開発P…
事業戦略の提案や助言がメインのビジネスコンサルティング会社と、 業務効率化のためのシステム設計・開…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】決済領域…
・iOSネイティブアプリ開発における進捗、課題の推進及び管理 ・開発工数からの開発スケジュール策定…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Node.js】自動車サブスクリプション…
弊社が運営しているモビリティサービス事業のサービス開発をご担当いただきます
週4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Java・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Salesforce…
現行ECサイトをSalesforceのB2BCommerceへとリプレイスを行うにあたり、PM及び開…
週5日
410,000円以上/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
①全体テスト管理、推進業務 ・各種テスト計画支援 ・テスト仕様書フォーマット、ドラ…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
①全体テスト管理、推進業務 ・各種テスト計画支援 ・テスト仕様書フォーマット、ドラフト…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
オンラインカーリースサービスに関するフロン…
▼業務内容 オンラインカーリースサービスに関するフロント開発をメインに行なっていただきます。 ・…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【Java / 週4日〜】某流通系システム…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う。 構成管理:プログラムに使用する項目…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・Shell・Java・COBO… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
・フロントエンドに関わる開発業務全般のリード ・LIssueに対してのスケジューリング ・開発方…
週5日
570,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / UX / 週5日】自社サー…
自社サービスのユーザー体験に紐づく全体の戦略策定を担っていただける方を募集します。 ・ユーザーニー…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
・フロントエンドに関わる開発業務全般のリード ・LIssueに対してのスケジューリング ・開発方…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / UX / 週5日】自社サー…
プロダクトを中心に、エアリアルパートナーズのデザインに関わる業務全般の実務を担っていただきます。 …
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】社内…
社内インフラの刷新を行っているのですが、その中で各システムからログを収集する必要があります。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
当社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js・Gi… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】FXの顧…
FXの顧客向けバックエンドシステム開発の案件です。 本プロジェクトは、システム管理者やアプリケ…
週5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外シンガポール |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・C#・Linux・Apache… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】コ…
既存のコンシューマ向けスマホアプリ開発業務におけるディレクション業務全般をメインに行なっていただきま…
週5日
410,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
下記業務をご担当いただく想定です。 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・製造 ・単体テス…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・VB.NET・SQL | |
定番
【リモート相談可 / GCP / 週5日】…
ゲーム会社が開発/運営しているスマホアプリゲーム用のインフラ環境の運用監視業務、ログ解析やアラートに…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
商品、在庫管理等を行うシステムの再構築。 開発はオフショアを利用するため設計書の作成・変更及びPG…
週3日・4日・5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 神奈川天王町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
音楽及び映像ソフトの企画・制作、発売及びプロモーションアーティストのマネージメントを展開している会社…
週3日・4日・5日
240,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【RPA / 週5日】通信キャリア向け業務…
・通信事業者の業務効率化におけるRPA、AIサービス導入支援 ・某通信キャリア、工事業者、資材業者…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・生命保険会社におけるインターネット保全手続きのバックオフィス用Webシステム開発 ・オンライン・…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
SNS・WEBプロモーション、R&D開発、イベント企画、ブランディングや地域プロモーションなどの、企…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Laravel/Vue /…
・要件・仕様レビュー・コードレビューを通じた品質管理 ・開発チームの生産性を向上するための提案 …
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】We…
・PHPを使ったCMSプラグインの開発・実装 ・Webアニメーションのコーディング ・外部API…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅、恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
プログラミングスクールにおけるシステムの保守運用をお任せいたします。 ・サービスサイトの保守業務お…
週4日・5日
740,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Nest.js・Next.js… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
テックリードとして(希望されマッチする場合、将来的なVPoE・CTOポジション含め)活躍される方を募…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Laravel・V… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】プ…
(今後開発するPDT含む)社内全プロダクトに関するデザイン、UI/UXの責任者です。 ・既存事…
週3日
290,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【Objective-C / 週4日】土地…
社内システムに関わる業務全般に携わっていただきます。 ・社内で使用するアプリケーション開発のマネジ…
週4日・5日
520,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Ob-C・事業会社内におけるIT化の推進、ITを駆使… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国のデ…
国の案件ですが、かっちり決まった仕様があるわけでなく、変化に柔軟に対応する必要があります。 ・少数…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国のデ…
国の案件ですが、かっちり決まった仕様があるわけでなく、変化に柔軟に対応する必要があります。 ・少数…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
地方創生を支援するプラットフォームを担う社会貢献型企業を目指している会社です。 今回は、新規の…
週5日
150,000〜250,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸上本町 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
・主に自社のフロントエンド開発(React .js、Vue.js) ・ビジネス要件を踏まえた最適な…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週5…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【Java / 週5日】流通系システム運用…
運用保守業務をご担当いただきます。 ・日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・Shell | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
流通業者のアクワイアリング事業のエンハンス支援を実施するPMO。 複数のステークホルダーやベンダー…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【.Net / 週3日〜】大手自動車メーカ…
システムの脆弱性に対応するため、セキュリティ対策の一環として、古いOS/ミドルウェア等のサーバー環境…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・.Net | |
注目
【マーケター】HRtechベンチャーでのマ…
人材派遣業向けクラウド管理システム(SaaS)におけるマーケティング業務をご担当いただきます。 …
週1日・2日
160,000〜220,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOマーケター(上流) |
| GoogleAnalytics・GoogleSear… | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週3日〜…
企画・デザイナーと密に意思疎通を図りながら、iOSアプリの開発業務全般を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
弊社では家庭用ゲーム機での長年のハイエンドゲーム開発やゲームエンジン開発の経験を元に、各企業様のニー…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・ブループリント・C++・Unreal・E… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
弊社では家庭用ゲーム機での長年のハイエンドゲーム開発やゲームエンジン開発の経験を元に、各企業様のニー…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | 3Dグラフィックスエンジニア |
| C・C++・ブループリント・C++・Unreal・E… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
自社ツールのサーバーサイド開発と配信サーバーを開発していただきます。 高いトラフィック且つ低レ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級のランニングポータルサイトのスマートフォンアプリの開発業務を行っていただきます。 エン…
週5日
410,000〜950,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin・Ma… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
日本最大級のランニングポータルサイトの開発業務を行っていただきます。 エンジニアの方より新機能の…
週5日
630,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Node.js・AWS | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・オンラインプログラミング教材を作成するための業務支援 ツールの開発・運用 ・教材の直接作成ではな…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】人材業…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
自社マッチングアプリの開発に携わっていただきます。 資金調達を行ってサービスを加速させるフェーズで…
週3日・4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・ionic・Ang… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
- 新規プロジェクトの工数見積もり,設計,開発 - 各種ツール・フレームワークの選定 - HTM…
週3日・4日・5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Swift/Android…
最長1週間分のオリジナル献立自動作成アプリのリニューアルを担当頂くアプリエンジニアを募集しています。…
週4日・5日
300,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
ロールプレイングゲームのような壮大なストーリーの中で、従来の学習コンテンツとは全く異なる、ケ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・Sket… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
若い世代やひとり暮らしの方のための新しいホームセキュリティのサービス提供をしています。 今回は…
週3日・4日・5日
240,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
某ショッピングサイトなどへ出品を行う会社様向けの、在庫管理システムの改修をお願いしたいと考えておりま…
週4日・5日
350,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
賃貸管理会社様のためのスマートホームプラットフォームを運営しております。 UIUX改善提案やウェブ…
週3日・4日・5日
240,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
WEBサービスの企画・設計・開発・運用業務やサイトの改善・改修 新サービス開発プロジェクトにおける…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
出張撮影マッチングサービスの設計・開発・運用を行っていただきます。 ユーザーが自身のニーズに合った…
週3日・4日・5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
フロントエンド開発をリードしていただきます。 デザインを構築・設計だけではなく、企画立案の段階から…
週3日・4日・5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週4…
自社が運営しているWebサービスのWEBサイト、スマホアプリ等のデザイン全般をご担当いただきます。 …
週4日・5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
サイトリニューアルにおいてのUI設計及びUIデザイン(PC/SP) 具体的には、ディレクターのもと…
週4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / React / 週5日】自…
当社が運営するサービスに関するフロント開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービスにおける…
週5日
580,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
Web サービスの運用、及び新規開発に関わる HTML・CSS・JavaScript の設計・実装業…
週4日・5日
480,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
住生活プラットフォームサービスの開発を募集しています。 クラウド入居者管理システムを中心に、バック…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
ITを活用した食の流通プラットフォームを構築しています。 新規サービスの開発も進んでいてフリーラン…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
• ビジュアルデザイン(ランディングページ、バナーのデザイン) • UIデザイン(動的ページ、機能…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿宝町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Android / 週5日】業務用帳票作…
受託開発案件に携わっていただきます。 現在募集している案件は、業務用帳簿作成アプリのエンジニアです…
週5日
350,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
当社運営メディアのデザイン関連作業全般 ・グラフィック制作(タイトル、バナー、ボタン、フレーム、そ…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿江戸川橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【PMO / 週5日】国際送金会社における…
次期国際送金システムの開発および既存システムの改修に係るPMO業務を担っていただける方を募集します。…
週5日
830,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社システム…
・要件定義~リリースまでのPM業務 ・外部ベンダー、提携先との調整 ・上申資料の作成等
週5日
550,000〜1,150,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】新規顧客獲得施策の検討…
・アライアンス企業との調整(日程、制作物等) ・アライアンス企業とのマーケ施策議論、調整 ・We…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
自社で新規に開発している、マッチングアプリの開発に携わっていただきます。 勤務時間に指定はなく、リ…
週3日・4日・5日
280,000〜780,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木1丁目駅、神谷町駅、六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
幼稚園・保育園向け写真販売システム、および本サービスに関連する新プロダクトの開発業務をお任せいたしま…
週4日・5日
480,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社事務統括…
・ネット証券会社における業務改善に向けた企画検討支援 ・新業務構築に向けた整理、ヒアリング等 ・…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】製造業_情報システム部…
お客様の情報システム部門の業務支援となります。 ユーザ企業側PMとしてITインフラ導入PJ推進、ベ…
週5日
620,000〜1,330,000円/月
| 場所 | 品川六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】製造業_情報システム部…
お客様の情報システム部門の業務支援となります。 情報システム部門は東京都内(品川区)にもあり、基本…
週5日
620,000〜1,330,000円/月
| 場所 | 品川六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / LaravelPHP / …
自社サービスの各種ポータルサイトの開発を行っていただくエンジニアを募集しております。 ユーザー…
週3日・4日・5日
310,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・LaravelPHP | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】アプリ…
メーカーにおいて現在、EOSに伴うインフラ部分(サーバー、VMware、ストレージ、NW等)と既存ア…
週5日
500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新富町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザイン全般をお任せします。 -コーポレイトサイトデザイン -UI/UXデザイン -LPのデザ…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
予約困難店に特化した飲食店とお客様をつなぐ予約サービスの開発をご担当いただきます。 飲食業界におい…
週3日・4日・5日
500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
急成長サービスの開発メンバーとして、 機能検討・設計・開発手法の導入など裁量を持ちながらサービスの成…
週4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Yii・※新規ではLaravelを検討中 | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
300%成長を実現した急成長サービスの開発メンバーとして、機能検討・UIUXデザインの検討から実装ま…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
WebやモバイルアプリのUI/UXの設計やデザインを行っていただきます。 UI改善や新規機能のブ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
デザインを構築・設計だけではなく、企画立案の段階から参加し、デザイナーやサービス運用チームと協力しな…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
弊社は企業の広報担当者を育成するサービスを展開していますが、この度サブスクリプション型ITビジネスを…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
Linuxサーバー、Windowsサーバー、VMwareなどの仮想化、ネットワークなどの複数案件がご…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
iPhoneを管理するシステムをお客様へ提供していますが、このシステムの改修や拡張部分の新規開発を実…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Swift | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
デザインを構築・設計だけではなく、企画立案の段階から参加し、デザイナーやサービス運用チームと協力しな…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
【データアナリスト】最新技術を用いたファン…
【企業概要】 NFT・ブロックチェーンの技術を応用し、アニメや漫画などのIPタイトルのファンコミュ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・R・BigQuery・Explorat… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
出張撮影マッチングサービスの設計・開発・運用を行っていただきます。 ユーザーが自身のニーズに合った…
週3日・4日・5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週5…
新規サービスの開発を行いながらも、必要に応じて既存サービスの機能追加などにかかわって頂く可能性も御座…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバエンジニア |
| JavaScript・Scala・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
- API/サーバーサイド開発を主にGo言語を用いて行っていただきます。 - 希望に応じてTyp…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS | |
メタバースPJ立ち上げをリードするディレク…
【企業概要】 NFT・ブロックチェーンの技術を応用し、アニメや漫画などのIPタイトルのファンコミュ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー/ディレクター |
定番
【AndroidJava / 週5日】An…
某ネット系企業サービス開発/通信キャリアのAndroidエンジニアをご担当いただきます。 ・P…
週5日
390,000〜1,490,000円/月
| 場所 | 品川浜松町または桜木町 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【AndroidJava / 週5日】ロボ…
新規アプリ企画の為のPoC(概念実証) アプリ開発、アプリ品質改善の為の技術調査/調整、技術観点での…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【AndroidJava / 週5日】キャ…
キャリア向けAndroidアプリ開発に携わっていただきます。 キャリアが展開する主力サービスのスマ…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
既存の複数ECモールへの出品及び在庫管理システムの改修。 PHP主体ですが連動システムがJavaで…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷・表参道駅または五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【Java / 週5日】電子書籍取次システ…
グループ会社数社でそれぞれ所持しているシステムの統合プロジェクトです。 主にシステム間連携に関する…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋竹橋駅または神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
IoTプラットフォーム上に、各IoTサービスから呼ばれるWebAPIの設計、開発に携わっていただきま…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【PHP / 週5日】キャリア向けアプリに…
次期エージェントアプリにおけるサーバサイド開発に携わっていただきます。 顧客からの要望を整理し、必…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【PHP / 週5日】キャリア向けアプリに…
次期エージェントアプリにおけるサーバサイド開発におけるPMO業務です。 開発上流工程に対する業務進…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| PHP | |
定番
【PM / 週5日】新規ロボット開発推進P…
開発パートナー会社のコミュニケーション窓口(メール/電話等)、開発パートナーとのアクションアイテム管…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【UI/UX / 週5日】自社サービススマ…
・自社サービスのスマートフォン向けwebデザイン・コーディングです。 ※サービス自体はスマートフォ…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
医師専用コミュニティサービスの継続開発になります。 地域医療に関わるサービスとなっており社会貢献性…
週5日
550,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Express… | |
定番
【フルリモ / フルスタック/ 週2日〜】…
【担当業務】 ・債権回収最適化SaaSの開発業務 ・フロントエンドからバックエンドまで幅広く携わ…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・・ | |
定番
【広告×AI事業】クリエイティブデザイナー
<具体的な業務内容> ・ ユーザーインサイトに基づいたLINEチャットボットのクリエイティブ制作 …
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | クリエイティブデザイナー/ディレクター |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社ECサイト、マッチングサイトを展開する企業のクリエイティブユニットにて、自社サービスで培ったUI…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
オンラインプログラミング教材を作成するための業務支援 ツールの開発・運用をお願いします。 教材を直…
週4日・5日
500,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js・React.j… | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
大手通信会社向けのシステム開発・保守案件でiOSエンジニアを募集しています。 ※Android開発…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
ブランドプリペイドカードのアプリ開発を担当していただきます。 バックエンドエンジニアと共同でAPI…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・PHP/Laravelを使用したWebアプリケーション開発、API開発 ・アプリケーション要件に…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・TypeScript・Rea… | |
定番
【PM/EM候補|週4日~】自社印刷事業に…
【案件概要】 弊社印刷事業部において既存もしくは新規のプロダクト開発のリードをしていただける方を募…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby | |
定番
PM
- 各ステークホルダーへのヒアリングをもとにした、プロダクトロードマップの策定 - プロダクトビジ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ー | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週5…
自社広告配信プロダクトにて使用する、ターゲティングデータ管理システムのリニューアルをご担当いただきま…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Rails・Sinatra・F… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社ITコンサルタントとともに、クライアント先の業務システムの受託開発を要件定義から行っていくリード…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週5…
Microsoftの各種ソリューションをクライアント企業に提案・構築支援を行っていくMicrosof…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
ECショップ構築ASPサービスや、その他自社システムの開発・改修をお任せします。 各システムについ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・インプット情報… HTML、ワイヤー(PPTで作成) ・インプット情報から、Bootstrapを…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ハイエンドファッションブランドのECサイトのWebデザイン開発に携わることができます。 多国籍なメ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿信濃町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ハイエンドファッションブランドの公式ECサイトの開発に携わることができます。 多国籍なメンバーが在…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿信濃町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】部門…
当社は、急拡大中のインターネット広告業界の中でも特に注目されているベンチャー企業です。 今回ご…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
独自サービスである電力及びガスの小売り事業支援サービスにおける、開発・運用・保守を担当していただきま…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
上位社員2名と同じサーバ基盤が担当しているシステムの基盤維持チームでの要員を1名募集しております。 …
週5日
200,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| UNIX・Linux・ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
クラウドソーシングサービスをより使いやすく、 より便利にするための機能開発や新サービスの開発における…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
求人媒体のフロントエンド開発 HTMLによるコンテンツのマークアップやCSSを使用したスタイリング…
週3日・4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
新規ライフサイエンス系サービスのソフトウェア開発業務をご担当いただきます。 開発要件に基づいたソフ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / SRE / 週3日〜】Pa…
・Goで書かれた、大規模なリクエストを受け取るアプリケーションの追加開発 ・各種システムの監視 …
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
生損保Webシステム新規開発プロジェクトメンバー募集となります。 要件定義が終了したサブシステ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / RPA / 週5日】…
大手小売業様向けにRPAの事業支援をしていただきます。 現在元請会社より3名客先オフィスに駐在し、…
週5日
590,000〜780,000円/月
| 場所 | 神奈川大船駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
キャリアが提供している各アプリケーションに関する技術支援業務です。 OSのバージョンアップ時にOS…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・- | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
電子マネーシステム開発のPM業務です。 クライアントとの要件定義打ち合わせ、要件定義書の作成、開発…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
フリーランスの方が抱える様々な課題に対して複数のソリューションを展開していくことで、個人が会社機能を…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・nodejs | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
モーショングラフィックスとグラフィックデザインを駆使して、 会場を演出するプロジェクションマッピング…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週3…
弊社では、著名な芸能人からファンに対してテレビ電話を掛けることができ、 その様子をライブ配信できる…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala | |
定番
【リモート相談可 /サーバーサイド / 週…
オンラインカジノの市場において、 データマイニングは売り上げに直結するため、 単純なデータ解析ではな…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野毛駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
概念モデルの要件定義後のER化をご担当いただきます。 作業としては、下記を想定しております。 ・…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デバイスからスマホアプリ、Webサービスなど、一気通貫で開発・提供しています。 全社横断的にビ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・Vue.js・React.js | |
定番
【リモート相談可 / BigQuery /…
Google Cloud Platformパートナー企業にてプライム案件における下記を行っていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| BigQuery・RDB・GCP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
Google Cloud Platformパートナー企業にてプライム案件における下記を行っていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Java・Go・BigQuery・RDB・GCP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
CMSにおける新機能の開発をご担当いただきます。 具体的には、 ・AWS/GCP/Azure…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| PHP・C# | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】クリ…
サービス拡大により新たなプラットフォームの構築を検討しています。 プラットフォームに必要な機能の設…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外久屋大通駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / サーバサイド / 週4日〜…
サービス拡大により新たなプラットフォームの構築を検討しています。 プラットフォームに必要な機能の設…
週4日・5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 東京23区以外久屋大通駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では企業のデジタルマーケティングを支援していくために自社運営メディアを用いて企業の課題を解決して…
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
Linuxサーバー、Windowsサーバー、VMwareなどの仮想化、ネットワークなどの複数案件がご…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京上野駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
事業の急成長に伴い、一緒に次世代の宿泊サービスを創るフロントエンドエンジニアを募集しています。 …
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Angular.js・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
サービス本体の開発に加え、サービス運営に必要な管理画面など各種プロダクトのサーバーサイド開発を担当し…
週4日・5日
750,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
飲食業界に特化したBtoBプラットフォームを提供。 現在はプラットフォーム内で複数サービスを開発・運…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
サイトリニューアルにおいてのUI設計及びUIデザイン(PC/SP)を依頼します。 具体的にはディレ…
週4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
サイトリニューアルにおいてのUI設計及びUIデザイン(PC/SP) 具体的にはディレクターの下、外…
週4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
フリーランスの方が抱える様々な課題に対して複数のソリューションを展開していくことで、個人が会社機能を…
週3日・4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】イ…
通信キャリア案件におけるプロジェクトマネジメント業務をお願いいたします。 インフラ専門のプライムベ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 千葉幕張駅/海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【UNIX / 週3日〜】流通系システム運…
・運用保守 日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う (店舗定型作業、本番稼…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・COBOL・Shell | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
大手企業様の案件でして、IoT機器からデータを取得してブラウザ上に表示するようなWEBシステムになり…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】サポート…
都道府県民割キャンペーンをはじめとする事業のカスタマーサポート、およびシステム保守のマネジメント業務…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】宿泊施設…
本求人では、この新規提供システムの企画・開発・事業立ち上げを社長と共に行うリーダー候補を募集していま…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】宿泊予約…
本求人では、このCRSを企画・開発するプロジェクトリーダー候補を募集しています。 ・対象システムの…
週5日
670,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
上位社員2名と同じサーバ基盤が担当しているシステムの基盤維持チームでの要員を1名募集しております。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川泉岳寺 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| UNIX・Linux | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】帳票OC…
・顧客要件に応じたOCR製品のカスタマイズ ・製品に関する問い合わせ対応 ・プロジェクト内部の開…
週5日
350,000〜520,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
マーケティング組織でのデザイン業務を担っていただける方を募集します。 SNS広告に関連するLP、バ…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【マーケター|フルリモート・正社員切り替え…
【案件概要】 スタートアップ・ベンチャー企業をメインターゲットとしたToB・ToC向けSaaSやサ…
週5日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
大手電機メーカーG企業にて、新規サービス開発 メンバーは4名 (PL1名、エンジニア3名。) …
週5日
480,000〜1,280,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
大手電機メーカーにて、新規サービス開発です。 メンバーは4名 (PL1名、エンジニア3名。) …
週3日・4日
590,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
「婚活」「妊娠・出産・育児」サービス領域で、エンジニアが身近にいる環境で、協力しながらアプリのUIデ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
コンセプトとしては個人がいつでも抜けられるチーム作りでありかつ、ジョインしやすいチームでもある仕組み…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・FIGMA | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
「婚活」「妊娠・出産・育児」サービス領域で、エンジニアが身近にいる環境で、協力しながらアプリのUIデ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
知的財産管理システムの新規開発案件です。 RDB→グラフデータベースを利用するにあたり、データエン…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・– | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
自社開発提供を行うDMPのダッシュボード開発をご担当いただきます。 同社では国内最大級の質・量を誇…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Rails・… | |
定番
【Kubernetes】自社システムのKu…
1プロダクト2000人を超える規模の開発者が利用するサービスがEC2で稼働しています。今後、更なる負…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島平駅 |
|---|---|
| 役割 | Kubernetesエンジニア |
| Kubernetes・ | |
定番
ペットテック業界で活躍するプロジェクトマネ…
サービスの方向性や施策の優先順位などを決めて、 グロースさせる事業責任者を募集しています。
週3日・4日・5日
2〜2.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
ペットテック業界で活躍するインフラエンジニ…
・AWSを用いた設計、構築、運用 ・IaCを用いたインフラの構築 ・コンテナ技術を用いたシステム…
週1日・2日・3日・4日
2〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
【Scalaエンジニア】BtoC向けSNS…
・開発内容: 今回、BtoC向けSNSサービスの開発をお願いします。 ・依頼工程: 詳細設…
週5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Scala | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社のクラウド営業支援ツールの新規機能開発や、運用、周辺開発を担っていただきます。 業務内容と…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Cake・PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
顧客から受注したWebサイトの制作などをメインで行って頂きます。 メインビジュアルの制作からコーデ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
現在企画中の、ビックデータと機械学習を活用したサービス(BtoB、社内向け)をご担当いただきます。 …
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
受託でWEBサイトやアプリのデザインを行う企業様のWEBデザイナーを担当していただきます。 WEB…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
Google Cloud Platform上で構築された旅行代理店を管理するシステムのリプレイス案件…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Python/Go …
自律移動型ロボットを開発している企業様におきまして、画像処理・音声処理を主に担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| JavaScript・Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
自社で開発をしているSCMシステムのiOSアプリの開発を主にご担当いただきます。 開発の実装は以下…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
交通機関の情報比較サイト等、複数のWebサイトを運営しております。 ご参画後は、サイト上の文言や数…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
今回は機械翻訳Web アプリケーションの開発業務を全般的にご担当頂きます。 また、本事業の案件に関…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Perl | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 今回は独自映像技術を…
週4日・5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
エンタメ×映像領域で最先端のテクノロジー活用したプロダクトを開発するスタートアップです。 特殊映像…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
これまで、制作は外部への委託がメインでしたが、この度内製化を目指して、エンジニア様を募集しております…
週4日・5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ECサイトのコンサルティングから制作、運用まで一気通貫でサポートするサービスを運営しています。 …
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
新規・既存開発案件のPHPエンジニアを募集しております。 新規サービスの開発が多いので1からプロジ…
週5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
自社サービスの制作がメイン。(一部受託も有) ・LP ・キャンペーンページ ・アイキャッチ・バ…
週3日・4日
180,000〜270,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・フロントエンド構築 ・基本的な業務は、HTML5、CSS3を使用したコーディングからWordPr…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby/PHP / 週4…
日々メディアにも掲載されrる業界No.1の注目度を誇る自社サービスでのバックエンド開発業務になります…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Go・Rails・Laravel・… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】W…
・大手製造メーカーのコーポレートサイトTOPページおよび企業情報カテゴリTOPページのリニューアル …
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川北品川 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
今回、事業案をもとにWebエンジニアとしてプロトタイプ開発及びプロダクトの改善に向けた追加開発/保守…
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】サ…
・プロダクトデザインチームや関連システムの開発チームメンバーとサービス開発を行う ・保守性/可読性…
週4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【Unity/C#】ゲーム開発エンジニア
・Unityを⽤いてゲームもしくはエンタメコンテンツの開発経験 ・C#での開発経験
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋池袋 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C#・Unity・Discord | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
新規・既存開発案件のPHPエンジニアを募集しております。 新規サービスの開発が多いので1からプロジ…
週5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社サービスの制作がメイン。(一部受託も有) ◇LP ◇キャンペーンページ ◇アイキャッチ・バ…
週3日・4日
180,000〜270,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】英語必須…
大手クライアントがマーケティング等で使用するSNSのマネジメントシステム開発のプロジェクトマネジメン…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日〜】…
自社サービスとしてモーションキャプチャ技術を応用したシステムの研究、設計、開発、販売行っています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
新規事業としてゲームのまとめサイトを運営しており、現在はデイリー十数万PVを誇っているメディアです。…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
受託している案件を新規又は途中から参画していただきます。 現在既存で行っているサービスとしては、大…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・PHP・Laravel | |
定番
【React.js】受託開発のフロントエン…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく 形になります。 現在既存で行っているサー…
週1日・2日・3日・4日・5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービスとし…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービスとし…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京都賀駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
ファッションを中心としたECサイトの運営を行っています。 現在ECサイトを含めたフロントエンド基盤…
週5日
480,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿若林駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】業…
弊社ITコンサルタントとともにクライアント先の業務システムの受託開発を、要件定義から行っていくリード…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社ITコンサルタントとともにクライアント先の業務システムの受託開発を、要件定義から行っていくリード…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
現在弊社上位様メンバーが参画しているリプレース案件の増員となります。 ・複数システムのデータ統合に…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
お任せするお仕事は、主に自社サイトの開発/保守/運用が中心になります。 また、新たにスマホアプリの…
週5日
240,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】国内…
採用支援Webサービスのインフラエンジニア業務をお任せいたします。AWSのフルクラウドの環境になりま…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・LINUX | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手消費財メーカーやサービス事業者などに対してのCRMソリューションプラットフォームのモジュール開発…
週3日・4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】要件定…
創業以来、Webプランニング力、技術力を武器に、様々な大手クライアントのデジタル施策の企画から制作・…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】自社開発…
今までのpython, go などの知識を用いたサーバーサイドのテクノロジーだけではなく、solid…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Python・Java・Go・Node.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】決済…
あらゆる業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)化の影響により、当社の独自サービスの需要…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
すべての人に、いつまでも健康で美しく生きるための商品・サービスを提供している企業です。 今回は、自…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】インフ…
これまで役員がプロジェクトマネージャとして全体をマネジメントしてきましたが、プロジェクトが大きくなっ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社にて開発・運用されているゲームタイトルのキャラクターから背景まで一枚のイラストをご担当いただきま…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
| HTML・CSS・‐ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
求人サイト開発を設計~運用保守までお願いいたします。 長期的に就業いただける方を希望します。 日…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
お仕事内容としては、新規のリプレイス開発のみならず、既存のプロダクトの開発も担って頂く可能性がござい…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
AIを活用した橋梁の内部鋼材破断を検知する非破壊検査ソリューション開発プロジェクトにおけるフロントエ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
バーチャルタレントと1:1のビデオチャットで疑似恋愛が楽しめるサービスのサーバーサイドの開発。 ・…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Go・T… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
請求書等の集計作業の自動化 PDF化した請求書をOCR読み取りし、AIを使い抽出したテキストを各項…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西武新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
大手電機メーカー企業にて、新規サービスの開発を行っております。 今回は、Railsでのバックエンド…
週3日・4日・5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / JQuery / 週…
弊社では、コンサルからWEBメディアまで幅広い業務を行っています。 デザインからコーディングまでお…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・JQ… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
独自のバイオセンシング技術を使って取得される時系列の身体データを解析することで、新たな価値を生み出し…
週3日・4日・5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
物流販売を行う会社です。 スプレッドシートにて配送状況を管理していましたが、システム化し管理できる…
週3日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
医療機関向けに展開している、自社サービスアプリに携わっていただきます。 Vue.jsでの開発をお願…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
・アプリケーション企画の為のPOCアプリ開発 ・品質改善の為の技術調査 ・リリース済みのロボット…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
新規番組情報入力画面、APIの開発の開発をお願いしたいです。 今回はreact/mobxが通信する…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅、築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社で運営しているWebサービスのWEBサイト、スマホアプリ等のデザイン全般、ランディングページ制作…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
新サービスやARライブ配信の新規サービスを提供予定しております。 ・バーチャル配信系の新規サ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・現行システム保守開発対応 ・改修要件の確認と設計、開発テスト、リリースまで対応 ※不明瞭な…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】コン…
今回は、大手人材コンサルティング企業向けの受発注システムの開発に設計~製造~テストまで対応していただ…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Zend・Framew… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
eコマース総合支援会社にて、 ECサイトのデザインをはじめ、ランディングページやバナーデザインに携わ…
週3日・4日・5日
150,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】S…
某大手ITコンサルティングファームの品質管理チームにメンバーとして入り、納品物のチェックをしていただ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
潜在的な顧客に対する需要喚起や新たな価値提案を目的としたクリエイティブ企画・制作に取り組みます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅、東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
①PoC(要件検証)の実装サポート ②プロダクトのベータ版のデザイン 弊社では社労士などを…
週3日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 池袋巣鴨駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / SDK / 週3日〜】倉庫…
RFIDを用いた倉庫管理システムの構築を行っております。 RFID端末とスマートフォン間アプリのA…
週3日・4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿岩槻駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
生産・販売業務(見積、契約、発注、仕入・倉庫搬入、出荷、売上請求、その他)を管理する基幹システム一部…
週5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川三田駅or赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
弊社で提供するサービス/プロダクトの新機能開発や既存機能の改修を中心として、企画/設計/開発/運用…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】オ…
ゲームセンターのクレーンゲーム機をスマホやPCから遠隔で操作し、景品を獲得したら自宅に景品を配送する…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ゲームセンターのクレーンゲーム機をスマホやPCから遠隔で操作し、景品を獲得したら自宅に景品を配送する…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
これまで数々のヒットアプリを生み出してきた弊社で開発中の新規タイトルを担当いただきます。 【サ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
要件定義や設計書作成などの上流工程や開発メンバーのマネジメント、コードレビューをお任せできる方を募集…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
当社自社プロダクト(競馬予測AIサービス)の運用保守、改善対応業務を担っていただける方を募集します。…
週5日
450,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
お客様のWEBシステムから画像を取得し、弊社のAI結果をレスポンスするAPIを設計・開発を行います。…
週5日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
物流に特化したビジネスを展開している当社。 こちらで改修などを行ってくださるコーダーの方を募集して…
週3日・4日・5日
160,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Webサイト制作では 不動産関連サイトやコーポレートサイト、 ネット広告などのサイト制作を中心に行っ…
週5日
160,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / SaaS / 週3日…
社内業務改善をお願いできる方を探しています。 salesforceの連携やフロー整理・最適化などP…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
ブロックチェーンのソーシャルネットワークプロジェクトへ参画していただきます。 サービスのスマホアプ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
バーチャル疑似恋愛サービスを運営しております。 アプリにて展開されているマッチングサービスと同…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】業…
①PoC(要件検証)の実装サポート ②プロダクトのベータ版の開発 具体的には新サービスβ版リ…
週3日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Node.js・gola… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
人材データの収集・解析を行うWebアプリケーションの開発です。 今回の募集瀬は、人材領域に関する社…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・SQL・React・… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
実際の現場経験のあるメンバーがいる強みを活かし、 建物メンテナンスに関する総合ITシステム開発を推し…
週4日・5日
2.4〜6.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿麴町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
処方箋のネット受付やお薬の宅配予約等を行えるサービスのデザインを担当いただく予定です。 同社は…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
Webサービス、アプリのUIデザインやランディングページデザインをお願いいたします。 サービス全般…
週5日
30,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / ハードウェア / 週5日】…
電子回路関連の設計や品質管理、プロダクト化などの開発業務から、仕入れ業者とのやり取りやソフトウェアエ…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python/Go …
SREを担うメンバーとしてインフラ構築・運用・自動化や障害対応を行っていただきます。 また継続…
週4日・5日
660,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 秋葉原人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Go・GIN | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
本アプリは様々な事業部のサービスをアグリゲートするため、各サービスのビジネス要件を吸収し、お客様体系…
週3日・4日
530,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
インターネットを活用したライブ授業を無料で配信しています。 60万人以上の中・高校生の勉強をサポー…
週3日
250,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】新…
保険会社が新しく作ろうとしている新システムの企画/要件定義/設計をお任せします。 開発・実装の部分…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】社…
・業務効率改善、サービス改善のための技術的調査、検証、導入、RPA基盤の構築 ・Rails, AW…
週3日・4日・5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
・既存の複数ECモールへの在庫管理システムの改修及びPMO ・既存のEC出品、在庫管理システム、業…
週5日
550,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| PHP・Linux | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
自社開発のスマートロックデバイスの開発チームに加わって頂き、製品の企画から量産に至るまでの様々なフェ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 組込みエンジニア |
| C・C++・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】Saa…
弊社の提供するSaaSサービスの再構築及びオプションサービスの開発に携わっていただきます。 こ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】S…
SaaSサービスの再構築及びオプションサービスの開発に携わっていただきます。 ネットワーク・仮想化…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
AIを使用した分析サービスの開発 (今後規模を拡大していくためのプロトタイプを現状開発中) …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小杉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【kotlin / 週5日】大手放送事業会…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
サイトの改善・改修 WEBサービスの企画・設計・開発・運用業務 新サービス開発プロジェクトに…
週4日・5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
現在企画中の、ビックデータと機械学習を活用したサービス(BtoB、社内向け)の開発を担当いただきます…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Ruby・Rea… | |
定番
【フルリモ / AI / 週5日】データを…
株式会社レッジではAI・データを用いたシステム・サービスの設計と開発運用業務を行っています。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】グル…
弊社のサービスを確固たるものにし、食のプラットフォームを構築したいと思っております。 またその他E…
週3日・4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿落合駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・EC… | |
定番
【Linux / 週5日】ミドルウェア構築
サーバとミドルウェアの構築をお願いいたします。(ネットワーク構築はありません) ・環境構築 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Python / 週5日】機械学習エン…
クラウドサービス、機械学習、エッジデバイス関連の数年先の技術シーズ、トレンドの把握を目的とした技術調…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・AWS・GCP | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週4日〜】…
自社物流プラットフォームサービスのQA(品質管理・品質保証)に関係する業務 ・プロダクトリリー…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
現在、自社で仮想通貨のポイントキャッシュバックアプリを開発しており、そのUI/UXデザインを担ってい…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【UI/UX / 週3日〜】自社駐車場管理…
車両ナンバー認証カメラで車をデジタル管理することを特徴とする自社駐車場管理システムを自社で開発し、運…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
コンテンツ管理システムの実装を担当いただきます。 ・基本既存を踏襲するため、キャッチアップが必要と…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby | |
定番
【C/C++ / 週5日】業務システムの運…
・ヘルプデスク業務 ・運用管理業務 (データベース管理、稼動監視、セキュリティパッチ適応、ジョ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿霞ヶ関駅、虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET | |
定番
【C/C++ / 週5日】業務システムの運…
・ヘルプデスク業務 ・運用管理業務 (データベース管理、稼動監視、セキュリティパッチ適応、ジョ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿霞ヶ関駅、虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週5日…
・ネイティブアプリ版の開発 ・既存アプリの改善を目的としたアップデート ・新規アプリケーションの…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
社内の運用担当者からの要望を受けたデザイン・機能要件を備えた、フロントエンドデザイン、コーディングを…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外不問(シンガポール) |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Bo… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
FXの顧客向けバックエンドシステム、決済システム(顧客管理・トレーディング管理・入金出金等) ・資…
週5日
280,000〜850,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【HTML/CSS / 週3日】自社の広報…
自社で人材管理ツールの開発、企業様に提供を行っております。 今回は自社の広報、採用に関わるデザイナ…
週3日
20,000〜370,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Java / 週5日】オンラインショップ…
オンラインショップシステムのリプレースに伴い、新システムの運用設計をお願いいたします。 (障害対応…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【NW / 週5日】社内ネットワークの各種…
社内ネットワークを担当する部門にて、各種運用・管理から再構築プロジェクトまでお任せ致します。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【PHP / 週5日】業務アプリを用いたオ…
業務アプリを用いたオークションシステムのサーバリプレイス作業、およびリプレイス後のEC在庫管理システ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【グラフィック / 週5日】自社不動産サー…
オフラインツール(ポスター、ロゴ、サイン、チラシ、POPツール、ノボリ、ノベルティなど)主に紙媒体の…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【サーバ運用オペレーター|フルリモート|シ…
【概要】 当グループ会社のお客様が利用するアプリケーションの動作や、各種ツール、Webサービスの環…
週4日・5日
250,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Li… | |
定番
【リモート相談可 / Swift/kotl…
・Xcode/AndroidStudioによるアプリケーションの開発 ・スマートフォンアプリ、xR…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Swift / 週5日】大手放送事業会社…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【インフラエンジニア|フルリモート】WEB…
【概要】 当グループ並びに、当グループ関連会社で手がける、WEBサービスのネットワーク、サーバー、…
週5日
250,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Li… | |
定番
【3DCGデザイナー歓迎!フルリモ】人気ア…
人気アイドル系IPタイトルのクリエイティブの進行管理を担当していただきます。 ・発注資料のチェック…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | 【ゲーム系案件】事業責任者 or クリエイティブディレクター or 2Dデザイナー ※募集枠作成していないのでこちらにマッチングお願いします |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
①CentOSによる業務環境構築全般 ②Oracle、PostgresQL、MariaDB等でのD…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・鍼灸院検索サイトや鍼灸院経営基幹システムの開発・運営および新規サービスの立ち上げ、開発、構築 ・…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
スタートアップを中心として製品開発の0→1の受託開発を行っていただきます。 主にスマホアプリの開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・J… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
スタートアップを中心とした製品開発で上流工程をメインに受託開発を行っていただきます。 案件が複数あ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
スタートアップの受託案件を中心としたデザインを行っていただきます。 主にUI/UXデザイナーやディ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
アニメのセル画やマンガの絵など、デジタルのアートの所有権をブロックチェーンに載せて、売買できるサービ…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
・Androidアプリケーションの新機能設計・開発および機能改善 ・プロダクトマネージャーやデザイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
社内システムの既存システム、新規システムの運用を行っていただきます。 ・日々の提携業務 ・運用業…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
社内で複数プロジェクト走っており、ご自身の興味範囲や志向性、スキルセットに応じてアサインする案件が決…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・django | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
アルバイト採用のコミュニケーションを変革すべく誕生した、おしゃれなバイト探しメディアの開発・メンテナ…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
今後サービスをグロースしていく上でWebディレクターとして、サービスの改善・新規機能の追加など、日々…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Typescript・vue.js・mysq… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
クライアント企業から受託案件になります。 既存サーバーからAWS置き換えにあたり、 ・インフラ設…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木多摩川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
現在社内にも正社員のデザイナーはいるのですが、お客様向けの制作をしていて、社内向けの制作人数を増員し…
週3日・4日
180,000〜270,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービス…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービス…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京都賀駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
ファッションを中心としたECサイトの運営を行っています。 現在ECサイトを含めたフロントエンド基盤…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿若林駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / セキュリティ / 週5日】…
国内最大級の人材紹介サービス事業を展開している企業様において、サイバーセキュリティグループのセキュリ…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日〜】…
健保組合の財務会計システムの開発へ参画していただき、実装を担当していただく方を募集しております。 …
週3日・4日・5日
1.6〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・.netFW | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
当社サービスのクライアントサイドWEBアプリケーション、ハイブリッドモバイルアプリケーション(iOS…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
「EC・顧客管理システムリプレイスプロジェクト支援」に情報システム部門の立場で関与いただきます。 …
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 / 馬喰町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
サーバーサイド開発が出来るエンジニアを募集します。 ・プログラミング ・システム設計書類の作…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 千葉柏駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
大人気ゲームの開発を担当していただきます。 HTML/CSS/JavaScriptによるゲーム…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【広告運用】大手広告代理店内の生命保険デジ…
大手広告代理店内の生命保険デジタル広告の営業業務 広告マーケター、ディレクション経験者を募集し…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター/ディレクション |
【Kotlin/Swift】タクシー向けア…
・タクシーアプリの機能追加開発業務 ・基本設計/詳細設計/実装業務 ・開発の進捗管理業務
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
【Go】動画配信サービスのアジャイル開発
・クライアントPOとの要件すり合わせや画面定義書作成/新規機能の設計 ・要件定義 ・機能設計書 …
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
【PM】大規模ISP/サービス基盤運用監視…
・大規模ISP/サービス基盤運用監視PJ ・グループリーダーとして既存PMの補佐をする ・課題発…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【Webデザイナー】広告向けクリエイティブ…
広告向けクリエイティブの作成 及び プランナーとの協働が主な業務になります。※クリエイティブは、静止…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
【Java】新規プロジェクトのPL支援
・新規案件の要件定義、設計から開発、検証
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ、UI/UXデザイナー、週4日〜…
■具体的な業務内容 医療領域のドメインスペシャリストなどのメンバーとともに患者(toC)・医療従事…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・Figma・XD | |
【NW】NW機器設定・パラメータ管理の上流…
・NW機器にAnsibleを使って自動設定+パラメータ管理するアプリの開発支援 ・設計、実装
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| SQL | |
定番
企画デザイナー
・2D CADの操作経験必須 ・デザイナーの実務経験をお持ちの方 ・グラフィックやプロダクトデザ…
週5日
220,000〜260,000円/月
| 場所 | 東北:仙台菊川 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
注目
【フルリモ|週5日】Webディレクター/リ…
【仕事内容】 ・自社サイトの運用保守・マーケティング・分析・集計・問い合わせ対応等の企画業務 ・…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 秋葉原東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー(マーケティング含む)【正社員切替案件】 |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / 3DCG / 週5日】3D…
・3Dソフトを使用した手付けアニメーション制作 ・外注対応(FB・調整等の連携対応) ・アニメー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・コンテンツの企画立案 ・Wordpressなどの管理ツールを使ったWEBサイトの更新・運用業務 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
ユーザー側に関しては、React、管理者画面に関しては、Angularを使用している為、フロントエン…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】リフ…
人事・社員に負担をかけず、低価格で質の高い候補者を採用するリファラルリクルーティングプラットフォーム…
週4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Go・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】運用タイ…
スマートフォン向けゲーム開発~運用UIデザイナーを募集しています。 既存タイトルの改修提案やレイア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社の各プロダクトが利用するバックエンドサービス(アカウント管理、プロダクト管理、認証基盤、オンライ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週4日〜】…
業務アプリからIoT、ゲーム、VR・ARまで幅広いプロジェクトに携わっていただきます。 ご参画いた…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
社内業務を統合する新システムのバックエンド開発をPHPを用いて行っていただきます。 社内用のシステ…
週3日・4日・5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
当社が請けているプロジェクトにてECサイト保守案件の担当をお任せいたします。 ECサイトの小規模エ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Seaser2 | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
設計・開発支援に携わっていただきます。 大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネス…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社モバイルアプリの開発・運用プラットフォームを通じて大手企業様のWebサービス、iPhone、An…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
今回は社内で保守運用を行っている、wordpressサイトのフロントエンドの保守・運用に携わっていた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにてデザイン業務に携わっていただ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
弊社の自社サービスの開発を行っていただきます。 AWS上に構築されサービスインしているWebアプリ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js/Rea…
- Webアプリやモバイルアプリのプロトタイプ(動くもの)製作 - 機械学習/深層学習技術を活用し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
Windows系業務アプリケーションの開発業務をお願いいたします。 スキルや経験によっては、要件定…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外日野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
各アプリケーションやデバイスとのつながりの中枢となる部分ですので、業務内容はサーバーサイド開発を中心…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
今回ご対応いただく主な業務として、 ・設計書を元にCMS内の検索・一覧表示・詳細表示 ・管理・編…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・VB.NET・.NET | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
金融・不動産系の企業様の決算説明会資料や株主総会資料をPowerPointで作っていただける方を募集…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋茗荷谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
自社モバイルアプリの開発・運用プラットフォームを通じて大手クライアントのWebサービス、iPhone…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
自社モバイルアプリの開発・運用プラットフォームを通じて大手クライアントのWebサービス、iPhone…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週3日〜…
弊社では短期間・短時間の仕事に特化し、柔軟な働き方を望む個人と必要な時に必要な分だけ人材を活用したい…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Kotlin・Go | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
コミュニケーションに特化した対話型AIを搭載した自社アプリの開発案件です。 クライアント企業の…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・C… | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
コミュニケーションに特化した対話型AIを搭載した自社アプリの開発案件です。 クライアント企業ア…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
アパレルのプラットフォームを展開しているクライアントにてデザイン業務を行っていただきます。 ベン…
週3日
140,000〜220,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
主に旅のオーディオガイドアプリ・WEBの提供を行っておりスマホでの観光地巡りをガイド(文化音声ガイド…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
複数の新規アプリケーションサービスを開発中でそちらのお手伝い頂けるエンジニアの方を探しています。 …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / wordpress …
今回は社内で保守運用を行っている、wordpressサイトのフロントエンドの保守・運用に携わっていた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【フロントエンドエンジニア】クラウド型電子…
・新規追加機能の設計、実装、テストを実施 ・現実装済み機能の改修作業
週5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・AWS・EC2・AurolaD… | |
【サーバーサイドエンジニア】クラウド型電子…
・クラウド型電子カルテシステム構築(追加機能開発) ・新規追加機能の設計、実装、テストを実施 ・…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・C#・AWS・EC2・Aurola… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
メイン業務は以下の通りです。 ・要件定義 ・基本設計 ・詳細設計 ・製造 ・単体テスト/結…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Springboot | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
プラットフォームのいずれかのプロダクト、もしくはプロダクト横断の課題を解決する開発を行っていただきま…
週3日・4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Java・G… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】WEBシ…
Drupal(多言語対応CMS)を使ったWebシステムの開発業務全般を行っていただきます。 全ての…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Python・Java・Typescript… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】大手会計…
デスクトップ向け会計ソフトウェアの設計~テストまでを担当いただきます。 外部設計書を基に、テス…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | テストエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby/Go / 週4日…
・AAIプラットフォームの機能拡張 ・AAIプラットフォームを活用した新サービス開発 ・レガシー…
週4日・5日
840,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【インフラ / 週5日】ネットバンク基幹シ…
非機能を中心としたインフラの要件定義~リリースまでを対応いただく予定です。 ベースとなるシステムの…
週5日
660,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有明駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JP1・Oracle | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
・サービスプロダクトの要件定義 (文章レベルでのやりたいことから、具体的な画面デザインや挙動等を整…
週4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
教育系DXを推進するSaasサービスの新規立ち上げに伴い、サーバーサイド構築をリードできるエンジニア…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Java / 週5日】Android機器…
開発中のAndroid機器の認識機能において、実際の事象がうまく測定できていない懸念があり調査をして…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
AIを活用した、サービス展開、開発をしているAIベンチャーです。 金融に関する社会課題を解決するプ…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Flutter・Django | |
定番
【Ruby / 週5日】BtoB/BtoC…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
フードデリバリーコンサルティング事業を展開する当社の運営する注文管理システム、情報サイトのインフラエ…
週3日・4日
260,000〜550,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / グラフィック / 週3日】…
アプリ内で商品を紹介するランディングページの作成を行っていただくデザイナーを募集しております。 コ…
週3日
110,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
お任せする仕事は、クライアント様より依頼を頂いているWebサイトの保守作業やWordPressによる…
週3日・4日・5日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
新規事業の立ち上げに際して、要件を策定し、ビジネスを理解し、 サービスローンチと価値創造まで一気通…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅,西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【インフラ / 週5日】社内インフラ設計構…
社内のシステム刷新、グループウェア入れ替えに伴いインフラ環境を構築します。 現行システムの適性を確…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Java / 週5日】ECサイト保守案件
当社が請けているプロジェクトにてECサイト保守案件の担当をお任せいたします。 ・ECサイトの小規模…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・tomcat | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】英語…
新規開発と開発運用中システムの保守対応(不具合対応含む)を担当いただきます。 ・英語学習アプリの新…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
料理を注文されるお客様向け、飲食店様向け、配達員向けといった3つのアプリが存在し、フロント部分を中心…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・React.js・Reactn… | |
定番
【リモート相談可 / Python/Kot…
AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 詐欺被害など…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Kotlin・Ktor | |
定番
【HTML/CSS / 週3日】Webペー…
食品を中心としたグループ会社のWeb基盤の安定的な運用サポートを目的として会社のHPの運用更新や、キ…
週3日
140,000〜220,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】健…
AWS基盤の設計・構築 ・Quorum(ブロックチェーン)を用いた取引システムを、AWS上に構…
週5日
410,000〜800,000円/月
| 場所 | 秋葉原四ツ谷、麹町、赤坂見付駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
弊社が完全独自開発した、家事代行業界のDXと事業成長を後押しする業務管理システムの開発。 ・フ…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
システム開発とWebサイト制作を軸に、 不動産・建設業界を中心とした 多くのお客さまの課題を解決…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
保険関連のマッチングアプリを自社開発している企業となります。 新しくリリース予定の機能開発に携わっ…
週4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Cake・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社の開発チームにて、フロント部分のコーディング業務を担当いただきます。 サービストップページ…
週5日
460,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Sass | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
・レガシーなLAMP構成の現在のECサイトの新規開発に携わっていただきます。 ・すでに十数年運営し…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
自社開発のWEBマーケティング支援ツールの開発と運用 ・少人数での開発のため、インフラからフロ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】英語…
新規開発と開発運用中システムの保守対応(不具合対応含む)を担当いただきます。 ・英語学習アプリ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails(6系) | |
定番
【AndroidJava / 週5日】ナビ…
当社プロパーと共に顧客サービスの開発をご支援頂きます。 ・顧客折衝 ・設計業務 ・実装業…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅or泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java | |
定番
ゲームプランナー
アナログの紙ゲームをデジタルサイネージ化。 子供向けに防災知識を身に着けて貰う新規事業になります。…
週1日・2日
130,000〜260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿荻窪 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
【Java / 週5日】ECモールおよび在…
既存の自社ECサイト、および店舗機能やマルチテナント連携における各種プログラムおよびWebフロントの…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SAStruts・Jersey | |
定番
【Java / 週5日】大手ECサイト向け…
大手ECサイト向けコアAPI開発コアプラットフォームAPIの刷新を行います。 移行導入に向けて新旧…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【PHP / 週5日】電子書籍取次システム…
稼働しているシステムに対する機能拡張の改修作業です。 今後AWSへの移行計画で、新規立ち上げに参入…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Ruby / 週5日】BtoB、BtoC…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
コンサルタントと共にAIや機械学習を用いてクライアントの業務変革を行っていただきます。 データ分析…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・仮想通貨のシステム開発・システム設計・システム構築 ・システム改善・システム運用上の、管理・プロ…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・既存のECの商品/販売関連機能をWordpressを利用した新規EC機能にリプレースするプロジェク…
週5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【AWS / 週4日】クラウドでLAMP環…
・既存のECの商品/販売関連機能をWordpressを利用した新規EC機能にリプレースするプロジェク…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【コミュニケーションデザイナー】ブロ…
【企業】 NFT技術を応用し、アニメや漫画などのIPタイトルのファンコミュニティアプリを開発・提供…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
【スマホアプリエンジニア】SNSマッチング…
SNSマッチングアプリのグロースハックをご担当いただきます。 既存サービスのための新規機能開発、運…
週5日
750,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| PHP・Swift・Kotlin・Java・Swif… | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
450万DLのコスメのクチコミアプリの、エディトリアルデザイナーを募集しています。 ・コスメの…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 池袋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
M&A事業関連の新規ポータルサイト(マッチングサイト)の制作を行っております。 現在プロジェクトチ…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/Swi…
自社オフィスにて、新車カーリースサービスのネイティブアプリ開発の立ち上げチームに参画いただきます。 …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 東京23区以外つくば駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・React・Native | |
定番
【システム開発/運用】ERP Dynami…
ロジ(販売、購買、在庫)の追加開発(画面、機能、帳票、インターフェース等)。 テストフェーズにおけ…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Dynamics365 | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
プラットフォーム開発担当として 、リプレイス、現サービスの新機能開発、新サービスの設計、開発ほか、 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【UI/UX / 週5日】キャリアのコンシ…
アプリ強化のため、UI/UXの設計・制作をお願いいたします。 企画部門と共にサービス要件に基づいた…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
自社サービス開発・運用と多角的に事業展開をしている企業にてサーバーサイドエンジニアとして業務を行なっ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・JIRA | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
クラウド基盤の開発、アプリケーションの新機能開発、改修はもちろんのこと、 ビジネスサイドのメンバー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【AWS / 週5日】エンタープライズシス…
AWS上に次世代業務システムのインフラ設計・構築を担当して頂きます。 Oracle ERP Clo…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿またはめじろ台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
自社WEBサービスの運用をサポートとしていただけるエンジニアを募集しております。 Wordpr…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【システム開発/運用】ERP Dynami…
ロジ(販売、購買、在庫)の追加開発(画面、機能、帳票、インターフェース等)。
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木横浜 |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
| Dynamics365 | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
美容業界の求職者向け求人ページ作成システムのリニューアル案件です。 リニューアルに伴い求職者・…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【C# / 週5日】オンラインゲームにおけ…
通信システム設計やDB設計やゲームロジック実装などサーバサイドのアプリケーション開発が主な業務内容に…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・.netFW | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/PHP /…
会員登録をし、テンプレートを選択して写真やテキストを用意するだけで簡単にホームページを作成できるサー…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby | |
定番
【PM / 週4日〜】海外送金システムの運…
要件定義、社内調整、ベンダーコントロール、資料作成・整理、システム企画 ※プロジェクトに応じて幅広…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木1丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
広告配信プラットフォーム開発を依頼します。 Google広告やYahoo広告のAPI対応などをおこ…
週4日・5日
670,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java / 週5日】プリペイドカードシ…
・プリペイドカードシステムの開発タスク(基本設計、詳細設計、製造、試験) ・開発案件を調整、推進し…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留(新橋) |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【C# / 週5日】社内ポータルの運用保守…
社内ポータルのシステム管理者として運用保守、またシステム開発を行っていただきます。 対象システムは…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
サービスリリース以降、機能追加などを徐々に予定しており、開発にご協力いただけるエンジニアを募集してお…
週3日・4日・5日
580,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Keras・CNN | |
定番
【PHP / 週5日】自社開発パッケージソ…
最先端技術を駆使した、自社サービス開発を積極的に行っております。 自社で開発しているパッケージソフ…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Smarty | |
定番
【C# / 週5日】特定施設向け入所者行動…
顧客サービスを導入している特定施設向けに入所者個々人の施設内の行動を、監視カメラの映像から顔認識AI…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【C# / 週5日】見積システム再構築
見積システム再構築に関する下記業務をお願いいたします。 ・要件定義 ・基本設計 ・現行の基幹シ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Node.js / 週5日】自社クラウド…
自社クラウドサービスの開発をお任せできる方を募集しております。 ・Webスクレイピング、RES…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座一丁目 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Vue.js/Nuxt.j…
クラウドソーシングサービスの機能開発や新サービスの開発における 設計、開発を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt.j… | |
定番
【フルリモ / Vue.js/Next.l…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
・システム開発プロジェクトのプロジェクト計画、システム要件定義、見積もり、プロジェクト管理、リリース…
週3日・4日・5日
580,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には以下の開発項目を想定して…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・Flask | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
・自社サービスiOSネイティブアプリの設計・開発 ・社内向けiOSアプリ・ツールの開発 ・サーバ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
[フルリモート] AWS スペシャリスト …
【案件内容】 ・ビジネスのスケールアップに追随できるアーキテクチャ構想立案と実践 ・スタートアッ…
週2日・3日
360,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿丸の内駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Terraform | |
【Webディレクター】自社サイトの制作ディ…
業務内容】 自社サイトのリニューアルを検討しており、制作に関するディレクションについて お任せを…
週2日・3日
1.6〜2.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社が運営しているモビリティサービス事業のサービス開発をご担当いただきます。 ・モビリティサー…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】基金・キャリアアッ…
某基金様のキャリアアップシステム(DX)の開発をお願いいたします。 新規インフラの立ち上げのため、…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
経験者のサポートを得ながら、Drupal7の独自モジュールのリファクタリング、 単体・結合含むテス…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
連携データチェック・加工システム開発に携わるエンジニアを募集しております。 ・データ取り込み ・…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅/永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】不動産T…
当社が運営する不動産Techメディアにおいて、フォーム内の画像作成や記事内のバナー作成、オリジナル画…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】クラ…
弊社ではサーバーの多様化するニーズに対応した、豊富なサービスを展開しております。 サーバー管理の専…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにてデザイン業務に携わっていただ…
週3日・4日・5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【Java / 週5日】新ECモデルのシス…
この度は日本での「S2b2C」モデルのECサイト立ち上げにあたり、エンジニアを募集いたします。 …
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
新規サービスはESG(Environment Social Governance)の観点で企業評価を…
週3日・4日・5日
280,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】新…
新規サービスはESG(Environment Social Governance)の観点で企業評価を…
週3日
140,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
・新規BFF基盤の全体設計・基本設計の作成作業に参加し、提案・アドバイス・設計 ・AWSの各種サー…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
・AWSの各種サービス・ソリューションを有効活用し、サーバーレスを意識した開発 ・CI/CD・マイ…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】人材…
IT業界の人材マッチングサービス(Webサービス)のプラットフォーム化に伴う追加機能開発をご担当いた…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【JavaScript / 週5日】ソーシ…
この度は新タイトルリリースに向けてソーシャルゲーム開発において、設計・実装および高速化・最適化の業務…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア |
| JavaScript・node.js | |
定番
【Swift / 週5日】通信キャリアの記…
通信キャリアの記事系のサービスアプリ(iOS)についての要求仕様検討の支援を行います。 ・…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【インフラ / 週5日】Web教科書配信シ…
小中学校にて利用するWeb教科書配信システムの新規開発業務に携わっていただける方を募集します。 …
週5日
370,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
アプリケーションのサーバー・フロントの開発を行いつつ、アプリケーションへの広告配信を行うためのSDK…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社SaaSプロダクトにおけるAWSを使用したシステムの構築検討、保守に携わっていただきます。 制…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
エンジニアとして既存サービスの保守運用と新規サービス立ち上げに従事していただきます。 ・クラウド型…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日の出駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
グラフィックデザイナーとして下記業務に従事していただきます。 ・クライアントのブランディング戦…
週5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市民広場駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】マーケティ…
マーケティング組織でのマークアップエンジニアリング業務を担っていただける方を募集いたします。 …
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / JavaScript /P…
・POS向けマスターデータ(商品マスタ、POSボタンへの割当など)を編集するクライアント(Windo…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三越前駅/新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js | |
定番
【Java / 週5日】通信事業者BtoC…
通信事業者の会員向け契約変更システム開発チームで基本設計作成およびオフショア部隊の詳細設計書・ソース…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seaser2 | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・暗号資産取引所システムの基盤インフラ・ネットワークの設計・構築 ・顧客システム要件に沿った構築・…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Go / 週5日】WEB開発エンジニア募…
新規データ収集基盤での開発業務を行っていただきます。 現在データベースの導入について検討しています…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Python・Ruby・Java | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
新たにIT部門を設立し、アプリ開発やグループ内基幹システムの構築などを検討しており、社内業務システム…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】ECサ…
弊社クライアント(EC系)の改修案件にて開発業務(設計、実装、テスト・デバッグ、ソースコードレビュー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】EC…
EC系の改修案件にて開発ディレクション業務を担当いただきます。 稼働中の大規模システムの改修案件に…
週3日・4日・5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony | |
定番
【リモート相談可 / PM/PMO / 週…
・要件定義~リリースまでのPM業務 ・外部ベンダー、提携先との調整 ・上申資料の作成等 ・課題…
週5日
500,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】公…
・某公共系法人の公開サイトリニューアル案件のPM ・プロジェクトの全体マネジメント ・顧客調整 …
週5日
750,000〜1,590,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Go / 週5日】WEB開発エンジニア募…
新規データ収集基盤での開発業務を行っていただきます。 現在データベースの導入について検討しています…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Python・Ruby・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
某大手CD販売店や、大手化粧品メーカー、大手鉄道グループなどの案件を直で企画から運用までワンストップ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Go / 週…
建設業における顧客向け品質管理・検査アプリをより多くの人に使ってもらうプロダクトとして成長させていく…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋-- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Go・Lar… | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】インバウン…
この度、インバウンド事業のキャンペーンプロジェクトに向けたコーダーを募集します。 新規ドメインのサ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
ニューノーマル社会の実現に向けたゼロトラストソリューションの実現に向けデバイスログ/認証ログ/アクセ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
コアプラットフォームAPIの刷新、ノンブロック構成(非同期)のWebAPIプログラムの改修・機能追加…
週5日
440,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
弊社はAIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決をAIベンチャーです。 詐欺被害な…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Kotlin・Typescript・React | |
定番
【Ruby / 週5日】アパレル系在庫管理…
在庫管理アプリ向けのAPIをRailsで開発します。 入出庫や棚卸しの機能を提供するAPIの設計・…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・新規Webサイト開発および既存Webサイトアップデート ・企画フェーズでの要件定義、ユーザ体験 …
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アジャイル開発プロジェクトでの、Webアプリケーションフロントエンド開発 およびバックエンド開発を…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
アプリ開発業務のみならず、ユーザーへのヒアリングやユーザー体験含め、企画から携わって頂く予定です。 …
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】アプ…
アプリ開発業務のみならず、ユーザーへのヒアリングやユーザー体験含め、企画から携わって頂く予定です。 …
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Go | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
・新機能の導線設計や詳細機能の設計を行います。 ・サービスの利用分析に基づいた機能改善及び整理を行…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
・主に Go (ver. 1.11 以降) を用いた自社サービスのためのサーバーサイドの設計・開発・…
週4日・5日
480,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木1丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Scala・Go・AWS・GCP | |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
・自社サービスのフロントエンドのSPA開発(新規機能追加や運用保守)に携わっていただきます。 ・バ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社サービスのフロントエンド開発をメインにお任せいたします。 具体的には ・HTML5/CS…
週3日
140,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
プロダクト開発に携わっていただきます。 具体的には、プロダクトマネージャー・デザイナー・サーバサイ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
受託や自社開発における様々なWebサイト制作、アプリケーション開発プロジェクトに参加いただけるエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
クライアントと連携するサーバサイドのプログラムの設計・制作を行っていただきます。 サーバー構成を設…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】サー…
ソーシャルゲームの運用業務・開発業務 (バックエンドメイン、一部Webフロントエンド) ・バトル…
週5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
弊社広告事業におけるアドシステムの開発を行っていただきます。 ・アドシステム開発における技術的…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Scala | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
クライアントである銀行から受けたWEB開発案件のエンジニアを募集いたします。 PHPを使用した開発…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・・Laravel | |
定番
【C/C++ / 週5日】組み込みシステム…
イーソル製各種組み込みシステム向け製品のインテグレーション作業に従事していただきます。 インテグレ…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
旅行系ToC新規サービスの開発業務です。 iOSスマートフォンアプリの開発の設計と実装をお願いしま…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【React / 週5日】自社SaaS系サ…
弊社が開発を進めるsaas系自社プロダクトの開発チームに加わっていただきます。 主にフロントエンド…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【Swift / 週3日〜】自社ヘルスケア…
睡眠に関するヘルスケアアプリを自社で開発しています。 立ち上げたばかりのスタートアップ企業で、事業…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【SQL / 週5日】外資系監査法人向けア…
・Excel VBA、SQL等を使用しての業務ツール新規作成/改修/保守 ※場合によってはJav…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【jQuery / 週3日〜】アパレルブラ…
ECサービスの運営・自社開発を行う日本のアパレルブランド企業です。 現在広告用LPを複数作成す…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
フロントメインの業務となりますが、スキル分野比率としてDBなどのバックエンド3、フロント7位の割合で…
週3日・4日・5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄木駅、代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Co… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
これまで開発してきたシステムのレガシーな部分をリファクタリングし、機能追加ができる状態にしたいと考え…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails4 | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
・ウェブとモバイルアプリの開発を行っています。 ・フルスタックでTypeScript開発をしており…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Swift・typescrip… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
自社サービスのフロントエンド開発案件です。 PHP経験者に限らず、Java によるシステム開発や、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js・Redux・… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】メガ…
連携のためのSaaSの機能把握とスクラッチで実現するべき機能の検討など、機能配置やアーキテクチャ検討…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Framework・GitH… | |
定番
【リモート相談可 / PM/PMO / 週…
自動車業界向けKeySQLサンセット対応・販社Tableau対応(業務部門)のPM支援作業 →各チ…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
・法人向けクレジットカードサービスでPMやデザイナーとともに開発 ・バックエンド、フロントエンドを…
週4日・5日
840,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / jQuery / 週3日〜…
GPSやWiFiデータなどの電波情報から屋外だけでなく屋内の位置測定もできるシステムを開発。 …
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
自社サービスのフロントエンド開発案件です。 軸としてはPHP経験者に限らず、Java によるシステ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js・Redux・… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
創業期につきゼロから共にサービスを作り、新たな市場を開拓していくチームメンバーを募集してます。 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Java・Scala・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
当社はベンチャー・中小企業の資金調達をトータルに支援するプラットフォームの提供を通じてベンチャーエコ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【Kotlin / 週5日】自社マッチング…
Android ネイティブアプリケーションの開発に携わっていただけるエンジニアを募集します。 順調…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】自…
iOS ネイティブアプリケーションの開発に携わっていただけるエンジニアを募集します。 順調にユーザ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインのフロントコーディング業務をお願いいたします。 JS部分もしていただけるのであれば歓迎です…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
順調にユーザー数・売上げを伸ばしているマッチングサービスの開発をお願いできる方を募集しています。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
子連れで行ける場所だけを集めた口コミ情報サイトや全国の子供の習い事教室を比較検索・体験申し込みができ…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
複数人配信で視聴者を魅了する、受託案件の生放送アプリケーション(iOS)に関するサーバーサイド開発業…
週3日・4日・5日
550,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go | |
定番
【フルリモ / Scala / 週4日〜】…
当社はベンチャー・中小企業の資金調達をトータルに支援するプラットフォームの提供を通じてベンチャーエコ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木ー |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Scala・Scala・Akka・HTTP・Skin… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
Web作業に関してはGUI上でのページ修正、追加作業となり、 基本は画像作成とテキスト流し込み、レイ…
週3日
90,000〜200,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / .NET / 週4日…
既に販売済みの自社製パッケージシステムの製品開発のスピードを加速させ、バージョンアップや機能追加を見…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東神奈川駅、仲木戸駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週5日】受…
企画段階からディレクターやアートディレクターとともにお客様先に出向き、コンセプトワークを行う機会もあ…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】ソ…
メイン事業である、ソーシャルゲームの運営/買取/再生事業を担当いただきます。 スマートフォンゲ…
週3日・4日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
GPSやWiFiデータなどの電波情報から屋外だけでなく屋内の位置測定もできるシステムを開発。 …
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・LAMP・A… | |
定番
【フルリモ / Android / 週3日…
既存サービスのチャットフィクションアプリ、または、新規サービスの開発に携わっていただきます。 新し…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅、中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】チ…
既存サービスのチャットフィクションアプリ、または、新規サービスの開発に携わっていただきます。 新し…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木代官山駅、中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【PM / 週4日〜】ヘルスケアIoT装置…
自社プロジェクトのマネジメント、プラットフォームの前進に必要な戦略や機能の立案、遂行、エンジニアと協…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Scala / 週3日〜】…
本プロジェクトでは Java で書かれたモノリシックなシステムを段階的にScala でマイクロサービ…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Scala | |
定番
【Go / 週5日】日本最大級の料理動画メ…
日本最大級の料理動画メディアのサーバーサイドを担当していただきます。 ・GoでのAPI設計・開発 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・WebアプリケーションのサーバサイドおよびAPIの設計/開発/運用 ・サイトパフォーマンスとスケ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社イ…
・AWS上でのシステム構築作業&障害試験対応。 ・Immutable Infrastrucureに…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【React.js / 週5日】自社案件で…
・Angular.jsを利用した法人向けサービス管理サイトの開発 ・フロントエンドの試験の自動化 …
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
毎日4000枚、累計100万枚の写真が投稿されている大規模コミュニティのアプリ開発業務を担当いただき…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【PHP / 週4日〜】自社サービスCMS…
テンプレートを選択して写真やテキストを用意するだけで誰でも早く簡単に1ページのホームページが作成でき…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・LAMP開発 | |
定番
【AndroidJava / 週5日】自社…
・マッチングサービスなどのスマートフォンアプリの設計、開発、テスト(アジャイル開発方式) ・更なる…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・ハイブリッドアプリの開発 スキルや貢献度に応じて以下のフィールドにも参加していただきます。 -…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・React・Native | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
時系列ヘルスデータを収集するプラットフォームを開発。 各アプリケーションやデバイスとのつながり…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
急成長中の勢いのあるベンチャー企業で、開発業務に携わっていただける人材を募集しています。 メン…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・React.js | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
急成長中の勢いのあるベンチャー企業で、開発業務に携わっていただける人材を募集しています。 メン…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
UI/UXを意識したアプリケーション開発に携わったことがある、デザイナーを募集しています。 プロト…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
AIを活用したSNSマーケティング運用支援プロダクトのUI設計開発をしていただきます。 機会があれ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋、九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
既存サービスのチャットフィクションアプリ、または、新規サービスの開発に携わっていただきます。 新し…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木代官山駅、中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
・自社/既存サービスの新機能開発、改善ディレクション ・サービス全体像の設計(UIを含む) ・U…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
・マッチングサービスなどのスマートフォンアプリの設計、開発、テスト(アジャイル開発方式) ・更なる…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
大規模教育サービスを運営するクライアントと一緒に、デザインの視点からUI/UXの改善を行います。 …
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【jQuery / 週3日】受託案件デザイ…
受託案件にてWEBサイトデザインからコーディングまでをお任せいたします。 ・各種Webサイト構築 …
週3日
190,000〜340,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【SQL / 週3日】データの設計・要件定…
BI(ビジネスインテリジェンス)ツール利用にあたり必要となるデータの設計・要件定義を含む導入支援業務…
週3日
250,000〜490,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅、半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手企業様のWEBページのコーディング作業をお願いできる方を募集します。 デザイン済みのページを納…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Github/Slack/JIRAを活用して開発フローを構築。 フロントエンドの現技術構成としては…
週4日・5日
750,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社サービスの機能の追加開発・改善運用業務を行っていただきながらチームリードをお任せできる経験豊富な…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony2.6 | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
宿泊事業者やマンスリーマンション運営事業者向けに行う運用管理サポートサービスや宿泊施設の需給統計デー…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
自社ブランドのWeb/グラフィックデザインをご担当いただきます。 特に、新ブランドのグラフィックデ…
週3日・4日・5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
弊社の新規プロダクトであるデータ分析ウェブサービスの開発に携わっていただきます。 言語としてTy…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】自社デ…
弊社の新規プロダクトであるデータ分析Webサービスの開発に携わっていただきます。 Go言語(Gi…
週4日・5日
660,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Gin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
大手ゲーム会社様でのオンラインゲームインフラの運用、構築を行っております。 最新の技術、高い専門性…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 東京23区以外大森駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・GCP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
RPAの為、顧客システム環境に応じ幅広い環境の知識、システム連携の知識が求められます。 とはいえ、…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋駒込駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
美容系Webとモバイルアプリの開発を行います。 バックエンド、API開発やほかのAPIとの接続を…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
急成長しているサービスで力を発揮してくれるデザイナーを募集しています。 ・サービスのUI/U…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ビジネス向けウェブサービスの設計・開発・運用 ビジネスパーソン向けのウェブサービスの設計・開発をリ…
週5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby・Java | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】店舗H…
①店舗HP管理CMSのパフォーマンス・チューニング DBレスポンスの改善やAPIなどのコードチ…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ネット証券サービスを展開している企業にて、自社サイトのリニューアルを予定しておりPowerCMSを採…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・PowerCMS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるクレジットカードや電子マネーの支出を一括管理するモバイルアプリ、キャッシュレス決済…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社製品の新機能開発、性能改善のに携わっていただきます。 実際に手を動かす実装メインのお仕事です。…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
デジタルトークン発行管理プラットフォームのバックエンド開発業務です。 APIの新規実装、改修が主な…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Notes / 週5…
・NotesからSharePointを利用したシステムへ移行 ・アジャイル開発に近く、現場でツール…
週5日
830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
ヘルスケアIoT装置を使ったプラットフォームを開発するスタートアップです。 独自のバイオセンシン…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
インターネット広告の出稿を内製化する、作業効率化ツールの開発に携わっていただきます。 新規事業です…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails・React | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
睡眠に関するヘルスケアアプリを自社で開発しています。 立ち上げたばかりのスタートアップ企業で、事業…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Android/IO…
アプリ(iOS/Android)をよりユーザーに価値を提供するためプロダクト価値を高めることが出来る…
週5日
350,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・AWS・Slack・Confl… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
建築業界に特化した会員制掲示板サイトの新機能開発をお願い致します。 有料機能をリリースする予定の為…
週5日
350,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
サービスの質の向上と事業拡大に向けて、インフラエンジニアの方を募集。 具体的には、サーバー保守・…
週5日
350,000〜630,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・Spring・Boot・Linux・MyS… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日〜】…
自社プロダクト製品の開発を担当いただきます。 今回は既存システムの改修を中心に、社長直下で進め…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・C… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週5日】広告S…
プロダクトの立ち上げにあたり、適切な技術選定を行い、fluct内外のエンジニアチームと協力しつつ、競…
週4日・5日
630,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・Ob-C・Kotlin・AWS… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主には自社メディアに携わって頂き、レンダリングエンジンを利用したコーディング業務を担当頂きます。 …
週4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 東京23区以外本町駅,溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【Node.js / 週4日〜】自社スポー…
自社で開発した人工知能をメディアに搭載し、プロ野球を中心に勝敗予測、3D一球速報を展開しています。 …
週4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 東京23区以外本町駅,溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
今回お任せする業務は、 ・自社インフラの構築/運用 ・自社WEBサービスの開発 ・データ作成に…
週5日
460,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・CakePHP・Linu… | |
定番
【フルリモ / サーバーサイド / 週3日…
貿易×ITのシステムを開発している当社にて、開発実務とエンジニアの育成をお任せするリードエンジニアを…
週3日・4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・現行システム保守開発対応 ・改修要件の確認と設計、開発テスト、リリースまで対応 (不明瞭な点…
週5日
880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麹町 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】大企…
企業コミュニケーションの課題をITで解決し、企業の生産性向上を支援する企業です。 大企業向けのWE…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川高輪台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
【PM】販売管理のシステムのPM
【業務内容】 ・産業廃棄物の処理をする業者のこれから作成する社内構築システムのPM └原価管理、…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿亀戸駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| AWS | |
定番
【コミュニケーションデザイナー】ブロ…
【企業】 NFT技術を応用し、アニメや漫画などのIPタイトルのファンコミュニティアプリを開発・提供…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿代田橋 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
1. 行動解析など画像解析とソフトウェア機能の連動/コントロールの実現 2. 深層学習による骨格抽…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
本プロジェクトでは、システム管理者やアプリケーション開発者デザイナー、UI/UX設計者など、多くのチ…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
某大手CD販売店や、大手化粧品メーカー、大手鉄道グループなどの案件を直で企画から運用までワンストップ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
動画配信・オンラインのイベントサービスの統合化を行いながら、機能強化を図る目的でエンジニアを募集しま…
週5日
590,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
【サーバーサイド】自動車業界向けのシステム…
一般会計(本社 経理部門)現金・預金日報/仕入・支払管理の伝票処理をメインフレームで利用しているが、…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| COBOL・COBOL・JCL・AWS | |
定番
【Ruby,Typescript,Reac…
【業務内容】 ・ワークフロー機能の開発 ・データパイプラインの設定情報をGitHubから取り込む…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
テストエンジニア
薬局経営を支援する薬局ダッシュボードの検証・デバッグ、テストコードの作成を担当して頂きます。
週2日
150,000〜260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】…
・プロダクト(Web/iOS/Android)のUI/UXデザイン ・スクラム的なPMと協力しての…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【セキュリティ / 週4日〜】自社セキュリ…
この度は、導入企業の増加に伴い、 導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集いた…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【ネットワーク / 週4日〜】新規通信事業…
この度は新規Wi-Fi事業の推進にあたり、各自治体への高速Wi-Fi設置に向けた設計を担っていただけ…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
Windows PCに接続したWindowsのタブレット上で、PCに接続したカメラで撮影した動画をリ…
週3日・4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
顧客で契約しているデータセンター廃止にともない、データセンターに設置しているネットワーク機能に代わる…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】上場…
・インフラ開発・運用戦略および計画の策定 ・弊社サービスを提供するインフラの設計・実装・運用 ・…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
-次世代ゲーム機の画像処理関連の開発業務。 -カメラから入力された画像を、ディープラーニングを用い…
週5日
480,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
外国籍の方向けの新規アプリ内の追加アプリ開発チームの立ち上げを、担当者とともに進めていただきます。 …
週3日
440,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京‐ |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
今回は弊社のWebアプリケーション開発にご協力いただけますエンジニアの方を募集いたします。 主に運…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
自社健康診断パッケージのバージョンアップをご担当いただきます。 現時点では計画、立案が終わり、調査…
週5日
500,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js・jQuery | |
定番
【C/C++ / 週5日】無線通信装置向け…
無線通信装置のIC制御に必要となるプログラムの実装および、動作確認の実施。 -ICの変更に伴い、既…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵小金井駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【C# / 週5日】自動車メーカ・重量管理…
自動車メーカ・重量管理管理システムの開発業務になります。 生産管理系プラットフォームをベースとした…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・C#・SQL | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
統合開発環境に対する機能拡張・不具合調査・その他改善活動 弊社開発の統合開発環境およびGDBインタ…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C・C++ | |
定番
【Swift / 週5日】ヘルスケアのスマ…
新規開発を行いリリースを行ったものの、不具合や残課題が多数残っている状態です。 それに対し、不具合…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
プロダクトの大幅なアップデートのため、開発組織の責任者として、一緒にグロースさせていけるリードエンジ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】国内最大…
タクシーアプリやその他新規事業におけるサーバサイド開発を総合的に行っていただきます。 アーキテクチ…
週5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
郵便系システムのインフラ部分(保守、および、新規構築)。 次期案件の構築中のため増員いたします。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle・Linux・ShellScri… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
2つのサービスについての設計および開発 ・マイクロフロントエンド化の推進等、サービスの大規模化に備…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Storyboo… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
2つのサービスについての設計および開発 ・需給に関するデータパイプラインとダッシュボードの新規開発…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・tableau | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
自社で開発を行っているアプリの企画や設計、開発、運用といった、全フェーズに携わっていただける方を募集…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
現在稼働中のシステム基盤の製品EOS対応を通じてパブリッククラウド上にシステムを移行いただける方を募…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 東北:仙台天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】プ…
お客様内のプロダクト開発PJにおけるPM業務を担当していただきます。 EUの要望のヒアリングにより…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【セキュリティ / 週4日〜】自社セキュリ…
この度は、導入企業の増加に伴い、導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集いたしま…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
以下の業務をお任せします。 ・医療機関データ処理の運用保守 ・データ品質改善の取り組み ・業務…
週5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】デジ…
生命保険会社の営業ツールが紙の帳票からタブレットに移行する中で 業務システムの一環として、AWS上…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋天王洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・基幹システムの設計、開発作業。 ・申込管理、FAX管理、法人与信、原本管理などのシステムの設計開…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・.NETFramework | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
大手通販サイトの既存システムをマイクロサービス化していくプロジェクトになります。 参加当初は、AP…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】不動産…
不動産会社様の物件紹介のサイトをCMSで構築しています。 メインのユーザー向けサイトと、複数のサテ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・最善の措置、開発プロセス、およびコーディング基準の追求 ・よく設計された、信頼性の高い、保守性の…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東松原駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプログラマー |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 自社が携わるサービスのQA業務をご担当いただけ…
週5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Android/iOS /…
iOS/Androidエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションのネイティブアプリ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
企業のデジタル変革をテクニカルコンサルティングの立場から、顧客の経営視点に立ち、課題解決を提案するこ…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿茅場町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・Python・Nod… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社で開発したプロトタイプのアプリをベースに、それをクラウドサービス化するプロジェクトの開発担当エン…
週3日・4日
450,000〜930,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】法人…
Web開発をご担当いただき、新機能開発・改修に取り組んでいただける方を募集いたします。 ・Ru…
週5日
570,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / C /C++ / 週5日】…
-弊社製ファイルシステム製品の機能拡張/改修。 -他社製Linux互換ファイルシステム製品…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
-デジタル複合機向けの検査機能開発(GUI、画像処理、マイコン制御)を担当頂きます。 -顧客より要…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / グラフィック / 週3日〜…
全国の広告代理店から商業デザインをメインに幅広いデザインを制作に携わることができます。 ・Illu…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄呉服町駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| PhotoShop・Illustrator | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】オン…
日本最大級オンラインギフトプラットフォームのソフトウェアエンジニア(Webアプリケーション)のサーバ…
週4日・5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Git・Fluentd・Sentry・Dat… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】オンラ…
日本最大級オンラインギフトプラットフォームの、ソフトウェアエンジニア(Webアプリケーション)のサー…
週4日・5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Go・Git・PHP・Fluentd・Sent… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
日本最大級オンラインギフトプラットフォームのアプリエンジニア開発(Android)を担当いただきます…
週4日・5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Android・CircleCI・Fi… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
・toC開発プロダクトのアプリ(特にiOS)においてユーザーやビジネスサイド、PdMからの要求事項か…
週3日・4日・5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Flutter | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
地域企業に特化した副業・兼業を紹介する大都市と地域の人材シェアリングサービスを運営しています。 …
週3日・4日・5日
570,000〜2,150,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
自社副業マッチングサービスにおけるフロントエンドの開発を行っていただけるエンジニアの方を募集いたしま…
週3日・4日・5日
570,000〜2,150,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】店舗…
・PHP/LaravelにてB2B自社サービスを開発しています。 ・Google 等の WebAP…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
既存サービス/新規開発サービスの立ち上げ、各種施策等の企画段階から枠組み、画面遷移、グラフィックにお…
週4日・5日
480,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| CSS3・Illustrator・Photoshop… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
既存メディアおよび新規事業サービスの企画、およびコーディング全般をお任せします。 デザイナーやサ…
週4日・5日
480,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
事業開発ノウハウを活かして、新規toBとtoCサービスのシステム開発全般をお任せします。 サーバ…
週4日・5日
480,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・WordPress・Solr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】シス…
システム開発に特化した発注先選定支援サービスをRails/AWS(場合によっては React / G…
週5日
300,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails・react | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】オン…
・新規サービスのシステム開発(メイン) ・商標登録を安心、カンタンにできるようにするクラウドサービ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / フルスタック / 週5日】…
Deep Learningを使った最先端システムの開発や強化学習を使ったロボット動作最適化学習などに…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄井尻駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Swift・Kotlin… | |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
3D自律移動ロボットのSW開発・品質向上・保守を行って頂きます。 -三次元空間を移動するロボット内…
週5日
660,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
-車載開発のMISRA-C適用開発 -車載開発のセキュアコーディング適用開発 ※上記両件とも使用…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / フルスタック / 週…
当社は、大手企業にマーケティングサービスを提供しています。 マーケティングサービスの中で、重要や役…
週4日・5日
300,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
弊社の画像認識アルゴリズムの提供基盤をさらに展開するにあたって、iOS/Androidのモバイル開発…
週3日・4日・5日
240,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Python・Swift・AndroidJava・K… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】オンプ…
- オンプレ→AWS化・移転案件を中心としたプロジェクトマネジメント - 方式検討・見積対応等の受…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Java・AWS | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】PMO…
建機レンタル営業支援関連システムの運用改善・保守 ・変更案件の要件まとめ~本番受入、本番導入 (実…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
170,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週5日
220,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Ruby・AWS・Django・Lin… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
バックエンドエンジニアとして、チャットボットを構築、運用するWebアプリケーションを中心に機能拡張を…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】大学…
大学の願書出願システムの継続開発案件において、以下をお任せします。 ・機能追加 ・不具合修正 …
週5日
300,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・Java・Script・CSS・… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
従業員の成功を加速させるオンボーディングプラットフォームの採用・組織/人事領域のクラウドサービス(B…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
組織/人事領域のクラウドサービス(BtoB SaaS)のフロントエンド開発を行っていただきます。 …
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
少人数での開発になりますので、アプリの開発、リリースをまで担当し、要件定義~実装までベンチャーならで…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Python・Swift・Kotlin・‐ | |
定番
【フルリモ / CSS / 週3日〜】HR…
-プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認・テスト、デプロイ) …
週3日・4日・5日
570,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
-プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認・テスト、デプロイ) …
週3日・4日・5日
570,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Python・Type… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
-プロダクト開発(主に新機能開発) (要件定義、設計、開発、実装、動作確認・テスト、デプロイ) …
週3日・4日・5日
570,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| CSS・Python・Typescript・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
-主にカムコーダのUI操作系(Menuなど)や各種機能に基づくMWとのIF開発において、設計~実装~…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【illustrator/Photosho…
■webサイトデザイン サイト構造を考慮したナビゲーション、情報設計に基づいたレイアウト、質感の高…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| illustrator・Photoshop | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社SaaSサービス開発におけるフロントエンド・サーバーサイドを幅広くご担当いただきます。 ・…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Python・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるモニターアライアンス基盤とクライアントのサービスが連携した共同事業のシステム開発に…
週5日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・PhalconPHP | |
定番
【UIデザイナー】大手ゲーム開発会社のUI…
【業務内容】 スキル感に合わせてUI設計、画面遷移、UIアニメーション/エフェクト付けを行っていた…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| SpriteStudio・AfterEffects | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社で開発した人工知能をメディアに搭載し、現在はプロ野球を中心に勝敗予測、3D一球速報を展開していま…
週4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京本町駅,溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・R・ApacheHadoop・AWSA… | |
定番
【Ruby / 週5日】VRプラットフォー…
RubyonRailsによるサイトの開発、スマートフォンアプリケーションの開発、画像・映像処理プログ…
週5日
280,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿馬喰横山駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・UNIX・AWS | |
定番
【TypeScript / 週3日〜】デー…
新規プロダクトであるデータ分析サービス開発に携わっていただきます。 言語はTypeScript、フ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,280,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】メデ…
今回は、ポイントサイトを、ユーザとクライアントからより支持されるプロダクトに育てていく為に、サービス…
週4日・5日
630,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
フロントエンド・バックエンドともにTypeScriptを採用しています。 フロントエンドやバックエ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| JavaScript・-・ | |
定番
【フルリモ / Kotkin / 週5日】…
今話題の、グループレッスンやパーソナルトレーニングが可能な鏡型フィットネスサービスの開発業務をご依頼…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
日報を管理し共有するアプリを展開しております。 自社開発アプリUIのリニューアルにつき、Web版ア…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川馬車道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
AIを活用したSNSマーケティング運用支援プロダクトのUI開発です。 弊社ディレクターが設計したU…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋、九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
AIを活用したSNSマーケティング運用支援プロダクトのバックエンド開発です。 機会があれば、AI基…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋、九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・serverless・framewor… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
WEBアプリケーションの開発に携わっていただける方を募集します。 (Web view ベースのハイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザインのABテストを行い、PDCAを回していく業務を行っていただきます。 社内の営業や他関連部署…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Ruby / 週4日〜】VRを通じた新規…
VRクリエイターマッチングプラットフォーム、VRクリエイターツールの開発を行っていただきます。 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Cake・Rails | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
主に依頼する作業は、新しい機能のためにRDBを設計、CRUDのAPIを作成をお任せします。 RDB…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Play・Frame… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
累計10億超の資金調達を終え、IPOを目指す段階に入った国内No.1クラウドファンディングプラットフ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / Android/IOS /…
自社で運営しているWEBサービスのアプリ開発を担当いただきます。 仕様は既に固まりモック作成まで完…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Java / 週5日】広告系自社サービス…
ネイティブアドネットワークサービス、レコメンドエンジンサービス、コンテンツ集客に特化した広告配信プラ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java | |
定番
【PHP / 週5日】広告配信サービス開発…
自社サービスである広告配信システムの開発全般において、要件に基づき、依頼元の営業さんと調整を行ってい…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Ruby / 週5日】広告系自社サービス…
ネイティブアドネットワークサービス、レコメンドエンジンサービス、コンテンツ集客に特化した広告配信プラ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【AWS / 週5日】広告系自社サービスの…
弊社が手掛ける広告系自社サービスにおけるインフラ設計、構築、保守業務全般をお任せいたします。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・GCP | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
案件は大手ゲーム会社様でのオンラインゲームインフラの運用、構築を行っております。 オンラインゲーム…
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大森駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【コーダー】自社SEO対策用オウンドメディ…
【業務内容】 ・CMS上での記事入稿作業を行っていただきます。 └SEO&コンテンツマーケチーム…
週3日・4日・5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Vue.js / 週5日】法人向けオンボ…
大企業様向けのオンボーディング(新しく入社したメンバーが早期に活躍できるよう、組織としてサポートする…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
新規の写真サービス立ち上げに伴いiOSアプリで開発していただけるアプリエンジニアを募集しております。…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Java / 週3日〜】税理士・会計事務…
本プロジェクトでは Java で書かれたモノリシックなシステムを段階的に Scala でマイクロサー…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Scala | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現行システムの帳票画面の入力項目の修正を、主担当エンジニアの指示・アドバイスを受けながら実施していた…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
ゲームの背景を制作できるデザイナー
【業務内容】 ダークファンタジー(現代の街が崩壊した世界)、写実的なもの(洞窟、サイバー空間)、バ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸大阪 |
|---|---|
| 役割 | ゲーム背景デザイナー |
| SpriteStudio・AfterEffects | |
注目
[Unityエンジニア]開発及び技術基盤の…
自社プロダクトの開発及び技術基盤の改善を行っていただきます。 ■Unityを使用した新企業パビ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
大手ゲーム開発のプランナー
【業務内容】 ゲームのプランナー業務 ■稼働開始 即日 ■スキル ゲームの背景制…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸大阪 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
| SpriteStudio・AfterEffects | |
定番
【動画ディレクター】TVのCM制作の経験者…
【業務内容】 デジタルサイネージ(商品訴求が多い)などの動画ディレクターとして動画コンテンツの制作…
週2日・3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄博多 |
|---|---|
| 役割 | 動画ディレクター |
定番
【映像制作】商品PRなどの映像制作や編集業…
【業務内容】 デジタルサイネージ(商品訴求が多い)などの映像制作の実務業務 【使用ツール】 …
週2日・3日
140,000〜160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作 |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社サー…
・課題やニーズのリサーチ、事業インサイトの分析 ・プロダクト戦略の検討 ・サービスの企画、仮設検…
週5日
840,000〜1,700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java / 週5日】大手会計ソフトウェ…
会計システム(クラウド版)の課金部分の設計~テスト工程を担当いただきます。 プラットフォームを…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Struts・Seaser | |
定番
【PL】toC向け自社ECサイト開発(フル…
■業務内容 マーケティング支援会社で、toC向けのwebサービスを複数、開発運用しております。サー…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PL |
| JavaScript・PHP・CentOS・MySQ… | |
定番
【フロントエンドエンジニア|週3~5日・フ…
【案件概要】 当社では日本最大級のゲーム総合情報メディアを運営しており、今回はゲームメディアの新規…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Vue.js | |
定番
【サーバーサイドエンジニア|週3~5日・フ…
【案件概要】 当社では日本最大級のゲーム総合情報メディアを運営しており、今回はゲームメディアの新規…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・RubyonRails・Larav… | |
定番
【リードエンジニア|週3~5日・フルリモー…
【案件概要】 当社では日本最大級のゲーム総合情報メディアを運営しており、今回はゲームメディアの新規…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | リードエンジニア |
| PHP・Ruby・RubyonRails・Larav… | |
定番
【フルスタックエンジニア|フルリモート】顧…
【案件概要】 顧客向けFXシステム開発においてフルスタックエンジニアとして以下の業務に携わっていた…
週5日
390,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Li… | |
定番
【HTML/CSS / 週3日〜】新規ブロ…
新規事業における開発業務をご支援いただけるコーダーを募集しています。 ご自身のキャリアアップを目指…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PM / 週5日】銀行向けシステム企画・…
【企画】 ・プロジェクト管理、予算管理、請求処理 ・各ベンダーの選定、契約、折衝、検収 ・ユー…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東陽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
1. アプリUIの改善施策 *ユーザー体験の定義や導線設計、CTA設計など考えて デザインする…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【JavaScript / 週5日】リフォ…
【基幹システム再構築】 ・現行システムの再構築における設計、開発、テスト ・開発基盤の検討、実装…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王(六本木一丁目) |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringBoot | |
定番
【Rython / 週4日〜】考動分析ツー…
顧客が持つデータを使用し、AI技術でデータの価値を分析します。 解析技術よりデータ内容や分析結果を…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【React / 週3日〜】BtoB向けW…
・PCとスマホ両方の開発 ・自社サイトの更新・運用 デザインはデザイナーが行うため、エンジニアリ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【UI / 週4日〜】自社サービスに関する…
定期的に開催されるイベントや特集系のバナーのデザインを作成する機会が多いサービスです。 アプリの…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【Go / 週3日】APIの新規開発、保守…
• GoのAPIの新規開発、保守運用、バグ修正 • クライアントからの問い合わせの調査、対応 (…
週3日
350,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【PM / 週3日】Webシステム・Web…
Webシステム・Webサービスの開発のプロジェクトマネージャー・PMをお任せしたいと思っています。 …
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋日暮里 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Linux / 週5日】内視鏡AIサービ…
新規のPCに弊社のソフトウェアをセットアップするOSのインストーラーの作成及びカスタマイズをご担当し…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Linux | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週4日〜】…
プロジェクトの中心メンバーとなって新規で開発を進めていただける方を募集しています。 Unityの最…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【PM / 週5日】不動産データ顧客管理及…
不動産データの顧客管理システム、または物件管理システムの構築・管理をご担当いただきます。 現在、実…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| _ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
今回の案件の内容は、仮想通貨取引所のインフラ構築および構築に必要なソフトウェアコンポーネントの評価と…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
自社開発中のエンジニア向けアドテクPaaSサービスのフロントエンジニアを募集します。 社内外のエン…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
分析から改善、イラストの作成など、一貫した2つのサイトの維持改善業務になります。 主に次の2つのサ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅,新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
ノーコードで本格的な開発ができる開発OSSのサービス拡大に伴い、UI/UXデザイナーを募集しておりま…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
大きな顧客基盤を持つ自社採用管理システムの新機能追加や、新規開発案件をお任せいたします。 営業…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高輪ゲートウェイ駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Coldfusio… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・追加機能の基本設計 ・結合試験仕様書作成、試験支援業務 サーバーサイドのアプリ開発がメインにな…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
主にマーケティング活動で使用するWeb/グラフィックデザインの業務を依頼します。 業務比率→Web…
週3日・4日
190,000〜660,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
当社のサービス基盤を企画~開発~運用まで幅広く経験できる業務です。 ・当社が提供する決済システ…
週4日・5日
480,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【Java / 週5日】メディアサイトの会…
・メディアサイトの会員管理システムの要件定義、設計、実装、テスト、運用 ・会員管理機能(API、バ…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Seasar… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
弊社の複数プロダクトのAndroidアプリ、iOSアプリ開発を担当いただきます。 Androidア…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【Swift / 週5日】iPadアプリケ…
iPadアプリケーションソフトウェアの設計、コーディング、テストまでご対応いただきます。 -主に…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・XCode | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】A…
キーレス社会実現のために、アクセス認証基盤を構築し、マイクロサービス化されたサービス開発を行なってい…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ア…
顧客内にて開発を行っているアプリ開発支援 ・顧客折衝 ・要件定義 ・設計以降の開発見積作業支援…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP/JavaScrip…
日本国内の大手企業の課題解決や新規事業開発を目的としたDXコンサルティングを中心に事業を展開しており…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
・某ネット銀行様(エンドユーザー企業)での新規サービス構築、新認証方式導入などを設計、開発をメインに…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅、大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアントであるリフォーム業者のWebサイト・LPのデザインおよび改修。 アクセス数の増加といっ…
週3日・4日・5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
案件推進を行うPMO業務、システム構成/NW構成の検討、見積資料、定義書等の作成方針検討、テスト/P…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務。 …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手通信サービスのプロジェクト推進をご対応いただきます。 プロジェクト企画書や要件定義書を読み解き…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Java | |
定番
【Java / 週5日】大手医療系メーカー…
弊社は創業以来プライム案件にこだわる独立系SIerとして、様々な業種のお客様から直接案件を頂いており…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上前津駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・VB.NE… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。 現時点でワイヤー…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダッシュボード系シ…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
統合マーケティングの知見や、機械学習/統計解析を活用したデータ分析技術を可視化するダッシュボード系シ…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Typescript・‐ | |
定番
【Javaエンジニア】アプリケーション開発
【業務内容】 システムの企画・開発、及び保守・運用を担当いただきます。 構築するシステムは主に設…
週5日
440,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明石駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Python・Java・VB.NET・SQL・・ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社のトレーディングデスク事業部にてクライアントワークにおけるバナー、動画、ランディングページのWE…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・-・‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
UI/UXデザイナーとして下記業務に携わっていただきます。 ・立ち上げメンバーとのすり合わせからワ…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【Typescript / 週5日】AI証…
金融×AIに取り組む自社サービスのUI開発・改修業務。 深層学習(ディープラーニング)などのA…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【Java / 週5日】生命保険会社 Li…
Windows環境で構築されたシステムをLinux環境で再構築します。 DBをOralceからMy…
週5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
新しい機能開発やその周辺のツール開発を行います。 - API、WEBアプリケーションの設計、開発 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前/表参道 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・GitHub・AW… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
・ユーザ理解のためのユーザインタビュー・アンケート、ユーザ定義、ユーザ体験定義 ・コンテンツ案出し…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
婚活サービス領域で、集客のためのクリエイティブ(LP、動画バナー、バナー)を実際に手を動かして制作し…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【C# / 週5日】大手会計ソフトウェア開…
デスクトップ向け会計ソフトウェアの設計~テストまでを担当いただきます。 ・企画・要求定義から要…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【Java /C# / 週5日】大手会計ソ…
基盤システム部分の設計~テストまでを担当いただきます。 企画・要求定義から要件定義・設計・開発…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java・C# | |
定番
【Java / 週5日】大手会計ソフトウェ…
会計システム(クラウド版)の課金部分の設計~テスト工程を担当いただきます。 プラットフォームを…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・新規デスクトップ・クラウドアプリやWebサービスのUX設計 ・上記に付随したIA設計およびUIデ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・VC++ | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】新…
現行基幹システムが構築から20年ほど経過しているため、新基幹システムを構築します。 システムの統一…
週5日
670,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・-・ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】不動…
不動産管理業務を効率化するAIを活用したSaaSサービスと不動産・建築業界に特化した様々なコンサルテ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Typesc… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
Java/TypeScriptを使用したWebサービス(SaaS)開発で、下記2案件の開発に携わって…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・Next.js・ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自治体向け医療・介護関連データ利活用ビジネスに関するシステム開発 ・自治体が保有している介護及…
週5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
以下の業務を遂行するために、プロダクトマネージャーやエンジニアと協業しながら意思決定に関与頂きます。…
週3日・4日・5日
440,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿関内駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】カス…
カスタマーサクセス支援/顧客エンゲージメント向上ツールを提供しています。 まだまだ若い組織が故…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】デ…
・データドリブンを主導する部門様に対し、マーケティングデータ、アカウンティングデータからビジネス効果…
週5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・R | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】某…
・業務:宅配、店舗システムでのプロモーション再構築 ・対応工程:要件整理、要件定義、システム要件設…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C#・SpringBoot | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
システムインテグレーション スマートフォンアプリ開発、業務アプリケーション開発等様々な事業を行ってお…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
自社製品の開発 ・お客様要望あるいは製品として必要な機能の改修および新規開発 ・ご対応いただきた…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・spring | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社製品の開発 ・お客様要望あるいは製品として必要な機能の改修および新規開発 ・ご対応いただきた…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
受託開発の会員サイトのWEBページ開発に携わっていただきます。 コーディングが得意な方や、サーバー…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川青物横丁駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】受託案件の…
自社アプリケーションの開発およびシステム開発保守等を行う企業です。 会員サイトのフロントエンド開発…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 品川青物横丁駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
現在開発中のブロックチェーンを使ったサービス開発に伴いコーダーの方を募集しております。 新しい技術…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】コーポレー…
ソフトウェアの品質保証・テストの専門企業において、コーポレートサイトの改修や企業の情報発信におけるW…
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【Ruby / 週5日】日本初のサロン予約…
新しい機能開発やその周辺のツール開発を行います。 - API、WEBアプリケーションの設計、開発 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前/表参道 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・GitHub・AW… | |
定番
【Java / 週5日】AI証券システムの…
金融×AIに取り組む自社サービスの開発・改修業務を担って頂きます。 深層学習(ディープラーニン…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・springboot | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
機械翻訳関連サービスのインフラ管理を担当していただきます。 AWSを管理している現担当者の既存…
週3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつかある…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・・- | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつかある…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・- | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつかある…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・- | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつかある…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】医療…
診療所における経営サポートシステムのフロントエンド開発をお任せします。 世の中には予約管理システム…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / SalesForce…
・新しい事業を成功させるための業務フローシステム構築 ・各事業の会計数値を集約、分析するための基盤…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
| Ruby・Salesforce・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
ポイントサイトとポイント交換サービスの開発、運用を担当していただきます。 ・既存機能の改善と新…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
GPSやWiFiデータなどの電波情報から屋外だけでなく屋内の位置測定もできるシステムを開発。 …
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・LAMP・G… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】動…
業務テーマとしては、国内有数の大手メディア企業が収集するビッグデータの動画視聴データ基盤の開発・保守…
週5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| GCP(BigQuery・CloudFunction… | |
定番
【Ruby / 週4日〜】VRを通じた新規…
VRクリエイターマッチングプラットフォーム、VRクリエイターツールの開発を行っていただきます。 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Cake・Rails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
社内外に提供しているシステムの、運用業務における課題を改善する活動を担当していただきます。 直近で…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / jQuery / 週3日〜…
Web接客サービスで想定されるシナリオを、クライアントである企業様に合わせて、シナリオ事例集としてコ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅、東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / swift / 週3…
昨年停止したアプリを本年度稼働するための対応をお願い致します。 ・広告SDK(adjust)対応 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
ご経験によっては、設計/コーディングだけでなく、オリジナルデザインの管理を行っていだたく場合もありま…
週3日・4日・5日
330,000〜820,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅、末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・Sass | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
・スポーツクラブ、インフルエンサー、アイドルなどのサービス内外に出す広告物/バナー画像/LPなどの制…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
戦略的ウェブマーケティングの総合支援をおこなっている当社で、新規のマーケティングツールを開発いたしま…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【Ruby / 週5日】自社インターネット…
自社にて運営している3つのサービスの企画、開発、運営に携わっていただきます。 ・AWS または…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rails・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
フロントエンドエンジニア(DMP事業) 自社開発提供を行うDMPのダッシュボード開発をご担当いただ…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Rails・… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
自社で開発と運営を行っている、シェアリングアプリ内のレイアウト調整を行っていただきます。 新規…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava | |
定番
【GOエンジニア】クラウド型勤怠管理システ…
・既存サービスのデータを利用して、アプリの開発環境を提供するサービスの構築 ・β版の開発を実施、今…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Go・C# | |
【Typescript】クラウド型勤怠管理…
・既存サービスのデータを利用して、アプリの開発環境を提供するサービスの構築 ・β版の開発を実施、今…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【コンテンツマーケター】事業に関する広告運…
・広告やSNS投稿の入稿・配信設定 ・ユーザーデータ、配信広告分析のための集計/レポーティング業務…
週3日・4日・5日
250,000〜380,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西18丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | コンテンツマーケター |
定番
大手QRコード決済会社証券における口座開発…
①開発保守②障害対応③問い合わせ対応 ①社内ユーザー部門から要望を聞き、現行システム調査、要件整理…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Fue… | |
【マーケティング】中小企業顧客へのマーケテ…
【業務内容】 MAツール活用 Marketoを利用し、LPの制作・改善、メール、SFDC連携 …
週3日・4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケティングコンサルタント(販売部門) |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社BtoB WEBサービスのアーキテクチャの設計や技術選定、開発、運用をお任せいたします。 ソー…
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Kotlin / 週5日】動画配信プラッ…
動画配信サービスにおいて国内トップクラスの経験を持つCTOをはじめ、優秀なメンバーによる少数精鋭のチ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【Go / 週5日】自社サービス恋活マッチ…
恋活マッチングアプリのWebサービスに精通したサーバサイドエンジニアとして、大規模プロジェクト、新規…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【C# / 週5日】メール移行アプリケーシ…
NotesメールをPSTファイルやExchangeへ移行する弊社プロダクトの改修作業をお願いします。…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C# | |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】施設予約…
全体的な業務指示は、弊社PLより実施致します。 構築 :画面や機能の構築 テスト …
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
自社インキュベーション事業部で始める新規事業、動画配信サービスの立ち上げにて、サーバーエンジニアを募…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・LAMP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社運営の医療系webメディアおよび新規事業のデザイン業務をお任せします。 ・コミュニティサービス…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアントを理解した上で、保守性や拡張性を意識したコーディングを行っていただきます。 新規/既存…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・es2015… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
- 各種ツール・フレームワークの選定 - HTML、CSS、JS のコーディング - リリース後…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / Go/PHP / 週5日】…
既存および新規プロダクトのAPI、Webアプリケーション設計、開発をお任せいたします。 その他、他…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
某ビッグデータの予測モデル開発の自動メタ化/自動記事化、自動字幕化をお願いできる方を募集します。 …
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・R | |
定番
【JavaScript / 週3日〜】新規…
貿易×ITのシステムを開発している当社にて、開発実務とエンジニアの育成をお任せするリードエンジニアを…
週3日・4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
業界はエンターテーメント系、アパレル系、不動産系、位置情報系等のさまざまです。 ネイティブ言語のみ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝公園駅、大門、浜松町、赤羽橋 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
[ディレクター]企画段階からサービス設計、…
企画段階からサービス設計、開始後の運用・改善まで一貫して担当いただきます。 ■どうすれば子ども…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【フルリモ / セキュリティ / 週3日〜…
セキュリティエンジニアとしての経験がある方を探しています。 大手でも開発が難しいセキュリティ製品を…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
リードエンジニアとして、下記業務を対応いただきます。 ・プロダクト新機能の仕様設計 ・Cak…
週4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・LAMP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービスの管理画面改修や機能追加などを行っていただきます。 具体的な業務内容としては下記を想定…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Node.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
アプリのサーバーバックエンド全般に関する業務を行って頂きます。 ・モバイルアプリのサーバーサイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
・インサイトの抽出 ・ユーザーシナリオ、カスタマージャーニーマップなど作成、ユーザーの一連の体験…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
・Unity/Unrealの得意なエンジニア ・VR/AR/MRが得意なエンジニア ・ゲーム制作…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【Ruby / 週3日〜】CS(顧客満足)…
CS(顧客満足)領域に関するSaas型自社新サービスを開発中。 ステータスとしてはプロトタイプは…
週3日・4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
昨年停止したアプリを本年度稼働するための対応いただける方を募集します。 ・最新verへの対応 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
昨年停止したアプリを本年度稼働するための対応をお願いできる方を募集します。WEBビュー部分の開発(一…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
・「スマホアプリ/スマホサーバ」と「決済システム/会員管理システム」の間を取り持つAPサーバ(機能)…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・WebAPI | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】見…
見積比較サービス開発を受託しており、要件定義から開発までご担当いただきたく考えております。 U…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
オープンイノベーションのプラットフォームサービスの開発に携わっていただきます。 サーバーサイドはR…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
プロトタイプ開発が終わり、本開発のスタートタイミングです。 ChatbotとAI Webシステム…
週5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【PHP / 週3日〜】社内SE業務
弊社の情シス = ユーザーサポート 〜 ASP設定、業務効率化支援、ハードウェアのお守りあたりをメイ…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】若手…
コミックアプリに付随する、既存および新規プロダクトのAPI、Webアプリケーション設計、開発をお任せ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【インフラ / 週4日〜】コミックアプリの…
自社で運営しているコミックアプリの開発。 ・オーケストレーションツールを使用したインフラ設計/運用…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
個人事業主の向けの確定申告サービス開発 ・Webアプリケーション開発 ・新規機能の開発 ・不具…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
昨年停止したアプリを本年度稼働するための対応をお願いできる方を募集します。 ・最新verへの対…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】電気機器…
監査プロセス標準化・効率化(データ利活用)の施策のグループ内展開、データレイクの経理・財務業務、監査…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社プロ…
弊社の複数事業において、横断的にスクラムマスターとしてプロジェクトを円滑に進めていただきます。 …
週5日
660,000〜1,980,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Photoshop / 週…
ゲーム内に展開されるキャラクターの衣装デザイン制作を担当します。 ※Windows環境での業務とな…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ゲーム、マッチングアプリ、VRなど様々な事業を展開し成長を続けている企業です。 今後市場が伸びるこ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【PHP / 週5日】コンシューマ向け情報…
・設計、実装、テスト(単体・結合)、リリース作業、保守作業 ・基本的には上記作業を行っていただきま…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・smarty・AWS・… | |
定番
【AWS / 週5日】コンシューマ向け情報…
・業務拠点:築地市場(エンドユーザ社内) ・AWSサーバーの運用・管理・監視 ・コンシューマ向け…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・AWS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
国内最大級のクラウドソーシングのプラットフォームのマークアップエンジニアを募集しています。 ユーザ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【ライティング】自社サービスのメルマガやL…
チャットボットを実運用し、その結果データを分析した上で、シナリオの改善 - 実運用データを分析し…
週4日・5日
250,000〜530,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | シナリオライター |
定番
【C# / 週5日】受託開発をしているゲー…
弊社はVFX、スカルプティング、モデリング、アニメーション、エンジニアリングを統合的に制作できるVF…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C・C++・C#・Unity | |
定番
【グラフィック / 週5日】受託開発をして…
弊社はVFX、スカルプティング、モデリング、アニメーション、エンジニアリングを統合的に制作できるVF…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Maya・Photoshop | |
定番
【C# / 週4日〜】自社駐車場管理システ…
車両ナンバー認証カメラで車をデジタル管理することを特徴とする自社駐車場管理システムを自社で開発し、運…
週4日・5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C# | |
定番
【Ruby / 週5日】ゲーム開発のサーバ…
ソーシャルゲームやエンターテイメントサービスの企画、開発、運用をご担当していただきます。 本人のご…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【C/C++ / 週5日】ゲーム開発のクラ…
ソーシャルゲームやエンターテイメントサービスの企画、開発、運用をご担当していただきます。 その中で…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Ob-C・C・C++・Cocos2d-x | |
定番
【Unity / 週5日】ゲーム開発におけ…
運用中開発タイトルにおける下記業務をご担当していただきます。 ・画面遷移制作 ・画面レイアウト制…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ₋-・₋- | |
定番
【NW / 週5日】ネットワーク設計構築業…
NW以外にもサーバ、クラウドのSaaSなどの様々な案件があるため、 興味を以って自身の対応範囲の拡…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【HTML/CSS / 週3日】植物を通し…
少しでも多くの方にみどりのある暮らしと、植物を通したコミュニケーションを体験して頂き、豊かな暮らしの…
週3日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週3日〜】自社新規…
PC・スマートフォンのwebマーケティング、web制作、メディア運営を行っております。 自社新…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Azure / 週5日】出金管理システム…
業務詳細:出金管理システムの画面開発をお願いいたします。 主にHTML(Angular)、Rest…
週5日
720,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Azure | |
定番
【SQL / 週5日】出金管理システム開発…
業務詳細:出金管理システム開発におけるSQLServer設計、チューニング、ストアドプロシージャの作…
週5日
720,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| SQL・Azure | |
定番
【PHP / 週4日〜】広告運用に関する自…
マーケティングツールの開発並びに運用・解析などのコンサルティングを行う企業です。 今回は自社で運営…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神楽坂 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【PHP / 週5日】大手クライアンント向…
小売業様のEC・POS等の刷新が中心となり、その上でフロント側でアプリ等、バック側で基幹や物流等、多…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社の交通費精算や営業支援クラウド型ツールで提供しているアプリのデザインを主にご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【Unityエンジニア】アプリケーション開…
【業務内容】 製品開発に役立つVR/AR/MRアプリケーション開発 プロモーション用XRコンテン…
週3日・4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸明石駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Scala/GCP / 週…
【業務内容】 ・チャットボットの改修・機能追加・運用業務 【求める人物像】 分からないこと…
週5日
500,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・GCP・・kubernetes… | |
定番
【Go】動画配信サービスにおけるサーバーサ…
案件内容: 動画配信サービスの開発をご担当いただきます。 アジャイル開発で進めています。 …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・golang・gin・AWS・RDS・Gith… | |
定番
【VB.net】ERPシステムカスタマイズ…
【業務内容】 受託開発を行っているERPシステムのカスタマイズ・保守についてご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝浦ふ頭駅 |
|---|---|
| 役割 | VB.NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
[アニメーションデザイナー]新規パビリオン…
自社プロダクトのアニメーション作成をメインに、UI設計など幅広く携わっていただきます。 ■Un…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アニメーションデザイナー |
【Swift】iOSアプリエンジニア
iOSアプリのコードの理解 iOSアプリの新規機能開発・既存機能改修 iOSアプリ開発チームメン…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSアプリエンジニア |
| Swift・Swift・Xcode・RxSwift・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】某大手事…
webシステム開発・アプリ開発をメインに、ニーズに沿った受託開発やSESで対応しております。 ソリ…
週5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】
受託制作/開発事業を運営中です。 今回は、Web制作の案件を中心に受託(Webサイト制作、CMSを…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週5日…
SaaS事業として、クライアント先のマーケティングDXを推進させるツールを自社内で開発・提供していま…
週5日
580,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
自社Webサービスの設計・開発、AWSを 中心したインフラ運用をお任せします。 具体的には、 …
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・PostgreSQ… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
グループが運営するサービスのiOS/Andoridアプリの開発・運用を担当します。 具体的には…
週5日
550,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・Ob-C・Kotlin・Lin… | |
定番
【フルリモ / PHP/Ruby / 週5…
当社が運営するサービスのAPI・WEBアプリケーションサービスのサーバサイドの開発・運用を担当いただ…
週5日
550,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Perl・… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
スマートフォンアプリケーションの開発と運用です。 主にスマートフォンアプリケーションのクライアン…
週4日・5日
610,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Go・Node.js・Ma… | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
広告導入に関する技術面での課題解決を担当していただきます。 メディアソリューションパートナーとして…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
新しいシステムを作成予定で、写真プリントをインターネットを介して注文を受けるラボのシステムが対象。 …
週5日
300,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉赤羽駅からバス10~15分 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・MySQL | |
定番
【PHP / 週5日】大手カメラ販売サービ…
大手カメラ販売サービス会社が手掛けるECサイトのシステムの見直し検討および改修業務支援。 シス…
週5日
300,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・MySQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
現在サービスはプロトタイプを使ったテストを実施している段階で、本格的な製品開発に向けて体制を構築し始…
週4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ゲームを始めとした、弊社の提供する製品やサービスのWEBプロモーションに関する制作業務全般に携わって…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社運営の3サービスの開発および開発メンバーのフォローアップを支援いただける人材を募集しております。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅、広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby・CakePHP・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
アパレル系ECサイトの運営や住宅系CRMシステムの運営など何れのプロジェクトでも、以下の業務を中心に…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅、大門、浜松町、赤羽橋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
大手不動産企業版へのカスタマイズ開発。 大手不動産会社向けカスタマイズ版の開発に際して、先方へ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
ビジネスコンサルティングから入って、プロトタイプ開発、実装までを受けている会社です。 WEB開発チ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木広尾駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
「生産者支援」を手掛けるスタートアップです。 ITを活用した農畜水産物の流通支援プラットフォームを…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社で運営するスポットコンサルサービスのWebサービスのUI/UX・パフォーマンス改善のために、フロ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
フロント画面や管理画面等の開発をお任せしたいと考えてますが、ご本人の志向性や希望に応じて、サーバサイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
フロント画面や管理画面等の開発をお任せしたいと考えてますが、ご本人の志向性や希望に応じて、サーバサイ…
週4日・5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
子どもの世界観、遊びの世界観を大切にしたいという弊社の考えに共感していただける方を希望です。 …
週3日・4日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 品川大井町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
店舗(エンドユーザー)向けの業務自動化ツールの開発業務。 自社サービスの開発であり、かつ全国…
週5日
480,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】住宅…
住宅ローンサービスのレスポンシブサイトの開発支援をしていただきます。 具体的には、 ・サー…
週5日
310,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿宝町駅、京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・Java8・Node.js | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
業界屈指のインフルエンサーマーケティングプラットフォームのサービス開発を担当頂きます。 個人…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・react.… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
業界屈指のインフルエンサーマーケティングプラットフォームのサービス開発を担当頂きます。 個人…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Java・Node.… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Ruby /…
・小〜中規模サイトのCMS構築 ・大規模サイトのバックエンド開発 ・Webアプリケーションの設計…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京上野駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
広告配信システムプラットフォームの開発業務を行っていただきます。 ・第三者配信プラットフォー…
週3日・4日・5日
390,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Vue.js・An… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
プロダクトマネージャー、エンジニアと協力し、ユーザーに最高の体験を届けるためのリサーチ、プロトタイプ…
週4日・5日
390,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
太陽光や風力などの自然エネルギー活用システムの制御ソフト開発など、積極的に事業を展開していきます。 …
週5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅/鹿島田駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】イン…
太陽光や風力などの自然エネルギー活用システムの制御ソフト開発など、積極的に事業を展開していきます。 …
週5日
390,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿武蔵溝ノ口駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
メガバンクの預金システムや大手クレジット会社のポイントシステムなど多数の企業様のシステム開発を受託し…
週5日
300,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
業界屈指のインフルエンサーマーケティングプラットフォームのサービス開発を担当頂きます。 個人へ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【Python / 週5日】発電システム開…
発電予測プログラムの開発です。 大手顧客の事務所に常駐して、クライアント企業担当者と共に業務システ…
週5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 神奈川溝の口 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
VMウェア、オラクルなどでの構築系SEの募集をしています。 (上流工程可能な方) ①ORACLE…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
AdTech企業にて、 ・DSP/DMP で生み出される大規模なデータを分析するための基盤作り …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Go・C・C++・R・Apache・H… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
中古車事業会社におけるフロントエンドシステム技術支援 ・関われる技術 Ruby(onRail…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
・サービスの開発・保守 ・外部API連携 自社サービスアプリの開発・保守をお任せします。 その…
週5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】メディ…
同社プロパー社員の方が、PM、webエンジニアとして参画するプロジェクトへの増員です。 大手メ…
週5日
440,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| PHP・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
自社開発&運営している新規・既存ゲームタイトルのUI/UXデザイン及びディレクションを担当して頂きま…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
タクシー車載器になるアンドロイドタブレットのアプリケーション(ナビ、無線機、そのほか営業支援等)開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川新馬場駅、大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | AndroidJavaエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
通信事業者の一般コンシューマー向けスマホ販売ECサイトの要件定義チームでのお仕事です。 要件定義…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
安心安全は前提のもと、美味しさにこだわった食材・商品を、使いやすく、また思わず買いたくなるようなサイ…
週5日
260,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
BitcoinやEthereumなどブロックチェーン技術に関わるプログラミング、設計、ドキュメント作…
週4日・5日
500,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | ブロックチェーンエンジニア |
| JavaScript・Java・C#・Node.js | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
同社の中心プロダクトでもある、スマートフォン広告ソリューションツールの国内・海外でのサービス展開をさ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
オープンソースCMSを活用したWeb構築に伴う業務を行っていただきます。 ・オープンソースCMS…
週5日
480,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】会員マ…
CMSベースの会員マッチングサイト開発に携わっていただきます。 ・PHPプログラム開発 ・モジュ…
週5日
260,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
CMS/HTMLの設計/制作を行っていただきます。 ・Drupalのテーマ制作、画面制作 ・Ja…
週5日
260,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・BitcoinやEthereumなどブロックチェーン技術に関わるプログラミング、設計、ドキュメント…
週4日・5日
500,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・C#・Node.js | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
新規プロジェクトにおいてデザイン業務を担当していただきます。 単純なページデザインだけでなく、PL…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML / 週3日…
コーポレート、サービス両軸でブランディングを構築する部署において、 様々なデザイン業務に取り組んでい…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅、中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Andoroid /…
スマートホームセキュリティアプリのAndroidアプリの設計・開発エンジニアを募集しています。 …
週3日・4日・5日
250,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Andoroidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
スマートホームセキュリティアプリのiOSアプリの設計・開発エンジニアを募集しています。 防犯・ホー…
週3日・4日・5日
250,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・各種サービスへの入り口となるサイト(PC、スマートフォン、携帯)、一部会員向けサービスについての保…
週5日
350,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Struts | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
下記のいずれかに携わっていただきます。 ・自社製品開発(通信・IoT関連) CTIシステム、I…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄博多駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
・広告サーバーのエラー確認・問題修正 ・広告サーバーの追加機能開発 ・広告サーバーのテスト実施(…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】顧…
自社にてECサイト・口コミサイトを開発運営している大手企業でのアプリ開発案件になります。 リモート…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Java / 週5日】共通部品開発におけ…
ビジネス側からの要求の整理と、それに伴う要件定義業務の実施 要件定義を元にした基本設計・詳細設計・…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Kotlin・Spring・… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】Aut…
・SAPERPがS/4HANAへ移行されるため同時にロボットの改修を行う ・現行v11+SAPER…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】Io…
ドローン、IoT製品等からのデータをクラウド上で処理し解析するプラットフォームの新規開発。 製…
週5日
440,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
睡眠に関するヘルスケアアプリを自社で開発しています。 立ち上げたばかりのスタートアップ企業で、…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】電子申請…
・電子申請システムとの連携システム開発(画面、ビジネスロジック) ・10画面程度の画面製造と外部シ…
週5日
440,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| C#・NET・Framework | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手メディア運営会社で、webとも連動したSNSアプリ(iOS/Android)のリニューアル案件で…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
① HTML/CSSを用いた、弊社プロダクト内テンプレートの作成 ② コーポレートサイト/プロダク…
週3日・4日・5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木銀座駅、東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
データ分析やユーザーインタビューに基づき、ユーザー目線でサービス改善を行い、新規ユーザー・リピーター…
週3日・4日・5日
470,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
【Java】サーバーサイドエンジニア
・健診機関向けに提供する健康診断予約システムへの問合せに対する回答、調査、個別カスタマイズの対応等 …
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・C# | |
定番
AWS移行支援
・インフラの要件定義検討支援 ・ドキュメント作成(インフラ要件定義書/構成概要図) ・現行システ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・Windows・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
ネットバンク系システムのソリューション開発をお願いできる方を募集します。 クラウド、OSSを利用し…
週5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Framework・Git・… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】Pos…
暗号化PKGの完全リプレース案件です。 Oracleで構築されたものをPostreSQLに移行しま…
週5日
700,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL・PostreSQL | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
弊社が運営するファッションECサイトのコーディング業務を行っていただきます。 具体的にはHTML、…
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京宝町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
当社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のアプリ開発を担当していただきます。 少人…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| React・Native | |
定番
【リモート相談可 / DB / 週3日〜】…
オンラインカジノの市場において、 データマイニングは売り上げに直結するため、 単純なデータ解析ではな…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野毛駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
クライアントが保有する様々なデータを統合的に分析・解析できるようなデジタル系のプロダクト開発を進めて…
週3日・4日・5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
クライアントが保有する様々なデータを統合的に分析・解析できるようなデジタル系のプロダクト開発を進めて…
週3日・4日・5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
プログラミングスクールのマーケティング部門で、インハウスデザイナーを募集します。 業務の幅は広く、…
週3日・4日・5日
360,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】記帳業…
サービスの中心部を支えるチームにてデータ化システムの開発 アジャイルベースでの開発手法をとっており…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】セールス…
・開発チームのテックリードとして技術的意思決定と開発推進及びチーム構築。 ・PMやメンバーとの開発…
週5日
840,000〜2,400,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
PM【英語】
M365に関して、日本本社海外G会社との責任・対応範囲を明確にし、海外の責任部分については、海外各社…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】保険会…
保険会社向けSaaSを開発するプロダクトチームで、開発を円滑に進めるためのプロジェクトマネジメントを…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿梅田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
新設されました社内システム構築等の開発および分散しているデータ収集などを担当していただきます。 顧…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ご対応頂きたい内容として、 ・給与前払いシステムのフロント、バックエンド(API、バッチ、管理画面…
週5日
480,000〜950,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋淡路町駅、小川町駅、御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・LAMP環境(Fuel… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週5日】建…
社員の経費精算等を行う出金管理システムを全面リプレースします。 共通基盤・画面・処理・社員用スマホ…
週5日
500,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・Java・Swift・Ob-C・A… | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
複数ベンダーが関わっているリニューアルPJのPMの支援を行っていただきます。 主な作業は以下の通り…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PHP / 週5日】Fintech企業内…
当社は資産運用のコンサルティングを主軸に、ソーシャルレンディングサービスを展開しております。 現在…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
自動車をはじめとする移動体から走行データを収集し、それを可視化・解析することでサービスに活用します。…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
お客さま相談室専用システムにおいての顧客との機能追加の打合せや要件定義、仕様書作成、開発チームへの指…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
当社が開発を手がけるシステムは、お客さま窓口の業務負荷を軽減するシステムとなり、下記業務をを担当頂き…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Redux・React | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
プラットフォームの設計・構築をご担当いただきます。 ・本番/テスト環境の構築 / 監視設定 ・開…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
デザイナーやサーバサイドエンジニアと協力し、名刺管理サービスのiOSアプリの開発をご担当いただきます…
週3日・4日・5日
520,000〜990,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
現在自社動画サービスを開発しており、iOSアプリ、Androidアプリ、Webにて展開しております。…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週4…
システム対象業務として、 ・引合い管理 ・受注管理 ・取引先管理 ・クレーム管理 ・工事管…
週4日・5日
480,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
Androidアプリ開発案件です。 企画から始まるプロジェクトも多く上流工程から携われます。 サ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
アパレルのiOSアプリ開発案件です。 企画から始まるプロジェクトも多く上流工程から携われます。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS/ 週3日…
データ分析やユーザーインタビューに基づき、ユーザー目線でサービス改善を行い、新規ユーザー・リピーター…
週3日・4日・5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
iOS/Androidアプリ開発をお願いします。 企画から始まるプロジェクトも多く上流工程から携わ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
弊社取引先のアプリーケーション開発を担当頂きます。 主にシステム化対象業務をお任せします。 …
週4日・5日
480,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】W…
弊社グループ企業のアプリーケーション開発を担当頂きます。 企画から要件定義、設計、開発、テスト…
週4日・5日
480,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
将来を見通したマイクロサービスアーキテクチャを設計し、マイクロサービス毎に組成されたチームメンバーと…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
広告配信システムや、位置情報ベースの検索APIシステムなどの新規サービス開発に携わっていただきます。…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Scala・finch・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
新サービスの立ち上げに伴い、フロントエンドエンジニア(フロントコーダー)の方を探しております。 …
週3日・4日・5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄木駅、代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】仮想通…
将来を見通したマイクロサービスアーキテクチャを設計し、マイクロサービス毎に組成されたチームメンバーと…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
位置情報活用型のマーケティング支援プロダクトである、自社プロダクトの、マーケティング 分析 機能のア…
週4日・5日
480,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ファッションアイテムのサイズレコメンドエンジンを作り提供しています。 身長、年齢と簡単なアンケ…
週3日・4日・5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
Web サービスの運用、及び新規開発に関わる HTML・CSS のコーディング業務を担当していただき…
週4日・5日
390,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / HTML / 週5日…
デザイナーが作成した素材を元にコーディングして頂きます。 メイン画面内にタブが複数あり、それぞれ別…
週5日
390,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Java…
ウェアラブル楽器ガジェットの開発やAI作曲ソフトの開発など音楽に関するサービスを開発・提供する企業に…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
他デザイナーや、エンジニア、マーケター等と協働し、UIによる問題解決と事業の成長を主導いただきます。…
週3日・4日・5日
520,000〜990,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】自…
自社サービスのソフトウェア開発に関するプロジェクトのプロジェクトマネージャーの役割を担って頂く方を募…
週3日
260,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
事業者向けの広告配信プラットフォームのUI開発をお任せいたします。 ・モダンな開発環境でスキルを積…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
GPSやWiFiデータなどの電波情報から、屋外だけでなく屋内の位置測定もできるシステムを開発。 …
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・LAMP・A… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当社で展開しているチャットフィクションアプリのWEB版及びiOS/Android版のWEBビュー部分…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅、中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社サービスのWEBデザイン、コーディングをご担当頂きます。 既に公開している自社サービス2つに…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
プロダクトのUI/UXを刷新したいデザイナーの方を募集しております。 「サービスの世界展開」「…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
事業をグロースさせるデザインチームをつくるためのプロダクトデザイナー(UI/UX)の募集になります。…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
Web/HP制作依頼のニーズが高まったきたため、CMSやWordPressカスタマイズ、PHPまでで…
週3日・4日
190,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
既存メディアの機能追加・改修、(可能であれば)若手のサポートやインフラ周りの作業など、任せられる方を…
週3日
190,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・WordPress | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
WEBサイトリニューアルに際してDBの設計・構築を担当して、その後にサーバーサイドをメインの開発を行…
週3日・4日・5日
500,000〜930,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・広告を掲載するサイトに合致するデザインでのコーディング -約50メディア/月 -用意してあ…
週5日
220,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
以下の業務がメインとなります。 ・iOSアプリの設計・開発・運用 ・Swift ・UI/UX改…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
業界随一のインストールベースを持つインテリア・コーディネートのための3Dシミュレーターの次世代版を自…
週3日・4日・5日
520,000〜930,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿江戸川橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
排泄予測デバイスを用いた IoT サービスに関するソフトウェア開発(iOS用アプリ)と、そのチームリ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| PHP・Python・Java・Scala・Swif… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
* ディレクターとの議論を通した、機能要件の定義 * Go / Vue.jsによる各種機能開発 …
週4日・5日
500,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・-・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】フ…
新しくリリース予定のフラッグシップサービスの開発を行っていただきます。 リリース後の運営は自社内で…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
今回は特にLPのデザイン〜コーディングをお任せしたいと考えています。 ※業務にはディレクション…
週4日・5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】ソー…
以下業務をご担当いただきたいと考えております。 ・インフラ移行とサーバの見直し、最適化 ・弊社の…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社内で使用しているシステムの大幅なリプレイスプロジェクトが予定されております。 そちらのアプリケ…
週4日・5日
410,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】新会…
日本最大級CtoC向けフリマアプリにて月イチ払いができる機能実装をお手伝い頂きます。 作業内容は機…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】新会…
日本最大級CtoC向けフリマアプリ・Web版の決済周りの機能改善をお手伝い頂きます。 作業内容は、…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】新会社…
CtoCマーケットプレイスで培った膨大な情報をもとに、新しい金融・決済事業を新しく始めるにあたりエン…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
-Androidネイティブアプリ開発 -ペイメントSDKの設計・開発 -バックエンド(新開発のM…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Andoroidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
今回ご対応頂く業務としては今後様々なPRをするにあたりキャンペーンサイトやLPのデザイン・作成が出来…
週4日・5日
330,000〜950,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python/Rub…
弊社の各プロダクトが利用する、バックエンドサービス(アカウント管理、プロダクト管理、認証基盤、オンラ…
週4日・5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
睡眠に関するヘルスケアアプリを自社で開発しています。 立ち上げたばかりの当社で、事業企画から関わり…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React.js / 週5…
AIを活用したSNSマーケティング運用支援プロダクトのUI設計開発をしていただきます。 ソーシャル…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・React.js | |
定番
【リモート相談可 / Java/Ruby …
ソーシャルビッグデータとAIを活用し、フロントエンドはreact.js、バックエンドはServerl…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋、九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・React.js | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
バックエンドエンジニアを募集します。 プロダクトのサーバーサイドAPIの実装をしていただきます。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋、九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby/Python /…
・自社アプリのサーバーサイドの開発・運用・保守 ・外部サービスとのシステム連携 ・UXデザイナー…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Spring・Fr… | |
定番
【COBOLエンジニア】自治体向けの開発案…
【業務内容】 自治体に対して、法律改正に伴うシステム改修。 具体的には設計書の修正、COBOLの…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 千葉海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | COBOLエンジニア |
| COBOL・・ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
就職・転職クチコミ・リサーチサイトのUX/UIの設計・デザイン・実装 ・ワイヤーフレームの作成 …
週4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
自社Webサービスの新規機能開発およびシステム保守。 業務は、ビジネスサイドのメンバーと打ち合…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアント様オフィスに常駐し、弊社フロントエンド制作チームの一員として業務いただきます。 …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
Adobe AIRを用いて開発していたデスクトップアプリケーションを、高速化・安定稼働を目的としてブ…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
インフラ(NWを除く)全般の運用保守部隊の上級SE(リーダー格)として、顧客となるグループ会社との要…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】要件定…
インフラ(NWを除く)全般の運用保守部隊の上級SE(リーダー格)として、顧客となるグループ会社との要…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】健…
健診代行サービスシステムのマスタ設定等を行う機能の開発が中心ですが、その他の機能開発等も担当していた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木四ツ谷 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・.net | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】大…
・OS/ミドルウェアのバージョンアップ ・各種ハードウェア、OS/ミドルウェアの環境パラメタ設計 …
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| .net | |
定番
【フルリモ / PHP/Java / 週4…
Webアプリケーション開発、またはスマートデバイス向けアプリ開発作業全般をお願いします。 企…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるフロントエンド側の開発業務をご担当いただき…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
・Webサイトの改善施策の提案 ・主にフロントエンドの開発、改善 ・コードレビュー、テスト …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
アプリ分析支援事業で培った知見を活かした、スマホビジネスのワンストップソリューションを提供している企…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Android… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
アプリ分析支援事業で培った知見を活かした、スマホビジネスのワンストップソリューションを提供している企…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Xcode・Firebase | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
アプリ分析支援事業で培った知見を活かした、スマホビジネスのワンストップソリューションを提供している企…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
人工知能での機械学習を用いて、人や組織に最適なニュース記事をレコメンドするサーバーサイドエンジニア募…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】シス…
受託案件の開発を進める為の増員募集です。 業務支援の商材(比較サイト)の立ち上げをお任せいたします…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
大手携帯キャリアと共同開発を行っている、AIチャットボットの新機能追加・運用・保守業務をご担当いただ…
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
・「プロダクトコンセプト」を体現し、実感できるプロトタイプの開発 ・仮設設定、リサーチ、UX設計…
週4日・5日
410,000〜630,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| JavaScript | |
【グラフィックデザイナー(Webデザイン含…
【業務内容】 ・広告のデザイン業務 └グラフィックデザイン、Webデザインの割合は要相談だが、グ…
週4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
【Python】データ編集スクリプトの開発…
【案件概要】 弊社ツールの新規利用企業のデータ移行のための インポート作業を支援いただける方を募…
週2日・3日
250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町(千代田区) |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
現在、優先して募集しているのは、フロントエンドのエンジニアです。 Nuxt.js、Vue.jsの実…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Nuxt.js・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
UI/UXを考慮したデザインとコーディングまでお任せいたします。 幅広くスキルアップを目指すデザイ…
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
在宅医療や医療機関システムの効率化を進め、 次世代に還元できる社会システムの構築を推進したいと考えて…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
在宅医療や医療機関システムの効率化を進め、 次世代に還元できる社会システムの構築を推進したいと考えて…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・WEBサイトの更新業務・ページバナーの制作業務 ・分析ツールを基にしたUI/UXの改修企画・実行…
週3日
70,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿用賀駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】WE…
ヘアサロン向け専売品の製造・販売を目的としたプロフェッショナル事業、一般市場向け製品の製造・販売を目…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
・デザイナーおよびバックエンド実装者と連携したUIの構想・設計 ・ UI構想を踏まえたバックエンド…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
・既存製品の開発~導入 └システム開発から導入までのプログラミング └クライアントのニーズに合わ…
週4日・5日
330,000〜820,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
アプリ分析支援事業で培った知見を活かした、スマホビジネスのワンストップソリューションを提供している企…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Angular・ypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
人工知能での機械学習を用いて、人や組織に最適なニュース記事をレコメンドするサーバーサイドエンジニア募…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リードエンジニア】各種自社システム開発業…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | リードエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
現行RPGで構築されているシステムをJavaで新たに構築します。 要件定義フェーズについての募集で…
週5日
610,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・- | |
定番
【マーケター(広告運用)】自社プロデュース…
<業務内容> ◎Webプロモーション・販促支援 ・Web運用型広告の各種設定(タグ設置・URL発…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 豊洲有明駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
【Java・PHP】社内システム開発
■作業内容 社内システムの開発業務となります。 ■作業場所 ・リモートワーク可 ・作業場…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・SQL・- | |
定番
【テクニカルサポート/ヘルプデスク|週5日…
【案件概要】 コールセンターまたは事務センターにおいて各種管理業務の責任者として業務に携わっていた…
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート/ヘルプデスク(運用責任者) |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】DX…
化粧品等の製造開発からEC販売から、化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのため…
週3日・4日・5日
330,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Go・Typescript・L… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】某…
現行ECサイトの既存画面からUI・UXを鑑みた改善デザインを提案いただく業務です。 先方のBuss…
週5日
750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Figma | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】 …
化粧品等の製造開発からEC販売から化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのための…
週3日・4日・5日
440,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】イ…
ITインフラ関連プロジェクトの管理・顧客折衝・サービス企画などを担当していただきます。 また社内…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
企業向けクラウド導入支援、移行サービス、運用サービスに関連する業務。 ・要件定義~運用・保守 全…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
インフラSIer企業内にてデザイン業務を担当いただきます。 アイエスエフネットのブランディングを「…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
人材紹介業向け基幹システム開発の新規プロダクト開発チームのリードエンジニアをご担当いただきます。 …
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・JSフレームワーク(… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
人材紹介業向け基幹システム開発(自社開発クラウドシステム)の新規プロダクト開発チームのフロントエンド…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・JSフレーム… | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
子供の“学び”に関するITサービスを提供する企業にて動画教材のAndroidアプリ開発業務をご担当い…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
化粧品等の製造開発からEC販売から化粧品やヘルスケア商品、そのブランディングやマーケティングのための…
週3日・4日・5日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
WEBアプリーケーションエンジニアとして既存サービスのリプレイスを担当頂きます。 当社が提供する既…
週4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・AWS・Laravel… | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週5…
新規サービスの開発を行いながらも、必要に応じて既存サービスの機能追加などにかかわって頂く可能性も御座…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Scala・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日】既存サ…
WEBアプリーケーションエンジニアとして、既存サービスのリプレイスを担当頂きます。 当社が提供する…
週4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・AWS・Laravel… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】デ…
要件定義など上流工程から入っていただき、基本設計、詳細設計までを主にご担当いただきます。 実装はオ…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Linux | |
定番
【PM / 週5日】VDI導入支援/調査分…
現行の利用ツール改修要件のまとめや、影響範囲の調査、移行方針策定や運用設計作成を実施、構築ベンダーと…
週5日
830,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VDI・VMW | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
技術検証を目的とした、オーディオ系ローレベル ドライバの開発 ・マルチコアCPUを意識したプログラ…
週5日
610,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿両国近辺または中野坂上 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
国内最大級のスタートアップコミュニティを運営しています。 クラウド型イノベーションプラットホー…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】大…
大規模ショッピングサイトのフロントエンドの開発を担当していただきます。 具体的には、 ・プラ…
週5日
440,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・jQuery・Git・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社サービスを全国展開し、安定的なサービスの提供を実現するために、サーバーサイドエンジニアを募集しま…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / swift / 週3日〜】…
WEB系、アプリ系の開発案件が全国に複数ありこちらを皆様にご対応頂きます。 適正に応じて企業様に案…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
大手の金融機関が新しい技術として取り上げているツールのカスタマイズ開発です。 案件(WEB系、アプ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・AngularJS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社運営女性誌サイ全般の広告企画・運用をご担当いただきます。 広告の運用だけでなく、広告売上最大化…
週5日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
飲食業界の顧客にとって使えるメディアやツールの開発を行っております。 Rubyを用いた開発経験があ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
バックエンドエンジニアとして、上記APIに対して新機能追加や各種計測・改善業務を行っていただきます。…
週5日
570,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
自社で開発しているカメラサービスや新規サービスの開発を担当していただきます。 現在、正社員または業…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
ブロックチェーンのソーシャルネットワークプロジェクトへ参画していただき、 サーバーサイドエンジニア…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・rails | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
Rubyにて自社開発のコンシューマー向けサービスになりますので、経営陣と相談しながら要件検討するなど…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
・自社サービスのWeb/モバイルアプリへの新規機能追加 ・自社サービス同士の連携のための連携方式設…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Java・React… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】Ct…
日本最大級CtoC向けフリマアプリの開発にてCSツールの管理画面改修もしくはAPIの改修をおまかせし…
週4日・5日
570,000〜1,740,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・DietCake | |
定番
【リモート相談可 / Java/Go / …
既存システムからデータを受け取り、Google Cloud Platform上にデータレイク、データ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・BigQuery・RDB・GCP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】プ…
・サーバー、ネットワークの詳細設計~運用保守 ・ヘルプデスク ・クライアントPC等の展開作業 な…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】Windows10移行…
全国のクライアント向けにWindows7,8からWindows10への移行作業のプロジェクトが大々的…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
クライアント(外資系企業)の中に入っていただき、現在の社内情報システム部門の巻き取りを実施。 PM…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】データ…
メーカー系企業が内製で運用している(40名)データセンター内の業務の一部をアウトソースする方向性で検…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
内視鏡AIを作るのに必要な教師データを作成する目的で、データアノテーションを効率良く行う為に独自の社…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】会計パッ…
・会計パッケージの消費税、元号対応のための改修をお願いいたします。 ・詳細設計書~改修、テスト …
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・SQL-Server | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
画像認識技術と人工知能技術(AI)を活用したAIレジを提供しており、UI部分の開発を担当頂きます。 …
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
画像認識技術と人工知能技術(AI)を活用したAIレジを提供しており、レジ機能(画面・サーバ)等のWe…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週4日〜】…
画像認識技術と人工知能技術(AI)を活用したAIレジを提供しており、レジ決済機能部分の開発を担当頂き…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
画像認識技術と人工知能技術を活用したAIレジの開発を行っている企業での社内SE業務です。 ・Lin…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
画像認識技術と人工知能技術(AI)を活用したAIレジを提供しており、画像解析部分の開発を担当頂きます…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
社内で長年研究してきた自然言語処理技術を活かし、コールセンターなど顧客支援システムの自動化を目指すプ…
週5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
基本設計~詳細設計~実装~テストまで一貫して実施。 アプリ層へのI/F提供。 状態制御を行うミド…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八王子駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・Linux | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・AS400基幹システムの再構築。 現行RPGで構築されているシステムをJavaで新たに構築します…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・terasoluna | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
・自社の業務管理システムの開発業務 ・新規システム開発や既存システムの改修などの業務 (業務改善…
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・rails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社サ…
・自社運営サイトの運営・改修業務 (WEBサイト内の記事の更新など) ・LPの制作やCMSの変更
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
・自社メディアサービスのデザイン(UI設計・デザイン) ・PCデザイン・SPデザイン・ポップアップ…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
自社サービスのECプラットフォームの新規機能の追加及び改修が主な業務となります。 IaCやコンテナ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】周…
・基幹系システムリフレッシュに伴う、周辺システムの生産性向上検討、要件ヒアリング、要件整理、要件定義…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋光が丘 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Java・C#・AWS・AzureGo・og… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
不動産業界の自社サービスリリースに向けて、サーバーサイド開発をメインとする業務にご対応頂ける方を募集…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
カスタマー向け不動産マッチングサービスを開発しております。 サービスリリースに向けて、WEBのデザ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・spring… | |
【React/Go】動画配信サービスにおけ…
案件内容: 動画配信サービスの開発をご担当いただきます。 アジャイル開発で進めています。 …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・g… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
解析ツールの機能開発プロジェクトを統括するプロダクトマネージャー。 ビジネス優先順位とエンジニアの…
週5日
830,000〜1,900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【HTML/JavaScript / 週5…
WebのUI/UXエンジニアリングに長けたエンジニアが必要です。 弊社はデータ分析をしてサイト改善…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
新規プロダクト開発チームのQAエンジニアをお願いします。 AWS環境での運用になり、サービス間を繋…
週5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
スタートアップの礎を創るフロントエンドエンジニアを募集! 大事な事は、既存の考えにとらわれず状況に…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
スタートアップの礎を創るフロントエンドエンジニアを募集! 大事な事は、既存の考えにとらわれず 状…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Node | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
スタートアップの礎を創るフロントエンドエンジニアを募集! 大事な事は、既存の考えにとらわれず 状…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
写真・動画の撮影や編集、Web構築からメンテナンスまで、上手な物件のイメージづくりをスムーズに支援し…
週3日・4日・5日
230,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川東京 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【HTML/CSS / 週3日〜】自社サー…
子連れで行ける場所だけを集めた口コミ情報サイトや全国の子供の習い事教室を比較検索・体験申し込みができ…
週3日
250,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
・ECサイト構築パッケージ『ecbeing』用のコーディング業務,JavaScriptの開発・実装 …
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・自社サービス(新規プロダクト含む)の開発及び運用 ・開発フローやプロセスの改善 ・インフラ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
当社が運営するサービスのフロントサイド側の開発又は 受託フロントサイドシステム開発を主に担当してい…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
フリーランスの方が抱える様々な課題に対して複数のソリューションを展開していくことで、個人が会社機能を…
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・node.j… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】医…
医療系求人紹介・求人媒体サービスとそれに付随するサービスのサーバーサイドの開発です。 今回は、社内…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
社内の顧客・不動産管理システムカスタマイズなどの開発をメインに携わっていただきます。 複数自社サー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・cakePHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
HTML5/CSS3/Javascript/WordPress/ワイヤーフレーム/ペンタブを使用した…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】調達グロ…
外資系ベンダから海外グループ各社も使えるグローバルディスカウントを獲得・活用するコスト削減に取組んで…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PM |
| _ | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】下流…
自分自身で構築作業を行うのではなく、他者が作成した成果物のレビュー・テスト・技術指導をお願いいたしま…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・_ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
感情に寄り添った会話を行うロボットをつくるため、様々な手法を組み合わせた会話AIの開発を担当していた…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
WEBマーケティングと開発系スキルの両方を備えたWEBデザイナーになれます。 GoogleAnal…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規/既存のWebサイト ・アプリのデザイン ・UI/UXデザイン サービスや商品のWebサイ…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅,代々木駅,外苑前駅,五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
受託開発を請け負っている金融系のスマホアプリ開発案件となります。 改修と追加機能開発などが続く長期…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】銀…
複数ベンダーが関わっているリニューアルPJのPMの支援を行っていただきます。 主な作業は以下の通り…
週5日
590,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅・東陽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
CADシステムの開発・販売クラウドサービス「顧客志向」の開発・販売WEBサービスの運営などをメイン事…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週5日】国…
リモートテクノロジーをコアとしたリモートサポート事業を中心に、クラウドサポート、モバイルサポートなど…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
仮想通貨取引所・決済サービスおよびメディアを運営するクライアントからの受託案件です。 決済サービス…
週5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
仮想通貨取引所・決済サービスおよびメディアを運営するクライアントからの受託案件です。 仮想通貨取…
週5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
AI監査ソフトウェアの企画・開発・運営を担っていただける方を募集します。 リスクとコストを削減…
週3日・4日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask等 | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
官公庁や大学、民間企業など様々な団体組織のプロモーション活動を代理店として総合的に手がける企業です。…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・- | |
定番
オリジナルコンテンツの配信管理・運用業務
【業務内容】 ・オリジナル記事・動画の配信管理業務(シートでの配信記事の管理、実際の配信記事の各種…
週3日・4日・5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 配信管理・運用 |
定番
【Go/React/Typescript】…
【担当業務】 - パートナーエコシステムクラウドの開発 【案件の魅力】 - 大手SIerや…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】基…
・Notesシステム集約/移行の設計 (フェーズとしては基本設計/詳細設計以降) ・実装/単体以…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 東京23区以外六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| OutSystems | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Python…
下記いずれの業務に参画して頂く予定です。 ①不動産データプロ(ライブラリ)の開発 Googl…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・- | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
世界最大の某外資コンサルティング会社の案件となります。 エンドのクライアント様にて質問に答えてい…
週5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田無駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
世界最大の某外資コンサルティング会社の案件となります。 エンドのクライアント様にて質問に答えてい…
週5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田無駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
メインでフロントエンド業務をご対応頂ける方を募集しております。 ・ソーシャルゲーム、メディア等…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
現在運営中の医師同士のオンライン医療相談サービスのサービスとその他の新サービスの開発を対応していただ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・HTML/CSS/JavaScriptによる開発 ・レスポンシブWebデザインほかサイトUIの設…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
レコメンドウィジェット型のネイティブアドネットワークの開発をしていただきます。 技術選定や、現状の…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・AWS | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
事業責任者・PM・エンジニアと協力し、ユーザーに最高の体験を届けるためのリサーチ、プロトタイプ開発、…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
弊社が運営する不動産同時査定サービスにおいて、WEBデザイン業務を担当していただきます。 ・事…
週4日・5日
300,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社の会員システムの基幹部および周辺サービス開発・運用 Webアプリケーションの開発および保守 …
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ハイエンドファッションブランドの公式ECサイトの開発に携わることができます。 多国籍なメンバーが在…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿信濃町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
システムインテグレーション スマートフォンアプリ開発、業務アプリケーション開発等様々な事業を行われる…
週4日・5日
440,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
BtoBのECサイトのリニューアルです。 現行のアプリケーションをフロントエンドとAPIに分離し、…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・ 配信システムの改善による広告効果向上のための開発 ・ より安定的に大量のトラフィックやデータを…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
各種生保・損保系申請書について、自社公共向けOCRスキャンシステムと連動するコールセンターを持ってお…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【Ruby / 週5日】HR系インターネッ…
自社HR系メディアのサーバーサイドの設計、開発、および運用を担当していただきます。 設計・仕様〜実…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyOnRail… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
自社不動産系メディア及びそのサブシステムの開発 /保守運用業務をご担当いただきます。 具体的には物…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Java・S… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】AW…
現在のWindowsサーバーをAWS(もしくはAzure)上に移行するプロジェクトです。 現行シス…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
請求書や特許庁が出しているドキュメントの読み込みを実行する、OCRのライブラリ開発ができるエンジニア…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Python・Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
不動産情報B2Cサイトの改修案件の開発者を募集します。 ・現在サービスインしているB2Cサイトに対…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・AWS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・既存修正(軽微な修正以外の広範囲、内容重めの修正など) ・新規ページやキャンペーンページ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】証券会社の…
証券会社のサイトの定常運用・新規案件デザイン ・主にマーケ部からの依頼案件の対応 …
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
既存のECシステムのクラウド化プロジェクトです。 上流工程から携われ、且つ下記の技術経験を持って開…
週5日
630,000〜960,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・- | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
エンドクライアントのビジネスを理解し、保守性や拡張性を意識したシステム開発(webアプリケーション・…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / swift / 週5…
IoT制御用ポータルアプリのリファレンスApp作成をお願いいたします。 最初は、既存Appをまねて…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
テクノロジーの進化やSNSの普及によって、誰もが表現者となることができて、誰もがクリエイティブを発信…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
弊社はAI、ブロックチェーン開発を中心としたフィンテックを主な事業体とした、システム開発及び経営戦略…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Cake | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
物流会社の基幹システム全面リプレースにおけるWMS(倉庫管理システム)再構築を行っています。 現在…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
サービスのUI/UXの企画・開発、業務改善、新技術導入等をお任せします。 新規事業の求人情報サービ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社開発のCMS・CRMパッケージの新規開発やリニューアルに携わることが可能です。 クライアン…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop …
ゲームグラフィック制作専門の弊社のリードデザイナーとして、ソーシャルゲームにおけるアートディレクショ…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
| Photoshop・SAI・CLIP・STUDIO | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
女性向け無添加ヘアケア商品を自社ECサイトで販売している企業様で、WEBデザイン制作をメインで担って…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 池袋高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
スタジアムや球場、アリーナ施設の360度全周にカメラを設置し、スポーツや格闘の決定的瞬間を、時間軸や…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社サービス(クラウド版)のフロントメインデザインをお任せします。 ・新規ページのUI/UX設計~…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
クラウドソーシングサービスをより使いやすく、より便利にするための機能開発や新サービスの開発における設…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
・コーディング / テスト(必須) ・設計(スキル見合い) 弊社で稼働いただくすべてのエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
・自社サービスのインフラ(サーバ、ミドルウェア)運用や改変、設計・構築 ・SRE 的な開発チームの…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日】…
自社で運営しているマッチングサービスやSalesforceの改修がメインとなります。 デジタル…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Apex | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
マーケティングオートメーション分野のパッケージソフトウェア導入に関わる保守開発をご担当いただきます。…
週5日
460,000〜820,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
「動線分析」「インストアマーケティング」「機械学習」分野のパッケージソフトウェア導入に関わる保守開発…
週5日
460,000〜820,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大企業様向けのオンボーディング(新しく入社したメンバーが早期に活躍できるよう、組織としてサポートする…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
大手不動産業 社内インフラ整備における業務の見える化、要件定義、運用設計書作成等、運用業務をお願いい…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
検索がいらないサロン予約アプリの新機能開発、運用をお願いします。 日本初のプロダクトを生み出す…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
不動産情報B2Cサイトへの新規機能追加、新規ビジネス施策に関する技術調査案件の開発者を募集します。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
勤怠打刻・勤怠申請・個人情報の変更申請等、PC/タブレット用Webアプリケーションとバッチの開発です…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
現在企画中の、ビックデータと機械学習を活用したサービス(BtoB、社内向け)の開発を担当いただきます…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
現在企画中の、ビックデータと機械学習を活用したサービス(BtoB、社内向け)の開発を担当いただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / LAMP / 週5日…
Linux環境構築に伴う、システム要件定義・設計・構築およびシステム運用・設計・構築業務をご担当いた…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】分散…
テレビ視聴データを分析するデータ基盤のインフラエンジニアとして、特に AWS EMR での Spar…
週3日・4日・5日
750,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】コーチ…
組織の経営トップおよび経営層に対してエグゼクティブ・コーチングを実施し、それを基点に組織を変えるビジ…
週3日・4日・5日
920,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
医療系検査機器の異常検知システムのフロントエンド側の開発に携わっていただきます。 バックエンドで異…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
クライアント様のご希望に合わせてWEBサイト制作やアプリ開発、システム開発を行っている企業様におきま…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js | |
定番
【PM / 週5日】銀行向けシステム企画・…
・プロジェクト管理、予算管理、請求処理 ・各ベンダーの選定、契約、折衝、検収 ・ユーザー部門、経…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東陽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
クラウドシステム(飲食店向けPOSデータ登録・配信等)におけるリファクタリング・機能追加 既存…
週3日・4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿人形町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【PM / 週5日】銀行向けシステム企画・…
・プロジェクト管理、予算管理、請求処理 ・各ベンダーの選定、契約、折衝、検収 ・ユーザー部門、経…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東陽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
①インフラ枠 SNS企業からのデータを加工し契約法人向け配信しているシステム基盤の構築と維持を行っ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Java・Linux・Hadoop | |
定番
【Java / 週5日】自社開発の人材紹介…
人材紹介業向け基幹システム開発(自社開発クラウドシステム)の開発業務をご担当いただきます。 大手ユ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・C#・VB.… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ウェアラブル楽器ガジェットの開発やAI作曲ソフトの開発など音楽に関するサービスを開発・提供する企業に…
週3日
290,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
ウェアラブル楽器ガジェットの開発やAI作曲ソフトの開発など音楽に関するサービスを開発・提供する企業に…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
ウェアラブル楽器ガジェットの開発やAI作曲ソフトの開発など音楽に関する開発を行っていただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / swift / 週5…
自社アプリの開発に携わっていただきます。 ユーザー数の増加、新規サービス拡充と並行して、仮説を立て…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Java / 週3日〜】某流通系システム…
・業務:宅配、店舗システムでのプロモーション再構築 ・対応工程:要件整理、要件定義、システム要件設…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・C#・SpringBoot | |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社における…
・外部機関からの指摘事項を取りまとめ ・対応方針の検討支援 ・対応状況の進捗管理
週5日
620,000〜1,330,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】製造業におけるITイン…
・製造業におけるサーバやストレージ周りでのセキュリティ対策の検討を推進できるPM ・サーバーやスト…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
・B向けアプリケーションの開発におけるPM ・現在無償PoCという形で提供しているアプリケーション…
週5日
580,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】日本…
主軸とした各種事業のWebサービスの開発組織マネジメントやリーダー業務を行っていただきます。 1〜…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトのグロースを加速するバックエンドエンジニアを募集いたします。 オンライン会議…
週5日
580,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
ゲームアプリの開発経験をお持ちの方を、幅広く募集しております。 ゲームが好きで日頃からたくさんのゲ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・Cocos2d-x | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop …
これまで様々なヒットアプリを生み出してきた企業が、更なる事業拡大に向け新規タイトルの開発を進めており…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
演習中心のアシスタント案件となります。 講義スキルは必要とせず、技術スキルをお持ちで、かつ、受講生…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
各種タクシーアプリのサーバサイド(主にAPI)の各種機能開発、インフラ周りの運用、新機能の提案から実…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Ruby・C#・Rails | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
通販系ECサイト構築の受託案件となります。 Java・PHPによる開発を予定しており、本案件におけ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【Vue.js / 週3日〜】IoTプラッ…
AIを活用した橋梁の内部鋼材破断を検知する非破壊検査ソリューション開発プロジェクトにおけるフロントエ…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・Vue.… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
不動産屋にいかずチャットでお部屋探しができる仲介手数料無料の賃貸仲介アプリの開発を行う企業様にて、A…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【.NET,C♯】不動産投資信託の業務管理…
【業務内容】 ・不動産投資信託の業務管理システムの上流〜保守的・開発(追加機能開発)
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
BtoB/BtoC向け学習系Webサービスの新規事業展開に伴う開発業務です。 新規学習系WEB…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SpringBoot… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
仮想通貨ウォレットの作成・修正、取引所システムの構築・修正、ECサイトの変更・修正、ゲームに関わるシ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Nod… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
テクノロジーと弁護士の高度な法的知見を掛け合わせることで、より多くの人や企業が地域や経済力にかかわら…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・V… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】デー…
AIを用いた契約書レビューを行う機能をメインとした、大企業法務部門向けBtoB Saasプロダクトを…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【PHP / 週5日】不動産情報B2Cサイ…
不動産情報B2Cサイトへの新規機能追加、新規ビジネス施策に関する技術調査案件の開発者を募集します。 …
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
社内向けシステムに関しては営業管理システムを更新しており、社内ユーザーが使いやすく、そして業務効率ア…
週3日・4日・5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
製造業向けのIoT・AI化を推進する企業として、人工知能によってどう解析するかまでを、ワンストップで…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Python・Java・Djabgo | |
定番
【swift / 週4日〜】「AI音声認識…
AI音声認識アプリ(英会話学習アプリ)の開発者を募集いたします。 イメージといたしましては、アプリ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
債権管理システムの開発作業です。 ・機能追加 詳細設計~開発~テスト実施 ・データ移行処理 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Python/C# …
サーバーサイドの得意なPythonエンジニア (データ分析など理系寄りの方希望) 食品購…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C# | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週5…
スマートフォン向け既存ゲームのサーバサイド設計、開発、運用、機能追加、改善業務となります。 (アク…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
-プロダクト・ディベロップメント事業 自社製クラウド型業務アプリケーションやパートナーソリューショ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
ウェアラブル楽器ガジェットの開発やAI作曲ソフトの開発など音楽に関する開発を行っていただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
自社会計パッケージシステムの開発・カスタマイズをお任せします。 官公庁・公益法人の会計・給与という…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 千葉稲毛駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
スマートフォンアプリやPCサイトで画像認証や音声認識を使用し食事を記録すると、食生活改善アドバイスが…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【PHP / 週3日〜】自社サービス/受託…
以下の自社サービス/受託開発等に携わって頂く予定です。 ・自社サービス(シニア向けの仕事マッチング…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ケ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスとして、電源を入れるだけで農業IoTを始められるクラウドサービスを運営しています。 温…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西武新宿 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
不動産業支援のオールインワンのクラウドシステムで、管理システムから不動産会社のホームページ制作、不動…
週3日・4日・5日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
様々なクラウド環境や、自動化ツールを活用したクラウドソリューションの受注案件に関し、インフラエンジニ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 神奈川秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
モバイル開発グループに加わり、新サービスを開発していただきます。 基本設計、(詳細設計、コー…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・macOS・MacBook・or・MacB… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
子供の“学び”に関するITサービスを提供する企業にて動画教材のWEB開発業務。 新規PJとして…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【JavaScript / 週4日〜】HR…
弊社の運営するIT エンジニア専用転職サイト/デザイナー専用転職サイトのWEBデザイナーとして、ビジ…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
BtoB向け自社サービスの開発業務です。 ・API、アプリケーションの設計、開発 ・営業チーム…
週3日・4日・5日
500,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・o… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
ブロックチェーンのソーシャルネットワークプロジェクトへ参画していただき、 サーバーサイドエンジニアと…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
一部ブロックチェーンを利用したソーシャルネットワークプロジェクトへ参画していただきます。 自社サー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社サービスのWEBアプリデザイン業務です。導線設計やワイヤーフレーム作成、デザイン制作業務をお願い…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
スマートフォン向けのアプリ開発、VRの実用化を行っている企業です。 納期が迫る中で開発中のプロ…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 池袋末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin・L… | |
定番
【PHP / 週5日】受託でのスマホアプリ…
スマートフォン向けのアプリ開発、VRの実用化を行っている企業です。 納期が迫る中で開発中のプロ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
スマートフォン向けのアプリ開発、自社サービスでVRの実用化開発を行っている企業です。 今回参画…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
国内最大級の導入実績を持つクラウド型電子マネー発行システムの他、アプリケーション開発、または運用担当…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅/京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【C#/Java / 週5日】工程管理シス…
前フェーズ(要件定義)のアウトプットである適用企画書(システム要件定義書および基本設計が記載されたド…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
放送局のディレクターの方がお使いになるWebサイトの修正、加工が可能な方募集。 基本的にはデザイン…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
アルバイト・転職や住宅領域等をはじめとした複数のメディアの企画・開発、および新規事業・新規メディアの…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
弊社が運営する国内最大のレンタルスペース予約サイトのシステム開発をご担当いただきます。 具体的には…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
オンラインプログラミング教材を作成するための 業務支援ツールの開発・運用をお願いします。 教材…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【Java / 週5日】仮想通貨ウォレット…
自社パッケージである仮想通貨ウォレット管理システムのサーバー、ネットワーク運用・保守をご担当いただき…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅&飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自然派食品宅配業界の最大手企業様が運営支援を行っております、某大手小売業グループ企業様のECサイトの…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
膨大なデータベースから必要な情報を的確に探し出すための検索テクノロジーの開発業務 フルスタック…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Go / …
・日本最大AIプラットフォームと連携し、様々な機械学習モデルを運用(学習及び予測)できるSaaS開発…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・Rails・V… | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週3日…
・日本最大AIプラットフォームと連携し、様々な機械学習モデルを運用(学習及び予測)できるSaaS開発…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
直接取引のクライアントから依頼を受けたWebサイト、プログラム実装と連携する案件のコーディング作業を…
週5日
350,000〜550,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
アプリ運用のディレクション業務となります。 顧客との窓口・コミュニケーションおよびエンジニアとの調…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
今回はフロントエンドでのWEB開発が出来るエンジニアを募集します。 案件自体は流動的なため、ご相談…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 千葉柏駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
iOSフロントのUIエンジニア 食品購買データの分析やレコメンドシステムや自然言語処理を利用し…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【Webマーケター|週2日~3日・フルリモ…
【案件概要】 現在、新卒メディア/エージェント事業、スクール事業、中途エージェント事業など複数のサ…
週2日・3日
90,000〜290,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(上流) |
定番
【PM】基幹系システム再構築も含めた、全社…
■募集目的 全社の基幹系システム再構築も含めた、全社DXの推進プロジェクト ※詳細は未定ですが、…
週5日
1,100,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【データベースエンジニア】基幹システム更新…
【業務内容詳細】 基幹システムの更新を目的に、Dynamics365の導入を推進中。今回の対象業務…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
定番
【PM/フルリモート】データ分析基盤構築
【業務内容】 pN-Integration: ・データ分析基盤に関する要件定義・設計・開発・テス…
週3日・4日・5日
530,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
リフォームメーカーの現行Webシステム(RubyonRails)を、Cloud上でのMicroser…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】バ…
アルバイト採用のコミュニケーションを変革すべく誕生した、おしゃれなバイト探しメディアの開発・メンテナ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
新電力総合支援サービスで業界最高クラスの成長率のEnergyTech企業での開発・運用をお任せします…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
クライアント企業から受託案件になります。 既存サーバーからAWS置き換えにあたり、 ・インフラ設…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木多摩川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
電子マネーアプリの開発(機能追加等を含む)全般をお願いいたします。 最初はアプリの理解を目的に小中…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Python・AndroidJava | |
定番
【C# / 週5日】3D細胞解析ソフトウェ…
3D細胞解析ソフトウェア開発及び保守として、GUIの開発を行って頂きます。 機能追加、仕様変更に対…
週5日
700,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿八王子 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
集客支援の開発プロジェクト * 新聞折込・ポスティング・DMサービスの開発・運用業務 * PHP…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Symfony2.6 | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】決済プラ…
各サービスが利用する決済プラットフォームの安定稼働とユーザーへの快適なサービス提供を目指し、Lift…
週5日
330,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin・Go・C#・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
日本最大級の料理動画メディアにおいて、デザイン業務を行っていただきます。 制作物は紙~Webと多岐…
週5日
300,000〜560,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
サービス全般のサーバーサイド開発業務と合わせてCTOに準ずる技術者マネジメント業務を、ご希望や相性に…
週3日・4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Ruby・C・C++・Keras.te… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
クライアントサイドをUnity / C#で開発しています。 Unity開発としては珍しく、ネイティ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C#・UniRx・DOTween | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
WEBサイトにおけるサーバーサイド・フロントエンドの設計から開発までをご担当いただける方を募集致しま…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社開発しているAI OCRを中心としたAIプラットフォームのフロントエンドエンジニア案件です。 …
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Nuxt.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ペットに関する自社運営サービスの開発業務を支援いただける人材を募集しております。 ・PHP・R…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・CakePH… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
保険会社システムの改修業務です。 現在は、テストフェーズ。IF部分のテスト/調査を行い、必要に応じ…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Go / 週…
利用ユーザーが好きなバーチャル配信者と1:1の通話ができたり、通話内でミニゲームを楽しんだりできます…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Vue / 週5日】…
地方の中小・ベンチャー企業や個人商店を救うためのサービスを提供しています。 日本企業の99.7%は…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Nu… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
得意分野のインフラ技術における要件定義/設計/構築、およびタスク管理 ※案件ごとに求められるインフ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社にて開発・運用されているゲームタイトルのキャラクターから背景まで一枚のイラストをご担当いただきま…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
| HTML・CSS・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
トラック専門のオンライン・オークションサービスを自社webサービスとして運営している会社です。 今…
週3日・4日・5日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
IoT・Big Data・AI等を活用した業務変革や新規事業開発の支援を行なっています。 自然言語…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
・新規電子決済システム導入加盟店、開発ベンダーへの電子決済システム仕様の説明 ・新規…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
新規ドメインで新たにリリースを致します。 大枠の開発はシステム会社に外注予定ですが、並行して常駐で…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・ca… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】SN…
SNSを活用した店舗集客・販促施策・認知拡大・UGC解析によるマーケット分析など、SNSを活用したマ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
現在、受託のWeb制作に加えて、自社サービス開発にも注力しており、 両軸でご活躍頂ける方を探しており…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
現在、受託のWeb制作に加えて、自社サービス開発にも注力しており、 両軸でご活躍頂ける方を探しており…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
セレクト・アウトレット型ECサイトのフロントエンド部分の保守開発業務を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
自社で運営しているWebサービスのWEBサイト、スマホアプリ等のデザイン全般、ランディングページ制作…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
BtoC/BtoB向けダイレクト版デジタル広告運用サービス開発においてのインフラエンジニアを募集いた…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【C# / 週5日】財務会計システム開発の…
『財務会計システム』の開発へ参画していただき、詳細設計~結合テストまでを担当していただくPGを募集し…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
アルバイト・転職や住宅領域等をはじめとした複数のメディアの企画・開発、および新規事業・新規メディアの…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・RubyOn… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・AS400基幹システムの再構築。現行RPGで構築されているシステムをJavaで新たに構築します。具…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・terasoluna | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ECサイトの制作業務を担っていただける方を募集しております。 具体的な業務内容はECサイトの商品ペ…
週3日・4日
150,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
製造・建設・製薬・金融・流通サービスがメインとなっております。 ご経験や保有スキルによって、マッチ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Node.js・React.・… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
・中規模WEBアプリのバックエンド開発 既存WEBアプリの新機能追加や修正、リファクタリングを行っ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、広告デザインから…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
ホームページ制作/SEO対策をはじめ、ソリューションベンダとしてWEBのあらゆる角度から、各種提案・…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP・SQL・La… | |
定番
【インフラ / 週3日〜】自社セキュリティ…
【業務内容】 自社サービス・クラウド型サーバセキュリティのインフラ構築/運用 ▶プロダクショ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
PHPを使用したシステム開発を中心にいくつかのPJが進んでいます。 今回は「新聞社向けシステム開発…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅/九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
優秀な正社員エンジニアが気軽に副業案件を始められるサービスをリリース予定しております。 今回は、こ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【JavaScript / 週5日】Win…
点群データ(3次元の座標データ)をもとに描画する機能を有するWindowsアプリケーションの開発に関…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・C・C++ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】作…
・Ruby on Railsを利用したWebアプリケーションの開発 ・JavaScriptを利用…
週3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・rails | |
定番
【インフラ / 週5日】カード会社向けAS…
カード会社向けASPサービス提供事業者にてDB設計から運用、本番リリースまでご対応いただきます。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL・Oracle | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
家事代行クラウドソーシングサービスにおける、フロントエンド開発・運用をお任せします。 自社サービ…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
新規スマートフォンゲームのサーバーサイド開発、運用を担当していただきます。 ・Golang /…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
ロールプレイを通じて、ビジネスで使える実践的な英会話が学べるような、新規スマホアプリ開発を進めており…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
元々、Adobe AIRを用いて開発していたデスクトップアプリケーションを、高速化・安定稼働を目的と…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
元々、Adobe AIRを用いて開発していたデスクトップアプリケーションを、高速化・安定稼働を目的と…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
業務詳細:決済代行システムおよび周辺システムの開発、保守運用、運用改善等です。 システム/業務の現…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留(新橋) |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seaser2 | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】社…
ガイドを元に、バージョンが4.2のシステムを5.0にバージョンアップする対応を行なってただきます。 …
週3日・4日・5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
ユーザーと小売店をつなぐ国内最大級のモバイルメディアを運営しております。 サービスをさらにグロース…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・TypeScri… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
金融という高い公共性の求められる分野で、サービスを一緒にドライブしていただける、優秀なエンジニアを募…
週4日・5日
550,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【Python / 週3日〜】受託案件にお…
クライアントのWebサービスのデータ分析、分析結果を元にしたデータ・ドリブン施策提案などの業務をお願…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・R | |
【UXデザイナー|週3日~5日・フルリモー…
【案件概要】 企業やブランドの調査分析・課題を洗い出し・課題解決のためのユーザー体験を企画/設計す…
週3日・4日・5日
220,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿学芸大学 |
|---|---|
| 役割 | 【20~30才未経験歓迎】UI/UXデザイナー(兼コーダー) |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
お金がより自由に届けられ、より明るく楽しい世界を実現できるように、 コンシューマー向けのアプリと、…
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
【フロントエンドエンジニア|フルリモート・…
【案件概要】 デザイナーが設計したWebやモバイルアプリなどUIデザインを実装していただけるフロン…
週3日・4日・5日
220,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿学芸大学 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
海外投融資(融資)に関するシステム構築プロジェクト。 現行有償資金協力システムで管理している円建て…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】ゲー…
某ゲーム会社におけるプランナー業務 ゲーム仕様決定、仕様書作成、ゲームバランス調整、シナリオ作成、…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
【Python / 週4日〜】DX推進支援…
証券業界を先導するリーダー企業におけるDX推進部門の支援や、事業部門におけるデータ/AI活用支援及び…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・VBA・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】金融系…
改修 ・各サービスの一部システムの改修 ・SE→改修要件精査、実装仕様の策定 ・PG→PLの指…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・javascriptベースで駆動するデータチェック自動化ツールのプロファイル改善・運用 ・新規商…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
大手電機メーカーG企業にて、社内で長年研究してきた自然言語処理技術を活かし、新規サービスの開発を行っ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
人工知能での機械学習を用いて、人や組織に最適なニュース記事をレコメンドする自社サービスのサーバーサイ…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
ゴルフ場予約サイトの機能改修やUIのリニューアルを目的としており、開発に関してはベンダーに任せている…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトリーダー |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
* 自社CMSの新規機能開発 * 新規自社サービスの立ち上げ・開発 * (リードエンジニアに相当…
週4日・5日
580,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・-・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Illustrato…
新規スマートフォンゲームのモーションデザイン制作業務を担当していただきます。 主に、Spineを使…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | モーションデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・SAI・… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
デザイナーの方と協業して、WEBサイト制作に携わっていただきます。 フロントエンドエンジニア、また…
週3日・4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・vue・re… | |
定番
【リモート相談可 / VB.net / 週…
受託での通信・金融系をメインとしたシステム開発、クライアント先システムの根幹となるインフラ設計を手掛…
週5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】映…
自社製品である非接触バイタルセンシングソフトウェアの開発作業、技術検証作業をお願いいたします。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
10名程度のチームの開発メンバーとして参加して頂きます。 該当ソフトウェアは、コンフィグレーション…
週5日
1,250,000〜1,900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / 組み込みエンジニア …
■USBドライバ開発(Host / Function) / プロトコルスタック相当の機能開発 …
週5日
1,010,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【フルリモ / VBA / 週5日】製薬向…
・検証者(アプリ運用担当者)からの問い合わせ管理 ・チーム内課題管理 ・会議準備、議事録取得 …
週5日
570,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
不動産のコンサルティングをしている会社です。 今まで物件の空室情報などを社外でDB管理していました…
週3日・4日・5日
500,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
不動産のコンサルティングをしている会社です。 今まで物件の空室情報などを社外でDB管理していました…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】大手S…
IoT、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に関するデータ収集およびダッシュボートの開…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / セキュリティ / 週…
リーダーの配下にてWebアプリケーション診断、プラットフォーム診断、メール訓練のプリセールスから案件…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・セキュリティサービス基盤に関する -Linux系/Windowsサーバの構築/運用 ・セキ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
スタートアップの受託案件を中心としたデザインを行っていただきます。 主にUI/UXデザイナーやディ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Webディレクターが作成するワイヤーフレームやWebデザイナーが作成するデザインカンプをもとにHTM…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
インフラメンバーとして、基幹システムの各種インフラ作業を担当していただきます。 直近は「外接ネット…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】顧客…
- 追加機能、不具合改修時の詳細設計(画面設計、バッチ設計等) - 不具合発生時の調査(不具合個所…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
- 追加機能、不具合改修時の詳細設計(画面設計、バッチ設計等) - 不具合発生時の調査(不具合個所…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・ オンプレミスで構築された既存システムを、同じくオンプレミスで次期メールシステムへ更改する。 ・…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】大手…
- 追加機能、不具合改修時の詳細設計(画面設計、バッチ設計等) - 不具合発生時の調査(不具合個所…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・ オンプレミスで構築された既存システムを、同じくオンプレミスで次期メールシステムへ更改する。 ・…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】某大手企業サポート…
・サポートセンターの運用受入部隊(日勤) として弊社サービスを用いて運用設計 ・構築されたお客様シ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社が提供するサービスサイトの新規立ち上げと既存サイト更新などに携わっていただきます。 多数ある…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【インフラ / 週5日】某官公庁系Webシ…
1) ITSMS管理対象システム 2) 東西DC Active-Active構成 3) 某大手マ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・Linuxサーバのシステム設計、構築、テストとそれに伴うドキュメント作成をご担当いただきます。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・Gitを使用したリリース作業 ・コーディング品質チェック ・HTML/CSSコーディングの本番…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Azure / 週5…
某石油元売企業様における基幹周辺システムのオンプラ環境からAzure への移行案件となります。 移…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】大手SIer内での…
既存本社で導入したOffice365環境(13,000acc)で7,000accをOffice365…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
今回は、既存本社で導入したOffice365環境(13,000acc)で7,000accをOffic…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】大手SIer内での…
既存利用中のOffice365に関連会社のメール環境を統合する案件において、PL、もしくはPLと連携…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Nexus / 週5…
主務:DC/拠点ネットワークの構築業務 ・人材系大手グループDC/拠点内のネットワークインフラ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
Exchange Onlineへのメールシステム移行 案件において、PL、もしくはPLと連携しながら…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
Office365向けネットワークシステムのインフラ運用および派生案件の構築作業 -QA対応 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
海外18ドメインの1テナント統合案件において、PLと連携しながら要件の整理、設計、構築、テスト、移行…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
不動産のコンサルティングをしている会社です。 今まで物件の空室情報などを社外でDB管理していました…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【iOSエンジニア|フルリモート】家電連携…
◇案件概要 家電連携アプリの開発案件開発をお願いします ◇勤務地:リモート可 ◇稼働:週5…
週5日
670,000〜800,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸元町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア(Objective-C、Swift) |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
攻撃トレンドを抽出し、AIによるAWS WAF上での最適なセキュア環境提供を可能にしたセキュリティプ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
・クラウド型Webセキュリティプロダクトの新規機能開発 ・プロダクトグロースのために新機能のアイデ…
週5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
・プロダクトビジョン策定、仕様策定、設計レビュー ・事業/ユーザー両側面からのプロダクト課題抽出 …
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
自社サービス、持ち物の価値がいつでもみえるアプリ開発に携わっていただきます。 ・Androi…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】WE…
自社で運営している複数事業にて、サーバーサイド開発をお任せいたします。 要件定義から実装、テスト、…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
ペット関連のWebサービスの改修、新機能開発。 外部ベンダーで開発していたが、スピードアップのため…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
国内最大級の転職サイト事業を運営している人材紹介企業様において、スクラムマスターとして、プロダクトオ…
週3日・4日・5日
1,010,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・C・C++・C# | |
定番
Androidカーナビの開発
◇案件概要 Androidカーナビの開発案件に常駐で入って頂きます。 ◇勤務地:JR神戸駅周…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
製造業向けのIoT・AI化を推進する企業として、人工知能によってどう解析するかまでを、ワンストップで…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Java・Django | |
定番
【組み込みエンジニア】カーナビの開発案件
◇案件概要 カーナビの開発(組込み側)案件に常駐で入って頂きます。 ◇勤務地:JR神戸駅周辺…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
業務詳細:経費精算などの申請・承認業務を主とした画面開発をご担当いただきます。 ・エクセルベースの…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Angular | |
定番
【リモート相談可 / T-SQL / 週5…
業務詳細:経費精算などの申請・承認業務を主としたDB関連の開発をご担当いただきます。 ・T-SQL…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
疑似恋愛が楽しめる自社サービスのUnityエンジニアを募集しています。 3Dキャラクターのモーショ…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
4年前にリリースした主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、R…
週4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
4年前にリリースした主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、ハ…
週3日・4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Ruby・Java | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、ハイスキルなSREエン…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
4年前にリリースした主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、ハ…
週3日・4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・DBサーバー240台ほど ・移行にあたってのシステム開発 ・<旧>Maria DB→<新>Ma…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二俣川 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Fuel | |
【PM/ディレクター】AI開発ディレクター
【案件詳細】 誰もが知るような、大手企業のありとあらゆるデジタル課題に対し、AIを活用した独自のサ…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/ディレクター |
【MySQL, PostgreSQL】自社…
【案件内容】 ・MySQL, PostgreSQLによるデータベース運用 ・各種サービスサイト用…
週4日・5日
410,000〜470,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| MySQL・PostgreSQL | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
自動化ツールを活用したクラウドソリューションの受注案件に関し、インフラエンジニアとしてシステムの提案…
週5日
330,000〜680,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社で開発している自分の時間をチケットにしてシェアできるサービスのデザイン業務をご担当いただきます。…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
自分の時間をチケットにしてシェアできるサービスを提供しており今回は開発のフロントエンド業務を依頼した…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / Java/PHP /…
ドイツ発の業務データ管理プラットフォームの顧客向けカスタマイズの開発をお任せいたします。 Java…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・VBA | |
定番
【リモート相談可 / Linux/AWS …
・オンプレミス環境、ハイブリッド構成の複数クラウドを併用したインフラの構築、運用 ・1,000台以…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・人間と同じ空間で動作することができる安全なアームロボット(協働ロボット)の最新仕様を調査し、現シス…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
・WEBインターフェースのUI/UXデザイン や空間におけるUI/UXデザイン ・高いプレゼンス…
週3日・4日
260,000〜910,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
コンシューマ向け会員ユーザ向けサービスの業務側からくる要件を基本設計に落とすため、他の連携システムや…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PM/PMO / 週…
・ベンダーへ詳細確認 ・プロジェクトのタスク管理 ・プロジェクトの進捗/進行管理 ・その他付随…
週5日
670,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
・CI/CD によるシステムとオペレーションの自動化 ・システムの信頼性やパフォーマンスを改善 …
週4日・5日
750,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】既存…
今回は下記既存システム(PHP)全般の改修・運用業務をご依頼したいと考えております。 ・古いバー…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・fu… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
事業のあとつぎを探したい方から、後を継ぎたい方への経営のバトンタッチを、 全国約900の士業事務所、…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社Webサイトの更新や改修ができるWebデザイナーを募集しています。 対象サイトは、自社サイトで…
週3日・4日
260,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / Java/PHP /…
①CentOSによる業務環境構築全般 ・DMZ構築 ・Dockerで仮想環境構築 ・ファイルサ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
AIや画像解析技術を活用し、簡単なアンケートに答えるだけで、身体にぴったり合うサイズを表示してくれる…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
マネキンや什器を中心としたディスプレイ製品メーカー。 有名ラグジュアリーブランドや大手アパレルメー…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
インハウスWebデザイナーとして、事業部門が運営している既存サービスサイトのページ制作・更新案件が主…
週3日・4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・ー | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
自動化ツールを活用したクラウドソリューションの受注案件に関し、インフラエンジニアとしてシステムの提案…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
データエンジニア/機械学習エンジニアとして業務を行っていただきます。 マンションの価格査定サイ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
お客様のWEBサイトに関するコーディング・プログラミング) 運用業務は自社作業となります。 ま…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
・ゲームアプリケーションの企画制作 ・WEBプロモーションなどインタラクティブコンテンツの企画制作…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / SE / 週5日】共…
共通ポイントシステムサポートデスク業務(お客様窓口的な業務)をお願いします。 ・共通ポイントシ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
・デジタルカメラのUXデザイン (市場調査や分析、顧客の要求分析、ユーザ体験の設計、関係チームと…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・要求仕様、設計仕様等のインプットに基づくテスト設計およびテストケースの作成 ・検…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】建…
建設業向けの会計(建設仕訳)に関する部分を開発するにあたり、要件定義をご担当いただきます。 対…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
業界最先端のアドテクノロジーを使ってメディアや広告市場を支援する、マーケティングプラットフォームのフ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
業界最先端のアドテクノロジーを使ってメディアや広告市場を支援する、マーケティングプラットフォームのサ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
業界最先端のアドテクノロジーを使ってメディアや広告市場を支援する、マーケティングプラットフォームのサ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
業界最先端のアドテクノロジーを使ってメディアや広告市場を支援する、マーケティングプラットフォームのサ…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・node.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
求人サイトのリニュールサイト本体のシステム構築やアップデートを行っていただきます。 詳細設計か…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
下記業務をお願いする予定です。 ・開発メンバーとして、最新Android TVの機能を活用したTV…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週4…
スマートグリッドに関わる最先端のソリューションの開発・販売を手掛けている企業です。国内だけでなくグロ…
週4日・5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京石川町駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Java・Scala・Play・Framework | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
ソフトウェア開発事業、ネットワーク事業、デザイン事業といった、主に3本柱の事業を行っている会社でござ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】受託…
保険会社向け OEMスマホアプリ及びWEBアプリ開発を行っていただきます。 ・オリジナル版のアプリ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京リモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・WEBサイトやアプリケーションのプロトタイピング ・WEBサイトやアプリケーションの UI デザ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
共通アプリケーション基盤を利用した開発作業 客先での作業は、上記の開発に加えて仕様検討も含む場…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅/代官山・恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【Python / 週5日】バーコード決済…
共通アプリケーション基盤を利用した開発作業 客先での作業は、上記の開発に加えて仕様検討も含む場…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
当社WEBサイトの更新・改修を担当者と打合せし、制作・公開いただきます。 ・WordPress…
週5日
150,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
今回は無人レジシステムの開発に携わるHW/IoT/組込系エンジニアを募集致します。 商品を棚か…
週3日・4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | 組込みエンジニア |
| Python・C・C++・Keras・tensorf… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
共同開発の英語テストサービスに関する案件。 1.開発・運用・保守 2.現在の仕様の調査および、改…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木青山一丁目駅、赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【SE / 週5日】法人向けITコンサルテ…
営業職のテクニカルサポートエンジニア業務をご担当していただきます。 営業の取得した案件に対して…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / サーバーサイド / …
・インフラストラクチャに安定したメインフレームストレージとハードウェアサポートを提供 ・製品のイン…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【Python / 週4日〜】新規開発(検…
日々皆さんが使う検索エンジンの価値にフォーカスを当て、新たな価値を創造してく。 『検索エンジン…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川馬込駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当社が運営する不動産Techメディアにおいて、フロントエンドの開発を担当していただきます。 お任せ…
週5日
370,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
シェアリングサービスに関する新規サービスを立ち上げるにあたりシステム開発全体を一手に請けています。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋/汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
国内最大級の転職サイトを運営している人材紹介企業様において、プロダクトマネージャーの業務に携わってい…
週5日
920,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
受託開発をメインで行っており、そのコンテンツチームにて、WEBサイトの制作等を実施いただきます。 …
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】製…
・「主要拠点のNW改善」「SASEの安定化」「エンドポイント管理適正」「バックアップEoL対応」など…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 東京23区以外多摩市 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】イ…
・製造小売業会社のDX推進に向けて、セキュリティ領域におけるインフラ基盤整備の推進するPM ・顧客…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】新規プラ…
●新規プラットフォーム構想 ・自動車メーカーのサプライヤーにヒアリングし、課題やニーズを整理する …
週5日
550,000〜1,150,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】化粧品メ…
・オープンする化粧品サロンの店舗とタブレット端末での顧客体験を設計し、タブレットアプリ開発にむけたP…
週5日
280,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手パー…
・大手パーソナルトレーニングを全国展開する企業が、ID基盤やマイページ機能の構築を構想しています。 …
週5日
580,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手通信…
・業界 大手通信会社 ・概要 大規模システムに関する提案書執筆支援 ・顧客打合せ、提案書の骨子作…
週5日
500,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
国内屈指の転職サイトを運営されている企業様におきまして、コーポレートサイトや社内インフラ、社内ツール…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
データマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、アプリエンジニアを募集しております。…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / ハードウェア / 週…
・BAU:ロット日程計画、ロット処理、ハウスキーピング ・z / OS、DB2、CICS、IMS、…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
当社のカスタマイズSectionにて、フルスタックエンジニアを募集いたします。 ・自社サービス…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Python・N… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するEdTechのベンチャー企業です。 学習塾向けの新…
週4日・5日
580,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
電子マネー決済システムへのクレジット機能追加 環境:WebAPI, tomcat, Apache,…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・WebAPI | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】大手m…
・SAP Hybrisを使って構築されている既存のマルチテナント向けECシステムをマイクロサービスア…
週5日
500,000〜1,320,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】大手m…
・SAP Hybrisを使って構築されている既存のマルチテナント向けECシステムをマイクロサービスア…
週5日
670,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】大手m…
・SAP Hybrisを使って構築されている既存のマルチテナント向けECシステムをマイクロサービスア…
週5日
750,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
新着
定番
【SAPコンサルタント 】SAPバージョン…
【業務内容】 現状使用している会計システム(AP・AR・GL・AA)がECC6.をオンプレからS/…
週5日
1,100,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿23区 |
|---|---|
| 役割 | SAPコンサルタント |
定番
【コンサルタント】会計部門IT業務およびI…
【業務内容】 総合商社の会計部門でのIT関連業務およびITプロジェクト業務の支援になります。ITプ…
週5日
920,000〜1,280,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京23区 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント |
定番
【コンサルタント/PM】製造販売業SAP …
■プロジェクト全体概要 ・対象モジュール:ロジ(SD/MM)、会計(FI/CO) ※今回は基本的に…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント/PM |
定番
【コンサルタント】大手通信業Ariba導入…
【概要】 SAP Ariba導入済企業のヘルプデスク構築支援 【役割】 SAP Ariba…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川大森駅 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント |
定番
【リモート相談可 / Maya / 週4日…
カタログ画像制作、WEB画像制作、映像制作 設計データを元にしたMayaデータに質感やマテリアルを…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門/神谷町 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
今回はクライアント様のチラシ・パンフレットのデザインをしていただきます。 アートディレクターからの…
週5日
160,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅、新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
大手テレビ局にてAndroidアプリエンジニアとして業務をおこなっていただきます。 開発会社と共同…
週3日・4日
450,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷駅、六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
今回は自社HP、LP、バナー広告の制作、設計をお願い致します。 当社の自社サービスは大手外食チェー…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
随時新規リリースを進めている、以下アプリケーションのReactによるフロントエンド開発をお任せいたし…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
スマートロックに関わるモバイルアプリ、Webアプリや自社ECサイトのトラブルシューティング、保守運用…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / 組み込みエンジニア …
業務詳細:倉庫管理システムの再構築プロジェクトにおいて、キーエンス(KEYENCE)の経験者を募集し…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Visual・Studio | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社プロダクト開発を通じて、多くのブロックチェーン関連事業をグローバルに展開していく予定の企業様の案…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Nuxt.js | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
主にiOS/Androidアプリ開発の受託開発事業を展開しています。 アプリ以外の引き合いも多く、…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React.js | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
・テスト仕様書あり →正常系テストデータあり(エラーデータは仕様書より作成が必要) →テスト結果…
週3日・4日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿和歌山市駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
市場投入済み医療機器の機能追加、保守開発です。一部アーキテクチャ見直しによる技術要素検討を含みます。…
週5日
900,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
Windowsインフラ運用における非定型作業をご担当いただきます。 ・顧客からの新規要件に対し…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
全国約7000台のPCでインプレースアップグレードします。 インプレースアップグレードはMicro…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / .Net / 週5日…
製薬会社の実験用化合物管理システムの再構築案件です。 以下、ご担当いただく業務内容です。 ・…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C# | |
定番
【C#/Net / 週5日】検査サブシステ…
・クライアント・サーバー型システムの保守 インシデント対応 依頼作業(マスタデータ登録、トラ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
コワーキングスペースやイベントなど、コミュニティの中でオープンで横断的なコラボレーションを促進するW…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Docker・MyS… | |
定番
【コンサルタント】SCM需給管理効率化・高…
【業務内容】 コンビニ、スーパー向け包材卸の需給管理業務(メーカー発注)と、東西2か所の中継拠点か…
週5日
920,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京23区 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
オンプレ環境からAWSへの移行案件となりますが、 参画中のメンバーと共に、要件定義フェーズの課題検討…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外府中駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【インフラ / 週5日】ISP内 DC内基…
ISP内データセンター ネットワーク業務です。 某官公庁にて提供しているインターネット接続サービス…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
弊社はソフトウェア技術による語学学習のAI英会話アプリの開発・運営を行っております。 ソフトウェア…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
「人材支援」「資金支援」「テクノロジー」を組み合わせ、国内No.1の成長産業支援プラットフォームの構…
週3日・4日・5日
390,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週5日】…
国内屈指のHRテック企業様において、各サービスの共通基盤の構築や共通モニタリング基盤の構築・監視等の…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
公庁・自治体等を対象とする入札情報速報サービスのリプレイスプロジェクトをお任せ致します。 ソースコ…
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
旅行業基幹システムの改修業務です。 主に画面とそれに伴うDB連携部分の改修要件に対して、基本設計~…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・VB.NET | |
定番
【上流SE / 週5日】WMS(倉庫管理シ…
倉庫管理システムの再構築プロジェクトにおいて、ハンディ業務に使うキーエンスアプリの開発経験者を募集し…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新横浜 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
詳細設計書(新規/改訂版)をもとに、Webアプリケーションのプログラム作成/改修作業を行っていただき…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社はソフトウェア技術による語学学習のAI英会話アプリの開発・運営を行っております。 ソフトウェア…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・React・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・AS400基幹システムの再構築。現行RPGで構築されているシステムをJavaで新たに構築します。具…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・terasoluna | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社サービスのフルリニューアルにあたり、 ・スタイルガイドライン策定 ・ワイヤーフレームの作成(…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田/田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】某大手…
某大手メディア企業内で、アプリ開発及び保守作業をお願いいたします。 ①PHPによるCMSの機能…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
内視鏡AIを作るのに必要な教師データを作成する目的で、データアノテーションを効率良く行う為に独自の社…
週3日・4日・5日
460,000〜820,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】通信…
通信事業者の端末販売ECサイト(アプリ)の要件定義チームでの業務となります。 リニューアルやイベン…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
税理士をターゲットとした新サービスの開発におけるフロントエンド開発をご担当いただきます。 ・フ…
週3日・4日・5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
自社タイトルのゲーム開発を行う企業が提供する「ファンコミュニティ促進サービス」のWebサイトの設計・…
週5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】会員向…
宅配業界に強味を持つシステム開発会社様でオンプレ環境をメインにITサービスを構築されてきました。 …
週3日・4日・5日
840,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東陽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Andriod / 週5日…
Javaでの Androidアプリ開発をご担当いただける方を募集いたします。 既存アプリの改修や新…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | Andriodエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
某外資企業製Webコンテンツマネジメントシステムの運用保守・カスタマイズ。既に稼働中のシステムにおけ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿淡路町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
地理情報を活用し、ウェブやモバイルアプリケーションを通じて様々なオペレーションを行う企業様の業務効率…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React.js… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
自社開発のスマートロックデバイスの開発チームに加わって頂き、製品の企画から量産に至るまでの様々なフェ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 組込みエンジニア |
| C・C++・React | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】移…
現在会社様が抱えられているシステムを他社にリプレイスをする際のディレクション業務となります。 社内…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【サーバーサイドエンジニア】保守開発エンジ…
【職務内容】 医師向けサービスにおける保守開発を担当頂きます。 【業務内容】 ・既存サービ…
週2日
330,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| RubyonRails | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】アプリサービス…
【業務内容】 当社の歩数計アプリサービスの運用開発に従事していただきます。 コンテンツの追加や、…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
新規スマートフォンゲームのフロントエンド(Unity)開発、運用を担当していただきます。 ・Uni…
週5日
460,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・C・C++・C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
車好きコミュニティアプリのUI改善をメインでお願いしたいと考えております。 コミュニティサービ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社で開発を行っている、クラウド人材管理ツールの新規機能の開発や既存機能の改善対応、バグの修正を行っ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel | |
定番
【3DCG / 週4日〜】新規モバイルゲー…
新規モバイルゲーム開発における、3Dモーションデザイン業務をお任せいたします。 ・キャラクター…
週4日・5日
480,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Maya・MotionBuilder | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
・大手企業と共同での事業開発業務 ・新規事業 / サービスの企画 ・既存事業の最大化に伴う戦略立…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
大手電機メーカーG企業にて、新規サービスの開発を行っております。 今回は、Railsでのバック…
週3日・4日・5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】世…
UnrealEngine4を駆使したVRアクションゲームの開発に従事して頂きます。 ユーザー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・C・C++ | |
定番
【AWS / 週5日】VRゲームのアートセ…
VRゲームは、ユーザーの体験することを重視しながら、想定と実証、検証を繰り返してVR空間ならではの新…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | エフェクトデザイナー |
定番
【Unity / 週5日】VRゲーム(MO…
世界市場に向けた新規VRタイトル(MO型RPG)のグラフィック/VR空間で表現する2D UIの制作を…
週5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
まだ世の中にないプロダクトを生み出すことで人々に新しい体験を提供し続ける会社を目指しています。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿明治神宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【テスター|フルリモート】Webサービス及…
【案件概要】 Webサービスや開発システムにおける品質管理及びデバックテスト業務ができるテスターを…
週5日
250,000〜530,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海外 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【Unity / 週5日】 VRゲーム(M…
世界市場に向けた新規VRタイトル(MO型RPG)のグラフィック/VR空間で表現する2D UIの制作を…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| UnrealEngine4・Maya・MotionB… | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
自社サービスの開発や自社基幹システムの開発・保守・運用をお任せします。 業務委託としてはもちろ…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
弊社の社内SEとしてトラブル対応などのヘルプデスク業務や、既存の基幹システムの保守運用、システムの改…
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
潜在的な顧客に対する需要喚起や新たな価値提案を目的としたクリエイティブ企画・制作に取り組みます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅、東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
クライアントの成功体験づくりに参加するデザイナーは、サービス利用開始時から利用中に関するプロダクト周…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅、東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため医療統計データサービスを提供している会社です。…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】診…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するために医療統計データサービスを提供しています。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大門駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
この度の募集では、システムの運用保守をお願いいたします。 ・日々のルーチン作業の実施 ・データ運…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
UnityにてUI/UXの改善、バグ修正を担っていただきます。 また未実装の新規機能のクライア…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / Ruby/Go / …
法人向けクラウドサービスおよびコンシューマー向けモビリティサービスアプリケーションにおいて、バックエ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go・rails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社が運営する医療メディアをスケールさせるために、既存サービスのPDCA、メンテナンス、新サービス開…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
チラシやポスターなど広告印刷物のグラフィックデザインや、チャットツールなどで広告配信する際のテンプレ…
週5日
160,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
既存プロジェクトでのCOMPANY運用保守業務です。 まれにBPO業務支援もあります。 CO…
週5日
1,010,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【AWS / 週5日】B2Bの自社サービス…
地方の中小・ベンチャー企業や個人商店を救うためのサービスを提供しています。 ・AWS を用いたイン…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】S…
某大手ITコンサルティングファームの品質管理チームにメンバーとして入り、納品物のチェックをしていただ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / http://adm…
弊社は統計学とコンサルティングのを活かしたニーズに特化した分析をするためのアプリケーションを自社開発…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
既存Webサービスおよび新規WebサービスのWeb開発エンジニアを募集しています。 企画、設計、開…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
通信キャリアのポイントカードスマホアプリのiOS/Androidバージョンアップ対応をお願いいたしま…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
今回はサーバーサイド開発を中心に担っていただきます。 ・インターネット広告配信やアクセスログ解析に…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
eコマース総合支援会社にて、ECサイトのデザインをはじめ、ランディングページやバナーデザインに携わっ…
週3日・4日・5日
150,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【Vue.js / 週4日〜】仮想通貨・ブ…
当社はベンチャー・中小企業の資金調達をトータルに支援するプラットフォームの提供を通じてベンチャーエコ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Java・Scala・Vue.… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
SET (Software Engineer in Test)としてデータ分析ウェブサービスの品質の…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Go・Gin・G… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務 -サービス情報サイトやLPの作成、更新 -広告…
週4日・5日
250,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
医師専用コミュニティサービスの継続開発になります。地域医療に関わるサービスとなっており社会貢献性の高…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Vue.js・Nuxt.js・Vuetify | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
医師専用コミュニティサービスのリニューアル開発になります。 地域医療に関わるサービスとなっており社…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
要件定義や設計書作成などの上流工程や開発メンバーのマネジメント、コードレビューをお任せできる方を募集…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / フロントエンド / …
通信事業者の運用チーム内での業務です。 既存のElasticsearchとKibanaのバージョン…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
キャッシュレス決済の自社サービスを開発するGoエンジニアとして、マイクロサービスアーキテクチャを設計…
週4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GCP | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】機…
機械翻訳サービスを提供しているユーザ企業に常駐し、ITディレクターという立場でシステム企画~運用まで…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
スマホ向けオンラインゲームの企画・開発・運営を行なう企業です。 ゲームやWebサービスのイン…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
スマホ向けオンラインゲームの企画・開発・運営を行なう企業です。 今回は、iOS/Android向け…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
お客様向けにデザイン思考とUXデザインを駆使した新規サービスの企画・既存プロダクトの改善や、AI/I…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JQuery / 週…
次世代型の電子薬歴システムのサービスページ・コーポレートサイトデザイン・コーディングを担当いただきま…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】W…
生保向けペーパレスシステムの保守案件のプロジェクト推進をお願いいたします。 ・要件の取り纏め、ベ…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】某企…
新規機能の開発、既存機能の改善対応、バグの修正 業務の流れ Redmineで案件管理されてい…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
※原則、基盤チームのため、主に不具合改修や調査などが主業務となります。 一番主要な作業はコンテナ開…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Angular・ion… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
下記業務にご参画いただけるエンジニアを募集いたします。 ・現在、使用している基幹システムのKi…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Android/iO…
WEBアプリケーション・WEBサービスを受託にて企画・戦略立案・設計・開発・保守などを行われている企…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
自社ネットワークセキュリティシステムの新規開発 現在設計の段階で、Ruby on Railsで…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
人材紹介業向け基幹システム開発(自社開発クラウドシステム)の開発業務をご担当いただきます。 大手ユ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・C#・VB.… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
弊社の新規プロダクト開発チームのエンジニアとして業務をご担当いただきます。 AWS環境での運用にな…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】セ…
金融系の不正送金ならびに不正ログインを防止するため製品を導入するプロジェクトのPMをお願いいたします…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社開発のほか研究機関や事業会社との共同研究によりノウハウを蓄積しています。 今後は同分野でのサー…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿成増駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・C・C++・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
ユーザーへ価値を届ける最前線となる機能開発やそのバックエンドのAPIを開発する責務を担って頂きます。…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| JavaScript・Python・TypeScri… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
事業ごとにビジネス課題の抽出、課題分析~解決に向けた提案や機械学習による効率化を行うにあたって、全事…
週5日
880,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため、医療統計データサービスを提供している会社です…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・VB.NET・SQL | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】先…
大学受験に臨む高校生の方を対象にした教育のプラットフォームを運営する企業様です。 今回は生徒と先生…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【iOS/Android / 週4日〜】マ…
女性の妊娠~出産を支える、ママ向けコミュニティアプリやビッグデータアプリを開発しています。 機能ご…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
弊社クライアントサービスのインフラ構築支援。 AWS上での環境構築、設定、システムテストを行ってい…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP/Ruby /…
既存サービスにおける開発・運用マネジメントや新規サービスにおけるシステム開発マネジメントをお任せしま…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
WEBアプリケーション・WEBサービスを受託にて企画・戦略立案・設計・開発・保守などを行われている企…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
求人サイトの改修において企画、設計、ディレクションから実装まで幅広く関わる案件です。 具体的には、…
週4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
求人サイトの改修において企画、設計、ディレクションから実装まで幅広くかかわることの案件です。 具体…
週4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
Webサービス、アプリのUIデザインやランディングページデザインをお願いいたします。 サービス…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【UI/UXデザイナー|フルリモート・週3…
【案件概要】 環境領域GX SaaSをグロースするUI/UXデザイナーとして以下の業務に携わってい…
週3日
250,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【コンサルタント】運輸会社の営業部門の業務…
【業務内容】 貿易に関する情報連携をデジタル化していくプロジェクトになります。 ユーザー部門・I…
週5日
950,000〜1,230,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京23区 |
|---|---|
| 役割 | コンサルタント |
定番
プロダクトマネージャー
・KPI達成のための施策の立案&実行 ・SEO施策 ・WEBサービスの改善・成長(グロースハック…
週2日
200,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトマネージャー |
定番
【データアナリスト】学習塾における基幹デー…
■対応内容 ・保守運用 AWSのデータ取り込みの管理、運用 デイリーバッチの理解と管理 …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| SQL・AWS | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるフロントエンドの開発です。小学校~高校、専門学校の…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週4日〜】…
スマホ向けアプリをUnityとC#を使いリプレイスする開発を行っていただきます。(C++は読めれば問…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
データサイエンスプラットフォームサービスの立ち上げメンバーとして、サービスの企画・開発から運用までを…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】人材紹介企…
転職サービス、メディアサイト、プロモーションサイト、コーポレートサイトなどを担当するデザイン部署のポ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため医療統計データサービスを提供している会社です。…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大門駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
実際の現場経験のあるメンバーがいる強みを活かし、建物メンテナンスに関する総合ITシステム開発を推し進…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・CodeIgniter・Rails | |
定番
【Railsエンジニア】Web3サービスを…
自社サービスに関わる業務を担当していただきます。 <募集職種> Railsエンジニア(Rai…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Railsエンジニア |
| Ruby | |
定番
【インフラエンジニア】各種自社システム開発…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ/ フロントエンド/ 週5日】W…
【担当業務】 WordPressの改修(フロントエンド) 【案件の魅力】 ・完全リモート可…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
新規事業立ち上げに伴う、新サービス開発(Ruby)のサーバーサイドでの設計・開発業務です。 開発業…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【WEBデザイナー】自社サービスのデザイン…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
業界は、旅行/観光系や、食品、省庁関係等、幅広いジャンルの案件を扱っております。 今回は、キャンペ…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
同社で展開されているサービスのWEBデザイナー職で募集しています。 複数並行して展開している様々な…
週3日・4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
ブログの内容を理解して、改善できる人を希望しています。 また今論文の内容を実装していますが、現在の…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅、築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
定番
【WordPressエンジニア】海外HPに…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / VB.net / 週…
バス会社に提供するシステムの開発をVB.NETを用いて行っていただきます。 ※いくつかのプロジェク…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉川口駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| C#・VB.NET・VBA・.NETFW | |
定番
【.NET / 週3日〜】新規商用パッケー…
自社で開発したプロトタイプのシステムをベースに、商用パッケージを新規開発するプロジェクトの開発担当エ…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京九段下 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VB.NET・.NET・Framework | |
定番
【リモート相談可 / VB.net / 週…
バス会社に提供するシステムの開発をVB.NETを用いて行っていただきます。 ※いくつかのプロジェク…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉川口駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| C#・VB.NET・VBA・.NETFW | |
定番
【WordPressエンジニア/PM】海外…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア/PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
自社で開発したプロトタイプのシステムをベースに、商用パッケージを新規開発するプロジェクトのデザイン・…
週3日・4日
390,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
建設業向けの会計(建設仕訳)に関する部分を開発するにあたり、基本設計~テストまでご担当をお願いいたし…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・EJB | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】プ…
・プロジェクトマネジメント標準、工程標準の制定 ・計画書や設計書などのテンプレート等の作成・修正 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
要件定義・企画から、ユーザーへのアプローチ方法を検討し、ユーザー体験を設計して、プロダクト全体をデザ…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
今回はコンシューマーゲームの開発に携わっていただきます。 特にクライアントサイドの開発を担当します…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++・C#・Unity・Unreal・Engi… | |
定番
【SQL / 週5日】店舗管理POSシステ…
導入先顧客向けにネットカフェ店舗管理POSシステムのカスタマイズを行います。 顧客折衝含む、設計、…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
受託会社におけるデザイナー業務です。 Webサイトのデザイン業務全般を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
240,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
コミュニティサイトのRubyを使用したサーバーサイド開発になります。 フロントエンド(JQuery…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】大…
大手卸売業会計システムを再構築しており、そこへの事務管理側からの機能追加要望への対応を行なって頂きま…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】自…
担当していただくプロダクトのiOSアプリの開発・運用業務を中心にお任せいたします。 ・iOSアプリ…
週5日
670,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【デザイナー / 週5日】WEB・アプリ・…
今回は、社内デザイナーとして業務を行っていただきます。 ・WEBデザイン ・自社開発アプリ・シス…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅・都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Adobe・XD・Photoshop・Illustr… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
社内のオペレーション作業を自動化するためのシステムを自社内で開発をしております。 今回の募集では、…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
自社サービス、新規サービス、クライアント案件などの設計・開発・運用をメインに携わっていただきます。 …
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社サービス、新規サービス、クライアント案件などの設計・開発・運用をメインに携わっていただきます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
・ユーザー体験向上のための、UI/UX改善 ・ワイヤーフレームやUIモックアップなどによるプロト…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Rails・… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
クレジットカード業務システムにおけるバッチ業務アプリケーションの開発です。 DB to DB、また…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅、新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・logstashによるデータのフィールド分割および加工 ・既存システムのバージョンアップ対応 …
週5日
590,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
リフォーム事業において人気の高いシステムキッチン・ バス・トイレなど 、水回りのリフォームを主軸にサ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週3日〜】中小企業…
自社サービスとして中小企業の口座情報を基に信用度を図る動態モニタリングシステムの運営を行っております…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 新サービスをゼロから立ち上げる醍醐味を味…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ソーシャルゲームのデータ分析業務を担当していただきます。 ・イベント等のデータ集計、レポート作…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・SQL・R | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社サービス全体で集めたデータを分析する社内ツールの新規開発になります。 集めたデータを今後さらに…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
医療領域、認知症医療に特化した自社サービスを開発しています。 今後、事業拡大していくなか自社サービ…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】国…
構築済みの海外WMSベースシステムを、国内の顧客向けにカスタマイズいただきます。 業務は入荷検品・…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Go / 週…
事業急成長につき、安定したサービス基盤を提供するべく開発チームを大幅増強中です。 工程管理などのP…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
IoT・ビッグデータ活用の自社サービスの事業急成長につき、安定したサービス基盤を提供するべく開発チー…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / swift/Kotl…
主にiOS・Androidのアプリ開発を行っていただきます。 取引先には大手クライアントが多く、ス…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京馬喰横山駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Sw… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
選挙・政治活動におけるコミュニケーション・サポーターである弊社にて、InDesign、Illustr…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京木場駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
2Bサービスのプロダクト開発を連続して立ち上げる予定があり、現在は開発速度を優先してRuby on …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Go・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
東証一部上場証券会社が、最先端のテクノロジーを活用した次世代金融サービスを創出し、展開していくために…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・機械学習の技術を用いたデータ分析業務 ・機械学習の技術を用いたシステムの開発・運用 ・NoSQ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・SQL・R | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
募集企業は、まだ若い企業であるため毎日変化のある環境ですが、デザインに対して社員全員がアイデアを出し…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
ゲームには複数のステージがあり、各ステージのテーマと音楽に合わせた演出(リズム、カメラワーク、配置さ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Androidjav…
アプリ開発支援クラウドサービス ネイティブ開発言語不要のクラウド型アプリ開発支援サービス。 HT…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリエンジニア |
| Ob-C・AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
ビジネスを効率的かつ創造的に推進するための"指針"となることを目的としたデジタルマーケティング総合支…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
基本業務としては、事業部門が運営している既存サービスサイト(約19サイト)のページ制作・更新案件をH…
週5日
240,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
・ベンダーコントロール ・IT周りのコーディネート ・サーバリプレイスについてのアドバイス ※…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅/表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
ユーザーと小売店をつなぐ国内最大級のモバイルメディアを運営しています。 BtoC、BtoB双方の位…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Flask・SQ… | |
定番
【PHP / 週3日〜】e-learnin…
システムは、Yii2 というフレームワークで構築されています。 国内では、あまり聞き慣れないフ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Yii2 | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
リリース後の課題解決のための機能改修や追加機能の開発、新規ユーザー獲得に向けたマーケティング施策実施…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】入…
入館・退館管理のシステム開発を担当していただきます。 本システムはVB.netとC#.netで開発…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿曙橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
リファラル採用をより活性化するためのWEBサービスを開発しています。 既存で運用されているWEBサ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社サービスの勤怠管理システムのリニューアルプロジェクトが現在走っています。 そのプロジェクトにお…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Salesforce…
新規PJT/業務拡大の為、Salesforceエンジニアを募集しております。 具体的には、 Sa…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Salesforce | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社開発のAIの技術を取り入れたプロダクトの機能追加開発などに携わっていただきます。 あらゆる書類…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
- ビジネスパーソン向け動画見放題サービスアプリの開発 - 数年以内に検討している、学び放題のグ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Pivotal・Track… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
- ビジネスパーソン向け動画見放題サービスのフロントエンド開発 - 今後展開予定のオンライン学習…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・react-red… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
-ビジネスパーソン向け動画見放題サービスのバックエンドの開発 -数年以内に検討している、学び放題…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails5・RSpec | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
- 新規プロダクトのインフラ設計・構築業務 - ビジネスパーソン向け動画見放題サービス「グロービス…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
大手百貨店における、モバイルアプリ開発です。 既存のアプリケーションに対して、機能追加を行います。…
週3日・4日・5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
新たに展開するサービス全般にわたるインフラ領域をお任せします。 AWSにデジタルサービスのインフ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / RPA / 週3日〜…
RPAソリューション開発支援事業にて、RPAツール使用のセミナーやお客さまがRPAを導入する際…
週3日・4日・5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
創業から現在までにチャット、エンタメ、銀行系、IoTなど様々なスマホアプリを開発してきました。 扱…
週5日
440,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
・Unity製ネイティブゲームの開発・運用業務 ・UI/UX 開発 ・InGame 開発 ・ネ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【フルリモ / JQuery / 週3日〜…
WEB技術をベースにコーポレートサイトや業務システムからネットショップ開発・運営までを行っています。…
週3日
170,000〜260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
処方箋のネット受付やお薬の宅配予約等を行える、スマホアプリの開発をご担当いただきます。 弊社アプリ…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Google・Vision・Api | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週5日…
案件増加に伴い、フロント・サーバーサイドそれぞれ開発経験があるSEを募集しています。新規~追加開発が…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社既存サービスの機能追加開発を要件定義含め進めていきます。 要件から整理する必要のある部分もござ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】通…
通信事業者のBtoC料金系システムに関して、業務部門と要件定義を行っていただきます。 外部・内…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
新規スマートフォンゲームのUIデザイン制作業務を担当していただきます。 ・企画、画面設計、UIデザ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Photoshop | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現在は自社プロダクトで様々な角度からアプローチをし、得たノウハウで企業と協業で新たな価値を創造してい…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
ビッグデータを処理するための、インフラや基盤システムの構築、開発、保守、データ加工等を行っていただき…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,若葉台駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| PHP・Python・Java・SQL・AWS | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】工…
顧客社内システムである工作機器ソフトウェア開発です。 顧客要求をもとに要求仕様作成~アーキテクチャ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新木場 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社が運営するHR系サービスにおいて、マークアップエンジニアとして業務を行っていただきます。 メイ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
Androidアプリのプロジェクト設計/実装をご担当いただくお仕事です。 ・Android …
週5日
660,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / セキュリティ / 週4日〜…
・エンドユーザ様情報システム部でのSOC(Security Operation Center)での運…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
iOSアプリのプロジェクト設計/実装をご担当いただくお仕事です。 ・Swiftを利用したiOSアプ…
週5日
660,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【Java / 週5日】一部上場のグループ…
グループ会社のリクルートライフスタイル社のAirプロジェクトの主にサーバーサイドの設計/実装をご担当…
週5日
660,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Seasar | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
新聞折込・ポスティング・DMサービスの開発・運用業務をご担当いただきます。 PHP/Symphon…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
会員登録をし、テンプレートを選択して写真やテキストを用意するだけで簡単にホームページを作成出来る自社…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / .NET / 週5日…
現行アプリケーション(mod_plsql)の仕様調査・仕様書作成業務をご担当いただきます。 具…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| HTML・JavaScript・VB.NET・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週5…
スマートフォン向け既存ゲームのサーバサイド設計、開発、運用、機能追加、改善業務となります。 (アク…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Play・Framework・… | |
定番
【Python / 週5日】エンジニア育成…
Pythonのメイン講師のサポートをしてくれる方を募集しております。 業務内容は新卒受講生の方への…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / データエンジニア /…
自社内で取り扱っております、SFA&CRMデータの基盤部分のデータ移行業務を担える方を募集しておりま…
週3日・4日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
PHP、ブロックチェーン、アプリ開発を担当して頂きます。 詳細は、面接時にお伝えします。 基本的…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
PHP、ブロックチェーン、アプリ開発を担当して頂きます。詳細は、面接時にお伝えします。 基本的には…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
PHP、ブロックチェーン、アプリ開発を担当して頂きます。 詳細は、面接時にお伝えします。 基本的…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
スタートアップ企業向けサービスのマルチプラットフォーム開発です。 ・サービス全体のアーキテク…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
弊社が運営するHR系サービスにおける、フロントエンド開発業務をご担当いただきます。 サービスを運用…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
商談に関する膨大な動画、音声、テキストデータを蓄積しており、これらを解析することで、これまで個人個人…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Backlog・Redash・Elas… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
メディア事業とコンテンツ事業の2本の柱で事業展開を行うデジタルメディア・コンテンツ開発企業です。 …
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社が運営する不動産同時査定サービスにおいて、フロントエンドの開発を担当していただきます。 フロン…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
1 Webアプリケーション(WEB GIS)、javascriptのフロントエンドの開発 2 We…
週5日
460,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C#・.ne… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】自社…
・開発者がより高速に開発できるための開発環境の改善 ・CI/CDやデプロイパイプラインの改善 ・…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
コミュニケーションに特化した対話型AIを搭載した自社アプリの開発。 これまで「調べることを便利…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
コミュニケーションに特化した対話型AIを搭載した自社アプリの開発。 これまで「調べることを便利…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【JavaScript / 週3日〜】自社…
具体的な作業米用として、 物流クラウドサービスの開発 ・Webアプリケーションのサーバサイドおよ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
主にiOS・Androidのアプリ開発を行っていただきます。 取引先には大手クライアントが多く、ス…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
メディア事業とコンテンツ事業の2本の柱で事業展開を行うデジタルメディア・コンテンツ開発企業です。 …
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Cake | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
メディア事業とコンテンツ事業の2本の柱で事業展開を行うデジタルメディア・コンテンツ開発企業です。 …
週3日・4日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
人に寄り添い、まるで秘書や親友のような存在となる。そんな、コミュニケーション・関係性に特化したAIを…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・C… | |
定番
【正社員/ リモート可能】新規事業における…
【担当業務】 ・Web版漫画サービスの新規開発・運用改善 ・CS対応、一部インフラリソースの設定…
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
ベンチャー企業特化の就職サイトを更にスケールさせるべくUI・UXの改善をお任せします。 ・自社…
週3日・4日・5日
250,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / CakePHP / 週4日…
・開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 ・機能開発における設計~実装~リリースまで ・ユ…
週4日・5日
580,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・CakePHP・Vue.js | |
定番
サーバーサイドエンジニア(マンガ新規事業)
当漫画事業では新規開発、運用改善などの開発をはじめ、CS 対応を行っていただきます。基本的には Go…
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】El…
ニューノーマルな働き方を推進するゼロトラストセキュリティサービス実現のため、デバイスログ/認証ログ/…
週5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手メデ…
大手メディア企業が保持するユーザー視聴ログおよび外部データを利用した広告商品開発・効果最適化を目標と…
週5日
750,000〜1,900,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| SQL・GCP(BigQuery・CloudFunc… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
弊社では短期間・短時間の仕事に特化し、柔軟な働き方を望む個人と必要な時に必要な分だけ人材を活用したい…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Kotlin・Gin | |
定番
【C# / 週5日】勤怠管理システムの基盤…
SaaS型サービスの勤怠システム・仕事可視化システムを扱う部署で、アプリを構成するフレームワークやツ…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・C#・-・SpringFramework・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
サイト上で募集しております様々なファンドから気に入ったものを選んで資産運用に参加ができるクラウドファ…
週4日・5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Fuel・PHP | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
自社の情報システム部をとして自走できるように移管作業中に伴い、情報システム領域を専任者としてご担当い…
週3日・4日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】広告効果…
大手メディア企業が保持するユーザー視聴ログおよび外部データを利用した広告商品開発・効果最適化を目標と…
週5日
750,000〜2,270,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
事業拡大と生産性向上の両立を図るために、SFAやCRM、ワークフローなどバックオフィス関連システムの…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
現在、会社規模拡大中のためエンジニアリーダーとしてのスキルを磨きたいメンバーを募集中です。 今回募…
週5日
330,000〜680,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
自社サービスの新機能設計・開発および機能改善に携わっていただきます。 ・自社サービスのAPI、…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Go・Types… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
コーポレートサイトやオウンドメディア、キャンペーンページ等のデザイン業務を担当していただきます。 …
週5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
弊社では短期間・短時間の仕事に特化した1日単位のお仕事プラットフォームの開発を行っております。 …
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Kotlin・Go | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
サービス表層のデザインだけでなく、企画の段階から、事業リーダーやエンジニアたちとサービスを共創したい…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【大手コンサルファーム案件】日本の大手製薬…
【案件内容】 製薬会社のSAPコンサルを担当していただきます。 ▼業務内容 ・海外の…
週5日
470,000〜2,370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | SAPコンサルタント/エンジニア |
| ・ | |
定番
【リモート相談可 / UX / 週3日〜】…
サービス表層のデザインだけでなく、企画の段階から、事業リーダーやエンジニアたちとサービスを共創したい…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / photoshop/…
Webサイト版を新規で作成するにあたり、新たにデザイナーの方を募集いたします。 画面遷移やワイ…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
自社でサービスを展開しております、エネルギー業界専門ニュースアプリのUI/UXデザイナーの方を募集し…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
当グループは、人材派遣業・求人広告事業・人材紹介事業を主軸に 様々な事業を展開し、人と組織の課題解…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・VB.NET・SQL… | |
定番
【リモート相談可 / Jquery / 週…
JavaScriptからAPIを実行し、取得したjsonの情報を元に、Queryで画面に反映いただき…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社が展開しているスマートフォンアプリ情報サービスのデザイン業務をご担当いただきます。 弊社プロデ…
週3日・4日・5日
370,000〜690,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【リモート相談可 / 社内SE / 週5日…
全国の中小、ベンチャー企業の社内SEを請け負っている会社にて以下業務を担当頂きます。 具体的に…
週5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西日暮里駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift/Java…
コミュニティサービスの事業を開発しております。 世界的にみてもユーザー規模の大きい弊社コミュニティ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社の各プロダクトが利用する、バックエンドサービスに関連する開発となります。 (アカウント管理、プ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・定形(日次、月次、年次)的な各種運用業務(特定データの抽出など) ・各種ログの収集や調査 …
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
大手通信キャリア向けのNW/仮想化基盤(AWS)開発業務です。 方式検討、設計、コンフィグ作成・手…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / AWS/NW / 週…
大手通信キャリア向けのNW/仮想化基盤(AWS)開発業務です。 方式検討、設計、コンフィグ作成・手…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Python, Vue.js, Bootstrap4などを用いたWebサービスの開発・運用などを担っ…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
交通手段に比較サイト等、複数のWebサイトを運営しております。 ご参画いただいた後は、自社で運営し…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、フロントエンドエンジニ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週3日〜】…
自社で開発を行っておりますOMR(光学式マーク読取専用装置)やOCR(光学式文字読取装置製品)の追加…
週3日・4日・5日
500,000〜950,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、UI/UXデザイナーを…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
製薬業界をメインとしたWEBサイト制作を行っています。 ディレクターと共にWEBサイトのデザイ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手フィナンシャル・グループのネット金融サービスの中核会社として、グループ各社との連携によりさまざま…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】大手株式投…
大手フィナンシャル・グループのネット金融サービスの中核会社として、グループ各社との連携により、さまざ…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C++/C / 週5…
業務詳細:組込み用RTOS等を用いた環境向けに以下の対応をお願いいたします。 デバイスドライバ開発…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++・言語:C++・・C | |
定番
【リモート相談可 / IOS/Androi…
現在サービスリリースに向けて開発中の、カスタマー向けのマッチングアプリ開発に携わっていただきます。 …
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
建機メーカー向けサービス開発にインフラエンジニアとして携わっていただきます。 業務の内容としては、…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京宝町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWSLambda・NoSQL | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・WEBサイト制作/運営/更新 ・コーディング ・LP制…
週3日・4日・5日
230,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外牛浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
・Fintech: Financeテクノロジーに特化したコンサルティング・サービス開発 ・Mar…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】V…
グループ企業の不動産会社にてVDI導入後、翌年には支店も含めた8000台を対象として本番展開中。 …
週5日
830,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VDI・VMW | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ソーシャブルカート向けのunity/unreal engineアプリ開発を行っていただきます。 …
週3日・4日・5日
720,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社媒体からの集患を目的とした、WEB制作(紙・WEB)をご担当いただきます。 現在クリニックを4…
週3日・4日・5日
250,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
完全自社開発の社内システム開発に携わっていただきます。 ・社内管理ツールの新規機能開発/追加機…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
Webアプリケーションとして既にサービスを運営をしておりますが、今回スマホアプリ化するプロジェクトが…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
保険の業務系システムに携わっていただき、機能追加や保守運用業務を行っていただきます。 当社は、…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C・C++・VB.NET | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
主軸の投資コンサルティング事業に加えて、不動産セミナー事業にも力を入れはじめました。 その不動産セ…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社プロダクトのサーバーサイドの開発を担当していただきます。 サービス企画サイドとの連携もしながら…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
プロダクトデザイナーやUIデザイナーと連携しながら、より良いプロダクトになるよう新しい機能の開発を業…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【Java / 週5日】Java開発案件
本件はJavaを用いた業務システム開発の保守・運用業務を想定しています。 設立以来40年が経過…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
経営陣や現場メンバーと擦り合わせながら、自社プロダクトのスマートフォンアプリの開発全般をお任せ致しま…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
プロダクトデザイナーや他のUIデザイナーとも連携しながら、より良いプロダクトになるように画面デザイン…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Python / 週5日】企業向けプログ…
新入社員向けIT研修にてサブ講師としてメイン講師のアシスタントをしていただける方を募集しております。…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Java | |
定番
【インフラ / 週5日】個人認証基盤運用リ…
IT部門における運用リーダーとして、個人認証基盤の運用部隊との調整や関係各所との調整をおませします。…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
受託しているWebサイト更新・開発業務を行っていただきます。 業務内容はCMS(MT)での更新…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python/SQL…
顧客が保有する数年分の予約実績データや、イベントデータなど外部データを基に、需要・売上着地予測など、…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】ノーコ…
ノーコードツールを用いたシステム開発を行う企業での品質管理に関わる業務をお任せ致します。 フルリモ…
週3日・4日・5日
280,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
人材データのサーベイおよび対象者へのAIを用いたアドバイスを行うWebアプリケーションの運用開発を行…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社開発サービスを軸に、周辺サービスの立ち上げ、それに伴う中核APIサービスのリファクタリング、既存…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
新規モバイルゲーム開発における2Dアニメーション業務をお任せいたします。 ・Spineを用いた…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
| Unity・AfterEffects・Spine・S… | |
定番
【リモート相談可 / イラスト / 週4日…
自社開発ソーシャルアプリケーションに使用されるキャラクターやアイテムなどのイラスト制作業務をお任せし…
週4日・5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
定番
【HTML/CSS / 週4日〜】自社We…
自社WEBサイトのコーディングを担当いただきます。 当社メディア運営の中での修正・変更、新ページの…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
新規事業立ち上げに伴う、新規サービスのWebフロントの設計・開発業務です。 開発フェーズとしては、…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・G… | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
「婚活」「妊娠・出産・育児」サービス領域で、エンジニアが身近にいる環境で、協力しながらアプリのUIデ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社で運営するファッション系ECサイトのバナー作成などデザイン業務や、主催するファッションイベントに…
週3日・4日
190,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【Java / 週5日】資金取引の管理シス…
某大手銀行(NY拠点)では、資金取引の管理を行うシステムを新規構築します。 本案件は、現行システム…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前または新宿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SQL・Shell | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
・設計・開発支援 大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスの認証決済サブシステム…
週3日・4日・5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当社は、価値ある車好きコミュニティの提供にチャレンジしております。 今回は、新規で立ち上げるE…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
受託でWEBサイト制作やリニューアルを行なっております。 現在、美容室に通う会員向けポイントサービ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
自社モバイルアプリの開発・運用プラットフォームを通じて大手クライアントのWebサービス、iPhone…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】自社サービスの…
自社サービスのシステム拡張に伴いエンジニアを募集いたします! クライアントの要望に合わせてカス…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・jQuery・MySQL | |
定番
【ゲームプランナー|週4日~5日】コンシュ…
【案件概要】 国内外に様々なゲームを提供している会社において、グローバル展開予定コンシューマーゲー…
週4日・5日
170,000〜380,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
自社モバイルアプリの開発・運用プラットフォームを通じて大手クライアントのWebサービス、iPhone…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
コーポレートサイトの大規模リニューアルに向けたコーディング、デザイン業務(メインは制作会社に頼まれる…
週3日・4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【SAPコンサルタント 】S/4HANA導…
【業務内容】 ・S/4の標準機能+設定で対応できないため追加開発する機能に関する、以下の要件定義資…
週5日
1,100,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京23区 |
|---|---|
| 役割 | SAPコンサルタント |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】銀…
業務詳細:某銀行様におけるAML(anti-money laundering)関連案件のPMO作業全…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿勝どき |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、コーダーを募集しており…
週4日・5日
370,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
弊社が運営するコンシューマー向けヘルスケアアプリのデザイナーとして、ユーザー向けプロダクトのUI/U…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規自社サービスのデザインやLPのデザインをお任せできる方を募集しております。 また、ご経験のある…
週3日・4日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
創業から現在までにチャット、エンタメ、銀行系、IoTなど様々なスマホアプリを開発してきました。扱う領…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / 運用保守 / 週5日…
顧客の情報システム部門と共に、Salesforceの活用検討を行っていただきます。 調査/検証しな…
週5日
630,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・ECサイトサービスシステムのリニューアルに伴い、既存システムのDB分析~新システムでのDB設計、構…
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Go】AIによる契約書レビューサービスの…
【仕事内容】 - AI契約管理システムのバックエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テ…
週4日・5日
410,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・SpringFramework・SparkFr… | |
定番
【UI/UXデザイナー】患者/医療従事者に…
医療領域のドメインスペシャリストなどのメンバーとともに、患者(toC)・医療従事者(toB)に向けた…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・Figma・XD | |
定番
【経理スタッフ】金融系Saasの経理リーダ…
FinTechスタートアップでの事業拡大に伴う経理リーダーを募集。 【仕事内容】 (1)各種…
週3日・4日・5日
160,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 経理 |
新着
定番
自動車業界のWebデザイナー業務
概要:大手自動車メーカー案件。APIポータルのデザイン対応(追加開発対応) 詳細:Figmaでのデ…
週3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 品川豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【SQL/Python】ECサイトにおける…
・新規案件の改善提案用分析(ツール:GoogleAnalytics他アクセス解析ツール ・ECシス…
週4日・5日
160,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【PHP】(自社開発)国内最大級のショッピ…
国内最大級のショッピング・オークション相場検索サイトの機能開発をご担当いただきます。
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア(正社員) |
| PHP・Python・Ruby・Perl・FuelP… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
電子決済アプリケーションの既存コードの解析、改修に対し設計~実装、並びに必要に応じてリファクタリング…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / VBA / 週3日〜】VB…
図形の描画をExcel上でVBで行います。 1. 水平の黒いラインの描画 2. 黒いラインの上の…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿南新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| Java・VB.NET・VBA | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
自社タイトルであるカジュアルゲーム(パズル)の 開発・リファクタリング・運用をお任せします。 ・ゲ…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
自社タイトルであるカジュアルゲーム(パズル)の 開発・リファクタリング・運用をお任せします。 …
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
お客様のご契約されている保険の内容や、将来に関しての不安やお悩みをヒアリングし、お客様に合った最適な…
週3日・4日・5日
460,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
クラウドソーシングサービスの各種機能開発、および運用・保守をお任せいたします。 機能改善やUI…
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Nod… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社サービスを開発・運営しています。 すでに多数企業様にて導入いただいており、より高性能なサービス…
週3日・4日・5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 神奈川関内駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
某金融系のシステム開発において、インフラ設計・構築ができる基盤系エンジニア様にご協力お願いいたします…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
スタートアップの立ち上げフェイズの会社で、自社サービスのバックエンド開発をメインに行っていただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
自社開発サービスを軸に、周辺サービスの立ち上げ、それに伴う中核APIサービスのリファクタリング、既存…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【Java / 週5日】通信キャリアBto…
通信キャリアの一般コンシューマ向けWebサービスの要件定義業務です。 企画部門との要件調整、開発部…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
メール誤送信防止システムを自社で開発しております。 今回は既存のメール誤送信防止システムの追加…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京テレコムセンター駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週3日…
様々なお客様のWEBシステム開発案件にて、企画・提案・開発・サポートまで行っていただきます。 Ja…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
当社クライアント向けのテーブルオーダーに関する新規サービスの開発プロジェクト、または旅行やコスメ系サ…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
自社プロダクトの開発エンジニアを募集しています。 具体的には、 クラウド基盤の開発、アプリケ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Wordpressでのウェブサイト更新、改修を行うサイト管理者、HTML、CSS、PHP等Wordp…
週3日・4日
130,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
当社クライアント向けの業務システム開発や、テーブルオーダーに関する新規サービスの開発プロジェクト、ま…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
アパレルのプラットフォームを展開しているクライアントにてプロダクトのデザイン業務を行っていただきます…
週3日・4日
260,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
弊社が運営する医療メディアをスケールさせるために、既存サービスのPDCA、メンテナンス、新サービス開…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Sass | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
社内業務フロー改善/生産性UP/IPO基準の体制構築を目的とした、自社基幹システムの開発運用をお任せ…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Symfony | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
マーケティング技術に基づくホームページ構築やWebシステム開発などの受託事業に取り組んでおります。 …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新たに立ち上がったWEBチームで自社サイトやスマホアプリのデザインを行っていただきます。 既にある…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
業務システム設計 ・画面デザインを含む業務システムの基本設計~詳細設計を行っていただきます。 ※…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・Sprin… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当社が運営する不動産Techメディアにおいて、フロントエンドの開発を担当していただきます。 お…
週4日・5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにて、プロモーションサイト改修、…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにてデザイン業務に携わっていただ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
今回は自社サービスの新規会員獲得に向け、WEBデザイナーの方を募集いたします。 ①上記サービス…
週4日
330,000円以上/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
・新クレジット追加機能要件検討 ・「スマホアプリ/スマホサーバ」と「決済システム/会員管理システム…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・WebAPI | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
フリーランスプラットフォームのシステム設計・開発・運用の中で、新規開発の運用を依頼いたします。 …
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・弊社の3年後までを見据えた理想のアーキテクチャ設計、技術選定 ・技術トレンドのキャッチアップと検…
週4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Ruby・CakePHP・RubyonRai… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
今回は社内で保守運用を行っている、wordpressサイトのフロントエンドの保守・運用に携わっていた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
AIを使い誰でも簡単に動画を作ることができる自動生成ツールの開発をしてくれる仲間を募集しています。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・TypeSc… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
LINE APIを活用した弊社の自社サービスの開発を行っていただきます。 AWS上に構築されサ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Go・Linux・docker・AWS・GCP・Re… | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
旅行系ToC新規サービスの開発案件になります。 今回は、iOSスマートフォンアプリの開発の設計と実…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
自社音声・映像・メッセージングによるリアルタイムコミュニケーション関連プロダクト・サービスの開発と、…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ob-C・C# | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
会計パッケージの保守業務です。お客様やベンダーとやり取りをしながら作業を進めていただきます。 ・…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
定番
【リモート相談可 / 社内SE / 週5日…
インフラの保守、運用および改善業務 ・サーバー監視 ・ネットワークトラブル対応 ・サーバ…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂見附 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Android / 週3日…
スマホアプリの0→1立ち上げを担当いただきます。 現在社内にはスマホアプリの知見が無く、要件定…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【PHP / 週5日】「超高齢社会」×「イ…
プラットフォームの運営を中軸事業として、インターネットマーケティング支援やビジネス情報誌など、 特…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・独自FW | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービス広告効果分析MAプラットフォームの開発をご担当いただきます。 大きなリニューアルも検討…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社サービス広告効果分析MAプラットフォームのデータエンジニアを募集しています。 今後さらに事業拡…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Rails / 週3…
弊社内の社内インフラの運用管理や環境構築を主に担当いただきたいと思います。 社内の他メンバーか…
週3日・4日
330,000〜640,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
新規サービスの開発業務全般に携わっていただきます。 また自社サービスのため、直接ユーザーの声を聞い…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
自社にて、まるで猫と一緒に生活しているかのような疑似体験ができるアプリの開発を行います。 流行…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
自社にて、まるで猫と一緒に生活しているかのような疑似体験ができるアプリの開発を行います。 流行…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rubyonrails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
詳細設計以降のフェイズを担当していただきます。 PHPでのサーバーサイド開発業務で、既存のサービス…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
訪問介護業務をサポートするシステムを自社開発・販売しており、今回はそのシステムの機能追加開発や改修な…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| PHP・Smarty | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
不動産関連の自社WEBサービス保守開発を行っていただきます。 サーバーサイド開発がメインとなる予定…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Salesforce…
全国の歯科医院で導入されている電子カルテシステムをはじめ、医療関連機器・ITシステムを自社開発・自社…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ワ…
今回は自社サービスの開発に従事していただくサーバーサイドエンジニアを募集致します。 今後の市場拡大…
週3日・4日・5日
440,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
チャットボットプラットフォームサービスの稼働に必要なバックエンドサービスの構築や実装を個社カスタマイ…
週3日・4日・5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・PHP・Node.js・Pup… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
自社サービスのコンサルプロジェクト管理ツールの開発 ローンチ予定のコンサルティング業界向け…
週3日・4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
今回は、提供しているWebサービスのサーバーサイド開発を中心に対応していただきます。 既存サー…
週5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
提供しているWebサービスにて自然言語で記述されるケアプランや画像を含む介護施設の情報など、介護に関…
週3日・4日・5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・Flask | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとして既に…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL | |
定番
【2D / 週5日】新規スマートフォンゲー…
新規スマートフォンゲームのイラスト制作業務を担当していただきます。 ・キャラクターのコンセプト…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・SAI・… | |
マーケター
当社ToCブランド品販売サービスのWEBマーケティング Google広告、Yahoo広告、LINE…
週2日・3日
190,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ・Google、Yahoo広告のチューニングができる… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
膨大なデータベースから必要な情報を的確に探し出すための検索テクノロジーの開発業務。 フルスタックエ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
製造業向けのソフト開発のプロジェクトをレンタルしているオフィスでベンダー様と共同で行っております。 …
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS/Scala …
国内最大級のハイクラス転職サイト事業を運営しておりますビズリーチ様において、AWSを利用した新業務ツ…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin | |
定番
【フルリモ / TypeScript/Ja…
撮影したコンテンツを編集、加工、SNSに共有するためのWebアプリケーションです。 既存のWebア…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】自…
日本企業の99.7%は中小企業だと言われていますが、中小企業にデジタルマーケティングは浸透していませ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Perl / 週3日…
C向け自社アプリのサーバーサイドをPerlを用いて開発していただきます。 機能追加などの保守・運用…
週3日・4日・5日
460,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Perl・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
PHP、ブロックチェーン、アプリ開発を担当して頂きます。 詳細は、面接時にお伝えします。 基本的…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿早稲田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
エンターテイメント向け業務支援システムの機能追加開発。ポジションとしては、PMとメンバーの間に立ち、…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
受託開発企業としてIoTサービスに関するエンドデバイスの開発・生産からシステム開発までをワンストップ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
営業からの要望要件をとりまとめ、カスタマイズ開発、自身での試験実装や進捗管理を担います。実現性考査や…
週5日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Puppete… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
BtoB向けのSaas型マーケティングツールを自社開発しております。 今回はマーケティングツー…
週3日・4日・5日
660,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
海外不動産検索ポータルサイトフロントエンドとサーバーサイド開発業務をご対応いただきます。 メン…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
アパレル企業のEC支援がメイン事業です。 右肩上がりのECのマーケットのなかで、柔軟にご対応するこ…
週4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
漫画家の方のためのコミュニティプラットフォームにもなっており、共同制作ノウハウの共有や漫画の投稿が気…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
VRに関するプロジェクトを担当していただきます。 キャラクターのセットアップ、およびキャラクターや…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・DB&AWS(サーバーやネットワーク)運用(CAC社員1名) ・ N/W、サーバー管理保守全般(…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Unity / 週5日】VRの開発エンジ…
リアルタイムVRを使ったプラットフォーム創生というエンターテイメントの事業を行っています。 VR …
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーエンジニア |
| Ruby・Go・-・Unity・Angular | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
自社サービスのニュースサイトアプリの開発に携わっていただきます。 今後SwiftやKotlinへの…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅/西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Web、スマホ向けネイティブアプリケーションを中心にお客様のご要望に合わせて開発を行っていただきます…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【リモート相談可 / .NET / 週5日…
自社CMSパッケージのシステム開発・カスタマイズ ・対応業務詳細について ⇒設計書を元にCMS内…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C#・VB.NET・.NET | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
新規事業推進部において、広告関連サービスのLP・バナー作成デザイン・コーディングをご担当いただきます…
週4日・5日
460,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
自社事業の教育サービスのWEBサイトのデザインからコーディングまで、お任せできる方を募集しております…
週4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
自社プロダクト(HR Tech領域の業務システム)におけるシステム基盤構築・設計・開発・改修 …
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Node.js / 週3日〜】証券会社投…
・ 証券会社投信システム(約定計算)の開発 ・ 作業範囲: 投信システム(約定計算)の製造・…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
メンタルヘルスTechサービス・リアルサービスの両軸を手掛けている、メンタルヘルスケアに特化した会社…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JQuery / 週…
自社サービスのメール配信システムのWEBデザイン業務をお任せいたします。 一般のお客様(購読者)向…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ブロックチェーン技術を活用したWebアプリケーション開発サービスを展開しております。 いくつかある…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・IONIC・… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
当社の社内情報システム関連業務、ファシリティマネジメント業務全般に携わっていただきます。 ・社…
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
アパレル系ECサイトの運営や住宅系CRMシステムの運営など、様々なプロジェクトの業務をメンバーとして…
週5日
410,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Spring・JQu… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
IRコミュニケーションをはじめとした様々なPRを行っております。 ファッション系企業様のコーポレー…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋茗荷谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
お客様のご契約されている保険の内容や、将来に関しての不安やお悩みをヒアリングし、お客様に合った最適な…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
国内リサーチ会社シェアNo.1のサーベイツールの開発業務を行っていただきます。 ・開発ニーズ検…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
レジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供している企業です。 今回の案件は、100…
週4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
レジスターやPOSシステムといった機械やソフトウェアを提供しています。 100%自社サービスの…
週4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社サービスのインフラチームの一員として上流設計~構築、運用業務に携わっていただきます。 積極…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【PM / 週3日〜】自社開発のメタバース…
メタバース領域のエンターテイメントプロジェクト開発をお任せします。 新卒4名エンジニアと共に、自由…
週4日・5日
250,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Swift・Kotlin・C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】某…
某メーカーの基盤構築に伴う、業務システム開発案件に携わっていただきます。 基本設計以降、若しくは詳…
週5日
580,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
自社サービスのインフラチームの一員として上流設計~構築、運用業務に携わっていただきます。 積極…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスのQAチームの一員として基幹システムの品質評価から各種連携先のシステムを想定したテストケ…
週5日
330,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / サーバーサイド / …
自社サービスのQAチームの一員として基幹システムの基幹システムの品質評価から各種連携先のシステムを想…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】Bt…
自社サービスのゴルフ場の予約システム、顧客管理システム、精算システムなどの開発。 積極的に正社員登…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
ユーザーからの要求定義を受け要求分析、要件定義、設計、開発、将来的にはメンバー管理までプロジェクト全…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / PL / 週5日】美…
多店舗展開している美容チェーン店向け役務管理(チケット管理)システムを構築する必要があり、全体的な設…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
コーポレートサイトのデザイン制作を行えるWEBデザイナー募集 ・WEBサイトの受託制作における…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
下記2つの開発プロジェクトにおきましてチームを組んでプロジェクト推進を行える方を募集しております。 …
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
サイト制作・更新者は、多数所属するライターさんからの原稿や、取引先のWebサイトの更新情報を編集し、…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外シンガポール |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
社内の運用担当者からの要望を受けたデザイン・機能要件を備えた、フロントエンドデザイン、コーディングを…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Bo… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
下記2つの開発プロジェクトにおきましてWEB予約システムの開発を行える方を募集しております。 …
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
海外の日本ファン向けに、日本国内のオークションサイト、ショッピングサイトでの購買代行サービスを手掛け…
週5日
250,000〜560,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
医療領域での自社サービス開発をしています。 自社サービスのスマホアプリ開発経験をお持ちの方を募集し…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
今回は開発中である次世代の物流情報プラットフォーム、その開発にフロントエンドエンジニアとして携わって…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
企業間物流に関わるあらゆる事業者がデジタルに繋がる物流情報プラットフォームを構築し、持続可能な社会を…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・CircleCI・Confluence・JIR… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
ビジネスチャットやテレビ会議等を行える無料グループウェアサービスを提供しております。 今回は自社サ…
週5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
世界有数の仮想通貨取引所を運営している親会社の日本法人である弊社にて、スマホアプリ開発を行っていただ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
世界有数の仮想通貨取引所を運営している親会社の日本法人である弊社にて開発を行っていただきます。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週5日】…
世界有数の仮想通貨取引所を運営している親会社の日本法人である弊社にて、スタートアップの成長を加速させ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
世界有数の仮想通貨取引所を運営している親会社の日本法人である弊社にて、インフラ業務(AWS)を行って…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
世界有数の仮想通貨取引所を運営している親会社の日本法人である弊社にて、ブロックチェーンエンジニア業務…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Java・Go・‐・・- | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
新規広告バイイングプラットフォームのインフォメーションアーキテクト/UX/UIデザインを推進するポジ…
週3日・4日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
・日々業務フローの再作成やオペレーションの改善 ・ネットワーク環境改善のための要件定義 ・不正侵…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社サービスのUI/UXを改善していただくデザイナー様を募集いたします。 ◯システム開発、企画…
週3日・4日・5日
330,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
家事代行をクラウドソーシングの形で提供している企業になります。 ~家事代行サービスのシステム開…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Typescript・React(Redu… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
多様なクライアントの要件をヒアリングし、デザインに落とし込んでいただきます。 チームとして役割分担…
週4日・5日
280,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
B2C×エンタメ領域の事業を展開している当社にて、現行・新規スマホアプリ(iOS/Android)の…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
Angular8とNode.jsを用いたGoogleカレンダーと連携したスケジュール調整や、某SNS…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
ベンチャー企業向けにコミュニティを運営している会社です。シェアオフィスを提供しているので様々な起業家…
週3日・4日
180,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社サービスのRubyエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申し込みをいただいている中で…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
既存求人サイトの改修や保守・運用を担っていただける方を募集いたします。 ・求人サイトのスクレイピン…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
設立当初からの高い技術力を持った開発集団ですが、更なる成長を遂げる為、新しい知識、情熱、考え方を持っ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop(テクスチャ)Flash(アニメー… | |
定番
【リモート相談可 / 3DCG / 週4日…
設立当初からの高い技術力を持った開発集団ですが、更なる成長を遂げる為、新しい知識、情熱、考え方を持っ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【Rubyエンジニア】社内システム保守/O…
【業務内容】 現在、社内システムで利用している『CentOS7』が、2024年6月末にEOSLを迎…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅/初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・React.js・MySQL・MongoD… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
建築、エステ、フィットネス、健康食品、教育、などのあらゆる業界のお客様のサイトの制作業務を、Webコ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
建築、エステ、フィットネス、健康食品、教育、などのあらゆる業界のお客様のサイトの制作業務を、Webコ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
事業内容としては上記取引先のパンフレットとHPの作成です。 ・デザイン案をもとにHTML、CS…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
店舗インフラ全般的整備に伴い、下記の業務をお願いいたします。 ・WiFi AP(AccessPoi…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】人…
自社サービス開発・運用と多角的に事業展開をしている企業にてでサーバーサイドエンジニアとして業務を行な…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・JIRA | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
自社サービス開発・運用と多角的に事業展開をしている企業にてでサーバーサイドエンジニアとして業務を行な…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・JIRA | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
日本のものづくりの技術と世界の技術をマッチングさせる新規マッチングプラットフォームサービスの開発に従…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Nux… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
本ポジションでは、ネットショップ作成サービスのフロントエンド開発を担っていただく方を募集します。 …
週4日・5日
580,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
2つの新規アプリのデザインに携わっていただきます。 旅行者向けクチコミアプリと飲食店クチコミアプリ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
WEBシステムの導線/使いやすさを検討いただきながら 下記デザインを行っていただきます。 ・画面…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Reactnative /…
飲食業界で業界トップ評価を受ける、人材育成・採用の仕組みをお持ちの会社様とのコラボレーションです。 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| React・Native | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
メインで監視・運用保守いただいているベンダーと連携しながら安定したシステム運用を実現していただきます…
週5日
280,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週4…
1)社内システムおよびネットワークの維持/管理 2)拠点追加に伴うネットワーク工事 3)ISMS…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Angular / …
各種機能のフロントエンド開発業務になります。 データをどのように可視化したらいいのかということ…
週4日・5日
460,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【インフラ / 週5日】広告代理業Mac端…
ユーザー部門にてwindows端末とMac端末の2台を利用しているユーザーについて、Mac端末1台に…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
本ポジションではバックエンドリードエンジニアとして、既存のRailsアプリケーションコードのリファク…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
本ポジションではバックエンドリードエンジニアとして、既存のRailsアプリケーションコードのリファク…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / React.js / 週5…
今回の募集では、経営陣と共にプロダクトのの未来について考え、開発をリードしていただき、使いやすいサー…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】企業…
今回の募集では、経営陣と共にプロダクトの未来について考え、開発をリードしていただき、使いやすいサービ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
今回は、デジタル印刷プラットフォームのコアメンバーとして開発に携わっていただきます。 正式ローンチ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【Python / 週5日】 AI・推進プ…
日本だけでなくアジア、ヨーロッパ、アメリカにビジネス展開しています。 今回は、中国案件プロジェクト…
週5日
610,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社の採用WEBサイトを作成するにあたりWEBデザイナーを募集しています。 ・自社採用サイトの…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原稲荷町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
日本だけでなくアジア、ヨーロッパ、アメリカにビジネス展開しています。 面談時に詳細をお伝えさせてい…
週5日
610,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/Swi…
新車カーリースサービスのネイティブアプリ開発の立ち上げチームに参画いただきます。 スマートフォンア…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 東京23区以外つくば駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・React・Native | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週4日〜…
Salesforceで基地局事業に関する業務統合マネジメントシステムを開発しています。 その際に工…
週5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| VBA | |
定番
【Linux / 週5日】情報システム部業…
1)社内システムおよびネットワークの維持/管理 2)拠点追加に伴うネットワーク工事 3)ISMS…
週5日
480,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
「品質管理×IT」という領域で現場をペーパレスにすることで、作業品質を向上させることを目的としたサー…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】特…
人追尾ソリューションのPoC開発です。 顧客サービスを導入している特定施設向けに入所者個々人の施設…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手企業のブランディングから先進的サービスの共同開発まで、クライアントニーズからの企画・提案・運用ま…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
ReactNativeとネイティブ(Swift/Kotlin)をブリッジさせてアプリを開発しており、…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
最先端技術を駆使した、自社サービス開発を積極的に行っております。 自社で開発しているパッケージソフ…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Smarty | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Java /…
金融(クレジットカード)系企業が運営する、各種webシステムの維持管理、運用業務をお任せいたします。…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿銀座一丁目 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
オンライン、オフライン広告の素材をデザインする業務です。アプリゲームから、ツール系アプリや、ファッシ…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】見…
見積システム再構築に関する下記業務をお願いいたします。 ・要件定義 ・基本設計 ・現行の基幹シ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【PM】基幹系システム再構築も含めた、全社…
■募集目的 全社の基幹系システム再構築も含めた、全社DXの推進プロジェクト ※詳細は未定ですが、…
週5日
1,100,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 豊洲新宿駅/初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【サーバーサイドエンジニア】飲食店向け予約…
【業務内容】 飲食店向け予約管理システムと付随するCRMシステムにおいてのサーバーサイドの開発保守…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・PL・SQL・Oracle・Struts・… | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
受託開発案件でのPHPエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお話しさ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Lararvel | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
自社運営の旅行メディアのAndroidアプリ開発をご担当いただきます。 ・機能追加 ・リニューア…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidアプリエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
自社運営の旅行メディアのIOSアプリ開発をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・Andr…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社運営の旅行メディアのサーバーサイド開発をご担当いただきます。 ・Railsを使ったウェブア…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
自社運営の旅行メディアのデータ分析業務をご担当いただきます。 ・ユーザ行動の分析(主にBigQ…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL・‐・- | |
定番
【iOS/Android / 週4日〜】自…
自社運営の旅行メディアのUI/UXデザイン業務をご担当いただきます。 Web、iOSアプリ・A…
週4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
自社新製品である映像編集アプリケーションのUI/UXデザインを担当いただくデザイナーを募集いたします…
週4日・5日
410,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅/青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
こちらはホテルや医療機関向けに自動精算機や受付、フロントなどの管理システムを提供している会社です。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
今回は自社のAIプロダクト・サービスなどのUX設計UIデザイナーをの方を募集しております。 ・…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大門駅 |
|---|---|
| 役割 | UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
オフラインツール(ポスター、ロゴ、サイン、チラシ、POPツール、ノボリ、ノベルティなど)主に紙媒体の…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社カスタムオーダーファッションサービスのフロントエンド開発をリードいただける方を募集します。 …
週3日・4日・5日
2.4〜4.9万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / React/Redu…
国内最大級のスタートアップコミュニティを運営しています。 クラウド型イノベーションプラットホー…
週3日・4日・5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社業…
ホテルや医療機関向けに自動精算機や受付、フロントなどの管理システムを提供している会社です。 要…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
アパレルショップの販売員向けサービスを運営しています。 本自社サービスの管理画面のUI改善や、フロ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】マ…
・ドメイン管理、SSL証明書管理 ・AWSを用いたインフラ・ネットワーク設計、構築、運用 ・コン…
週3日・4日・5日
550,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / GCP / 週4日〜】Sa…
エンド企業内で、Saas開発インフラ支援を行っていただきます。 -アプリケーションインフラの設計・…
週4日・5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】地方創生…
・クライアントの要求ヒアリングと要件定義 ・サービスの企画提案 ・クライアントへの報告等窓口 …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| AWS・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】自…
iOSを中心に技術面でチームをリードしていただき、技術課題のマネジメントや開発フローの整備など、様々…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
美容医療の口コミ・予約サービスアプリの開発です。 プロダクト全体に関わっていただきながら、技術を軸…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
某金融系DWHシステム更改対応。オンプレ→AWSへの移行 ・現在詳細設計、製造、単体テスト工程中 …
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・SQL・DataStage(… | |
定番
【Java / 週4日〜】新クレジット+ス…
・新クレジット追加機能要件検討 ・「スマホアプリ/スマホサーバ」と「決済システム/会員管理システム…
週4日・5日
330,000〜780,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・WebAPI | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・要件に応じたDB設計〜機能の実装 ・開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソース管理 ・仕…
週5日
580,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
・Webフレームワークを使用したフロントエンド開発(主にVue, Nuxt.js, React, N…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
当社のSI部門にて、Androidエンジニアを募集いたします。 ・スマートフォンアプリの仕様、…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語アプリサービスを運用しております。 今回は、自社英…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
アプリサービスの開発をご協力いただける、サーバーサイドのエンジニアを募集しております。 社内に…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
スキマ時間に効率的に英単語を覚えられる英単語アプリサービスを運用しております。 英単語学習アプ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Sketch | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
エピゲノムを中心とし、ゲノムやメタゲノムまで、次世代シーケンサーを用いた大規模データの解析を行います…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP/Ruby /…
ファッションのカスタムオーダーサービスを開発しています。 PHPを用いてサーバーサイド開発ができる…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・CakePHP・Laravel・R… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
弊社にて社内SE業務をご担当いただきます。 ・社員用PCのセットアップ ・社内グループウェア…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Photshop /…
アバター機能のモデリングやモーション作成を行っていただきます。 ・衣装等のアバターモデリング ・…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
現在企画中の、ビックデータと機械学習を活用したサービス(BtoB、社内向け)の開発を担当いただきます…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Ruby・Rea… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
薬局ダッシュボードを作成するにあたり、データを可視化させるための画面開発する責務を担って頂きます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・d3.js | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】企…
自社アプリに関わるUI業務全般 →新機能のUI作成から既存UIの改善まで、幅広くおまかせします。 …
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Photoshop・Iillustrator | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
データ解析、データマート設計/開発、レポーティングメイン。 レコメンドアルゴリズム開発業務をお任せ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・R | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
主にSREの役割を担当して頂くポジションです。 運用を見据えた自動化などの設計・開発タスクをPHP…
週4日・5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・CodeIgniter・AWS・GCP | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
春頃リリース予定の小中学生向けICT教材アプリのバックエンド開発をお任せします。 基本はバックエン…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 東京23区以外烏丸駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Swift・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / C#/Java / …
某大手CD販売店や、大手化粧品メーカー、大手鉄道グループなどの案件を直で企画から運用までワンストップ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
iOS向けニュース系キュレーションアプリのサーバーサイド開発 - web上からキュレーションし…
週3日・4日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
「自社開発中」のiPhone向けニュース系アプリの開発(swiftを使用します) メインの開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
グルメ系ECサイトのサービスを確固たるものにし、食のプラットフォームを構築いただける方を募集します。…
週3日・4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿落合駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・EC… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】国…
ハードウェアの開発も行なっているため、IoT関連の理解が得られます。 ・仕様書および設計書を元…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
・法人向けのタクシー配車サービス(Web)の機能拡張や改修に伴う設計・実装・テスト ・法人向けのタ…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
今回は自社開発中のデータ統合プラットフォームのサーバーサイドエンジニアを募集します。 - k8…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Scala・Go・React.js・Next.js・… | |
定番
【リモート相談可 / SRE / 週4日〜…
- k8s on GCPを使った自社DaaSサービスのSRE業務、API開発業務 - AWS(EC…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
コーポレートアイデンティティの設計〜実行までを担当していただけるデザイナーを募集しております。 …
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【PM / 週5日】バーチャルライブ・イベ…
バーチャルライブ・イベント制作におけるプロジェクトマネジャーを募集しております。 チームの生産…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 【具体的な仕事内容(一例)】 ・収支計画・KPI設… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
グループ会社であるシステム会社で、弊社の社内システムを開発をしています。 弊社がIT企業でないこと…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・‐ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
※中国語と日本語が分かる方※ 中国にあるシステム会社の窓口/社内運状況の管理と、対応/システム…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Sw… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
車両ナンバー認証カメラで車をデジタル管理することを特徴とする自社駐車場管理システムを自社で開発し、運…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
英語学習アプリのコンテンツ管理システムの実装を担当いただきます。 ・管理システムの側部分の利便…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サイトのシステム側の開発や新規ビジネスのシステム開発(モック含めて)に携わっていただきます。 …
週3日・4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・Webアプリケーション開発(新規/流用/改造) ・要件定義から導入までが業務範囲 ・クライアン…
週5日
610,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅/汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| CSS・JavaScript・PHP・C#・Cake | |
定番
【Webディレクター】クラウド型健康管理サ…
クラウド型健康管理サービスのマーケティング部にて、WEB/サイト改善のディレクションを主に行います。…
週1日・2日・3日
290,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Webマーケティング |
定番
【データサイエンティスト】顧客・市場セグメ…
■対応内容 ・分析の内容は、新たなブランドポートフォリオを作成するための下記3つです。 ・外部の…
週4日・5日
1,050,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【Ruby on Rails, Golan…
創業期のFintechスタートアップで、著名エンジェルからの資金調達も済ませてプロダクト開発を進めて…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・Go・Ruby・on・Rai… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
(未ローンチにつき、詳細はお伝えできませんが、) 機械部品や消耗品などを扱うメーカー、商社向けの、…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Node.js・… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回は、ヘルスケアプラットフォームの開発に携わっていただく、IoT/Deep Learingの開発・…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋岩本町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・S3・Redis・PyCharm・Nu… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
ヘルスケア・美容事業やライフスタイル事業、プラットフォーム事業を展開しています。 広告用LP・広告…
週3日・4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
・ローンチ直後のサービスのバグ修正 └前任者の引継ぎ用のドキュメントをもとに、バグを修正していた…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・React | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
WebアプリケーションをデザインをするUIデザイナーを募集します。 具体的には ・UIのビジュ…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・会計システム開発 ・PHPでのサービス開発 ・チームマネジメント(ディレクション) エンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Cake・Rails・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
通話録音システムやCTI システムを幅広い業界に展開する当社にて、顧客からの問い合わせ 対応、ログ解…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
通話録音システムや自社 製品の開発エンジニアとして、製品のアップグレー ド、調査・導入、R&D、既存…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
弊社情報システム部門にて経理システム(OBIC)の業務支援業務をご担当いただきます。 具体的にはO…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / FileMaker …
エンド様より受託しているシステム開発をFileMakerを利用してご対応いただける方を募集しておりま…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日〜】…
リモートワークを推進するタスクマネジメントツールのバックエンド開発をリードいただけるGO言語エンジニ…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】社…
社内ポータルのシステム管理者として運用保守、またシステム開発を行っていただきます。 対象システムは…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
プログラミングスキルを診断、見える化し、社内評価やエンジニアの就活・転職に役立つサービスを提供してい…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 品川勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Jquery | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
社内向け管理ツールを自社開発しています。WEBアプリ・スマホアプリ版のデザインに携わっていただきます…
週3日・4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
現在、自社で仮想通貨のポイントキャッシュバックアプリを開発しており、そのUI/UXデザインを担ってい…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週3…
・サーバの構築・管理・運用(オンプレ・クラウドAWS) ・ネットワークの構築・管理・運用 ・IT…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿若林駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
4年前にリリースした主要事業であるデータマーケティングプラットフォームのバージョンアップに伴って、シ…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
プリペイドカードシステム開発プロジェクト案件です。 ・要件定義、基本設計、詳細設計、製造、試験、商…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【Java / 週3日〜】某電子マネー後方…
・某電子マネー後方系システムの保守 ・上記①は常時作業があるわけではないので、作業が無い時は、…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・JavaScript・Java・Angul… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】自社製品…
光計測器(分光器、積分球など)を動作させるためのソフトウェアを開発頂きます。 お客様ごとに仕様が異…
週5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| Java・C・C++・C#・java・C#・C+・C… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】D…
・毎月機能のアップデート ・業界内関連サービスとのAPI連携など最新のマーケット状況・顧客ニーズを…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
◇コーディング作業について ・PC、スマホTOPページの軽量化 ・TOPページのスライドを管理し…
週3日・4日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / React/Native …
企業の社内で使う業務系のアプリから、たくさんのエンドユーザーの目に触れるiPhoneアプリまで、対応…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
企業の社内で使う業務系のアプリから、たくさんのエンドユーザーの目に触れるiPhoneアプリまで、対応…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・FuelPHPもしくは類するphpのMV… | |
定番
【PM/Java / 週5日】システム管理…
システム運用タスク(仕様問い合わせ、データ抽出依頼、データパッチ依頼、トラブル解析など)のディスパッ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿藤沢駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
MRやARなどのゲーム開発案件です。 MRグラスとiOSで動く複数人数参加型のゲームアプリケーショ…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新規ポータルサイトの制作を行っております。 現在プロジェクトチームを発足し企画構成を固めている段階…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
天気予報専門メディアのiOS/Androidアプリ開発のエンジニアを募集しております。 天気予…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿江戸川橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
主にベンダー会社と協力いただき、サイトのフロント画面(デザイン、コーディング)やDTPの制作業務に携…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
某ITメガベンチャーにて自社データインフラグループのデータ移行作業を担当頂きます。 1. AWSの…
週5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
急成長ECプラットフォームのO2Oモバイルアプリ新規開発【Swift/Kotlin】 多くの事業者…
週5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア・Androidエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Python/C++ / …
このたび、弊社の画像解析アプリを用いて、機器メーカーとPoC(実証)をやることになりました。 その…
週3日・4日・5日
670,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
下記業務にご参画いただけるエンジニアを募集いたします。 ・現在、使用している基幹システムのKint…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飾磨駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
京都のお寺にいるような本格的な禅体験ができるプログラムをiOSアプリで提供しています。 より多く…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】エ…
エンタメ系事業を展開する部署で、音楽、動画配信を取扱うCMSのマイグレーションを担当していただきます…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・spring・boo… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・レガシーなLAMP構成の現在のECサイトの新規開発に携わっていただきます。 ・すでに十数年運営し…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
Fintechスタートアップ企業にて、React + Reduxを使用した当社のSSRアプリケーショ…
週4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / React/Ruby…
・少人数での開発のため部分的な機能をお任せというよりも、インフラからフロントまで幅広くお任せいたしま…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・React・rail… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
AI-OCR基盤の開発に伴う新規WEBシステムのUIデザインを上流(要件定義)から下流まで行っていた…
週3日・4日・5日
410,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
・少人数での開発のため部分的な機能をお任せというよりも、インフラからフロントまで幅広くお任せいたしま…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日〜…
パートナー企業(クライアント)が投資に関する操作をされる際の社内システムのデザインを行っていただける…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| SQL・Illustrator・Photoshop・… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】英語…
新規開発と開発運用中システムの保守対応(不具合対応含む)を担当いただきます。 ・英語学習アプリの新…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails(6系) | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
大手のIP案件でスマホのRPGゲームの開発を行っていただきます。 ・クライアントの新規実装 …
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】分析ア…
本案件のクライアント様は統計学とコンサルティングのを活かしたニーズに特化した分析をするためのアプリケ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社採用サイト、一般社団法人のサービスサイト担当のエンジニアを募集しております。 メイン業務は、 …
週3日・4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社採用サイト、一般社団法人のサービスサイト担当のエンジニアを募集しております。 メイン業務は、 …
週3日・4日・5日
250,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】通…
エッジクラウドサービスのプラットフォーム構築におけるRFI、RFPに添った提案書を作成する作業を主に…
週5日
330,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
自社プロダクトの開発PjMとして、ユーザーや顧客企業と向き合いながらプロダクト開発をマネジメントして…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・RubyonRails・Vue3・Vite | |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】大…
大手卸売業会計システムの周辺システムを再構築への機能追加要望の対応を行って頂きます。上位会社の責任者…
週4日・5日
330,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Java・Oracle・AWS | |
定番
【Java / 週4日〜】高速道路関連業務…
既存高速道路関連システムの新システムへの移行追加開発を行っており、9月からの詳細設計・製造フェーズへ…
週4日・5日
330,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Java・JSP・intra-mart・P… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
某金融系DWHシステム更改対応。オンプレ→AWSへの移行 ・現在詳細設計、製造、単体テスト工程中 …
週4日・5日
330,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Java・SQL・DataStage(… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社サー…
カスタマーサクセスの実現にコミットし、弊社の収益維持・拡大を担うプロフィットセンターとして、 高い顧…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / RPA / 週5日】…
UiPathを用いたRPA開発・保守 ※状況やスキル等に合わせて、ゆくゆくは要件ヒアリング・ソリュ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹橋 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
Webサイトのデザインやコーディングをお任せします。 Webサイト制作では不動産関連サイトやコ…
週3日・4日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
自社で日本初のエネルギー業界専門ニュースアプリを展開しております。 今回はそのWebサイト版を新規…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
クライアントから依頼をいただいている、金融機関向け営業支援系システム保守案件をご担当いただきます。 …
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東村山駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
日本最大級のクラウドファンディングサービスを運用しております。 本ポジションでは、Webフロン…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
現在、標準的なRubyonRailsアプリケーションとしてAWS 上に構築されていますが、今後の素早…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】管理シ…
既存社内管理から、社内管理システムへの移行、管理システムの新規開発を行っていただきます。 今回はリ…
週5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】管理シ…
既存社内管理から、社内管理システムへの移行、管理システムの新規開発を行っていただきます。 今回はP…
週5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・PostgreSQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS …
今回は自社製品のPR(広告)に関するクリエイティブの制作を行っていただくデザイナーを募集しております…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Photoshop/…
当社が運営する不動産Techメディアにおいて、WEBデザイン業務を担当していただきます。 具体的に…
週3日・4日・5日
240,000〜440,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| Illustrator・Photoshop | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
「婚活」「妊娠・出産・育児」サービス領域で、エンジニアが身近にいる環境で、協力しながらアプリのUIデ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・Adob… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
自社で開発運営しているWEBブラウザゲーム(戦闘機や戦艦等が登場するミリタリー系)のデザイン業務を行…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| Illustrator | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
自社アプリの開発に携わっていただきます。 ユーザー数の増加、新規サービス拡充と並行して、仮説を立て…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アーキテクチャ設計・サーバーサイド・フロントエンド・インフラストラクチャなど、今後もテンポよくサービ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
自社IoTプロダクトのスマホアプリのデザイナーを募集しています。 iOS、Andoridアプリのデ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
自社開発のシステムを用いてオンライン営業のサービスを提供している企業です。 この度は現環境版の新機…
週5日
500,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
仮想通貨のシステム開発・システム設計・システム構築 システム改善・システム運用上の、管理・プロセス…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・‐ | |
定番
【AWS / 週4日〜】化粧品販売の製造開…
・既存のECの商品/販売関連機能をWordpressを利用した新規EC機能にリプレースするプロジェク…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / イラストレーター /…
ネイティブプラットフォームでのソーシャルゲームの立ち上げにアニメーションデザイナーとして携わっていた…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
定番
【フルリモ / React/Native …
企業の社内で使う業務系のアプリから、たくさんのエンドユーザーの目に触れるiOSアプリまで、対応してお…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
テレビ視聴者の視聴状況に関するデータ収集の研究開発プロジェクトを行っております。 このプロジェクト…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / 3DCG / 週3日…
サービスの内容としては、利用ユーザーが好きなバーチャル配信者と1:1の通話ができたり、通話内でミニゲ…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Scala / 週3…
Fintechスタートアップ企業にて、自社サービスの新機能開発をメインにご担当いただきます。 また…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Scala・PlayFW | |
定番
【フルリモ / SRE / 週5日】クラウ…
今回は社内のSREポジションを担っていただける方を募集しております。 - CAMPFIRE 関…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、D2C領域もしくはリテール領域をメインに幅広いデザイ…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
新規プロダクトチームのエンジニアとして、プロダクト開発に携わっていただきます。 - 要件定義・…
週3日・4日・5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
AWS上に次世代業務システムのインフラ設計・構築を担当して頂きます。 Oracle ERP Clo…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿またはめじろ台 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / DCC / 週3日〜…
遊技機系の映像制作などを中心に受託でいくつかのプロジェクトが走っているため、そちらのプロジェクトに配…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | エフェクトデザイナー |
定番
【システム / 週5日】送金に関する金融サ…
募集ポジションが複数ございます。 ご経験に応じて面談時に適切な案件をご紹介させていただければ幸いで…
週5日
280,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
オーダーメイドブライダルリングのブランドの、EC化プロジェクトに参画いただけるWebデザイナー兼コー…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週3…
業界随一のインストールベースを持つインテリア・コーディネートのための3D シミュレーターの次世代版を…
週3日・4日・5日
520,000〜930,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・社内情報システムの運用管理業務 ・情報システム部職員の各種業務支援 (ユーザ要求実現手…
週5日
410,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】受…
企業の社内で使う業務系のアプリから、たくさんのエンドユーザーの目に触れるiOSアプリまで、対応してお…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
インフラの保守、運用および改善業務 ・サーバー監視 ・ネットワークトラブル対応 ・サーバ…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤坂見附 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
子会社立ち上げのため、社内環境インフラ整備および運用保守全般をお任せできる方を募集します。 ・…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
現在ベータ版はリリースされておりますが、正式版の開発を進めており機能追加などに付属するフロントエンド…
週4日・5日
310,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川高輪台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
ファイナンス領域のインターネットメディア事業を行っております。 カードローンをはじめ、⾦融メディア…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / ネットワーク / 週…
クライアントの要望に沿ったスキル要件をヒアリングし幅広い技術領域から最適なソリューションサービスを提…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
クライアントの要望に沿ったスキル要件をヒアリングし幅広い技術領域から最適なソリューションサービスを提…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / salesforce…
クライアントの要望に沿ったスキル要件をヒアリングし幅広い技術領域から最適なソリューションサービスを提…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin/jav…
下記の業務に携わっていただきます。 ・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 / オンライン教育…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・-・React | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ハ…
メインのプロダクトになりますハイクラス複業プラットフォームの開発を行っていただけるエンジニアの募集を…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【Ruby / 週5日】BtoB/BtoC…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
レガシーなLAMP構成の現在のECサイトとCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生産管理を含む管理ダ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【VBA / 週5日】JavaScript…
Salesforceで基地局事業に関する業務統合マネジメントシステムを開発しています。 その際に工…
週5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / 社内SE / 週3日…
社内の端末の管理やネットワークに関するサポートを行っていただける人材を募集しております。 ・社…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
基本的に広告・デザイン・UI/UXといったところをお願いしたいのですが、同時にSEO対策を行っていく…
週3日・4日
390,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
開発体制の強化のため、今回Ruby on RailsのWebエンジニアを募集します。 自由度の…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
開発体制の強化のため、今回VR・AR開発に携わっていただくエンジニアを募集します。 自由度の高…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・-・Unity・Unreal・Engin… | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】コスメ…
アプリ内で商品を紹介する、ランディングページの作成を行っていただくデザイナーを募集しております。 …
週3日・4日
160,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Illustrator・Photoshop・各種デザ… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
お任せする仕事は、クライアント様より依頼を頂いているWebサイトの保守作業やWordPressによる…
週3日・4日・5日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【Linux】ネットワークの設計・構築に関…
受託している案件にてネットワーク関連の設計・構築を担当いただける人材を募集しております。 ①Lin…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王多摩センター駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社で運営するクラウドソーシングプラットフォームのフロントエンド画面改修や機能追加などを行っていただ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主にECサイトの画面作りをしていただきます。 現在2名のUIUXチームで、現状把握のドキュメント作…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
クライアント様オフィスに常駐し、弊社フロントエンド制作チームの一員として業務いただきます。 ・…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
不動産売却領域で複数の事業を展開しています。 具体的な業務内容としてはプロダクトの目的、目標を…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
社内システムの企画、仕様設計、テスト、導入、保守の実施をお願いします。 ・各事業部へのヒアリン…
週3日・4日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにて プロモーションサイト改修…
週3日・4日・5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / illustrator/P…
フリーランスを活用したweb制作にて、助成金コンサルタントを提携をして「助成金+LP制作」の販売をし…
週3日・4日
200,000〜390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| illustrator・Photoshop・等 | |
定番
【Python/SQL / 週4日〜】テレ…
・事業側およびクライアントの要件/要望を理解し、それらに沿って仮説出しを行い分析方針を決め、SQLお…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
既存プロダクト開発のフロント・バックエンド開発に携わっていただける方を募集いたします。 プロダクト…
週4日・5日
720,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Java・Vue.js | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
新規事業を立ち上げるチームにジョインいただき、webデザインに加えて、使い易さや顧客体験を想定し、U…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Sketch・AdobeXD・photoshop・i… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
教育系DXを推進するSaasサービスの新規立ち上げに伴い、サーバーサイド構築をリードできるエンジニア…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】e-…
ゲーム・エンターテインメントサービスのPL/エンジニアを募集します。 アジア・ヨーロッパを中心に、…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木上野毛駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・- | |
定番
【GOエンジニア募集|フルリモOK】リニュ…
■仕事内容 toC,toB向けの既存プロダクトのリニューアルや新規事業である高等教育機関向けDXサ…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | GOエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Go・‐ | |
定番
【フロントエンジニア募集|フルリモOK】社…
■仕事内容 社会人教育事業、高等教育機関向けDX事業のフロントエンド開発をお任せします。 ・…
週5日
500,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
デジタルサイネージの広告配信に携わるプラットフォーム開発での、開発メンバーを求めております。 …
週3日・4日・5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Kotlin・Go・React… | |
定番
【リモート相談可 / React/Pyth…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| ScipyNumpy・ScikitLearn・Pan… | |
定番
【フルリモ / DevOps / 週3日〜…
複数広告代理店に対して出向している広告の成果を、記録・集計・報告するシステムの開発を担当していただき…
週3日・4日・5日
570,000〜740,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日】不…
Webデザイン、コーディングがメイン業務となります。 現状だと不動産会社の物件サイトのデザイン作成…
週3日
130,000〜390,000円/月
| 場所 | 秋葉原末広町 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Notes/Shar…
・NotesからSharePointを利用したシステムへの移行。 ・客先情シス担当様のサポートとし…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【Java / 週4日〜】新クレジットシス…
・新クレジット追加機能要件検討 電子マネー決済システムへのクレジット機能追加にあたり決済後のデータ…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・WebAPI・tomcat・Apache・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】求人…
。WEBサイト制作・運用・保守 すでにデザインは決まっているので、フロントとサーバーサイド側どちら…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
・マッチングサービスのサーバーサイドの開発・運用業務を中心にお任せいたします。 └サーバーサイドの…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js/Vu…
- 人材配置最適化サービスの開発:労働人口の減少が喫緊の課題である今日の社会において、技術の力によっ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
今回はAWS上でPythonを使用していただき、サーバー/ソフトウェアの開発業務に従事していただきま…
週3日
290,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
受託しているデザイン案件を企画から実装迄行っていただけるWebデザイナーを募集しております。 …
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photsh… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
企業の生産性を可視化し、従業員の働き方を変えることで、生産性を向上させ営業利益を拡大を支援する次世代…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / DevOps / 週3日〜…
スマートフォンをメインターゲットとした、オーディオブックサービスの開発を担当していただきます。 具…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / http://admin.…
複数広告代理店に対して出向している広告の成果を、記録・集計・報告するシステムの開発を担当していただき…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
複数広告代理店に対して出向している広告の成果を、記録・集計・報告するシステムの開発を担当していただき…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
複数広告代理店に対して出向している広告の成果を、記録・集計・報告するシステムの開発を担当していただき…
週3日・4日・5日
570,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社サービスプラットフォームの開発 私達は場所や時間にとらわれることなく、パフォーマンスを最大…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
パートナー企業(クライアント)が投資に関する操作の際の社内システムの開発を行っていただけるフルスタッ…
週3日・4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【フルリモ / iOS/Android /…
リードエンジニア候補/新規自社開発プロジェクト管理ツールのモバイルエンジニアとしてアプリ開発を中心に…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄博多駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Python/C++ / …
自社開発音声認識エンジンの機械学習エンジニア(Python/C++)を募集しています。 音声認識に…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄福岡駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・C・C++・Django・Vue.js | |
定番
【フルリモ / SRE / 週3日〜】自社…
SRE(Site Reliability Engineering)として、サービスを支えるサーバ・ネ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄福岡駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】自社開…
自社開発の音声認識エンジンの開発を行っており、こちらのテストをメインで対応いただけるQAエンジニアを…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄福岡駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ECサイトのデザイン及び運営に付随するクリエイティブの制作を行っていただけるWEBデザイナーを募集し…
週3日・4日
260,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
自社開発のシステムを用いてオンライン営業のサービスを提供している企業です。 この度は現環境版の新機…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Laravel・Vue | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
・デザイナー業務 - 当社サービスのアプリやブラウザのUI/UX - 機能仕様の策定及び画面設計…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】リー…
・SRE/インフラ関連の営業時間内での業務全般 ・運用・保守における効率化、省力化 ・ドキュメン…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Android… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】英…
新規開発と開発運用中システムの保守対応(不具合対応含む)を担当いただきます。 ・英語学習アプリ…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
コーポレートサイトのリプレイスに伴う人材の募集となります。 上流の設計は完了し始めているため、…
週3日・4日
260,000〜500,000円/月
| 場所 | 中国・四国岡山駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
ゲーム内UI素材の作成を担当していただきます。 スマートフォン向ゲーム開発のプロジェクトにてU…
週4日・5日
240,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
通信事業者の会員向けシステムに関して業務部門と要件定義を行っていただきます。 外部・内部連携システ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
当社が運営する不動産Techメディアにおいて、フロントエンドの開発を担当していただきます。 お任せ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
BtoCアプリ機能追加のための開発業務を対応いただけるアプリエンジニアを募集します。 お車をお持ち…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Node.js・Serverless・… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
企業向けECサイト開発をメインで担当いただけるエンジニアを募集しております。 パッケージは最低限の…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・SpringBoot・Thy… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
企業向けECサイト開発をメインで担当いただけるプロジェクトリーダーとなるエンジニアを募集しております…
週5日
480,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・SpringBoot・Thy… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
私たちはWEB制作会社からスタートした、小さなクリエイティブスタジオです。クリエイティブとテクノロジ…
週3日・4日
190,000〜390,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
事業側およびクライアントの要件/要望を理解し、それらに沿って仮説出しを行い分析方針を決め、SQLおよ…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
通信事業者の会員向け契約変更システム開発チームで、基本設計作成およびオフショア部隊の詳細設計書・ソー…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川天王洲アイル |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seaser2 | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
人に寄り添うデジタル・プロダクトを開発するグローバル企業です。 BtoCアプリ機能追加のための開発…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Serverl… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
新規コンシェルジュサービス立ち上げに向けて下記業務をご担当いただきます。 ・既存サービスからの…
週5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Nux… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
内視鏡AI開発に関わる画像認識モデルの作成を技術的側面でリードし、製品化を推進する業務をご担当いただ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・自社ホームページの修正・改善 ・HTML, CSS, JavaScript,PHP コーディング…
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週5日…
Salesforceで基地局事業に関する業務統合マネジメントシステムを開発しています。 その際に工…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
自社スマホ証券アプリのUIデザインとコーディングをご担当いただきます。 綺麗なだけのデザインではな…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / AndroidJav…
現在自社内にてチャットツールの開発をおこなっており、そのプロジェクトに参画いただける人材の募集を行っ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅/永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・firebase | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】
顧客の課題解決やプロジェクト成功のためにコンサルティングサービスを提供し、顧客満足体験の創出や企業価…
週5日
330,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社モ…
自社で仮想通貨に関するアプリの開発を行っており、日本語で書かれているドキュメントを英語で翻訳しつつ、…
週3日・4日・5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社で仮想通貨に関するアプリの開発を行っており、日本語で書かれているドキュメントを英語で翻訳しつつ、…
週3日・4日・5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| PHP | |
定番
【Swift / 週5日】大手エンタメ系ク…
大手エンタメ系クライアント向けスマホアプリ開発をご担当いただきます。 具体的には既存アプリの新規機…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・デモシステム(AWS環境)構築 ・AWSやオープンソースのツールなどの技術調査 ・アジャイル標…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
自社サービスをご利用いただいているユーザー様の顧客満足度及び、信頼性向上のためのUI/UX改善や新機…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
◇BtoBtoC向けサービスの運用/機能開発のPL 今回は、自社データベースをブランドのマーケティ…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js・Lara… | |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
今回開発いただくのは、オンラインカウンセラーの方々が自身でのカウンセリングサービスを簡単に開設できる…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React.js | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】.…
想定プロジェクト① 医療機関(院内イントラネット)において、電子カルテやレセプト等のデータを集計・…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大門駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】HR領域…
HR(人材)領域で、クライアント向けサービスのデザインを担当いただきます。 ・web/spサイ…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
1.POS向けマスターデータ(商品マスタ、POSボタンへの割当、など)を編集するクライアント.(Wi…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三越前駅/新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
・営業やCSなどのドメインエキスパートと会話をしながら、本当に解決するべき課題を発見し、その課題を解…
週4日・5日
660,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
大手卸売業会計システムの周辺システムを再構築への機能追加要望の対応を行う。上位会社の責任者の方のサブ…
週4日・5日
330,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Java・Oracle・AWS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
住宅ローンに関するあらゆる課題を解決するプラットフォームを始めとする、様々なシステムの開発・運用や適…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Sw… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
エンジニアとして既存サービスの保守運用と新規サービス立ち上げに従事していただきます。 ・クラウ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿日の出駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当社は戦略デザインプラットフォームとして様々な事業を展開しています。 グラフィックデザイナーと…
週5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市民広場駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
大手求人系サイトで使用するメール配信システムのバックエンドAPI実装の案件になります。 画面上でメ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅、東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / 2D / 週5日】ス…
スマートフォンゲームのキャラクター(ファンタジー、美少女系)やモンスターのイラスト制作業務全般を担当…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
私たちは、プリントメディア、Webメディア、アプリケーションという異なる3タイプのコミュニケーション…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
現在自社内にてチャットツールの開発をおこなっており、そのプロジェクトに参画いただける人材の募集を行っ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤坂見附駅/永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート可/ フロントエンド/ 週5日】…
【担当業務】 ・金融・資産運用サービスの開発 ・VRT(Visual Regression Te…
週5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【副業】自社サイトに掲載する記事
定期的に発生しますライティング案件に対して時間稼働or固定精算で対応いただくイメージとなります。 …
週1日
30,000〜40,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
業界初出会い課金型転職支援サービスの設計・開発・運用をお任せします。 ・集客に関わるプロモーシ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 /PHP / 週3日〜】…
受託や自社開発における様々なWebサイト制作、アプリケーション開発プロジェクトに参加いただけるエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
クライアントと連携するサーバサイドのプログラムの設計・制作を行っていただきます。 サーバー構成を設…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【2D / 週5日】スマートフォンゲーム開…
キャラクター(ファンタジー、美少女系)やモンスターのイラスト制作業務全般を担当していただきます。 …
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
弊社広告事業におけるアドシステムの開発を行っていただきます。 ・アドシステム開発における技術的…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Scala | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】銀行系…
クライアントである銀行から受けたWEB開発案件のエンジニアを募集いたします。 PHPを使用した開発…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週4…
弊社商品の各種組み込みシステム向け製品のインテグレーション作業に従事していただきます。 インテグレ…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】ス…
開発中のスマートフォン向けオンラインゲームのクライアント開発に携わっていただきます。 具体的な…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】ハ…
設立当初からの高い技術力を持った開発集団ですが、更なる成長を遂げる為、新しい知識、情熱、考え方を持っ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムと自社製AIカメラを連携させたプロダクト開発にお…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
デジタルトークン発行管理プラットフォームのバックエンド開発業務です。 APIの新規実装、改修が主な…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
当社は、映像に特化したシステムインテグレーターです。 映像を活用したシステムのコンサルティングから…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
現在、新規事業の展開を検討しております。 それに伴い、パンフレット作成や雑誌・広告等の紙媒体の作成…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
デザイン会社からWEBサイトの校正案をインプットにHTML、CSS、JavaScriptを利用し、サ…
週3日・4日・5日
410,000〜690,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・‐ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
主にエステサロンなど美容関係のクライアント様を中心に、SNSを使ったWeb広告からチラシなどのリアル…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【AWS / 週5日】基盤移行運用
某金融系顧客ホールディングス向けオンプレ→AWS基盤への移行(Windows、Linux、各種DB等…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿水天宮 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
弊社は、インターネットを通じてサービスを提供し成長してきました。 本質的に価値のあるものを提供して…
週3日・4日・5日
360,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / GCP / 週5日】…
オンラインクレーンゲームシステム開発に従事していただけるインフラエンジニアを募集致します。 ゲーム…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
オンラインクレーンゲームシステム開発に従事していただけるフロントエンドエンジニアを募集致します。 …
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週5日…
オンラインクレーンゲームシステム開発の上流設計に従事していただけるエンジニアを募集致します。 ゲー…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
オンラインクレーンゲームシステムのアプリ開発(Android)を行っていただける人材を募集します。 …
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
金融系サービスを展開する大手クライアントの運営するWeb開発案件に参画いただきます。 弊社チームと…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
学生と教育機関を繋げるオンラインプラットフォームを自社開発しております。 今回は自社の教育系オ…
週5日
1,010,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
自社スクレイピング代行ツールや自動化ツールなどのマーケティングチームの所属で、マーケティングに関わる…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 豊洲新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】フ…
自社プロダクトのバックエンドの新機能開発、既存機能改修、運用改善をお任せします。 高速にサービ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Go・C#・Type… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
1. 行動解析など画像解析とソフトウェア機能の連動/コントロールの実現 2. 深層学習による骨格抽…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
現在、AIによる契約書レビューサービスを軸とした、企業の契約書作成を包括的にサポートするSaaSを開…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| SQL | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】税務…
某大手CD販売店や、大手化粧品メーカー、大手鉄道グループなどの案件を直で企画から運用までワンストップ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】仮…
マーケティング部にてデジタルマーケティング施策及びプロダクトの企画開発を行なっています。 マーケテ…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyOnRail… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
公庁・自治体等を対象とする入札情報速報サービスのリプレイスプロジェクトをお任せ致します。 現在…
週4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
弊社では開発において、積極的に新しい技術を採用し、快適な基盤を構築することを目指しています。 …
週5日
740,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【HTML/CSS / 週3日〜】EdTe…
どこの誰にでもフェアな学習チャンスを提供する急成長中の「オンライン家庭教師事業」を展開しています。 …
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】Saa…
・営業やCSなどのドメインエキスパートと会話をしながら、本当に解決するべき課題を発見し、その課題を解…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Go・構成管理ツール(Terraform・… | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】O…
自社で開発を行っておりますOMR(光学式マーク読取専用装置)や、OCR(光学式文字読取装置)製品の新…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
開発中のAndroid機器の認識機能において、実際の事象がうまく測定できていない懸念があり、調査をし…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
・ 新規IoTプロダクト向け組み込みシステム開発にて、アプリケーションプログラムの構築に参画いただき…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新卒就職支援サービスサイト運用業務に携わっていただきます。 既に公開済みサイトの新機能や施策の実装…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
在庫管理アプリ向けのAPIをRailsで開発します。 入出庫や棚卸しの機能を提供するAPIの設計・…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週5…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
中小企業に特化した、自社プロダクトの開発メンバーを募集しています。 • オンライン動画セミナー…
週5日
500,000〜990,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Re… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Webサイトの開発・運営や、アプリのデータ管理のための管理画面の開発などを担当していただく予定です。…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 千葉柏の葉キャンパス駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
BtoB向けの営業代行サービスのWebデザインやUIデザインをできるお任せできる方を募集しております…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社のデジタルトランスフォーメーション(DX)事業において、新規ポータルサイトの立ち上げにおけるデザ…
週5日
370,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Illustrator・Photo… | |
定番
【フルリモ / 上流SE / 週5日】国内…
オンライン商談システムのWebRTCに関わる開発をメインに担当していただきます。そこでWebRTC開…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
自社サービスの電力供給システムの新機能開発・改修業務をご担当いただきます。 クラウド型プラットフォ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Node.js・Re… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
リラクゼーションサロンに関するデザイン業務全般をご協力いただけるデザイナーを募集しています。 …
週3日・4日・5日
250,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるサーバーサイドの開発を行っていただきます。 小学…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Cake・Laravel・Fuel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるフロントエンドの開発を行っていただきます。 小学…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Angula… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業内外の様々なデータを価値ある情報に変換し…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
定番
【ライティング案件】採用サイトに掲載する記…
◆依頼したい内容: インタビュー及び記事原稿作成 ※3人で対談している記事に仕上げたいです。 …
週1日
30,000〜40,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
| ・・ライティング経験 ・エンジニア言語やゲームに詳… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
スマートフォンゲームのキャラ、背景、エフェクト、UI制作などを、個々のスキルに応じて担当してもらいま…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
| Photoshop・Illustrator | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
無料漫画アプリのフルリニューアルプロジェクトの開発全般~リリースまでご担当いただきます。 - リリ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
無料漫画アプリのフルリニューアルプロジェクトの開発全般~リリースまでご担当いただきます。 - …
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Anguar / 週…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとしてサー…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・SQL・ionic・Angul… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
総合人材企業の人事施策における新システムの開発をご担当いただきます。 具体的にはグループ間での人事…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
京都のお寺にいるような本格的な禅体験ができるプログラムをiOSアプリで提供しています。 より多く…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三条駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Rails / 週4日〜】…
自社サービスに関わる以下の業務を担当していただきます。 ・自社サービスアーキテクチャ設計・開発…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails5 | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
自社システムであるクラウド受付システムの導入企業様よりいただいているシステムのカスタマイズ依頼や、こ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービスの各種ポータルサイトの開発を行っていただくエンジニアを募集しております。 ユーザー…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
ブロックチェン関連のプロダクト開発に従事していただけるフルスタックエンジニアを募集しております。 …
週3日・4日
450,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京 小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・AngularJ… | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
・飲食店向けの業務支援アプリケーションの設計・実装(Rails/React + TypeScript…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go・Typescr… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
・デザイン及び新機能のUX・UI設計や既存のUX・UI改善 ・企画バナー画像や、コーポレートブラン…
週3日・4日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
非ゲーム領域での新規事業立ち上げに伴う、新規サービスのWebフロントの設計・開発業務です。 開発の…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
新規案件でグローバルを意識したアバターデザイン/IPキャラクターの制作/背景制作等を担当いただきます…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
1. 顧客の分析要望に合わせたアドホックな分析対応、アウトプット作成 2. 分析ソリューションの開…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
「金融に触れる機会創出」を行う、コミュニケーションデザイナーを探しています。 一般向け金融メディア…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
サーバーサイドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 プロダクトの目的、目標を理解…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
業界初出会い課金型転職支援サービスの設計・開発・運用をお任せします。 ・ユーザー画面・クライア…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
業界初出会い課金型転職支援サービスの設計・開発・運用をお任せします。 ・WEBアプリケーション…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Djang… | |
定番
【フルスタックエンジニア】派遣事業会社向け…
【担当業務】 - 派遣事業会社のスタッフ管理サイトのリニューアル 【案件の魅力】 - 大規…
週5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅/初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・React・Next.js・OpenAPI | |
定番
【フルリモ / C++ / 週5日】RPG…
大手のIP案件でスマホのRPGゲームの開発を行っていただきます。 ・クライアントの新規実装 …
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
AIを用いた契約書レビューを行う機能をメインとした、大企業法務部門向けBtoB Saasプロダクトを…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
当社でSaaS型の新規ブランド支援サービス開発に携わっていただきます。 すでに一次リリースしており…
週3日・4日・5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
アプリ向けの広告配信基盤開発をお任せできる方を募集いたします。 アプリケーションのサーバー・フロン…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
- AWS環境におけるサーバやコンテナ(EC2、Fargate)、ネットワークの構築、運用 - 各…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| - | |
定番
【リモート相談可 / Vue / 週4日〜…
HTML/CSS/JavaScriptの設計・コーディングを行い、ユーザー体験の改善や新機能・新サー…
週4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
TVメディアに強みをもつマーケティング支援会社である弊社にて、AIマーケティングシステム開発のテック…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Django | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
自社Webメディア運営や、新規自社開発事業の事業拡大に伴う人員増員のため 自社のWeb開発における…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 今回は、メディアコンサル事業におけるメディアの…
週3日・4日
330,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
下記4点のいずれかのフロントエンド開発をご担当いただける方を募集しております。 ・【営業所事務…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js・Vuet… | |
定番
【Java / 週5日】企業向けプログラミ…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C・C++・… | |
定番
【フルリモ / Ruby/React / …
メインサービスとして、自分の時間をチケットにしてシェアできるサービス提供しておりますが、今回は、新規…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週4…
自社サービスの作業服、事務服、ユニフォームの刺繍、プリントデザインを行っている会社です。 今回…
週4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
現在、某大学と共同開発中のエッジデバイスがあり、クラウドとの協調処理型のAIとして実装いただくデータ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Swift/Andr…
センサーデータと現在開発中のエッジ処理用独自アルゴリズムを使って、コロナ禍で医療崩壊を防ぐために体調…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Swift・AndroidJa… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / …
IoTとWebサービスを掛け合わせて新しい機能を創るクリエイティブな開発をお任せします。スマートホー…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
新卒向け就業支援サービスを展開している企業内でのデザイン業務。 Wordpressでのウェブサイト…
週3日・4日
190,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・オンラインのイベントサービスが社内に複数存在している状況の為、サービスの統合化を行いながら、機能強…
週5日
590,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Java/PHP /…
・新規BFF(Backends For Frontends)基盤の全体設計・基本設計の作成作業に参加…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・AWSの各種サービス・ソリューションを有効活用し、サーバーレスを意識した 開発を行う。 ・CI…
週5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
医療×AIにおけるクラウドサービスの開発・評価をご担当いただきます。 ・医療画像を扱ったクラウ…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Flask・Re… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】デー…
データ分析基盤の構築・運用をおまかせします。 ・各種システムからのBigQueryへのデータパイプ…
週4日・5日
840,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・GCP・BigQuery・Redshift・… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
弊社では、企業のSaaS導入の推進と、DX化を強力に推し進めることを目指しております。 世界中…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / swift/Kotl…
ゲームや他インターネットサービスの効率的な要件定義、設計、実装、運用を行っていただきます。 社員や…
週4日・5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
ゲームや他インターネットサービスの効率的な要件定義、設計、実装、運用を行っていただきます。 社員や…
週4日・5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】仮想…
マーケティング部にてデジタルマーケティング施策及びプロダクトの企画開発を行なっています。 マーケテ…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自社のAI空間情報システムを利用し、地方創生プロジェクトの開発をご担当いただきます。 iOSを…
週3日・4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Swift・Ob-C・Flask・ng… | |
定番
【フルリモ / Vue.js/ / 週5日…
今回はAWS上のWebアプリケーション開発にご協力いただけるエンジニアを募集します。 ・設計や…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Go・S… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
新規プロダクトで、自社ハイエンド層向け恋活マッチングサービスを開発しています。 エンジニア、PMと…
週3日・4日・5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
新規調査データのクラウド側処理機能を開発するサーバーサイドエンジニアを募集します。 依頼業務と…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Go・Larav… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】リフ…
人事・社員に負担をかけず、低価格で質の高い候補者を採用するリファラルリクルーティングプラットフォーム…
週4日・5日
500,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Go・FuelPHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
ECサイトやポイントサイト、会員管理システムなどのWebシステム設計・開発。 クライアントは大手企…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
トレーディングプラットフォーム:eSquare データプラットフォーム:eCompass ・上記…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js・Express | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・需給に関するデータパイプラインとダッシュボードの新規開発 ・enechainフォワードカーブの作…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・tableau | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
自動運転システムの開発など。 主に、自動車に設置されたセンサーデータを元に有意義な情報をユーザにフ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】Fin…
国内最大級のMAツールで大規模トラフィックなプロダクト基盤のインフラ構築・運用をミッションとしていま…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / GO / 週5日】某スポー…
メインとなるのは新しい機能の実装ですが、随時バグ改修も行います。 新しい機能を実装する際には要件定…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| - | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】完全ク…
AWSを活用したサーバ設計、構築、運用をインフラエンジニアとして担当いただきます。 具体的には…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】金融…
LDAP Managerで構築運用されているデータセンターのオンプレ環境をパブリッククラウドに移行し…
週5日
500,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】金融…
LDAP Managerで構築運用されているデータセンターのオンプレ環境をパブリッククラウドに移行し…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社で運営しているサービスサイトのコーディング、ディレクションを担っていただける方を募集します。 …
週3日・4日
130,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川港南台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】基幹…
経営者とクラウドサービスをつなぐBtoBマッチングプラットフォームを運営しておりますクライアント様の…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】新機能を…
c新機能の実装を中心とし、プロジェクトによっては企画や要件定義から関わっていただけます。 具体的な…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 新規ビジネスを推進していくためにPythonの…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C#・Azure | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・現在対応中のアグリゲーションサイトの開発マネジメント ・その他今後システム開発に伴い案件のマネジ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新栄町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
Javascriptフレームワークなどを用いたWebアプリケーションを構築。 特にUIデザインの改…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
デモ用Webアプリケーション及びバックエンドAPIの作成支援を担っていただける方を募集します。 …
週5日
330,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・Vue.js・ | |
定番
【Linux / 週5日】官公庁向けシステ…
①プロキシサーバ移行業務 Linux(RHEL)技術者 プロキシ:InterScan W…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 東北:仙台仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【リモート相談可 / AWS/Azure …
受託開発案件でのインフラエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
金融系クライアント向けに自社サービスのリリースを予定しております。 AWSを使用しており、運用面や…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go・AWS | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】データ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながら、データベースの…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】地域…
主に、地域共通ポイント事業を中心としたスマートフォンアプリの開発をお任せします。 ※希望に応じて、…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 東京23区以外東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】自…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】ア…
-プロダクトオーナーから提示される仕様のレビューやフィードバック -テスト設計および実行。バグだけ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
デザイン思考とUXデザインを駆使した新規サービスの企画・既存プロダクトの改善や、AI/IoT、プロト…
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・React・Express・G… | |
定番
【フルリモ / システムエンジニア / 週…
・2週間スプリントでのアジャイル開発 ・toB向けプロダクトの各種機能の設計・開発 ・社内システ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・RubyonRa… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】医療系V…
営業部門との調整や、クライアントサイドと連携しながら、サーバーサイドチームのプロジェクトマネージャー…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Java・Ob-C・C#・Nuxt.js・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】TVCM…
下記の業務をメインでご担当いただきます。 -サービスの成長に必要な新機能の立案を行う -新機能の…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Go・Vue.js・AWS | |
定番
【Java】バス・タクシー運転手の運転者情…
バス・タクシー運転手の運転者情報や血圧測定値など、多種の運行管理クラウドシステムの開発
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋池袋 |
|---|---|
| 役割 | アプリエンジニア |
| Kotlin・AWS:EC2、ElasticBean… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
弊社はイベント情報比較検索サービスをメインに運営するベンチャー企業です。 この度、新規事業の立…
週3日・4日
220,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
リリース予定の教育Webアプリケーションの開発業務に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・TypeScript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Photoshop/Ill…
この度は生徒数の増加に伴い、生徒からの壁打ち依頼や成果物の添削をご担当いただける講師の方を募集いたし…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】マー…
プラットフォームのWeb開発(RubyonRails/HTML/CSS/JavaScript)をご担…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・Typescript・-・A… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】D2…
下記の業務をメインでお任せします。 ・毎月機能のアップデート ・業界内関連サービスとのAPI連携…
週5日
410,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・A… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】プラ…
既存システムの開発・改善や企画などを幅広く担当していただくバックエンドエンジニアとして、以下のような…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Go・Typescript・RubyonR… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】農業…
申し込みフローの電子化 ・上記PJの要件定義から開発まで(要件定義、実装、テスト) ・API開発…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| PHP・Ruby・RubyonRails・Larav… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】コス…
・新規機能の開発(新規toBサービス、新規ECサービスの企画/設計/実装/改善) ・既存機能の改善…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js・AW… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
キャラクターコンセプトアート制作 背景コンセプトアート制作 その他アセットに関するコンセプトデザ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
| Photoshop・Flash・ActionScri… | |
定番
【ディレクター】自社のクリエイティブディレ…
【業務内容】 ・クリエイティブの与件/要件の理解、整理 ・企画、ラフ案作成 ・制作の進行管理/…
週4日・5日
290,000〜460,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | クリエイティブディレクター |
定番
【PHP】ペット保険関連のWEBサイト開発…
株式会社アニマライフがクライアント様と取り組んでいる、 ペット保険関連のWEBサイト開発と保守をお…
週1日・2日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・-・Laravel・・… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
商談に関する膨大な動画、音声、テキストデータを蓄積しており、これらを解析することで、これまで個人個人…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Backlog・Redash・Elas… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
開発や改善業務を担当していただきます。 今回は既存のシステム基盤を刷新し、新たなシステム基盤を…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java・Go・Lar… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
660,000〜1,490,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
・非IT企業のAI/データ活用を支援を目的としたアセスメントシステムの追加開発 ・アルゴリズム(A…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Kotlin・j… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
この度、インバウンド事業のキャンペーンプロジェクトに向けたコーダーを募集します。 新規ドメイン…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
プログラミングのオンライン学習サービスを提供している企業です。 学習教材は「直感的に分かる」を大事…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / セキュリティ / 週…
自社の各サービスにおけるモニタリング等のセキュリティ施策を推進していただける方を募集します。 その…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
自社のインフラ基盤の設計・構築・運用を担っていただける方を募集いたします。 ・非機能要件を考慮…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社の新サービスの開発に携わっていただきます。 社員とともに基盤構築からサーバー・フロントの開…
週4日・5日
740,000〜1,700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・TypeScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
当社は、マンションに関する情報サイト「マンションレビュー」をメインにWeb事業を展開しています。 …
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / 3DCG / 週3日〜】ゲ…
私たちは、日本国内大手のパブリッシャーからの受託制作を中心に、数多くのオリジナルゲーム、及び有名IP…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Maya | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
550,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
仮想通貨に特化したフォロートレードサービスの開発に従事していただけるWebエンジニア様を募集しており…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Phalcon・Laravel・Cordov… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自由…
自社サービスにおける ■機能の実装~テスト~本番環境への反映~リリースまで ■DB設定など、お客…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸JR大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
通信事業者向けシステム開発業務です。 API開発やRestで投げられたデータをサーバサイドのAPI…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】介…
食事宅配サービスサイトのRubyを使用したサーバーサイド開発になります。 フロントエンド(JQue…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】飲…
WEBサービスの企画・設計・開発・運用業務やサイトの改善・改修 新サービス開発プロジェクトにおける…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
フロント画面や管理画面等の開発をお任せしたいと考えてますが、ご本人の志向性や希望に応じて、サーバサイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
オンプレミス環境にAIを用いた防犯のための映像解析システムを導入するシステム開発に携わっていただきま…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Google・Drive・Conflu… | |
定番
【フルリモ / Rudy / 週5日】AI…
オンプレミス環境にAIを用いた防犯のための映像解析システムを導入する システム開発に携わっていただ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails・Google・Drive・Co… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
これまで外注していたデザイン部分を内製化し始めておりまして、最近入社したデザイナーへの教育と、実際の…
週3日・4日
260,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
某基金様のキャリアアップシステム(DX)の開発をお願いいたします。 新規インフラの立ち上げのた…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
当医院は不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関として、産科経験豊富な医師達のもと、赤ちゃんにも…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小田原駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
システム企画・開発・導入支援等を行うITコンサルティング企業にて自社開発をされている「オンライン展示…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Vue.js・Lara… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
新プロダクトのサーバーサイドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 参画頂くタイ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
広報/マーケ面の体制強化のため、既存メンバー(エンジニア1名、デザイナー2名)と連携してリリースに向…
週3日・4日・5日
330,000〜850,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄福岡駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
主力のアウトソーシング事業において、大手上場企業を中心とした顧客からお預かりする会計業務(連結決算、…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【自社プロダクト】PHPエンジニア(運用保…
弊社プロダクトの機能改修の設計・製造及び保守をお願い致します。 PHP、Smarty、MySQLを…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝浦 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
SoftwareEngineer
与信、暗号資産・資産運用の機能を一つのウォレットで提供していく等、より簡単に金融サービスを利用できる…
週4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・GoogleBigQuery | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
日本最大級の音楽・エンターテインメント企業のWEBサイト制作業務をご担当いただきます。 ディレクタ…
週5日
670,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】Web制…
自社サービスのwebページのデザイン、HTML/CSSのコーディング、修正、保守、運用業務全般を担っ…
週5日
750,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】財務会計…
SAP-FIモジュールコンサルタントとして、大手企業のSAP導入等の大型プロジェクトに参画いただきま…
週5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PdM / 週5日】自社の…
医療AIベンチャー(大型資金調達済)のプロジェクトマネージャーとして、認知症領域の事業に係る企画・開…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】アプリ開…
大手総合商社グループ100%出資の元立ち上げられたスタートアップです。 お客様にコンサルティングか…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【PHP / 週3日〜】自社システムや外販…
PHP開発。自社システムや外販システムの開発、改修、保守 ・工事スケジュールと対応する班の割り…
週3日・4日・5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・Linux・Tomcat・Apach… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
IT会社の社内システム開発業務です。 調査、設計、製造、試験をご担当いただきます。 既存メンバー…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアを開発します。 ・アーキテクチャ選定のサポート ・…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| SQL・Node.js・React | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
エンド企業にて開発 / 展開中の不動産業界特化型の自社サービス開発PJに従事いただきます。 ネイテ…
週5日
670,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Java・Ob-C・Kotlin・Spring・No… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】EC…
・某ITベンチャー企業にて自社ECショップ構築ASPサービスのリプレイスPJで、サーバーサイド開発が…
週5日
620,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
設計、製造、テストをアジャイル(スクラム)のように進めています。 要件の変更が頻繁に発生しますので…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Angular | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】We…
AEM(Adobe Experience Manager)で構築されたWebサイトの運用支援業務をご…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・A… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】美…
美容医療の口コミ・予約サービスの開発業務に関わっていただきます。 美容医療自体の体験向上のために、…
週4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / UIUX / 週4日〜】国…
・プロダクトの利用実態の調査 ・UIのユーザビリティ上の課題調査 ・インタビュー設計や実施 ・…
週4日・5日
330,000〜990,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・複数のfreee製品から参照利用される共通マスタの開発です。 ・フロント、バックエンドどちらも含…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Go・Typescript・RubyOnRails・… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】クラ…
サーバーサイドは主にシステム基本設計〜実装に至るまで裁量を持って携わっていただくことができ、更にご希…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js・Bo… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
当社が運営する新規サービスに関するバックエンドの実装をご担当いただきます。 - 既存サービスにおけ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails・AW… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】動画系…
社会人向けオンライン学習サービスのWebアプリケーション開発。 主に、法人の管理者・利用者向けのプ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・RubyonRails… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】広告…
自社プロダクトの広告運用自動化webアプリ開発となります。 アジャイル開発で進めており、設計、開発…
週5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
・ネイティブアプリが利用するAPIサーバー、予約データ管理やネイル画像の管理などの、ネイリーのバック…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js・EXPRESS… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
今回の募集では、自社プロダクト(HR領域)開発全般をご担当いただきます。 ・機能拡張/改善の設計、…
週5日
390,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】製造…
設計、製造、テストをアジャイル(スクラム)のように進めています。 要件の変更が頻繁に発生しますので…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【Vue/Kotlin/Java】AIサー…
【担当業務】 - 新規機能開発・改善 - ビジョン策定、設計、実装、テスト、リリースまで一貫して…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Kotlin・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Wordpress …
・自社サイト(WordPress)への機能追加 ・デザイナーが制作したデザインのサイト実装 ・W…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】某既存…
販売サイトを運営している企業にて某既存BtoC向けWebサービス開発案件にご参画を頂きます。 FW…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
大手SIerにおける開発環境モダナイズ部隊の基盤運用自動化チームにて、エンドユーザや社内他事業部に対…
週5日
500,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Kubernetes | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】イン…
国内大手教育事業者様がインド法人にて学力テスト事業を展開しています。 (インド現地にて模試の実施〜…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel・React・ | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
・ServiceCloudのカスタマイズ作業(設計、実装、テスト) ・ExperienceClou…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週5日】フ…
・ファイル管理システムの新規開発。 ・サーバサイドに関してはお客様側のプラットフォームに API …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週4日〜…
クラウド基盤デリバリ・SREおよび技術整備支援をしていただきます。 大手SIerのクラウド技術部隊…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】転職サー…
転職支援・採用支援サービスの新機能開発を行っていただきます。複数チームがございますので、PJにより担…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
国内最大手保険会社にてプロジェクトマネジメント・サポートをお任せいたします。 他社と協業したデジタ…
週5日
750,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Typescript・TypeScript・Next… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】独自…
上記システム刷新における要件定義、設計、開発を主に担当いただきます。 Node.jsポジションにて…
週5日
330,000〜930,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週4…
VR:Unityエンジニア。VRライブアプリ関連の開発に携わっていただきます。 Unityの最…
週4日・5日
250,000〜1,340,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・C# | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】フ…
国内プラットフォームにおけるフロントエンドエンジニアを募集します! ・担当工程 ・要件定義/…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】大…
大手電機メーカーの、Webサイト作成になります。 主にReactベースでフロントエンド開発を担って…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / SpringBoot…
会計系データ連携システム ・広告・人材サービス・出版を行っている企業様の管理会計関連システム機能追…
週4日・5日
250,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
某ITベンチャーにて、自社製ECプラットフォームの新規開発でのサーバーサイド側を担当頂きます。 …
週5日
620,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【Java / 週4日〜】特許情報提供シス…
(1)OSS PostgreSQL10から、Enterprise PostgreSQL13へのバージ…
週4日・5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Java・Spring・Sprin… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】ID統合…
・データ活用基盤のゴール設計に向けた設計・開発・運用の先導 ・情報セキュリティ知見を生かしたAIM…
週5日
370,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】独自…
クライアントが展開しているCXM型の独自マーケティングシステムのフロントエンド開発になります。 ※…
週5日
330,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・AWS・Docker・GCP | |
定番
【フルリモ / .NET / 週4日〜】某…
・同サイトのサーバーサイドの詳細設計/開発/テスト ・定例MTG対応 ・仕様書等ドキュメント作成…
週4日・5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | .NETエンジニア |
| C#・.NET・Framework・.NET・Cor… | |
定番
【AWS / 週5日】医療保険関連システム…
・本番稼働中のオンライン資格確認システム(以下、オン資と略称)に対する追加開発・改修。 ・オン資・…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週4日〜…
・ユーザー部門向けのツール作成 エクセルVBA ツール、AccessVBAツール ユーザー部…
週4日・5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
| JavaScript・VBA・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Laravel / …
建設現場調査・情報共有アプリケーションを開発しており、今回はLaravelエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Slack・Jira・ | |
定番
【フルリモ / PHP/Laravel /…
弊社既存クライアントの内部システムをリプレイスいただき、主に要件定義からご支援頂く事を想定しています…
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel・AWS | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにデザイナーとして関わっていただける方を募…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python/Typ…
主に下記の業務をご担当いただきます。 ・各SaaSサービスのインテグレート、設計、開発、マネジメン…
週5日
480,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| JavaScript・Typescript・AWS・… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】LA…
①想定しているアサインプロジェクト ・作業内容としてはCMS(内容管理システム)の開発です。 …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿野並駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
cocos2d-xを使用してゲームのクライアント実装をします。 運用タイトルの機能バージョンアップ…
週4日・5日
330,000〜930,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++・Xcode | |
定番
【Python / 週5日】動画編集デスク…
医療データの動画を効率的に管理するために、新しく動画編集機能及びアノテーションを行うデスクトップアプ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】専門…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/UXデザインやコーディ…
週4日・5日
370,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
顧客システムの運用保守をお任せいたします。 主には以下の業務を担当いただく想定です。 Ora…
週5日
410,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| OCI・Oracle・Linux・RHEL | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
オンラインサロンに特化したプラットフォーム・クローズドSNSの開発に携わって頂きます。 ・基本…
週3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・React・Redux・Redux-Sa… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】デー…
オンプレミス → AWSへの移行 本件は契約情報を取り扱っているシステム 現時点ではVmware…
週4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
サービス運用のための管理画面開発(標準的な WEBAPP もしくは SPA)業務や、サービス運用に必…
週3日・4日・5日
330,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Pyth… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
要件定義〜テストまでをお願いしますが、PdMを置くため、要件定義後の設計・実装・テストが主な仕事です…
週5日
330,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
・物理シミュレーションと機械学習(AI)の融合に関する事業を担当して頂きます。 ・数値流体解析(C…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・某ITベンチャーにてアスリート応援プラットフォームのフロント/サーバーサイド両面での開発(フルスタ…
週3日・4日・5日
750,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
・広告代理業 ・イベント事務局の運営 ・催事、コンベンション及び会議の企画立案、制作、運営及び管…
週3日・4日・5日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
・某ITベンチャーにて、自社製チャット型WEB接客プラットフォームに採用しているengagebotの…
週5日
580,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Typescript・- | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
経営サポートシステムリニューアルに際して、基幹システムのリプレイスのご依頼となります。 BPR…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・ReactJS… | |
定番
【リモート相談可 / システム / 週5日…
クライアント課題に合わせて、2,3名でチームを組みFileMakerでクライアントの希望を確認しなが…
週5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・現行のシステムの保守改善の業務として日々発生する案件対応 ・新サービス開始に伴う、既存システムへ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| JavaScript・Java・Linux | |
定番
【リモート相談可 / VBScript /…
-某製薬会社標準PDF編集ソフトウェア(Foxit)のバージョンアップ -要件定義支援、設計、スク…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VBScript・PowerShell | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では企業のデジタルマーケティングを支援していくために自社運営メディアを用いて企業の課題を解決して…
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【インフラ / 週5日】某大学向けコンピュ…
以下構成におけるコンピュータ室更改作業 ・LDAP・ファイルサーバ(RHEL 8) ・バックアッ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 東北:仙台仙台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週…
本研究所の研究成果を公開するサービスにおけるWEBフロントエンジニアを募集いたします。 本サービス…
週3日
350,000〜600,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・toB向け広報系DXツールを展開している某ITベンチャー企業にて、自社商材であるWebサービス/サ…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・ロボット制御システムの開発・実験(AI、人工知能領域など) ・画像処理・データマイニング・機械学…
週5日
670,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
現在、クラウド型スキル管理ツールをリリース。 更なるサービスの質の向上と事業拡大に向けて、リードエ…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Java・Spring・Boot・Linux… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手配送会社向けの配送連携システムのリニューアル案件となっております。 詳しい案件内容については面…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・- | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
今回は事業急拡大に向けて、新しいメンバーを募集致します。 以下の業務をお任せします。 ・自社…
週4日・5日
480,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| PHP・Laravel・WordPress・Solr… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】大…
HR系プロダクトのアジャイル開発において、ディレクション業務を担っていただきます。 - 制作ディレ…
週3日・4日・5日
750,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
・カスタマージャーニーの設計と上流からのUX構築 ・サービス、アプリケーションなどのUIデザイン …
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
・新領域開拓に向けた新規商品・サービスの構想推進 ・技術者、マーケッターと連携した活動、チームビル…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】クラ…
自社プロダクトを支えるインフラにおいて、下記の業務を行っていただきます。 ・ネットワーク、サーバ構…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸なんば駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
会計ソフト・クラウドサービスを提供する当社にて、社内SEとして下記の業務に携わっていただきます。 …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【PHP / 週5日】WEBアプリケーショ…
クラウド業務システムの開発に携わっていただきます。 自社プロダクトなのでプログラミングだけではなく…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Typescript・CakePHP・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
・某システム会社にて自社製教育系コンテンツ管理システムの2次開発を予定しており、基本設計~開発~テス…
週5日
670,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】請求…
Webサイト・Webシステム・スマートフォンアプリ・データ放送コンテンツ等の制作・開発を手掛けていま…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
受託開発案件でのPHPエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお話しさ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Lararvel | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
- AI契約管理システムにおける要件定義・設計・開発・テスト・リリースまでのプロジェクトマネジメント…
週4日・5日
750,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Typescript | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週3日…
弊社クライアント(HR系)の法人マーケのチームでフロントエンドエンジニアを担当いただきます。 単純…
週3日
250,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】自…
自社プロダクトにおけるインフラ設計構築及び保守運用業務となります。 アプリケーション開発メンバ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【セキュリティー / 週4日〜】自社セキュ…
この度は、導入企業の増加に伴い、導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集いたしま…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / セキュリティ / 週5日】…
※内視鏡と外部接続される機器のネットワーク監視の為のセキュリティオペレーションセンター(SOC)構築…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日
240,000〜450,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
PHPを用いたFintech領域セルフレジプラットフォームの開発案件レンタルPOSのサービスはとして…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【PdM】AIによる契約書レビューサービス…
製品開発のプロジェクトマネージャーとして、以下の使命を果たしていただきます。 - LegalTec…
週4日・5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| AWS・・・GCP | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週4日〜…
システム開発プロジェクトの初級PMOをご担当頂きます。 ・集計作業(進捗状況見える化作業) …
週5日
200,000〜560,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋九段下 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・基幹システムおよび公開サイトの共通部品のメンテナンスおよびアーキテクト支援。 ・新規案件に発生時…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台、新宿 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】新…
・複数のWEB制作プロジェクトのデザイナーとして参画 -クライアントmtgの参加 -社内メン…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
定番
【フルリモ / QA / 週4日〜】自社物…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
Ruby on Railsエンジニア
◇案件概要 受託開発案件(直クライアント)にてチームとしてご活躍いただけるRuby on Rail…
週4日・5日
460,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Ruby on Railsエンジニア |
| Ruby・言語:Ruby・・TypeScript … | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】特殊…
特殊データ集計サービスの保守・改善業務 ・既存のコードの理解と保守改善 ・既存システムへの新規機…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・Typescript・Rus… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】PHP…
※SES案件になります(弊社⇔SES⇔エンド)※ 主にWebシステムの受託開発をしている企業にて、…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】サーバー…
WEBアプリやサービスなどの受託案件を多数抱える企業にて、Goを使用したサーバーサイドエンジニアの方…
週5日
160,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国際センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GO・AWS・ShellScript | |
定番
【リモート相談可 / セキュリティ / 週…
急速に拡大していく事業に対して、様々なセキュリティの対応を行っていかなければならないと考えおり、すで…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
自社サービスアプリのサーバーサイド開発、または、社内業務を支援するツールの設計開発に携わっていただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにデザイナーとして関わっていただける方を募…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
今までコストをかけずにステルスで成長を続けていたのもあって、ハイブリッドアプリ(ionic)としてモ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとして既に…
週3日・4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・SQL | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
今までコストをかけずにステルスで成長を続けていたのもあって、ハイブリッドアプリ(ionic)としてモ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三越前 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・₋- | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
デジタルマーケティング新サービスリリースにあたり、各社にまたがる多様なデータソースシステムを統合し、…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【C++/】ハイエンド系のアクション等のゲ…
志望、スキル、経験等を考慮の上、下記いずれかの業務に携わっていただきます。 ・プレイヤーキャラクタ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週4日〜…
自社サービスとして展開をしているマッチングプラットフォームシステムをWebアプリケーションとしてサー…
週4日・5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
新規IoT開発案件において、AndroidTV向けアプリケーション開発を行います。 開発工程につい…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【フルリモ / データベース / 週5日】…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながら、データベースの…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【インフラ / 週5日】OracleでのD…
当社サービスはOracle基盤で構築していますが、大型案件の開始に伴い、Oracleからクラウドへの…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
優秀なメンバーと一緒に、開発経験豊かなテックリードの下、プロダクトを作り上げていく開発メンバーとして…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
大成長しているSaasサービスの開発に携わっていただきます。 開発経験豊かなテックリードの下、…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大成長中…
事業責任者と密に連携し、プロダクトを作り上げていく開発リーダーとしてご活躍いただきます。 ■サ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Python・Django・A… | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
当社サービスの主にフロントエンドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用しております。…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Django… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
当社サービスの主にフサーバーサイドの開発を担っていただきます。 当社ではスクラムを採用しております…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・DjangoRESTframework | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
自社プロダクトを支えるリードエンジニアを募集しています。 クラウド基盤の開発、アプリケーションの新…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / プロダクト / 週3…
フィットネスアパレルの販売を行う会社です。販売ルートとして店舗とECサイトの2つを持っています。また…
週3日・4日・5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【ネットワーク / 週4日〜】新規通信事業…
この度は新規Wi-Fi事業の推進にあたり、各自治体への高速Wi-Fi設置に向けた設計を担っていただけ…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Typescript / …
弊社は急拡大の投資フェーズにおりますが、事業課題の解決及び更なる成長を遂げていきたく、新規事業企画を…
週4日・5日
660,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週4日〜】E…
・プロジェクト内容: 弊社のECサイトのセキュリティ面強化。 ・情報セキュリティ・システムのWA…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
戦略立案~制作/広告運用までデジタルマーケティングを一気通貫でサービス提供を行っております。 …
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / WEBデザイナー / 週3…
戦略立案~制作/広告運用までデジタルマーケティングを一気通貫でサービス提供を行っております。 …
週3日・4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
当社の研究開発部門にて、全文検索システムに関わる研究開発をお願いします。 当社では条文検索、類…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
広告配信プラットフォーム及びメディア向けレポート一元化ツールWebアプリケーションのフロントエンド開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
サーバサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発やインフラ設計・保守など…
週4日・5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
モバイルアプリの開発において、技術選定から設計・開発・運用までをリードいただきますので、大きな裁量を…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Flutter・React・N… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】C…
CRM(Salesforce)をより業務に最適化した形で活用すべく、追加要件への対応と日々の運用体制…
週5日
830,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
ネイル情報サービスのWEBエンジニア兼AWS運用エンジニアを募集しております。 ・ネイルサービ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Typescript・Django | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
アプリもWEBもあるネイル情報サービスのUI/UXデザイナーを募集しております。 ・アプリのUI/…
週4日・5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【セキュリティ / 週4日〜】自社セキュリ…
この度は、導入企業の増加に伴い、導入後の運用を担当していただけるセキュリティエンジニアを募集いたしま…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【デザイナー / 週3日〜】自社ブランドで…
自社ブランドでの化粧品やサプリメントの開発や販売を行っております。 実店舗のほか、ECサイト(自社…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【BIエンジニア】顧客連携基盤の開発支援
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | BIエンジニア |
| Python・SQL・R | |
定番
【バックエンドエンジニア】顧客連携基盤の開…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(顧客連携) |
| PHP・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
既存のコーポレートサイトのリニューアルや新規事業部でのキャンペーンサイトやLP制作のデザイン・コーデ…
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) アーキテクチャー設計/製品サポー…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Java・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】E…
多くのECスタートアップに利用されているRuby on Rails製のオープンソースECパッケージを…
週3日・4日・5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北与野駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サロ…
このたび事業拡大に伴い、サロン向け顧客管理システム開発に携わっていただけるフルスタックエンジニアを募…
週3日・4日・5日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸伊勢駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】モ…
モバイルオーダーやセルフレジなどのモバイル自動化ソリューションで、飲食店のデジタル変革化(DX)を支…
週5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
ドキュメント作成業務および、PMのサポート業務をお願いしたいと考えております。 アウトプットに…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
社内の複数サービスが抱えるユーザを統合し、データの蓄積及び、検索が可能なデータ基盤のシステムの開発・…
週4日・5日
410,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
パートナー企業(AWSの認定パートナー)にて運用チームを作り、AWSのテクニカルサポートを行っており…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】行…
自社サービスである行政ビッグデータと行動科学を応用した公的通知サービスをリニューアルしていくプロジェ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
建設業における顧客向け品質管理・検査アプリをより多くの人に使ってもらうプロダクトとして成長させていく…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【社内SE / 週3日】ヘルステックベンチ…
グループ全社のクライアントPCやそれに付随するヘルプデスク業務をご担当いただきます。 ・キッティン…
週3日
170,000〜340,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】社…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署と連携してプロダクトのUIデザインをご…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】V…
バーチャルライブの基盤となるシステム開発からモバイルアプリケーション開発、演出制作などクライアント開…
週5日
300,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】官公…
官公庁向けのシステムを一部リプレースします。 MQで汎用系システムやオープン系システムに電文のやり…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
大手バックオフィス系アプリケーション開発企業内のマーケティングチームにてデザイン業務に携わっていただ…
週3日・4日・5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川五反田 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【Java / 週5日】新ECモデルのシス…
この度は日本での「S2b2C」モデルのECサイト立ち上げにあたり、エンジニアを募集いたします。 …
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
ECにおけるWebマーケティング
LEC分析 L数字分析 L広告戦略、販売 L部署連携で売上を上げていく…
週3日・4日・5日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京幡ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ECマーケター |
定番
【UI/UX / 週3日〜】新ECモデルの…
この度は日本での「S2b2C」モデルのECサイト立ち上げにあたり、 UI/UXデザイナーを募集いた…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋新大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】投資サ…
受託プロジェクトにて少額で株式投資ができる投資サービスのマネタイズアイデアの企画検討をご支援いただき…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週5日】医…
人気モデルやアイドルをキャスティングした自社ブランドのカラーコンタクトレンズや、次亜塩素酸水スプレー…
週5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 品川大崎広小路駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
当社は“暮らしに希望を 家族のように寄りそって”を理念に掲げ、健康食品やサプリメントといった機能性食…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
クライアントに対してブランディングデザインからご提案する機会も多く、コーポレートサイトのリニューアル…
週3日・4日・5日
150,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
AWSを用いて自社サービスのインフラ構築や運用をご担当いただけるインフラエンジニアを募集しております…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
システムを支えるAPIプラットフォームの拡充、新サービス開発、他社サービスとのアライアンスによる開発…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
Androidエンジニアの方には、プラットフォームの上で、新サービス開発、他社サービスとのアライアン…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【PM|フルリモートOK】FXの顧客向けバ…
【プロジェクトの概要】 FXの顧客向けバックエンドシステム (顧客管理・トレーディング管理・入金…
週5日
250,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海外 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
ECにおけるWebマーケティング
LEC分析 L数字分析 L広告戦略、販売 L部署連携で売上を上げていく…
週3日・4日・5日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 新橋・銀座・東京幡ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ECマーケター |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
本ポジションでは、当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのフロントエンド開発を担っていただく…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】C…
・GitLabを利用したCI/CDパイプラインの検証、設計、環境構築 ・上記のCI/CDパイプライ…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
定番
【リモート相談可 / 3DCG / 週4日…
この度は、ゲームコンテンツ開発・運営事業において、SNSゲームの開発に向けた3DCGデザイナーの方を…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender・Unity | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js・N… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
この度は、社内アクセラレーションプログラムから生まれたスマートウォッチシリーズの開発に携わっていただ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
iOS/Androidアプリ・Webでの総合的・横断的なUI/UXデザインをリード頂ける方を募集して…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで、サービス全般に関わる様々な…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
①HR(人材)領域で、クライアント向けサービス ・web/spサイトのデザインを担当いただきます(…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週5日】自…
①HR(人材)領域で、クライアント向けサービス ・web/spサイトのデザインを担当いただきます(…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】自社サー…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】自社サー…
この度は、当社の運営する、外国人管理に特化した人材管理ツールの開発に向けたエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】新規の集…
既存のプロフェッショナル人材サービスで得たノウハウを活かして、社内メンバー(コンサルタントおよび事業…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸心斎橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ネ…
各エンドユーザ向けにセキュリティ製品の導入プロジェクトを行っております。 そのため、下記のポジショ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) MongoDB, Neo4j, Ka…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】新規サー…
弊社の新規事業で立ち上げを行っているプロダクトの各フェーズにサーバーサイドエンジニアとして関わってい…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・N… | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】オン…
すでにWEBアプリで公開しているオンラインマッチングサービスのiOSアプリ立ち上げに伴い、iOSエン…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
toB、toC両方で運営するオンラインマッチングサービスの拡大に伴い、Rubyエンジニアを募集してい…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
SMS社で運用する、ケアマネジャー向けのコミュニティサイトのフルリニューアルPJに参画いただきます。…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・PHP・C#・CakePHP・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】上場…
・インフラ開発・運用戦略および計画の策定 ・弊社サービスを提供するインフラの設計・実装・運用 ・…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
オンラインクレーンゲームシステム開発に従事していただけるサーバーサイドエンジニアを募集致します。 …
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
現在自社でのSAPの導入を進めており、現行のERPをSAPに置き換えていくフェーズです。 SA…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・Spring・Vue… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】リプ…
・レガシーなLAMP構成の現在のECサイトとCMS/発送管理/顧客管理/在庫管理/生産管理を含む管理…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京小伝馬町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・Ruby・- | |
定番
【Java】AIによる契約書レビューサービ…
【仕事内容】 - AI契約管理システムのバックエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テ…
週4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・SpringFramework・Spark… | |
定番
【PHP案件|原則リモートOK】行政DXで…
【業務内容】 ポータルサイトのシステム開発・運用 管理するシステムの開発を要件定義から設計・コー…
週5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・・FuelPHP(8割) | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
フィットネス音声ガイドアプリのデザインチームに参画し、マーケターやエンジニアと共に、広告デザインから…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Node.js・f… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週…
ヘルスケア音声ガイドアプリマーケティングやWEB制作など、幅広く関連事業を行っている企業です。 フ…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
統計分析の技術を用いてオフライン、オンラインの広告/販促効果を最適化するソフトウェア開発を行っており…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
自社サービス開発・運用と多角的に事業展開をしているLHLで主にバックエンドエンジニアとして業務を行な…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・PHP・Python・Djan… | |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
新規事業立ち上げにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきます。 サービスを運用すると同時…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】会計仕…
当社では仕分けソフトを大手税理士事務所や会計事務所などに提供しております。 サービス普及後の事…
週5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】新プロ…
新プロダクトの企画担当を担っていただける方を今回募集しております。 ・協業先との共同事業の立ち…
週5日
830,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
新サービスに必要なバックエンドでのバッチ開発をご担当いただきます。 作業範囲 ・設計からテストま…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
クライアントから請け負っているECサイト構築のフロントエンド開発を担当いただきます。 業務内容とし…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
外国籍の方向けの新規アプリ内の追加アプリ開発チームの立ち上げを担当者とともに進めていただきます。 …
週3日
440,000〜910,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Flutter | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】Mic…
この度は事業の拡大に伴い、C#エンジニアを募集いたします。 ・クラウドサービスを利用した開発業…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
3D空間上でバーチャルイベントを開催するプラットフォームの開発およびプラットフォーム上の空間構築に携…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| Unity | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】Mic…
この度は事業の拡大に伴い、SEを募集いたします。 ・クラウドサービスを利用した開発業務 -…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
社内で動いている複数のPJにPMとしてご参画いただきます。 ▼PJ例 ・広告データベースの構築 …
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
サブスクリプション型プログラミングスクールサービスとしてリリースをした新サービスのフルスタックエンジ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
今回は弊社でご活躍いただけるUI/UXデザイナーの方を1名募集いたします。 ・サービスのコンセ…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
自社の開発プロジェクトのPMとして、チームマネジメント、協業先会社やSIerとの渉外、利用技術の選定…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】契…
自社開発を行っております契約書レビュープラットフォームを、今後さらに多くのユーザーに使っていただくた…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
リーガルテック領域のサービス開発に携わっていただきます。 社員とともに幅広く裁量を持ってお任せ…
週3日・4日
520,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
日本最大級の料理動画メディアのAndroidアプリ開発を担当していただきます。 アプリの開発・運営…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】テレ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトの基本設計において、アーキテクトと連携しながらインフラの検討及…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Scipy・Numpy・Scikit-Learn・P… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】Mi…
この度は事業の拡大に伴い、データエンジニアを募集いたします。 事業拡大に伴う体制強化が必須であり、…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】M…
インフラ領域の運用エンジニアとして開発を推進していただく方を募集します。 3D空間上でバーチャ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】M…
事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 昨年ローンチしたバーチャルイベントをはじめ、ヘ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
事業拡大に伴う体制強化が必須であり、増員募集です。 昨年ローンチしたバーチャルイベントをはじめ、ヘ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】クラウ…
この度は事業の拡大に伴い、バックエンドエンジニアを募集いたします。 3D空間上でバーチャルイベント…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社メディア・国内最大級規模の金融プラットフォーム事業部門の技術責任者を担っていただける方を募集して…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週3日】…
人事データを活用するための開発プロジェクトでのデータエンジニアを募集しております。 大きくは、経営…
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【Javascript / 週5日】Lin…
①CentOSによる業務環境構築全般 ・DMZ構築 ・Dockerで仮想環境構築 ・ファイルサ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋大塚駅 |
|---|---|
| 役割 | Javascriptエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・React | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
3D空間上でバーチャルイベントを開催するプラットフォーム開発およびプラットフォーム上での開発や、また…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸四日市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】テレビ…
大規模なWebシステムの開発プロジェクトで、PMOチームとして複数サブプロジェクトの開発マネジメント…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
この度社内システムの再構築に向けたエンジニア様を募集いたします。 下記プロジェクト内にてご希望や適…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【Vue.js / 週5日】レンタル機器サ…
弊社で受託開発を行っている、レンタル機器メーカーの基幹システムの構築のフロントエンド部分をご担当いた…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原錦糸町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
Google Cloudを用いた以下のいずれかの基盤の設計・構築・運用に携わっていただける方を募集い…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
東証1部上場企業のグループ会社である弊社にて、業務提携先のパートナー企業と協業しながら、歩数計アプリ…
週4日・5日
570,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】自治体及び行政のDX化…
この度は事業の拡大に伴い、PMを募集いたします。 自治体とともに、行政のDX(デジタルトランス…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
弊社のグループ会社にてBtoC向けポイントメディアにおけるアプリケーション開発をご担当いただきます。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・Ruby・Symfony・Laravel・R… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
チームの技術的リーダとして業務を遂行していただきます。 1) MongoDB, Neo4j, Ka…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
スマホアプリ開発において、フィジビリティ確認およびセキュリティ方式の設計構築を行っていただきます。 …
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・Java・React(reac… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】新…
複数のWEB制作プロジェクトのデザイナーとして参画 -クライアントmtgの参加 -社内メンバ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】QAテ…
スマホアプリサービスにおけるテスト計画の策定やテスト設計、テストの実施、テスト結果の確認(分析) …
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | QAテストエンジニア |
| ₋- | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
当社はゲーム感覚で学習できる対話型オンラインアニメーション教材企画・開発と販売を行っている会社です。…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社は美容業界向けにICTを駆使し、成長を続ける「美容サロン向けICT事業」、全国の美容サロンの繁栄…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
ヘルステック分野におけるライフログプラットフォームのWEBデザイン、ユーザー向けプロダクトのUI/U…
週3日・4日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】自社H…
自社WebサイトまたはアプリのUIデザインからランディングページ作成まで様々なデザイン業務に携わりま…
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【API / 週4日〜】連携システムにおけ…
弊社提供サービスと、お客様で利用中の既存サービスとの連携開発をメインで行っていただきます。 連…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Nginx・AWS・Docker | |
定番
アジャイル開発エンジニア
・自動運転システムの開発など。 ・主に、自動車に設置されたセンサーデータを元に有意義な情報をユーザ…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【リモート相談可 / java / 週3日…
・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 / オンライン教育を行うシステムの開発 ・主に他の開発…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・Kotlin・-・React | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
健康食品やサプリメントといった機能性食品の研究開発・製造・販売を手がけている会社のECサイト開発に携…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
・最善の措置、開発プロセス、およびコーディング基準の追求 ・よく設計された、信頼性の高い、保守性の…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東松原駅 |
|---|---|
| 役割 | クライアントサイドエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】自…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 自社が携わるサービスのQA業務をご担当いただけ…
週5日
410,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
自社技術を活用した観光アプリ開発におけるUI/UXデザイナーを募集しております。 ※Taskベース…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】社…
人事給与会計関連の社内業務の効率化を目的としたシステム開発の立案から開発・運用をお任せします。 -…
週4日・5日
500,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
ニューノーマル社会の実現に向けたゼロトラストソリューションの実現に向けデバイスログ/認証ログ/アクセ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・SpringBoot・Kotlin | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / UI / 週3日〜】…
融資の申し込みを管理したり、社内稟議を回すなど金融機関や銀行で使用する 社内向けパッケージのデザイ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週4日〜】…
マルチキャリア対応のモバイルソリューションの開発をお願いします。 新しい製品の提案はもちろん、最新…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / PdM / 週4日〜…
子育て中のママパパ様向けアプリ・Webメディア事業のマネジメント全般を担っていただける方を募集いたし…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】理…
理系学生に特化した新卒採用サービスを運営しており、研究領域で事業群を構築していくことを目指しています…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・Play2Framework | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
・当社の戦略をもとに、各サービスごとにチームで開発しています。 ・対応する機能については、エンジニ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Swift / 週5日】大手不動産会社の…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【AndroidJava / 週5日】大手…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週5日】新…
・ストーリーテストや探索的テスト、UATなどのテスト計画/設計/実施 ・開発メンバーとともに企画段…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週4…
スマートフォンアプリやソーシャルアプリ等、様々なデバイスで利用されている最新のアプリケーションをコア…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
新プロダクト開発において、以下のような業務に従事していただきます。 ・機械学習アルゴリズム選定、モ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Typescript | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】不動…
デジタルトランスフォーメーション事業本部の開発基盤グループに所属して以下の業務を担っていただきたいで…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムと自社製AIカメラを連携させたプロダクト開発にお…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・C・C++・- | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
弊社は医師の研究や新薬開発をサポートし、医療の質向上を目指す医療データ解析プラットフォームの開発を行…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
医師の研究をサポートするプロダクトにおけるUI/UXデザイナー募集しております。 ・ペルソナデ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Adobe・XD | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
企業中枢を管理する次世代型経営管理クラウドの開発提供をしております。 弊社は創業当初から全てのコー…
週3日・4日
470,000〜800,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎広小路駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / Android / 週4日…
開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 ・機能開発における設計~実装~リリースまでを一気通貫…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・ReactNative | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
本ポジションでは、当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのiOSアプリ開発を担っていただきま…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・ReactNative | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
本ポジションでは、当社メイン事業であるネットショップ作成サービスのiOSアプリ開発を担っていただきま…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・ReactNative | |
定番
【リモート相談可 / 組込みエンジニア /…
弊社 eMCOS POSIX 製品の開発および検証業務に従事して頂きます。 -3~ 50名程度のチ…
週5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | 組込みエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
自社サービスを利用した開発の推進、事業の企画、立上げにも携わっていただきます。 ・バックエンド…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue・React | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週3日〜…
受託開発案件でのインフラエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
受託開発案件でのQAエンジニア(インフラエンジニア)を募集しております。 開発案件内容の詳細に…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿牛込神楽坂駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| PHP・Java・Laravel・CakePHP・V… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社の下記事業の中での新規事業案件のサービス開発におけるフロントエンド開発をご担当いただきます。 …
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
460,000〜820,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
ゲーム事業部を新設し、自社サービスとしてゲームを開発を行っております。 サーバーの構築やUnity…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原末広町 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
AndroidもしくはPHPのリードエンジニアとしての役割をお任せする予定です。 (ご面談時にご相…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・AndroidJava・Kotlin・And… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・CMS開発 現行のCMSから当社開発のものにリプレースすることを想定しております。 ・業界地図…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
国内ウェアラブルデバイスの開発プロジェクトです。 現在、ベータテストを終了し、リリースに向けて最終…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / WEBデザイナー /…
ライブコマースサービスのデザイン業務をご担当いただきます。 具体的には下記のような業務をお任せ…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週4日〜】ク…
クラウド型オープンイノベーション支援サービスのバックエンド開発をお任せしたいと思います。 ・サ…
週4日・5日
500,000〜960,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot | |
定番
【リモート相談可 / PdM / 週3日〜…
アプリケーション開発担当として、以下の業務をリード頂きます。 ・ プロトタイプアプリをベースとした…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【リモート相談可 / 上流SE / 週3日…
不動産会社の情報システム部門で、 ①不動産仕入部門の業務システムの設計・開発 ②ダッシュボードサ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【リモート相談可 / Swift/Kotl…
新規機能の仕様策定 ・仕様策定:要件に基づきアプリ/サーバーの仕様策定を行います。 ・予算策定:…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
・ペット手帳のウェブアプリケーションの開発、テスト、運用 ・古いコードベースの改善、リファクタリン…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・J… | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
■新規 / 修正実装 ・新規実装:仕様に基づき機能の実装を行っていただきます。 ・修正実装:…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
■新規 / 修正実装 ・新規実装:仕様に基づき機能の実装を行っていただきます。 ・修正実装:…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 埼玉志木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
注目
【C#,JavaScript】システム開発…
自社で開発を行っておりますOMR(光学式マーク読取専用装置)やOCR(光学式文字読取装置)製品の開発…
週5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBエンジニア(C#,JavaScript) |
| JavaScript・C# | |
定番
【Androidエンジニア】家電連携アプリ…
◇案件概要 家電連携アプリの開発案件開発をお願いします ◇勤務地:リモート可 ◇稼働:週5…
週5日
700,000〜820,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸元町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
クラウドファイルストレージをSaaSとして提供している企業様での導入コンサルト業務になります。営業か…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Unity / 週5…
新規スマートフォン向けRPGゲームのクライアントサイドエンジニアとしてゲームアプリ開発を担当していた…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
新規スマートフォン向けRPGゲームのサーバーサイドエンジニアとして開発~リリース、運用をご担当してい…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・自社アプリ事業 ・システム開発およびコンサルティング事業 ・IoT(Internet of …
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合わせから見えてくるバグの特定および修正 ・…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin・C# | |
定番
【PHP / 週5日】ソーシャルゲーム開発…
ソーシャルゲーム開発において、サーバーアプリケーションの設計・実装および高速化・最適化の業務を行って…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【Unit / 週5日】ソーシャルゲーム開…
ソーシャルゲーム開発において、クライアントサイドの新規機能開発・既存機能改修・ゲームリリース作業を行…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C#・Unit・CocosCreator | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
弊社求人事業部の運営するメディアの開発業務をご担当いただきます。 ・コンバージョンの良い案件を…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
新規企業のスターティングメンバ―だからこそ、エンジニアとして培ってきた知識やノウハウを活かし、更なる…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週4日〜】…
自社デジタルチケット管理サービスの開発業務になります。 要件から整理する必要のある部分もございます…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | アーキテクト |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・データプラットフォームの構築 - GCPやAWS、TreasureData、MAツール、WEB…
週3日
350,000〜680,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Java・SQL・R | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって頂けるポジション…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
企業評価をスコアリングするためのサービス開発を行います。 企業ごとのスコアリングの結果を表やグラフ…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
データ基盤開発部 への配属となります。 Web開発の知識や医療システムの知識が豊富なエンジニアが集…
週3日・4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】自社Sa…
下記2つのいずれかの業務に携わっていただけるリードエンジニアの方を募集いたします。 ・ステムの刷新…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・C# | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
弊社が運営する「外壁塗装の窓口」の顧客管理システムの開発、改修をご担当いただける方を募集いたします。…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
Med Tech領域で、皆それぞれにとって価値のあるヘルスケアの実現を通じて、自分らしく生きられる世…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
ニュース記事要約システム、もしくは物流倉庫向け業務可視化システムのフロントエンド部分の開発に携わって…
週4日・5日
570,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】社…
データ分析基盤の構築・運用をおまかせします。 ・各種システムからのBigQueryへのデータパイプ…
週4日・5日
500,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
社内ネットワーク運用・改善を中心に、各種ITサービスやPC・スマートフォンなどの管理、利用サポートに…
週3日
190,000〜360,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日比谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| - | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
-Androidのコアな部分に対する修正。 -Ver.UPに追従し、コアコードの都度修正。 -リ…
週5日
660,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| C・C++・Android・Flamework | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
世界最先端のBlockchainプロジェクトと共同している国内屈指のブロックチェーン技術に特化したソ…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python/C++ / …
このたび、弊社の画像解析アプリを用いて、機器メーカーとPoC(実証)をやることになりました。 その…
週3日・4日・5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
フロントエンジニアとしてtoC向けのオウンドメディアの開発をお任せいたします。 ・自社CMSの開発…
週4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・Next.j… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
AWSアドバンスドコンサルティングパートナー企業として、弊社AWS事業全般に関わって頂けるポジション…
週3日・4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
①フロントエンド 顧客から受けているシステム(動画配信、求人検索、レッスン管理システムなど)のメ…
週3日・4日・5日
280,000〜590,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】インフ…
新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務していただきます。 開発言語はGpで…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / iOS / 週4日〜】スマ…
iOSエンジニアとして、マルチキャリア対応のモバイルソリューションのネイティブアプリケーションの保守…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
今回開発いただくのは、オンラインカウンセラーの方々が自身でのカウンセリングサービスを簡単に開設できる…
週3日・4日・5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸丹波口 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
販売員が使用するモバイルアプリ(ios/Android)と管理者(本社の方)が使用するWEB画面(コ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿/都庁前 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
自社で開発したプロトタイプのアプリをベースに、それをクラウドサービス化するプロジェクトの開発担当エン…
週3日・4日
450,000〜930,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・Python… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
弊社が運営するアルバイト求人メディアのデザイン業務をご担当いただきます。 UIデザイン及びコー…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
Hubspotの構築ができる人を募集!
【案件概要】 Hubspotの構築の実行をして頂きます! 【勤務地】 リモート 【稼…
週3日・4日・5日
330,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | Hubspotの構築業務 |
定番
エンタープライズ向け製品のセールスマネージ…
【業務概要】 今回は会社の営業マネージャー候補として、下記の業務に携わって頂きます。 ・プロ…
週3日・4日・5日
500,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道 |
|---|---|
| 役割 | エンタープライズ向け製品のセールスマネージャー |
| ・ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
ファンの方々への自社コミュニティサイトの立ち上げを行います。 ・自社開発のクラウドファンディン…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
シェアリングサービスのエンジニアとして、インフラ、バックサイド、フロントサイドなど、開発に関わる全て…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
ビジネスメンバー、デザイナーと協力しながら圧倒的なユーザー体験の設計・UI開発・パフォーマンスチュー…
週4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【リモート相談可 / GAS / 週4日〜…
Googleフォームの検証フォロー・品質チェック担当 採用面接、入社手続き、雇用契約書作成、雇…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | テストエンジニア |
| GAS | |
定番
【インフラ / 週5日】BtoC向け既存W…
BtoC向け既存WEBシステムのサーバーリプレースのインフラ作業を依頼します。 ・AWSでの環境構…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週3…
今回、金融系クライアントから受託開発を請け負っている案件ではなく、新規プロダクトとしてスマホアプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| AdobeXD | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
日本最大級のレシピ動画アプリのデザイナーとして、バナーデザインを中心に担当いただくデザイナーの方を募…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・障害発生時の原因調査、不具合対応 ・問い合わせに対する調査、回答 ・改善要望の一連の対応(顧客…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社マ…
自社でマーケティングオートメーションツールの開発を行っており、今回はそのシステムのインフラ部分の設計…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
現在対応をしているフロントエンジニアが退縮することとなり、後任のエンジニアを探しております。 メイ…
週4日・5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Angular / 週4日…
・EmotionTech CX / EX の管理画面の新規開発、改修、運用・保守 ・E2Eテストの…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】アジャ…
1) セキュリティ・監視・運用設計 2) リリースフローの運用 3) インフラの構築・保守・監視…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現在様々な企業と協業し、サービス拡大していく中で必要となる機能の開発からサービスの運用を担当します。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python | |
定番
【フルリモ / DB / 週4日〜】インフ…
新規kubernetes基板構築に伴うインフラ構築/支援業務していただきます。 基盤担当者と共…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】H…
UIデザイン及びコーディングに関連する実務、プロダクトマネージャーやエンジニアとの協働が主な業務とな…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
-弊社製 FAT/exFAT ファイルシステム製品の機能拡張/改修 -他社製Linux互換ファイル…
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【Python / 週5日】大規模医療デー…
医療データを100を超える医療施設から収集を行っています。動画データが従来より高品質なフォーマットで…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Ansible | |
定番
【Python / 週5日】動画編集デスク…
医療データの動画を効率的に管理するために、新しく動画編集機能及びアノテーションを行うデスクトップアプ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python | |
定番
自社開発のWebディレクター兼PdM
【業務内容】 事業拡大のため、デジタルマーケター(兼PdM)を募集致します。 介護職専門のマッチ…
週3日・4日・5日
470,000〜570,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中野坂上 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター兼PdM |
| Linux(CentOS)、Apache、MySQL… | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週3日〜】…
弊社サービス(SaaS)のマーケティングにおけるデザイナー業務をご担当いただきます。 ・サイト…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Il… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】仮…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
・ECサイト構築・運用におけるHTML/CSSコーディング ・PC/SP版、またはレスポンシ…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
海外向けのECサービス、もしくは新規サービスのユーザー向けWebサービスの設計・開発、進行管理をご担…
週5日
500,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・日本商品の海外向けインターネット通販サイトの運用を支える基盤システムの運用と管理をご担当いただきま…
週5日
350,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】専門…
プロダクトのアーキテクトとして、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの開発の推進を担っていただ…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・- | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
自社サービスのサーバーサイド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定買取と販売を主…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社商…
・当社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・当社グループにおける新…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
・障害発生時の原因調査、不具合対応 ・問い合わせに対する調査、回答 ・改善要望の一連の対応(顧客…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅(徒歩6分)/新宿駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・PHP・SQL・Laravel… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
自社サービスAzure開発のエンジニアリングマネージャーをお任せします。 当社は、ブランド品や骨董…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Azure | |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】自社事…
開発・分析業務の補佐していただきます。 - マスタデータ整備 - SQLを利用したデータ抽出…
週5日
570,000〜1,240,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
| SQL | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
新規プロジェクト開始に伴い、下記内容に参画頂けるエンジニアを募集いたします。 ・顧客製品の製品…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
新規プロジェクト開始に伴い、下記内容に参画頂けるエンジニアを募集いたします。 ・顧客製品の製品…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄旭橋駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・React.j… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・5~6年前にリリースした基幹システムおよび公開サイトの共通部品のメンテナンスおよびアーキテクト支援…
週5日
660,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台、新宿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・React・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 プロジェクト…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
新規プロダクトとしてスマホアプリの新規サービスを検討しております。 新規PJのため一種に考えて開発…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・航空券予約販売サイトのフロントエンド開発業務全般 ・新規サービスの開発、およびAPI設計 ・既…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
AWS ECS上にDjangoRestFrameworkを用いてAPI開発をする作業になります。 …
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
・概要:5Gを活用したフラッグシップサービスの開発 ※フラッグシップサービスとは、自由視点映像やx…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・-・Three.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】航…
大手Web系企業(旅行サービス)にてさらにサービス向上に向けて、当社サイトのプロジェクトを指揮してい…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
更なる事業拡大に伴い、新メンバーを募集することになりました。 ・航空券予約販売サイトのバックエ…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・CakePHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
更なる事業拡大に伴い、新メンバーを募集することになりました。 航空券予約サイトのサーバ周りの強…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
様々な分野・産業に対し戦略、業務、ITなどのあらゆるコンサルティングを 行ってらっしゃる企業様の情…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Typescript / …
弊社のグローバル展開予定の自社サービスにてTypescriptのご経験のあるエンジニアを募集致します…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・angular・Node.js… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】新事…
新規事業のペット保険サービスにかかわるシステム開発のPM職を募集します。 PHPを用いて新規機…
週4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・CakePHP | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週4…
経営陣やビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/UXデザインや…
週4日・5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週4…
ビジネスサイドのメンバーやエンジニアたちと連携しながら、各種プロダクトのUI/UXデザインやコーディ…
週4日・5日
370,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】住宅…
オンライン完結で提供する自社住宅ローンサービスのバックエンド開発におけるリードエンジニアをご担当いた…
週4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
自社の経営チームに置ける技術サイドの責任を担い、開発組織の立ち上げをリードするCTOを担っていただけ…
週5日
610,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
オンライン学習システムの開発・改善に携わっていただけるフロントエンドエンジニアの方を募集いたします。…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Rubyonrai… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
Webサイト開発、改修のフロントエンドエンジニア業務を依頼します。 ・実装、レビュー、検証、リリー…
週5日
350,000〜530,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
顧客からシステム開発の発注を受け、WEBデザイナーとしてフロントエンドでの開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
AWSで構築しているパーソナル情報信託システムの2次開発。 既存のシステムに新たな機能を追加。 …
週5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】大…
バックエンドエンジニアとして、自社副業マッチングサービスにおけるバックエンド開発/保守を行っていただ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社副業マッチングサービス「JOINS」におけるフロントエンドの開発を行っていただけるエンジニアの方…
週3日・4日・5日
570,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社は独自の画像解析・AI技術により、製造業における検査・検品の自動化をサポートするスタートアップで…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Flask・Django | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発での募集となります。 人材派遣会社にて就業中(又は求職中)の…
週5日
570,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】人…
アプリ開発における要件定義担当者としてのご依頼になります。 ・事業部担当者と新システムに向けた要件…
週5日
5,910,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】自…
今回弊社事業をさらに推進したいと考えており、その為のUIデザインとフロント周りを対応できる方を探して…
週3日
290,000〜680,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・illust… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】プログラ…
サーバーサイドエンジニアとして自社サービスのサーバーサイド開発、各種API開発やインフラ設計・構築、…
週5日
660,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】急成長…
・ サービス全体に関する意思決定 ・ 戦略立案と開発計画ロードマップの作成 ・ 全体の施策管理マ…
週3日・4日・5日
660,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社商品…
・当社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・当社グループにおける新…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
基本的に、PMの指示の下、作業を行って頂く形となります。 ただし、具体的な指示ではなく、要求整理を…
週5日
570,000〜800,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・ReactJS… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
弊社クライアントの受託開発案件にご参画いただきます。 生保業界向けネイティブアプリ開発となります。…
週5日
410,000〜780,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】高校生向…
プロダクトマネージャーとして ・プログラミング学習教材の企画・制作・ディレクション ・教材で必要…
週5日
260,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / 組み込み / 週5日…
・「Media Foundation APIでアプリ等からカメラデバイスとしてアクセスできるドライバ…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
役割:クラウドネィティブシステムの 維持、改善サポート ・マルチクラウドから AWSへの移行(一…
週5日
570,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Rust / 週3日〜】ク…
・EmotionTech CX / EX のマイクロサービス化、既存システムの改良 ・Web AP…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Scala・Go | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、WebアプリケーションインフラおよびWindowsサーバーの監視…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Androidエンジニア】家電連携アプリ…
◇案件概要 家電連携アプリの開発案件開発をお願いします ◇勤務地:リモート可 ◇稼働:週5…
週5日
700,000〜820,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸元町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ヘ…
業務提携先のパートナー企業と協業しながら、歩数計アプリサービスのプロジェクトマネージャーとしてサービ…
週5日
570,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】MEO支…
自社SaaSサービスの新規プロダクトPMとしてご参画いただきます。 ベースは自社開発のストアマーケ…
週3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
社内SEとして既存システムの改修や機能追加、または新規のシステム開発を行います。 ・社内イントラネ…
週3日・4日・5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトで開発チームのエンジニアをご担当頂きます。 PM・PLと…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
・Webフロントエンドの実装(主にReact + Reduxの構成) ・3Dアルゴリズムシステムと…
週5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】Webプ…
今回は自社のWebプロダクトの企画、要件定義や開発プロジェクトのディレクション業務に携わっていただけ…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】基幹…
経営サポートシステムリニューアルに際して、基幹システムのリプレイスのご依頼となります。 ・要件…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP・SQL・ReactJS… | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週4日…
自社サービスアプリのWeb版フロントエンド開発をお任せします。 当社は、ブランド品や骨董品等の査定…
週4日・5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・Dart・Flutter | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・- | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【PHP / 週4日〜】自社サービスにおけ…
今回、各事業部よりリソース不足の声を受けてエンジニアの増員を検討しております。 既存のシステムに対…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Zend | |
定番
【リモート相談可 / テスター / 週5日…
弊社が運営するヘルステックサービスにおいての大規模テストにおけるアプリテスト業務をご担当いただきます…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【フルリモ / Linux / 週4日〜】…
自社サービス基盤としてのシステムインフラの継続的な構築/運用を主として担って頂くポジションです。 …
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PHP・Java・Linux・LAMP | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グループにおける新…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue.js | |
定番
【C/C++ / 週4日〜】家庭用ゲーム機…
ゲーム会社の事業拡大に伴う、ゲーム開発プログラマの募集をいたします。 具体的には、コンシューマ…
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C・C++ | |
定番
【3DCG / 週4日〜】家庭用ゲーム機の…
ゲーム会社の事業拡大に伴う、3DCGデザイナーを募集をいたします。 コンシューマ向けゲーム開発全般…
週4日・5日
460,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】LA…
作業内容としてはCMS(内容管理システム)の開発です。 ※詳細に関しましてはご面談にてお話させてい…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿野並駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】自…
自社で展開しているSREサービスに従事する、クラウドエンジニアを募集しております。 サービス提…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・Go・GCP・AWS・Azure・Do… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】プロ…
・ボディメイク事業における新規プロダクト/サービス企画およびプロダクトマネジメント ・新規プロダク…
週4日・5日
570,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / Swift/Kotlin …
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】オンライ…
・システムの開発ディレクション ・スケジュール管理 ・要件ヒアリング ・要件・非機能要件定義、…
週5日
480,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】オン…
医療領域のドメインスペシャリストなどのメンバーとともに患者・医療従事者に向けたサービスの情報設計およ…
週4日・5日
480,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週4日・5日
300,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
当社は暗号通貨取引所の開発を始めとして、ブロックチェーントークンの制作、 チャートツール開発に携わ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
新規プロダクト開発チームへのアサインとなります。 ・新規プロダクトの初期立ち上げに伴う技術調査・検…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・Vue.js・Node.js | |
定番
【フルリモ / Laravel / 週4日…
自社で開発しているリアルな顧客コミュニケーションとオンラインを繋げる営業活動サポートツールの開発に携…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 埼玉川口元郷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
機器の状態を可視化、機器の設定を行うWEBサイトにおいて、グラフやテーブル・の描画、フォームの描画と…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・React・Node.js・n… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】新の人工…
Deep Learningを使った最先端システムの開発や強化学習を使ったロボット動作最適化学習などに…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄井尻駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby・Java・Swift・Kotlin… | |
定番
【C/C++ / 週5日】ロボティクス関連…
3D自律移動ロボット(ドローン)のSW開発・品質向上・保守を行って頂きます。 -三次元空間を移動す…
週5日
660,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
今後は、開発ラインを増やし、カジュアルゲーム開発も並行して展開するほか、コンシューマーゲームの開発も…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京末広町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・₋- | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
弊社デザイン部署にてWebコーダーとして、PV数の高いサイトを責任もってご担当いただける方を募集いた…
週5日
220,000〜510,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
大手通信系企業様から学校法人・福祉など様々な業界から受託開発を行っております。 当社ではWEBサー…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
大手通信系企業様から学校法人・福祉など様々な業界から受託開発を行っております。 今回当社ではWEB…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸長堀橋 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
バックエンドエンジニアとして、チャットボットを構築/運用するWebアプリケーションを中心に機能拡張を…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
医療用自社プロダクトのサーバーサイドの開発業務に携わっていただけるサーバーサイドエンジニアの方を1名…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・SQL | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】社内…
医療機関のお客様からいただいたデータを分析する際に、社内で可視化して区別できるよう、社内で保管するた…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Tableau・AWS | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
-クラウドサービス(マルチカメラライブ)向けの設計・実装・評価を行っていただきます。 -複数台のカ…
週5日
660,000〜990,000円/月
| 場所 | 神奈川新高島駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / PdM / 週3日〜】自社…
・各プロダクトの戦略立案と浸透業務 ・KGI・KPIマネジメント ・全体の施策管理マネジメント …
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
UI/UXデザイナーとしてiOS向け音声アプリのデザイン、世界観を受け継ぎながら、今後の機能アップデ…
週3日・4日・5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【PHPエンジニア】在庫管理システムの機能…
【業務内容】 在庫管理システムを運営しています。機能の開発ができる人材を募集します! 設計は不要…
週3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 千葉巌根駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・MySQL | |
マーケター(MOps|アプリPUSHの配信…
【企業】 某通信会社グループのアセットを活かし、お客さま・出店店舗さま増加によるECマーケットのさ…
週2日・3日
140,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(MOps・アプリPUSHの配信設定) |
| SQL・・SQLの実務経験 ・ECサイトをよく利用… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
iOS向け音声アプリの開発に関わっていただきます。 (順次Andoroidブラウザアプリもリリース…
週3日・4日・5日
390,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】Ama…
ショッピングサイト運営を自動化するネット販売システムを開発・運営しており、企業や個人のお客様にショッ…
週4日・5日
740,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・AmazonMWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】建設・…
建設現場調査・情報共有アプリケーションを開発しており、今回はLaravelエンジニアを募集いたします…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Slack・Jira | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
弊社サービス(SaaS)のフロント部分のコーディングや付随するLPやサイトのコーディングをご担当いた…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
・プロジェクトマネジメント関連作業 ・PMの管理業務サポート/情報サービス会社向けのBPR推進プロ…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
ライター(WEB広告記事)
◆業務内容 WEB 広告記事(いわゆる記事LP)のライティング ◆募集背景 業務拡大におけ…
週1日
40,000〜130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | ライター(WEB広告記事) |
| ・記事LP・ライティング経験者 ・ポートフォリオの… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】家具の…
自社サービスの家具の会員制シェアマーケットを成長させるための機能追加、改善案の企画・実施、業務システ…
週3日・4日・5日
330,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・Java・Apache・Tomca… | |
定番
Microsoft製品の技術支援
Microsoft社の新製品を使用した業務ユーザによるアプリケーション開発環境において、システム開発…
週5日
880,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Microsoft製品の技術支援 |
定番
SAPの運用・保守
ERPシステム(SAP(会計))の運用チームリーダーとしてのアサインを想定しています。 ロケーション…
週5日
880,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | SAPの運用・保守 |
定番
【データアナリスト】Adjust SDKの…
【お任せしたいこと】 新規事業開発部で立ち上げている越境EC事業のプロジェクトマネージャー(業務委…
週2日・3日
350,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・Typescript・Flutter・… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
自社CtoCサービスにおいて今後サービスをグロースしていく上で、開発全般をお任せできるテックリードを…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
AIアルゴリズム/Webサービス/MLopsシステムとミルキューブ(自社製AIカメラ)を連携させたプ…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
弊社が運営するBtoB向けのIT製品の比較サイトのフロントエンド開発をご担当いただきます。 現…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【Linux / 週5日】為替システム更改…
御社は1973年に設立されたIT業界における老舗企業です。 ・アプリケーション開発 ・インフラソ…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Linux | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
システム運用業務の効率化を検討する企業へ、自社プロダクトの提案から要件定義・設計を行い、自動化プロジ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Vue | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
主に中高生向けの学習塾紹介メディアを自社で運営しております。 今回は上記メディアのサーバサイド…
週4日・5日
410,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】子育て…
今回は子育て支援サービスに関するアプリのAPI周りの開発に携わっていただけるエンジニアの方を募集いた…
週4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では企業のデジタルマーケティングを支援していくために自社運営メディアを用いて企業の課題を解決して…
週5日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手通…
大手通信会社のユーザ向けスマホアプリ開発における、要求部門からの個別案件に対して、受付から要件定義、…
週5日
660,000〜790,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
・Flutterを用いたアプリ開発 Flutterを用いたアプリ開発のプロジェクトがあり、Fl…
週3日・4日・5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大駅前 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】De…
多様なシステムのインフラ設計・開発・運用をお願い致します。 ・安定稼働を実現するためのサービス…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿駒場東大前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】ボディ…
オフショア開発に伴うPM/ブリッジエンジニアとして活動出来る方を募集しております。 ・要件定義…
週4日・5日
570,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】自社サービス開発におけ…
・コンシェルジュプラットフォームの構想を企画・仕様設計・プロダクト構築・運用までお任せします。 ・…
週5日
330,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・TypeScri… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】自社運…
EMとしてプロジェクトのマネジメントをお願いします。 リフォーム産業のデジタル化で、安心できる暮ら…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・CakePHP・Ang… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】EC…
多くのECスタートアップに利用されているRuby on Rails製のオープンソースECパッケージを…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyOnRails・‐ | |
定番
【Javascript / 週5日】自社サ…
自社サービス開発全般(主にフロントエンド開発)業務を依頼します。 ・クライアントが利用する提供機能…
週5日
330,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Go・Nuxt.js(Vue.… | |
定番
【PHP / 週5日】自社サービス開発にお…
自社サービス開発全般(主にバックエンド開発)業務を依頼します。 ・クライアントが利用する提供機能の…
週5日
330,000〜990,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・Go・C・… | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】経済メ…
弊社アプリのUIデザイン情報設計・経験により以下業務を担当して頂きます。 - プロダクト/サー…
週4日・5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
B2B領域で、AIプロダクトのUIUXデザインを行っていただきます。 具体的には、 - ワイヤー…
週4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるモニターアライアンス基盤とクライアントのサービスが連携した共同事業のシステム開発に…
週5日
330,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御成門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・PhalconPHP | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
現状、自社で運営する多数のメディアのアクセス増に向け、クラウドインフラ基盤の品質向上をできる方を求め…
週4日・5日
2.4〜5.5万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
弊社が開発しているAIソフトウェアにおけるPMO業務をご担当いただきます。 ・スケジュール管理(W…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| ‐ | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ワ…
現在、プロダクトの企画開発を加速すべく、プロダクトマネージャーの外部要員を募集しております。 …
週5日
830,000〜1,770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手出版社のサブスクリプションモデルを導入した新規ビジネスで対象となるWebコンテンツ開発、もしくは…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Vue… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
人々の創造力やデザイン思考力を定量化するシステムを開発している企業様で今回はその自社新規システムに関…
週5日
570,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
表面上のUIをデザインするだけではなく、社内のPMと一緒に企画立案から携わり、プロジェクトメンバーと…
週4日・5日
410,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイン |
| HTML・CSS・SQL・AWS・GitHub | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
主にページパフォーマンス改善や、UI/UXの改善。また直近でJamstackでの開発を進めており、そ…
週4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React・… | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週3日…
現状、社内のセキュリティインフラの構築段階でして、今回はセキュリティインフラの立案、設計、実装を担っ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週5…
大手企業のブランドサイトやプロモーションコンテンツを中心としたWebサイト開発のデザイン業務全般をお…
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】新規金…
自社金融サービスのサーバーサイド開発業務をお願いいします。バックエンド、フロントエンド、インフラなど…
週4日・5日
740,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】Fi…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Perl | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】Fi…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】Fin…
決済とマーケティングの融合を目指し、CRMマーケティングを通じてFintechに関するソリューション…
週4日・5日
610,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
RPAなどを用いてECサイト運用にあたる各種業務の自動化、商品ページ自動生成する仕組みを作れるエンジ…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・- | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
・DX(デジタル化)推進人材のスキル可視化 / オンライン教育を行うシステムの開発 ・フロントエン…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / ReactNative /…
・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) ・更なるサービス拡大…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / C# / 週4日〜】次世代…
エンジニアとしての経験を活かし、次世代CADの要件と仕様の理解を行い、チーム開発を牽引します。 …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】オンラ…
サービス/プロダクト概要としてコンセプトの「治療支援ツール」になります。 患者の治療継続を支援し、医…
週3日・4日・5日
740,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript・- | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・アルゴリズム開発 ・アーキテクチャ設計 ・プロトタイピング、具体的な機能開発 経験に応じて …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / C/C++ / 週3日〜】…
・アーキテクチャ設計 ・プロトタイピング、具体的な機能開発 経験に応じて ・コードレビュー、ク…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】大手建…
上流工程だけでなく設計や開発、状況によっては運用まで関与できるのでプロジェクトに関係するシステムの全…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| C・C++・C#・VB.NET・SQL・Batch・… | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週5…
要件定義から機能仕様作成でドキュメンテーションがメインです。 もし可能であればユーザビリティのお手…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| C・C++・Shell・Script | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】ク…
現在、案件の規模が大型化してきている状況を受け、エンジニア組織を増員・強化中です。 当社の優秀…
週3日・4日・5日
410,000〜910,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】E…
想定プロジェクトB、プロジェクトC ・両案件ともクライアントは同一で、とある大手ECサイト運営会社…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【リモート相談可 / illustrato…
自社のコーポレートサイト並びに、ECサイトのリニューアルを計画しており、専任でデザイン業務をしていた…
週3日・4日・5日
160,000〜370,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・illust… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
WEBデザイナー|(SaaS等のBtoB無…
【業務内容】 ・自社で開発したツールのマーケティング活動に伴うバナー等のクリエイティブ制作 →…
週3日・4日・5日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸淀屋橋 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー|(SaaS等のBtoB無形商材のバナー制作・SNSマーケティング支援) |
| ・BtoBのバナー制作経験(LPでも検討可) ・短… | |
定番
【動画制作】住宅設備製品に関する動画制作
【業務内容】 取引先や工事業者向けの製品に関する教育向けの動画を制作していただきます。 その他社…
週2日
130,000〜160,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋 |
|---|---|
| 役割 | 動画制作クリエイター |
定番
【リードエンジニア(新規案件)】新規案件の…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | リードエンジニア(新規案件) |
| PHP | |
定番
【PM|一部リモート可】国内外におけるテク…
【業務内容】 国内外におけるTechnology project推進を担当していただきます・ G…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(サポートデスク) |
【PHP開発案件|常駐必須】EV急速充電器…
【案件内容】 EV急速充電器システムサーバ開発案件に携わっていただきます。 ・主に下記作業をご担…
週5日
670,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木江坂駅(大阪) |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / Chatbot / 週4日…
Chatbot, チャットフレームワークを利用したWebアプリケーションの開発を遂行していただきます…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Java・Go・… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
社内のデザイン業務に関して、モック作成など上流の部分から業務をご依頼いたします。 デザインのみをお…
週5日
160,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| illustrator・Photoshop・Adob… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
東証一部のガス会社から直請けの案件(業務システムの開発DX推進)に携わっていただきます。 5名チー…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・Gut・Docker | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手総合…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週5日
610,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手総…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Python・Go | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
Google Cloudに特化した技術者集団として、お客様にコンサルティングからシステム開発、運用・…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【フロントエンドエンジニア】介護支援サービ…
【仕事についての詳細】 当社グループでは、「Supporting Doctors, Helping…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週5…
グラフィックに特化した新規ゲーム事業におけるUI/UXデザイナーの業務を依頼します。 ・画面遷…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / UIUX / 週5日…
運用中開発タイトルにおける下記業務をご担当していただきます。 ・画面遷移制作 ・画面レイアウト制…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
| ₋-・₋- | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
セールスやカスタマーサクセスの業務効率改善のため、システムの要件定義や設計をご担当いただきます。 …
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| JavaScript・‐ | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナー/サーバーサイ…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・₋- | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・自社サービスの全面リニューアル ・HP構築・新規システム設計・構築 ・デザイナー/サーバーサイ…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新木場駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・₋- | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
・既存機能のリファクタリング及びチューニング ・Flask + ECS + Auroraを利用した…
週5日
520,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿お茶の水駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・Ruby・Flask・Django | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】社内シ…
・社内の簡易ツールシステムの開発を行っていただきます。 ・言語選定も自由です ・一部HPの変更な…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Java・₋- | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】新規…
リリースしたばかりのiOSアプリのインフラ部分を担っていただくインフラエンジニアを募集しております。…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】テ…
AIを用いたソフトウェアのテスト自動化プラットフォームを自社開発・提供しています。 今回は、機…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS …
地方の車社会のユーザーに対して月定額でマイカーを利用できるサブスクリプション型サービスを提供していま…
週3日・4日・5日
330,000〜530,000円/月
| 場所 | 品川五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
スポーツビジネスの活性化は上記の課題の多くを解決出来る可能性を秘めています。 我々はテクノロジーを…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社プロダクトをPHPのLaravelで開発しております。今回は社内ツールの作成や、自社メディアの保…
週5日
160,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・- ・ | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
本案件はエンタープライズ向けのウェブシステムを構築するプロジェクトにおける、基盤環境を構築するエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・React・Dj… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週4日…
・当社が提供する決済システム&サービスの要件定義~設計~開発~テスト~商用リリースおよび運用~サポー…
週4日・5日
480,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】某交通…
作業:該当システムに関する、 ・連絡窓口の設置、保守対応性の維持 ・調査及び確認作業、技術的な問…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
スポーツビジネスの活性化は上記の課題の多くを解決出来る可能性を秘めています。 我々はテクノロジーを…
週4日・5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿国分寺駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Nuxt・V… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】Web…
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ・Go言語によるWeb…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
最先端の映像技術を開発するテクノロジー系ベンチャーでのお仕事となります。 - 視聴者がインタラ…
週4日・5日
670,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川不動前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin | |
定番
【フルリモ / テスター / 週5日】自社…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトにおきまして、SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【フルリモ / AI / 週5日】自社グル…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
自社開発しておりますデータ活用Paasのアプリケーションからインフラレイヤーまで、様々な開発・改善を…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】ス…
新規事業として、スマホアプリのブロックチェーンゲーム開発を予定しており、立ち上げからご参画いただける…
週5日
250,000〜680,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。将来を見通したマイクロサービスアーキテク…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。将来を見通したマイクロサービスアーキテク…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社プロ…
弊社のいずれかのプロダクトにおけるプロジェクトマネージャー(PM)として以下の業務をお任せします。 …
週5日
390,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
自社プロダクト(HR領域)開発全般をご担当いただきます。 ・機能拡張/改善の設計、実装、効果検証 …
週5日
390,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / ABAP / 週5日】検索…
SAP ABAPを使用して検索アルゴリズム・検索システムの開発を遂行していただきます。 チャットフ…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | ABAPエンジニア |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
・新規開発する法人企業向けのSaasプロダクト開発 ・要件定義と基本設計 ・テックリードエンジニ…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務システムの開発を…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・₋- | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】仮…
自社で仮想通貨に関するアプリの新規開発を行っており、今回はそのプロジェクトにおけるプロダクトマネージ…
週5日
740,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM/ 週3日〜】自社プロダクトのPM
弊社プロダクトにおけるプロジェクトマネージャー(PM)としてプロダクトの方向性の決定に深く関わりなが…
週3日・4日・5日
410,000〜610,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
事業承継コンサルティング株式会社は、資産運用・相続・事業承継を専門とするコンサル会社です。 フ…
週3日・4日
330,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京茅場町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ph… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
自社で仮想通貨に関するアプリの新規開発を行っており、今回はそのプロジェクトにおけるプロダクトマネージ…
週3日・4日・5日
740,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
AI技術を用いて法律業務の効率化や法務経営の実現を目的とするリーガルテックサービスを開発しています。…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js・Angular.… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】オン…
React/Reduxを用いたフロントエンド開発 1週間単位のイレレーション開発で、 アサインされ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
DSLでの処理記述や内部でPythonライブラリ使用するためPython記述の対応をお願いします。 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Kotlin/Swift …
弊社の複数プロダクトのAndroidアプリ、iOSアプリ開発を担当いただきます。 Androidア…
週5日
570,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Scala・Swift・AndroidJa… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】転職/…
具体的な業務内容は自社で運営している人材紹介サービスの運用設計、運用、保守、監視。 ほかにも要件定…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】動…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週4日・5日
2.8〜3.4万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿、初台 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・React・Node.js・Apache・… | |
定番
【Java / 週5日】AIスタートアップ…
クライアントより依頼をいただいているECサイトのシステム移行プロジェクトにおいて、移行チームメンバー…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・VBA | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
以下の業務をお任せいたします。 ・テストデバッグ:弊社で運用しているテストデバッグ表に基づきWeb…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋今池駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアアを開発します。 一般ユーザーと広告主をマッチングさせる…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・Illustrator・Sketch | |
定番
【フルリモ / SQL / 週4日〜】クラ…
クライアントが持つ多種多様かつ⼤規模なログデータを活⽤し、データ分析・活用を支える業務をお任せします…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・R | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週4日…
ブラウザ拡張機能を活用したポイントメディアを開発します。 主な機能 ①一般ユーザー向け:登…
週4日・5日
330,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| SQL・Node.js・React | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 エンジニアリングで社会…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 新たに手掛ける決済・金…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
自社サービス(飲食店向けシステム)のUI/UX改善業務 ・自社アプリ、HPのUI/UX改善→提案 …
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery | |
定番
【リモート相談可 / Kotlin / 週…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状況を…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
旅行系ToC新規サービスの開発業務です。 iOSスマートフォンアプリの開発の設計と実装をお願いしま…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
美容業界の求職者向け求人ページ作成システムのリニューアル案件です。 リニューアルに伴い求職者・雇用…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
自社サービスであるクレジットカードや電子マネーの支出を一括管理するモバイルアプリ、キャッシュレス決済…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / TypeScipt / 週…
臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポートするサービスです…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go・Typescript | |
定番
【PM/フルリモート】AIによる契約書レビ…
製品開発のプロジェクトマネージャーとして、以下の使命を果たしていただきます。 - LegalTec…
週4日・5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| AWS・・・GCP | |
定番
【Java|フルリモート】次世代物流プラッ…
◇業務内容: 物流業界における、荷主と倉庫を繋げる為のプラットフォーム(nest)の開発です。…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot、SpringBatc… | |
Webディレクター(SEO分析・レポート・…
【企業】 某通信会社グループで法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープ…
週3日
250,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター(SEO分析・レポート・施策立案) |
| ・下記のツールを利用して、結果からレポーティングでき… | |
定番
【Go言語】高トラフィック環境、独自データ…
【事業内容】 店舗スタッフによるコーディネートなどのコンテンツを通じてEC売上や貢献を可視化するテ…
週5日
750,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | 【Go言語】高トラフィック環境、独自データを駆使して小売業DXを推進するエンジニア募集 |
| PHP・Python・Ruby・Java・Go・Re… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日】自社サー…
英語の勉強をもっと楽しく新しい体験をしていただくためにCD教材をサービスとして展開してきました。 …
週3日・4日・5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
基幹システムの詳細設計~リリースまでの開発案件です。 リゾートウェディングで披露宴から引出物などの…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキを…
週5日
500,000〜1,250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React・Node.js・JavaSpr… | |
定番
【SQL / 週5日】Citrix Vir…
AWS東京上にCitrix Virtual Apps and Desktops環境があり、BCP環境…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
従業員のES向上を目的としたWEBサービス(iOS/アンドロイド向けのアプリではない)の構築 ※P…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】Ok…
※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 弊社のクライアント企業である某鉄鋼メーカー様にて認証基盤の…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 神奈川鶴見駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Swift / 週3…
当社の基盤事業である医師専用コミュニティサイトを、より医師の診療に無くてはならないサービスとするため…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
受託や自社開発における様々なWebサイト制作、アプリケーション開発プロジェクトに参加いただけるエンジ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
自社にてクラウド型の人材管理ツールを開発、販売を行っております。 今回は下記業務に携わっていただけ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【リモート相談可 / React / 週4…
新規プロダクトのフロントエンドエンジニアとしてプロダクト開発に携わっていただきます。 具体的にはプ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React.… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】テレビ視…
テレビ視聴データをBI提供するレアSaaS開発において、主に開発チームのPMを募集します。 テ…
週5日
920,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Typescript・Vue | |
定番
【フルリモ / 3D / 週3日〜】VRの…
VRのミニゲームを制作しており、開発を手伝ってくださる方を募集しております。 小物や背景を含めた、…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外保谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】フリ…
フリーランスプラットフォームのシステム設計・開発・運用の中で、マーケと連携しSEO関連の開発対応をご…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】カウ…
この度はプラットフォームのリプレイスに向けてエンジニアを募集いたします。 ・React(Next.…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】決裁シ…
下記の業務がメインになります。 ・決済(クレカ等)システムサーバー構築 ・決済画面フロントエンド…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】ドキュ…
・対カスタマーのドキュメント(要件定義、MTGアジェンダ等)作成 ・対エンジニアのドキュメント作成…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Swift・AndroidJava | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】家事…
家事代行クラウドソーシングサービスにおける、サーバーサイドとフロントエンドの開発をご担当いただきます…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】動…
自社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当していただきます。 …
週4日・5日
580,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Ember.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】急成…
・マッチングサービスなどのシステムの設計・開発・テスト(アジャイル開発方式) ・更なるサービス拡大…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】自社…
自社プロダクト(HR領域)開発全般をご担当いただきます。 ・機能拡張/改善の設計、実装、効果検証 …
週5日
390,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Scala・Kotlin・Go・Types… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
臨床開発デジタルソリューション事業は、製薬企業向けに、臨床試験や新薬の治験をサポートするサービスです…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / iOS/Androi…
ウェブサイトや証券取引アプリ(iOS/Android)の顧客体験向上・顧客満足度向上を図る、CXディ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Adobe・Photoshop・Illustrato… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】人…
自社新規サービスのプロダクトマネージャー業務をお任せします。 ・新規サービスの全体像の設計(おおま…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| Jira・Figma・Notion | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】超有…
・超有名美容系予約サイトの改修・機能追加に携わって頂きます。 ・要件定義~から関わって頂きたく、基…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / sharepoint/Ex…
①Sharepointの移行:notesまたはオンプレミスのsharepointから、移行ツールを使…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿不明駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| sharepoint・Exchange | |
定番
【フルリモ / デザイナー / 週4日〜】…
クリエイティブ・ディレクター、デザイナーとして、新規チャット広告事業における、クリエイティブ作成、そ…
週4日・5日
330,000〜800,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
大手通信会社がビジュアルコミュニケーションをアップデートする、インハウスのブランドクリエティブチーム…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
- 成長戦略を踏まえたKPI設計 - サービス運営で定常的に発生する分析企画と工数分析 - KP…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・- | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・払戻業務負荷軽減のための対応⇒払戻情報表示サイトの刷新、払戻受付webサイトの新規構築など ・問…
週5日
480,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・shell・teraterm・sq… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
当社が提供するサービスのソフトウェア開発のポジションです。 本募集においては主にフロントエンド開発…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
今回は既存サービスに関連した新規事業を成功させていくために、システムの根幹を担うサーバーサイドエンジ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【リモート相談可 / Kotolin / …
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
・ゲームのサーバ側APIの設計と実装 ・基盤ライブラリ、フレームワークの調査、利用、拡張 ・開発…
週5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
現在自社が展開するオンラインカウンセリングサービスををより使いやすくするための機能開発や、新しいプラ…
週3日・4日・5日
480,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
ある程度ある型にあわせて、週1本程度デザインや、バナーなどを対応いただくと共に、デザインチェック、多…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ₋- | |
定番
【フルリモ / PdM / 週3日〜】クラ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
自社HP制作や課金コンテンツの発信やライブ配信などの運営を行うサービスのフロントエンド開発業務。 …
週3日
290,000〜520,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神泉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
※詳細は面談時にお伝えさせて頂きます。 PaloAltoのPrismaAccessを多数導入してい…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【SREエンジニア】プロダクトの可用性を高…
【お任せしたいこと】 オルツでは AI SaaS サービス、議事録作成システム『AIGIJIROK…
週3日・4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Python・Typescript・Flutter・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】ドラッグ…
現在のECサイトのAP保守開発リーダーとしてドラッグストア様やベンダーとの調整、業務推進を行っていた…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】Goo…
・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基盤の構築 ・第…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グループにおける新…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【PM / 週5日】大手自動車会社でICT…
大手自動車会社に常駐していただきます。 ・ベンダーコントロール ・クライアントへのプレゼン ・…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】リユ…
AWSをベースにした商用インフラの新規構築/新サービス追加/業務改善を行って頂きます。 AWSに精…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
弊社が運営するSaaSプロダクトのWEBフロントエンド(SPA)の開発全般を担当していただきます。 …
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
弊社が運営するプロダクト(SaaS or ニュースアプリ)のサーバーサイド開発全般を担当していただき…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・Django・Flask | |
定番
【フルリモ / 3DCG / 週3日〜】T…
弊社請け負ったCM制作やプロモーション映像の制作の担当をお願い致します。 TV番組やCM用の制作を…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿四ツ谷 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| AfterEffects・Unity・Unreal・… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】公共…
弊社サービスの根幹を支えるクラウドインフラの設計支援を行って頂けるインフラエンジニアの方を募集します…
週3日・4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
Web体験全般におけるプロダクトのブランドイメージに沿ったコミュニケーション設計、実装をしていただき…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・‐ | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】ロボテ…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署と連携してプロダクトのUIデザインをご…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
機械学習のための学習データ(画像)の検索、表示、選択し、外部にタグ付け依頼をする業務システムの開発 …
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・-・Django | |
定番
【フルリモ / Next.js/TypeS…
弊社のプロダクト群から共通で利用される認証基盤の開発プロジェクトに携わっていただきます。 ユーザ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基盤の構築 ・第…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザインプロジェクトの開発です。 自社で開発したプロト…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けのスマホアプリの開発。 就業中(求職中)の派遣スタッフとのエンゲージメント強化を…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週3…
弊社内のデザインチームにおいて、自社プロダクトやSI事業におけるフロントエンド開発のデザイン業務を担…
週3日・4日・5日
480,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日】デジタ…
当社グループでは、2007年設立当初に開始したインターネット広告事業を中心としたBtoB事業、Bto…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】AI…
今回ご参画いただくのはAIを活用したシステムデザイン(AASD)プロジェクトの開発です。 自社で開…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋市ヶ谷駅,九段下駅,半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
・新規開発/機能改善/追加における開発の全工程(機能提案、設計/実装、リリース) ・お客様導入案件…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿築地市場駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CodeIgniter | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】デジタ…
当社グループでは、2007年設立当初に開始したインターネット広告事業を中心としたBtoB事業、Bto…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| CSS・JavaScript・C#・Typescri… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
アプリケーション向けのCMS(配置情報とARコンテンツ等を管理し、配信するシステム)の開発を行ってお…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・VueJS | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
新規事業となる某マーケティング企業様との共同プロダクト開発に携わっていただける方を募集いたします。 …
週4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / AWS / 週4日〜】暗号…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Go / 週4日〜】…
サービスの急成長に伴って事業的にやりたい機能開発がたくさんあります。 機能開発スピードの向上に中長…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go | |
定番
【フルリモ / QA / 週4日〜】リリー…
・内製、外注を含んだ受入検査の実施 ・事業全体を把握し、製品の仕様を把握した上での適切な品質保証体…
週4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / Flutter / 週4日…
ネイティブ (Swift / Kotlin) で実装されたアプリをFlutterを用いてフルリプレイ…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
弊社が運営するニュースアプリのiOSアプリ開発全般を担当していただきます。 ・iOSアプリ開発…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・UIKit | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
弊社が運営するニュースアプリのAndroidアプリ開発全般を担当していただきます。 ・Andr…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【SNS運用・企画ディレクション】自社アウ…
・Webデザイン及びコーディング ・複数サイトのUI/UX大規模リニューアル ・新規Webサービ…
週3日・4日・5日
160,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・-・WordPressなどのCMS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】自社…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】オンラ…
新サービス立ち上げのための 0 => 1 フェーズの開発にコミットいただきます。現時点でワイヤーフレ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript・- | |
定番
【フロントエンドエンジニア】サービスサイト…
■概要 成長中のスカウトサービスにて、下記内容を含むアップデート対応をしていただきます。 ・新機…
週5日
370,000〜550,000円/月
| 場所 | 神奈川鎌倉駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PM 】中堅Sire_生命保険会社事務企…
保険事務センター移転にかかる支援 -什器・機器類の要件とりまとめ -センター社員向け…
週5日
500,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎 |
|---|---|
| 役割 | 【PM 】 |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】グロ…
- 当社が開発をしているECサイトの開発・テスト・運用・改善 - 新規サービス及び、新規機能のため…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】GC…
・顧客サプライチェーン全体におけるKPI(約40)を自動収集し見える化できるデータ基盤の構築 ・第…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 プロジェクト…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】医療×…
医療×ITのSaas型タレントマネジメントシステムのバックエンド開発をご担当いただきます。 PHP…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸福島駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】新…
・ゲームのサーバ側APIの設計と実装 ・基盤ライブラリ、フレームワークの調査、利用、拡張 ・開発…
週5日
500,000〜640,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
【業務内容】 アジャイル開発プロジェクトにおいて、Webアプリケーションの開発を行なっていただきま…
週3日・4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
・AWS上でのSSL-VPN(FortigateもしくはF5 BIG IP APM)のPoC対応 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原門前仲町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| FortiGate | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】社内構…
インフラ運用全般を担当するMSPサービスを展開しており、物理環境から仮想・クラウドまで、お客様インフ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
自社サービスのWEBコーディングを依頼させていただきます。 ・自社独自CMSを活用したWebサ…
週5日
330,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / スマホアプリエンジニア /…
スマートフォンゲームの企画、開発及び運用を担当していただきます。 ・画面仕様作成、詳細仕様作成…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】新規事…
当社の新規事業のサービス開発をご担当いただきます。 世の中にない新しい価値を生み出すべく、ビジネス…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
自社開発のクラウド人材管理ツールのUI/UXデザインを担っていただける方を募集いたします。 自社サ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
弊社の運営するHR系Webサービスのサブシステムの保守・運用開発業務をご担当いただきます。 業務内…
週3日・4日・5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 品川目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・PHP・Ruby・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】ライブ…
・プロダクトマネージャーや運営からの案件要望の吸上げと把握 ・仕様書作成 ・中国開発チームへの要…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】自社HR…
自社HRサービスのUIデザイン全般をご担当いただきます。 ・ユーザー側のプロダクト:求職者が使…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】アプ…
オフショアで開発したtoC向け自社アプリのクラウドインフラ(AWS/GCP/Azure)の運用管理設…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
・会社横断のマーケティングチームにおけるランディングページ、フライヤー、HTMLメールなどの販促を目…
週4日・5日
2.4〜4.9万円/日
| 場所 | 豊洲汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
当社が提供するサービスにおけるソフトウェア開発のポジションです。 本募集においては主にフロントエン…
週3日・4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
主にWebアプリケーションのAPIサーバー開発と、フロントエンドサーバー開発のコードレビューを中心業…
週4日・5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバサイドエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【フルリモ / kotlin / 週5日】…
ケアマネジャーと介護を必要とされる方の自立支援を一緒に考えるパートナーとして使用すればするほど人工知…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python | |
定番
【フルリモ / SQL / 週3日〜】自社…
健康保険組合向け製品の開発・運用、健康保険組合の加入者向け通知物の開発・運用業務に携わっていただける…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
受託開発案件でのPHPエンジニアを募集しております。 開発案件内容の詳細については面談時にお話…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Lararvel | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
自社サービスのRubyエンジニアを募集します。 サービス開始後、多くの申し込みをいただいている…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木永田町 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
フィットネスなど有名サービスを複数展開する企業様のインフラ全般を担当する情シス部門の社員代替の業務に…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木南青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
フロントエンドエンジニアとして、情報管理及び振込代行機能を備えた Webシステムの開発に携わってい…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Photoshop / 週…
自社で運営するマンガ配信サービス、リスティング広告などに使用するバナーを制作して頂きます。 既…
週3日・4日・5日
150,000〜370,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】航…
某航空会社の発券予約システムの開発を行います。 基本的にフロントメインとなりますが、サーバーサイド…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・React.js | |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】広告…
1人目の専任PdMとして、チャットブーストCVのサービスのグロースを担当していただきます。 1人目…
週4日・5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
UIUXデザイナーとして、自社サービスを始めとしたサービス・プロジェクトに Webデザイナーとして…
週4日・5日
440,000〜660,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / React.js / 週4…
※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・弊社クライアントの某証券会社のスマホ向けのリプレイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【フルリモ / Go/Ruby / 週3日…
弊社が運営しているリーガルドキュメントのバージョン管理SaaSソフトウェアにおいて中核を成す検索機能…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Ruby・Go・‐ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】G…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ・販売管理(予約管理、受発注、見…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】GCP…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ・販売管理(予約管理、受発注、見…
週3日・4日・5日
500,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Ruby・Java・Go・C#・Spring・Spr… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ・販売管理(予約管理、受発注、見…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Spring・SpringBoot・R… | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】GCP…
自動車関連のクラウドサービスにて、下記業務の依頼になります。 ・販売管理(予約管理、受発注、見…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Spring・SpringBoot・Rubyo… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
グルメサイトのWebサイトエンハンス開発の募集です。 エンハンス開発中の品質担保、向上を目的に複数…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】暗号資…
キャッシュレス決済の開発をするエンジニアを募集しております。 将来を見通したマイクロサービスアーキ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go・Shell・SQL | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 ・加盟店向けのダッシュ…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
主にWebアプリケーションフロントエンドに関するソフトウェア開発をバックエンドエンジニアと協調して行…
週4日・5日
500,000〜1,280,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】グルメサ…
HPグルメサイトのWebサイトエンハンス開発において、推進統括担当としてプロダクト全体に関わって頂き…
週5日
570,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Seasar2・SAStruts・Spri… | |
定番
【リモート相談可 / shopify / …
業績好調につきデザイナー&EC担当として活躍いただける方を募集しています。 海外向けの当社オリジナ…
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王線平山城址駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・Photoshop・Illustr… | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週5…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Kotlin・‐ | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
各事業におけるサービス開発を担当していただきます。担当事業や配属は、ご本人の志向や適性、組織の状況を…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
今回クライアントである大手製造業向けの受注~製造~運送までをDX化するPJへサーバーサイドエンジニア…
週3日・4日・5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / UI / 週4日〜】ソーシ…
ソーシャルゲームのUIデザイン制作業務を担当いただきます。 UI/UXデザイナーとして、企画・画面…
週4日・5日
300,000〜720,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・V… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】技術情報…
技術情報を使ったグラフ化、可視化が中心の新規Webサービスの開発が主な業務です。 顧客から頂いた情…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸桂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / Java/PHP / 週3…
弊社にて、企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいてリリース後の…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】オンラ…
弊社のプロダクト群から共通で利用される認証基盤やビデオ通話関連基盤の開発プロジェクトに携わっていただ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
ICTを活用したクラウド型学習支援サービスに関わるAndroidの開発です。 ・既存アプリの安…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Flutter | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週4日…
下記2つの業務のうち、いずれかに携わっていただきます。 案件① 本ポジションでは、クラウドネ…
週4日・5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
これまで単独でグロースさせてきた事業群をプラットフォーム化することにより、更なる事業シナジーを創出し…
週5日
390,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Scala・Kotlin・Typescript・Pl… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ペット事業とメディアコンサル事業を運営しています。 ・自社メディア開発 ・自社サービス開発 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
自社EC系パッケージソフトの開発をお任せします。 機能追加や改修、保守がメインですが、新製品の開発…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋西岐阜駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
自社の主力事業の管理システムに対して、『Salesforce』を活用したデジタル化をお任せします。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Java・Apex | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】自…
大手総合商社100%子会社である当社は、新規事業の開発・運営に注力しております。 主にはカーメンテ…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
弊社は、製造業に専門特化したインターネットサービスを提供している会社です。 今回は主に下記の業務を…
週3日・4日・5日
240,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川関内駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週4日〜…
弊社にて受注した2つの大手保険会社様の企業向け団体保険加入申込システム開発を行っていただきます。 …
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
自社のAndroidアプリ開発をご担当いただく方を募集いたします。 WebやiOSが機能先行…
週5日
480,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では、月間400万人が利用する金融経済メディアを、次のフェーズ・金融 プラットフォームへと向…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C++ / 週5日】…
以下のどちらかの機能を想定しております。 ①分散ストレージシステムにおいて、ホストマシンとの接…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川戸塚駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込み系エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週4日〜】某外…
弊社ではAI関連の受託業務を拡大しつつ、お客様と共同で同業他社にも役に立つプロダクトを開発しておりま…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
想定プロジェクトB、プロジェクトC ・両案件ともクライアントは同一で、とある大手ECサイト運営会社…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Springboot… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】基幹シス…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。依頼予定の…
週5日
570,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
株式やFXなどの金融商品を扱う オンライン金融サービス デザインチームでマークアップエンジニ…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JQuery | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
・新規サービス、プロダクトのCVR、LTV、MAUや自然流入数、及びNPS向上に向けた業務 ・ペ…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
創業フェーズの当社において、プロダクトチームでのサービス開発と運営改善における、バックエンド/フロン…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・R… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
・自社のiOSアプリ開発 ・UIの設計と実装 ・クラッシュログやいただくお問い合わせから見えてく…
週4日・5日
570,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手企業を中心としたECサイトコンサルを行っております。 今回は、コンサルで受注した企業様のECサ…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / SRE / 週4日〜】開発…
・開発者がより高速に開発できるための開発環境の改善 ・CI/CDやデプロイパイプラインの改善 ・…
週4日・5日
570,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日】ヘ…
現在開発中のヘルス管理系新サービスでのUI/UXデザイナーの募集となります。 立ち上げ間もない…
週3日・4日・5日
330,000〜950,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Figma・AdobeInDesign | |
定番
【フルリモ / SE / 週4日〜】データ…
お客様の課題解決にあたり、当社プロダクトの導入支援、および運用サポートを担当いただきます。 顧…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
【新規サービス】サーバーサイドエンジニア
弊社が新たに開発中の新規プロダクトの機能改修の設計・開発及び保守をお願い致します。 開発はバックエ…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川芝浦 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| ・Webアプリケーションの設計・開発・運用経験 ・… | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
・クライアントとの要件定義MTG ・外部設計、インフラ設計 ※英語が使えれば望ましいですが日本…
週4日・5日
570,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 秋葉原上野駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Javascript | |
定番
【リモート相談可 / Typescript…
NFTサービスの機能追加・改善を当社の社員と一緒に対応してくれるエンジニアを探しています。 AWS…
週4日・5日
660,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・React・node.js | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週3日…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
「サービスを1から作ってみたい」 「組織と共に自分の力を大きく伸ばしていきたい」 「ベンチャー企…
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Rubyon… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社は「スマートフットウェア」を中心としたウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラッ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】写真…
自社オリジナルソフトの開発を担当していただきます。 画像をサーバーに送信し、ユーザーに転送するシス…
週4日・5日
190,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸神戸駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
既に上位会社参画中の案件に弊社リーダーと一緒に参画いただけるメンバーを募集しております。 アジャイ…
週5日
410,000〜530,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】広告代…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 大手…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
【Python】機械学習技術を使用した、新…
【業務内容】 ・Deep Learning を活用した新たな Web サービスや新機能の構築 ・…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】広告代…
地方企業やベンチャー企業に特化したWebマーケティングテクノロジーの開発を提供する企業です。 大手…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Java・Vue.js・MySQL・AWS・… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】広告代理…
当社提供しているサービスに伴う開発業務をお任せします。 具体的には、 弊社テックリードと協力し、…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Vue.js・MySQL・AWS・Circle… | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
新規立ち上げ予定の動画メディアのUI/UXデザイナーとして、下記業務など幅広く担当して頂きます。 …
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
外資系コスメブランドのクリエイティブ関連の業務を下記を中心にお任せいたします。 ディレクションは米…
週3日・4日・5日
330,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】中古…
大手中古車販売会社の社内基幹システムの開発になります。 現在50数名の体制で弊社1社のみで開発…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
暗号資産やブロックチェーンに関するサービスの企画・開発を行っています。 今回は、下記の業務をメイン…
週4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PM】大手通信会社において、官公庁への提…
■案件概要 大手通信会社において、官公庁への提案にむけた次期システムのあるべき像の検討支援 …
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川青物横丁駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / React / 週3…
各商材ごとのシステムのリプレイス業務に携わっていただきます。 +既存のホームぺージのフロントを一新…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門/神谷町/六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue・Re… | |
定番
【リモート相談可 / QA / 週3日〜】…
既存のiOS / AndroidアプリのFlutterリプレイス版における、品質を担保してリリースす…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
リサーチ領域における母集団推定モデルの研究開発運用に関する各業務をご担当いただきます。 ・国内…
週3日・4日・5日
840,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト |
| Python・R | |
定番
【Javaエンジニア】配送システム大規模改…
流通小売業界大手クライアントのセンター化に伴う配送システム大規模改修をご支援いただきます。 サービ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBatch・・Spock | |
定番
【Javaエンジニア】顧客管理システム開発…
クライアントの顧客管理システムの開発・保守をご支援いただきます。 弊社プロパーをPMとして、シ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】決…
日本国内の大手企業の課題解決や新規事業開発を目的としたDXコンサルティングを中心に事業を展開しており…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】オフシ…
製造/プラント/建設業界で使用されるBIMのプラグインソフトウェアの設計・開発において10名以下規模…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・C# | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
3D スキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
3Dスキャンをもとにした情報管理 (デジタルツイン) アプリケーションの開発にご協力いただけるソフト…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | Reactエンジニア |
| JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
新規で開発しているオンライン授業プログラミングプロダクトのWebUI/UXデザイン業務をお願いします…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| Skech・Figma | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 新サービスをゼロから立ち上げる醍醐味を味…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 新サービスをゼロから立ち上げる醍醐味を味…
週3日・4日・5日
410,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】新規…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】新…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】新…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】新規事…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / C# / 週3日〜】新規事…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週3日〜…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
新規事業プロジェクトに開発エンジニアとして参画頂きます。 これからプロダクトの拡大期なので、新サー…
週3日・4日・5日
410,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】基幹シ…
基本的に、PMの指示の下、作業を行って頂く形となります。 PMにて実施するPM業務のサポートやチー…
週5日
610,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】基幹…
経営コンサルを行う企業様の基幹システムリプレイス案件です。 ・移行設計 既存システムと新規システ…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Java・SQL・jQuery… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
弊社が開発している外食業向け業務改善プラットフォームにおける、予約管理システムのフロントエンド開発業…
週4日・5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】クラウ…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・la… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週3日〜…
弊社は点群処理業務を効率化する、クラウド型のオンラインプラットフォームを運営しるスタートアップです。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋大手町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PMO / 週3日〜】社内…
・プロジェクトに関する社内プロセスの管理 ・プロジェクトのデータを収集と共有、関連する書類作成やプ…
週3日・4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
Splunk ①アラートやカスタムサーチコマンドの作成 ②サーチクエリ、ダッシュボードの作成 …
週3日・4日・5日
740,000〜1,650,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日〜】自社…
事業の成長に合わせて、新たに発足するプロジェクトのインフラ構築、運用を担当頂きます。 本業務の最上…
週3日
190,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
弊社内で活用している、業務サポートシステムの改修を行っていただきます。 要件定義等は、各部署の要望…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL・GCP・Docker | |
定番
【フルリモ / Wordpress / 週…
自社コーポレートサイトのリニューアルに伴い、Wordpressエンジニアを募集いたします。 サ…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上野駅 |
|---|---|
| 役割 | Wordpressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】飲…
弊社にて新規事業開発をしている飲食企業向けのSaaS開発におけるフロントエンド、サーバーサイド開発を…
週3日・4日
470,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Go・RubyOnRails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】広…
※詳細は、面談時にお伝えさせていただきます。 ・自社Webアプリケーションの開発をお願いしたく思っ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
当社では、主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、及びそのためのイ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・Framew… | |
定番
【JavaScript,TypeScrip…
受託開発及び自社サービスのの設計、開発、運用をお任せいたします。(JavaScript(React.…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PdM】地方企業の新規戦略を描くプロダク…
CPF、PSF、SPFなどの新規事業の戦略フェーズを主にお任せします。 ・クライアントの事業理解や…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸- |
|---|---|
| 役割 | プロダクトマネージャー |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】投資…
弊社では、主に機械学習や深層学習などのAIを応用したプロダクト開発・システム最適化、及びそのためのイ…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Python・SQL・Laravel | |
定番
【フルリモ / QA / 週5日】新システ…
自社SaaSシステムの刷新プロジェクトです。 SaaS型WebサービスおよびAndriodプラ…
週5日
550,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / React.js / 週3…
Webサイトとブラウザ拡張機能をベースとしたポイントメディアを開発予定。 具体的には、我々のブラウ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| SQL・Node.js・React | |
定番
【iOS / 週3日〜】新規アプリ開発業務
ユーザーがまだ体験したことのない新しいアプリの立ち上げに携わっていただきます。 企画・デザイナーと…
週3日・4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】自社新規…
当社が運営するサービスに関するフロント・バックエンド開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サ…
週5日
570,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Rea… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】国内最…
タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行…
週4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Typescript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
-デザインのエレメントパーツの洗い出し・重みづけ -エレメントパーツの制作 ※エレメントパーツ=…
週3日・4日・5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS | |
定番
【リモート相談可 / Javascript…
顧客や内部でコミュニケーションをしつつ、自ら開発が出来るエンジニアを募集しています。 今回募集する…
週5日
580,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・vue.js・React・An… | |
定番
【フルリモ / アーキテクト / 週5日】…
基幹システム(セミナー管理システム)の構築をお願いできるITアーキテクトを探しております。依頼予定の…
週5日
570,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | アーキテクト |
| HTML・CSS・JavaScript・Java・S… | |
定番
【Javaエンジニア】配送システム大規模改…
流通小売業界大手クライアントのセンター化に伴う配送システム大規模改修をご支援いただきます。 配送シ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Kotlin・PosgreSQL・・Int… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
人材サービス業向け社員向けスマホアプリ開発においてアーキテクチャを募集致します。 プロジェクト…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅、新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・React(react・・redux・・r… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】マスタ…
顧客のマスターデータマネジメントのプロジェクトに携わっていただける方を募集いたします。 ※詳細はご…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
今回は膨大なSNSマーケティングデータを扱うtoB向けSaaSプロダクトのML開発業務をご担当いただ…
週3日・4日・5日
1,210,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グループにおける新…
週5日
660,000〜13,710,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社シス…
・自社グループの利便性や各種KPIの向上のための、新サービスの機能の開発 ・自社グループにおける新…
週5日
660,000〜1,360,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / UI/UX / 週4…
実施率向上に向けた、仕組み作り、業務効率化を目的としたSaaS化、情報設計、UI/UXデザインをお任…
週4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日・5日
660,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】受託開…
弊社提供の観光系Saasサービスシステムにおいて複数のエンハンス案件に対応して頂きます。 (メイン…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
弊社はCM・Web映像・グラフィック・サイト構築・iPhone用アプリ・Webアプリなど、ビジュアル…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / QA / 週5日】スマホア…
スマホ 、タブレット、ウエアラブルの金融(証券)アプリのテストまで。 └受託or自社かは面談時に、…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
弊社では金融メディアプラットフォーマーという立ち位置で、WordPress、RCMS、自社CMSでW…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / VBA / 週5日】ハンデ…
以下の業務に伴うハンディターミナルを用いて、帳票・ラベルQRの読み取りとチェックを行い、中継アプリケ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【フルリモ / Nuxt.j / 週5日】…
フロントエンドの技術としては、アプリ側をReact Native、Web側をNuxt.jsで作ってい…
週4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】ス…
下記機能追加の開発、単体テスト設計、テスト実施、結合テスト設計・実施、UT実施 ・POP売価登…
週5日
330,000〜820,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】新規ス…
新規スポーツマーケットプレイスの開発をリードいただくPMの方を募集しています。 ・MP全体の構…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿名古屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
弊社では煩雑化する会計周りをシンプル化・DX化を促進する為、経理業務管理ツールの開発を進めてます。 …
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町半蔵門駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・Django | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
- Webサービス、アプリのUI/UXデザイン - プロトタイプ制作・画面設計 - デザインカン…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】自社プロ…
プロダクト開発を行うチームにテックリードとして従事し、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの技…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Go | |
定番
【ヘルプデスク】【運輸】社内ITサポート業…
社内ITサポートとして、5名体制の部署で1メンバーとしてご参画いただきます。 ご担当頂く業務として…
週5日
330,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿港区新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | ヘルプデスク |
定番
【Ruby+Vue.js】チャットブースト…
【担当業務】 - Webエンジニア 【案件の魅力】 - スクラムを実践し、プロダクトディス…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Vue.js | |
定番
システム開発PMO
基幹系システム刷新プロジェクトにおけるPMOとして、プロジェクト進行状況・課題の把握・報告を実施する…
週5日
670,000〜970,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム開発PMO |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】販促…
総合印刷サイト、販促物・印刷物発注システムの開発におけるサーバーサイド開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
150,000〜500,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・CakePHP・FuelPHP | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国内最…
開発メンバーマネジメント 効率的な開発体制作り Akerunの基盤となるAkerun APIの開…
週4日・5日
500,000〜950,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・Ruby | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
資産管理アプリの利便性向上のために、課題選定と解決策の考案をしていただきます。 ・解くべき課題…
週3日・4日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社グ…
・API、Webアプリケーションの設計、開発 ・査定アプリケーションまたはBtoBオークションシス…
週5日
570,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP | |
定番
【リモート相談可 / Vue.js / 週…
薬局・医療機関のDXを支援する新たな基幹サービス開発にあたってフロントエンドエンジニアを募集します。…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js… | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日〜】…
大手企業~中小企業の幅広い案件の提案から開発、運用までの全ての行程に携わっています。 クライア…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| Unity | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
決済代行会社様にて追加開発、新規開発、チームの一員として、お客様と対話しながら、一緒に開発を進めてい…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】サー…
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わっていただきます…
週3日・4日・5日
660,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三軒茶屋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・PHP・TypeScript・Git・UNI… | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・LinuxへのOSパッチ適用作業(年数回) ・顧客とのコミュニケーション:定例会参加、障害があれ…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Linux | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
具体的な作業内容は以下参照 NW ・FW、ルータ設定変更 ・障害時にFW、ルータのログ調査…
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Typescript / …
教育系サービス開発に参画していただき、フロントエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希…
週3日・4日・5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】顧…
TypeScript・React(Next.js)を利⽤したWebフロントエンドの開発を⾏っていただ…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・ | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
データ分析・仕組み化の観点から携わっていただきます。 具体的には、 ・サービスの現状分析および課…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Vue.js・MySQL・AWS・Ci… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社プロ…
自社プロダクトの導入プロジェクトに携わっていただきます。 ・アプリベンダー/SIerへのSDK導入…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
自社開発をしているクラウドファンディングシステムのクライアントページのデザインを今回お願いしたいと考…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Angular.js / …
弊社が運営する電子チラシ配信サービスにおけるフロントエンド開発業務をご担当いただきます。 ・cor…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大久保駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・cordov… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
SaaSプロダクト(CRM、請求機能など)に関するフロントエンド開発を担当いただきます。 プロダク…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
某大手銀行のシステム運用 ・WINDOWS系の運用・保守経験者。 ・VBA、SQLがわかる方。(…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| VBA・SQL・MSActiveDirectory・… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社顧客…
弊社の下記システムのPMを担っていただきます。 現在弊社では下記のサービスを開発しております。 …
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】自社…
・エンジニアサポート業務 ・ドキュメント、チュートリアルの整備 ・技術コンテンツの執筆 ・バッ…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】オ…
RubyonRailsが扱えてバックエンドを中心とした開発をお願いします。 ・自社プロダクト・…
週3日・4日・5日
500,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Azure / 週3日〜】…
主にセキュリティに関するシステム概要設計・構築 ・WAF等を用いた脆弱性対策の検討 ・FAQ …
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure・Web・Application・Fire… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
ビジネスサイド(マーケ、UXチームなど)と一緒にサービスグロースのためにサーバーサイドエンジニアとし…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / QA / 週3日〜】薬局と…
WEBサービス、アプリの動作検証、仕様確認 テスト仕様書(項目)をもとに、WEBサービス、アプリの…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】化粧品メ…
・上場企業様公式ネイティブアプリの開発・運用業務 ・クライアント企画/要望を受けての要件定義、設計…
週5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Swift・Kotlin・Laravel・G… | |
定番
【リモート相談可 / React / 週5…
人材サービス業向けの社員向けスマホアプリ開発と、スタッフ向け一般公開アプリの技術リードおよびアーキテ…
週5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・React(react・・re… | |
定番
スマホアプリ開発 チームリーダー
クライアントのスマホアプリケーション開発事業につき、クライアントのエンジニアとともにアジャイル開発を…
週5日
670,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】フードデ…
企画:画面の構成を検討したり、競合他社とのサービス比較してどんなサービスにするかといった要件を出して…
週5日
500,000〜1,540,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Typescript・SpringBoot… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】アセス…
需要予測ソリューションの導入に向けたアセスメントフェーズのプロジェクトマネジャーを募集します。 具…
週4日・5日
660,000〜1,500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / アプリ / 週3日〜】新規…
新規開発を行っているVRデバイスのアプリ開発にご参画いただきます。 Unreal Engineを使…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| C・C++・C#・Unreal・Engine | |
定番
【フルリモ / 3DCG / 週3日〜】V…
今回はVRプラットフォーム上でのアバターを中心に3DCG(キャラクター)デザインをご担当いただきます…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 3DCGデザイナー |
| Blender | |
定番
【Ruby+AWS】チャットブーストCVの…
<具体的な業務内容> ・プロダクト開発 ・新機能や新プロダクトの要件定義、設計、開発、運用 …
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・AWS・Terraform・・Docker | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
弊社が受託にて開発予定の薬品会社内での実験機器の自動化ソフトウェアの開発をご担当いただきます。 具…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
介護のチーム内で一緒に業務を行って頂きます。 目先の開発スピード向上と長期的なチーム開発力向上を目…
週4日・5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Typescript・React | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週4…
弊社は画像認識技術、紙メディアのデータ収集、管理、集計など先端技術で企業の作業効率化を目指しているベ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / WordPress …
クライアントワークにおいて、Webサイト制作においてHTML、CSSでのマークアップ業務を行っていた…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
定番
【HTML/CSS / 週5日】輸入車サー…
車関連サービスの開発チームや社内プロダクト関連の、デザイン作成業務を行っていただきます。 主に…
週5日
190,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】映像配…
弊社が運営する動画配信サイトへ書籍の配信サービスを追加するため、このサービスの追加機能の開発をお任せ…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木上原駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモ / UiPath / 週3日〜…
RPA(UiPath)単独ソリューション提供に加えて、持つ様々なAI/データサイエンスソリューション…
週3日・4日・5日
580,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / Go / 週3日〜】インフ…
・Go言語を用いたバックエンド開発 ・React(TS)を用いたフロントエンド開発 ・運用後のフ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Typ… | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】自社E…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GCP | |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】自社…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / PdM / 週4日〜】自社…
ECアプリを運営しています。 これから伸びていくEC市場で一緒に事業成長に貢献していただける方を募…
週4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
プロダクトのAPIサーバー開発を中心として、サービスを安定運用するための基盤システム整備まで幅広い開…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django | |
定番
【インフラエンジニア】AWS環境でのデータ…
■案件概要 AWS環境でのデータ基盤改善とセキュリティ構築 ■想定業務 ・データ基盤の改善…
週5日
460,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・S3・・Glue・・Athena | |
定番
【フルリモ / React / 週3日〜】…
アルゴリズムを安定運用するための基盤システムから、ユーザーの使用するダッシュボード画面のシステムまで…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
新しいアーキテクチャ(jamstack、サーバーレス)の構成における設計、構築、テストをリードしてい…
週5日
580,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 品川戸越銀座 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| JavaScript・Python・Vue・Reac… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
稼働中のECサイトを新サービスに適用させるための大規模改修として、オンプレからパブリッククラウドへの…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Java・SQL・Shell・Script・SQL・… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
インフルエンサー関連事業、デジタルマーケティング事業、クリエイティブプロデュース事業等のサービスを展…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Nuxt.js | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
インフルエンサー関連事業、デジタルマーケティング事業、クリエイティブプロデュース事業等のサービスを展…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Java・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
官公庁・自治体等の案件入札・落札情報を探せる自社サービスの周辺サービスとしての新規事業として、プロト…
週3日・4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
Fintech企業の決済アプリのプロダクトデザイン全般をお任せします。 プロダクトマネージャー、U…
週5日
550,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
| Figma・Illustrator・Photosho… | |
定番
【フルリモ / ゲーム / 週5日】レベル…
・スマートフォンタイトルの企画及び仕様作成、簡易なデバッグについて、開発~リリース、運用までを担当し…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週4日〜】…
今後、主力事業だけではなく、法人向けサービスの拡大や新規事業の展開を行っていく上で 各プロダクトのグ…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・JQuery | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】自社プ…
弊社のデータプラットフォームである自社プロダクトの開発管理に携わっていただきます。 弊社のプロ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
①HTMLタグの配置業務 WEBの多言語サービスに対応するための、プログラマーが制作したソースに、…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【リモート相談可 / PHP/PM / 週…
・ECサイトの保守(機能追加等)のディレクション ・顧客対応、メンバーへの指示 ・プログラムの修…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川日本大通り |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
定番
【リモート相談可 / MLOps / 週3…
全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる入札情報速報サービスを自社事業として展…
週3日・4日・5日
670,000〜1,230,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / UI / 週3日〜】自社サ…
現在自社サービスを拡大させるためのUI開発をしております。 具体的には、SEOの改善や成約率アップ…
週3日・4日・5日
500,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Photos… | |
定番
【PMO】AIによる契約書レビューサービス…
新規開発プロジェクトの成功を確実なものにするためのプロジェクトマネジメント - 問題の特定…
週3日・4日・5日
500,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| AWS・・・GCP | |
定番
【React.js】自社プロダクト開発のフ…
【業務内容】 ・React を使ったフロントエンドの設計、開発、運用 └本案件が選挙に関連した1…
週3日・4日・5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
プラットフォームサービスの保守開発(サーバ…
具体的な業務としては ・既存サービスの追加開発における設計、開発、テスト ・バックエンド領域のC…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | GraphQlエンジニア |
定番
【フルリモ/ TypeScript/ 週5…
【担当業務】 - フロントエンドエンジニア 【案件の魅力】 - 既存サービスの追加開発 …
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
Webシステム開発をご担当いただきます。 基本的な業務は、お客様の課題に合わせたBtoBのWEBア…
週3日・4日・5日
500,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【フルリモ / 組み込みエンジニア / 週…
・アプリの設計・実装・検証・運用 ・他社サービスとの連携機能開発 ・プラットフォームを利用した新…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Go・C・C++・C言語・NodeJS・Go・She… | |
定番
【グラフィック / 週3日〜】版権キャラク…
自社商品もしくはOEM商品の玩具・キャラクター雑貨のデザインと周辺業務をご担当いただける方を募集いた…
週3日・4日・5日
240,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】新規機…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週4日・5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】E…
自社プロダクトが各種データソース(DB、広告API、CRMツール等)とのデータ連携を行うための、Em…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
RubyonRailsによる API サーバーの開発・運用、各種非同期処理部分の開発・運用がメインの…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木日比谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Go・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
対顧客やチーム内でコミュニケーションが取れつつ開発ができる、フルスタックエンジニアを募集しています。…
週4日・5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【リモート相談可 / shell / 週4…
運用保守 ・日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う ・店舗定型作業、本番稼…
週4日・5日
410,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・COBOL・-・Shell | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社サ…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】受託…
弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいてリリース後の運…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】受託…
弊社にて企画提案からリリースまで対応している複数クライアント様の受託開発PJTにおいて、リリース後の…
週4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】スポー…
ブロックチェーンを活用したアプリの開発 スマートコントラクトの開発 スマートコントラクト…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Solidity・Rails | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】EC…
ECサイトサービスに関するサーバーサイド開発に携わっていただけるエンジニア様を募集いたします。 …
週5日
500,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【リモート相談可 / PL / 週5日】シ…
新しいアーキテクチャ(jamstack、サーバーレス)の構成における設計、構築、テストをリードしてい…
週5日
740,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川戸越銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・Python・Vue・Reac… | |
定番
【フルリモ / テスター / 週5日】Co…
クライアントが利用しているChatbotの改修をご支援いただきます。 現在ビジネス全部門が利用して…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【フルリモ / RPA / 週5日】RPA…
UiPath Studio/Orchestratorを使用したRPAの要件定義、設計、開発、テスト、…
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
スキルにより、リーダーまたはメンバーとして業務をご担当いただきます。 ①全体テスト管理、推進業務 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
AWS上に構築されたシステムのRDSバージョンアップ対応 RDSバージョンアップに関する課題対応、…
週5日
410,000〜850,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| PowerShell・JP1・AWS | |
定番
【フルリモ / SRE / 週5日】システ…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したシステムの監視・運用設計および監視・構築…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
アジャイル開発プロジェクトにおいて、AWSサービスを利用したアプリケーション開発および基盤の構築を担…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Djang・Vu… | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】決済プラ…
大規模決済プラットフォームのデジタル化案件です。 状況によりアサインチーム(弊社チーム、他チーム)…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Java・Go・Vue.js・React | |
定番
【リモート相談可 / デザイナー / 週4…
広告出稿、サービス開発に関わるクリエイティブを担当していただきます。 開発ディレクター、プランナー…
週4日・5日
350,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ‐ | |
定番
Microsoft製品の技術支援
Microsoft社の新製品を使用した業務ユーザによるアプリケーション開発環境において、システム開発…
週5日
840,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜 |
|---|---|
| 役割 | Microsoft製品の技術支援 |
定番
システム開発PMO
基幹系システム刷新プロジェクトにおけるPMOとして、プロジェクト進行状況・課題の把握・報告を実施する…
週5日
670,000〜970,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システム開発PMO |
定番
ビジネスアナリスト
基幹系システム刷新プロジェクトにおける現状業務の可視化、新業務設計支援として、ビジネスユーザーのヒア…
週5日
670,000〜970,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ビジネスアナリスト |
定番
動画編集者
【業務内容】 - テレビ、TikTok、YouTubeなどの動画編集 【求める人物像】 -…
週5日
160,000〜220,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京若松河田駅 |
|---|---|
| 役割 | 動画編集 |
定番
【リモート相談可 / Android / …
Android向けのSMTP/IMAPに完全対応したメールアプリの開発プロジェクトになります。 ・…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Git・Firebase・C… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
タクシー社内に設置している、乗務員様用iOSアプリの開発を担当して頂きます。 今回は、主に各種デバ…
週3日
340,000〜810,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・金融商品取引業者の会員システム開発業務 ・国内株式に関する新規サービスの構築及び、既存システムの…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Eclipse・SVN | |
定番
【フルリモ / Unity / 週3日】大…
大手鉄道会社から委託を受けているスマホアプリ開発のエンジニアを募集します。 ※ペアプログラミングで…
週3日
390,000〜890,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・Kotlin・-・Swift・Kotli… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
さらなる事業お拡大に伴い既存サービスやHPコンテンツの改善を行うにあたってデザイナーを募集いたします…
週3日・4日
260,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
主な作業内容として、 ・暗号資産のディーリングシステムの開発・保守 ・プライシング、ポジション管…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】RO…
顧客ヒアリングからPGへの指示出しと工数算出いただき、障害時の調査対応やPGのコードレビュー、実装相…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日】RO…
顧客ヒアリングからPGへの指示出しと工数算出いただき、障害時の調査対応やPGのコードレビュー、実装相…
週3日・4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】toB…
toB向けSaaSプロダクトのサーバーサイドの新規機能開発を担当していただく方を募集いたします。 …
週4日・5日
570,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / jQuery / 週…
弊社はECサイトの制作/構築における、企画プランニングから制作ディレクションをワンストップで行ってお…
週3日・4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】自社サ…
当社では企画・設計・デザイン・開発・運用まで全て対応致します。 今回ご担当いただく主な業務は以下で…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 東北:仙台山形駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / UI / 週4日〜】…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスの、クリエイティブ全般UIデザイナーを募集します。 主な…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスの、クリエイティブ全般UIデザイナーを募集します。 …
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】ふ…
ふるさと納税の老舗サイトおよび関連サービスにおける以下の業務に携わっていただきます。 主な仕事…
週5日
410,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| - | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
現在、UI/UXデザイナー1名、バックエンド兼フロントエンドエンジニア4名、PM、SREチームで開発…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
今回ご担当いただく業務として下記がメインとなります。 ・スポーツ関連webサイトのデザイン制作 …
週5日
330,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Swift / 週5日】 …
動画配信サービスのiOS・tvOSアプリの開発及び運用を担当していただきます。 ・動画配信モバイル…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Android / 週5日…
国内最大級動画ソリューション企業にて動画配信モバイルアプリ開発を担当していだだきます。 ・Andr…
週5日
330,000〜830,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
ご紹介企業のフロント開発をご担当いただきます。 ご希望やご経験に合わせて、案件内容はご相談をさせて…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】クライア…
大きくは2つございます。 1. 個別具体なクライアントの課題解決を担うコンサルティング要素の動き …
週5日
700,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Javascript / …
■Must:フロントエンドに関わる開発業務全般のリードをご担当いただきます。 LIssueに対して…
週5日
570,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】受託…
新卒HR領域のカスタマー側のサービスにおけるバックエンド開発をご担当いただきます。 新規サービスリ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週5日】受…
人材業界最大手のHR事業プロダクトにおいて、機能改善施策・エンハンス施策に関わるデザインが主業務とな…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / UI / 週5日】受託案件…
・教育支援webサービスのUI設計 ・画面遷移図制作 ・デザインシステムの設計・運用 ・画面仕…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
レガシーブラウザ(IE7)を前提としていたシステムをIE11とchromeに対応するように改修する案…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】農…
現状、紙ベースでの申し込みになってしまっている会員サイト上でWeb申し込みができるよう勧めて頂きます…
週3日・4日・5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Git・Docke… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
・サーバープログラムや機能の設計・開発 ・新規システムの要件定義・設計・開発 ・AWSを用いたア…
週3日・4日・5日
570,000〜850,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【フルリモ / UI/UX / 週3日〜】…
弊社サービスのユーザー体験に紐づく全体の戦略策定を担って頂きます。 ・ユーザーニーズ分析(インタビ…
週3日・4日・5日
570,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【Java / 週5日】企業向けプログラミ…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java・Spring | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】WEB…
・FXの顧客向けバックエンドシステム (ウォレットシステム・ポートフォリオ管理・顧客管理) ・資…
週5日
410,000〜930,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
事業のコアになる、データ分析を共に担えるメンバーを募集しております。 ・KPI改善のためのデー…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Lob分析サービス開発運用プロジェクトになります。 TVなどの操作Logをもとにランキングなどを出…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS・React.js・EMR・Re… | |
定番
【リモート相談可 / swift / 週5…
店舗で利用されているAndroidアプリ(お客様独自で生成されているアプリ)をiOSアプリに移行する…
週5日
700,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Git | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
大手消費財メーカーやサービス事業者などに対してのCRMソリューションプラットフォームのモジュール開発…
週3日・4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】顧客に…
AWSを利用し、弊社製品の動作環境を顧客毎に構築/運用して頂きます。 アプリケーション側エンジニア…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千駄ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】自…
・ユーザー側の機能についての新規機能の実装・既存機能の保守運用 (例)会員獲得のための自己分析ツー…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Unity / 週5日】新…
新規スマートフォン向けRPGゲームのクライアントサイドエンジニアとしてゲームアプリ開発を担当していた…
週5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| C#・Unity | |
定番
【Java / 週5日】自社VODサービス…
VODサービスそれに付随するストレージ商品・ネットワーク機器の提供をしています。 今回は、大手ケー…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
某キャリア向けモバイルコア5GCアプリケーション開発 コントロールプレーンネットワークファンクショ…
週5日
460,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Wireshark | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
RubyonRailsで構築された社内向けWebアプリケーションをJava/JavaScriptを用…
週5日
370,000〜940,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / Flutter / …
現行のドローン制御用タブレットアプリをクロスプラットフォーム化いたします。 Androidにて実装…
週5日
500,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
ドローンシステム向けWebアプリの開発を実施致します。 Webアプリの作成としてHTMLの作成、J…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・JavaScript | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
スポーツに特化したビジネスを展開している当社にて デザイナーの方を募集いたします。 既存大手ナ…
週5日
330,000〜690,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・- | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
自社SaaSプロダクトにおけるフロントエンドの企画・設計・実装・テスト・計測・改善を担当していただき…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
EDRから取り込んだアラートログを元にした、Splunk上での分析機能の既存機能更新、機能追加をお願…
週3日・4日・5日
740,000〜1,030,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| PHP・Python・GCP・Docker・Redm… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週3日】自社イ…
事業の成長に合わせて、新たに発足するプロジェクトのインフラ構築、運用を担当頂きます。 本業務の最上…
週3日・4日・5日
330,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / spaCy / 週5日】ア…
自然言語処理の開発を遂行していただきます。 1) ソフトウェアの全体設計と実装 2) ソースコー…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python・Java | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】大規…
大規模SaaSのスクラッチ開発プロジェクトでSaaSチームのPLをご担当頂きます。 設計から行いチ…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・Kotlin・AWS | |
定番
【リモート相談可 / C# / 週5日】新…
新入社員向けJava研修の講義・教室運営をお任せします。 メイン講師の方と一緒に講義を行う、サブ講…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東陽町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| C#・VB.NET・Spring | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
キャリア向け音声認識エンジンサービス開発業務支援プロジェクトとなります。 音声認識エンジン(SDK…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・C・C++・AWS・Android・i… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】医療・…
新業務フローの取りまとめ、人事側の運用策定、推進を出来る方、各テストの進捗課題管理を人事側に寄り添っ…
週5日
500,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 品川御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
スキルにより、リーダーまたはメンバーとして業務をご担当いただきます。 ①全体テスト管理、推進業務 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
現行CI/CD環境のフルリプレースに伴い、既存スクリプトを新しく書き直すエンジニアを募集しています。…
週3日・4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 池袋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
基本設計以降の開発業務を行います。 ・基本設計/詳細設計の成果物作成およびレビュー 例)API…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
Redmineで案件管理されています。 以下はアサインされた後の流れになります。 1、仕様書…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社サー…
こちらの募集ポジションは、当社並びに、当社関連会社(証券会社・FX会社)で手がけるWEBサービスの、…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・no… | |
定番
【リモート相談可 / グラフィック / 週…
マーケティング組織でのデザイン業務を担っていただける方を募集いたします。 主な業務は下記になります…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
定番
【リモート相談可 / HTML/CSS /…
マーケティング組織でのデザイン、マークアップ業務を担っていただける方を募集いたします。 - …
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【AWS案件|フルリモート】WEBサービス…
【仕事内容】 ・AWSでのサーバ構築(EC2、RDS、セキュリティ、ネットワーク設定など) ・各…
週5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海外 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
定番
【フルリモ / Node.js / 週3日…
教育系サービス開発に参画していただき、バックエンド開発をご担当いただきたいと思います。 ※ ご希望…
週3日・4日・5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・Node.j… | |
定番
【リモート相談可 / NW / 週5日】公…
公共系イントラネットのサーバ、クライアント端末の大規模開発プロジェクトになります。 結合試験工程以…
週5日
410,000〜910,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| VmwareESX・ActiveDirectory | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
通信会社向けインフラ構築検討・運用支援プロジェクトになります。 主な作業は下記の二つです。 …
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| OpenStack・Git・Kubernetes | |
定番
【フルリモ / Go / 週4日〜】自社プ…
プロダクト開発を行うチームにテックリードとして従事し、バックエンド、フロントエンド、インフラなどの技…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【リモート相談可 / TypeScript…
幼稚園・保育園向け写真販売システムの開発業務をお任せいたします。 約 3,000 の園に導入いた…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / Python / 週4日〜…
Pythonを用いた分析処理のバッチシステム開発を行います。 主に分析処理の前処理にあたるデータ加…
週4日・5日
580,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
ご紹介企業のフロント開発をご担当いただきます。 ご希望やご経験に合わせて、案件内容はご相談をさせて…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / 2D / 週5日】人気アイ…
ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた会社です。 …
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 2Dデザイナー |
定番
【Java / 週5日】某流通系システム運…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う 構成管理:プログラムに使用する項目の…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Shell・Java | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
TV/映画/アニメ等のコンテンツ配信サービスに関わるデータ連携システムの更改開発作業になります。 …
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿川崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Perl・SQL・BusinessOb… | |
定番
【リモート相談可 / PL / 週5日】A…
AWS上で稼働しているシステムに対する機能拡張の改修プロジェクトになります。 ・開発・保守作業…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 神奈川竹橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Java・AWS | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
企業や団体の課題に対してIT技術を用いた課題解決策を分析/提案をご対応いただきます。 オンプレ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Azure・OpenShift・kubern… | |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週3…
・Webコーディング(HTML、CSS、javascript) ・Shopify、カラーミーショッ…
週3日・4日・5日
350,000〜910,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
・TypeScript, React, Next.jsを使用したSPAの開発 / 設計 ・フロント…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / SRE / 週5日】介護系…
今回は介護系自社サービスのSREを担当いただきます。 詳細部分は面談内でご説明させていただきます。…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【リモート相談可 / RPA / 週3日〜…
RPAソリューション開発支援事業にて、RPAツール使用のセミナーやお客さまがRPAを導入する際…
週3日・4日・5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】We…
・PHPを使ったCMSプラグインの開発・実装 ・Webアニメーションのコーディング ・外部API…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Java | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週3日〜】社…
・社内システムの運用、整備 ・バックエンド開発案件の見積もり作成、開発、実装 ・バックエンド開発…
週3日・4日・5日
460,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】商品デ…
・AWSに構築されたデータ品質チェックシステムの保守運用 ・システムはCloudWatch、Far…
週5日
240,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | SQL |
| SQL | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週3日〜…
・ベンダコントロール(アプリベンダ、UATベンダ) ・部内およびIT部門との社内調整 ・プロジェ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Node.js / 週5日】某オンライン…
当社はデジタルクリエイターのタレント集団が在籍しており、クライアントに最高のクリエイティブを提供する…
週5日
550,000〜820,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Node.jsエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
主に自社サービス開発業務 案件は多数(入札案件等も行っている)あり、常に50~60のPJが動いてい…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週3日〜…
・ベンダコントロール(アプリベンダ、UATベンダ) ・部内およびIT部門との社内調整 ・プロジェ…
週3日・4日・5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】健康・福…
既存システムの改修や簡単な新規開発のサポート業務をご支援いただきます。 基本的にはバックエンドシス…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】自社顧客…
弊社の下記システムのPMを担っていただきます。 ①顧客管理システム ②①に紐づくLMS(ラー…
週5日
570,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】自社シ…
弊社の下記システムの開発を担っていただきます。 現在では下記の開発をしております。 ・カウン…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| PHP・Ruby・RubyonRails・PHP・L… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】都市…
具体的には下記のような業務をお任せいたします。 ・事業計画に基づく開発/改修計画の策定 ・開発リ…
週4日・5日
460,000〜690,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
データ基盤は、GCP(BigQueryなど)で構築されており、各ゲームタイトルのデータを集約して、分…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python | |
定番
【フルリモ / システム / 週5日】決済…
決済代行会社のシステム部門でのお仕事です。 今や欠かすことのできない「オンライン決済」や「店舗向け…
週5日
610,000〜1,070,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京竹芝駅 |
|---|---|
| 役割 | システム運用/保守エンジニア |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
・音楽業界向けのシステム開発を行う企業様で現在運用中のウェブサービスの開発を行っていただきます。 …
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京四ツ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・Linux・Postgr… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
当社のMissionを理解し事業戦略を踏まえた上で、社内他部署や社外パートナーと連携してプロダクト・…
週3日・4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
大手SIerのアーキテクチャデザイン支援部隊にて、エンドユーザや社内他事業部に対して現行運用のヒアリ…
週5日
330,000〜850,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Springboot・Vue.… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週3日〜】…
iOSを中心に技術面でチームをリードしていただき、技術課題のマネジメントや開発フローの整備など、様々…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・CircleCI | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
大手宅配運送会社向けの配送連携システムのリニューアルに向けてPJを立ち上げております。 開発内容と…
週5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Java・Spring・FrameWork・Post… | |
定番
【データサイエンティスト/アナリスト】市場…
■案件概要 ・車両企画担当部署における電気自動車の車両全体性能に関する分析依頼 ・電気自動車の各…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,麻布十番駅 |
|---|---|
| 役割 | データサイエンティスト/アナリスト |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
ドライバーの運転診断サービスの開発を行なっております。 デジタルタコグラフなどから取得した大量の運…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・・Django | |
定番
【Java / 週3日〜】某流通系システム…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う 構成管理:プログラムに使用する項目の…
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・Shell | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
インテグフローを理解した、ローカルビルドの実施と運用をご担当いただきます。 具体的にはビルドエラー…
週5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| Python・Shell・Git・Android・A… | |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
•製品の問題を分析し、正確なテクニカルレポート作成 •特定された問題に固有の自然言語処理および音声…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川綱島駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Java・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
小売業のECモールへの新規出店、出品、受注在庫管理を行うシステムの機能追加、改修。 業務システムの…
週5日
410,000〜820,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・jQ… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】プロ…
全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を一括検索・管理できる入札情報速報サービスを自社事業として展…
週3日・4日・5日
410,000〜1,080,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【チャットサポートメンター|フルリモ】【自…
【業務内容】 自社プログラミングスクールの受講生からの質問への回答と課題レビューをお任せします。プ…
週3日・4日・5日
2.8万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | チャットサポートメンター |
| Python・・Pythonの業務経験1年以上、また… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国のデ…
国の案件ですが、かっちり決まった仕様があるわけでなく、変化に柔軟に対応する必要があります。 ・少数…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】国のデ…
国の案件ですが、かっちり決まった仕様があるわけでなく、変化に柔軟に対応する必要があります。 ・少数…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週3日…
テックリードとして(希望されマッチする場合、将来的なVPoE・CTOポジション含め)活躍される方を募…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Laravel・V… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
・主に自社のフロントエンド開発(React .js、Vue.js) ・ビジネス要件を踏まえた最適な…
週4日・5日
500,000〜80,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / Andoroid / 週5…
・スマホからの位置情報を取得してkafkaなどのイベント処理システムを経由してデータを蓄積し、そのデ…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Kotlin・‐ | |
定番
【Java / 週5日】流通系システム運用…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う (店舗定型作業、本番稼働検証(日中日…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・COBOL・Shell | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】流通事…
流通業者のアクワイアリング事業のエンハンス支援を実施するPMOを担っていただける方を募集します。 …
週5日
830,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新富町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【.Net / 週5日】大手自動車メーカー…
・システムの脆弱性に対応するため、セキュリティ対策の一環として、古いOS/ミドルウェア等のサーバー環…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・.Net | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週3日〜…
企画・デザイナーと密に意思疎通を図りながら、iOSアプリの開発業務全般を担当していただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿みなとみらい駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【リモート相談可 / IOS/Androi…
アプリ(iOS/Android)をよりユーザーに価値を提供するためプロダクト価値を高めることが出来る…
週5日
350,000〜850,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・AWS・Slack・Confl… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】人材業…
弊社プロダクトである人材紹介会社、人材派遣会社、及び企業の採用担当者向けに、採用管理業務を支援する基…
週5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
飲食業界に特化したBtoBプラットフォームを提供。 現在はプラットフォーム内で複数サービスを開発・運…
週4日・5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・R… | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
・生命保険会社におけるインターネット保全手続きのバックオフィス用Webシステム開発 ・オンライン・…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
SNS・WEBプロモーション、R&D開発、イベント企画、ブランディングや地域プロモーションなどの、企…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【フルリモ / Laravel / 週5日…
・要件・仕様レビュー・コードレビューを通じた品質管理 ・開発チームの生産性を向上するための提案 …
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿小川町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Laravel・Vue… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日〜】We…
・PHPを使ったCMSプラグインの開発・実装 ・Webアニメーションのコーディング ・外部API…
週3日・4日・5日
460,000〜930,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代官山駅、恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモ / Javascript / …
プログラミングスクールにおけるシステムの保守運用をお任せいたします。 ・サービスサイトの保守業務お…
週4日・5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| JavaScript・Nest.js・Next.js… | |
急募
【C言語】血流認証システムなど当社開発製品…
【業務内容】 ソフトウェア開発技術者として、血流認証システムなど当社開発製品の制御ソフトウェアの開…
週4日・5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸堺筋本町 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PdM / 週5日】…
既存のコンシューマ向けスマホアプリ開発業務におけるディレクション業務全般をメインに行なっていただきま…
週5日
410,000〜1,190,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京有楽町駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【Ruby|週1出社必須】効果測定プロダク…
【業務内容】 - 広告事業における効果測定プロダクトや周辺の開発案件に携わっていただきます - …
週4日・5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】業界最…
弊社内で収集したデータをもとに、相関分析など主に統計的な手法により、課題とその発生要因の特定を目指し…
週3日・4日・5日
660,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Node.js / …
・自社サービス貿易サポートシステムのバーションアップ、後進育成 ・フロントエンド・バックエンド開発…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京芝公園駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Node.js | |
定番
【フルリモ / PM / 週4日〜】テレビ…
テレビ視聴データをBI提供するレアSaaS開発において、主に開発チームのPMを募集します。 具…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】受託プ…
・弊社の取り扱うデータ関連プロダクトのサポート、プリセールス、コンサルティング ・データ分析基盤に…
週5日
660,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・‐ | |
定番
【フルリモ / WordPress / 週…
・社内既定により算出したスケジュールでのクライアント折衝 ・必要に応じて社内のプロジェクトメンバー…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】大…
商品、在庫管理等を行うシステムの再構築。開発はオフショアを利用するため設計書の作成・変更及びPGレビ…
週3日・4日・5日
520,000〜790,000円/月
| 場所 | 神奈川天王町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
ドリルやマシンを製造している企業の基幹システムの刷新に伴う、システム構築 Javaを用いて、シ…
週5日
420,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日〜…
音楽及び映像ソフトの企画・制作、発売及びプロモーションアーティストのマネージメントを展開している会社…
週3日・4日・5日
240,000〜720,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python | |
定番
【RPA / 週5日】通信キャリア向け業務…
・通信事業者の業務効率化におけるRPA、AIサービス導入支援 ・NTTや工事業者、資材業者、消費者…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
定番
【フルリモ / SQL / 週5日】大手ふ…
大手ふるさと納税サイトにて、Webサイト・サービスのプロダクト開発のシステムエンジニアを募集します。…
週5日
410,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| PHP・SQL・- | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
・ネットワーク機器の運用・保守を担当 ・インフラ・ネットワーク機器でのトラブル対応・切り分け ・…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【リモート相談可 / PMO / 週5日】…
①全体テスト管理、推進業務 ・各種テスト計画支援 ・テスト仕様書フォーマット、ドラフト作…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】大手E…
①全体テスト管理、推進業務 ・各種テスト計画支援 ・テスト仕様書フォーマット、ドラフト…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Java / 週4日〜】某流通系システム…
日次検証:手順書を見ながら、稼働の確認やデータ検証などを行う 構成管理:プログラムに使用する項目の…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・COBOL・Shell・Java・COBO… | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週5日】…
フロントエンドに関わる開発業務全般のリード LIssueに対してのスケジューリング L開発方針の…
週5日
570,000〜1,210,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / Vue.js / 週4日〜…
フロントエンドに関わる開発業務全般のリード LIssueに対してのスケジューリング L開発方針の…
週4日・5日
570,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】社内…
社内インフラの刷新を行っているのですが、その中で各システムからログを収集する必要があります。 今回…
週5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】新…
当社の新規事業である動画制作プラットフォームの各種機能のサーバーサイド開発を担当いただける方を募集し…
週4日・5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・Vue.js・Gi… | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】FXの顧…
本プロジェクトは、システム管理者やアプリケーション開発者、デザイナー、UI/UX設計者など、多くのチ…
週5日
240,000〜750,000円/月
| 場所 | 東京23区以外クラークキー駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・C#・Linux・Apache… | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】新規機…
自社で下記2点の新規機能開発を進めております。 ・Webサービスの新規機能開発/リニューアル開発 …
週5日
500,000〜1,110,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Vu… | |
定番
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
・弊社のiOSアプリ開発 ・既存機能の改善、新機能の開発、バグの調査および修正等 ・ユニットテス…
週4日・5日
570,000〜1,150,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | IOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】開発チー…
・プロダクトオーナーと共に各PDT、PJTの開発進捗確認・管理を行う ・開発仕様の検討 ・プロダ…
週5日
330,000〜930,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】フ…
・健康経営SaaSのプロダクト開発 ・提供するサービスの新規開発及び機能拡充、性能改善 ・マイク…
週3日・4日・5日
570,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【フルリモ / Java / 週3日〜】某…
・業務:宅配、店舗システムでのプロモーション再構築 ・対応工程:要件整理、要件定義、システム要件設…
週3日・4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 神奈川横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】大手ふ…
大手ふるさと納税サイトのCMS開発やAPI開発など、要件定義から設計・コーディング・保守運用まで一貫…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・SQL | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】自…
当社が運営するサービスに関するフロント開発をご担当いただきます。 - 運営中の既存サービスにおける…
週5日
580,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Go・Rea… | |
定番
【フルリモ / ReactNative /…
最長1週間分のオリジナル献立自動作成アプリのリニューアルを担当頂くアプリエンジニアを募集しています。…
週4日・5日
300,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| JavaScript・ReactNative | |
定番
【PMO / 週5日】国際送金会社における…
・次期国際送金システムの開発および既存システムの改修に係るPMO業務。 ・各会議体への参加や各シス…
週5日
830,000〜1,510,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社システム…
・要件定義~リリースまでのPM業務 ・外部ベンダー、提携先との調整 ・上申資料の作成等
週5日
550,000〜1,150,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社マーケテ…
・アライアンス企業との調整(日程、制作物等) ・アライアンス企業とのマーケ施策議論、調整 ・We…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】ネット証券会社事務統括…
・ネット証券会社における業務改善に向けた企画検討支援 ・新業務構築に向けた整理、ヒアリング等 ・…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
ブロックチェーン関連業務の効率化に向けたBA 当社のビジネス向けデータサイエンス研修LADのた…
週5日
500,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・Typescript・AWS・Dock… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】大手建築…
・大手建築会社における大規模DXプロジェクト支援 ・建築現場のDXのためのソリューション企画検討支…
週5日
500,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】製造業_情報システム部…
お客様の情報システム部門の業務支援となります。 ユーザ企業側PMとしてITインフラ導入PJ推進、ベ…
週5日
620,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【PM / 週5日】製造業_情報システム部…
お客様の情報システム部門の業務支援となります。 情報システム部門は東京都内(品川区)にもあり、基本…
週5日
620,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川六本木駅,乃木坂駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / LaravelPHP / …
自社サービスの各種ポータルサイトの開発を行っていただくエンジニアを募集しております。 ユーザー…
週3日・4日・5日
310,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・PHP・LaravelPHP | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】アプリ…
メーカーにおいて現在、EOSに伴うインフラ部分(サーバー、VMware、ストレージ、NW等)と既存ア…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新富町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート相談可 / javaScript…
既存、新規事業のウェブ開発、運用やサービス管理ツール開発を行っていただきます。 教材を直接作成…
週4日・5日
500,000円/月
| 場所 | 品川白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Node.js・React.j… | |
定番
【フルリモ / Node.js / 週5日…
医師専用コミュニティサービスの継続開発になります。地域医療に関わるサービスとなっており社会貢献性の高…
週5日
550,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Node.js・Express… | |
定番
【フルリモ / SRE / 週3日〜】Pa…
・Goで書かれた、大規模なリクエストを受け取るアプリケーションの追加開発 ・各種システムの監視 …
週3日・4日・5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Java | |
定番
【リモート相談可 / Java / 週5日…
生損保Webシステム新規開発プロジェクトメンバー募集となります。 ・要件定義が終了したサブシステム…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【PMO / 週3日〜】海外送金システムの…
要件定義、社内調整、ベンダーコントロール、資料作成・整理、システム企画 ※プロジェクトに応じて幅広…
週3日・4日・5日
500,000〜1,390,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| CentOS・WindowsSever・GitHub | |
定番
【リモート相談可 / RPA / 週5日】…
大手小売業様向けにRPAの事業支援をしていただきます。 現在元請会社より3名客先オフィスに駐在し、…
週5日
590,000〜780,000円/月
| 場所 | 神奈川大船駅 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
定番
【Swift/Kotlin / 週5日】ス…
仮想通貨・FX・証券会社向けトレーディングのスマホアプリ開発案件となります。 新規機能追加、既存機…
週5日
670,000〜820,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Java・Swift・Ob-C・AndroidJav… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週4日…
サービス本体の開発に加え、サービス運営に必要な管理画面など各種プロダクトのサーバーサイド開発を担当し…
週4日・5日
750,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【リモート相談可 / SQL / 週5日】…
クライアントから依頼をいただいている、DB整備をご対応頂ける方を探しています。 PostgreSQ…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
クライアントから依頼をいただいている、生命保険新契約査定システムのCloud化を推進いただきます。 …
週5日
500,000〜1,160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / jQuery / 週3日】…
本研究所の研究成果を公開するサービスにおけるWEBフロントエンジニアを募集いたします。 本サービス…
週3日
350,000〜600,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
定番
【フルリモ / Python / 週3日】…
本研究所の研究成果を公開するサービスにおける画像処理・処理システム構築のエンジニアを募集いたします。…
週3日
350,000〜600,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Python・R・シェルスクリプト | |
定番
【リモート相談可 / JavaScript…
主な業務はサービスサイトやLPのデザイン制作物のコーディングです。 HTML、CSS、Javasc…
週3日・4日・5日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】サポート…
・StayNavi、GOTOトラベル事業、都道府県民割キャンペーンをはじめとする事業のカスタマーサポ…
週5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】宿泊施設…
・対象システムの要件定義、モック作成 ・プロダクト開発の推進、エンジニアとの連携 ・営業メンバー…
週5日
410,000〜1,120,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】宿泊予約…
・対象システムの要件定義 ・プロダクト開発の推進、エンジニアとの連携 ・営業メンバーとの連携、販…
週5日
670,000〜1,060,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【Java,Kotlin】自社開発 子育て…
・子育てプラットフォームの企画・開発・保守 ⇒補助金・監査・ダッシュボード等の、自治体と保育園な…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java/Kotlin) |
| Java・Kotlin・SpringBoot・Doc… | |
定番
【フルリモ / Linux / 週5日】D…
上位社員2名と同じサーバ基盤が担当しているシステムの基盤維持チームでの要員を1名募集しております。 …
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川泉岳寺 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| UNIX・Linux | |
定番
【フルリモ / C# / 週5日】帳票OC…
・顧客要件に応じたOCR製品のカスタマイズ ・製品に関する問い合わせ対応 ・プロジェクト内部の開…
週5日
350,000〜520,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C# | |
定番
【リモート相談可 / iOS / 週5日】…
大手通信会社向けのシステム開発・保守案件でiOSエンジニアを募集しています。 ※Android開発…
週5日
330,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木不動前 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AndroidJava・Kotlin | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】業…
弊社ITコンサルタントとともにクライアント先の業務システムの受託開発を、 要件定義から行っていくリ…
週5日
2.4〜3.6万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木神谷町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Python・Ruby・Java・C#・VB.NET | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
上位社員2名と同じサーバ基盤が担当しているシステムの基盤維持チームでの要員を1名募集しております。 …
週5日
200,000〜560,000円/月
| 場所 | 品川泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| UNIX・Linux・ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
新規・既存開発案件のPHPエンジニアを募集しております。 新規サービスの開発が多いので1からプロジ…
週5日
460,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・La… | |
定番
【フルリモ / PM / 週5日】英語必須…
大手クライアントがマーケティング等で使用するSNSのマネジメントシステム開発のプロジェクトマネジメン…
週5日
660,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモ / HTML/CSS / 週5…
・フロントエンド構築 ・基本的な業務は、HTML5、CSS3を使用したコーディングからWordPr…
週5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】急拡…
日々メディアにも掲載される業界No.1の注目度を誇る自社サービスでのバックエンド開発業務になります。…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・Go・Rails・Laravel・… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日】W…
・大手製造メーカー(売上4000億円規模)のコーポレートサイトTOPページおよび企業情報カテゴリTO…
週3日
290,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川北品川 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / React.js /…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービスとし…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・React | |
定番
【リモート相談可 / C/C++ / 週3…
受託している案件を新規又は途中から参画していただく形になります。 現在既存で行っているサービスとし…
週3日・4日・5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京都賀駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週3日〜…
・現行システム保守開発対応 ・改修要件の確認と設計、開発テスト、リリースまで対応 不明瞭な点…
週3日・4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町麴町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
今後サービスをグロースしていく上でWebディレクターとして、サービスの改善・新規機能の追加など、日々…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Typescript | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週3日】業…
①PoC(要件検証)の実装サポート ②プロダクトのベータ版の開発 具体的には新サービスβ版リリー…
週3日・4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| JavaScript・Go・Node.js・gola… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
・お客様のWEBシステムから画像を取得し、弊社のAI結果をレスポンスするAPIを設計・開発 ・イン…
週5日
390,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / VBA / 週5日】…
生産・販売業務(見積、契約、発注、仕入・倉庫搬入、出荷、売上請求、その他)を管理する基幹システム一部…
週5日
250,000〜880,000円/月
| 場所 | 品川三田駅or赤羽橋駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
弊社で提供するサービス/プロダクトの新機能開発や既存機能の改修を中心として、企画/設計/開発/運用…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・C・C++ | |
定番
【リモート相談可 / Go / 週5日】オ…
ゲームセンターのクレーンゲーム機をスマホやPCから遠隔で操作し、景品を獲得したら自宅に景品を配送する…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・Echo | |
定番
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
ゲームセンターのクレーンゲーム機をスマホやPCから遠隔で操作し、景品を獲得したら自宅に景品を配送する…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel・Vue | |
定番
【リモート相談可 / WordPress …
今回は社内で保守運用を行っている、wordpressサイトのフロントエンドの保守・運用に携わっていた…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【リモート相談可 / Ruby / 週5日…
コミュニケーションに特化した対話型AIを搭載した自社アプリの開発。 これまで「調べることを便利…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅/西新宿五丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイド |
| Ruby | |
定番
【VBA / 週5日】業務システムの運用・…
・ヘルプデスク業務 ・運用管理業務 (データベース管理、稼動監視、セキュリティパッチ適応、ジョ…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿霞ヶ関駅、虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| C・C++・C#・VB.NET | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】サ…
デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造を変革することを目指し、Bt…
週4日・5日
500,000〜1,130,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・RubyonRails・Vu… | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週3日〜】…
・システム開発プロジェクトのプロジェクト計画、システム要件定義、見積もり、プロジェクト管理、リリース…
週3日・4日・5日
580,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 品川田町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / Python / 週…
Webサービス開発におけるバックエンド開発業務をお任せします。 具体的には以下の開発項目を想定して…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・Flask | |
定番
【フルリモ / iOS / 週3日〜】iO…
・自社サービスiOSネイティブアプリの設計・開発 ・社内向けiOSアプリ・ツールの開発 ・サーバ…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Android / 週5日】ナビゲーショ…
当社プロパーと共に顧客サービスの開発をご支援頂きます。 ・顧客折衝 ・設計業務 ・実…
週5日
500,000〜820,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅or泉岳寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java | |
定番
【AIエンジニア】R&D部門のAIリードエ…
【業務内容】 R&D部門のAIリードエンジニアとして以下業務をお任せします。 ・自社大規模言…
週3日・4日・5日
570,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch・・HuggingFac… | |
定番
【AIエンジニア】PM等と連携しながらの実…
【業務内容】 R&D部門におけるAIエンジニア(Generative AI Specialist)…
週3日・4日・5日
700,000〜1,050,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch・・HuggingFac… | |
定番
【AIエンジニア】PM等と連携しながらの実…
【業務内容】 R&D部門のAIエンジニアとしてCSO、プロジェクトマネージャー等と連携しながら、分…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・PyTorch・・HuggingFac… | |
定番
【データエンジニア】CTO、CSO等と連携…
【業務内容】 当社の提供する各種サービスをひとつのIDで使用できる統合管理システムを運用しておりま…
週3日・4日・5日
500,000〜910,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Typescript・Flutter・… | |
定番
【Webディレクター】開発に関わるWebデ…
■業務内容 既存の大手クライアントのスポーツ関連Webサイトに関するWebディレクターを募集いたし…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【PM】大規模システム開発のプロジェクトマ…
ゼロベースからアプリプラットホームを構築するシステム開発を行います。 その中でPMとして基礎設…
週5日
1,170,000〜2,360,000円/月
| 場所 | 秋葉原浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトマネージャー |
定番
【PM】Web・AIシステム開発プロジェク…
【企業】 20年以上培ったWebインテグレーションと最新のAI技術を用いて、お客様視点で問題解決を…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | PM(Web・AI制作会社) |
定番
【フルリモ / React / 週5日】自…
【業務内容】 ・React を使ったフロントエンドの設計、開発、運用 ※短期参画の想定です。詳細…
週5日
620,000〜920,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ/ フルスタック/ 週5日】フル…
【担当業務】 大手半導体業界メーカーのデータ収集基板構築(オンプレサーバー上にて構築)に伴い、シス…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタック(インフラ/GO) |
| Python・Java・Go・オンプレ | |
【C#】自社開発ウェブアプリケーションのサ…
【企業】 当社は、住宅瑕疵保証のパイオニアとして、35年以上の歴史の中で培ってきた実績と信用力を継…
週4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京御成門 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Angular、oracle、AWS | |
定番
【フルリモ/ フルスタック/ 週5日】自社…
【担当業務】 - 自社プロダクトの新規機能開発・既存機能改修(バックエンド・フロントエンド) …
週5日
390,000〜900,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript | |
定番
【SREエンジニア】デジタルウォレットアプ…
■仕事概要 ▼募集ポジションについて デジタルウォレットアプリにおけるサービスインフラの設計・構…
週5日
800,000〜960,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| Go・AWS(ECS・Fargate・Lambda・… | |
定番
【UI/UXデザイナー】日本最大級のコーワ…
貸し会議室等のワークスペースを簡単に貸し借りできるプラットフォームサービスのUIUXデザインを通じて…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
[PHPエンジニア]既存システムの改修
【業務内容】 既存システムの改修業務(実装~テスト)を担当していただきます。 ※ドキュメントが少…
週3日・4日・5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川溝の口 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・・<歓迎するスキル> … | |
宿泊施設運営会社でのDX推進担当
【業務内容】 社内のDX推進について幅広く対応をいただきたいです。 ・各部署のニーズヒアリング …
週2日・3日
290,000〜350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿市川大野 |
|---|---|
| 役割 | DX推進担当 |
| DX推進として社内外の連携や調整を行った経験 | |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】O…
現在のOracleのシステムにExadataを導入し、システム効率化、集約化する案件となります。
週5日
620,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・ | |
定番
コールスタッフ【アウトバウンド】
人材採用を検討している企業へお電話にて、直接アプローチし、具体的な提案機会を獲得します。自社サービス…
週4日・5日
360,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿 |
|---|---|
| 役割 | コールスタッフ【アウトバウンド】 |
定番
【フレックス/リモート勤務可能!データ案件…
【案件内容】 ・医療機関データ処理の運用 ・データ取得作業 ※業務の詳細に関しましては、企業様…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア(医療関連) |
| SQL・ | |
定番
[ネットワークエンジニア]医療機関での現地…
医療ビッグデータの力で持続可能な国民医療を実現するため 医療統計データサービスを提供している会社で…
週5日
3〜3.2万円/日
| 場所 | 品川大門駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア(データエンジニア経験含む) |
| C・C++・SQL | |
定番
【コーダー/マークアップエンジニア】
【業務内容】 HTML.CSS,JavaScriptを用いたフロントエンド開発 ■開発環境 …
週3日・4日・5日
330,000〜580,000円/月
| 場所 | 神奈川溝の口駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・HTML・C… | |
定番
【Pythonエンジニア|フルリモート】新…
新プロダクトのバックエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 ご入社頂くタイ…
週5日
620,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python | |
定番
【リードエンジニア/フルリモート】新規事業…
新プロダクトのフロントエンドエンジニアとして、プロダクト立ち上げを担当して頂きます。 ご入社頂くタ…
週5日
620,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Python | |
定番
[マーケター(講師)]マーケター育成講座の…
コーチングをメインに担当していただきます。 運用経験者であり、人に何か気づきを与えられる方を求めて…
週3日・4日・5日
1.6〜2.8万円/日
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(講師) |
定番
【コンテンツ編集】コンテンツマーケ支援をす…
皆さんがユーザーとして使うWebサービスやオウンドメディアのコンテンツ制作をBtoBでサービス提供し…
週5日
220,000〜310,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | コンテンツ編集 |
| ・ | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週3日〜】自…
【業務内容】 - 既存のプロダクトの保守・運用 - RSpecの拡充:model, reque…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿吉祥寺駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Rails・React・Heroku・Gi… | |
定番
【Python,Go】自社サーバーサイドの…
・Pythonを使ったAPI、Webアプリケーションの設計、開発、運用 ・GCP・AWSを利用した…
週5日
670,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go | |
定番
【グラフィックデザイナー】保育士向け自社サ…
デザインの力でユーザーとサービスの距離を縮め、より日常的に使っていただけるサービスへと成長させつつ、…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 【グラフィックデザイナー】保育士向け自社サービス・子育て世帯向けWebメディア |
| ・デザインツール:・XD・・Photoshop・・I… | |
定番
プロモーションプロデューサー
プロモーションイベント(リアル/オンライン)やクリエイティブ制作、 PRなどの企画提案・ディレクシ…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿中目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | プロモーションプロデューサー |
定番
【Goエンジニア】キャッシュレス決済事業に…
前述のいずれかのサブチームに属していただき、 ・Webアプリケーション開発、API開発、バッチアプ…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・GoogleCloudPlatform・Com… | |
【Python,AWS,MySQL】データ…
【業務内容】 ログ数の増加やデータスキーマの多様化に対応すべく、データ基盤の運用安定化・効率化のた…
週4日・5日
530,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・AWS・MySQL | |
定番
【CTO/CTO候補クラス】 Rubyエン…
HRTechで新規事業開発中のベンチャー企業 CTO/CTO候補として、新規WEBサービス開発…
週2日・3日
600,000〜700,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | 【CTO/CTO候補クラス】 Rubyエンジニア 《自社HRサービス開発》 |
| PHP・Python・Ruby・Go・SQL・●Ru… | |
定番
【CMO/CMO候補クラスのマーケター】業…
士業特化の求人サイトのマーケティング担当として、マーケティング戦略の立案から推進を担っていただきます…
週2日・3日
600,000〜700,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | 【CMO/CMO候補クラスのマーケター】業界トップクラスのシェアを誇る人材系メディアを運営 |
定番
【データアナリスト・マーケター】業界トップ…
【業務内容】 ・webやリアル店舗(全国約1,000店舗)での売り上げや顧客のデータをBIツー ル…
週1日・2日・3日
140,000〜190,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【データアナリスト・マーケター】 |
| Power・BI・・Looker・Studio | |
【広報】大手メガネ会社で広報業務
【業務内容】 ・メディアリレーション ・既存サービス・取組に関するPR戦略立案 ・担当者と連携…
週2日・3日
140,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 【広報】業界トップクラスのメガネチェーン展開企業で広報業務 |
| ・PR戦略立案の経験(大小企業問わず) | |
注目
【事業開発】ベビーテックを世の中に広めるた…
【事業内容】 -事業開発(PM) 事業開発と案件提案・管理全般 【業務内容】 - ベビーテック…
週4日・5日
250,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | 事業開発 |
| ・事業開発、プロジェクトマネージャーの経験 ・他者… | |
定番
Salesforceエンジニア
【業務内容】 Salesforceエンジニア セールスフォース実案件のPM、PLができる方
週5日
250,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
定番
【JavaScriptエンジニア】既存クラ…
■業務内容 既存クライアントの特設スポートサイトの構築をお任せするエンジニアを募集いたします。 …
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・PHP | |
定番
【Ruby】AIによる契約書レビューサービ…
【仕事内容】 - 当社プロダクトのバックエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テスト・…
週4日・5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・MySQL・Aurora・・Redis・・… | |
定番
【React】AIによる契約書レビューサー…
【仕事内容】 - 当社プロダクトのフロントエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テスト…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】日本最大級のビ…
企画担当、マーケティング担当と情報共有することで、ユーザー、ビジネス、マーケットに精通することができ…
週3日・4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂見附駅 |
|---|---|
| 役割 | 【サーバーサイドエンジニア】日本最大級のビジネステンプレートサービスのリバースエンジニアリング |
| PHP・Python・Go・GCP・・Linux | |
定番
【急募!PM/PMO案件】生保系システム …
概 要:生命保険の新契約・保全・保険金業務について、システム子会社社員の支援を行う。 [業務内容…
週5日
710,000円以上/月
| 場所 | 東京23区以外小田急多摩センター駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/PMO |
| ー・ | |
定番
【Swift】自社ヘルスケア領域の新規事業…
スポーツにテクノロジーを導入し、個人のデータが容易に取れる仕組みの構築を推進する当社。その中で、iO…
週3日・4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・AWS・・Firebase・-・ | |
定番
【Python】自社ヘルスケア領域の新規事…
【業務内容】 企画、デザイナー、フロントエンジニアと連携し、ユーザーへのより良い体験を提供するため…
週3日・4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Linux | |
定番
【React, Vue.js】自社ヘルスケ…
【業務内容】 企画、デザイナー、サーバーサイドエンジニアと連携し、ユーザーへのより良い体験を提供す…
週3日・4日・5日
250,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Linu… | |
[アプリエンジニア]自社IoTアプリケーシ…
自社で開発しているウェアラブル機器と、そこから得られるデータを活用するプラットフォームを開発・運営し…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木八幡駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Swift・Kotlin・Flutter・Dart・… | |
【Webデザイナー】大手通信会社グループ
【企業】 大手通信キャリアグループの⼀員として グループ内はもちろん、他社のクライアントのニーズ…
週3日
250,000〜300,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【Webデザイナー】大手通信会社グループ |
| HTML・CSS・JavaScript・Adobe・… | |
定番
[UI/UXデザイナー|ハイブリット勤務]…
■業務内容 ・NFTマーケットプレイス「PLT Place」や新規プロダクト等のデザイン ・プロ…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
[Goエンジニア] 自社開発サービスのNF…
自社開発サービスのNFTマーケットプレイスに関するバックエンド開発業務を担当していただきます。 …
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
定番
【Python,Vue.js】自社機能改修…
【業務内容】 ・Python や Amazon Web Services を使ったサーバーサイドの…
週3日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Vue.js | |
注目
[フロントエンド]自社開発サービスのNFT…
自社開発サービスのNFTマーケットプレイスに関するフロントエンド開発を担当していただきます。 …
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
[マーケター]自社開発ブロックチェーンを基…
自社開発ブロックチェーンを基盤としたサービスの拡大に向けた戦略立案、分析、実施 ・サービスの改…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【UIデザイナー】自社開発・運営のB2B …
・新規機能開発・既存機能改善のUI/UX提案 ・PMやスクラムチームと対話しながら、最適な情報設計…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
定番
【人事】ビジネスサイド(セールス / カス…
【業務内容】 ・役員陣/現場とのコミュニケーション ・事業責任者との採用計画のチューニング ・…
週4日・5日
250,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | 人事 |
定番
【ディレクター】自社アパレルECサイトの運…
【業務内容】 自社ブランドのECサイトの数値分析・改善・運用業務をお任せできる方を募集致します。 …
週3日・4日・5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 東京23区以外玉川上水 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
急募
【AWS】週4~OK|インフラ基盤の開発や…
案件の内容 0 → 1 フェーズに位置しており、ビジネスオーナー・プロダクトマネージャー・デザ…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS) |
| AWS IaC(Terraform) Githu… | |
定番
【Python】データ分析・機械学習関連開…
自社サービスの事業拡大に伴い、データ分析・機械学習に関する開発業務をご担当いただける方を募集いたしま…
週3日・4日・5日
470,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・ | |
定番
【FFRPG】講師案件におけるRPGエンジ…
【業務内容】 弊社で受託している案件へご参画をいただきます。 ・RPGを使用している企業様へのメ…
週3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | RPGエンジニア・講師 |
| ・ | |
定番
【メンター】ITスクールの受講者サポート業…
●業務内容 ・受講生と13:00-22:30の時間内で定期メンタリング(オンライン)を実施 …
週1日・2日・3日・4日・5日
200,000〜290,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | メンター(WordPressコース) |
| HTML・CSS・フォロー体制がありますので、メンタ… | |
定番
【UI/UXデザイナー】受託案件のUI/U…
【案件概要】 CMS管理システムのUI・UXデザイン等をお任せします。 得意領域やスキル・ご経験…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋-- |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| -- | |
定番
【フルスタックエンジニア】自社サービスオプ…
【具体対応内容】 ・自社プロダクトのカスタマイズ案件の開発 ・自社プロダクトのオプション機能の新…
週5日
350,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・C#・Typescr… | |
定番
【AWS/Linux】テクニカルオペレーシ…
【業務概要】 ・共通のインフラ運用管理に使うツールの運用・保守・改善 ・共通のバックアップの運用…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Go・Terraform Kubernetes | |
定番
【フルスタックエンジニア】自社サービスオプ…
【具体対応内容】 ・自社プロダクトのカスタマイズ案件の開発 ・自社プロダクトのオプション機能の新…
週5日
300,000〜480,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Java・C#・Typescr… | |
定番
【Salesforce(ServiceCl…
[案件概要] Salesforce ServiceCloudの運用支援業務 [業務内容] …
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿 都筑ふれあいの丘 |
|---|---|
| 役割 | 【Salesforce】大手小売業におけるServiceCloud運用 |
| Salesforce | |
【Unity(WebGL)エンジニア】3D…
バーチャル住宅展示場開発案件 バーチャル住宅展示場は、リアルな住宅展示場とは異なり、 建築等…
週1日・2日・3日・4日・5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【Unity(WebGL)エンジニア】3Dメタバース(バーチャル住宅展示場)開発 |
| Unity | |
定番
【PHPエンジニア】医療機関のプロモーショ…
PHPのLaravelを利用しているサービスのバージョンアップが必要となり、対応できる方を募集してお…
週3日・4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Laravelエンジニア |
| PHP | |
定番
[Vue.js]ネットショップ作成サービス…
【担当業務】 - ネットショップ作成のフロントエンド開発 【案件の魅力】 - 全面リニュー…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| フレームワークとしてはAstroを利用して静的なペー… | |
【PM】開発チームをリードするプロジェクト…
【業務内容】 ・システム要件定義(外部システム利用や、内製含めた最適なシステムの検討) ・開発案…
週5日
670,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
注目
【AWS】大手金融機関向けネットワーク運用…
【業務内容】 大手金融機関向け SalesforceとAWS間のネットワーク運用保守 ※Sal…
週5日
250,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都内 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【PHPエンジニア】某上場企業の保有する全…
■募集背景 人材不足に伴い、追加の募集 ■業務内容 ・某上場企業の保有する全WEBサービス…
週4日・5日
670,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
[Webデザイナー]日本最大級の料理動画メ…
■主な業務内容 ・バナー、LPなどのビジュアルデザイン ・サービス向上の為のUIデザイン及び改…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ・ | |
【ライター】コンテンツマーケティング/テレ…
【業務内容】 マーケテイング施策の一環として、記事コンテンツの企画・執筆をお任せできる方を募集しま…
週2日・3日
140,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿田町駅 |
|---|---|
| 役割 | 【ライター】コンテンツマーケティング/テレビCM出稿、マーケティング、テレビ視聴率等に関する記事コンテンツの企画・執筆・校正 |
定番
[Typescript] HR領域の新規プ…
【業務内容】 HR領域の新規プロジェクトにおけるプロダクトの開発 Google Cloud Pl…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Go・Typescript・GraphQL(gqlg… | |
定番
【フルリモ / React / 週4日〜】…
HR領域の新規事業を立ち上げるために、2023年4月に組成したばかりの新しいチームです。 ターゲッ…
週4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
【PHPエンジニア】自社メディアの開発
【業務内容】 複数展開している各プロダクトのサービスサイト開発(PHP)をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 【PHPエンジニア】自社メディアの開発 |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・イン… | |
【フルリモートOK】上場企業の社内業務改善…
【業務内容】 ・RPA(PowerAutomate)開発を中心に業務改善を進行しています。 ※…
週2日・3日
190,000〜250,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア(WEB系言語開発経験含む) |
定番
【フルリモート!!/Webディレクター】コ…
・制作進行管理(スケジュール管理、タスク・制作指示のとりまとめ作業など) ・品質管理(制作物チェッ…
週3日・4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【フロントエンドエンジニア】スマホアプリの…
【募集背景】 スマホアプリのバージョンアップに向けた開発に力を入れている背景があり、 その点でス…
週4日・5日
310,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
【Webデザイナー】ロボットメーカー(最先…
【業務内容】 ・最先端家電商品のWebデザイン(LP、バナー)の制作 ※チラシの制作も発生の可能…
週1日・2日
260,000〜360,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原則リモート |
|---|---|
| 役割 | 【Webデザイナー】ロボットメーカー(最先端家電商品) |
定番
【AWS】人材管理ツールにおけるインフラエ…
自社で開発を行っているクラウド人材管理ツールのインフラ構築/運用業務 【業務一覧】 ・サービ…
週4日・5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Javaエンジニア】食のインフラを支える…
生鮮食品市場における取引はファックス、紙中心のアナログな対応が多く、 基幹システムについても、ホス…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【Javaエンジニア】食のインフラを支える生鮮食品市場のDXプロダクト開発 |
| Java・Spring・Framework・・AWS | |
定番
【3DCGアニメーター】ドローンショーのア…
【業務内容】 映画やゲーム、建築、車関係などで活用されたその3DCG技術を、 ドローンショーに生…
週2日・3日・4日
260,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 【3DCGアニメーター】ドローンショーのアニメーション制作 |
定番
【PHP→Ruby移行】ToCサービスにお…
【案件概要】 現在急拡大中のアルバイト求人メディアをご担当いただきます。 一般的な求人メディアと…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby | |
定番
【フルスタックエンジニア】自社AIを用いた…
【職務の概要】 ・自律的なチームを目指し、スクラムを目指すアジャイル開発 ・課題分析/施策検討/…
週3日・4日・5日
330,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・RDS・Docker・nom… | |
定番
【広告制作】自社の広告制作の補助や管理
【業務内容】 ・営業補助(広告案件の商談同席・議事録制作・見積書作成・企画書制作サポート) ・制…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告制作の補助/管理 |
| ・ | |
定番
Unityエンジニア
・Unityによるアプリケーション開発 ・Web、スマートフォンアプリ、xRデバイスなど多岐にわた…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
【iOSエンジニア】SwiftでのiOSア…
■業務内容 あなたを含めたチームの誰かが解消したいと思っている、自分ごとにできる通信への不満を、も…
週4日・5日
1.6〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【Pythonエンジニア】Wifiアプリの…
■業務内容 あなたを含めたチームの誰かが解消したいと思っている、自分ごとにできる通信への不満を、も…
週4日・5日
1.6〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Go・GCP・・Linux・・flas… | |
定番
【データアナリスト】施策に伴うユーザー行動…
■業務内容 通信への不満を解消する為の施策をメンバーが作成する際、精度を上げる為に定量面からサポー…
週4日・5日
1.6〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| HTML・CSS・JavaScript・Python | |
定番
【PMO】AI会話型ドキュメント検索サービ…
【背景・目的】 大手コールセンターの先端テクノロジーの研究をしている部門で AI会話型ドキュメン…
週3日
350,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | 【PMO】AI会話型ドキュメント検索サービスの導入支援業務 |
| JavaScript・Python | |
定番
【編集ライター】大手クライアントの雑誌、カ…
【企業】 サンポストは、1968年創業の東京・新宿にある広告制作会社です。 編集者、デザイナー、…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿御苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | 【編集ライター】大手クライアントの雑誌、カタログをメインに担当 |
定番
【ライター】ニュースレター原稿作成・配信・…
【業務内容】 ・ニュースレター原稿作成・配信・運用業務のライター業務 ・ニュースレターの原稿作…
週2日
80,000〜180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
| ・ | |
定番
【原則フルリモートOK】大手飲食業(全国チ…
【業務内容】 開発エンジニアとして、クライアント様のWEBサイトリニューアルをご担当いただきます …
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンド(React/TypeScript)※クラウドインフラ含む |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / Next.js(React…
【業務内容】 ・医療ヘルスケア・プラットフォームにおける新サービス設計・開発 ・上記を軸としたO…
週4日・5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Next.js・・HTML・・CSS・・Ja… | |
定番
【Goエンジニア】自社サービス開発における…
弊社が新たに開発中の新規プロダクトの機能改修の設計・開発及び保守をお願い致します。 フロントもバッ…
週5日
550,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝浦 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Go | |
定番
【Java|ハイブリット勤務】Java言語…
【業種】 生命保険 【業務内容】 Java言語を用いた生命保険・契約管理WEBシステムの保…
週5日
520,000〜550,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
【インフラエンジニア】自社プロダクト(医療…
【業務内容】 ・医療ヘルスケアプラットフォームにおける新サービス設計・開発に合わせたインフラ基盤の…
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【インフラエンジニア】自社プロダクト(医療・ヘルスケア領域)のインフラ設計から構築・運用 |
| AWS・Laravel・MySQL・GraphQL・ | |
定番
【UI/UXデザイナー】ヘルスケア×DXの…
【業務内容】 医療ヘルスケアプラットフォームに接続するアプリおよびWebシステムの開発に携わってい…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【UI/UXデザイナー】ヘルスケア×DXの自社プロダクト |
定番
【Webエンジニア】テレビメディアのDXサ…
【業務内容】 ・Webサービスの機能開発、改善 ・バックエンド・フロントエンドの開発 ・企画、…
週4日・5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【Webエンジニア】テレビメディアのDXサービス開発 |
| ・言語:Kotlin(Ktor)、Vue.js(Ty… | |
注目
【Go+PHP】クラウド人材管理ツールのA…
【業務内容】 ・新規機能の開発 ・実装メイン(設計が得意な方であればお任せする場合もあります) …
週4日・5日
570,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go・-・ | |
定番
【急募!フルリモートOK】社会人教育事業・…
【担当業務】 - toC向けサービスと法人向けサービスの開発 【案件の魅力】 - プロダク…
週5日
580,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンド |
| JavaScript・Vue・React・Rubyo… | |
定番
【Java】アプリデータ収集サーバー開発
【案件概要】 - アプリデータ収集サーバー開発 【業務内容】 - アプリケーションのデータ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Azure・SpringBoot | |
定番
【AWS|AWSインフラ構築と運用フローの…
【案件概要】 - 現行開発のシステムの運用方法の置き換えに伴い、AWSインフラ構築と運用フローの設…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【コミュニティ運営】SNSコミュニティー運…
インフルエンサーが所属している、コミュニティの管理・拡大、エンゲージメント向上
週4日・5日
1.6〜2万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町神田駅 |
|---|---|
| 役割 | SNSコミュニティ運営リーダー |
定番
【PMO|Windowsアプリケーション開…
【案件概要】 - 現行開発のシステムの運用方法の置き換えに伴い、AWSインフラ構築と運用フローの設…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【Java】某大手フードデリバリー会社の配…
【案件概要】 - 某大手フードデリバリー会社の配送システム開発 【業務内容】 - 設計~テ…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【一部リモート可 / マーケター/PR /…
【業務内容】 アーティストや楽曲コンセプトに沿ったメッセージや感動が伝わるよう国内外のパートナー企…
週5日
300,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ・首都圏在住の方に限ります。 | |
定番
【Python| データ分析業務とサーバ環…
【案件概要】 - データ分析業務とサーバ環境構築 【業務内容】 - データ分析業務とAI・…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・AWS | |
定番
【インフラエンジニア|フルリモート可】クラ…
【案件概要】 - クラウド案件に関わる業務支援 【業務内容】 - お客様の各事業部における…
週5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲青山一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / HTML,CSS / 週1…
アンケートLPの制作(※デザイン・コーディング含む) 美容系・求人媒体・学習塾など幅広い業種の中か…
週1日
40,000〜130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | コーダー・Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・ | |
定番
【基本リモート|データエンジニア】 データ…
【案件概要】 - データ分析システム基盤の構築およびSSRSを用いたレポート開発 【業務内容…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア(SQL、BI含む) |
定番
【基本リモート|データエンジニア】 分析基…
【案件概要】 - 分析基盤システム刷新に伴うBI画面の設計~開発 【業務内容】 - BI画…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア(PowerBI含む) |
【Java】各種ECモール連携機能の開発お…
【案件概要】 - 自社EC在庫の各種ECモール連携機能の開発および保守改修業務 【業務内容】…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Oracle | |
定番
【フルリモートOK!PdM案件】働きがいを…
▼業務内容 1人目のPdMとして、チーム全体のプロダクトマネジメントをリードいただきながら、既存/…
週2日・3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM(テックリード経験あり) |
| フロントエンド:JavaScript バックエンド… | |
定番
【Java】キャリア向けモバイルコア5GC…
案件概要 :キャリア向けモバイルコア5GCアプリケーション開発 コントロールプレーンネ…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Azure・SpringBoot | |
定番
[Webディレクター]医師向けWEBサービ…
【主な業務】 ●POや開発パートナーとの打ち合わせ・ヒアリング(ほぼオンライン会議) ●要件定義…
週4日・5日
390,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| ・※月1〜2回ほど、クライアントの会議室等で対面会議… | |
定番
[UI/UXデザイナー]医師向けSNSのU…
■業務概要 オンライン医局(医師向けSNS)のUIデザイン・UX設計をご担当いただきます。 可能…
週3日
180,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4~】アル…
- 以下の3つのプロジェクトのうちいずれかに、スキルやプロジェクト状況を考慮してアサインします。 …
週4日・5日
750,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【一部リモート / Android / 週…
証券、FX、暗号資産などの金融取引を行うための専用スマートフォンアプリの開発ができる方を募集します。…
週5日
920,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Android(Kotlin・Java… | |
定番
【一部リモート / PHP / 週4~】ス…
惣菜部門向けの新規システム開発 - アジャイル開発手法を用いたWebアプリの設計、開発、テスト
週4日・5日
750,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・SQL・・PHP・・Laravel・・Typ… | |
【PMO|キャリア向けサービス開発業務支援…
【案件概要】 - キャリア向けサービス開発業務支援 【業務内容】 - 某キャリアが展開する…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【インフラ案件|フルリモOK】大手半導体業…
【業務内容】 大手半導体業界メーカーのデータ収集基板構築(オンプレサーバー上にて構築)に伴い、シス…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(Kubernetesを利用) |
| オンプレ | |
定番
【フルリモート/サーバーサイドエンジニア】…
■仕事内容 新規機能の開発と既存機能の保守運用を担当します。主に2つのプロジェクトがありますが、案…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・JavaScript・PHP・Ruby・R… | |
定番
【フルスタックエンジニア】自社プロダクトの…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するEdTechのベンチャー企業です。 ■仕事内容: …
週5日
710,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・on・Ra… | |
定番
【PM】新造クルーズ船内のシステムの上流案…
【業務内容】 新造クルーズ船内の複数システムの要件整理を担当していただく方を募集しています。 大…
週4日・5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜駅 |
|---|---|
| 役割 | PM/PMO |
| -・ | |
定番
【UIデザイナー募集】地域通貨プラットフォ…
■仕事内容 地域通貨プラットフォームサービスのアプリのUIデザインを担当していただきます。企画のメ…
週3日・4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| デザインツール:figma・もしくは・figjam | |
定番
【UI/UXデザイナー】カジュアルスマホア…
スマホアプリゲームの運用や施策提案・仕様決定など、幅広くご対応をしていただくデザイナーを募集します!…
週4日・5日
250,000〜470,000円/月
| 場所 | 池袋池袋 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
自動車再生メーカー企業のIT推進に参加しま…
■事業概要 自動車買取から販売、修理までを一貫して手掛け、自社内で完結することが強み。また、ITを…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(正社員) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・HT… | |
[開発PM]大手通信キャリアポータルサイト…
■具体的な業務内容 ・現行システムへの仕様理解 ・開発要求定義のクライアントとのすり合わせ、…
週5日
1.6〜4.1万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【東京・文京区】BIシステムの新規機能開発…
- 仕事内容:既存BIシステムのデータ抽出画面の新規機能開発を担当します。 ※詳細は面談時に説明し…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データ抽出画面開発業務 |
| C#・VB.NET・SQL | |
定番
【インフラ案件】AWSクラウドサービス企画…
- 仕事内容: AWSクラウドサービスの企画から運営までを担当する業務です。サービス設計、環境提供…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浅草橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・AWS・・VMware・Sphere | |
【フロントエンドエンジニア】(React)…
サービス開発、マーケティング、XRソリューションと業界のプロフェッショナル達が集い、 それぞれのノ…
週3日・4日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React)_ハンズオン型受託開発 |
| JavaScript・-・Vue.js・・React… | |
定番
【フルリモート】新規立ち上げサービスのサー…
■仕事内容 新機能や海外向けを含む新規サービスの開発、開発・運用における環境改善、課題解決 …
週4日・5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(PHP/Java) |
| PHP・Java・言語:・PHP(Symphony)… | |
定番
【SAP】製造業向け基幹システムSAP開発…
【案件概要】 - 製造業向け基幹システムSAP開発支援 【業務内容】 - SAP/ABAP…
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | SAPエンジニア |
| ABAP・HANA | |
定番
【製造業向け基幹システムにおけるSales…
【案件概要】 - 製造業向け基幹システムにおけるSalesforce開発支援 【業務内容】 …
週5日
500,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| ABAP・HANA | |
定番
【Go,Typescript,Vue.js…
下記のような基盤(マイクロサービス化)の開発をお願いいたします。 -通知基盤 -メール配信基盤 …
週5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Go・Typescript・V… | |
注目
[React/Vue]金融ポータルサイトの…
■具体的な業務内容 ・現行システムへの仕様理解 ・Reactによるユーザー画面開発 ・Vue.…
週3日・4日・5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
[Go]金融ポータルサイトの機能追加の開発
■具体的な業務内容 ・現行システムへの仕様理解 ・Go言語でのクラウドネイティブなWebアプリケ…
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池尻大橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
新着
定番
【リモート可 / Android / 週5…
■主な業務内容 ・KotlinでのAndroidアプリの新規機能追加・既存改善 ・Andro…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・-・・ | |
注目
[VC(Visual Creative)]…
【業務内容】 所属アーティストと音楽に関わるビジュアルコンテンツ制作過程を進行します。 【業…
週5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作 |
定番
【Webディレクター】Web戦略設計コンサ…
【業務内容】 ・クライアントへのヒアリング・課題抽出 ・戦略設計、企画(Webコンセプト立案、コ…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【Java/フルリモ】漫画家向けプラットフ…
【企業概要】 マンガクリエーターと読者をつなげる『D2C事業』やWebマンガ誌を構築・運営する『マ…
週5日
470,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot | |
定番
【フルリモート/Javascript/週5…
【案件概要】 - 生成系AIを活用したWebアプリのPoC開発支援 【業務内容】 - 国内…
週5日
670,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Azure | |
定番
【フルリモート/PHP/週5日】駐車場管理…
【案件概要】 - 駐車場管理システムのサーバーサイド開発 【業務内容】 - 駐車場管理シス…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Larave・jQuery・Vue.js | |
定番
【フルリモート/TypeScript/Ru…
【案件概要】 - HR領域サービスのWebアプリケーションのサーバーサイド開発 【業務内容】…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Typescript・RubyonRail… | |
定番
【フルリモート/Java/週5日】Java…
【案件概要】 - 小売企業向けアーキテクト支援(Java/AWS) 【業務内容】 - 小売…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・AWS | |
定番
【フルリモート/Angular/週5日】教…
【案件概要】 - Angularを使用した、教育業向けタブレットアプリの機能拡張支援を行うプロジェ…
週5日
470,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・Angula… | |
定番
【フルリモート/TypeScript/週5…
【案件概要】 コンシューマー向けの終活・家族間コミュニケーション支援アプリの開発プロジェクトです。…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Native | |
定番
【フルリモート/TypeScript/Ne…
【案件概要】 コンシューマー向けの終活・家族間コミュニケーション支援アプリの開発プロジェクトです。…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Typescript・React・Native | |
定番
【リモート可/AWS/週5日】プライベート…
グループ会社向けのプライベートクラウド基盤提供サービスのアカウントSEとして、サービス利用者からの各…
週5日
930,000〜1,430,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS・OracleDB・ | |
定番
【リモート可/AWS/週5日】プライベート…
子会社や自社内の事業部門へ共通基盤を提供している基盤チームのPMO(サブリーダーポジション)として参…
週5日
840,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿三田 |
|---|---|
| 役割 | PMO(インフラ) |
| AWS | |
定番
【フルリモート/PHP/週5日】国内最大手…
国内最大手ポータルサイトの検索機能の改修を担うサーバーサイドエンジニアを募集します。 新規立ち上げ…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Zend・CakePHP・MySQL | |
定番
【リモート可/Java/週5日】アプリケー…
アプリデータを収集するサーバの開発業務を担うJavaエンジニアを募集します。 担当工程は追加開発〜…
週5日
580,000〜770,000円/月
| 場所 | 品川浜松町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモート/PM/コンサル/週3日】医…
医療サービスの新規事業化に伴い、コンサルタント・プロジェクトマネージャーを募集します。 新サービス…
週3日
390,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川三田 |
|---|---|
| 役割 | コンサル |
定番
【Ruby】急成長ToBサービスのRuby…
【業務内容】 ・自社サービスのサーバーサイド開発 └要件定義〜を想定 └10名以下の組織で特許…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋水道橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週5日…
【業務内容】 ・開発計画に基づく新機能のフロントエンド開発 ・ユーザーフィードバックなどを元にし…
週5日
580,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ・フロントエンド:JavaScript・React・… | |
定番
※短期案件※【Python】自社サービスの…
【業務内容】 ・Pythonを使ったサーバーサイドの設計、開発、運用
週5日
620,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・・React・および・TypeScri… | |
定番
【Ruby/テックリード】大手フィットネス…
【業務背景】 ・1次開発(リリース)を終えたtoC向けアプリ(会員30万人が使用)について、ベンダ…
週4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails | |
【Androidエンジニア】大手フィットネ…
【業務背景】 ・昨年10月にリリース済のフィットネスアプリについて、元々ベンダーだった体制を社員+…
週4日・5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・AndroidJava・Kotlin | |
【コンサル】新規事業立ち上げ・サービス開発…
【業務内容】 ・ジムにおける複数の新サービス・新規事業(セルフエステ、ゴルフ等々)の検討と実行推進…
週5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | コンサル |
定番
【Python】AI技術を活用した新規サー…
■具体的な職務内容 ・AI自社プロダクトの開発 ・AIソリューション事業にて提供するソフトウ…
週2日・3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(Python) |
| Python・クラウド:主にAzure(一部GCP)… | |
定番
【PM/フルリモ】大手フィットネス企業にお…
【業務内容】 ・各チーム(フロント、バックエンド、インフラ)の取りまとめを通じたプロジェクト課題管…
週5日
790,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【PM/フルリモ】大手フィットネス企業にお…
【業務背景】 複数の事業(パーソナルフィットネス事業、事業等)をまたぐID基盤の構築を背景に、フィ…
週4日・5日
840,000〜1,350,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【Python】自社プロダクトのサーバーサ…
当社の自社プロダクトの開発に携わって頂きます。 自治体の農地調査に関する課題を解決することを目的と…
週5日
580,000〜620,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸石生駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】アプ…
アーキテクト部隊にて、他事業部が実行しているプロジェクトに参画いただきます。 プロジェクトメン…
週5日
580,000〜770,000円/月
| 場所 | 豊洲フルリモート |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・-・Spring・EIP | |
定番
【フルリモ /Go / 週5日】大手半導体…
【業務概要】 大手半導体業界メーカーのデータ収集基板構築(オンプレサーバー上にて構築)に伴い、シス…
週5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Java・Go・Kubernetes | |
定番
【リモート可/Ruby/週5日】Lv4自動…
【業務概要】 Lv4自動運転によるモビリティサービスの実現に向けた、クラウドプラットフォームのアプ…
週5日
570,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京京浜急行羽田線 天空橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・A… | |
定番
【フルリモ/PHP/JavaScript/…
【業務概要】 WebRTCを利用したライブ配信サービスにおいて配信機能の設計、視聴、開発をご担当い…
週5日
670,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【フルリモ/React/週5日】ライブ配信…
【業務概要】 WebRTCを利用したライブ配信サービスにおいて配信機能の設計、視聴、開発をご担当い…
週5日
700,000〜1,040,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ty… | |
定番
【Java / 週5日】生命保険会社向けW…
・Javaを使ったWebシステムの脆弱性の改善 既にあるリストに対して、改善策を検討し、対応してい…
週5日
470,000〜580,000円/月
| 場所 | 豊洲赤坂 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Java | |
定番
【リモート相談可 / Linux / 週5…
・設計、構築、移行、運用試験及び手順の作成 クラウドへのWEBシステムの構築を行うための構成の検…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木御茶ノ水 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【動画広告編集】国内最大級CtoCアプリに…
▶YouTube・Twitter・TikTokなどSNS動画広告の編集業務 ∟既存広告のリサイズ…
週2日
40,000〜160,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作 |
| 想定稼働時間:月50時間程度 ※繁忙期の4~5月・… | |
定番
【フルリモ/React/週5日】HRテック…
【業務概要】 HRテックシステムの新機能開発、機能改善をご担当いただけるフロントエンドエンジニアを…
週5日
700,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PHP(Laravel) …
【業務内容】 ・新規プロダクトの開発 └技術選定、実装、開発チーム内コードレビュー等々
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモ/PHP/週5日】マーケティング…
【業務概要】 マーケティング人材育成サービス開発を担う、PHPエンジニアを募集いたします。 SE…
週5日
530,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【Azure / 週5日】某交通系会社にお…
【業務内容】 保全環境の認証機能に関わる設計/構築作業をご担当いただける方を募集いたします。 …
週5日
580,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿高田馬場 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| Azure | |
定番
【リモート可 / AWS / 週5日】自動…
【業務内容】 自動車リサイクル処理を適正に管理運用するためのシステムをクラウドに再構築するプロジェ…
週5日
580,000〜770,000円/月
| 場所 | 神奈川新川崎 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】大…
【業務内容】 設計、構築、移行、運用試験及び手順の作成。クラウドへのWEBシステムの構築を行うた…
週5日
970,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Vue.js・An… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】AWS…
【業務内容】 24/365型のAWS MSPサービスの事業拡大に伴うサービス改善・向上を担うSRE…
週5日
670,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
インフラ基盤運用の維持保守が中心となりますが、一部設計構築作業も依頼する予定です。 Solaris…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VMwareESXi・vCener・Redhat・L… | |
定番
【リモート相談可 / AWS / 週5日】…
【業務内容】 某顧客のインフラ環境におけるAWS構築支援業務をいただける方を募集いたします。 A…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浦田 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS | |
定番
【Oracle / 週5日】某財団法人にお…
■案件概要 自動車リサイクル処理を適正に管理運用するためのシステムを再構築するプロジェクトです。 …
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川新川崎 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Oracle・AWS | |
定番
【Kotlin/フルリモ】大手フィットネス…
【業務背景】 ・昨年10月にリリース済のフィットネスアプリについて、元々ベンダーだった体制を社員+…
週5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Kotlinエンジニア |
| Kotlin・ | |
定番
【Java / 週5日】営業顧客システムで…
・総合色彩化学メーカにて稼働している営業顧客システム(SAP)の保守開発に従事頂きます。 ・リーダ…
週5日
380,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿十条 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Oracle・AWS | |
定番
【リモート / AWS / 週5日】大規模…
・AWS上にDWH基盤構築を行うプロジェクトにご参画頂き、以下作業を実施頂きます。 - ドキュメ…
週5日
670,000〜710,000円/月
| 場所 | 神奈川豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート可 / PM / 週5日】基幹シ…
【業務内容】 クライアントの基幹システムの保守運用プロジェクトにおけるPMやPL(テックリード)の…
週5日
720,000〜750,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Java8・Linux・AWS・backlog・Te… | |
定番
【リモート可 / テスター / 週5日】警…
【業務内容】 クライアントの基幹システムのクラウドシフトと業務システムの新規開発プロジェクトにご参…
週5日
750,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿十条 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】官…
【業務内容】 官公庁職員が使用する情報系システムの更改プロジェクトにご参画頂きます。 …
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】顧客…
【業務内容】 会計ソフト製品開発メーカーでの、社内インフラ環境の構築/運用保守プロジェクトにご参画…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
UIUXデザイナー/UIUXディレクター
<業務内容> ・新規サービスやプロダクトにおけるUX設計 ・既存サービスやプロダクトにおけるUX…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿二子玉川駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー/UIUXディレクター |
定番
【インフラ / 週5日】金融系システム管理…
・行員様の補佐となり部内メンバー(行員)の案件PMO ・行員様の案件状況取りまとめや進捗フォロー …
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿内幸町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| SONYのSeatouch(座席予約)・Bizrob… | |
定番
【Flutter】ヘルスケア業界のオンライ…
<業務内容> ヘルスケア業界のオンライン診療予約アプリ開発をご担当いただきます。 Flutter…
週4日・5日
410,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter | |
定番
【基盤構築エンジニア】大手HR事業のデータ…
【案件概要】 弊社クライアント(HR系)のデータマネジメント部署にて、BIエンジニアとしてTabl…
週5日
410,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | データ分析基盤開発エンジニア/データエンジニア |
| AWS・GCP・Azure | |
定番
【PM】大手ふるさと納税サイトの開発におけ…
【案件概要】 ふるさと納税サイトの新規機能や新サービスに伴う開発のプロジェクトマネジメント業務を担…
週5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| - | |
定番
【SQL/RedShirt,BigQuer…
【案件概要】 クライアント(HR系)のデータ事業部にてデータ抽出業務を担当いただきます。 (主に…
週2日・3日
250,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| - | |
定番
【Webマーケター】日本最大級の音楽・エン…
【案件概要】 日本最大級の音楽・エンターテインメント企業のWebマーケティング業務をご担当いただき…
週3日・4日・5日
410,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | webマーケター |
| - | |
定番
【PM/データマート設計】大手HR事業のデ…
【案件概要】 国内最大級の転職サービスにおいて、データドリブン事業運営を構築するため、膨大なデー…
週5日
410,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| - | |
定番
【Java |基本リモート】バックオフィス…
<案件概要> メディア事業のバックオフィスの構築システム開発(Java)
週5日
580,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / リードエンジニア / 週4…
【業務概要】 医師向けのWebサービスの開発/運用/保守業務にリードエンジニアとして携わって頂きま…
週4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Node… | |
定番
【リモート / インフラ / 週5日】ED…
【業務内容】 受発注を行っているEDIプラットフォームの更改業務をお任せできる方を募集いたします。…
週5日
630,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川品川シーサイド |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ACMS | |
定番
【リモート / Java / 週5日】国内…
【業務内容】 決済代行システムのエラー発生時の原因調査、解消対応を対応いただきます。 【業務…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Linux | |
定番
[JavaScript]フロントエンド、サ…
■業務内容 オフィシャルサイト(証券)告知要件においてのフロントエンド、サーバ管理業務 ■求…
週4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
【業務内容】 フロントエンドの実装業務をご担当いただけるフロントエンドエンジニアを募集いたします。…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Typescript・React・MUI・A… | |
【リモート可 / フロントエンド / 週3…
【業務内容】 弊社が開発する脳科学×AIプロダクトのフロントエンド開発をご担当いただきます。 …
週3日・4日・5日
330,000〜840,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】AWS…
【業務内容】 オンプレDCからAWS環境へのシフトを検討されているクライアントにて、企画検討フェー…
週5日
740,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・Terraform | |
定番
【フルリモ / Go/Java / 週5日…
【業務内容】 新システムへの移行(Goで構築)にあたり、業務支援を頂ける方を募集いたします。 …
週5日
690,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・Go | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】H…
開発計画に基づく新機能のフロントエンド開発者を募集します。 【作業内容】 ・ユーザーフィード…
週5日
670,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【リモート可 / JavaScript /…
【業務内容】 自社PLMパッケージシステムの開発部門にてJavaScript、Vue.jsを使用し…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿センター南 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Eclipse・VisualS… | |
定番
【フルリモ / Azure / 週5日】デ…
Azureをベースとしたプラットフォーム開発のインフラ要員を募集します。 【案件詳細】 小売…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Azure | |
定番
【フルリモ / テスター / 週5日】某製…
【業務内容】 某製造業向けのシミュレーション業務のWeb化を対応を頂ける方を募集いたします。 …
週5日
640,000〜710,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | テスター |
定番
【リモート / AWS / 週5日】基幹シ…
【業務内容】 AWSを利用した基幹システムに対して、以下対応をいただける方を募集します。 【…
週5日
740,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿紀尾井町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / システムアーキテクト/PM…
情報システム刷新にあたり、外部人材を採用しようと考えております。 【業務内容】 ・各種の既存…
週2日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 【システムアーキテクト・PM】システムアーキテクチャーの全体統括 |
| ・ | |
定番
【リモート可 / 上流SE / 週5日】P…
【業務内容】 某パッケージメーカーにてパッケージ製品の改修やカスタマイズが定期的に発生するため、対…
週5日
510,000〜600,000円/月
| 場所 | 神奈川センター南 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| Windows・VB6.0 | |
定番
【AWS / 週5日】医療保険関連システム…
【業務概要】 本番稼働中のシステムに対する追加開発・改修をご担当いただける方を募集いたします。 …
週5日
630,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート / インフラ / 週5日】某ネ…
【業務概要】 某ネットバンクインフラ基盤の設計、構築、運用、保守業務をご担当いただける方を募集いた…
週5日
660,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川新橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| VMwareESXi・vCener・Redhat・L… | |
定番
【セキュリティ】大手SIer向け、セキュリ…
【案件内容】 大手SIerがセキュリティサービスの案件が増えてきたことにより、社内共有資料の作成を…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【インフラエンジニア(AWS)|フルリモー…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・ | |
定番
【ITコンサル/基本リモート】帳票コンサル…
【募集背景】 帳票サービスの新規導入、導入後サポートをメインにしておりますが、 事業拡大に伴う体…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ITコンサル(プリセールス) |
定番
【イラストレーター】広告漫画制作
LPや広告に使用される漫画の制作を担当していただきます。 イラストやキャラクターの制作から、商品の…
週1日
40,000〜90,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | イラストレーター |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】大手半導…
システム構築・データ処理などのプログラム開発、パフォーマンス検証等をご担当いただける方を募集します。…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 神奈川センター南 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Java・Go・Kubernetes・… | |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
警備会社向けシステム構築における基幹システムのクラウドシフトと業務システムの新規開発をしています。 …
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| JavaScript・Python・AWS(Boto… | |
定番
【ECマーケティング企画】スマート家電を中…
仕入れ先4,000社、販売パートナー10,000社、 ディストリビューターとして圧倒的な強さ。 …
週2日・3日・4日
330,000〜470,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京リモート |
|---|---|
| 役割 | 【ECマーケティング企画】スマート家電を中心とした自社ECモールのマーケティング |
| SQL・・ | |
定番
【ディレクター】大手化粧品業界の店舗DX化…
【案件概要】 DX推進責任者(顧客)をサポートしながら、下記の内容を円滑に進めるディレクター要員を…
週5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| - | |
定番
[Flutterエンジニア]ネイティブアプ…
【業務内容】 ネイティブアプリ(Flutter)の開発を担当していただきます。 テックリードクラ…
週4日・5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿代々木公園駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
【Rubyエンジニア】入札情報一括検索・管…
【業務内容】 官公庁・自治体等の入札・落札情報を探せる自社サービスの機能開発・保守開発をご担当いた…
週5日
670,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Ruby on Rails エンジニア|入札情報一括検索・管理システムの開発・保守 |
| HTML・JavaScript・Ruby | |
定番
【EC戦略マネージャー】通信キャリアグルー…
【企業】 仕入れ先4,000社、販売パートナー10,000社、ディストリビューターとして圧倒的な強…
週2日・3日・4日・5日
580,000〜840,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京リモート |
|---|---|
| 役割 | 【EC戦略マネージャー】通信キャリアグループのEC事業戦略の立案 |
定番
【リモート / インフラ / 週5日】公営…
現行システムを次世代システムに移行を行っており、現行システムから新システム構想に移行していただける方…
週5日
660,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川東京駅/京橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| サーバ(Linux・Unix・Windows)・ネッ… | |
定番
【RPA / 週5日】金融機関向けWinA…
WinActorのシナリオ開発中心にマクロ(VBA)とUipathによる開発/保守も対応できる方を募…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア |
| VBA・WinActor・Uipath | |
注目
【リモート可 / Javascript /…
航空業におけるAWS上のアプリケーションのフロンド開発をお願いできる方を募集します。 【業務内…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・AWS・Node.js | |
注目
【リモート可 / Typescript/J…
建設会社におけるファイル管理WEBシステムのフロント開発を行なっていただける方を募集します。 …
週5日
450,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
注目
【リモート可 / インフラ / 週5日】建…
データ連携APIアプリケーションの開発・テストをお願いできる方を募集します。 お願いする業務は詳細…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Typescript・AngularJS・Node.… | |
注目
【リモート / インフラ / 週5日】社内…
社内プライベートクラウドのNWの構築、運用をお願いできる方を募集します。 【作業内容】 ・機…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川三鷹 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| CiscoNexus7000番シリーズ | |
注目
【リモート可 / PM / 週5日】外資生…
外資系生保会社の代理店向け営業支援システムのリニューアルに伴い、PM支援業務をお願いできる方を募集い…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川乃木坂 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・- | |
注目
【社内SE / 週5日】OPEN領域(複数…
有識者SEとOPEN領域(複数システム)の維持保守作業を行っていただける方を募集します。 【作…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| JavaScript・Java・OS:Linux(S… | |
定番
【Vue/フルリモ】エンタメ系ECシステム…
エンタメ系ECシステムの追加開発で、フロントエンドエンジニア(Vue.js)を募集します。 【…
週5日
410,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Vue.js | |
定番
【フルリモ / PM / ToC】ネットシ…
■募集ポジションについて 本ポジションでは、ネットショップ作成サービスの決済サービスの開発において…
週5日
500,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【社内SE / 週5日】業務アプリケーショ…
某ネットバンクインフラ基盤の設計、構築、運用、保守業務をお願いできる方を募集します。 【業務内…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 品川千駄ヶ谷 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| C#・SQLServer・AWS | |
定番
【社内SE / 週5日】OPEN領域(複数…
有識者SEとOPEN領域(複数システム)の維持保守作業を行っていただける方を募集します。 【作…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 埼玉和光市 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| JavaScript・Java・Linux(Serv… | |
定番
【リモート可 / Javascript /…
航空業におけるAWS上のアプリケーションのフロンド開発をお願いできる方を募集します。 【業務内…
週5日
500,000〜610,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・AWS・Node.js | |
定番
【リモート可 / Typescript/J…
建設会社におけるファイル管理WEBシステムのフロント開発を行なっていただける方を募集します。 …
週5日
450,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】建…
データ連携APIアプリケーションの開発・テストをお願いできる方を募集します。 詳細設計~テストをお…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Typescript・AngularJS・Node.… | |
定番
【リモート / インフラ / 週5日】社内…
社内プライベートクラウドのNWの構築、運用をお願いできる方を募集します。 【作業内容】 ・機…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川三鷹 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| CiscoNexus7000番シリーズ | |
定番
【リモート可 / PM / 週5日】外資生…
外資系生保会社の代理店向け営業支援システムのリニューアルに伴い、PM支援業務をお願いできる方を募集い…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川乃木坂 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・- | |
定番
【リモート可 / Java / 週5日】A…
某ユーザーにおいてのAWS上のアプリ開発業務を対応いただける方を募集します。 【作業内容】 …
週5日
620,000〜750,000円/月
| 場所 | 埼玉蒲田 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Java・Node.js・Vu… | |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】取…
取引所システム内のインフラ構築をお願いできる方を募集します。 ActiveDirectory、及び…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 豊洲新豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ActiveDirectory・Windows・Se… | |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】建…
建機レンタル向けアウトソーシングサービスのインフラ保守をお願いできる方を募集します。 【主な作…
週5日
370,000〜460,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町神谷町 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・Windows・AWS | |
定番
【UI/UXデザイナー】経営管理支援新規プ…
【業務内容】 ・新規プロダクトの体験の設計 ・プロトタイピングの作成・検証 ・デザインシステム…
週5日
580,000〜920,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【マーケター/ディレクター】顧客のCVを最…
【業務内容】 コミュニケーションプランナー(マーケター)として、顧客のCVを最大化するためのプラン…
週4日・5日
670,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | リードコミュニケーションプランナー |
| ・ | |
定番
【Azure|リモート可】自社のAIサービ…
※本案件は、将来的に業務委託→正社員切り替え可能な方を中心に募集しております※ <お任せしたい…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(SRE) |
定番
【Azure|リモート相談可】AI技術を活…
■具体的な職務内容 ・インフラエンジニア(Azureでの開発) ・インフラストラクチャーの設計 …
週2日・3日・4日・5日
410,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(Azure) |
| クラウド:主にAzure(一部GCP) 言語・フレ… | |
定番
【インフラ / 週5日】非鉄器金属系ユーザ…
非鉄貴金属系ユーザー向けのサイバ―セキュリティー展開支援作業をお願いできる方を募集します。 【…
週5日
670,000〜710,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
【Swift/フルリモ】大手フィットネス企…
【業務背景】 ・昨年10月にリリース済のフィットネスアプリについて、元々ベンダーだった体制を社員+…
週5日
840,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Swiftエンジニア |
| Swift | |
定番
【一部リモート / PHP / 週4日〜】…
自社システムにおけるサーバーサイド開発をお願いできる方を募集いたします。 自社で利用しているトラッ…
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・ | |
定番
【リモート / Python / 週5日】…
ヘルスケア関連事業における社内データの可視化PJに参画いただける方を募集します。 【作業内容】…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Python(PySpark・・pan… | |
定番
【Laravel|フルリモート】システム開…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(twisted) |
定番
【フルリモートOK!Python講師案件】…
【業務内容】 Python、AI・機械学習、データ分析分野のオンラインプログラミングスクールにおけ…
週2日
180,000〜230,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Python講師 |
| Python | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】遊技機…
【業務内容】 某遊技機メーカーが運営するホール向けECサイトの追加開発をご担当いただける方募集いた…
週5日
440,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Sm… | |
定番
【リモート / React/Next.js…
【企業概要】 徹底的な顧客目線でプロジェクトに伴走、顧客と共に新しい価値を創出します。 スタート…
週5日
690,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Next.js | |
定番
【フルリモ / COBOL / 週5日】生…
生保向け統合パッケージシステムの保守〜改修等を担うCOBOLエンジニアを募集いたします。 担当工程…
週5日
740,000〜920,000円/月
| 場所 | 東京23区以外調布 |
|---|---|
| 役割 | COBOLエンジニア |
| COBOL | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】Go開発…
【具体的な業務】 ・自社サービスのバックエンドシステム開発及び関連するアプリケーションの実装 ・…
週5日
500,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Swift・Kotlin・Go… | |
定番
【フルリモ / VB.NET / 週5日】…
化学工場の製造実行システム(MES)構築における開発全般をご担当いただける方を募集します。 【…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 神奈川みなとみらい |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| VB.NET・RDB | |
定番
【大手SIer|フルリモートOK|インフラ…
【具体的な業務内容】 ・AWS構築〜運用までを担当として複数案件に横断的に参画していただきます。 …
週4日・5日
410,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS) |
| JavaScript・PHP・Go・AWS・Lamb… | |
定番
【一部リモート / AWS / 週5日】ク…
AWSのサービス構成のチェック~設計、構築をお願いできる方を募集します。 ■担当業務 ・Am…
週5日
670,000〜730,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町東陽町 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AmazonFSxforWindowsFileser… | |
定番
【フルリモ / PMO / 週5日】Tab…
Tableau基盤のオンプレからクラウド移行に伴い、タスク管理、課題管理等PMOとしての役割を担って…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 東京23区以外田町 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Tableau | |
定番
【C/C++ / 週5日】車載セキュリティ…
車載セキュリティにおける機能開発を支援いただける方を募集します。 【業務内容】 ・車載システ…
週5日
470,000〜510,000円/月
| 場所 | 東京23区以外鴨居 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| C・C++・Linux | |
定番
【リモート可 / PHP / 週5日】スマ…
スマートフォンアプリに関連したWebAPIまたはWEBサイト開発に携わっていただける方を募集します。…
週5日
630,000〜710,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木中目黒 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| JavaScript・PHP・LAMP・Zend・L… | |
定番
【セールスライター】ToC新サービスLPに…
・急成長中サービスのライティング業務 ・LPのライティング業務
週1日・2日・3日・4日・5日
250,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ライター【LP】 |
定番
【フルリモ / Python / 週5日】…
AI、機械学習等の評価に伴うデータ分析〜資料作成をいただける方を募集いたします。 Python、E…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Word・Excel・PowerPoi… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】基幹シ…
【業務内容】 ユニフォームのレンタル・リース・販売・クリーニング事業を展開するエンド企業にて基幹シ…
週5日
580,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】大手エ…
DVDやCD、本などを扱う通販サービス、ユーザー同士で中古品などの売買を行うマーケットプレイスサービ…
週5日
530,000〜600,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・LAMP | |
定番
【リモート可 / PL/SQL / 週5日…
ERPパッケージPositiveのアドオン開発をご担当いただける方を募集いたします。 主な業務は機…
週5日
450,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木三田 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| PL・SQL | |
定番
【リモート可 / Typescript/R…
【業務概要】 建設会社系WEBシステムのフロントエンド開発をご担当いただける方を募集いたします。 …
週5日
470,000〜550,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【フルリモ / AWS / 週5日】化学/…
化学/素材業界企業向けのインフラ対応を頂ける方を募集します。 【業務詳細】 ・情シス部門から…
週5日
810,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・SQL・Server・Windows | |
定番
【AWS / 週5日】サーバー(AWS)の…
電力サービスで実施するキャンペーン施策を管理するサーバー(AWS)の新規開発に伴う受入試験をお願いで…
週5日
810,000〜840,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| AWS・CloudWatch | |
定番
【リモート可 / Salesforce /…
銀行向けSalesforce保守運用プロジェクトにおけるPL業務をお願いできる方を募集します。 …
週5日
810,000〜840,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | SalesForceエンジニア |
| Salesforce | |
定番
【リモート可 / PHP / 週5日】エン…
エンタメ向けのECシステム開発をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】 ・映画関連 既存…
週5日
550,000〜580,000円/月
| 場所 | 品川大崎 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・LAMP・ZendFramework・Bac… | |
定番
[ディレクター/フルリモート]社内システム…
【案件内容】 ・主に事業部でExcelやSpread Sheetで管理運用している情報を概要設計を…
週4日・5日
570,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | システムアナリスト |
| ‐ | |
定番
【PM|フルリモート】システム受託開発のP…
■具体的な仕事内容 ・各種プロジェクトのテクニカルディレクション、プロジェクトマネジメント ・各…
週4日・5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(テクニカルディレクター) |
定番
【インフラ|フルリモート】システム受託開発…
■仕事の概要 当社では、成長戦略×テクノロジーを武器に企業様のビジネスやマーケティングの支援を通し…
週4日・5日
500,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データ(インフラ)エンジニア |
| ・ | |
定番
【PHP|フルリモート】(自社開発)国内最…
【業務内容】 毎年22兆円もの「商品」が、使われることなく企業から廃棄されている現状をご存知ですか…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 品川西五反田 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Python・Ruby・Perl・FuelP… | |
定番
【UIUXデザイナー】新製品のUI/UXデ…
この度、新製品の立ち上げを行うこととなりました。 この新製品は会社の意思決定プロセスを支援すること…
週5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | UIUXデザイナー |
定番
【上流SE|フルリモート】士業向け案件管理…
【業務内容】 ・士業向け案件管理システムの新機能追加・改善の要件定義及び企画書作成 └要件定義、…
週5日
460,000〜580,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【一部リモート / AWS / 週5日】A…
AWS上のシステムの設計・構築・テスト・運用をお願いできる方を募集します。 【作業内容】 ・…
週5日
640,000〜670,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・Apache・APサーバ(Tomcat・… | |
定番
【リモート可 / React/Vue.js…
求人掲載サイトにおけるクライアント管理サイトのフロント開発をお願いできる方を募集します。 主にお願…
週5日
640,000〜670,000円/月
| 場所 | 池袋小川町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Vue | |
定番
【フルリモ / Go / 週5日】バックエ…
バックエンド開発および関連するアプリケーションの実装をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】 …
週5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Swift・Kotlin・Go… | |
定番
【フルリモ / Ruby/JavaScri…
ECプラットフォームの開発支援業務をお願いできる方を募集いたします。 新機能開発をメインでご担当い…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【フルリモ / Ruby/JavaScri…
ECプラットフォームの開発支援業務(運用・保守)をお願いできる方を募集します。 【業務内容】運…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | 運用/保守エンジニア |
| JavaScript・Ruby・RubyonRail… | |
定番
【PHP|フルリモート】自社サービス(Wo…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(WordPress) |
| PHP | |
定番
【リモート可 / Python/PHP/P…
toC向けサービスの開発・保守・改修業務をご担当いただける方を募集いたします。 【業務詳細】 …
週5日
700,000〜800,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町乃木坂 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Perl・MySQL・Memc… | |
定番
【リモート可 / Scala / 週5日】…
顧客システムへの自社プロダクト運用保守業務をご担当いただける方を募集いたします。 【業務詳細】…
週5日
550,000〜630,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町浜松町 |
|---|---|
| 役割 | Scalaエンジニア |
| Scala・React・Vue.js・AWS・Mon… | |
定番
【リモート可 / Swift/Object…
toC向けマッチングアプリ(iOS)の開発をご担当いただける方を募集いたします。 【業務詳細】…
週5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川乃木坂 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週5日…
旅行関連事業に係るスマホアプリ開発(Flutter)ご担当いただける方を募集いたします。 Andr…
週5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Java・Swift・Kotlin・Firebase… | |
定番
【PMO支援/オンサイト→リモート】大規模…
【案件概要】 大規模開発プロジェクトの全体PMO支援/DX推進支援 コーポレート戦略案件等、複数…
週5日
330,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【リモート可 / Swift/Object…
toC向けマッチングアプリ(iOS)の開発をご担当いただける方を募集いたします。 【業務詳細】…
週5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 品川乃木坂 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C | |
定番
【大手SIer|フルリモートOK|フロント…
【案件内容】 iPadアプリをWebアプリケーションにリプレース 現在実装フェーズで実装要員が不…
週5日
410,000〜800,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【フルリモ / Angular / 週5日…
特殊データ集計サービスのフロントエンドの開発業務をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】 …
週5日
570,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Angular・BEM・CSS | |
定番
【TypeScript / 週5日】AI画…
AI画像検査システム開発におけるフロントエンド開発をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】…
週5日
570,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京勝どき |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Vue.… | |
定番
【フルリモ / React/TypeScr…
中規模ECサイトにおけるフロントエンド開発をお願いできる方を募集します。 ECサイトのフロントエン…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Next.js・R… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】旅…
旅行会社向けのフロントエンド開発をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】 ・要件の整理/…
週5日
750,000〜880,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・Typescript・React・Redux… | |
定番
【リモート可 / インフラ / 週5日】顧…
顧客システムネットワークの維持運用をお願いできる方を募集します。 オンプレ環境からクラウドへの移行…
週5日
410,000〜460,000円/月
| 場所 | 秋葉原築地 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Cisco・Linux | |
注目
[サーバーサイド|リモート相談可能]最大級…
◾️ 業務内容 ・開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 -機能開発における設計~実装~…
週5日
550,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
急募
【フルリモ / React / 週4日〜】…
【業務内容】 CS部門が使用する内部ツールの開発、自社実装のキャンペーンツールの設定作業(一部JS…
週4日・5日
330,000〜920,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| CSS・JavaScript・Typescript・… | |
定番
【Java案件|リモート可能】システム開発…
■作業内容 ・運用保守(窓口受付対応、詳細設計、実装・テスト、本番リリース準備、初動確認) ・開…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲品川シーサイド駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Java、SQL | |
定番
【リモート可 / AWS / 週5日】AW…
AWS環境における維持運用をお願いできる、AWS設計構築経験者を募集いたします。 【業務詳細】…
週5日
610,000〜720,000円/月
| 場所 | 豊洲築地 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS | |
定番
【リモート可 / 開発ディレクター / 週…
自社プロダクト開発支援を担う開発ディレクターを募集いたします。 【業務詳細】 ・開発スケジュ…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【リモート可 / 運用保守 / 週5日】パ…
パッケージ運用、保守支援、リーダー(補佐)業務をお願いできる方を募集いたします。 【業務詳細】…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | 保守/運用エンジニア |
定番
【テクニカルサポート / 週5日】デバッグ…
テクニカルサポート業務をご担当いただける方を募集いたします。 【業務詳細】 ・モンキーチェッ…
週5日
250,000〜330,000円/月
| 場所 | 埼玉小川町 |
|---|---|
| 役割 | テクニカルサポート |
定番
【フルリモ / Salesforce / …
SaaS企業のSalesforceシステム保守、Apexの修正および新規機能開発をお願いできるエンジ…
週5日
530,000〜630,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京日本橋 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforc | |
定番
【フルリモ / PostgreSQL / …
PostgreSQLでのテーブル構築、データ生成、FUNCTION作成をお願いできるエンジニアを募集…
週5日
530,000〜630,000円/月
| 場所 | 池袋田町 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| SQL・PostgreSQL | |
定番
【リモート可 / Active Direc…
クライアント向けサーバーの維持運用業務をお願いできる方を募集いたします。 主にADサーバーをご担当…
週5日
530,000〜630,000円/月
| 場所 | 豊洲築地 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Active・Directory | |
定番
【リモート可 / Vmware / 週5日…
仮想基盤(VMware)移行をお願いできる方を募集いたします。 【業務詳細】 ESXi、VM…
週5日
470,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川国際展示場 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Vmware | |
注目
[Webディレクターアシスタント/校閲・テ…
【業務内容】 ・メール制作フォロー 制作物の確認&送り戻し指示出し等での制作進行フォローが…
週5日
160,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
【PM/フルリモート】AISaaSサービス…
【業務概要】 ・AI技術に関する当社プロダクトのネイティブアプリケーション開発全般及び 開発プロジ…
週5日
580,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| 言語:Flutter、TypeScript、Pyth… | |
定番
【Flutter/モバイルエンジニア】世界…
■Dartでクリーンなコードを記述し、コードの品質を確保 ■ファームウェア、バックエンド、その他の…
週4日・5日
410,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京 茅場町 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
定番
【SE / 週5日】品質管理部門での案件分…
第三者レビュー (システム要件、基本設計、総合テスト、受け入れテスト等)をお願いできる方を募集します…
週5日
620,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
定番
【Linux / 週5日】コンビニエンスス…
コンビニエンスストアシステムのインフラ運用をお願いできる方を募集します。 主な業務内容はサーバ監視…
週5日
330,000〜370,000円/月
| 場所 | 東京23区以外三鷹 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux | |
定番
【フルリモ / IBM COBOL / 週…
オフィス家具メーカーのシステム開発をお願いできる方を募集します。 対象:受発注で納期回答をする…
週5日
460,000〜510,000円/月
| 場所 | 豊洲芝公園 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| IBMCOBOL・JCL・IMS | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】航空…
ネットワーク利用会社(社内、グループ会社等)やベンダ各社、通信キャリアと各案件調整を行い推進いただけ…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ / VBA/VB/C / 週5…
不動産関連広告システム事業支援システム開発旧基盤から新基盤(AWS:Windows環境)への移行案件…
週5日
500,000〜580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| VBA・VB・AWS・Windowsサーバ・SQLS… | |
定番
【バックエンドエンジニア】スマートシティ化…
・職種 : バックエンドエンジニア ・概要 : スマートシティ化において、よりよい体験を利…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【フロントエンジニア】スマートシティ管理者…
<業務内容> ・スクラムチームでのアジャイル開発 ・スマートシティ構想における管理者向けポータル…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【バックエンドエンジニア】スマートシティデ…
<業務内容> ・スクラムチームでのアジャイル開発 ・スマートシティ構想におけるデータプラットフォ…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
[PM/フルリモート]社内システム統合構築
【依頼内容】 ・主に事業部でExcelやSpread Sheetで管理運用している情報を概要設計を…
週4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【AWS案件|リモート可能】AWSクラウド…
■案件内容 AWSクラウドサービス企画運営業務関連 ■作業内容 ・企画~基本設計の上流工程…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋事務所 JR浅草橋駅 ・秋葉原拠点:JR秋葉原駅" |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS) |
| Java・SQL・Java、SQL | |
定番
【フルリモート/フルスタックエンジニア】E…
プログラミング教育を中心にサービスを展開するEdTechのベンチャー企業です。 ■案件内容 …
週3日・4日・5日
710,000〜920,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Ruby・on・Ra… | |
定番
【BizDev Ops】自社チャットボット…
【業務内容】 ・CPP部門のオペレーション(データドリブン含め)企画・改善・仕組み設計 ・イン…
週3日・4日・5日
410,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | オペレーション整備 |
定番
【急募!フルリモートOK】社会人教育事業・…
【担当業務】 ・フロントエンド開発全般 ・ユーザビリティを高めるUI/UXの検討、実現 ・機能…
週5日
580,000〜800,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・-・PHP・… | |
定番
【急募!C#案件】産業機器のPC設定ソフト…
■案件内容 産業機器のPC設定ソフトndウェア開発に携わっていただきます。 ■作業内容 …
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海浜幕張駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・Oracle・Database | |
定番
【Kotlin / 週5日】POSレジ向け…
POSレジ向けAndroidアプリの設計、開発、評価をお願いできる方を募集いたします。 既存のシス…
週5日
580,000〜800,000円/月
| 場所 | 豊洲築地市場 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
定番
【リモート可 / React/Vue / …
求人掲載サイトのフロントエンド開発をお願いできる方を募集いたします。 担当工程:詳細設計/実装/単…
週5日
580,000〜670,000円/月
| 場所 | 埼玉小川町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Vue | |
定番
【リモート可 / JavaScript/T…
大手求人掲載サイトのリニューアル開発におけるフロントエンジニアのリーダーポジションを募集いたします。…
週5日
800,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 埼玉小川町 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・Reac… | |
定番
【リモート可 / Node.js / 週5…
某社独自開発パッケージの開発におけるSEを募集いたします。 【業務詳細】 パッケージ製品を各…
週5日
500,000〜630,000円/月
| 場所 | 秋葉原神谷町 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・Node.js | |
定番
【フルリモ / Go/Swift/Kotl…
■業務内容 スマホアプリの開発案件 ① Go / Reactによる開発 上記どちらか一…
週3日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・React・AWS | |
定番
【フルリモ / データエンジニア / 週3…
【業務内容】 Linux(MySQL,Python)とBigQueryを連携したマーケ帳票出力業務…
週3日・4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・MySQL、Linuxにおける… | |
【フルリモ / React/Next.js…
【業務内容】 ドラッグストアでのサイネージ型の商品販売システムの開発を行います。 React N…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・Next.js | |
【Webディレクター|リモート併用可能】W…
既存の大手クライアントのWebサイトに関するWebディレクターを募集いたします。 Webディレクシ…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【C++、C#】自社パッケージの開発
【業務内容】(詳細は、打ち合わせ時にお伝えします) ・弊社パッケージの開発 【開発環境】 …
週5日
390,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++・C# | |
定番
【フルリモOK|フロント案件】企業むけ災害…
■案件内容 今回は、企業むけ災害情報・危機管理情報配信SaaSのエンジニアを募集します。 【主な…
週5日
410,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・GCP・・Vue.js・・Ty… | |
定番
【Java案件】パーキング機器製品のソフト…
■作業内容(パーキング機器製品のソフトウェア開発案件) ・パーキング機器製品の開発業務(組込ソフト…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿菊名駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Java、SQL | |
定番
【PM】証券会社様向けの画面設計書作成
【業務内容】 ・画面設計書の作成(詳細設計等々) 【求める人物像】 ・コミュニケーションが…
週5日
590,000〜670,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神田駅 |
|---|---|
| 役割 | 画面設計書の作成 |
定番
【急募!Kotlin/基本リモート】動画ア…
■業務内容 ・動画アプリの設計 / 実装 / リファクタリング ・フレームワーク・ライブラリ等の…
週5日
330,000〜670,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | スマホエンジニア(Kotlin) |
| Kotlin・対応デバイス:Android(スマホ、… | |
定番
【フルスタックエンジニア】店舗管理システム…
【プロジェクト概要】 店舗が利用する管理用サイトのリニューアル案件、大規模案件、エンハンス案件の開…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Spting・Boot・・JUNIT | |
定番
【VBA / 週5日】官公系システム管理支…
官公系システムにおける管理支援をお願いできる方を募集します。 【業務詳細】 ・進捗管理、課題…
週5日
450,000〜470,000円/月
| 場所 | 神奈川武蔵小杉 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA | |
定番
【週4リモート / SQL/Python …
大手エネルギー会社におけるデータエンジニア、コンサルタントを募集します。 主な業務内容は、Azur…
週5日
790,000〜940,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・databricks | |
定番
【原則リモート / PM / 週5日】某キ…
某キャリア向け・アプリ開発のPM担当を募集します。 【案件内容】 ・PM/PL業務 ・開発…
週5日
750,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【原則リモート / テスター / 週5日】…
大手SIerの開発環境モダナイズ支援部隊におけるテスト高度化チームにて、エンドユーザやPJ主管である…
週5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 豊洲豊洲 |
|---|---|
| 役割 | テスター |
| Playwright・Git | |
定番
【フルリモート/フルスタック】高精度測位サ…
■仕事内容 新規開発と既存機能の改修を行う開発メンバーを募集します。 フロントエンド開発/テスト…
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・C・C++・Node.js・・・AWS… | |
【TypeScriptエンジニア】派遣事業…
【PJT概要】 派遣事業会社のスタッフ管理サイト刷新 既存のスタッフ管理サイトの大規模リニューア…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・React・・Next.js | |
定番
【リモート可 / Java / 週5日】派…
【PJT概要】 派遣事業会社に登録されている派遣スタッフの方がご利用するユーザー向けサイト(MYペ…
週5日
790,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Oracle・Exadata・・Tomca… | |
注目
[テックリード]金融インフラの開発もしくは…
【業務内容】 ・グループの展開する金融インフラ(資産運用、保険、その他)の開発もしくは そのプ…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | テックリード |
| Go・【使用技術】 ■サーバーサイド Amazo… | |
定番
【PMO|フルリモート】新規事業立ち上げ・…
【業務内容】 ・ジムにおける複数の新サービス・新規事業(セルフエステ、ゴルフ等々)の検討と実行推進…
週5日
840,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
【PMO / フルリモート】大手フィットネ…
【業務内容】 ①ジムにおける企画の実施内容整理(WBS化と管理)・実行 ②ジム運営における改善施…
週4日・5日
790,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
【PMO】大手フィットネス企業の新規サービ…
【業務内容】 ・ジムにおける複数の新サービス(セルフエステ、ゴルフ等々)の実行推進支援 【そ…
週4日・5日
620,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【原則リモート / PM / 週5日】キャ…
キャリア向けサービス開発の業務支援をお願いできる方を募集します。 【業務内容】 ・某キャリア…
週5日
580,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木溜池山王 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【一部リモート / インフラ / 週5日】…
取引所システム内のインフラ構築をお願いできる方を募集します。 ActiveDirectory、及び…
週5日
500,000〜550,000円/月
| 場所 | 豊洲新豊洲 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ActiveDirectory・WindowsSer… | |
定番
【社内SE / 週5日】ネットワーク構築、…
ネットワーク構築や運用保守などの業務お願いできる社内SEを募集いたします。 【業務詳細】 ・…
週5日
470,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川桜木町 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| Linux・Juniper・WatchGuard・F… | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】自社…
<具体的な業務内容> 当社の運営するWebサービスのインフラの設計・構築・運用をご担当頂きます。 …
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| AWS・GCP | |
定番
【リモート相談可 / 社内SE / 週2日…
【業務内容】 コーポレートエンジニアとして、まずは2つの役割を期待しています。 ①コーポレー…
週2日・3日・4日・5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
| ■使用ツール、サービス・ -・IdP:Azure・… | |
定番
【PM】地域金融機関向けアプリ開発
【案件概要】 - 地域金融機関向けアプリ開発のPM 【業務内容】 ・顧客のシステム部長直下…
週5日
470,000〜810,000円/月
| 場所 | 豊洲六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
【PHPエンジニア|フルリモート】現行サー…
既存のクライアントのWebサイトに関するエンジニアを募集いたします。 現行のサービスからの移管業…
週5日
420,000〜590,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・AWS・・Docker・・Codelgnit… | |
定番
【インフラ / 週5日】基盤システムの設計…
基盤システムの設計〜構築業務をお願いできる方を募集いたします。 上位会社チームのメンバーの一員とし…
週5日
370,000〜440,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋飯田橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Linux・Weblogic・シェル | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】大手…
大手SIerが運用するポイントシステムのクラウド移行案件です。 移行に伴い、上流工程(調査・計画・…
週5日
500,000〜590,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麹町 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Oracle(OCI)・AWS・・… | |
定番
【原則リモート / PM / 週5日】自社…
通信企業にて自社アプリ開発案件のプロジェクトマネージャーとして、要件定義~開発・リリースまでの各工程…
週5日
730,000〜810,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【インフラ / 週5日】サーバシステム運用…
クレジットカード会社におけるインフラ運用保守業務をお願いできる方を募集いたします。 運用保守SEと…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 神奈川江田 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Windows・Linux | |
定番
【リモート相談可 / インフラ / 週5日…
【業務内容】 Azure上でAzure Red Hat OpenShift(ARO)を利用したコン…
週5日
590,000〜810,000円/月
| 場所 | 秋葉原東陽町 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| Azure・OpenShift・AzureBatch | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日…
- 仕事内容: Android TVアプリの新規開発を担当します。開始期間は12/1(金)~3/…
週4日・5日
470,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅/原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・・ | |
定番
【急募!PHP案件/リモート可能】電子契約…
■案件概要 エンド様が提供している電子契約(電子契約サービス3冠受賞)Saasの設計と開発作業を担…
週5日
330,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋曙橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| CSS・JavaScript・PHP・Laravel… | |
定番
【急募!Java案件/リモート可能】団体保…
■案件概要 団体保険システムを導入するPJに参画頂きます。 ■業務内容 新規でスタートする…
週5日
330,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋虎ノ門 / 虎ノ門ヒルズ駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・・アーキ クラウドサービスとしてAW… | |
定番
【急募!Python案件/基本リモート】大…
■案件概要 大手メガベンチャー様にて社内の内製サービスの運用及び 開発作業リソース確保の為、サー…
週5日
330,000〜730,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・OS:Windows、Mac(dock… | |
定番
【急募!フロント案件/基本リモート】某ベン…
■案件概要 ・某ベンチャー企業のWeb3・NFT事業部門にて提供するサービスのフロントエンド開発を…
週5日
330,000〜730,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Typescript・※下記は… | |
【QAエンジニア|ハイブリット勤務】事業会…
社内システムの品質管理の為、システムの要件定義書のチェックやテスト計画書の作成、テストの実施をお願い…
週5日
230,000〜390,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| HTML・SQL | |
定番
【フルリモートOK!Ruby案件紹介】to…
案件内容 ・toB向けSaasサービスを展開されている会社様になります。 ・バックエンドエンジニ…
週5日
580,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
定番
【フルリモートOK!Python案件紹介】…
■案件内容 エンタープライズ向けAI SaaSサービスを展開されている企業様になります。 【…
週5日
580,000〜900,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア(AI) |
| Python | |
定番
【一部リモート / Typescript/…
建設会社系のWEBシステム開発をお願いできる方を募集します。 対象:ファイル管理システム デー…
週5日
470,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・Redux | |
定番
【フルリモート/HR領域/Typescri…
【業務内容】 ・新規プロダクトの開発 └技術選定、開発チームのリード、コードレビュー等々 …
週5日
470,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【フルリモートOK!Python案件紹介】…
■企業概要 主にシステム内製支援、 採用戦略支援、 人材紹介、 ビジネスコンサルティングという領域…
週5日
580,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・言語:Python、TypeScrip… | |
定番
【フルリモートOK!PHP案件紹介】薬局業…
■案件内容 薬局業界向けプラットフォームの開発 【業務概要】 ・医療・薬局業界向けのWeb…
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【フルリモートOK!C#案件紹介】業務ソフ…
■企業概要 主にシステム内製支援、 採用戦略支援、 人材紹介、 ビジネスコンサルティングという領域…
週5日
580,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・言語・フレームワーク:C#・(ASP.NET)… | |
定番
【フルリモートOK!フロント案件紹介】生成…
■案件内容 PdMから要件をヒアリングし、それを元に設計書の作成、構築、テスト、運用まで一連の流れ…
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| Typescript・言語・フレームワーク:C#・(… | |
定番
【Java案件紹介】FXシステムの開発保守…
■案件内容 ・FXのシステム開発保守 ・その他の商品のシステム開発保守 【補足】 社内の…
週5日
580,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・言語・フレームワーク:C#・(ASP.NE… | |
定番
【フルリモートOK!インフラ案件紹介】to…
■案件内容 toB向けSaasサービスをのシステム管理・運用/保守に携わっていただきます。 We…
週5日
580,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【フルリモートOK!PM案件紹介】AIを活…
■企業概要 主にシステム内製支援、 採用戦略支援、 人材紹介、 ビジネスコンサルティングという領域…
週5日
580,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモートOK!PM案件紹介】不動産ク…
■案件内容 日本で最大規模の不動産会社向け業務用クラウドサービスの顧客側への導入プロジェクトに携わ…
週5日
580,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモート/開発エンジニア】大手自動車…
【仕事内容】 大手自動車部品メーカー様のプロジェクトに参画頂き、主にコンシューマー向けのアプリケー…
週5日
620,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Python・Swift・RDB(MySQL等)、A… | |
定番
【フルリモート/開発エンジニア】大手自動車…
【仕事内容】 大手自動車部品メーカー様のプロジェクトに参画頂き、主にコンシューマー向けのアプリケー…
週5日
620,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Python・Java・Kotlin・RDB(MyS… | |
定番
【フルリモート/開発エンジニア】大手自動車…
【業務内容】 - 役割: 開発エンジニア(Webサービス開発) - 開発環境/ツール: AW…
週5日
620,000〜840,000円/月
| 場所 | 神奈川新横浜 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Python・Ruby・Ruby・on・Rails・… | |
定番
【PHP|基本リモート】薬局/病院向け自社…
【案件概要】 医療向け(薬局/病院)のtoB / toCの自社サービス提供をしている企業の シス…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・・FW:FuelPHP、CakePHP(※P… | |
定番
【デザイナー/週3~5日|フルリモート】大…
大手フィットネスグループがECサイトで展開しているプロテインやお弁当などの売り上げを拡大するため、L…
週4日・5日
230,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【EC開発/フルリモ】小売業某社向けECサ…
【作業内容】 小売業某社システムのECサイトにおける改修・機能追加、試験等、あるいは、運用保守業務…
週5日
390,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木渋谷 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・VB.NET・SQL・AWS | |
定番
【フルリモートOK!Java案件紹介】基幹…
■案件内容 基幹システムの機能開発、及びインフラ移行をご担当頂きます。 ◆備考 ただタスク…
週5日
580,000〜740,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【フルリモ / PM / 週5】大手フィッ…
【業務内容】 大手フィットネス企業のパーソナルフィットネス事業の顧客管理画面を構築するプロジェクト…
週4日・5日
1,020,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモート】Data Manageme…
【案件概要】 現在、BigQueryの全社的な管理を行っており、主に2つの課題に取り組んでいます。…
週3日・4日・5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| インフラ:Google・Cloud・Platform… | |
定番
【原則リモート / Java/Kotlin…
既存の医療系営業支援プラットフォームの開発現場でメンバーを募集しています。 下記のようなプロジ…
週5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Scala・Kotlin・G… | |
定番
【WordPressエンジニア/WEBコー…
案件の内容としては、WP上でのホームページ、メディアサイト制作全般となります ・HTML/CSSコ…
週5日
330,000〜500,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | WordPressエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【PMO / 週5 / フルリモ】新規We…
■案件概要 : [業務内容] ・PMOとして、進捗状況の管理・アクションアイテムの管理・不具合の…
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 千葉海浜幕張 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| Java | |
定番
[VB.NETエンジニア / フルリモート…
Backendアプリケーション郡(新規および改修)において 設計~テストまでをメインに担当していた…
週3日
180,000〜370,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋伏見駅 |
|---|---|
| 役割 | VB.NETエンジニア |
| C#・VB.NET | |
定番
【フルリモート / TypeScript …
【業務内容】 - 配属プロジェクト: 大手小売業(家電量販店)のWebサイト開発プロジェクト …
週5日
550,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
注目
【フルリモ / 週5 / データ運用案件】…
▼具体的な業務 ・RDWH:週次・月次運用に集計 ・MEDUNI:月次集計 ※業務の詳細に関し…
週3日・4日
1.8〜2.8万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア(データ運用) |
| SQL | |
定番
【サーバーサイドエンジニア/フルリモート】…
【業務内容】 AWSによる、下記要求スキルに記載した内容のアプリケーション開発。 販売・調達・物…
週4日・5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区エリア |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Java・Typescript・AWS… | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】アプリケーショ…
【業務内容】 AWSによる、下記要求スキルに記載した内容のアプリケーション開発。 ホームセンター…
週4日・5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区エリア |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・AWS・・Lambda・・Dynamo… | |
定番
【常駐 / 週5 / 事務スタッフ】企画・…
【業務内容】 - 役割: 事務スタッフ 管理職の指示に基づき、委員会会合の日程調整・ロジ業務、…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO(事務スタッフ) |
定番
【フルリモ / 週5 / AWS設計構築】…
【業務内容】 AWSによる、下記要求スキルに記載した内容のDevOpsツール、監視、認証、アカウン…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区エリア |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
| AWS・・Terraform・ | |
定番
【フルリモ / 週5 / AWS】社内シス…
【業務内容】 AWSによる、上記要求スキルに記載した内容のセキュリティガイドラインを定義・構築。 …
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区エリア |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
| AWS・・Terraform・ | |
定番
【フルリモ / 週5 / AWS】社内シス…
【業務内容】 スクラムチームでのスクラムマスター遂行。 販売・調達・物流いずれかのドメインを開発…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木港区エリア |
|---|---|
| 役割 | スクラムマスター |
| Python・Java・・インフラ:・AWS ・O… | |
定番
【QA / フルリモート】DX推進プラット…
【本案件のポイント】 ・話題の生成AI(ChatGPT)に関連するサービスに携われることができる …
週5日
300,000〜390,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア |
| ・ | |
【Ruby,Python,React】デー…
【業務内容】 ・Ruby on Rails又はPython等を使ったWebアプリケーションの実装開…
週5日
420,000〜520,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby・-・React | |
定番
【フルリモ / AIエンジニア / 週4日…
■業務内容(例) ・機械学習を用いた3Dモデリングの開発 ・オペレーションズリサーチを用いたプラ…
週4日・5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
定番
【一部リモート / Azure / 週5日…
Azure databricksを使ったデータエンジニアを募集しています。 【業務内容】 ・…
週5日
810,000〜860,000円/月
| 場所 | 品川浜松町 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・SQL・Databricks | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週5日…
スマホアプリ開発(iOS/Android両方)を担当していただきます。 現状は大きなプロジェクト案…
週5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京麹町 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter・Firebase・Git・JIRA・… | |
定番
【一部リモート / Kotlin / 週5…
求人掲載サイトのバッチ開発をお願いできる方を募集しています。 【作業内容】 詳細設計、実装、…
週5日
560,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原小川町 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・AWS | |
定番
【フルリモ / PHP / 週5日】動画配…
■案件内容 動画配信サービスの配信システムに関する開発を担っていただきます! ■業務内容 …
週3日
230,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby | |
定番
【フルリモ / Java / 週5】大規模…
大規模総合ECサイトの開発業務に携わっていただきます。 ※具体的な業務内容に関しましては、面談にて…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringFramework・ | |
定番
【正社員】PM職【東証マザーズ上場】
【業務内容】 新規プロジェクトのプロジェクト運営責任者 また、技術担当取締役や営業責任者と連携し…
/月
| 場所 | 赤坂・永田町霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | PM職【当社グループ東証マザーズ上場】 |
| Java・C#・VB.NET・SQL | |
注目
【常駐 / 動画ディレクター / 週5】イ…
お客様の高い満足度を得ることを目的として、企画担当者と連携し動画ディレクションや編集 ハイブリッド…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町駅 |
|---|---|
| 役割 | 映像制作・動画編集 |
【コンサル・事業開発】新規事業に関するPM
【業務内容】 社長の直下で社長直下のポジションを想定しており、パートナー企業とのアライアンスや新規…
週1日・2日・3日・4日・5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京内幸町 |
|---|---|
| 役割 | PM/コンサル(新規事業開発) |
定番
【クラウドエンジニア/リモート】Azure…
【業務内容】 クラウド運用・接続サービス提供のための ・Azureに関する技術検証 ・構成設計…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木- |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| Azure | |
【フルリモ / 事業開発 / 週5】当社新…
【業務内容】 当社新規事業(オンライン診療など)の協業企業との運用業務にご従事いただきます。 …
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 事業開発 |
| ・基本週5フルタイム ・基本リモート ※必要に… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
Webバックエンドを中心として、クリニックのDX達成のために必要となるエンジニアリングをリードしてい…
週5日
700,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | テックリード/サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【フルリモ / 週4~5 / インフラエン…
【募集背景】 大手フィットネス企業におけるtoC向けアプリ開発 ベンダーが構築した、2022年1…
週4日・5日
790,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
【C/C++/組み込み/リモート】ファーム…
【業務詳細】 プレイングマネージャーとしてプロジェクトのマネジメントから開発までをお任せします。 …
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
| C・C++ | |
定番
【一部リモート可 / CMS / 週5日】…
【募集背景】 制作体制強化と組織の活性化を図るため“WEB制作・フロントエンドエンジニア”の募集を…
週5日
150,000〜390,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋神保町 |
|---|---|
| 役割 | CMSエンジニア |
定番
【Web/システムディレクター】スポーツ団…
会員管理サービスをベースとした自社SaaSサービスのフロント/バックエンドの機能追加の実施、 to…
週4日
350,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Web/システムディレクター |
定番
【フルリモ / Ruby / 週4日〜】デ…
新規プロダクトの開発となります。 ・フロントエンドからサーバーサイド、バッチの開発とフルスタックに…
週4日・5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Language:・… | |
定番
【広告運用業務 / フルリモート】広告運用…
広告運用マーケター・コンサルタントを募集しています。 最初はGoogle・Yahoo!・Faceb…
週1日
70,000〜120,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【フルリモ / マーケター / 週3日〜】…
【業務内容】 弊社のプロダクトである電子マネープラットフォームの事業全体のマーケ施策を考え、実行い…
週3日・4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川三田駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【インフラ / 週5日】某官公庁のサーバ更…
某官公庁様にて実施されているサーバ更改プロジェクトに参画頂きます。 主にWindowsServer…
週5日
400,000〜470,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大森 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| WindowsServer・ActiveDirect… | |
定番
【一部リモート / Oracle / 週5…
ネットバンク向けのインフラ提案~保守作業を一気通貫で対応いただきます。OracleDBチームにご参画…
週5日
550,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川品川 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| Oracle | |
定番
【バックエンドエンジニア】エネルギー業界の…
<業務内容> ・エネルギー業界の顧客向け業務システムの開発を担当して頂きます。 ・具体的にはスク…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Python | |
定番
【フロントエンジニア】コンテンツバージョン…
<業務内容> ・Webホスティングにおけるコンテンツバージョン管理システムのコントロールールパネル…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【PM / フルリモート】既存プロダクト又…
【ポジション概要】 既存プロダクト又は新規プロダクトの開発ディレクション業務 【作業内容】 …
週3日・4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【TypeScriptエンジニア / フル…
【作業内容】 当社にて開発中の医療分野のアプリケーション開発をお任せします。 <具体的な仕事…
週4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・React・・React・Na… | |
定番
【リモート相談可 / Ruby on Ra…
リリース済みのtoC向けアプリ(会員数十万人)の内製化に伴い、バックエンドエンジニアを募集いたします…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋三田 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・RubyonRails | |
定番
【リモート相談可 / Android / …
リリース済みのフィットネスモバイルアプリの開発(エンハンス)・ドキュメント作成をお願いできる方を募集…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋三田 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・Jetpackcompose | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
リリース済みのtoC向けアプリ(会員数十万人)の内製化に伴い、プロジェクトの管理を担うPMを募集いた…
週5日
700,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋三田 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【リモート相談可 / SwiftUI / …
リリース済みのフィットネスモバイルアプリの開発(SDK使用)・ドキュメント作成をお願いできる方を募集…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋三田 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・SwiftUI | |
定番
【リモート相談可 / PM / 週5日】大…
大手フィットネス企業におけるパーソナルフィットネス事業管理画面の構築プロジェクト管理を担うPMを募集…
週5日
700,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋三田 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【編集ディレクター】中学校数学・英語教材に…
【企業】 当社は創業から70年以上の歴史を持つ出版社です。主に教科書や教材、参考書、児童図書といっ…
週3日・4日・5日
230,000〜300,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸リモート |
|---|---|
| 役割 | 編集ディレクター |
定番
【AfterEffects / グラフィッ…
【企業】 コンシューマ、携帯ゲーム、スマホアプリ、遊技機などの他、DTPやHP制作を行っています。…
週5日
180,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜川(大阪) |
|---|---|
| 役割 | 2D/3Dデザイナー |
| AfterEffects・Illustrator・3… | |
【自社サービス】Webデザイナー
人材派遣管理システムのサイトをリニューアルするにあたって WebサイトのデザインやLP、バナーを制…
週3日
130,000〜330,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿芝浦 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
定番
【新大阪常駐/高単価】 組み込み機器のソフ…
■業務内容 組み込み機器のソフト開発(実装、テスト、不具合修正) ・サービス/アプリケーション…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア(組み込みエンジニア) |
| Java・C・C++・C# | |
定番
【新規事業/フルリモート】UI・UXデザイ…
サプライチェーン領域のデザインチームのUIデザイナーとして、要件整理後のワイヤーフレームからビジュア…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| CSS・ | |
【フルリモートOK!PHP案件】WordP…
■業務内容 弊社が展開している各プロダクトでは、グロースハックする手段として、WordPressを…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP | |
定番
【フルリモートOK!開発案件】CTO直轄プ…
TO直轄プロジェクトのため、CTOと直接連携を取りながら進めていただきます。 【具体的な業務】…
週2日・3日・4日・5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | テックリード |
| PHP・Python・Ruby・Java・Scala… | |
定番
【大手SIer|リモートOK|上流案件】配…
■案件概要 ・配送サービス業様向けオーダシステムリプレイスにおけるWebシステム開発 ■職務…
週5日
390,000〜730,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE(開発含む) |
| JavaScript・Typescript | |
定番
【大手SIer|リモートOK|フロント案件…
■案件概要 ・配送サービス業様向けオーダシステムリプレイスにおけるWebシステム開発 ■職務…
週5日
390,000〜880,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京八丁堀駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(PHP ・Vue.js or Vue.js) |
| JavaScript・PHP・Python・Type… | |
定番
【バックエンドエンジニア】Webホスティン…
<業務内容> ・Webホスティングにおけるコンテンツバージョン管理システムのバックエンドの新規開発…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Typescript | |
【組織開発/フルリモート】CPP部門企画
【募集背景】 圧倒的なスピードで事業成長している中、サービスの基盤となるCPP(以下配属部門で説明…
週4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | 組織開発 |
定番
【フルリモートOK|VBA案件】大手企業に…
【背景・目的】 ハウスクリーニング業などを展開されている大手企業の業務改革推進部からの案件です。 …
週2日・3日・4日
250,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
定番
【急募!リモート可能!インフラ案件】 プラ…
<作業概要> ・設備マスタのデータを管理したDBサーバ(PostgreSQL)の構築 -VMwa…
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【PM/基本リモート】既存レンタルECサイ…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトの追加開発と運用保守のPJで…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・Java・Apache・Wicket・・My… | |
定番
【フルスタックエンジニア/基本リモート】既…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトの追加開発と運用保守のPJで…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルスタックエンジニア/基本リモート】既…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトの追加開発と運用保守のPJで…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【米国向けLegaltec製品の開発、設計…
【仕事内容】 Global Teamのソフトウェアエンジニアは、米国チームと協力し、現地ニーズを把…
週3日・4日・5日
470,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア[テックリード] |
| Ruby・AWS・・・GCP | |
定番
【PM/基本リモート】既存レンタルECサイ…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトのパフォーマンス(速度)改善…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルリモートOK!デザイナー案件】デザイ…
■ 仕事内容 デザインを通じてユーザーとサービスの距離を縮め、日常的な利用を促進する。保育士・幼稚…
週3日・4日
120,000〜260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー(グラフィック含む) |
定番
【PM】Salesforce上の顧客マスタ…
◇要件定義フェーズに携わった経験 ※要件定義でお客様が行いたいこと ・顧客マスタの要件整理 ・…
週5日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Salesforce | |
定番
【Salesforceエンジニア】Sale…
◇お客様はクレジットカード会社様向け法人営業を統括している部門 ◇Apex/VFなど軽微なコーデ…
週5日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce・ | |
定番
【データベースエンジニア】既存レンタルEC…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトのパフォーマンス(速度)改善…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【PHPエンジニア】既存レンタルECサイト…
【業務内容】 ▼概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトのパフォーマンス(速度)改善…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ja… | |
定番
【フルスタックエンジニア】某スポーツ団体の…
■業務内容 11月にリリースを控えている某スポーツ団体の基幹システムと、 既に運用しているサブシ…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・SQ… | |
定番
【初日出社(六本木) / Go / 週5】…
■仕事内容 1to1のコミュニケーションの実現を中心とした小売企業のDXを推進しています。 その…
週5日
300,000〜860,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| JavaScript・PHP・Go・Typescri… | |
定番
【フルリモートOK|PdM案件】飲食店向け…
【業務内容】 ・プロダクト戦略/ロードマップの策定および遂行 ・定量/定性データを元にした課題定…
週3日・4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM(開発経験含む) |
【データアナリスト/フルリモート】自社チャ…
【業務内容】 ・新機能の導入・現場要望に応じてプロダクト部とコミュニケーションを取り、ログ設計やロ…
週5日
470,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | データアナリスト |
| Python・SQL | |
【リモート可能!テックリード/PM案件】技…
Web広告配信システムを始めとする自社サービスの開発や運用業務、 ご経験やご希望によってプロジェク…
週4日・5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | テックリード/PM |
| JavaScript・PHP・Python・Ruby… | |
【フルリモート/フロントエンド】新規サービ…
■仕事内容 運営画面のUI改善、コンポーネントライブラリの開発、npmライブラリの更新とセキュリテ…
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・・React… | |
定番
【年間1億PV!自社大規模サイト|フルリモ…
要件定義・実装・テスト、インフラ基盤の設計・構築、運用・保守など上流から下流まで幅広い開発フェーズに…
週5日
230,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【SEOライター/ディレクター】自社メディ…
【業務内容】 自社サイトのディレクションを中心にリライトなどを行っていただきたいと考えています。 …
週3日・4日・5日
230,000〜470,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOライター/ディレクター |
定番
[C++エンジニア]WindowsXP/7…
【案件内容】 ・WindowsXP/7で稼働しているシステムをWindows10に移行 ※Vi…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西宮駅(付近) |
|---|---|
| 役割 | C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【新大阪常駐/高単価】 組み込み機器のソフ…
■業務内容 組み込み機器のソフト開発(実装、テスト、不具合修正) ・サービス/アプリケーション…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| Java・C・C++・C# | |
定番
【新大阪常駐/高単価】 組み込み機器のソフ…
■業務内容 組み込み機器のソフト開発(実装、テスト、不具合修正) ・サービス/アプリケーション…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸- |
|---|---|
| 役割 | ERP導入/フロント/C言語 |
| Java・C・C++・C# | |
急募
【フルリモート/上流SE案件!/ 週2~可…
【案件概要】 スマートフォンアプリをはじめ、XR、AI、IoTなど最先端のアプリを開発するにあたり…
週2日・3日
270,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
定番
【Salesforceエンジニア】Sale…
某ネット銀行向けのSalesforce開発保守 与信審査などで利用をしており、SFA/CRMと…
週5日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce | |
【WEBコーダー】自社サービスに関するコー…
■業務内容: 男性専門総合美容クリニックのさらなる事業拡大へ向け、 既存サイトの改修を中心にコー…
週1日・2日
80,000〜140,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新大久保 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS | |
定番
【新大阪常駐|フロント案件】国内最大手製造…
■FA機器の表示画面の構築業務(フロントエンド) 〇主な工程 ・詳細設計20% ・実装60% …
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸新大阪駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【Go/フルリモート】自社プラットフォーム…
【案件概要】 ・新規機能の開発 ・マイクロサービス化に関わる開発 ・公開APIの開発 ・運用…
週4日・5日
580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・ | |
【フルリモ / 週5日】DX支援型SaaS…
自社開発や他社SaaSを複合的に組み合わせ、合理的に業務システムを構築する力を身につけていただけるか…
週3日・4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【一部リモート / セキュリティ / 週5…
【募集背景】 自社SaaSサービス企業拡大に伴うセキュリティ評価依頼の増加に対応するため、 セキ…
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・ | |
定番
【フルリモOK|データエンジニア案件】電動…
【仕事内容】 ・データの戦略、活用方法、データによる競争優位性の設計 ・Airflow, Big…
週4日・5日
550,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| JavaScript | |
【フルリモ / フルスタック / 週5日】…
【業務内容】 ・自社のフロントエンド、サーバーサイド開発 ・ユーザーの行動ログ分析 ・改善施策…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Java・Kotlin・Typescript・SQL… | |
定番
【フルリモ / React / 週5日】自…
【業務内容】 ・社内向けシステムのフロントエンド開発 ・ビジネス要件や長期のメンテナンス性を考慮…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・React・ | |
【ディレクター/リモートメイン】ポータルサ…
【エンド概要】 SIビジネスからの脱却に向け、全社レベルで様々なコンサル活動に取り組んでいる。 …
週5日
390,000〜990,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター |
定番
【大手SIer|フルリモートOK|PHP案…
【企業概要】 創造の世紀を迎え、電算システムはこれまで培った知的資産(ナレッジ)と人的資産(ノウハ…
週5日
390,000〜860,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP | |
定番
【C#,Java】自社プロダクトの機能開発
【業務概要】 ECサイト向けパッケージを用いて、クライアントのECサイトを構築頂きます 。顧客折衝…
週4日・5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
| Java・C#・AWS・特になし | |
定番
【リモート相談可 / クラウドエンジニア …
地方自治体が利用する基幹業務システムのクラウドリフトにあたり、Oracle CloudもしくはOra…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木浜松町 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
定番
【PHP/Typescript/フルリモー…
[概要] レガシーシステムが存在し、部分的にマイクロサービスへ切り出しを進めています。 レガシーシ…
週5日
620,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
【リモート相談可 / React/Next…
【業務内容】 大人気カードゲームNFTのECサイトを開発します。 グローバルなRWA NFT…
週5日
620,000〜940,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| React・Next.js | |
定番
【Salesforceエンジニア】(Inf…
◆概要 ・SalesCloud関連の導入案件(要件定義~) ・特にInfomaticaのご経…
週3日・4日・5日
470,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce・ | |
【フルリモ / Go / 週5日】画像生成…
【業務内容】 画像生成AIを用いたアパレル向けBtoBサービスのバックエンド(API・インフラ・D…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go | |
【PHP/フルリモート/週3~可能】求人マ…
新規開発案件です。 PHP+Laravelでのバックエンド開発になります。 フロント(React…
週3日・4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・インフラ:AWS データベース:MySQL… | |
定番
【フルリモ / Ruby/Typescri…
--------本ポジションで働く魅力------------ ・チーム毎の垣根がなく、協力し合う…
週3日・4日・5日
550,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Ruby・Java・Typescript・・ | |
定番
【正社員】お客様のWebサイトに関わる企画…
【案件概要】 ポジション:Webサイト制作に関するディレクション 想定年収 :400万~600万…
/月
| 場所 | 池袋池袋駅、雑司ヶ谷駅、目白駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS | |
定番
【正社員】お客様の課題やサービス内容に沿っ…
【案件概要】 ポジション:Webデザイナー 想定年収 :400万~600万 勤務地 :東京都…
/月
| 場所 | 池袋池袋駅、雑司ヶ谷駅、目白駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript | |
定番
【正社員】お客様の新規/既存Webサイトの…
【案件概要】 ポジション:Webコーダー/フロントエンドエンジニア 想定年収 :400万~600…
/月
| 場所 | 池袋池袋駅、雑司ヶ谷駅、目白駅 |
|---|---|
| 役割 | Webコーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
【フルリモートOK!24年3月開始!】動画…
【業務内容】 ・定量的・定性的な分析レポートの作成(週一度のレポート報告) ・分析結果からの施策…
週3日・4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | WEBマーケター |
定番
【マーケター/週3~4日|フルリモート】大…
【健康・美容関連領域における業務】 ①商品LPを使ったマーケ施策・運用 例:プロテインのLP…
週3日・4日
250,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
【フルリモ / AIエンジニア / 週5日…
【業務内容】 LLMを用いたプロジェクト/プロダクトの企画・立案・開発を行っていただきます。 ・…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python | |
定番
【Java講師】大手IT企業の新卒研修のサ…
【業務内容】 ・大手IT企業の新人研修のサブ講師 ・現地にて、受講生のサポート業務 (分からな…
週1日・2日・3日・4日・5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | サブ講師 |
| Java・・ | |
定番
【講師未経験者も大歓迎!】あなたの開発経験…
【業務内容】 ■準備期間 ※主にオンライン(Teams) ※講師登壇の学習期間 →カリキュ…
週4日・5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 講師(C言語/組み込み) |
| C・C++ | |
【商品企画/週3~5日|フルリモート】大手…
・美容・健康、生活雑貨、ライフスタイル等と幅広い領域における商品企画 - ECでの販売=商品L…
週3日・4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PdM |
【機械学習エンジニア募集】最先端技術を駆使…
■仕事内容 機械学習を活用した課題解決、AIチャットシステムの開発、レコメンドエンジンの構築、各プ…
週2日・3日・4日・5日
470,000〜1,580,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【正社員】スポーツ×デジタル 自社運営メデ…
【案件概要】 スポーツに特化したメディア&コンテンツのプロデュースカンパニーです。 弊社が運営す…
週5日
/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅/新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBディレクター |
| HTML・CSS・Wordpress | |
定番
【正社員】スポーツ×デジタル 自社運営メデ…
【案件概要】 スポーツに特化したメディア&コンテンツのプロデュースカンパニーです。 弊社が運営す…
週5日
/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅/新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBコーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【フルリモートOK!音声合成AIの開発! …
■仕事内容 音声合成AIの開発・研究・性能改善、対話AIやデジタルコンテンツへの応用開発、仕様策定…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | AI/機械学習エンジニア(※正社員切替え前提※) |
| Python | |
定番
【革新的プロジェクト】メタバース&ゲーム開…
■仕事内容 最先端のメタバース開発や、大手ゲーム会社と協業するIPゲーム開発など、多彩なプロジェク…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ゲームエンジニア(UnityやUE) |
| C・C++・C# | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週4日…
■仕事内容 フロントエンド開発、UI/UXの改善、アプリ設計、バックエンド開発、チームメンバーの教…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア※正社員切替え前提※ |
| Typescript・React・ | |
定番
【急募!週2日リモート可能!テスター案件】…
【業務内容】 既存製品(有人チャット、チャットボット、音声ボット、LINE配信、Visual IV…
週5日
390,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア/テスター |
定番
【急募!リモート可能!AIエンジニア開発案…
【業務内容】 ・自社のサービスデータを利用したAI関連設計/開発/テスト/運用 ・他社AIとの連…
週5日
390,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | AI・機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【急募!リモート可能!テスター案件】チャッ…
【業務内容】 既存製品(有人チャット、チャットボット、音声ボット、LINE配信、Visual IV…
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
【リモートOK!AI開発案件】AIチャット…
■当ポジションの魅力 ・自社サービスのコアメンバーとして携われるポジションです。 ・安定したコア…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | AI・機械学習エンジニア |
| Python | |
定番
【一部リモート可 / Swift / 週5…
プレイングマネージャーとしてプロジェクトのマネジメントから開発までをお任せします。 【業務詳細…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | Swiftエンジニア |
| Swift・Kotolin UML・SysML Gi… | |
定番
【3月開始!Java講師案件】講師未経験も…
【アシスタント講師業務内容】 ・質問対応 ・報告書作成など教室運営 ・各種評価報告書作成(研修…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | Java講師アシスタント |
| Java・・ | |
定番
【3月開始!インフラ講師案件】講師未経験も…
【講義内容】 1 IT基礎 5 ネットワーク 2 情報処理基礎 6 サーバ・クラウド 3 オペ…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラ講師アシスタント |
| ・ | |
定番
【フルリモートOKです!大手SIerのPM…
■業務内容 <メイン> ・システム開発における打ち合わせや会議の進行・運用・管理 ・ベンダーコ…
週5日
390,000〜940,000円/月
| 場所 | 品川市ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE/PM/PMO |
| Java | |
定番
【フルリモOK!フルスタック案件】リーダー…
▼具体的な業務(※スキル/経験に合わせて業務はお願いします。) ・自社サービスの企画、開発、運用 …
週3日・4日・5日
470,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・Typescript | |
定番
【フルリモOK!QAテスター案件】自社の勤…
▼具体的な業務(※スキル/経験に合わせて業務はお願いします。) テスト設計〜検証までに携わっていた…
週4日・5日
470,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | QAエンジニア/テスター |
| JavaScript・PHP・Typescript・… | |
定番
【動画編集】ホワイトボードアニメーションの…
業務内容】 下記ポジションのどちらかを想定しております。 ・Illustrator / Phot…
週1日・2日
120,000〜180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | 動画編集者 |
定番
【リモート相談可 / データエンジニア /…
BigQuery等を用いたデータ基盤の設計、開発、運用 BIツールを用いて情報を可視化するためのデ…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿青山一丁目 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
【フルリモOK!マーケター案件】カスタマー…
【業務内容】 ・月1回の定例Mtgのフロントを担っていただき、レポート内容の説明(レポートはほぼ自…
週2日・3日
270,000〜560,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | マーケター(コンサル要素あり) |
定番
【急募!リモート可能!フロント案件】主軸と…
自社開発プロダクトにて主にフロントエンジニアの業務を行っていただきます。 【具体的な業務内容】…
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【急募!フルリモートOK】社会人教育事業・…
【担当業務】 toC,toB向けの既存プロダクトのリニューアルや新規事業である高等教育機関向け」の…
週5日
580,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(GO経験必須) |
| Go・‐ | |
【1月開始!フルリモOK|PHP案件】入札…
- 仕事内容 今回、ジョインいただく方には、バックエンドエンジニアとして、 API開発をメインに…
週4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| HTML・JavaScript・Ruby・【業務で利… | |
定番
【グラフィック】ポスター、POP等の制作物…
【業務内容】 弊社の制作物に関わるデザイナー業務。 ▽想定される具体的な業務▽ ・ポスター…
週1日・2日
80,000〜120,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿桜新町 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| ・ | |
定番
【バックエンドエンジニア】スマートシティ化…
・職種: バックエンドエンジニア ・概要: スマートシティ化において、よりよい体験を利用者に提供す…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| Typescript | |
定番
【iOSエンジニア】スマートシティ化におい…
・職種: iOSエンジニア ・概要: スマートシティ化において、よりよい体験を利用者に提供するため…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモOK!週2日稼働可能!LP制作案…
【企業】 空気と水のコア技術を保有し、換気送風機器、空質家電、環境エンジニアリングシステム・サービ…
週1日・2日
80,000〜150,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・・ | |
【リモート可 / PHP/Go / 週5日…
■募集ポジションについて 本ポジションでは、ショッピングサービスの開発を担っていただく方を募集しま…
週5日
620,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Go | |
定番
【Python/Django / 週5日】…
【業務概要】 ①社内向業務システムの再構築を行う ②新規業務システムの開発(一般消費者向けはない…
週5日
2〜3.2万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿東池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・Django・ | |
【フルリモートOK!RPA案件】上場企業の…
【業務内容】 ・エクセルマクロの作成業務 ・RPA(PowerAutomate)開発を中心に業務…
週2日・3日
190,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | RPAエンジニア(WEB系言語開発経験含む) |
定番
【急募|リモート相談可能!社内SE案件】英…
【業務内容】 ・独自に開発した社員向けの売上や在庫を管理するシステムの運用保守・改善開発・ユーザー…
週5日
500,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE(テクニカルサポート含む) |
定番
【UXデザイナー/ディレクター】大手通信キ…
▼案件概要 大手通信企業が運営している通信キャリアサービスのWeb申し込みサイトの画面デザイン周り…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新富町駅 |
|---|---|
| 役割 | UXデザイナー/ディレクター |
| HTML・CSS | |
【一部リモート可 / PHP / 週5日】…
【仕事内容】 サーバ構築や、Webサイトおよびスマホアプリなどの制作に必要となるシステムの開発に携…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・LAMP・CodeIgniter・Larav… | |
定番
【上流SE/リモート】情シス部門の各種プロ…
【案件概要】 ・開発案件のPMO支援、テスト支援他、情報システム部門にて対応が必要な業務の支援をお…
週5日
470,000〜770,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
定番
【ハイブリット勤務!!SQLエキスパート】…
【業務内容】 SQLエキスパートとしてデータベースの管理やダッシュボード作成を担当していただきます…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SQLエンジニア |
| SQL・Tableau | |
[Webディレクター]自社開発/大手クライ…
【仕事内容】 企業サイト、企業・製品ブランディングサイト等のWebディレクション業務をお任せします…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
[UI/UXデザイナー]自社開発/大手クラ…
■業務内容 ・Webサイトの新規制作やリニューアルのデザイン提案 ・デザインコンセプト・トーン&…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【基本リモート / Swift / 週5日…
■案件内容 iOS顔認証アプリ開発をお願いします。 ■作業内容 ・顔認証SDKを組み込んだ…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | iosエンジニア |
| Swift | |
定番
【一部リモート可 / 上流設計 / 週5日…
■案件内容 通信キャリア向けインフラストレージ設計をお願いします。 ※インフラHW更改に伴い募集…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PMO(インフラ/サーバー経験必要) |
定番
【急募!C言語開発案件】大手SI企業でモビ…
■作業内容 組込制御分野のSW設計業務をお願いします。 (仕様検討~設計~実装~評価) 〇…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++エンジニア |
| C・C++ | |
定番
【急募!VB.net開発案件】大手SI企業…
■案件内容 生産管理システムの構築をお願いします。 ▼主な工程 ・外部設計(ユーザーインタ…
週5日
500,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | VB.NETエンジニア |
| VB.NET | |
定番
【ネットワークエンジニア】エンタメ企業向け…
【概要】 既に始まっており、某エンタメ企業のデータセンター内にある関連 子会社設備を分離させるプ…
週5日
790,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【高単価案件‼セキュリティエンジニア】金融…
【概要】 2024年2月よりGoogle社のドメインに係る規定が厳格化することに伴い、 金融機関…
週5日
790,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都内 |
|---|---|
| 役割 | セキュリティエンジニア |
定番
【フルリモ / Ruby on Rails…
【業務内容】 電子コミック配信サービスの保守開発業務をご担当いただきます。 【環境】 開発…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿池袋 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails・ | |
定番
PMM候補(プロダクト企画)
【業務内容】 1)現場課題の理解のため、現場業務に伴走 2)プロダクト&オペレーションの課題分析…
週4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | PMM |
定番
【SAP】SAP S/4HANAの導入案件
【案件概要】 詳細はご面談にてご説明いたします。 ・エンドユーザSIerアンダーでSAP S/4…
週5日
550,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | SAPエンジニア |
定番
【スクラムマスター】某大手エンタメ会社での…
【主な業務内容】 ①スクラムマスターとして、アジャイル型開発の進行管理 ②クライアントに対…
週5日
550,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スクラムマスター |
定番
【フルリモート‼/PM】自社グループの新規…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【フルリモート‼/バックエンドエンジニア】…
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| PHP・Typescript・・ | |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】共通…
店舗関連の共通サービスのリニューアル案件、大規模案件、エンハンス案件の開発を実施。 また、プロダク…
週5日
670,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot・・JUNIT | |
【フルリモ / 0.5人月案件 / And…
・小売店舗内に設置するサイネージAndroidアプリのアドオン開発案件が2023年1月から開始予定 …
週2日・3日
510,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
定番
【フルリモ / Java / 週5日】店舗…
店舗が利用する管理用サイトのリニューアル案件、大規模案件、エンハンス案件における開発メンバーを募集い…
週5日
550,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・Boot・・JUNIT | |
定番
【講師未経験者も大歓迎!】あなたの開発経験…
【稼働イメージ】 2024年3月上旬:アサイン案件の確定 2024年3月下旬:標準教材確認期間・…
週4日・5日
790,000〜1,730,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | エンジニア研修講師(Java or C言語) |
| ・ | |
定番
【フルリモート/UI/UXデザイナー】既存…
■作業内容 医療領域のドメインスペシャリストなどのメンバーとともに要件定義を行い、 具体のUIデ…
週5日
620,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【講師未経験者も大歓迎!】あなたの開発経験…
3)若手機械エンジニア向けのりスキル研修「組み込み研修」 ■2月/3月/5月実施(詳細未定10日間…
週4日・5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 講師(C言語/組み込み) |
| Java | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週4日〜】大…
【案件概要】 大手動画プラットフォームのインフラ(AWS)を保守・運用・構築していただきます。 …
週4日・5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(PHP経験含む) |
| PHP・・環境:AWS-・CDK、LAMP環境 ・… | |
定番
【基本リモート / PHP/Java / …
■概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトのパフォーマンス(速度)改善のPJです。 …
週5日
550,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Springboot・Larave… | |
定番
【基本リモート!!/データベースエンジニア…
■概要 当社で数年前に新規で開発したレンタルECサイトのパフォーマンス(速度)改善のPJです。 …
週5日
550,000〜700,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | データベースエンジニア |
| PHP・Java・Apache・Wicket・・My… | |
定番
【急募!Android開発案件】大手SI企…
■案件内容 車載向けAndroidアプリ開発 社内ディスプレイに表示するためのアプリ開発 …
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア(Java経験あり) |
| Java | |
新着
定番
【Webディレクター】既存大手クライアント…
■業務内容 既存の大手クライアントのWebサイトをご担当いただけるWebディレクターを募集いたしま…
週5日
410,000〜500,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【C#,Java】自社プロダクトの機能開発…
【業務概要】 自社SaaS側サービス(※)の社内サポート業務 ・社内の問い合わせ業務(導入サ…
週4日・5日
410,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サポートエンジニア |
| Java・C#・AWS・特になし | |
定番
【クリエイティブディレクター】顧客の広告ク…
【業務内容詳細】 ・クリエイティブの与件/要件の理解、整理 ・企画、ラフ案作成 ・制作の進行管…
週4日・5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | クリエイティブディレクター |
【フルリモOK!フルスタックで活躍したい方…
【業務内容】 ・今回、ジョインいただく際には、フルスタックエンジニアとして、API 開発からフロン…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア(サーバーサイド) |
| JavaScript・Typescript | |
[プロダクトマーケティングマネージャー(P…
■担当するプロダクト ・自社ブロックチェーン・ブロックエクスプローラー・API ・暗号資産ウォレ…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅 |
|---|---|
| 役割 | PMM |
定番
【フルリモートOK!動画編集案件】宿泊業界…
■案件内容 宿泊業界や保育業界、子育て世帯向けのメディアの動画編集、アニメーションをお任せいたしま…
週4日
250,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 動画編集 |
定番
【リモート可 / バックエンド / 週5日…
【業務内容】 メッセージングプラットフォーム基盤開発を担っていただける開発エンジニアを募集します。…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(Java、Golang、Python) |
| Python・Java・Go・-・ | |
【Webディレクターアシスタント】顧客先の…
[企業概要] 印刷ECサイトを運営する株式会社帆風のグループ会社としてデザインのみならず、企画・プ…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクターアシスタント |
定番
【フルリモートOK!バックオフィス業務】証…
■プロジェクト概要 ・FXの顧客向けサービス ・決済サービス ・コンシューマー向けFX⽐較サイ…
週5日
250,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿海外 |
|---|---|
| 役割 | バックオフィスオペレーター |
| ・ | |
定番
【フロントエンドエンジニア】自社サービス開…
■業務内容 ・自社サービス開発/運用/保守 ■開発環境 ・Ruby on Rails ・…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・o… | |
定番
【フルリモ / Kotlin / 週5日】…
スマートシティ化において、よりよい体験を利用者に提供するためのiOSアプリケーション開発をお願いでき…
週5日
500,000〜1,170,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町虎ノ門駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・・ | |
定番
【フルリモート!Rubyエンジニア】自社サ…
■業務内容 ・自社サービス開発/運用/保守 ■開発環境 ・Ruby on Rails ・…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・o… | |
定番
【フルリモート!インフラエンジニア】自社サ…
■業務内容 ・自社サービス開発/運用/保守 ■開発環境 ・Ruby on Rails ・…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Ruby・o… | |
【フルリモート!データエンジニア】電力需要…
【業務内容】 ・エネルギー企業様 電力需要予測基盤の構築 インフラ系のクライアント案件にて、Bi…
週3日・4日
370,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| SQL・・ | |
【フルリモート可!/BIエンジニア】
【業務内容】 BigQueryに収集されたデータを元に可視化ダッシュボードをLookerStdio…
週3日・4日
370,000〜500,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | BIエンジニア |
| SQL・・ | |
定番
【フルリモート可!カスタマーサクセス】自社…
【業務内容】 ・メール/LINE/サイト上で顧客に届けるコンテンツ企画・制作・配信 ・顧客に対す…
週3日・4日
250,000〜300,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | カスタマーサクセス |
| ・ | |
定番
【リモート可】2Dイラストレーターとしてゲ…
【会社概要】 ゲームを中心としたコンテンツで「世代を超えた感動を提供し続ける」をミッションに掲げた…
週4日・5日
300,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川- |
|---|---|
| 役割 | 2Dイラストレーター |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】DX…
【業務内容】 ・技術やアーキテクチャ選定 ・開発チームの生産性の向上 ・コードレビューを通じた…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Ruby・Go・・ | |
定番
【SNS運用】自社アパレルブランドのSNS…
【業務内容】 自社アパレルブランドのSNS運用を中心にご担当いただきます。 【具体的な仕事内…
週5日
300,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | SNS運用担当 |
定番
【Java案件|リモート可能】生産管理シス…
■作業内容 ・外部設計(ユーザーインターフェース設計) ・詳細設計 ・プログラム作成 ・単体…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲天王洲アイル駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SQL・Java、SQL | |
定番
[ディレクター]自社開発/大手クライアント…
【仕事内容】 主に以下のディレクション業務全般となります。 ・大手自動車企業へ納入中の自社開…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | ディレクター |
定番
【フルリモート可!UIデザイナー】自社スマ…
【業務内容】 ・自社のアプリのUIデザイン( iOS, Android ) ・自社のPC/SP …
週3日・4日・5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| ・ | |
【フルリモート可!デザイン兼コーダー】自社…
【業務内容】 ・要件書を基にしたデザイン作成 ・CTRを高めるバナー作成やボタン作成 など ~…
週5日
350,000〜470,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイン兼コーダー |
定番
[PM]自社開発/大手クライアント案件中心
【仕事内容】 スマホ、Webアプリ開発のディレクター(PM/PL)をお任せします。 スキルに合わ…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・ | |
定番
[UI/UXデザイナー]自社開発/大手クラ…
■業務内容 ・Webサイトの新規制作やリニューアルのデザイン提案 ・デザインコンセプト・トーン&…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
[フロントエンド]自社開発/大手クライアン…
【仕事内容】 クライアント案件サイトのサイト実装・サーバ構築やWebサイトおよびスマホアプリなどの…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿上町駅/桜新町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
定番
【Python】自社ヘルスケア領域の新規事…
【業務内容】 ・コンピュータビジョンおよびDeep Learning技術を用いたシステムの開発 …
週2日・3日・4日・5日
230,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿本郷三丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | (正社員切替前提)AI・機械学習エンジニア |
| Python・Linux・ | |
【フルリモート!マークアップ 兼 フロント…
【具体的な業務】 ・LPやコーポレートサイトのマークアップ(時期によるが7割前後) ・フロン…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿フルリモート |
|---|---|
| 役割 | マークアップエンジニア |
新着
定番
【一部リモート / Python / 週5…
画像認識に関する最新の知見を導入し、製品実装に向けた先行開発を担当していただきます。 ・最新の…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 池袋池袋駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・・ | |
定番
【フルリモ / Python/SQL / …
【業務内容】 専門知識を活かした機械学習システムの構築を主に担当していただきます。 ◆クラウド上…
週5日
670,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原秋葉原駅 |
|---|---|
| 役割 | AI・機械学習エンジニア |
| Python・SQL | |
定番
【フルリモOK / インフラ / 週5日】…
【業務内容】 パブリッククラウド(Google Cloud,AWS,Azure)におけるインフラに…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 秋葉原- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
[フルリモ!/新規事業/PM]生成AIに関…
【業務内容】 生成AIに関わる新規事業立上げメンバー募集しております。 アパレルEC向け画像生成…
週1日
120,000〜160,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
新着
定番
【開発ディレクター】クラウド人材管理ツール…
【業務内容】 ・カオナビの機能改善、新規機能の開発ディレクション、要件定義と開発進捗管理 ・他の…
週4日・5日
470,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 開発ディレクター |
| ・ | |
定番
【Swift/フルリモート】グローバル向け…
リリースに向け、組織として健全な開発体制を敷きたいと考えています。 開発するアプリのレベルが高難易…
週5日
590,000〜900,000円/月
| 場所 | 千葉新浦安 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア(Swift) |
| Swift・swift・AWSorGCP・git・G… | |
定番
【Kotlin/フルリモート】グローバル向…
リリースに向け、組織として健全な開発体制を敷きたいと考えています。 開発するアプリのレベルが高難易…
週5日
590,000〜900,000円/月
| 場所 | 千葉新浦安 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア(Kotlin) |
| Kotlin・ | |
定番
【Go言語/フルリモート】グローバル向け大…
リリースまでの開発組織はなんとか構築済みではあるものの、リソース的にはギリギリであり、組織として健全…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 千葉新浦安 |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・ | |
定番
【インフラエンジニア/フルリモート】グロー…
インフラエンジニアとしてアプリの開発に加わっていただけるメンバーを募集しております。 具体的にはラ…
週5日
510,000〜640,000円/月
| 場所 | 千葉新浦安 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【アカウントプランナー】自社デジタル広告の…
【業務内容】 ・クライアントのマーケティング/デジタル広告課題のヒアリング ・デジタル広告を中…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター(アカウントプランナーポジション) |
| ・ | |
定番
【フルリモートOK|開発案件】医療データ分…
【仕事内容】 ・バックエンド開発 ・ビジネス要件を考慮したアーキテクチャの設計、開発 ・技術観…
週5日
2〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | C# or GO エンジニア |
| Go・C#・・ | |
定番
【フルリモートOK|Ruby案件】健康相談…
【案件内容】 健康相談チャット/医師紹介サービス」のバックエンド保守運用をメインにご担当いただきま…
週5日
2〜3.6万円/日
| 場所 | 渋谷・新宿大門駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| SQL・・ | |
【PM/フルリモ‼】大手フィットネス企業に…
【業務内容】 大手フィットネス企業における業務改革 ・急速に拡大するフィットネスジムの業務が煩…
週5日
550,000〜670,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
【フルリモ / Flutter / 週3日…
【業務内容】 ・プロダクトの戦略立案から携わり、機能要求を満たすプロダクトの企画から設計 ・ユ…
週3日・4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| Flutter・ | |
【プロダクトデザイナー】契約書レビュープラ…
■どういう業務に取り組むのか - 在籍するプロフェッショナルたちと密に連携してソリューションに形…
週4日・5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
| ・ | |
定番
【フルリモ/マーケター】自社ECサイトの運…
【業務内容】 自社EC(食品)のグロースのため運用とInstagramの広告運用を依頼いたします…
週3日
180,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿丸の内 |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
定番
【フルリモ / 講師 / 週5日】人材育成…
■業務内容 ・対象は、若手社員育成を担う研修業務に参画いただきます ・社内で実施している「組込研…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲- |
|---|---|
| 役割 | 講師(組み込みエンジニア) |
| C・C++・ | |
定番
【プロダクトデザイナー】デジタルウォレット…
本ポジションは、デジタルウォレットアプリにおける、アプリのデザイン全般を担当するポジションです。 …
週5日
330,000〜450,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿表参道駅 |
|---|---|
| 役割 | プロダクトデザイナー |
定番
【基本リモート / Java / 週5日】…
【プロジェクト概要】 数年前に構築した大規模な基幹システムの、メンテナンスおよび新規開発案件の立ち…
週5日
790,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・React.js・Vue.js・Sprin… | |
【Webディレクター/フルリモート】サイト…
■想定プロジェクト ・某大手グループ企業 IRサイト・コーポレートサイトの新規構築~リニューアル…
週4日・5日
620,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
【フルリモOK|デザイナー案件】CRM強化…
【案件内容】 CRM強化のため、各種MAツールで配信する内容をグレードアップしたいと考えており、 …
週4日・5日
230,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | デザイナー |
| SQL | |
定番
【リモート可 / Typescript /…
【案件】 大手不動産会社の建築部門の実行予算管理システムの追加開発(長期案件) 【主な業務内…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大森駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・Vue.js・ | |
定番
【フルリモ / Androidエンジニア …
・保育IcTの企画・開発・保守 ⇒保育施設の業務効率支援システムとなり、 保育士や保護者…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin・・ | |
定番
【リモート可 / Java / 週5日】大…
【案件】 大手不動産会社の建築部門の実行予算管理システムの追加開発(長期案件) 【主な業務内…
週5日
500,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大森駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・SpringBoot・Docker・MyS… | |
定番
【フルリモ / 週5日】データ分析基盤のサ…
【企業】 大手SIer企業 【業務内容】 顧客向けに弊社のデータ分析基盤の構築ソリューショ…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川品川エリア |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Python・GitHub・Actions・・YAM… | |
定番
【フルリモOK!データ案件】電動モビリティ…
【仕事内容】 ・データの戦略、活用方法、データによる競争優位性の設計 ・Airflow, Big…
週3日・4日・5日
700,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【情報セキュリティ室/コーポレートIT担当…
【具体的な業務内容】 ・IT戦略の設計、立案 ・デジタルリテラシーの維持、向上 ・IT基盤、I…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | コーポレートエンジニア |
| ・ | |
定番
【情報セキュリティ担当】CSIRT(Com…
(1)グループ全体のセキュリティ戦略を策定し、セキュリティ活動がグループ全体にとって最適化された形で…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | 情報セキュリティ担当 |
| ・ | |
定番
【Pythonエンジニア|フルリモート】自…
バックエンドの設計および開発。新機能の追加開発や既存機能の改修などをご担当して頂きます。 必要であ…
週5日
620,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・ | |
定番
【テックリード】大手フィットネス企業におけ…
・リリース済のフィットネスアプリについて、エンハンスを日々実施しております。 ・元々はFlutte…
週3日・4日・5日
940,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・ | |
定番
【正社員】大手携帯キャリアの広告戦略におけ…
大手広告代理店内に常駐して広告企画、提案・マーケティング運用部隊のディレクション業務をお任せいたしま…
週5日
/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS・- | |
定番
【フルリモ / 週5日】AWS CDK関連…
■企業 SIer企業 ■業務内容 本プロジェクトは既存公開中のWebサイト/Webシステム…
週5日
560,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Typescript・CDK(Typescript)… | |
定番
【フルリモ / 週5日】AWSマイグレーシ…
■企業 SIer企業 ■業務内容 本プロジェクトは、地方自治体向けの弊社パッケージソフト(…
週5日
560,000〜710,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| Typescript・CDK(Typescript)… | |
定番
【フルリモ / Ruby on Rails…
■求人紹介 当社では、高校を中心とした既存サービスに加え、2022年4月〜小中学校も含めた保護者向…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails・・AWS・・R… | |
【副業案件‼Python、PHP】報道テク…
【業務内容】 ・PHP で書かれた情勢調査システムのPythonへのリプレイス ■具体的に…
週3日
510,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・・ | |
定番
【副業案件!月14時間〜シフト制!】子ども…
【仕事概要】 近年、子どもたちのより身近な相談場所としてSNSが注目されています。 今回募集…
週2日・3日・4日・5日
230,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 心理カウンセラー |
| ・ | |
定番
【リモート2日!フロント案件】脆弱性管理ク…
【業務内容】 ・脆弱性管理クラウドに関わる設計・開発・テストを担当いただきます。 ・API開発、…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・Typescript・ | |
【フルリモ / Python/Go / 週…
【業務内容】 ・自社システム運用や新規機能開発 <具体的には> Python、Go を使…
週4日・5日
860,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Python・Go・AWS・Vue.js・React… | |
【Ruby/フルリモート‼】自社チャットプ…
【業務内容】 バックエンドエンジニアとしてwebプロダクト開発。 スクラムに参加し、開発チケッ…
週4日・5日
940,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・RubyonRails・ | |
【PdM/フルリモート】自社チャットプロダ…
【業務内容】 1:プロダクト・ロードマップの作成 2:プロダクトのグロースに関わるKPI目標の…
週4日・5日
1,100,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
| Ruby・・ | |
定番
【講師(Java)】新人研修のメイン講師業…
■募集背景 ありがたい事にニーズが増えており、リソースが足りない状況の為、 人材を募集する背景…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅 |
|---|---|
| 役割 | 講師(Java) |
| Java・C# | |
定番
【リモート可能!フロント案件】ボイスボット…
■案件内容 ボイスボットサービスの大幅な機能アップデートを予定しており、 フロントエンドエンジニ…
週5日
390,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浜松町駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【Salceforceエンジニア/リモート…
【募集背景】 業績好調のため各事業領域での事業拡大に向けて、要員を募集しています。 【業務内…
週5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・・ | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
【作業内容】 ヘルスケア領域での自社プロダクトの開発をお任せいたします。 メインでお願いする…
週4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・Redwood.js・・Rea… | |
定番
【取材ライター】美容メディア
【業務内容】 美容メディアの編集者として、コンテンツの企画やチェック・校正・校閲・ライティングな…
週3日・4日・5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | 編集ディレクター |
定番
【フルリモ / フルスタックエンジニア /…
■業務内容 自社サービスのソフトウェア開発業務をお任せします。 該当自社サービスはすでにリリース…
週5日
390,000〜660,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京汐留駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Typescript・Chrome・・React・・… | |
【フルリモ / Unity/C# / 週4…
【案件内容】 新規タイトルにおけるクライアント開発担当者を募集します! Unityで開発する、…
週4日・5日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| C・C++・Unity・ | |
定番
【フルリモート可能!デザイン】オンラインR…
【案件内容】 オンラインRPGのドットデザイナーとして、 お客様により楽しんで頂くためのゲーム…
週4日・5日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
| C・C++・・ | |
定番
【Java案件|リモート可能】生産管理シス…
■作業内容 ・外部設計(ユーザーインターフェース設計) ・詳細設計 ・プログラム作成 ・単体…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 豊洲三田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(Azure) |
定番
【エンジニアリングマネージャー/フルリモー…
・ロール:Engineering Manager(新規案件) ・システム:新規案件 ・クラス:E…
週5日
700,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Engineering Manager |
| PHP・Typescript・・ | |
定番
【Rubyエンジニア/リモート可】自社サー…
■業務内容 ・自社サービスを新規顧客/既存顧客に届けるための機能開発 ・お客様の法務業務を深く理…
週5日
390,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・Java・Go・Typescript・Ru… | |
定番
【サーバー構築/フルリモート‼】大手フィッ…
・店舗内機器・デバイスとの接続、データ取得と制御システムの設計、実装、PoC ・スマホアプリや既…
週4日・5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | オンプレエンジニア |
定番
【組み込み/フルリモート‼】大手フィットネ…
・組み込み機器のPoCの作成、ファームウェア設計、実装、検証 ・センサーデータの加工分析、制御ア…
週4日・5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 組み込みエンジニア |
定番
【フルリモ / PM/PdM / 週4日〜…
・店舗に設置する各種機器やデバイスと、それと連携するシステムの企画 ・仮説に基づいたPoCの実施 …
週4日・5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PdM |
【フルリモOK|Ruby案件】官公庁や自治…
【業務内容】 官公庁・自治体等の入札・落札情報を探せる「入札情報速報サービス 」及の機能開発・保守…
週5日
670,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| HTML・JavaScript・Ruby・・ | |
新着
定番
【リモート可能|インフラ案件】カード認証基…
■案件内容 クレジットカード認証プラットフォーム開発におけるインフラを担当していただきます。 …
週5日
500,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋事務所 JR浅草橋駅 ・秋葉原拠点:JR秋葉原駅" |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
| Java・SQL・Java、SQL・ | |
定番
【リモート可能!COBOL案件】都市銀行内…
【案件内容】 都市銀行内国為替維持メンテナンス ▼業務内容 ・保守 バッチ業務 ・既…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | COBOL |
| COBOL・ | |
定番
【リモート可能!上流SE案件】大手損保新契…
【案件内容】 大手損保新契約連携支援を担当していただきます。 ▼業務内容 ・基本設計~結合…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 上流SE(設計メイン) |
定番
【リモート可能!ServiceNow案件】…
【案件内容】 大手SI企業社内システム開発を担当していただきます。 ▼業務内容 Servi…
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | ServiceNowエンジニア |
定番
【大阪常駐|C#案件】産業機器のPC設定ソ…
■案件内容 ・業界メーカー向けの部品製造会社 ・産業機器のPC設定ソフトウェア開発に携わっていた…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿浅草橋事務所 JR浅草橋駅 ・秋葉原拠点:JR秋葉原駅" |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週3日】動画配…
■業務内容 ・動画配信サービスの配信システム機能拡張 - 動画に関する各種データ(インプレッシ…
週2日・3日
270,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・PHP・・ | |
注目
【リモートOK|UI/UXデザイナー案件】…
■案件内容 当社ではtoBからtoC向けまで複数のサービスを展開しており、 今回は各サービスのU…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京神田駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・ | |
定番
【フルリモートOK!動画編集案件】宿泊業界…
■案件内容 宿泊業界や保育業界、子育て世帯向けのメディアの動画編集、アニメーションをお任せいたしま…
週4日・5日
300,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【アシスタント】自社事業企画部門のアシスタ…
【業務内容】 ・企画アシスタント〜高度な企画業務まで幅広くお任せできたらと考えております
週3日
130,000〜180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | アシスタント |
| ・ | |
定番
【C#/Java / 週5日】自社SaaS…
【業務内容】 ・ECパッケージの機能開発 ・周辺SaaSサービスの開発
週5日
390,000〜500,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Java・C#・・ | |
定番
【東京常駐|C#案件】産業機器のPC設定ソ…
■案件内容 ・業界メーカー向けの部品製造会社 ・産業機器のPC設定ソフトウェア開発に携わっていた…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京テレポート |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・ | |
定番
【社内SE/リーダー候補】社内システムにお…
<具体的な業務内容> ・uSonarを活用し、Salesforce内にある顧客情報の整理 ※S…
週5日
300,000〜560,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | 社内SE |
【PM/フルリモート‼】自社チャットボット…
【業務詳細】 1:プロジェクトの進行管理 ・CTO, PdMの指揮の元、開発PJTをPMとして…
週4日・5日
790,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・ | |
【フルリモ / Typescript/No…
【業務内容】 事業の拡大やデータ量の増加に伴った新システムへの移行業務をお願いできる方を募集いた…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿五反田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Typescript・SQL・Laravel… | |
定番
【マーケター】自社アプリのマーケティング担…
自社オンライン通販アプリのマーケティング担当として、 ブランドのアプリシェア率向上に向けた分析およ…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ・ | |
定番
【グラフィック】グラフィックデザイナー・P…
【業務内容】 PR事業本部にてグラフィックデザイナーとして、 グループ各ブランドSNSで使用する…
週5日
230,000〜440,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | グラフィックデザイナー |
| ・ | |
定番
【WEBデザイナー】自社ブランドサイトのデ…
【業務内容】 グループブランドのオフィシャルWEBサイトにおけるサイトデザイン業務をお任せいたしま…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBデザイナー |
| ・ | |
定番
【フルリモ / システムエンジニア / 週…
【概要】 日系化学品製造業のD365展開プロジェクト(US、2025年2月稼働予定)にて、財務会計…
週5日
1,260,000〜1,410,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京丸ノ内駅 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
【Rubyエンジニア】開発・工数見積関連作…
【募集背景】 組織・事業拡大に伴い、社内体制をより強化していく段階になります。 業務フローがまだ…
週1日
150,000〜180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PMO |
| PHP・Ruby・ | |
[フルリモ/インフラ]大手エンタメ会社向け…
【業務内容】 クライアント先のサービス(グローバル含む)におけるインフラ(主にクラウド)の設計、構…
週3日・4日・5日
300,000〜1,230,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町赤坂駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
定番
【Salesforceエンジニア】大手SI…
◇案件概要 大手SIerへの社内Salesforce導入 本番利用開始前(トライアル期間)、他開…
週5日
470,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲 |
|---|---|
| 役割 | Salesforceエンジニア |
| Salesforce・ | |
定番
【SEOマーケ】リーガルテック企業における…
【案件概要】 弊社の事業全体のマーケ施策を考え、実行いただくポジションでの募集になります。SEO…
週4日・5日
470,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿西新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOマーケター |
| ・ | |
[Typescript/リモート‼]自社T…
◾業務内容 ・開発プロジェクトにおけるフロントエンド開発 ・機能開発における設計~実装~リリー…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ・ | |
【フルリモOK|Java案件】AIを用いた…
【案件内容】 AIを用いた自社サービスのWEBアプリ開発 ▼業務内容 ・バックエンド領域…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・ | |
【フルリモOK|AI/機械学習案件】Web…
【案件内容】 AIの領域でプロダクトを複数開発/運営するクライアントにて、AIエンジニアの方を募集…
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | AI・機械学習エンジニア |
| Python・ | |
定番
【PHPエンジニア/フルリモ!】自社グルー…
・ロール:バックエンドエンジニア(新規案件) ・システム:新規案件 ・クラス:メンバー以上 ※…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア |
| PHP・Typescript・・ | |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週5日…
・ロール:フロントエンドエンジニア(新規案件) ・システム:新規案件 ・クラス:メンバー以上 …
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Typesc… | |
定番
【フルリモ / PM / 週3日〜】モバイ…
【案件内容】 AIの領域でプロダクトを複数開発/運営するクライアントにて、プロジェクトマネージャー…
週3日・4日・5日
750,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM(IOSまたはAndroid) |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
【EM/フルリモ!】自社サービスに関するE…
・ロール:Engineering Manager(WEB系) ・システム:自社システム ・クラス…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Engineering Manager(WEB系) |
| ・ | |
定番
【PHPエンジニア】自社サービスに関するバ…
・ロール:バックエンドエンジニア(WEB系) ・システム:自社システム ・クラス:メンバー ※…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(WEB系) |
| JavaScript・PHP・・ | |
定番
【PM/フルリモ!】自社サービスに関するプ…
・ロール:プロジェクトマネージャー(WEB系) ・システム:自社システム ・クラス:PM ※業…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | プロジェクトマネージャー(WEB系) |
| ・ | |
定番
【Flutterエンジニア/フルリモ!】自…
・ロール:toC Platform(フロントエンド) ・システム:toC ・クラス:メンバー …
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Flutterエンジニア |
| ・ | |
【フルリモOK|PHP案件】CRMシステム…
【案件内容】 CRMシステムのリプレイス開発における、PHPエンジニアの方を募集します。 ※サッ…
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・ | |
定番
【フルリモ / Flutter / 週5日…
■仕事内容 当社のtoC向けサービスのスマートフォンアプリ開発をご担当頂きます。 バックエンドエ…
週5日
580,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア(Flutter) |
| ‐ | |
定番
【フルリモ / Unity/C# / 週4…
【案件内容】 新規タイトルにおけるクライアント開発担当者を募集します! Unityで開発する、…
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア(ゲーム経験不要) |
| C#・ | |
【アシスタントPM】装置製造メーカーのデジ…
【業務内容】 ・装置製造メーカーのデジタルマーケティング戦略策定 ・具体的なデジマ施策に落とし…
週3日・4日
440,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿北品川 |
|---|---|
| 役割 | PMO |
定番
【フルリモ / TypeScript./ …
■作業内容 フロントエンド開発を担当するスクラムチームにおいて スプリント単位での画面開発業務を…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿初台駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・React・・Next.js | |
定番
【TypeScriptエンジニア】大手フィ…
フィットネス企業におけるtoC向けサービスに関連するwebサービスのフロントエンドを構築していただき…
週3日・4日・5日
790,000〜1,180,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・ | |
定番
【フレックス勤務可!フルスタック案件】スタ…
【案件内容】 サービスローンチより3年が経過し、導入社数は4000社を超えました。 今後更なる…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Typescript・ | |
Pythonの研修講師
【具体的な業務内容】 <共通> ・研修の企画・準備 ・研修の実施と運営 ・顧客へのレポーテ…
週5日
1,580,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Python研修講師 |
| Python・ | |
定番
【フルリモ / フルスタック / 週5日】…
【業務内容】 ・Ruby on Rails, Python等を使ったWebアプリケーションの実装開…
週5日
560,000〜790,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| Python・Ruby・・ | |
【リモート可!PM案件】複数プロジェクトを…
【案件内容】 現在、ファシリティマネジメント及びプロパティマネジメントに特化した システム開発を…
週2日・3日
270,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【女性向け自社メディア】ライター
【業務内容】 自社で運営しているメディアサイトの編集者として、SEOコンテンツ制作・編集業務に従…
週3日・4日・5日
150,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
【大手企業!リモート可!AI開発案件】Io…
【案件内容】 カメラ画像・データから機械学習モデルを構築し業務を最適化。 IoT カメラの選定…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | AI・機械学習エンジニア |
| Python・ | |
定番
【サーバーサイドエンジニア】特権ID管理製…
■依頼内容 お客様の自社製品である特権ID管理製品、または、操作記録・監視製品の開発プロジェクトで…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京水天宮前駅、浜町駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Ruby・Ruby・on・Rails・・・Vue.j… | |
定番
【広告×AI事業】リードデザイナー
<具体的な業務内容> ・ ユーザーインサイトに基づいたLINEチャットボットのクリエイティブ制作 …
週4日・5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 秋葉原湯島駅 |
|---|---|
| 役割 | リードデザイナー |
定番
【Pythonエンジニア】HR系企業のデー…
具体的な作業内容は下記となります。 ・分析用データマートの開発 └データマート(テーブル)設計…
週5日
550,000〜590,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋東京駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア |
| Python・SQL・・ | |
定番
【Goエンジニア】GOを用いたAPI開発案…
社内コミュニケーションサービスや大手クライアントのシステム受託開発を展開している企業にて、今回はGo…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 水道橋・飯田橋- |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・ | |
定番
【PHPエンジニア】自社配送サービスシステ…
【企業概要】 ネットスーパー事業を展開する企業です。ネットスーパーでの注文から自宅での受け取りま…
週3日・4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Laravel | |
定番
【4月開始!リモート可!PM案件】顧客社内…
ーーーーーーーーーーー ★おすすめのポイント★ ・大手SI企業で安定した稼働ができます! ・リ…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(Java経験) |
| Java・ | |
定番
【フルリモ―ト!Typescript/Re…
【仕事内容】 - 当社プロダクトのフロントエンド領域における設計や機能開発・実装・レビュー・テスト…
週4日・5日
500,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンジニア |
| JavaScript・Typescript・・ | |
定番
【4月開始!大規模SI事業のJava案件】…
■案件内容 医療機器における遠隔操作用Webアプリ開発及びPM業務 ■業務概要 ・医療機器…
週5日
500,000〜880,000円/月
| 場所 | 豊洲赤羽駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア(react経験必要) |
| JavaScript・Java・ | |
定番
【即日開始可!大規模SI事業の組み込み案件…
■案件内容 システムのプラットフォーム化に伴うLinux環境構築でのシステム開発 ■業務概要…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 豊洲菊名駅 |
|---|---|
| 役割 | C/C++/組み込みエンジニア |
| C・C++・ | |
定番
【フルリモート!SNSマーケター】美容医療…
【業務内容】 - 自サービス・クリニックのSNS運用 - 外注先のクオリティコントロール -…
週3日・4日・5日
230,000〜390,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | SNSマーケター |
【4月開始!フルリモOK!上場企業/フロン…
【業務内容】 官公庁・自治体等の入札・落札情報を探せる「入札情報速報サービス 」及の機能開発・保守…
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(PHP経験含む) |
| HTML・JavaScript・PHP・・ | |
【4月開始!フルリモOK!上場企業/フロン…
【業務内容】 官公庁・自治体等の入札・落札情報を探せる「入札情報速報サービス 」及の機能開発・保守…
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア(vue.jp経験含む) |
| JavaScript・PHP・・ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】自社…
【案件概要】 自社で運営する、動画プラットフォームの開発・運用・保守をしていただきます。 今後発…
週4日・5日
550,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・ | |
注目
【フルリモ / Kotlin / 週4日〜…
■求人紹介 当社では、高校を中心とした既存サービスに加え、2022年4月〜小中学校も含めた保護者向…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Kotlin | |
注目
【フルリモ / Swift / 週4日〜】…
■求人紹介 当社では、高校を中心とした既存サービスに加え、2022年4月〜小中学校も含めた保護者向…
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift | |
定番
【フルリモ / 週4日〜】患者・医療従事者…
【作業内容】 患者(toC)、医療従事者(toB)に対するUIUXデザインをご担当頂きます。 …
週3日
370,000〜470,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
定番
【フルリモ / Ruby,React.js…
■業務内容 国内最大級のゲーム情報サイトを運営されている企業での新規サービスの開発案件です。 …
週5日
420,000〜590,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・React.js | |
注目
【インフラエンジニア】国内初プラットフォー…
■企業について システム開発事業、レンタルシステム事業、イベントソリューション事業の3つの事業で自…
週5日
410,000〜570,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
【PM・サーバーサイドエンジニア】事業横断…
▼業務内容 ・インフラ、データベースのシステム移行の要件定義、計画、調整などのプロジェクトマネジ…
週5日
700,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| Ruby・ | |
【リモート可 / フロントエンド / 週4…
自社印刷ECプロダクトのアプリケーション開発案件です。 ビジネス要求に答える開発案件と運用、技術負…
週5日
700,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Ruby・Typescript・ | |
定番
【フルリモ / PHP / 週4日〜】クレ…
【案件概要】 ・サーバーサイドエンジニアとして、PHPを用いたシステム開発と保守のサポート業務 …
週4日・5日
550,000〜810,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・ | |
定番
【週3日OK!フルリモートOK|Andro…
■案件概要 主力サービスのコミックビューア開発、電子小説サービスのや関連サービスにおけるネイティブ…
週3日・4日
370,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿外苑前 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Swift・Ob-C・AndroidJava・Kot… | |
定番
※2024年4月〜5月【インフラ/ネットワ…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラサブ講師 |
| Linux・ | |
定番
【フルリモ可能!WEBサイト制作案件】大手…
<プロジェクト概要(現在の想定)> ・クライアント -大手家電量販店 ・プロジェクト一例…
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(インフラ経験含む) |
| JavaScript・- | |
定番
【Ruby経験豊富な方募集!】 感情データ…
【案件内容】 感情データを活用して顧客体験を改善するクラウドサービスの保守・改善に携わっていただ…
週5日
580,000〜880,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町永田町駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・ | |
定番
【4月開始!Java講師案件】Javaエン…
【企業】 当社は、人材教育、研修、セミナーを中心に事業を展開しております。 【業務内容】 …
週5日
470,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Java講師 |
| Java・・ | |
定番
【フルリモ / コーダー / 週4~5日】…
■業務内容 WordPressにてコーポレートサイト、HP等をコーディングする業務を想定しておりま…
週4日・5日
230,000〜300,000円/月
| 場所 | 群馬・栃木・茨城- |
|---|---|
| 役割 | コーダー/マークアップエンジニア (WordPress使用) |
| HTML・CSS・JavaScript・SCSS・・… | |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
■ポジション概要 TypeScriptのバックエンドとフロントエンド(Redwood.js, Pr…
週4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・Redwood.js・・Pri… | |
定番
【スマホアプリエンジニア】自社配送サービス…
ラストワンマイルDXを進めるためのtoB、toC向けスマホアプリの開発及び運営を担当していただきま…
週4日・5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 関西:大阪・京都・神戸西中島南方駅 |
|---|---|
| 役割 | スマホアプリエンジニア |
| Swift・・ | |
定番
【フルリモOK!Webデザイナー案件】旅行…
【案件内容】 デザインをはじめ、ホームページの構成から撮影までできるチーム編成により、 質の高い…
週4日・5日
150,000〜330,000円/月
| 場所 | 九州:福岡・沖縄大分 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・-・Mac、Illustrator… | |
定番
【急募!フルリモOK|フロント案件】社会人…
【案件内容】 社会人教育事業、高等教育機関向けDX事業のフロントエンド開発をお任せします。 …
週5日
580,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンド |
| JavaScript・Vue・React・Rubyo… | |
定番
【リモート可能!インフラ案件】某大手自動車…
【案件内容】 当ポジションは、AWS、Dockerを用いてIVI (車載関連システム)の環境構築、…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(AWS/Azure) |
| AWS・Docker・CI・CD・ | |
定番
【Java講師案件|2024年4月~6月】…
新入社員向けIT研修にてメイン講師を担当していただける方を募集しております。 今回の案件では、カリ…
週5日
2.4万円以上/日
| 場所 | 渋谷・新宿-駅 |
|---|---|
| 役割 | C#,VB.net,ASP.netサブ講師 |
| C#・VB.NET・・ | |
定番
【インサイドセールス】自社のインサイドセー…
【業務内容】 ・お問合せ対応業務 ┗電話対応 ┗メール対応 ┗アポイント獲得のアプローチ …
週3日・4日・5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京駅 |
|---|---|
| 役割 | インサイドセールス |
| ・ | |
【PdM/ハイブリッド勤務】印刷事業におけ…
基本的には安定運用している集客支援事業部Scrumの運用を回していただきつつ、 スポットでロイヤリ…
週5日
790,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【即日可!リモート可!C#案件】キャリアに…
■案件内容 ロボットソフトウェアの開発を担当していただきます。 ■作業内容 下記①~③のど…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿東京ビックサイト駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア(Java経験メインでもOK) |
| Java・C#・ | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
★おすすめのポイント★ ①難易度高い技術的課題に向き合い、問題解決力が身に付く環境 ②モダンな技…
週5日
620,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンド |
| JavaScript・Vue・React・Rubyo… | |
定番
【フルリモ / JavaScript / …
======================= ★おすすめのポイント★ 直接顧客のPOと折衝対応…
週5日
700,000〜880,000円/月
| 場所 | 秋葉原- |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(インフラ経験含む) |
| JavaScript・- | |
定番
【4月開始!フルリモOK!上場企業/フロン…
★おすすめのポイント★ ・0→1のプロダクトに携わることができる ・行政・公共入札という日本を支…
週5日
700,000〜880,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(PHP経験含む) |
| HTML・JavaScript・PHP・・ | |
定番
【フルリモ / Typescript / …
=============================== 今回の募集は新規プロジェクトに携わ…
週5日
550,000〜750,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町リモート |
|---|---|
| 役割 | 【沼田さん案件】フロントエンドエンジニア |
| JavaScript・Typescript・・ | |
定番
【週3日~ / フルスタックエンジニア /…
■募集背景 技術組織の拡充とともに、お手伝いいただける人材を探している背景 ■業務内容 …
週3日・4日・5日
1,100,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(フロントエンド寄り) |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
【大規模SIer|フルリモ案件】1人称で対…
【案件内容】 某大手不動産契約者ページの改修対応を担当していただきます! ※電子契約の改修案件に…
週5日
410,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java | |
定番
【週3日~ / フルスタックエンジニア /…
■募集背景 技術組織の拡充とともに、お手伝いいただける人材を探している背景 ■業務内容 …
週3日・4日・5日
1,100,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(バックエンド寄り) |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
定番
自社サービスHPのWeb UIデザイナー
事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先…
週5日
470,000〜530,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー / UIデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・Illust… | |
定番
【フルリモ / Webデザイナー / 時短…
■業務内容 スポーツに特化したビジネスを展開している当社にてWEBデザイナーの方を募集いたします!…
週5日
380,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| HTML・CSS・JavaScript・SCSS・・… | |
マーケター
【ミッション】 店舗スタジオ事業・オンライン事業におけるデジタル施策を通じた新規顧客獲得、LTVの…
週4日・5日
300,000〜410,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【フルリモ!サーバーサイドエンジニア】フル…
▼採用ポジション 自社エンジニアとして稼働しつつ、開発チームをリードする役割を担っていただきます。…
/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅/北参道駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア(PHP/リーダー候補) |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Ru… | |
定番
【フルリモートOK!フルスタック案件】保育…
■案件内容 自社プロダクトにおける新規機能開発・既存機能改修を行っていただきます。 【具体的…
週5日
470,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Typescriptエンジニア |
| Typescript・フロントエンド:・TypeSc… | |
定番
【フルリモOK!フロント案件】全国拡大中の…
【案件内容】 Webフロントエンジニアは、主に社内向けのWeb管理画面を中心とした Webフロン…
週4日・5日
410,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(Typescript) |
| Typescript・ | |
定番
【JavaScriptエンジニア】大手新聞…
■業務内容 Nuxt.jsを使用したサイトの管理画面を作成をお願いいたします。 ただ、作業として…
週5日
420,000〜590,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京三田駅、もしくは田町駅 |
|---|---|
| 役割 | JavaScriptエンジニア |
| JavaScript・Nuxt.js・・Vue.js | |
定番
【マーケター】自社サービスに関するSEOマ…
【募集背景】 ブランド品や貴金属の買取専門店を展開する当社。設立6年目にして全国40店舗以上を展開…
週5日
300,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | SEOコンサルタント |
| ・ | |
【フルリモ / LLM / 週5日】生成A…
【業務内容】 開発したい機能の概要やスコープは社内メンバー(アドバイザリ含む)で整理が進んでいる…
週5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | LLMエンジニア |
| Python・Typescript・・ | |
【リモート相談可 / AIエンジニア / …
■業務内容 ・AIモデルのエッジデバイスへのデプロイと運用 ・エッジデバイス上で動作するカメラ…
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | AIエンジニア |
| Python・・ | |
定番
【フルリモOK|コンサル案件】ビジネスコー…
▼案件概要 ・海外企業の運営する会員制コミュニティサイトの日本版サービスを検討中 ・概念検証、試…
週2日・3日・4日
250,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | コンサルティング |
【リモート可 / PM / 週5日】金融系…
【案件内容】 金融系端末更改プロジェクトのプロジェクトマネジメントをお願いします。 ※2025…
週5日
470,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
新着
定番
【フルリモOK!労務事務経験ある方へ】人材…
【案件内容】 人材紹介・派遣事業における労務/契約事務周りを担当していただきます。 ▼作業内…
週2日・3日
270,000〜750,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | 労務事務担当 |
【フルリモ / iOSエンジニア / 週5…
【業務内容】 某マッチングアプリ(iOSアプリ)開発作業において 要件定義から実装、単体検証ま…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | iOSエンジニア |
| Swift・Ob-C・・ | |
【フルリモ / Androidエンジニア …
【業務内容】 某マッチングアプリ(Androidアプリ)開発作業において 要件定義から実装、…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| Java・Kotlin・・ | |
【フルリモ / インフラエンジニア / 週…
■募集背景 技術組織の拡充とともに、お手伝いいただける人材を探している背景 ■業務内容 …
週3日・4日・5日
1,100,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿品川駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(フロントエンドorバックエンド寄り) |
| JavaScript・PHP・Python・Java… | |
新着
定番
【リモート可能!Kintone案件】Kin…
【案件内容】 Kintoneカスタマイズ案件(JavaScript・リーダー) ▼業務概要 …
週5日
470,000〜840,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Kintoneエンジニア |
定番
【EM/フルリモ!】自社サービスに関するE…
・ロール:Engineering Manager(オンライン買取) ・システム:自社システム ・…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | EM |
| ・ | |
定番
【フルリモOK|C#案件】車両部品管理のソ…
【案件内容】 ソフトウエア開発における修正対応/確認・追加機能構築 ▼業務内容 ・車…
週5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 千葉柏駅 |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・・ios・Androidエンジニア | |
定番
【フルリモOK|PM案件】建築関連の基幹シ…
【案件内容】 建築関係会社が使用しているシステムの設計書作成〜スケジュール管理まで ※建…
週5日
300,000〜700,000円/月
| 場所 | 千葉柏駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| PHP・PHP(Laravel)・・VisualSt… | |
定番
【Javaエンジニア】プロジェクト拡充に伴…
■エンドクライアント業界 生命保険 ■募集背景 プロジェクト拡充に伴った増員 ■業…
週5日
500,000〜670,000円/月
| 場所 | 東京23区以外京王多摩センター駅 |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア |
| Java・Spring・・Eclipse | |
定番
【フルリモOK|フルスタック案件】災害情報…
■案件内容 バックエンド、フロントエンド、クラウドアーキテクチャのフルスタック開発、運⽤、障害対応…
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿リモート |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Py… | |
定番
【フルリモ / Ruby / 週5日】We…
【案件概要】 新規事業開発を行う部署にて、Web3やNFTなどに関連する新規事業のエンジニアとして…
週5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby・ | |
定番
【フルリモOK|ディレクション案件】出版・…
【案件概要】 出版・映像事業において、webtoon作品の編集・ディレクション担当者として、 漫…
週5日
570,000〜660,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | 編集ディレクター |
定番
【フルリモ / フロントエンド / 週5日…
【案件概要】 新規事業開発を行う部署にて、Web3やNFTなどに関連する新規事業のエンジニアとして…
週5日
940,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木目黒駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア(React) |
| JavaScript・Ruby・ | |
定番
【フルリモOK|ディレクション経験】キャラ…
【業務内容】 弊社指示のもと、キャラモデル制作における現場でのリード/管理業務をご担当頂きます。 …
週5日
330,000〜620,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町- |
|---|---|
| 役割 | ゲームディレクター |
注目
【フルリモ / PHP / 週4日〜】コミ…
■業務内容 学校内で生徒、先生、保護者間で行われるコミュニケーションや連絡を行うための機能群の …
週4日・5日
500,000〜660,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿都庁前駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・Typescript・FuelPHP・・La… | |
[Goエンジニア]旅行系SaaSにおけるW…
【業務内容】 旅行サービスにおける、下記の業務を想定しております。 ・Goを用いたサーバサ…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Goエンジニア |
| Go・・ | |
定番
【正社員】スポーツ×デジタル 自社運営メデ…
【案件概要】 スポーツに特化したメディア&コンテンツのプロデュースカンパニーです。 弊社が運営す…
週5日
/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木虎ノ門駅/新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | WEBコーダー/マークアップエンジニア |
| HTML・CSS・JavaScript・Wordpr… | |
定番
【PM/リーダーの方へ】駐車場管理システム…
■案件内容 開発用に建設された新しい駐車場システム(コインパーキングシステム)にて、 プロジェク…
週5日
470,000〜1,260,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿守谷 |
|---|---|
| 役割 | PM/リーダー |
定番
【PHPエンジニア】自社サービスに関するバ…
・ロール:バックエンド・フロントエンドエンジニア(オンライン買取) ・システム:自社サービス ・…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア(オンライン買取) |
| JavaScript・PHP・・ | |
定番
【PHPエンジニア】新規案件に関するバック…
・ロール:バックエンドエンジニア(新規案件) ・システム:新規案件 ・クラス:メンバー以上 ※…
週5日
470,000〜1,010,000円/月
| 場所 | 品川品川駅 |
|---|---|
| 役割 | バックエンドエンジニア(新規案件) |
| PHP・Typescript・・ | |
定番
【法人営業担当】インフルエンサーマーケティ…
新規クライアント獲得をサポートする営業担当 ■具体的な業務内容 役割:法人営業 目標:目標…
週2日・3日
1.4〜1.8万円/日
| 場所 | 赤坂・永田町神田駅 |
|---|---|
| 役割 | 【法人営業担当】インフルエンサーマーケティング事業の営業担当 |
定番
【Webディレクター】既存クライアントであ…
■業務内容 【スポーツ×IT】を軸に事業展開している弊社にて、 日本サッカー界をメインとしたWe…
週5日
270,000〜350,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
| HTML・CSS | |
定番
【フルリモ / インフラ / 週5日】大手…
■案件内容 ディスパッチサーバーの基盤構築案件 ※大手自動車メーカーの街作りプロジェクトにおける…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿豊洲or日本橋 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・ | |
定番
【デジタルプランナー】課題抽出からソリュー…
■配属部署 デジタルチーム ■募集背景 事業拡大に伴い、積極的に人員強化中。コーディング…
週5日
470,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | デジタルプランナー |
定番
【アカウントディレクター】新規のBtoBク…
■配属部署 アカウントチーム ■募集背景 事業拡大に伴い、積極的に人員強化中。 グローバ…
週5日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | アカウントディレクター |
定番
【フルリモ / TypeScript / …
■ポジション概要 React(Next.js) / TypeScriptを用いたフロントエンド開発…
週3日・4日・5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | TypeScriptエンジニア |
| Typescript・React・・pnpm・wor… | |
定番
【フルリモ / クラウドエンジニア / 週…
■ポジション概要 AWSとBigQueryを用いたデータ基盤の設計、構築、運用をメインで担当いただ…
週2日・3日
270,000〜370,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
| AWS・・BigQuery | |
定番
【Go,AWS】自社プロダクトの新規機能追…
自社プロダクトの新規機能追加開発をお願いできるエンジニアを募集いたします。 【案件内容】 ・…
週4日・5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| Go・Typescript・React・Next・ | |
定番
【PMO】顧客マスタ整備プロジェクトPMO
■概要 顧客マスタの整備業務プロジェクトのPMO。 ・プロジェクトにおける進捗管理、課題管理、ド…
週5日
300,000〜560,000円/月
| 場所 | 秋葉原御徒町、上野 |
|---|---|
| 役割 | システムエンジニア |
定番
【コーダー】Webサイト制作にあたるコーデ…
■募集背景 ベテランの方が3月末に退職する事が決まり、その点で急ぎ人材補充をしたい背景 ■…
週5日
270,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・WordPr… | |
【リモート相談可 / PHP / 週5日】…
「婚活支援サービス」の既存サービスPJの開発プロジェクトになります。 現在は、既存機能は保守しつつ…
週5日
620,000〜790,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・ | |
[デザイナー]画像制作 / HP作成など
ホテル事業・飲食事業・レンタカー事業のWEBやSNSを使用した集客を強化するため デザイン制作を担…
週2日・3日
80,000〜150,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿千葉駅 |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー |
| ・ | |
※フリーランス→正社員切り替え案件※【UI…
<職務内容> - UIデザイン - 既存コンポーネントを使った画面レイアウトデザイン …
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿麹町駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
| ・ | |
[広告運用マーケター]リスティング広告運用
【業務内容】 生活者に弊社事業の魅力、価値を伝え、来訪数、実際に提供する各サービスでの利用体験数…
週3日・4日・5日
370,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 広告運用マーケター |
| ・ | |
Unityエンジニア
テクノスポーツと呼称しているARを利用したスポーツ競技、観戦事業を展開しております。 その中で競…
週5日
300,000〜700,000円/月
| 場所 | 品川台場 |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
定番
【基本リモートOK!PM案件】IaC技術支…
■案件内容 SDN(CISCO/ACIと SDA) の構築・運用の自動化業務におけるマネジメントを…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | ネットワークエンジニア |
定番
【フルリモ、UI/UXデザイナー、週3日〜…
【サービス概要】 サービス① スマートフォンやPCから、病院の予約・問診・診察・処方箋 または…
週3日・4日・5日
620,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | UIデザイナー |
| HTML・CSS・Figma・XD | |
[Webアプリケーションエンジニア]金融サ…
◾️ 業務内容 ・開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発 -機能開発における設計~実装…
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Python・Go・・ | |
新着
[データエンジニア]TableauClou…
【企業】 コグラフは、「社員と家族、すべての人を幸せにする」という経営理念を掲げ、日々奮闘してい…
週5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| ・ | |
定番
【基本リモートOK!PM案件】生産管理シス…
■案件内容 生産管理システム導入案件における開発リーダーをお任せします! ▼作業内容 導入…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【基本リモートOK!開発案件】生産管理シス…
■案件内容 生産管理システム導入案件における開発をお任せします! ▼作業内容 Teamce…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Javaエンジニア/組み込みエンジニア |
| Java・C・C++・-・ | |
定番
【リモート可能!データ案件】Busines…
■案件内容 BusinessSPECTRE製品の導入・保守作業を担当していただきます。 〜B…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
定番
【リモート可能!インフラ案件】AWS/Az…
■案件内容 AWS/Azure/Snowflakeのクラウドベースのデータ基盤構築を担当いただきま…
週5日
500,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
運営サポート業務
【サービス運営サポート業務】 B2Bの顧客向けに実施している、6か月間のコーチング型マネジャーにな…
週3日・4日・5日
230,000〜550,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿九段下駅 |
|---|---|
| 役割 | 運営サポート業務 |
【リモート / TypeScript / …
・スクラムチームでのアジャイル開発 ・スマートシティ構想におけるデータプラットフォームの開発 …
週5日
470,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿虎ノ門 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Python・Go・ | |
【リモート可!インフラ案件】某大手自動車会…
【案件内容】 弊社では、2000人規模のユーザーが使用するインフラ環境のメンテナンスを受託していま…
週5日
790,000〜1,100,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(Kubernetes経験含む) |
| ・ | |
新着
[コーダー]ウェブサイト制作 (デザイン・…
【業務内容】 ディレクターの方の指示に基づいて制作していただきます。 ・WordPress…
週2日・3日
60,000〜130,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー / WordPressメイン |
| HTML・CSS・JavaScript・jQuery… | |
[事業開発]新規事業(オンライン診療など)…
【業務内容】 当社新規事業(オンライン診療など)の協業企業との運用業務にご従事いただきます。 …
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿新日本橋駅 |
|---|---|
| 役割 | 事業開発 |
| ・ | |
定番
【Androidエンジニア】自社クラウド型…
■業務内容 自社サービスであるクラウド型POSシステムのandroidアプリ開発全般をお任せします…
週5日
390,000〜490,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | Androidエンジニア |
| AndroidJava・Kotlin・Android… | |
定番
【フルリモOK|マーケ案件】日本の漫画/ア…
▼案件名 ゲーム会社における海外マーケティング支援 【背景・目的】 クライアント:国内でソ…
週2日・3日・4日・5日
620,000〜860,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
定番
【コーダー】Webサイト制作に伴うコーディ…
■募集背景 4月中に納品予定の業務が増えた為、人材補充をしたい背景 ■サービス概要 ・We…
週4日・5日
270,000〜390,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京銀座一丁目駅 |
|---|---|
| 役割 | コーダー |
| HTML・CSS・JavaScript・PHP・Wo… | |
【フルリモ可能!事業責任担当案件l】ゲーム…
【案件内容】 現在開発中で今年夏頃のリリースを予定する、大型IP(男性キャラクターメイン、 主…
週4日・5日
620,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM/事業責任者/プロデューサー |
【フルリモ可能!インフラ案件l】ゲーム経験…
【案件内容】 現在開発中で今年夏頃のリリースを予定する、大型IP(男性キャラクターメイン、 主に…
週4日・5日
620,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
【フルリモ可能!サーバーサイド案件】仮想空…
【案件内容】 おもにメタバースプラットフォーム関連のサーバーサイドの設計、 開発、運用を行って頂…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PHP/C#エンジニア |
| PHP・C#・gRPC・・・C#・(Unity)・・… | |
【フルリモ可能!C#案件】メタバースにおけ…
【案件内容】 メタバースプラットフォーム内におけるゲームサーバーの開発および運用をお任せいたします…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | C#エンジニア |
| C#・ | |
【フルリモ可能!Unity案件】仮想空間プ…
【案件内容】 2月に再リリースを行った、生まれ変わった仮想空間プラットフォーム上の 機能開発全般…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Unityエンジニア |
| C#・ | |
【フルリモ可能!ゲームプラン案件】新規ソー…
【案件内容】 現在開発中で今年夏頃のリリースを予定する、大型IP(男性キャラクターメイン、 主に…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | ゲームプランナー |
【リモート可!PM案件】複数プロジェクトを…
【案件内容】 現在、ファシリティマネジメント及びプロパティマネジメントに特化した システム開発を…
週3日・4日・5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | PM |
【リモート可】フルスタックエンジニア
Webアプリケーション開発案件です。 お客様に対するコアバリュー提供にフォーカスしたプロダクト…
週5日
790,000〜1,020,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| PHP・Ruby・・ | |
【SRE】自社プロダクトのAIアナリストサ…
■業務詳細 1.サービスの可用性向上 ・既存システムの負債部分解消、既存ミドルウェアのバージ…
週5日
390,000〜470,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿御茶ノ水駅 |
|---|---|
| 役割 | SREエンジニア |
| ・ | |
定番
【フルリモOK!Ruby案件】業界初のゲー…
【案件概要】 新規サービスにおける課題設定からMVP構築、その後の開発を中心に担当していただきます…
週5日
500,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Rubyエンジニア |
| Ruby | |
【PdM】AIコーチング事業における
独自のAIコーチングサービスの開発を進めています。 このポジションは、プロダクトマネージャーとして…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町九段下 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
プロダクトマネージャー
基幹事業である印刷事業では、国内No.1の200万人を超えるユーザーに向けてネット印刷のサービスを提…
週5日
550,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿目黒 |
|---|---|
| 役割 | PdM |
定番
【UI/UXデザイナー】医療機関特化型Sa…
■具体的な業務内容 ・企画、仕様の検討、新サービス立ち上げに対するアイデア出し ・各プロダクトの…
週5日
310,000〜530,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京東銀座駅 |
|---|---|
| 役割 | UI/UXデザイナー |
新着
定番
【フルリモ可能!PHP案件】海外向けコミッ…
■企業概要 主力サービスの『まんが王国』および新規立ち上げの海外向けコミック配信サービスの サー…
週5日
500,000円以上/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | PHPエンジニア |
| PHP・・PHP(Symfony) | |
定番
【急募!サーバーサイド開発案件】自動組版シ…
■案件内容 自社サービス(自動組版システム)の保守運用・開発業務やクライアント向けシステム開発の …
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿祐天寺駅 |
|---|---|
| 役割 | VBA/VB.net/Java/PHPエンジニア(いずれかでOK) |
| PHP・Java・VB.NET・VBA・- | |
定番
【急募!PM開発案件】自動組版システムの提…
■案件内容 ・自社サービス(自動組版システム)の提案からプロジェクト管理を行ってもらいます。 …
週5日
390,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿祐天寺駅 |
|---|---|
| 役割 | PM(経験少なめでもOK) |
| PHP・Java・VB.NET・VBA・- | |
定番
【Webディレクター】日本サッカー界の公式…
■所属部署 サッカー事業部 ■案件概要 弊社大手クライアントである日本サッカー界の公式サイ…
週3日
270,000〜310,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京新橋駅 |
|---|---|
| 役割 | Webディレクター |
定番
【リモート可!大阪/受託開発案件】成績管理…
【案件内容】 成績管理システムの詳細設計〜開発〜運用まで ※詳細は面談でお伝えさせていただきま…
週5日
410,000〜700,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京霞が関駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| JavaScript・Go | |
【事業戦略/サービス企画責任者】TikTo…
【業務内容】 ・インハウス向けイベントの企画、運営 ・ビジネス戦略策定 ・サービス戦略策定 …
週5日
470,000〜790,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | 事業戦略/サービス企画責任者 |
| ・・事業企画/事業開発経験 └メディアやtoC向け… | |
【スクラムマスター】2000人規模のユーザ…
////////////////// 「技術が好きで、新しい技術のキャッチアップに積極的な方」にお…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | スクラムマスター |
| ・ | |
定番
【サーバーサイドエンジニア/リモート可】グ…
【募集背景】 業績好調のため各事業領域での事業拡大に向けて、要員を募集しています。 【業務内…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 品川大崎駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Ruby・・ | |
[企画/PM]自動精算機の内部システムの開…
【業務内容】 新しくゴルフ場で使用する自動精算機の内部システムを開発 ポジション:企画/PM …
週3日・4日・5日
300,000〜940,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋 越後曽根駅 |
|---|---|
| 役割 | 企画/PM |
| ・ | |
新着
【SEOコンテンツディレクター】オウンドメ…
■業務内容 コンサルタントとともにクライアントのプロジェクトに入り、メディアの戦略を実現するため…
週2日・3日
180,000〜270,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神保町 |
|---|---|
| 役割 | SEOコンテンツディレクター |
新着
[PM]リアルとデジタルを融合させたサービ…
■具体的な業務内容 数名~数十名程度のチームのPMとして、プロジェクトの推進をお任せいたします。 …
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅/東京駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
| ・ | |
新着
[バックエンド]グループ全体のDXを大きく…
■具体的な業務内容 グループのDX推進に向けたサービス開発を担っていただきます。 数名程度のプ…
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅/東京駅 |
|---|---|
| 役割 | サーバーサイドエンジニア |
| PHP・Java・Go・Typescript・・ | |
新着
[フロントエンド]グループ全体のDX推進に…
■具体的な業務内容 グループのDX推進に向けた、Web/スマホアプリの開発をお任せいたします。 …
週5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅/東京駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| ・ | |
新着
【AWSエンジニア】AWSを活用した自動車…
■業務内容 現在運用中の某自動車保険システム基盤において、システム改善対応を実施する。 具体…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿相鉄線天王町駅、JR横須賀線保土ヶ谷駅 |
|---|---|
| 役割 | AWSエンジニア |
| ・ | |
新着
【リモート可能!インフラ案件】保険システム…
///////////////////// ★案件の魅力★ 長期プロジェクトで安定した環境、在…
週5日
470,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・ | |
新着
[Webデザイナー(講師)]Webデザイン…
【業務内容】 Webデザインスクールの講師 受講人数:全40名 ※マンツーマン…
週1日・2日・3日・4日・5日
150,000〜300,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | Webデザイナー(講師) |
| ・ | |
新着
【Ruby,Vue.js】急成長ベンチャー…
【募集背景/業務内容】 ・税理士紹介プラットフォーム開発の人員拡大 ┗設計〜開発までを担当(今…
週3日
330,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿原宿駅 |
|---|---|
| 役割 | フルスタックエンジニア |
| JavaScript・Ruby・Typescript… | |
定番
【PL】システムインテグレーション事業にお…
■業務内容 プロジェクトリーダーとして様々な規模(数人月~数十人月)のプロジェクトを推進していただ…
週5日
310,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PL |
新着
【フルリモOK!マーケター案件】デジタルマ…
■業務内容 自社メディア・サービスにおける課題解決のための企画、Webマーケティング、ディレクシ…
週3日・4日・5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
| ・・Webマーケティング・サービスに関する業界での実… | |
定番
【クラウドエンジニア】システムインテグレー…
■業務内容 主にGoogle Cloud を用いたシステム基盤構築や技術サポートを推進していただき…
週5日
310,000〜450,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | クラウドエンジニア |
新着
【ライター】デジタルマーケティングの未来を…
■業務内容 自社メディア・サービスにおける課題解決のための企画、Webマーケティング、ディレクシ…
週2日・3日・4日
250,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿六本木一丁目 |
|---|---|
| 役割 | ライター |
| ・・Webマーケティング・サービスに関する業界での実… | |
定番
【PM】システムインテグレーション事業にお…
■業務内容 プロジェクトマネージャーとして様々な規模(数人月~数十人月)のプロジェクトを推進してい…
週5日
450,000〜790,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | PM |
定番
【データエンジニア】システムインテグレーシ…
■業務内容 Google Cloudを用いたデータ分析基盤開発を推進していただきます。 具体的な…
週5日
310,000〜640,000円/月
| 場所 | 五反田・恵比寿・六本木白金高輪駅 |
|---|---|
| 役割 | データエンジニア |
| Python・Go・Vue.js・・Angular・… | |
定番
【フレックス&フルリモ可能】オリジナルレー…
■案件内容 お得感№1のコミック配信サービスで連載するオリジナルレーベル作品及び 漫画の企画・編…
週3日・4日・5日
300,000〜550,000円/月
| 場所 | 赤坂・永田町外苑前 |
|---|---|
| 役割 | 漫画編集者 |
新着
【フルリモOK|ゲームデザイナー案件】イラ…
【案件内容】 イラストレーターとして、カードイラストを作成していただきます! ▼業務内容 …
週5日
390,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | ゲームデザイナー |
| ・ | |
新着
【リモート可!インフラ案件】Kuberen…
【案件内容】 当ポジションは、Kubernetesで構築されたクラスターやサービスの運用を担います…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア |
| ・ | |
新着
【リモート可!インフラ案件】アプリケーショ…
【案件内容】 AWS上の主にEC2、RDS、EKSで稼働しているアプリケーションを 安定稼働させ…
週5日
470,000〜700,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿神田駅 |
|---|---|
| 役割 | インフラエンジニア(保守運用メイン) |
| ・ | |
新着
[上流SE]車両基準を満たすIoT通信機器…
【業務内容】 <製品イメージ> LTEモジュール、GNSSモジュール、CAN通信、加速度セン…
週4日・5日
470,000〜940,000円/月
| 場所 | 中京:静岡・名古屋 越後曽根駅 |
|---|---|
| 役割 | 上流SE |
| ・ | |
新着
【Flutter】嗜好品関連事業のアプリエ…
【業務内容】※詳細は、面談時にお伝えさせて頂きます※ ・日本で時価総額上位で嗜好品関連の事業を行…
週3日・4日・5日
550,000円以上/月
| 場所 | 渋谷・新宿恵比寿駅 |
|---|---|
| 役割 | アプリエンジニア |
| ・ | |
新着
定番
【シニアフルスタックエンジニア】事業部で開…
■ポジション概要 複数の既存プロジェクトのエンハンス、および、保守を実施していただきます。 スキ…
週2日
390,000〜600,000円/月
| 場所 | 新橋・銀座・東京大手町駅 |
|---|---|
| 役割 | シニアフルスタックエンジニア |
| Python・Ruby・Go・Typescript・… | |
新着
【フルリモOK!働き方柔軟!】資格試験向け…
■事業概要 新しくアプリケーション開発を検討している方向けに、 事業企画をスモールにスタートして…
週2日・3日
270,000〜410,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | Pythonエンジニア/Next.jsエンジニア |
| JavaScript・Python・Typescri… | |
定番
【リモート可能!VBA案件】自動判定するシ…
【案件内容】 ・不動産登記申請用PDFファイルからRPAで情報を抽出した後、 DB内に格納され…
週2日・3日
230,000〜370,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿渋谷駅 |
|---|---|
| 役割 | VBAエンジニア |
| VBA・ | |
新着
【新規事業立ち上げに貢献してくださる方募集…
【募集背景】 アフィリエイト担当部門は今期上期中に立ち上げ予定 (2024年7月目途で単独部署…
週3日・4日・5日
300,000〜620,000円/月
| 場所 | 渋谷・新宿- |
|---|---|
| 役割 | マーケター |
新着
【Typescript,React】AI✖…
【業務内容】 ・TypeScript, React, Next.jsを使用したSPAの開発 / …
週4日・5日
620,000円以上/月
| 場所 | 秋葉原神田駅 |
|---|---|
| 役割 | フロントエンドエンジニア |
| Typescript・React・ | |
MORE
メディア情報
キャリハイ転職にてPROsheetを紹介いただきました!
PROsheet(プロシート)の評判・口コミは?メリット・デメリットも解説